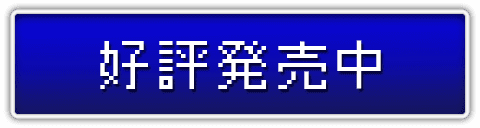久夛良木さんの“むちゃぶり”で中国へ
──というところで、いろいろと謎が深まっているところですし、そろそろ大和田さんのご経歴もお伺いしたいですね(笑)。そもそも大和田さんは、SCE(当時)で中国へのプレイステーションの展開などを担当されていた方なんですよね?
大和田氏:
もともとはSCEの「ゲームやろうぜ!」【※】出身なんです。当時はゲームクリエイター志望で、金髪ロン毛でプログラミングなどをやっていた。
※ゲームやろうぜ!
1990年代後半に当時のSCEが開催していたゲームクリエイター発掘オーディション。ここを経て商品化された作品や、SCEに入社したクリエイター、独立した制作チームを構えるクリエイターなどがいた。
──そっち側の人だったんですか。
大和田氏:
でもあるとき、僕が高校生のときに中国語を勉強していたことが、社長【※】にバレてしまって(笑)。「ソニーにゲームを作れるやつはいっぱいいるけどよお、中国語ができるやつはいねえんだ」など言われて、いきなり中国に飛ばされたんですよ。いちおう「そこでゲームは作れますか?」と聞いたら「たぶんね」と言っていたんですが……蓋を開けてみると、案の定マーケティング担当で。
※社長
久夛良木健氏のこと
「久夛良木が面白かったからやってただけ」 プレイステーションの立役者に訊くその誕生秘話【丸山茂雄×川上量生】
※スネークゲームのiPhone移植版の映像
「なんでそればっかり遊んでるの?」と訊いてみたら、「だって、これしかないから」と言うんですよね。そこでよくよく調べてみると、驚くべきことにその工場のほぼ全員の携帯の「2・4・6・8」が擦り切れていたんですよ!
それは、あまりに衝撃的な光景でした。そこには本当に携帯のクソゲーしか娯楽がなかったんです。
──この擦り切れている写真、確かに凄いインパクトですね。
大和田氏:
ええ、その光景を見たときあたりから、独立を考え始めましたから。
というのも僕はそれまで、言ってしまえばお金持ち向けの商品を売っていたわけです。それって超マニアを除いたら、映画、旅行、ご飯、キャバクラとさまざまな娯楽がある人に向けて、いかに「プレイステーションを買ってもらうか」という勝負をしているわけですよ。実際、そういう人たちをなんとか振り向かせるために、当時のソニーは年に何百億円というレベルでマーケティングに投資していましたしね。
でも、そんなふうに売られたプレイステーションのゲームって、人によっては2~3時間遊んで「つまんない」とひと言レビューを書いて中古ショップに売り飛ばしたりするわけです。彼らにとって、それはワン・オブ・エンターテイメントでしかないわけですから。
──まあ、そうかもしれません。
大和田氏:
一方、僕などの小さいころを思い返すと、もうファミコンのバネがバカになるまでずっと遊んでいたわけです。それって中国の工場で働く労働者の若者の話と同じで、要は「供給がないから需要が最大化している」わけですよね。
だから『スネークゲーム』をあそこまで遊ぶ子たちを目の当たりにしたとき、「ものづくりに携わる人間として、どんなお客さんに遊んでもらいたいのか」──ということは、やはり考えざるを得なかったわけですよ。そりゃ「お腹いっぱいの人よりも、喉が乾いている人に水を売りたい」と思うわけです。
しかも当時の中国ってひとりっ子政策の影響で、いちばんゲームが好きな15〜20歳の子たちが先の10年のあいだに17%減ることが判っていて。「これからシュリンクするマーケットなんて面白くないな」と思ったこともありました。それでソニーを辞め、自分のビジネスを立ち上げることにしたんです。
──そのあたりは、本当にゲームクリエイター出身の人の発想という感じがしますね。独立されてからはまず何をされたんでしょうか?
大和田氏:
中国の代わりに、ビジネスの主戦場に据えたのが東南アジアでした。理由は単純で、統計を見て「これから人口が増える新興国ばかりじゃん」と思ったからです(笑)。
そこで始めたのが、某社のある格闘ゲームを預かる形での現地配信でした。そのときは「プレイステーションの立ち上げもやっているし、ざっくり3000万は稼げるね」というようなノリで支持者の方々も僕を信頼してくださっていたんですが、蓋を開けてみると……結果は初月3000円でした。
──それが1ヵ月の売上!
ゲーム配信での挫折〜放浪の旅へ
──初月の売上が目論見の10000分の1だった……いったいなぜでしょう?
大和田氏:
当時はもう愕然としましたよね。「えー!? ケタが4つ違うじゃん!」と(笑)。
 |
そこで初めて、自分が自分のマーケットのことを「解っているつもり」だったことに気付いたんです。実際、当時は統計データを見ただけの、手触りのないマーケティングをやっていましたしね。
──まさに冒頭で批判していたような、軽いノリで海外展開を狙う日本企業そのものだった、と。
大和田氏:
もう大反省して「エンドユーザーのリアルな声を吸い上げなきゃいけない」と一念発起したんです。
そこで自分に課したのが、ゲームのテキ屋をやる放浪の旅でした。日本のゲーム機を並べて「はい、いらっしゃい! 日本のゲームを1回10円。おじちゃんのスコアに勝ったらアメあげるよ!」みたいなノリの生活を、30都市で1年続けました。
──また、泥臭い仕事の毎日が始まった、と。
大和田氏:
そこでお客さんのリアクションを徹底的に見たんです。「そもそもゲームに1回10円払ってくれるのだろうか」、「単価が倍だとどうだろうか」、「100円で5回セットだとどうだろうか」……そうしたパターンを、十何種類ものゲームで試していくんですよ。
すると次第に「この国の人はこんなゲームが好き」とか「どういうパッケージならお金を払ってくれる」という、“誰も持っていない統計データ”が出てくるんです。それはもう、東南アジアに限らず、インドや北アフリカなどあらゆる場所のデータを実地で取っていきました。
「Googleが取れない40億人」の実体
──その旅で得た知見を、話せる範囲で教えていただけますか?
大和田氏:
たとえば、スマホアプリのマーケットの“実体”は、予想していたものとかけ離れていましたね。
そもそも新興国って基本的に月給制じゃないんですよ。市場で働いている大半の、サラリーマンではない人は日払いで稼いでおり、インドネシアの場合だとワーカーの80%がそれにあたります。これって、つまり銀行口座を持ってる人がほぼ20%ということなので、クレジットカード払いのアプリなんてほとんどの人が買えないわけです。実際、インドネシアのクレジットカードの普及率は当時3%でしたね。
 |
だから、みんな最新のスマホを持っているけど、アプリのインストール数そのものが日本の1/3〜1/2程度なんですよ。スマホをほぼ出荷状態で使っている人が多く、実体はアプリのマーケットにすらなっていなかったんです。
──まさに統計を見ただけではまったく見えてこない、現地の生活の現実ですね。
大和田氏:
じつはGoogleやAppleが取れている層って、ざっくり言って世界の55億回線あるスマホマーケットのうちのまだ約10億人程度なんですよね。そのリアリティを実際に目の当たりにしたとき、「じゃあ、いままでのゲーム業界がアプローチできていなかった中間層・低所得層向けのモデルを作ろう」と思ったんです。つまり、彼らの所得は確かに日本の1/10とかかもしれないけれど、Googleが取れない残りの約40億人から1日1円貰えばいいじゃないか、と。
──まさに「喉が渇いた人に水を届けるモデル」そのものを作ろうと。
立ちはだかった「外国人」という壁
──そこからは具体的にどんな事業を始めたのでしょう ?
大和田氏:
まず考えたのが、ダウンロードステーションを作ることでした。問題なのは「ゲームを売ろうにも、通信インフラが悪い」という部分だったので、「コンビニに行って、スマホを繋げて無料でダウンロードができたらいいじゃん」と思ったんですよね。
──おお、それなら確かに使われそうですね。
大和田氏:
いや、それがもう散々で……100台設置したうち、3ヵ月経って生き残っていたのはたった3台でした。電源切れやら破壊やらで、全部がひどい状態になっていたんです。それでも頑張ってマネジメントしてプロモーションしてという努力を続けてはいたんですが、あるとき「もうなんか馬鹿馬鹿しいな」と思って(笑)。
そこでよくよく話を聞いてみると、彼らからしたら「そもそもなんで大和田に協力しないといけないの?」と思っていたことが判ったんですよ。結局のところ、僕らはどこまでいっても「外国人」でしかなかった。その背景には、中国から始まるアヘン戦争のトラウマがあったり、アジア通貨危機の時に華僑がお金を国から持ち逃げしてインドネシアルピアが暴落したり……という歴史があったわけです。彼らが思う外国企業って、いわば経済的侵略者だったんですよ。
──そこらへんは、多くの日本人には馴染みのない感覚かもしれません。
大和田氏:
それでハッと気づいたのは、現地を巻き込んで勝負するには「“大和田のビジネス”ではなく“自分たちのビジネス”だと思ってもらわなくちゃダメだ」ということでした。そう考えたとき、彼らが何より自分のものとして大事にしていたのって、やっぱりスマホなんですよ。
 |
ですので今度は、自分のスマホそのものをダウンロードステーションにできるようにしてみたんです。つまり、自分のスマホにあるアプリを「これ面白いからあげるよ」とWi-Fiで直接渡せるようにしました。要はモバイルP2P型のアプリケーション配信プラットフォームなんですが、通信速度の遅いGoogle Playで落とすと10分かかったのがこれだとWi-Fiなので10秒で済むんです。
しかも、通信料もかからないわけですよ。インドネシアって日本みたいなパケット使い放題がないので、だいたい50MBを落とすのに2000ルピアとかかかるんです。コカコーラ1本が4000ルピアなので、その半分の料金がいちいちかかっていたわけですよ。
──スマホを使って直接Wi-Fiでアプリを渡すほうが、速度的にも金銭的にもメリットがあったと。ただ、それだけだと「自分のビジネス」というには不十分な気もしますが……。
大和田氏:
そうですね。じつはもっともインパクトがあったのは、口コミ的にアプリを配って渡した相手がアプリ内でお金を使うと、自分にポイントが還元されるシステムでした。「友達がゲームを実際に遊んでくれたら、もっと大きなリターンがあるよ」と伝えるんですね。すると、ひとりひとりが自主的にゲーム大会を企画して、広報してくれたりするんですよ。
実際、ゲームって「ドカン」と広告を投下されるより、友達から「このゲーム面白いから一緒に遊ぼうぜー」と言われるのが、いちばんの遊ぶ動機になるじゃないですか。
──それはよくわかります。
バザール事業の驚くべき実績
──実際、業績はどうだったのでしょうか?
大和田氏:
それが凄まじくて……ある大学で最初にテストマーケティングをやったんですよ。すると、20人のディストリビューターが、たった3ヵ月で学内の8割のAndroidユーザーにアプリを配り終えていたんです。
 |
しかもデータを見ると、普通なら1万回広告を表示して3人クリックするかしないかの世界なのに、うちは当たり前ですが9割以上のアテンションがあった。インストール成功率も、インドネシアだとGoogleでだいたい20%ぐらいなんですが、うちは速くダウンロードできるうえに、トラブったら相手が目の前でサポートしてくれるので9割以上。そして何より凄かったのが、MAU(Monthly Active Users)率です。報酬欲しさに「このあいだ遊んであげたゲーム、まだ遊んでる?」みたいに定期的に声をかけてくれるので、これが6割以上でしたね。
あとは、ARPU(Average Revenue Per User)も良いんですよ。当時の統計によるとインドネシアのARPUはだいたい1ドルなんですが、うちは最大で4ドルありましたね。
──いろいろと凄い数字だと思うのですが、ARPUが相場の最大4倍……というのは、かなりの異常値ですよね。
大和田氏:
普通にゲームを買うときって、1枚15〜20ドルもするGoogleなどのプリペイドカードを使うんです。でも、クレカを持っていないからコンビニで買おうとしている人が、20ドルのキャッシュなんて持っていないわけですよ。実際、その料金設定って決済手数料のせいでそうなってるに過ぎなくて。一方うちでは、自分たちのポイントを流通させているので、1円から買えて非常にハードルが低いんです。
──ああ……なるほど。Googleの想定している世界観では、お金を使いたくても使えない人たちがいたわけですね。
大和田氏:
そういう経緯で、まずはインドネシアを取り、いまはほかの国への展開をいろいろ仕込んでいる最中ですね。自分らで「都落ち商法」と言っているんですが、どんどん通信インフラの悪い地域に僕らは駒を進めていくわけです。まあ、いつまでたっても日本には帰ってこれない会社ですね(苦笑)。
最初にインドネシアを攻めたわけ
──そう言ってるわりには、とても楽しそうですけどね(笑)。それにしても、アジアの中間層といってもいろいろな地域がある中で、なぜインドネシアから攻めようと思ったのでしょう?
大和田氏:
それは単純な話で、テキ屋時代にいちばん食いつきが良かったからですね(笑)。実際、インドネシアって日本のコンテンツを知っている子がもの凄く多いんです。もちろんタイやベトナムもそうなんですが、たとえば当時からインドネシアで人気だった初音ミクは、ベトナムではほとんど知られていませんでしたし。
 |
それから国の平均年齢が27.8歳だったんですよ。もう超絶凄いピラミッドになっていて、これから子どもが増えていく国なんです。
──それこそ中国などと比べたときに、将来性が全然違うわけですよね。
大和田氏:
そして言語の問題もクリアしています。当たり前ですが、ゲームのローカライズで重要なのって、国の人口ではなくその言語でカバーできる人口なんです。たとえば、一見インドは人口の多い国ですが、ヒンディー語圏の人口だと約4億人に目減りします。一方、インドネシアはどんな地方都市に行っても基本的にインドネシア語が解るので、この先人口が増えていっても国民のだいたいがカバーできるな、と。
もっと言うと、インドネシアはひとり当たりGDPの平均値がASEANの平均とほぼ一緒なんです。トップのシンガポールから始めて展開していくのも難しいし、底辺国のミャンマーから立ち上げるのもたいへんなので、いい意味でバランスがいい国だなと。
 |
……とはいえ、インドネシアそのものとの出会いは最低だったんですよ。一都市目でテストマーケティングをしていたら、強盗にクルマの中にボーンと押し込まれ、3時間くらいかけてボコられて殺されそうになったことがあって(笑)。
──えええ……それは無事だった……わけですよね?
大和田氏:
「ゲーム機と現金を全部置いていけ」と脅されたんですが、ひたすら殴られているうちに「あ、俺を殺しまではしないんだな」という交渉のボトムラインが判ったんですよ。要は、本気で欲しかったら即殺して盗っていくはずなので。それがボトムならということで「現金は全部やるけど、ゲーム機は渡さない」というディールを仕掛けたら、無事成立して解放されました。
──なんで一介のビジネスマンが、そんな修羅場を乗り切る能力を手に入れているのか……(笑)。
この記事に関するタグ
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合がございます
Amazon売上ランキング
集計期間:2024年4月19日15時~2024年4月19日16時
新着記事
-
電脳世界の歌姫ロロの唄が聴ける落ちものパズルゲーム『ロロパズミクス』のPC(Steam)版発売。バーチャルアイドルRoRoの楽曲が全19曲収録。テーマソング「ピカピカのわっふ♪」のミュージックビデオも公開
-
世界最大級のインディーゲーム紹介番組「INDIE Live Expo 2024.5.25」の番組内容発表。『少年期の終り』や『ピギーワン SUPER SPARK』などの話題作含め合計100以上のタイトルを紹介予定
-
『バニーガーデン』Steam版がリリース予定を大きく繰り上げていきなり発売。SNS上では“心清らかなお紳士様・お嬢様”たちが刺激的な“サービス”の評判を投稿しにぎわう
-
スクエニの新作ボードゲーム『ファイナルファンタジーモーグリ6兄弟のモブハント(仮称)』の先行体験会実施。「ゲームマーケット2024春」にて4月27日と28日に開催。短期決戦型ながら戦略性が試される
-
チラズアートの新作はまさかの“ラーメン屋台”ホラーゲーム、『拉麺屋台』発表。麺をすすらせ恐怖と対峙