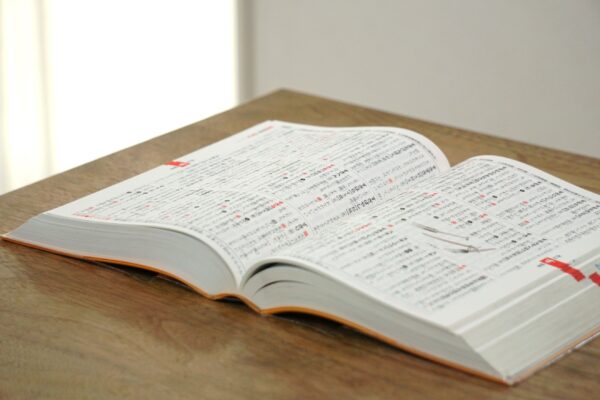今週土曜、「佐藤天彦叡王 vs Ponanza」の対局をもって、様々な名勝負を生み出してきた「電王戦」の歴史が遂に終わりを告げる。
第一回電王戦で、米長永世棋聖と将棋ソフト「ボンクラーズ」が対局したのは、2012年の1月。開始当時を思い返せば、そもそも棋士とAIが公開の場で戦う行為そのものが「衝撃的」であり、さまざまな物議を醸していた。
※「電王戦」終了の理由については、上記PVの中で説明がなされている。また、第2期電王戦記者発表会の席上で、ドワンゴ川上量生会長が「人間とコンピューターが同じルールで真剣勝負をするスタイルの現状の電王戦は、歴史的役割は終わったと考えて、今回で終了することに致しました」と発言してもいる。
それから5年――今やすっかり状況は変わった。ビジネス誌には「AIが人類の職業を奪う」などのセンセーショナルな見出しが躍り、昨年はGoogle主催のAlphaGo【※】対局で、“人類最強”の囲碁棋士イ・セドル氏の敗北が大きく話題になった。自動運転車の報道を見るまでもなく、もはやAIは私たち“人類”の社会に静かに浸透しはじめてさえいる。
だが、その先に待つ「AIのある人類社会」とは、一体どんなものなのか?
※AlphaGo
Alphabet社傘下のDeepMind社が開発した囲碁AI。将棋に比べ選択肢が膨大な囲碁ではコンピュータソフトの開発がなかなか進まず、アマチュアの棋力にも及ばない状態が続いていた。しかし画像認識やディープラーニングといった技術がブレークスルーとなり急速に進歩。2016年に当時最強の囲碁棋士のひとりであるイ・セドル九段と五番勝負を行い、4勝1敗で勝利。その衝撃は日本でも連日ニュースで取り上げられた。
電王戦について、主催のドワンゴ・川上会長の言葉を引いて、これまでに「21世紀の文学」という呼ばれ方をされたことがあった。例えば、19世紀の文豪ドストエフスキーが書いた文学作品は、しばしば「20世紀の人間を予見していた」と言われる。そんな意味で電王戦が「21世紀の文学」だったならば、この物語がどんな展開を見せて、今どんな結末を迎えようとしているのか――知りたくはないだろうか?
そこで我々は今回ゲームメディアとして、電王戦の終了を前に、この5年間の振り返りを行っておきたいと思う。インタビューするのは、棋士たちに積極的なフィールドワークを行い、AIと人間を巡る問題についての論考を発表してきた、一橋大学准教授・久保明教氏。気鋭の文化人類学者を迎えて、電王戦で人類が「何を目撃していたのか」を訊いた。
聞き手・文/稲葉ほたて
 |
なぜ文化人類学者が電王戦に興味をもったのか
――さて、今回の記事は2012年からの電王戦について振り返る長大なものになるので、先に久保さんについて少しだけ読者の方に紹介しておきたいんです。将棋ファンの中には、SYNODOSの電王戦振り返りの文章や、将棋ソフトを使いこなすことで有名な千田翔太棋士へのロングインタビューを目にした人もいるかもしれませんが、一般にはあまり知られていないと思いますので……。ご専門は文化人類学なんですよね?
久保明教氏(以下、久保氏):
文化人類学のなかでも「科学技術の人類学」が専門です。簡単に言うと、「人類にとってテクノロジーとはいかなるものであり、いかなるものでありうるか」を研究しています。
4/20公開予定 無料Webマガジン『E!』8号 特集「おもしろE!」
— エウレカ・プロジェクト (@eurekaprojectjp) April 18, 2016
千田翔太×久保明教(×澤宏司)
機械と人間、その第三の道をゆく#内部観測 #将棋 #電王戦https://t.co/53wbp7cg3T pic.twitter.com/2gNxD7Qc2t
以前、ドワンゴの川上会長が「電王戦は21世紀の文学的テーマになる」と発言されていましたが、自分は、かなり近いテーマを学問的に探究していると思っています。具体的には、「電王戦」や「AIBO」のような、人間に近い知能を持った機械と人間が相互作用する場面について、「参与観察」【※1】や「フィールドワーク」【※2】といった人類学的なアプローチで迫っているのだと思っていただければ、わかりやすいかもしれません。
今日お話しする内容も、電王戦を振り返るだけでなく、電王戦から見えてくるAIと人間の近未来のあり方、そこにどんな可能性や問題が出てくるのか、AIの進化に一喜一憂している現代の世界とはどのようなものなのか、という観点からのものになると思います。
※1 参与観察
定性的な社会調査法のひとつ。研究対象となる社会に加わり、数ヶ月から数年に渡ってその社会の一員として生活しながら対象社会を直接観察し、資料を収集する方法。文化人類学における異文化社会の研究などに用いられることが多い。
※2 フィールドワーク
実地研究など研究室の外で行う調査研究のことで、研究対象となっている人びとと共に生活をしたり、 アンケートやインタビューなどをを行う社会調査活動のこと。主に文化人類学・社会学・地質学・生物学などで用いられる。
――博士論文で「AIBO」のユーザー行動などをフィールドワークして、『ロボットの人類学―二〇世紀日本の機械と人間』という書籍にまとめていますよね。世代的には「カルチュラル・スタディーズ」【※】のような、サブカルチャー研究が華やかだった時代に学生生活を送られているので、そういう方向の興味から「電王戦」に向かわれた面もあるのかな……と思ったのですが。
久保氏:
うーん、「カルスタ」ですか。流行ってはいましたが、好きにはなれなかったですね。大学院に進学する頃には、「カルスタ」のように意味や権力の問題を扱うだけでなく、テクノロジーやサイエンスの内側にまで踏み込まなければ、文系の学問は面白くならないのではないかと考えていました。周りにいた大学院生も、「数学の哲学」(近藤和敬・現鹿児島大学准教授)や「臓器移植の人類学」(山崎吾郎・現大阪大学特任准教授)をテーマにしていくなかで、似た判断をしていたと思います。
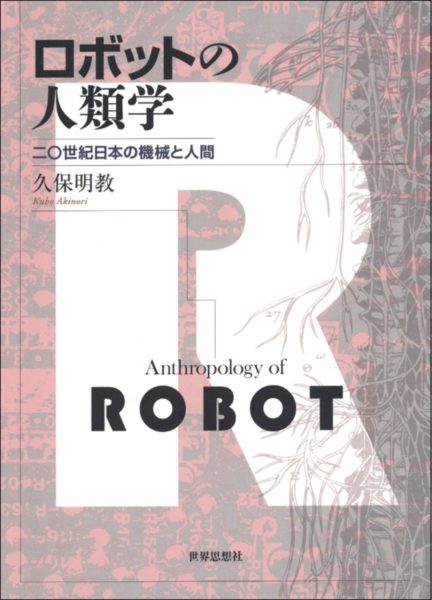
(画像はAmazonより)
※カルチュラル・スタディーズ
1964年にバーミンガム大学に設立された現代文化研究センター(CCCS – Centre for Contemporary Cultural Studies)の名称を起源とする、文化一般に対する学問領域の潮流。文化人類学や政治学などの様々な知見を領域横断的に利用して、日常生活に近い領域の文化を研究するのが特徴。そこにはアニメやテレビゲームなども含まれる。
――なるほど。では、改めて久保さんが電王戦に興味を持たれた経緯は何だったのでしょうか。そもそも、将棋自体が相当にお好きなように思います。かなり将棋を指していないと、出てこない分析や質問をしているようですが。
久保氏:
ネット対戦がメインですが、この6年ほど平均して一日一局は指しています。子供のころ少しやっていましたが、長らく将棋には触れていなかったんです。それが、ちょうど2011年の東日本大震災の後に、なんとなく再開したんですね。
 |
理由は――多少個人的な話ですが、震災の後に人文系の学者や批評家が話していることがどうにもヒドいものに思えて鬱々としていたんです。ちょうど博士論文を書きはじめた時期でしたが、「文系の学問ってどうしようもねぇな」と感じていました。色々な前提が崩れていることをみんなで覆い隠そうとしてるようで気持ち悪いなあ、と……。そういうときに、なんとなく将棋を指しはじめたわけです。
――なんだか、いきなりヘビーな話が出てきてちょっと面白いのですが(笑)、なぜまたいきなり将棋を?
久保氏:
将棋が好きな方はわかってくれると思うのですが、将棋って、上達すればするほど、それまで自分が理解してると思っていた場所の地盤が壊れていくような感覚を味わうゲームなんです。「ここまで強くなったぞ!」と新しいレベルに来たと思ったら、すぐにもっと強い連中にぶつかって、ガラガラと足場が崩れてまたやり直し、みたいな。そういう崩壊感を毎日味わうことで、自分の精神を安定させていたところがあったかもしれません。
半分は現実逃避だったと思いますが、それを言えば、震災で色んな前提が壊れていくことからみんながどんどん現実逃避していく状況だったわけで、“現実逃避からの逃避”だったのかな、と。
――でも確かに当時を思い出すと、ニコニコ動画でも「ぽぽぽぽーん」のようなCMをMADにするのが流行ったりして、なんというか現実逃避の雰囲気はありましたね。
久保氏:
そのうちに電王戦が始まって、第二回電王戦で「こりゃ何か訳の分からないことが起きてる!」となりました。
というのも――僕が感じていたような前提の崩壊に、ソフトと戦うプロ棋士も直面してるように見えたわけです。「こっちも地面壊れてんじゃねぇか」という感じですね。その感覚をもとに、ウェブジャーナル・SYNODOSで第二回電王戦の記事を書きまして、そこから調査の手を広げて、今に至っています。

(画像はSYNODOSより)
第一回電王戦:将棋とコンピュータの歴史
――それでは、ここから本格的に電王戦について、対局を時系列で振り返る形で進めたいと思うのですが、まずは米長邦雄先生【※1】の登場した2012年1月の第一回から話せればと思います。そもそも将棋連盟は2005年に、棋士・女流棋士が公の場で許可なくソフトと対局することを禁止していたんですよね。その間に、2007年に渡辺明竜王がBonanzaと対局【※2】するようなことはありましたが。
※1 米長邦雄
1943年生まれ、山梨県出身の将棋棋士。永世棋聖。1985年に十段・棋聖・棋王・王将の史上3人目となる四冠を達成した。2005年から2012年まで日本将棋連盟会長を務めた。2012年にコンピュータソフト「ボンクラーズ」と対局。既に現役を退いていたが熱心に研究し、敗れたものの軽妙な指し手を披露した。60代になってから始めたTwitterの活用にも積極的だった。
※2 2007年に渡辺明竜王がBonanzaと対局
2007年3月21日、大和証券杯ネット将棋・最強戦の創設を記念して、前年の「世界コンピュータ将棋選手権」で優勝した将棋ソフト「Bonanza」と渡辺明竜王との特別対局が組まれた。公の場でコンピュータ将棋がタイトル保持者と平手で対局するのはこれが初めてだった。対局は中盤までBonanzaが優位に進めたものの、渡辺が逆転勝利した。「竜王」というのは、全7タイトル戦の中の最高峰である竜王戦にて、七番勝負を勝ち抜いた者に与えられる称号。竜王位は名人位とともにプロ将棋界の頂点とされている。
久保氏:
2010年4月に情報処理学会【※】から「漸くにして名人に伍する力ありと情報処理学会が認める迄に強いコンピュータ将棋を完成致しました」という挑戦状が届き、それに当時の将棋連盟会長だった米長邦雄さんが応じるかたちで、コンピュータ将棋との対局は始まりました。

(画像は将棋スペシャル~第一回将棋電王戦特番~-0より)
※情報処理学会
情報処理技術の推進を目的に1960年に創設された一般社団法人。正会員数は約1万5,000人。2010年に創立50周年記念としてトッププロ棋士に勝つことを目標にしたコンピュータ将棋のプロジェクトを立ち上げた。2015年には十分にコンピューター将棋が強くなったという理由から同プロジェクトの終了宣言を出した。
半年後の2010年10月に当時の女流王将・清水市代さん【※1】と「あから2010」【※2】の対局が開催されます。「あから」が快勝して、次に米長さんが引退棋士として対局を申し出た。そこで日本将棋連盟・ドワンゴ・中央公論の共催で行われたのが、2012年1月の第一回電王戦、ということになります。
ただ、第一回は、米長さんが現役を引退していたこともあって、かなり「お試し」の側面が強かったと言いますか、イベントとして成功するかテストするという意味が大きかったようには思います。
※1 清水市代
1969年生まれ、東京都出身女流棋士。日本将棋連盟所属。1985年に16歳でプロ入り。女流棋士番号は7。高柳敏夫名誉九段門下。通算女流タイトル保持は43期で歴代1位。情報処理学会の50周年記念として2010年10月11日「あから2010」と対局。序盤から中盤は、一進一退の応酬が続くも、結果的にコンピュータ側の快勝となった。棋風は、序盤から激しい攻めを行い、相掛かりや右四間飛車を得意戦法とする。
※2 あから2010
2010年、情報処理学会創立50周年を記念して発足した「コンピュータ将棋『あから』強化推進委員会」の特製システム。国内トップ4プログラム(「激指」、「GPS将棋」、「Bonanza」、「YSS」)による多数決合議法を採用。2010年10月11日、清水市代と対局し、86手で勝利した。プロ棋士を負かしたという事実は、当時話題となる。2015年にプロジェクトは終了。
――ただ、その決断がどういう流れで決まったのかはわからないと思うのですが、少なくとも棋士とAIの対戦が成立しうるギリギリの時期に、非常に大きな決断をされたようには思うんですね。
久保氏:
有名な話として、大山康晴十五世名人【※】が将棋にコンピュータを導入することに反対していたという逸話がありますね。

(画像はWikipediaより)
米長さんは1943年生まれで、大山十五世名人(1923年生まれ)と羽生善治さん【※】の、世代的にちょうど中間にいた棋士ですね。若手の研究に関心が高く、特に羽生世代の感覚を取り入れることで、強さをキープできたという評価もある人です。そういう意味では、米長さんだからこそ実現した対局でもあると言えそうです。
※羽生善治
1970年生まれ。史上最強の棋士のひとりに数えられる将棋棋士。1995年に将棋界で史上初の7タイトル独占(七冠王)を達成した。竜王を除く6つで永世称号を保持している。同世代の棋士には森内俊之・藤井猛・佐藤康光などトップクラスの実力者が集中しており、「羽生世代」と呼ばれる。趣味のチェスでも日本トップクラスの実力者。著書に『人工知能の核心』(NHK出版)など。
――ここで少し、電王戦に至るまでの「将棋史」の文脈を読者と共有した方がいいかな、と思います。例えば、米長さんが若い頃に女性との「千本切り」に励んでいたという話があるんですよね(笑)。そんなことが直接的に将棋の強さに関係あるのかは全くわからないけど、勝負師というものはそういう行為を成し遂げるくらいの蛮勇が必要なのかなあ、と思う話ですね。90年代に台頭してきた「羽生世代」以前の棋士たちは、とにかく破天荒なエピソードが多いように見えます。
久保氏:
ただ、「羽生世代」は、そういう破天荒なひとたちが現役だった時代に、棋士になっていますからね。将棋の「外部」の経験まで含めて勝負事に活かしていく――棋士がまだ「勝負師」的な存在だった時代の良い部分も継承していると思います。
――とはいえ、やはり羽生さんの世代の最大の特徴は、将棋というゲームを非常に合理的に、一種の数理ゲームのようにしてロジカルに把握していったところにあるんですよね?
久保氏:
一つ強調しておくと、将棋におけるコンピュータの影響は将棋ソフトが初めてではありません。80~90年代からパソコンを使った棋譜のデータベース化が進み、それと並行する形で羽生世代が定跡との付き合い方を変えていった歴史がある。この辺りについては、『ウェブ進化論』で有名な梅田望夫さん【※】が2000年代後半の一連の著作で分析されていますが、端的に言えば、羽生世代が進めたのは「情報の探索における革新」だ、ということになると思います。

(画像はAmazonより)
――梅田さんの文章は、羽生さんにGoogleに通じる情報の扱い方のセンスを見いだしていこうとしていたと思うのですが、確かにそう聞くと、両方とも「IT革命」以降に登場した大量のデータを、いかに活かしていくかという問題に直面していたのかもしれないですね。
久保氏:
羽生世代は、ある戦型のある局面に関して、将棋ソフトにおける「全幅探索」のようにして、「読み」の可能性を徹底的に調べあげていったわけです。将棋ソフトが全幅探索を採用するのは2005年の「Bonanza」登場以降ですから、特定の局面のみとはいえ、「読みの革新」についてはむしろ棋士が先行したとも言えます。梅田さんが特に注目したのが、羽生さんが1997年から3年半にわたって「将棋世界」で連載した内容をまとめた『変わりゆく現代将棋』という本ですね。
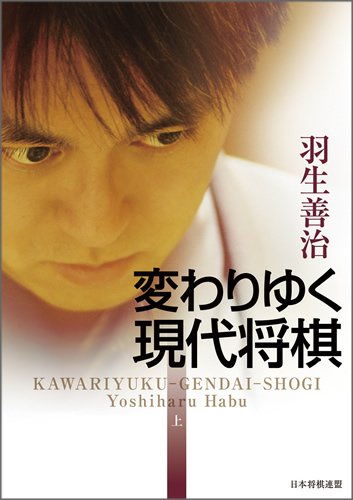
(画像はAmazonより)
――羽生さんが20代後半に執筆された連載をまとめた本ですよね。延々と矢倉【※】の序盤について、もう一手目、二手目、三手目と徹底的に分岐を考えていって結局、3年半の月刊連載の終わりまで五手目の検討を続けて「第一章 矢倉」のみで終わったという(笑)、伝説の連載をまとめた本です。
※矢倉
居飛車で使われる代表的な囲い。歴史がありさまざまな名勝負が繰り広げてきたことから「矢倉は将棋の純文学」と言われる。
久保氏:
あの本で羽生さんは、今まで想定されていなかった手まで、一から考え抜いて検討しています。まさに「情報の探索における革新」を体現する姿勢ですね。ただ、広がった選択肢を評価する「大局観」については、対局や「棋譜ならべ」を通じて前世代から継承した感覚を存分に活用していたと感じます。
それに対して現在、若手棋士を中心に生じているのは「情報の評価における革新」だと言えると思います。局面の形勢判断【※】や「大局観」に当たる部分が、ソフトの影響によって変化しているということです。
※形勢判断
その局面が、どちらに有利で、どちらが不利かを判断する行為。
――なるほど。ここで読者に向けて、少し用語の補足もしたいと思います。羽生さんなんかは、よく「直感」「読み」「大局観」の三つに分けて、棋士の思考プロセスを説明しています。
まず盤面を見て「直感」で指し手を数手にまで一瞬で絞り込み、次に「読み」でロジカルに指し手の分岐を考えていく。でも、その分岐可能性の計算は指数関数的に増えて情報爆発してしまうので、今度は終局までの時間軸での大戦略を見越した「大局観」を働かせて、再び考えるべき手を一挙に絞り込む――このプロセスで棋士は思考すると言うんですね。
ただ、羽生さんの場合は、「大局観」については将棋以外の勝負まで含めた「経験」で得るという感じのようですが……。
久保氏:
そこは、羽生さんがアナログとデジタルの「狭間の世代」だったことが大きいのではないでしょうか。
今の若い世代の棋士になると違ってきていますね。僕がインタビューした千田六段【※】の研究方法だと、ある局面から想定できる膨大な分岐をソフトに探索させて、自分は重要な局面でソフトが弾きだす評価値や候補手を検討することに集中していると言っていました。「読み」よりも「大局観」にあたる部分を鍛えるためにソフトを活用している印象です。
※千田翔太
大阪府生まれの将棋棋士(1994年~)。2013年に18歳でプロデビューした。コンピュータ将棋や各ソフトの棋風の違いなどに非常に詳しく、「1日10時間以上floodgate(コンピュータ将棋の対局場)を見ている日もある」と言うほど。「コンピュータ将棋の局面評価にいかに自分の局面評価を近づけるか」という理想を持っており、まさにコンピュータ将棋新時代を代表する棋士のひとりである。
――そこは、まさに「電王戦」を振り返って、それがもたらした影響を考える中で、重要になってきそうですね。
今振り返る勝負師の初手「6二玉」
久保氏:
そろそろ第一回電王戦に話に戻すと……米長さんが「羽生世代」に近い感性を持っていたからこそ電王戦が成立した一方で、「大山世代」的な勝負師の感性を強く持っていたからこそ、ボンクラーズとの対局が、あのような「技をかけにいって敗れる」将棋になったとも言えるように思います。
――なるほど。ただ、一つ気になるのが米長さんの初手の「6二玉」【※】ですね。物議を醸した手なのですが、彼の著作では事前の研究成果として導いたものだと主張されていました。終了後の会見でも「あの手を責めないでやってくれ」と話しています。

(画像は米長邦雄永世棋聖インタビュー 第2回将棋電王戦より)
久保氏:
「6二玉」については米長さん独特の感覚があったのではないかと思います。例えば、BSの番組でやっていた米長邦雄vs加藤一二三の「はさみ将棋」の動画を、この前YouTubeで見たんですよ。そうしたら、加藤さんが優勢になったタイミングで、米長さんが盤上を斜めに横切るように全ての駒を配置し始めたんです。ただのテレビのお楽しみ企画なのに、絶対に勝たせない布陣を引いてしまうという(笑)。
――ひどい(笑)。
久保氏:
決着がつかなくなって、動画ではそれ以降の局面はカットされていました。【※】
米長さんには、はさみ将棋でさえ加藤さんに負けたくない一心でそういう手を繰りだすような発想があって、第一回電王戦の「6二玉」も、いわば棋士が勝負師であった時代の発想の、非常に高度なバージョンだったのではないでしょうか。

(画像はAmazonより)
※
合議の結果、先手と後手を入れ替えて指し直しをすることになり、結局米長氏が勝利した。
――大山康晴が対局相手と麻雀を打つことで相手の性格のクセを見抜いて、それを勝負に活かしたという逸話を聞いたことがあるのですが、そういうノリで将棋ソフトを一種「擬人化」することで、そのクセを見抜こうとしたという感じでしょうか。
久保氏:
ただ、これは後に語る内容になりますが、電王戦も後期に入ると「アンチコンピュータ戦略」という発想が生まれてきます。簡単に言えば、どう指せば将棋ソフトがミスをしやすいかを、そのソフトを使って分析する手法です。
糸谷哲郎八段にインタビューしたとき、彼は、「米長元会長は初手6二玉というアンチコンピュータ戦略をとった」という言い方をされています。ただ、これはソフト対策の手法が確立したあとに、その言い方を当てはめているのだと思います。米長さん自身は、勝負師の発想でやっていたのではないか、と。
――確かに、ソフト解析で精度高くロジカルに勝ち筋を見つけていく手法とは、かなり思考プロセスが違っていたのかもしれないですね。
第二回電王戦:コンピュータはあきらめない

(画像は第2回将棋 電王戦 HUMAN VS COMPUTERより)
――そして、続いて2012年の3月~4月にかけて、おそらく最も多くの人が知っている電王戦の第二回が開かれました。第一局の阿部光瑠さん【※1】に始まって第五局の三浦弘行さん【※2】まで、名局と言えるかはわからないのですが、間違いなく名勝負の連続ではあって、電王戦そのものの光景が極まった形で現れたイベントでした。
※1 阿部光瑠
1994年生まれ、青森県出身の将棋棋士。2011年に16歳でプロ入り。2013年「第二回将棋電王戦」にてコンピュータ将棋ソフト「習甦」と対戦。先鋒として挑み、中盤以降で大差を付け、113手にて快勝した。オールラウンドプレイヤーとされており、居飛車から振り飛車までを得意戦法とする。
※2 三浦弘行
1974年生まれ、群馬県出身の将棋棋士。1992年に18歳でプロ入り。棋聖1期。2013年「第二回将棋電王戦」第五局にてコンピュータ将棋ソフト「GPS将棋」に対局を挑むも破れる。矢倉の脇システムなどの奥深い戦法を得意とする。
久保氏:
第一回でソフトに敗れた米長さんは、さほど動揺していないように見えました。ところが、第二回で敗れた佐藤慎一さん【※】や船江恒平さん【※】には、自分の棋士としての在り方をキープできなくなるほどの動揺が感じられました。ここに僕は非常に気になるものを感じて、一気に電王戦に興味を持つことになりました。
 |
※1 佐藤慎一
1982年生まれ、東京都出身の将棋棋士。2008年に26歳でプロ入り。2013年「第二回将棋電王戦」第五局にてコンピュータ将棋ソフト「Ponanza」と対局。将棋連盟公認の対局では現役棋士として初の敗北。中盤は優位に立つものの終盤で崩れ負けた。棋風は、じっくりとした指し回しが特徴。
※2 船江恒平
1987年生まれ、兵庫県出身の将棋棋士。2010年に23歳でプロ入り。2013年「第二回将棋電王戦」第三局にてコンピュータ将棋ソフト「ツツカナ」と対局し、敗れたが、同年の「電王戦リベンジマッチ」にて勝利を収める。過去に詰将棋の作者として、看寿賞を受賞している。
――当時のことを思い出すと、観客も「さすがにプロ棋士の側が勝つんだろう」とまだまだ思っていたし、解説棋士もそこに強烈な疑いはあまり差し挟んでいなかったように思うんです。ところが、その予断がガラガラと崩れ落ちていったのが、第二回電王戦だったように思います。
久保氏:
第一局の阿部vs習甦【※1】の対局は、まだ棋士の方が強いという予想を裏付ける感じがあったように思います。何よりも対局の進行として、「ソフトの側がちょっと良くないだろう」という手を指して、それを咎めて【※2】棋士が勝ったわけです。これは非常にわかりやすいですね。

(画像は第2回 将棋電王戦 第1局 阿部光瑠四段 vs 習甦より)
※1 習甦
2006年頃から趣味として竹内章が開発した将棋ソフト。プログラム名の由来は「評価関数群最適化」を意味する英名の略「Shueso」に漢字を当てたもの。2013年「第二回将棋電王戦」では阿部光瑠に破れる。2014年「第三回将棋電王戦」では菅井竜也に勝利する。
※2 咎めて
対局相手の疑問手・悪手を契機に攻勢に動くさまを指す将棋用語。
――我々「人間」が求める物語を提供した対局だったという感じでしょうか。
久保氏:
でも、阿部さんのその後の発言を見ると、かなりギリギリの戦いだったようです。例えば、阿部さんの「(コンピュータは)怖がらない、疲れない、勝ちたいと思わない、ボコボコにされても最後まであきらめない」という発言がありますよね。
――その後のAI将棋に対して、様々な棋士が発言した言葉の先取りですよね。
久保氏:
まあ、インタビュアーの編集で生まれた発言という可能性もあるので阿部さんご本人に確かめたいところですが、少なくとも彼の「あれはギリギリの勝負だった」という本音が強く込められた言葉があったのだとは思います。
SYNODOSの記事にも書きましたが、阿部さんが「咎めた」と言われている習甦三十四手目の△6五桂にしても、明らかな悪手ではありません。阿部さんはこの手について、「(自分がこの局面で習甦側を持っていれば)アマチュア五段程度の方にならまず勝つ自信がある」と発言しています。この言葉が示しているのは、「咎める」という表現は結果論でしか成立しない、ということです。咎めたくなる手があったとして、それを本当に「咎めた」というのは、優勢を築いてから初めて言えるわけです。

(画像は第2回 将棋電王戦 第1局 阿部光瑠四段 vs 習甦より)
ところが、人間vsソフトの文脈では、ハッキリしたミスや悪手を指したから「やっぱりソフトはダメだった」というわかりやすいストーリーを私たちは欲しくなってしまう。逆に言えば、終わってやっとそういう言葉が言える程度の、ギリギリの勝負だったということです。そのことがハッキリしたのが、現役棋士が初めてソフトに敗れた第二局だったんじゃないでしょうか。
――この第二局からが、まさに電王戦の幕開けとも言える展開でした。