 |
ゲーム語りの基礎教養第一回:
初代ドラクエはRPGへの逆風の中に生まれた――“ドラクエ以前”の国内RPG史に見る「苦闘」の歴史
ゲーム語りの基礎教養第二回:
ドラクエで堀井雄二はいかに“編集”したか?――初代ドラクエの「1泊2日観光ツアー」革命
さる10月21日、ついに厚いベールを脱いだ任天堂の新型ゲーム機「NX(開発名)」改めニンテンドースイッチ。そのビッグタイトルのひとつが、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』だ。この30周年を迎えた「ゼルダ」シリーズは、ゲーム市場を牽引し続けたアクションRPGというジャンルを象徴する存在でもある。

前回は初代『ドラゴンクエスト』(エニックス・1986)に至る国内・非アクションコンピュータRPG(以下、CRPG)の道のりを辿ってきた。80年代はじめ、海を渡ってやってきた海外CRPGというジャンル。その中でも人気の高かった『ウルティマ』(オリジン・1981)と『ウィザードリィ』(Sir-Tech・1981)の良いところどりをして、情報を整理するマルチウィンドウ、分かりやすいストーリーなど「ジャンプ漫画的」なアレンジを加えて誕生したのが初代『ドラクエ』だった。

そうした国内CRPGの歩みにおいて「ドラクエ型のCRPGと別れたもう一つの道」が、アクションRPG【※】だ。今回からは2回に分けて、今までほとんど語られてこなかった「アクションRPG」というジャンルの歴史を語ってみたい。まず今回は、『ゼルダの伝説』(任天堂・1986)登場までの歴史を語ってみたいと思う。
【※】アクションRPG
なお、本来は「アクションCRPG」と書くべきかもしれないが、ボードゲーム型のアクションRPGは原理的にありえないので、以下C=コンピュータを取った「アクションRPG」と表記している。
1984年はアクションRPG元年
そもそも80年代はじめ、日本は「アクションゲーム先進国」だった。
どのゲームが早く生まれたか、日本が先か海外が先かという時系列はさておき、この国で生まれたアクションゲーム『パックマン』(ナムコ・1980)が、国内のみならず世界中で大ブームを巻き起こし、「もっとも知られたゲーム」になったことは疑いない。その翌年の『ドンキーコング』(任天堂・1981)も、米国で発売された家庭用ハード「コレコビジョン」に移植されるや否や、本体の売上を後押ししてゲームハードの勢力図を揺るがすほどの影響力を持っていた。
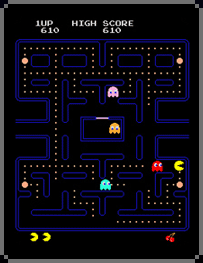
ヒットしたゲームとは「真似されるゲーム」――控えめに言えば、多くのフォロワーがあとに続くゲームのことだと言える。当時のゲームセンターは「最新ゲームのショールーム」でもあり、パソコンや家庭用ゲームハードにこぞって移植(あるいはインスパイア)されたゲームが作られた。『ドンキーコング』のキャラを●や■で置き換えた「勝手移植」は珍しくなかったし、その発想を元にしたゲームも次々現れたのだ。
そんなふうに、ゲーセンで盛んだったアクションゲームと、前回まで紹介してきたような、まだ日本に入ってきたばかりのRPGというジャンルとが融合した「アクションRPG」の登場は時間の問題だった。そして、その火ぶたは1984年、アーケードと家庭用パソコンゲームでほぼ同時に切って落とされた。前者が『ドルアーガの塔』(ナムコ・1984)、後者が『ハイドライド』(T&E SOFT・1984)だ。
成長を「アイテム」に置き換えた『ドルアーガの塔』
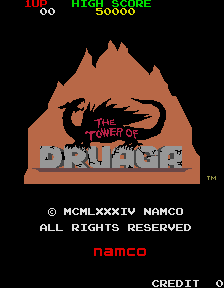
まずは、アーケードの『ドルアーガの塔』の話から始めたい。
このゲームは、その前年に『ゼビウス』(ナムコ・1983)の大ヒットで時の人となった気鋭のゲームクリエイター・遠藤雅伸氏が送り出したアーケードゲームだ。
今ではアクションRPGの元祖と言われているゲームだが、それは単純に年月でいうとこちらが先(7月稼働開始。『ハイドライド』は12月)だったこともあるし、生みの親ご本人が『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(Tactical Studies Rules・1974)の影響を語っていることもあるだろう。

だが、『ドルアーガの塔』をアクションRPGの原点に位置づけるのは、実はアクションRPGの定義に関わる話でもある。というのも、この『ドルアーガの塔』は、RPGの本質をアクションゲームの文脈に持ち込んだ作品なのだ。
『ドンキーコング』のマリオといいパックマンといい、アクションゲームの主人公たちは一時的にパワーアップしたが、一定の時間が経つと元に戻ってしまう。それに対して、『ドルアーガの塔』の主人公・ギルは、紛れもなく「成長」している――新たな剣をとれば攻撃力が、アーマーやシールドを取れば防御力がアップする。ステータスも表示こそされないが、頑丈なアーマーを拾うと、前はやられた敵の攻撃に耐えられるようになる。「成長」が隠し数値として存在しているのだ。
RPGの本質は「キャラクターの成長」だ。その意味ではギルは「成長する主人公」の条件をクリアしているのだ。成長とは、通常は「その姿を変え、能力を増していくこと」だ。変化して獲得された形質は保たれ、その上に変化が積み重なることを言う。
そして、そんなRPG的な「成長」はさらに抽象化して定義できる。RPGにおける成長とは「プレイヤーが利用できるリソースがどんどん変化していくこと(アイテムを失う、毒に犯されるなどマイナスのペナルティも含む)」なのだ。『ドルアーガの塔』では、画面下にジェットブーツやカッパーマトック、ホワイトネックレスなどがズラリと並び、それが使えるリソースが増えたのを表している。アクションゲームでこの発想が革新的だったことは、『ドンキーコング』どころか2年後の『スーパーマリオブラザーズ』でも、マリオのリソースが一面ごとに仕切り直しだったことからも分かるだろう。

そして、『ドルアーガの塔』で確立された「アクションRPGの条件」はもう一つある。
「敵に触れても一発では死なない」「体力あるかぎりキャラも生きている」という「ライフ制」だ。そもそも当時のアーケードでは「一撃死」は常識である。それ以前のアクションゲームやシューティングは――すべてのゲームを調べたわけではないので「なかった」と断言はできないが――「一撃死」ばかりだった。少なくとも、後続のゲームに影響を与えるぐらい成功を収めたアクションゲームでライフ制を採用したのは、『ドルアーガの塔』が初めてである。
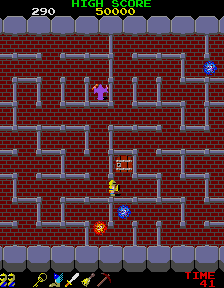
もちろん、厳しく言えば、『ドルアーガの塔』は剣を出さないまま敵に突っ込むと一撃死する。だが、それは「剣を出して敵とすれ違って攻撃」という基本アクションの習得にも繋がっている(「死んで覚えろ」だ)。また、このゲームにはレベルという概念もなく、強さや防御力などステータスの表示もなく、装備コマンドもない。今の考えで「RPG」とされている要素が色々と抜け落ちてもいる。それでもなお、この作品がアクションRPGの始祖と言われるのは、上記の「成長」や「ライフ制」などのRPGの大きな特徴を持ち合わせている点が大きいだろう。
アクションRPGの大衆化を先駆けた『ハイドライド』
今度は、家庭用パソコンゲームの側を見ていこう。
家庭で遊べるゲームにおいて、「アクションRPGの原点」とされるのが、1984年末に発売されたパソコンゲームの『ハイドライド』だ。それ以前にも、アクション性のある家庭用RPGはあったかもしれない。だが、このゲームが大ヒットして、今で言う「アクションRPG」のジャンルを根付かせた点については異論はないはずだと思う。
なにしろ当時、PCゲーム雑誌のランキングに2年間も留まり続け、「ハイドライド・シンドローム」と呼ばれたほどの影響力があったのは確かだからである。

主人公・ジムの目的は、3人の妖精にされたアン王女を見つけ出し、封印する宝石を探し出して悪魔バラリスを倒すこと。舞台はフェアリーランド。狭いフロアで立ち回る『ドルアーガの塔』とは違って、広い世界を歩き回り、そのあちこちにある迷宮に入ったりもする。今風にいうとオープンワールドだ。
そこで採用された「アクティブロールプレイング」と銘打たれたシステムは、後にアクションRPGの基礎となった要素をほぼ押さえているものだった。上下左右に移動できて、敵との戦いは体当たり。広いマップを走り回り、より強力な装備を身につけ、道を切り開くアイテムを集め、ラスボスに一歩ずつ近づいていく。もちろん、敵を倒すたびに経験値が得られ、一定量が貯まるとレベルアップするという「RPGの基本」もストレートに採用している。
だが、『ハイドライド』は、アクションRPGのジャンルにたまたま早く参入して、たまたま大ヒットしたのではない。
・「アクションの単純作業化」
・「経験値の見える化」
・「体力の自然回復(回復アイテムを使う面倒さの解決)」
という、それ以降のアクションRPGの基本要素を一度に確立してきたのだ。
例えば、このゲームの最大の発明は、「アクションを単純作業化したこと」だ。主人公のジムは剣を振ったりジャンプしたりせず、ただ体当りする。敵の強さによって「ATTACK」(攻撃)と「DEFENSE」(防御)のモードを切り替えるが、凝った操作は特にない。
それ以前のアクションゲームは、一体の敵を倒すだけでも反射神経を求められ、緊張を強いられた。短い時間でステージクリアするタイプのゲームならいいが、「より多くの敵」を倒して経験値を積み上げていくRPGとはどうにも相性が悪い。『ドルアーガの塔』は経験値をフロアアイテム(強力な装備)に置き換えて、この問題を回避していた。だが、広いフィールドを旅する『ハイドライド』では、「強力な装備を取るまでレベルアップお預け」とはいかない。そんな仕様にすると、敵の強いエリアでジムが瞬殺される。探索範囲をじりじり広げるオープンワールドには、「ちょっとずつ強く」していく単純作業の経験値稼ぎがピッタリだ。
とはいえ、単純作業は飽きる。刺し身の上にタンポポを乗せる仕事をいつまでも楽しいと思える人はめったにいない。そこで『ハイドライド』のもう一つの発明が、経験値とレベルアップの「見える化」だ。
メイン画面の横にLIFE(ライフ)とSTRENGTH(強さ)、EXP(経験値)のグラフを付けて、モンスターを倒すたびにEXPが少しずつ貯まり、メーター一杯になるとレベルアップという体にした。こうすることで、プレイヤーは単純作業が少しづつ報われ、レベルおよび強さ、ライフの成長が実感しやすい。

もう一つ重要な発明が「体力が自動回復する」【※1】ことだ。ジムは敵に触れずにフィールド上でじっとしていると、自然にライフが回復する。というより、それ以外の回復手段は基本的にはない。
RPGにおいて「成長」を形にする上で「体力」は欠かせない。が、体力があるということは、ダメージを受ければそれが減るということだ。そのときに回復手段はどうするのかという問題を、アクションゲームしか知らなかったユーザー向けに落とし込むのは意外に難しい。まだRPGの枠を超えて「ステータス画面」どころか「アイテムを使う」という概念そのものが広まってなかった頃(特殊武器を変更する『ロックマン』は1987年)なのだから。
こんなふうにアクション+RPGの楽しさをパッケージにして提供したのだから、2年も君臨し続けたのは当然だろう。
ちなみに、アクションの単純作業化は、ゲーム市場の中心がアーケードから家庭用にシフトしていく流れと寄り添っていた。アーケードは「一回○円」で収益を上げるため、「より短時間でプレイが完結する高い難度」と「上手い人が有利、下手な人は切り捨て」から成り立っていた。だが、家庭用はソフト買い切りであり、そこまで早くプレイヤーを「殺す」必要が薄い。それどころか、余りに難しいアクションは人を選び、売上の首を締める恐れさえある。その意味で単純作業にしてアクションの敷居を下げ、反射神経に関係なく平等に楽しめる『ハイドライド』の方向性は、「ゲームの大衆化」と一致していたのだ。
ただし、『ハイドライド』は決して易しいゲームじゃない。というのも、「謎解きの手がかりがない」のだ。後述の『ゼルダの伝説』のようにNPC(ノン・プレイヤー・キャラクター)との会話もない。どれだけ難しかったかは、クリアできない人向けに「ハイドライド手引申込書」が製品に付けられていたことからも(マニュアルを切り取る形だ)よく分かる。
つまり、『ハイドライド』も結局は「ゲームは難しくて当たり前」という風潮の中にあったのだ。その後も「ハイドライド」シリーズは、「ゲームは難しいもの」という方針を守り、続編の『ハイドライドII』はいっそう難解にした。その象徴が、クリアして表示されるパスワードを会社に送ると先着順にもらえた「終了認定証」だ。さらに初代『ハイドライド』をファミコンに移植した『ハイドライド・スペシャル』も、難しさは原作とほぼ同じだった。
そのため、『ハイドライド』は家庭用ユーザーの評判がいいとは言えなかった。分かりやすいインターフェイスで「ゲームの大衆化」を先駆けた『ハイドライド』が、「ゲームは易しく」という意味での大衆化の逆風にあったのは、少し皮肉な話だ。とはいえ、おかげでPCゲーム雑誌の攻略情報にニーズが高まり、ゲーム関連の出版物を定着させた貢献はあったかもしれない。
難解さが頂点に達した『ザナドゥ』
この事情は、この時代に登場したアクションゲームを語る上で欠かせない『ザナドゥ』(日本ファルコム・1985)にも響いている。
アクションRPGの「分かりやすさ」志向と、家庭用ゲーム機よりユーザー層の平均年齢が高いこともあって「難しさ」寄りとなった、80年代半ばの国内パソコンゲーム。その狭間で生まれた不思議な存在が「ザナドゥ」シリーズだった。

『ザナドゥ』は、「ドラゴンスレイヤー」シリーズの第2作だ。同じ作者・木屋善夫氏による前作『ドラゴンスレイヤー』も一応はアクションRPGに分類される(厳密にはリアルタイム性がないので微妙に違う)。だが、壁や家を移動させて拠点を作り、拾ったアイテムを成長させたりとパズル要素が強く、RPGどころか他のあらゆるゲームに近い存在がなかった。
それに対して、『ザナドゥ』は、前作と比べればアクションRPGらしい要素を備えていた。サイドビュー(横視点)のフィールドを歩き回り、戦闘ないしは塔(ダンジョン)に入るとトップビュー(見下ろし画面)に切り替わる。主人公は戦闘を繰り返すことで経験値を稼いでレベルアップし、強い防具や武器を集めて、最終的にはキングドラゴン・ガルシスを倒す。こう説明すると、特に変わったゲームとは思えないが、『ザナドゥ』の特徴は、そうした見かけにはない。

1985年末に発売された初代『ザナドゥ』の売上は約40万本。国内のパソコンゲームでこの記録を超えたものはないとされる、大ヒットゲームだ。しかし、開発・販売した日本ファルコムが手がけた続編やリメイクの他に、「ザナドゥ系」と呼ばれる他社のゲームはない。『ドラゴンクエスト』や『ハイドライド』のように影響を残すことなく、その系譜がこつ然とかき消えたのだ。よくネタにされるが、移植を思わせたファミコン版の『ファザナドゥ』(ハドソン・1987)も、似ても似つかないものだった。
理由は、その独特すぎるシステムにある。
『ザナドゥ』は「すべてのリソースが有限」である。『ドルアーガの塔』で、「アクションRPGの成長=プレイヤーが利用できるリソースが増えていくこと」と定義したが、このゲームのリソースには限りがある。モンスターの数もアイテムの総数も決まっていて、無限にわいたりしないのだ。
そのリソースを、主人公は割り振りしないといけない。武器で倒せば戦士レベルが、魔法で倒せば魔道士レベルが上がるが、どちらかに偏るとのちのち困る。そして武器・防具・アイテムにはすべて「熟練度」というパラメータがあり、使えば使うほど強くなる。が、武器で倒せばそれだけモンスターが減り、後で取った強力な武器が育てられない。防具は攻撃を受ければいいのでモンスターは減らないが、もちろん体力は減る。体力を回復するポーションを買うにはカネがかかるし、自然回復もできるが時間がかかる。すると食糧が減って、結局のところ食糧を買うカネが……。何から何まで「リソースの管理」がついて回るのだ。
逆にいえば、リソース管理さえできれば何をしようが自由だ。フラグにより移動が制約されることもなく、序盤から死ななければどこにだって行ける。いきなり最強に近い装備を取ってきて、有利なスタートを切ることだってできる。ただし、あちらに行っては死に、こちらで行き倒れ……というマップのあらましが分かった上で、低いレベルでぎりぎり買えるアイテムをそろえ、緻密な作戦を立てることが必要だ。
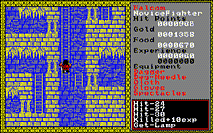
そこに当時のPCゲーマー達は挑戦心を燃やしたのも事実である。
『ザナドゥ』もまた、『ハイドライド』と同じようにPC用アクションRPGの頂点と限界を示したものだった。リソースを有限にした上で、その中でマネジメントをやりくりすれば何とかなる絶妙のバランス。そうした開発者とプレイヤーの高度な知能の戦いに、40万人以上の人々が参加したのは驚くべきことだし、攻略を支えるゲーム雑誌も共に成長していった。
しかし、安価なファミコンがゲームプレイヤーの年齢層を引き下げる中、知的に負荷の高い(ハイティーンでもきつかったはずだ)「リソース管理の戦い」で大きな市場をつかむのは難しかった。
アクションの「単純作業化」の点でもリソース管理の緩さにおいてもRPGは「易しさの時代」が近づいていた。
マリオとの差別化から来た「難易度の低下」
そんなときに登場したのが、1986年に登場した任天堂の『ゼルダの伝説』だった。

なにしろ、PC用アクションRPGになかった要素として、NPCのメッセージがある。 【ヒトリデハキケンジャ コレヲ サズケヨウ】や 【ユキドマリノキニハ ヒミツガアル】、【ナンカコウテクレヤ】……最後のはちょっと違うが、ダンマリを決めこんでいたアクションRPGが言葉でヒントを与えたことは、実は大きな転換点だった。長く迷わせたほうがいい、不親切こそがサービスという「業界の常識」がひっくり返されたのだ。
そんな『ゼルダの伝説』の発売は、初代『ドラゴンクエスト』に先駆けること3ヶ月前だった。ドラクエも初めはジワ売れで、人気に火がついたのはもっと先の話だ。まだファミコンでRPGブームが本格化する遥か前に、生みの親である宮本茂氏はどのようにして後にシリーズ化を重ねて世界的な大作となる初代『ゼルダ』を発想し、家庭用アクションRPGの始祖になったのだろう。
まず最初に一つ注目しておきたいのが、『ゼルダの伝説』がファミリーコンピュータ ディスクシステム【※2】用の第1弾ゲームだったことだ。

ディスクシステムは『ゼルダの伝説』と同じ86年2月に発売された。磁気ディスクによってソフトが供給され、それまでのROMカートリッジと違い、データを書き込むこともできた。その強みは、ざっくり言うと「大容量のセーブデータを書き込める」こと。両面合わせた容量は、当時のROMカセットの約3倍を誇り、電源を切ったあともセーブデータは保持できた。
実のところ、ディスクシステムは少々中途半端な代物ではあり、2年後には衰退してしまった。だが、アクションRPGは「冒険できる広大なエリアを収める容量」と「主人公の長時間にわたって成長させるためのセーブデータ」を必要とする。ディスクシステムは少なくとも1、2年は家庭用アクションRPGの成長を加速させ、16×8=128画面ものフィールドを冒険できる初代『ゼルダ』の誕生を促したのだ。
そして、そこで行われたのが初代『ゼルダの伝説』における、『スーパーマリオブラザーズ』との差別化だ。『スーパーマリオブラザーズ』は、ファミコンが発売から2年以上が経過して商品としての寿命が尽きるだろうということで、「カセットでの最後のゲーム」として作られていたという。それとディスクシステム用のゲーム、つまり『ゼルダの伝説』は同時進行で開発されていた。
初代『ゼルダ』は「ゴールに到達することに飽きてきた人たち」に向けて開発されたという。そのコンセプトに「どこにゴールがあるか分からないゲームなんか売れるわけがない」と猛反対されたという宮本氏は、主人公から剣を外して近くの洞窟におじいさんを配置し、「この先は危険じゃ」と剣を渡させた。そして次は盾、その次は……というふうにして「こういうゲームなんだ」と分かるようなゲームデザインにしたと語っている(DIGITAL CONTENT EXPO 2009での発言) 。
スーパーマリオは左から右にすすめばゴールが待っている(隠しステージはあるが、少なくともクリアはできる)。対して『ゼルダの伝説』は「ゴールをプレイヤーが探す」ゲームだ。これは『ゼルダ』以前の、なんの手がかりもなく世界に放り出されるPC用アクションRPGと似ているようで、大きく違う。その違いは、開発者にプレイヤーをゴールに導く意志があり、実際にガイドするゲームデザインが施されていることだ。
そのことは、ダンジョンに1~9の「レベル」を設定していることでも明らかだ。『ドラゴンクエスト』はフィールドを「橋」で区切って、それとなく敵の強さと進行度を仄めかしていたが、こちらはより直接的な「数字」だ。(プログラマでもあるが)文系的な堀井雄二氏に対して、工学的な宮本茂氏といったところだろうか。
ただし、初代『ゼルダ』の面白いところは、この「レベル」の順番には必ずしも従わなくても構わないことだろう。序盤はどのダンジョンから挑むのも自由。ただ、ある程度は攻略が進むと、必須のアイテムを取らなければ先に行けない……という風に、大きな枠の中での限られた自由になっている。野放しのようで「行き詰まったら手付かずのダンジョンヘ」という気づきが埋め込まれているのだ。

「ゼルダ」はアクションも「成長」する
そして初代『ゼルダ』をかたちづくる、最後のピースが「成長」だ。
例えば、画面下にジェットブーツやカッパーマトック、ホワイトネックレスなどがズラリと並ぶのは「成長」の証である。それは『ドルアーガの塔』と同じく、主人公が使えるリソース(資源)が増えたということになるからだ。(宮本氏はPCでRPGをプレイしている人達の会話から「成長」という要素に目をつけたと語っているが、「どのゲームをヒントにしたか」をぼかすため伝聞形にした……という憶測も成り立つかもしれない)。
主人公リンクの成長は主に「体力」と「装備」の2種類だ。どちらも「アイテムを取ること」で増強される点で、『ドルアーガの塔』と共通している。こちらも「剣を振る」、「敵の攻撃をシールドで受け止める」といったアクション性が高く、『ハイドライド』などの単純作業と対極にある。アクション性が高い(腕によって早解きもできる)ゲームは、プレイヤーの上手い下手を問わない単純作業型の経験値システムよりも、アイテム型の成長システムと相性がいいのだろう。

ここで「主に」と保留をつけたのは、体力や攻撃・防御いずれのカテゴリにも収まりきらない「Bボタンアイテム」があるからだ。
ブーメランや爆弾、弓矢などを取れば、たしかに主人公は強くなって「成長」する。が、これらは同時に「道を切り開く」機能も兼ね備えている。ブーメランは離れた敵を倒せるし(「敵を全滅させること」はダンジョンでは進行に必須だ)、弓でしか倒せない敵もいる。爆弾は文字通り壁を壊し、隠された通路を見つけられるようになる。つまり、『ゼルダの伝説』における「成長」とは、ただ攻撃力が高くなることではない。プレイヤーのできる操作が広がり、道を切り開く手段が増えることだ。
アクション性とRPG世界の広がりを、共に「成長」させる。この2つをアイテム一つでやってのけた初代『ゼルダ』は、宮本茂氏の語録にある「アイデアというのは複数の問題を一気に解決するものである」の最たる例だろう。
だが、「ゼルダの伝説」シリーズは、初代から「ゼルダとは何か」の核を確立した傑作ではあるし、後の他社ゲームに与えた影響も計り知れないが、決して万能の答えでもない。「スーパーマリオの宮本茂」の作品らしく、アクション性が高くやはりユーザーを選ぶからだ。そこで取りこぼされるユーザーには、経験値システムによる、単純作業型のいわゆる「レベルを上げて物理で殴る」タイプのニーズもある。
というわけで次回からは、今回とりあげた先行作品を受けて、国内のアクションRPGはどう進化していったのか、80年代後半の足取りを追っていく予定だ。
【※1】RPGにおける「体力」
このRPGらしさを考える上での「体力」の重要性は、逆の事例を考えることで、もっとわかりやすくなる。そこで取り上げたいのは、『頭脳戦艦ガル』(dB-SOFT・1985)だ。
本作は「スクロールRPG」を名乗ったばかりに、中村光一氏が「おかげでドラクエがファミコン初のRPGになれなかった」と嘆くことになったゲームだ。もっとも『ハイドライドスペシャル』が先に出ている(3月発売。初代ドラクエは5月)ので、どちらにせよ『ドラゴンクエスト』の「ファミコン初RPG」への道は閉ざされていたのだが。

『頭脳戦艦ガル』に対しては、ゲーム好きは「どこがRPGなんだ!」と突っ込むのがお約束のネタの一つになっている。誰もがRPGじゃないことに同意する作品だ。
だが、そのときに「ドラクエみたいじゃないから」というのは根拠として弱いのは言うまでもない。では、縦スクロールのシューティングだから……というのも、実は弱い。なぜなら、『スーパースターフォース 時空暦の秘密』を、「RPG」であることを否定する声は聞かないからだ。見かけの動きや、「弾を撃つ」というシステムは、RPGの本質とは関係がないのだ。しかも、『頭脳戦艦ガル』には一応「成長」があり、「一定数の敵機を撃墜する」毎にパワーアップしていく。全4段階の強化、つまり4レベルまであるということで、RPGの要素はなくはない。そんな数段階のパワーアップで良ければ、現代のシューティングはたいてい「RPG」なのではという疑問も湧くが、そもそも『ドラゴンクエスト』のヒット以降は「RPG的な要素」が他のジャンルに取り入れられた面が大きいはずだ。そして、当時まさにそういう先例がなかった頃ゆえに、『頭脳戦艦ガル』がRPGと自称しても許される雰囲気があった、ということが重要である。
では、なぜ現代の私たちは『頭脳戦艦ガル』をRPGと認められないのか。
それは「体力」の概念がないからだ。自機は敵弾ないし空中物や地形と触れると一発で死に、そこはそれ以前のアクションやシューティングと変わらないのだ。RPGにおける「体力」は、プレイヤーにキャラクターの成長を実感させる最も重要な要素だ。「一撃死」では、キャラクターの耐久力は変わらないままで、どれだけ生き延びるかは純粋にプレイヤーの腕前によってしまう。しかし「体力」はキャラクター自身が持つ属性であり、プレイヤーとは独立したもの。だからこそ「成長」の象徴になるのだ。
ちなみに、同じナムコの『ドラゴンバスター』(ナムコ・1985)も、剣と魔法と竜というファンタジーRPGそのものの世界観だが、やはり「体力上限の増加」が成長の象徴となっていた。アクションRPGの必要最小限の要素としての「利用できるリソースの“成長”」と「体力」は、こうして生まれたのである。
それにゲームのビッグサイズ化には、プレイの長時間化が付いてくる。電源を落とさずに続けろ、をいつまでもプレイヤーに強いることはできないし、セーブの需要もますます高まる。『ゼルダの伝説』から2年後に発売された『スーパーマリオブラザーズ3』も、説明書で「残念なことにバッテリーバックアップ機能がないため電源を切ると、また初めからのプレイになってしまいますが、コースのどこかに隠してある“笛”が何かの役に立つかと思います。」とフォローを入れていたぐらいだ。
【※2】ディスクシステム
採用した「ディスク」は、当時としても古臭い感のあったクイックディスクで、パソコンで一般的に使われていたフロッピーディスクより容量が小さかった。それにセーブデータの保存についても、翌年にはバッテリーバックアップ機能搭載のROMカートリッジが登場した。そんなわけで、ディスクシステムは2年後には早くも下火になっていた。「枯れた技術」を採用して価格を抑えたものの、枯れすぎていて寿命を縮めてしまったのだ。
ただ、家庭用ゲームの未来を先取りする上での方向性は正しかった。PCのフロッピーと比べて当時のROMカートリッジは容量が頭打ちになっていたが、ゲームが進化して規模が大きくなれば大容量化は避けられないからだ。
文/多根 清史


































