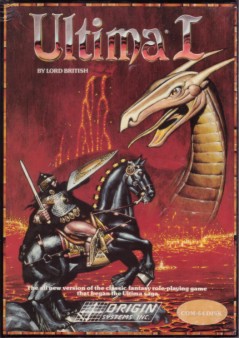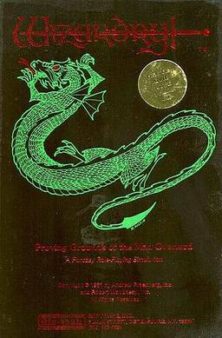ライトノベルの市場規模は、文庫本、単行本をまとめて約300億円市場と言われている。2015年がピークであったものの、その市場で息づく作品たちは、いまもつぎつぎとコミカライズ、アニメ化、ゲーム化されている状況だ。
そんな一大市場の始まりを考えたとき、コバルト文庫やソノラマ文庫など、いくつも言及すべきところはあるが、1980年代半ばに角川書店が創刊したパソコン誌『コンプティーク』に掲載されていた『ロードス島戦記』が、いまに繋がるライトノベル史の源流のひとつであることは衆目の一致するところだろう。
以来30年の時が経ち、書店の棚に、Webサイトに居並んでいるライトノベルを俯瞰すれば、その中心にいるのはいまなおKADOKAWAであることがわかる。
この流れを作った人物がいる。
それがこの記事で聞き手となっている佐藤辰男氏だ。

氏の立ち上げた、あるいは手掛けたものを見るといい。パソコン誌の黎明期にあって企画で異彩を放っていた『コンプティーク』誌の創刊、ライトノベルやいわゆるオタクコンテンツの一大潮流となったメディアワークス社と電撃ブランドの設立、そして巨大なコンテンツプロバイダーとなったKADOKAWAの統合推進など、いまあるオタク的な文化、とりわけ「ライトノベル」という文化シーンを作ったのが誰かと問われれば、まず間違いなくそのひとりとして佐藤氏の名前が挙がるのだ。
今回の記事ではライトノベルに注目し、佐藤氏に話を伺うのに最適な人物──同様に1980年代から現在にかけて、『週刊少年ジャンプ』、『Vジャンプ』という雑誌を軸に、また別の大きな文化の流れを担っていた人物──鳥嶋和彦氏を招き、聞き手をお願いすることとなった。
つまり、以前の記事の攻守が逆転した形だ。
【全文公開】伝説の漫画編集者マシリトはゲーム業界でも偉人だった! 鳥嶋和彦が語る「DQ」「FF」「クロノ・トリガー」誕生秘話
記事では、佐藤氏の経歴を振り返りつつ、ライトノベルはどういう経緯で大きなジャンルに成長したのか、ライトノベルの本質とは何か、それを送り出してきたKADOKAWAは出版業界の中でどういう役割を果たしてきたのか、そうした話を伺った。
一介の中堅出版社に過ぎなかった角川書店が、いかにして3大出版社に追いつき、そして4大出版社となるに至ったのか。佐藤氏の話からは、チャレンジャーとしての角川だったり、ほかの出版社と比べて異質なものとしてのKADOKAWAの姿が際立って見えてくるだろう。
同時に鳥嶋氏の視点を通じて、その背景にあるマンガ・アニメや『ジャンプ』の動向、出版社とテレビ局の関係、同時代の隣接的なジャンルがどういう変遷を遂げたかという大きな流れも語られている。
あの時期頂点にいて、間違いなくサブカルチャーを担っていたふたりが見ていた当時の景色を、この記事で読者の方々とともに垣間見られれば幸いだ。
今回の取材を行うにあたり、編集部が取材メモとして作成した年表を公開中です。
角川書店とKADOKAWA
記事中では、1945年に創業し2013年に至るまでの組織を「角川書店」(もしくは角川)と、2013年以降のアスキー・メディアワークス、エンターブレイン、角川学芸出版、角川書店、角川プロダクション、角川マガジンズ、富士見書房、メディアファクトリー、中経出版が合併してできた組織を「KADOKAWA」と表記している。
ドワンゴとの経営統合にあたって設立された持ち株会社は「カドカワ」としている。

いかにしてKADOKAWAは大手となったか
KADOKAWAとライトノベルの発祥
鳥嶋和彦(以下、鳥嶋)氏:
始めに話しておくけど、僕がライトノベルについて知っているのは、自分の仕事で関わったときどきの断片的な知識程度。だけど、そんな僕でも佐藤さんがライトノベルというジャンルを切り開いていまのKADOKAWAの礎を作ったことは知っているのに、それを佐藤さん自身は語っていないし、何よりもKADOKAWAが正しく評価していないんだよね(笑)。

佐藤辰男(以下、佐藤)氏:
評価していないってことはないかな(笑)。
鳥嶋氏:
(笑)。というふうに僕に思われているくらい、いまのKADOKAWAがどうやって形作られたのかを、佐藤さんがみずからきちっと語って残しておくのは大事なことなんじゃないかと思うんだ。少なくとも僕は聞きたいし読みたい。
ヒットした作品の中身について語られることはあっても、「全体がどう始まって、どうここまで来たのか」については、じつはあまり語られていないじゃない?
──そうですね。講談社、集英社、小学館という三大出版社の一角にKADOKAWAが入って四大出版社になっていく経緯と背景は絶対に面白くなる話です。
そこを鳥嶋さんに聞き手になっていただきながら、たとえば「『コンプティーク』や電撃文庫の立ち上げかたは、『週刊少年ジャンプ』や集英社のやりかたに照らし合わせるとどうだったのか」、「マンガやアニメ、ゲームなど当時の周辺の状況はどうだったのか」などの視点を含めて掘り下げていただければと思います。
鳥嶋氏:
なるほど。KADOKAWAの話を聞きながら、「いまのテレビではなぜメインの時間帯からアニメが消え、深夜やU局をKADOKAWAアニメが占めるようになったのか」など、そういう誰も知らないところを語ればいいのかな。
──ぜひお願いいたします。ライトノベルがなぜあんなに盛り上がったのかを、作家やヒット作の登場という表面的な話だけではなく、その背後にある市場の環境やパワーバランスなど、構造的な話を含めておふたりにしていただくことで、コンテンツを楽しんでいるだけの僕らにも、おふたりの見ている景色が垣間見られればと思います。
鳥嶋氏:
心得た。
佐藤氏:
では……そもそもの「KADOKAWAとライトノベル」という話からかな?

まず日本の出版界というのは、雑誌が中心なんです。その中でもとくに『週刊少年ジャンプ』、『週刊少年マガジン』、『週刊少年サンデー』などのマンガ誌や、『週刊文春』、『週刊新潮』などの総合週刊誌、女性誌、芸能誌などが王道で、いちばん大きなシェアを占めている。
これらを持っているから、集英社や講談社、小学館などは大手出版社たり得る。

(画像は今号のジャンプ情報|集英社『週刊少年ジャンプ』公式サイトより)
それに対してKADOKAWAの核となった角川書店は、1945年に始まる国史や国文学を扱う地味な書籍出版社だったんですが、角川春樹さん【※1】が角川文庫を売るために、「読んでから見るか 見てから読むか」というキャッチフレーズを掲げ、ある種のメディアミックスとして1976年に『犬神家の一族』で映画製作を始めたんだ。
それで飛躍するんだよね。

(画像は犬神家の一族(1976) : 角川映画より)
一方、こうした春樹さんの動きとは別に、角川歴彦さん【※2】の流れがある。歴彦さんは、アニメやゲームといった新しいジャンルに注目したんです。

角川書店創業者角川源義の長男。1965年に角川書店に入社。1971年に横溝正史ブームを仕掛け、1975年に父源義の死に伴い社長に就任。翌76年から映画製作を開始し、1980年代を中心に“角川映画”で一世を風靡する。93年に麻薬取締法などで逮捕に伴い退任。復帰後は角川春樹事務所を設立。
(Photo By Getty Images)

角川書店創業者角川源義の次男。1966年に角川書店入社。73年取締役、75年専務。『ザテレビジョン』、『東京ウォーカー』、『コンプティーク』など同社の雑誌事業を育て、92年に副社長となるが兄春樹と経営路線で対立し、1993年にメディアワークスを創業。同年の春樹氏退任に伴い、角川書店に顧問として復帰。その後社長に就任する。以降も角川書店のホールディングス化を進め、ホールディングスの代表取締役とCEOを退任後も、2013年のKADOKAWA統合や2014年のドワンゴとの経営統合(のちのカドカワ)においても、会長職や相談役を歴任している。
(Photo By Getty Images)
角川は文芸誌である『野性時代』(現『小説 野性時代』)を除けば、1980年代になってやっと雑誌に手をかけるんだ。まずは1982年の『ザテレビジョン』。
マンガも1985年の少女マンガ誌『月刊ASUKA』からかな。他社に比べてはるかに遅れたスタートなんです。
つまりスタートの時点で、王道の少年マンガや少女マンガ、総合週刊誌は大手にすでに寡占されていたため、大きな部数になったテレビ情報誌の『ザテレビジョン』も含め、そのあとに創刊したパソコン誌の『コンプティーク』(1983年)やアニメ誌の『月刊ニュータイプ』(1985年)など、すべてマニアックでマイナーなところから雑誌を始めざるを得なかったわけです。
──そこには「大手になりたいけどなれない」というジレンマがあったんですか?
佐藤氏:
大手に……「なりたくなかった」と言ったら嘘だな(笑)。やっぱり「なりたかった」と思うんだけど、「なれなかった」から独自路線を行き始めたんだ。
だから大手が「総合出版社」と名乗るのに対して、のちに角川は自分たちを「総合メディア企業」と言うんだよね。この言葉は、メディアミックスも意味しているし、出版と映像を手がけるという宣言でもある。
本質的にはディズニーのようなメディアコングロマリットとも言えるけど、自分たちでそこまで言うのはおこがましいので、「総合メディア企業」や「メガコンテンツプロバイダー」と言っているんだよね。
出版も映像もやりたい。そういうメディア企業になりたい。
だけどアメリカほど大規模にはできないから、「ニッチなものでやろう」となり、「ゲーム、アニメ、マンガのメディアミックスならできるだろう」というのが角川のコンセプトなんですよね。そこにいわゆるオタクの広がりがちょうど重なったから、いまのような形になったと。
鳥嶋氏:
歴彦さんは、アニメやゲームなどが好きだったのかな?
佐藤氏:
好きだったんだと思います。
もともと角川書店創立者の角川源義さんが俳人であり、本領である書籍以外に手を出さないという方針でいた。その源義さんが1975年に亡くなってから映画が始まったし、雑誌が創刊されていくんです。
歴彦さんが創刊していった雑誌のコンセプトは、「雑誌の種(seeds)になるものは、ブラウン管(=テレビ)のまわりにある」というもので、この考えから『ザテレビジョン』が生まれるんだよね。そのコンセプトの下で、僕が『コンプティーク』を立ち上げ、『ザテレビジョン』からは『月刊ニュータイプ』という雑誌が生まれていった。
鳥嶋氏:
『ニュータイプ』って、『ザテレビジョン』から生まれたんだ?
佐藤氏:
『ザテレビジョン』の別冊として始まっています。
 |
鳥嶋氏:
『機動戦士ガンダム』に「ニュータイプ」という言葉が出てきたのも、同じくらいの時期ですか?
佐藤氏:
1985年に『Zガンダム』の放送に合わせて創刊されているので、『ニュータイプ』という誌名は、まさに『ガンダム』から採っています。監督の富野(由悠季)さんからいただいたと聞いていますね。

(画像はAmazon.co.jp | 機動戦士Zガンダム メモリアルボックス Part.I (特装限定版) [Blu-ray] DVD・ブルーレイ – 飛田展男, 富野由悠季より)
そうして刊行されたそれぞれの雑誌の中に小説やマンガが載っていたんですよ。『コンプティーク』の中には、ライトノベルの源流となる『ロードス島戦記』【※1】などがあったし、後に刊行した『月刊コミックコンプ』(1988年)などのマンガ雑誌も、王道の少年マンガ誌ではなく、そのころ言われ始めた“おたく”に向けたマニア誌として、カルト的な人気のあった麻宮騎亜【※2】や伊東岳彦【※3】をフィーチャーしてスタートしたんだよね。

1986年から『コンプティーク』誌上に掲載された、『ダンジョンズ&ドラゴンズ』のプレイ紹介企画。当時グループSNEに所属していた水野良氏が小説化し、1988年に『ロードス島戦記 灰色の魔女』が角川文庫から刊行された。同年、ハミングバードソフトによりパソコンゲーム化。ほかにラジオドラマ、アニメビデオ、家庭用ゲーム機向けソフトなど、多数のメディアミックス作品が登場している。
(画像はAmazon.co.jp: ロードス島戦記 灰色の魔女 ORIGINAL EDITION (角川スニーカー文庫) eBook: 水野 良, 出渕 裕, 安田 均: Kindleストアより)
※2 麻宮騎亜……1963年生まれのマンガ家、アニメーター。1987年に『コンプティーク』掲載の『神星記ヴァグランツ』でデビュー。代表作に『コミックコンプ』掲載の『サイレントメビウス』、『怪傑蒸気探偵団』など。
※3 伊東岳彦……代表作に『コミックコンプ』掲載の『宇宙英雄物語』、『星方武侠アウトロースター』、『覇王大系リューナイト』などのあるマンガ家、イラストレーター、アニメーター。『ロードス島戦記』と同時期に『コンプティーク』で連載していた小説『聖エルザクルセイダーズ』の挿絵を「BLACK POINT」名義で担当。
スニーカー文庫の起こり
──その『ロードス島戦記』がどうやってスニーカー文庫に繋がっていくのでしょう?
佐藤氏:
まず角川は1986年に「ファンタジーフェア」という書き下ろしの文庫をリリースするフェアを展開したんだよ。当時の文庫は書き下ろしではなく、雑誌に連載されたものや、単行本として他社から出たものを譲り受けて出すのが普通だった。そんな時代に、オリジナル書き下ろしのフェアだったからか、これが大きく当たった。
そのファンタジーフェアの中に、僕らが作った『ロードス島戦記』などを入れていったことから、新しいジャンルとして“ゲームファンタジー小説”みたいなものが生まれてくるんだよね。
──ファンタジーフェアは、佐藤さんの企画だったんですか?
佐藤氏:
僕ではありません。僕よりひと世代上の人たちの企画ですね。
──本来であればバラバラになってしまう書籍を、束にして大きなプロモーションに乗せることで、孤立させない戦いかたをしたんですね。
鳥嶋氏:
それはさまざまな文庫がある中で、角川が「どう棚を確保して売るか」と考えたときに仕掛けた「横溝正史フェア」なんかと同じ考えかただよね。
オリジナルの書き下ろしオンリーにした必然性や理由は?
 |
佐藤氏:
それは当時、いわゆるファンタジー系の小説やコバルト系【※】の少女小説などが、新しいジャンルとして注目されていていたので、作家も新しく生み出したかったから。ただ、雑誌への掲載から始めていると時間がかかり過ぎるから、書き下ろしにすることで一挙に10作品などを展開したんです。
鳥嶋氏:
ボリュームが欲しかったからか。なるほど。
※コバルト系……
1965年に集英社が創設したジュニア小説の叢書コバルトブックスに源流をもつレーベルとその系統。1976年にコバルトシリーズとなり、少女向けの文学誌『小説ジュニア』(のちに『Cobalt』に改名)の掲載作品を中心に文庫化。1990年にコバルト文庫と改名し、その後も派生のレーベルを生みながら現在も続く。
──ボリュームがあれば、フェアを展開する本棚のスペースも増え、結局は書店でどれだけの面が押さえられるかという話に繋がるわけですね。
昔から疑問だったのは、たとえばマンガなどは雑誌での連載がそのままプロモーションになるから、認知度が高まって単行本が売れるわけですが、書き下ろしの小説などの場合はゼロからのスタート。売れる仕組みや構造が凄く不思議だったんですよね。
佐藤氏:
人気作家であれば書き下ろしは売れるんだよ。けど単行本でなく、いきなり文庫として書き下ろすのは、大量の部数を売る手法として当時も斬新だったと思います。
当時の状況で言うならコバルト系やSFファンタジー系が売れていたから少女小説やファンタジー小説を描きたい人たちがいて、彼らの書くものが新しいジャンルとして注目されていたという土壌がまずあった。
だけど当時の角川には雑誌がまだ『野性時代』しかなく、母体が脆弱だっだから、必然的にたくさんの作家に書き下ろしをお願いしたんです。すると人気ジャンルの人気作家の書き下ろしをドーンと平積みできるということで、書店に歓迎された。これが成功したので、ファンタジーフェアを毎年やる流れになっていったんだよ。
そうしてファンタジーが新しいジャンルとしてイケると判り、1987年に角川文庫の中に“青帯”というものができていく。昔は、帯の色でジャンルを分けていたので。
鳥嶋氏:
岩波文庫と一緒だ。海外文学は赤で、法律や政治経済が白みたいな。
佐藤氏:
そう。当時の角川文庫は、岩波文庫をひとつの規範にしていたので、現代日本文学のジャンル、通称“緑帯”の中からひとつのジャンルとして“青帯”が独立し、それが1989年にスニーカー文庫という名称に変わっていった。そのときに、それまでのSFやファンタジー、少女小説とは違う流れとして『ロードス島戦記』があったんです。
『ロードス島戦記』が鮮烈だったのは、テーブルトークRPGの『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(以下、『D&D』)【※】を母体にして、前提となる世界やルールを作り、その世界観でもって小説を書いたという点。これはそれまで誰もやっていなかった。

(画像は製品情報 | ダンジョンズ&ドラゴンズ日本語版公式ホームページより)
鳥嶋氏:
『ロードス島戦記』が登場したのは、ファミコンでRPGが出る前の時期なのかな?
佐藤氏:
いや、ファミコンはもう登場していた。パソコンRPGの時代でもあるね。『ロードス島戦記』の著者である水野良さんや、その師匠に当たる安田均さんは、『D&D』を自分たちのサークル、グループSNEで遊んでいた人たちです。
あのころは『コンプティーク』だけでなく、アスキーのパソコンゲーム誌『ログイン』でもRPGというものを新しいゲームとして紹介していた。『ログイン』では記事という形で取り上げていたけど、『コンプティーク』ではテーブルトークRPGのプレイの模様を再現する「リプレイ」という形で紹介したのが特徴で。
鳥嶋氏:
より解りやすくするために物語の形にしたんだね。じゃあ、挿絵なども結構工夫したはずだね。
佐藤氏:
ええ。出渕裕さん【※】に鉛筆画で描いてもらい、ファンタジーの質感を出したら、とても評判になったんです。
【『ロードス島戦記』出渕裕×『ペルソナ』副島成記:対談】「エルフの耳はなぜ長い?」次世代に受け継がれるビジュアル作りに隠された秘密を探る【新生・王道ファンタジーを求めて②】
※出渕裕
1958年生まれの、イラストレーター・漫画家・メカニックデザイナー・脚本家・監督など、多数の顔を持つクリエイター。1979年『闘将ダイモス』の敵ロボットデザインでデビュー。1986年から『コンプティーク』誌上で連載されていた『RPGリプレイ ロードス島戦記』のイラストを手がけ、小説『ロードス島戦記』のイラストも描く。『ガンダム』や『パトレイバー』シリーズ、スーパー戦隊シリーズなどの作品では、メカデザインやキャラクターデザインを手がけ、2002年にはテレビアニメ『ラーゼフォン』で初監督、2012年には『宇宙戦艦ヤマト』のリメイク版、『宇宙戦艦ヤマト2199』の総監督を務めた。
鳥嶋氏:
『指輪物語』に始まり、欧米で小説や『D&D』などボードゲームの形で楽しまれていたファンタジーものを、日本向けにリプレイの形で解りやすく紹介したと。それが始まりなんだね。
佐藤氏:
鳥嶋さんが堀井雄二さんたちと遊んでいたちょうどそのころ、彼らも『D&D』や『ウルティマ』、そして『ウィザードリィ』で遊んでいて、「こういうものを小説にしたら面白いよね」と思ったんだね。尖った人たちがそう思い始めた時期なんですよ。
『ウルティマ』(画像左)、『ウィザードリィ』(画像右)の海外版箱絵
(画像はWikipediaより)
鳥嶋氏:
僕らが「ドワーフ」や「エルフ」なんて単語を、まるで自分のもののように言っていた時期だね(笑)。
『ロードス島』は一度ボツになっている
佐藤氏:
『ロードス島戦記』はまずリプレイを記事とした。リプレイは会話で進むから、キャラクターがみんな若干おちゃらけていて、その楽しいやり取りが読者にウケたんですよね。
 |
それを水野さんが小説にするとき、担当だった吉田隆くんは、最初に上がってきた原稿を“ボツ”にしたんだよ。その理由は、水野さんがゲームのライブ感を原稿でも出してきたから。
それってつまりリプレイ記事と同じで、小説の体になっていなかったという判断だね。だから、「シリアスなファンタジーとして書いてみて」と書き直してもらったんだ。読んでもらうと判るけど、だから『ロードス島戦記』ってシリアスなんだよね。
その結果『ロードス島戦記』は、まず楽しげなテーブルトークのリプレイとして楽しみ、それからシリアスな小説として楽しみ、さらに小説とは時系列を入れ替えたような、こだわった映像としてのOVAを楽しむ、そういう作品になったんだよ。
鳥嶋氏:
それぞれのメディア特性に合わせた楽しみかたや、物語の展開をしたんだね。それにしても、最初の原稿をボツにするのは、相当勇気が要りますよ。だって、そのままでもそれなりに売れたと思うもの。
佐藤氏:
僕もそう思う。じつはそのとき『コンプティーク』では、たとえば『信長の野望』や『大戦略』など、いろいろなゲームのリプレイを掲載していたんですよ。それらはリプレイとしては読まれたけど、大ヒットにはならなかったんだよね。その試行錯誤のひとつなんです。
鳥嶋氏:
メディアミックスで、メディアごとに「どんなコンテンツや展開が合うか」と考えるのは正しいんだけど……なかなかやりにくいよね。楽じゃないし。
 |
佐藤氏:
『ロードス島戦記』がヒットしたのは、そういう部分を乗り越えて洗練されていたからという背景があったのかもね。
鳥嶋氏:
聞くと、「売れるべくして売れた」というのが解るね。もうちょっとイージーに売れたのかと思っていたけど(笑)。
佐藤氏:
頑張りましたよ。僕自身じゃなくて、僕の部下が頑張ったんだけどね(笑)。
鳥嶋氏:
でも、そのきっかけや土台を作ったのは佐藤さんだからね。
それにしても「新しいもの」というのは、それだけで吸引力を持つね。『ロードス島戦記』に熱中したティーンから20歳前後にかけての人たちって、いちばん感性が鋭い時期だから、絶えず新しいものを待っているし、新しいものが現れるとすぐに判るんだよね。
佐藤氏:
だからか『ロードス島戦記』が出たとき、読者たちに「僕も私も書きたい」という空気が出てきたんですよね。「待ってました」という空気でしたね。
 |
──リプレイの掲載って、単純なゲーム情報を載せるよりも労力がかかりませんか? なぜそうしたリプレイをあえてやったのでしょう?
佐藤氏:
正直に言えば、総合出版社には集英社や講談社などがいた一方で、ゲームやコンピュータの周辺にはアスキーがいて、情報だけだと敵わないんだよ。アスキーも巨大な出版社だったからね。
ゲーム情報誌の時代になっても、後から出てきた『Vジャンプ』が『ドラゴンクエスト』や『ドラゴンボール』を押さえていくし(笑)、それに対抗した『ファミ通』がそれ以外を押さえていたりしてさ。
「だったら角川は小説やマンガも作れるし文庫もあるので、自分たちでコンテンツを考えて作り、総体としてビジネスをしていこう」と切り替えざるを得なかったわけです。
鳥嶋氏:
それは僕らも凄く解る。『ファミマガ』や『ファミ通』などの専門誌に対して情報戦では勝てないから『ジャンプ』は『ドラクエ』で仕掛けることにしたんだよ。マンガ誌だからゲームの解析部隊なんて雇えないわけで。
佐藤氏:
当時はそういう戦争をしていたね。
鳥嶋氏:
そういう話を聞くと、角川は非常に辛抱強く粘り強く、「やれるところからやってみた」という手堅い印象を受けるね。大きなリスクは取らないように、やれるだけやって、目処がついたら一気にモノにしていく。手堅いくせに動き出すのは早い。動いたものに関しては、機を逸していないもんね。
佐藤氏:
素直に、情報戦では勝てないと思ったからね(笑)。
スニーカー文庫という名称
──初代『ドラゴンクエスト』と『ロードス島戦記』の発売が、どちらも同じ1986年なんですよね。
佐藤氏:
あのころ、尖った人たちがRPGを遊び、「この楽しさをみんなに伝えたい」と思った。そういう想いから水野さんが『ロードス島戦記』を書いたら、『コンプティーク』でライターをやっていた人たちが、「私もやりたい」と憧れたわけですよ。それで深沢美潮さんが『フォーチュン・クエスト』を、中村うさぎさんが『ゴクドーくん漫遊記』を書いたんです。
こうして『コンプティーク』の周囲から次々に才能が生まれ、スニーカー文庫のひとつの柱といえる“ゲームファンタジー”になっていった。
これは最初のファンタジーフェアの目玉だった『アルスラーン戦記』【※】のファンタジーとはまたひと味違うんですね。ゲームに触発された“新しいファンタジー”だった。
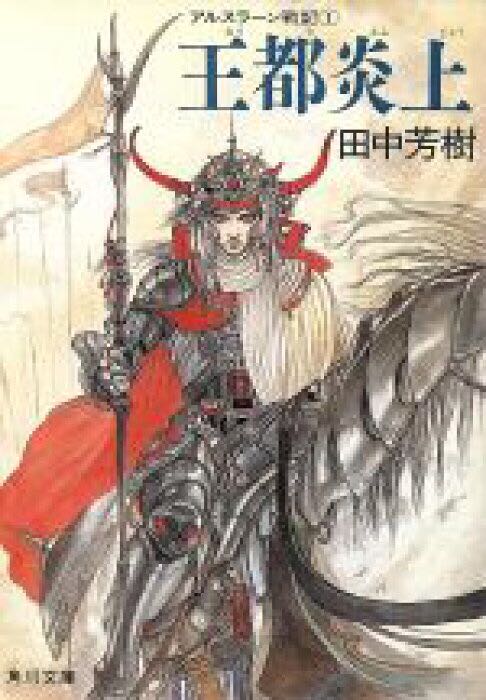
もうひとつの柱は、『月刊ニュータイプ』から生まれたアニメ系のもの。新しいアニメのライターたちと、新しいゲームをもとに話を書く作家たちが集結したのがスニーカー文庫だったわけです。
鳥嶋氏:
いまの成り立ちを聞くと、スニーカー文庫という名称に違和感を覚えるね(笑)。
おそらく青春小説や学園小説も入れないといけなかったんだね。それでラフなイメージを指す名前として“スニーカー”文庫になったんでしょ?
佐藤氏:
名称は公募ですが、スニーカー文庫を立ち上げた当時の編集長は角川書店の人で、彼としては少女小説のレーベルにしたかった。でも僕たち『コンプティーク』はゲームファンタジーを供給し、『月刊ニュータイプ』は『ガンダム』を供給したりして、極めてまとまりのない立ち上がりだったことがある意味問題だった(笑)。
 |
鳥嶋氏:
それぞれから出てきたものを勝手にハコに入れていったと。
じゃあ、入ってくるものとそれがどう売れたかによって、おのずとスニーカー文庫の性格が決まっていったんだ。
佐藤氏:
そう。『ガンダム』は当然強かったし、『ロードス島戦記』のような新しいゲームファンタジーも強くなっていったので、相対的に存在感を示す形にはなったけど、カラーそのものはバラバラだった。
鳥嶋氏:
それは非常に角川らしいよね(笑)。だけどそのハイブリットさが、その後のいろいろなことの柔軟性や強さに繋がっている気が凄くするね。
ラノベの行き詰まりと電撃文庫
佐藤氏:
ただそれから、あまりにもゲームファンタジーや『ガンダム』がずっと続き、業界として考えると、流れとして少し行き詰まったように見えた時期があってね。そこまではライトノベルもある種のジャンル小説や少年少女小説だったんだと思う。
そんなライトノベルに次の時代が来たのは、手前味噌な話なんだけど、やっぱり電撃文庫だったんじゃないかなと思うんですよ。
1993年に創刊した電撃文庫は、角川から跳び出て【※】創刊したレーベル。だから水野良さん、深沢美潮さん、あかほりさとるさん、中村うさぎさんの4人は、スニーカー文庫から出したものとは違う作品や、「新」という冠をタイトルに付けた作品を寄せてくれたんだ。
けれど、それ以外の人たちに手を出すわけにはいかなかったんだよね。
さらにその4人も、角川できちんと仕事をされていたので、そんなにたくさん書いてもらうわけにはいかなかった。そのため、新人を発掘せざるを得なかったんですよ。
鳥嶋氏:
まるで『ジャンプ』の始まりのようだね(笑)。
一同:
(笑)。
 |
※角川から跳び出て……1992年に角川歴彦氏の角川書店退社があり、翌1993年に歴彦氏は主婦の友社の協力を得てメディアワークスを創業している。その際に佐藤氏を含む旧・角川メディアオフィス(ゲーム・マンガ・アニメなどの雑誌を出版)の人員のほぼ全員が歴彦氏とともに退社し、メディアワークスに参加している。
佐藤氏:
新人を発掘するしかないから、「とにかく新人賞を始めよう」という話になり、1994年に「電撃小説大賞」の原型となる「電撃ゲーム小説大賞」が始まった。そのときに、「何でもいい」と、はっきりジャンルを問わなかったんですよ。
当時の富士見ファンタジア大賞などは、選考員の先生たちが非常に優秀かつ厳しいので、なかなか大賞を与えないんだけど、電撃文庫は大賞も与えるし、二人三脚で作家を育てるしかない状況なので、賞から外れた人も作家として育て始めるんだよね。
鳥嶋氏:
それは凄く解る。『ジャンプ』も手塚賞(ストーリーマンガ)や赤塚賞(ギャグマンガ)だと、審査員の方々がなかなか入選を出さないんですよ。だから育てたい相手は月例賞で入選させていた。
佐藤氏:
大賞を与えると「伸びない、育たない、驕る」というような理由で大賞を出さない、というのが多くの新人賞のパターンなんですよね。
鳥嶋氏:
それはたぶん嫉妬半分、強すぎる義務感半分ですよね。
佐藤氏:
強すぎる義務感だと思うね。そうした背景の中、SF系、ファンタジー系、ミステリー系、学園ラブコメなど、多彩な作品が電撃文庫から生まれたんです。
ファンタジア文庫と電撃文庫の棲み分け
鳥嶋氏:
ここでひとつ訊きたいんだけど、角川書店を筆頭に、富士見書房やメディアワークスなど、いくつもKADOKAWA傘下には会社があったじゃないですか。それだけあって、「なんでラノベをこんなにも同じ系列の中でやるんだろう?」というのが疑問で。僕から見ると意図や理由がよくわからないんだ。
佐藤氏:
それはある種の競争をさせているんですが、そもそも角川書店と富士見書房って不思議なことにわりと同種のものを平気でやるんです。そして競争して、やがて棲み分けるんです。
いまのKADOKAWAを構成するいろいろな会社の中に、最初は角川書店と富士見書房の2社しかなかったんだけれども、角川の青帯が1987年に始まって、富士見ファンタジア文庫が1988年に始まっている。ほぼ同時期なんだよね。
 |
スニーカー文庫は作品を供給する雑誌がバラバラで、新人賞もなかった。これを横目で見ていた富士見書房が、「その方法でレーベルを作れば強いだろう」と計画的に雑誌『ドラゴンマガジン』を立ち上げ、新人賞を謳って書き手を募集したんだ。
そうやって富士見ファンタジア文庫は計画的に設立され、その新人賞から神坂一さんの『スレイヤーズ!』(1989年)が生まれたりしてね、やっぱりガーッと伸びて結果を出すんですよ。

鳥嶋氏:
僕はそのあたりで、『ドラゴンマガジン』の存在を知ったんだよ。手に取って、「へー、こういうものなんだ」って。
ところで角川と富士見って、資本関係はあったわけですよね?
佐藤氏:
もちろん富士見は角川の100%子会社。ただ富士見書房だったものが、角川書店の富士見事業部になったり、また独立して富士見書房になったりするんだ(笑)。
さらに棲み分けの話をするなら、富士見ファンタジア文庫って、その名のとおりゲーム系のファンタジー小説ばかりだった。それに対して後発の電撃文庫というのは、SF系のものや、少しエッチなものなど、ジャンルとしてはちょっと違うものを意図的に入れていったんだよね。
だから棲み分けられたんだと思います。
──電撃って、それこそ「電撃ゲーム大賞」という名前で小説の大賞を開催しますが、そこで入賞するのは、いわゆるゲーム然としたジャンルじゃないものが多いですよね。あえて意図的にそういうSF文脈のようなものを取り込んだわけですね。
それにしてもKADOKAWAのライトノベルのヒット作って、言われてみると驚くほどSF色が強いんですよね。『涼宮ハルヒの憂鬱』しかり、『とある魔術の禁書目録』しかり。
佐藤氏:
結果としてはそうなんだけど、でもその始まりはたぶん偶然だと思う。
電撃大賞を催す前までは、前述の水野良さんやあかほりさとるさんなど、スニーカー文庫から来た作家が書いてくれたんだけど、1994年に初めて小説大賞をやったときに目立った入賞作がミステリー系の作品で……。
 |
鳥嶋氏:
ああそうか! その作品のヒットが流れを決めたんだ。
佐藤氏:
そう。その1作だけの影響ではないけど、そのあとかなりハイブローなSF系の小説が大賞を獲っていくんだよね。
賞の立ち上げからしばらくは「電撃ゲーム小説大賞」と、あえて「ゲーム」という言葉を付けていたんですが、それもあってか結構若い人たちも応募してきた。本当に最初のころは、作品のレベルになっていないようなものもいっぱいあったね。
鳥嶋氏:
そういう応募をしてくるのは、何歳くらいの人たちだったの?
佐藤氏:
たとえば第一回大賞の『五霊闘士オーキ伝』の作者の土門弘幸さんは、17歳くらいでしたね。

鳥嶋氏:
17歳か。若いなあ。
 |
佐藤氏:
当時は、SFクズ論争【※】と呼ばれる議論がSF界で起きる前後で、それまで活躍していた大きな名前のSF作家さんたちの時代が終わり、ある種のブームが去ったような状態だったんです。同時期に早川書房や徳間書店などの出版社どうしの争いもあり、SF全体が下降線をたどる結果になり、ジャンルとして終わったんじゃないかと思われていた。
※SFクズ論争……1997年2月に刊行された『本の雑誌』3月号の特集「この10年のSFはみんなクズだ!」が発端となって起こった論争。概要としては、日本のSF界が1970年代の華やかさを失い、90年代に至っては固定化されたファンに対してマニア化し、閉鎖的(=氷河期)となったという指摘とその反論で構成される。
そのころに電撃文庫でSF系の作家が現れたので、SFが好きな人も「電撃ゲーム小説大賞」に応募し始めた。そして第2回で『ブラックロッド』というサイバーパンクが入選し、「この賞は、ファンタジーもSFも取れるんだな」と認知されたと思うんです。

こうして電撃文庫は、いろいろなジャンルを抵抗なく受け入れるレーベルになっていったと。
ちなみにスニーカー文庫や富士見ファンタジア文庫は、ゲームファンタジーが売れていたので、その方面に特化していったんですよ。電撃文庫が新しいものを受け皿となっていった一方で。
鳥嶋氏:
行き場を失っていたSF作家たちがやって来たんだ。
佐藤氏:
既存の作家たちもそうなんですが、クズ論争の世代が落ち着いたあとの、新しい作品をSFで書きたいという人たちだね。市場はないけど、書きたい欲求を持っている人たち。
たとえばSFとミステリーをミックスしたようなスタイルの『ブギーポップは笑わない』(1997年)を書いた上遠野浩平くんとか。
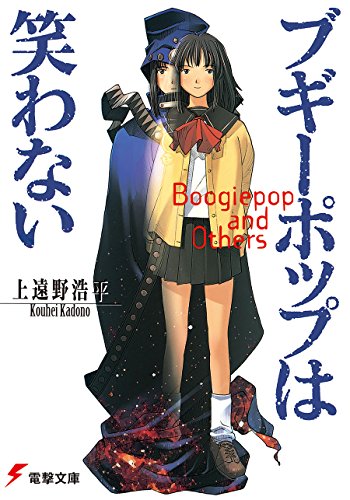
──なるほど。『コンプティーク』のときはファンタジーという文脈を取り込んで最初のライトノベルブームを起こし、電撃文庫のときはゲームに特化せずにSFの文脈を取り込むことで二度目のブームを起こしたんですね。
佐藤氏:
そうなるね。SFをきっかけに、ミステリー、ファンタジー、ホラー、青春、学園、ゲームなど「何でもアリだ」と、ジャンルを越えていったんだよ。
──電撃大賞がそうやって認知されてから応募してきた人たちの年齢層はどのくらいだったんですか?
佐藤氏:
『キノの旅』の時雨沢恵一さんや『ブギーポップは笑わない』の上遠野浩平さんは、20代後半だったかな(編集部注:刊行時で時雨沢氏は28歳、上遠野氏は29歳)。
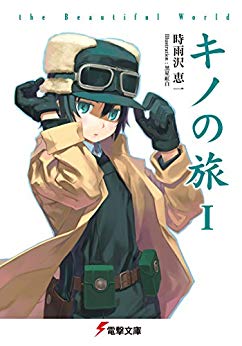
鳥嶋氏:
その彼らは、応募した時点で、もうプロとして活躍してた人たち?
佐藤氏:
いや、電撃文庫でデビューした。
鳥嶋氏:
じゃあ、広く知られるようになって、賞としてレベルが上がってきたということだよね。
佐藤氏:
そうですね。レベルはかなり上がったね。古くからファンタジーフェアがあったからか、ある種の作法というか、蓄積のある人たちがきちんとデビューし始めて。
 |
ライトノベルって一時は読み捨てみたいに言われていたけど、じつは文学性があって読み応えのあるものが充実していると初めて言ったのが、2004年に日経BP社から出た『ライトノベル完全読本』だった。
「それまでライトノベルは出版界の傍流のように言われていたけど、ひとつの大きな文芸ジャンルになった」とその本は宣言したんですよ。

ところがじつは当時はまだ業界でもラノベを知らない人のほうが多くてね。大手三社の新作の売上だと、普通なら紀伊國屋さんが書店1位を取るのに、角川だけはアニメイトが1位だったりした。
『ロードス島戦記』もそうだったし、『ブギーポップは笑わない』やアニメ化されるまでの『ハルヒ』もそうだった。もの凄く売れているのに、一部の人や中高生しか知らないジャンルだったんだよね。
ラノベの功績──SFの再発見
佐藤氏:
さらに編集者の中にも「ライトノベルは訳がわからん」、「ライトノベルとは呼ばれたくない」という人もいたんだけど……それまでエンターテインメント小説としてずっとあったSFやファンタジーなどのジャンルを、マンガの技術も使ってイラストレーションをきちんと入れ、カバーを美しくして中身を読みやすくしたことで、再発見させた功績があるから、ライトノベルというのはこれだけ大きくなったんじゃないかと僕は思うんですよ。
 |
──ライトノベルの盛り上がりの背景には、ある種の正当性があったように感じます。ニーズもそうですし、作家さんのクリエイティビティもそうですし。
ゼロから生まれたというよりは、既存のものを受け継いだうえでのブームということですよね。
佐藤氏:
そうそう。ちゃんとファンタジーやミステリー、そしてSFを再発見して、もう一回エンターテインメントに押し上げたのは、ライトノベルがあったからじゃないかって思います。ジャンル小説としてブームが去ったように言われていたものが、蘇った。
鳥嶋氏:
日本の小説って、編集と二人三脚で作らないんだよね。すると読者に近くならないから、結果的に面白くなく、小説が身近なものにならないんだ。これは佐藤さんも同意すると思うけど、日本の活字の本はつまらないんだよ。いわゆる20代、30代に読ませるための活字がない。あるものは“文学”とかそんな感じで、読めるものは相変わらず松本清張や司馬遼太郎などで。
佐藤氏:
それはそうだね。
鳥嶋氏:
挿絵と会話体の文章で、短時間で読ませたから、ライトノベルは読まれたんだね。
 |
そしてもうひとつ「あっ」と思ったのはSFってマンガじゃ当たらないという点。
その理由としてよく言われるのは、たとえば宇宙を描くとほとんどベタだったりしてマンガ映えしないということ。さらにSFはメカが中心なので、描くのに筆力が要る。すると、もともとジャンルとしても当たらないから編集部がさらに避けちゃうんだ。『ジャンプ』でも、諸星大二郎さんや星野宣之さんを除くと、ほとんど描いていないんだよ。
そういう意味で言うと、電撃文庫のライトノベルは空白の部分だったSFを上手く取り込んでいったのかなと思うね。
佐藤氏:
SF好きだった人が、ゲームにのめり込むパターンは多かったね。SF好きには先駆者気質がある。
鳥嶋氏:
コンテンツって、「需要がない」ことと「欲しいものがそこにない」が同じように見えるときがあるけど、欲しいものがないと思っていた読者に新しいものが「コレだ!」とウケて、一気に盛り上がることがある。電撃文庫は作り手と読者のタイミングが上手く合ったんでしょう。