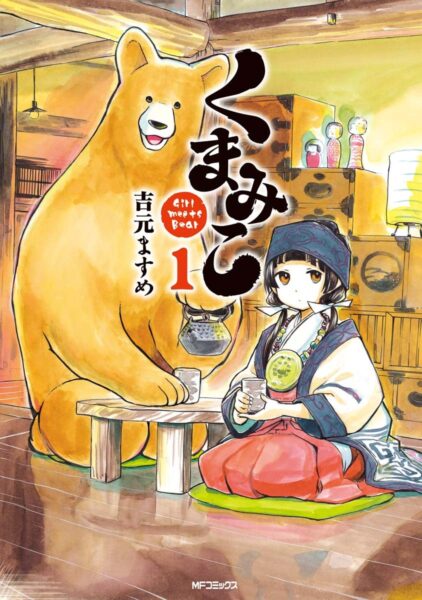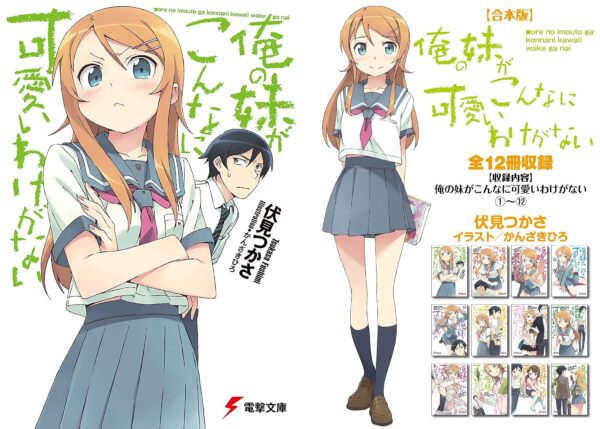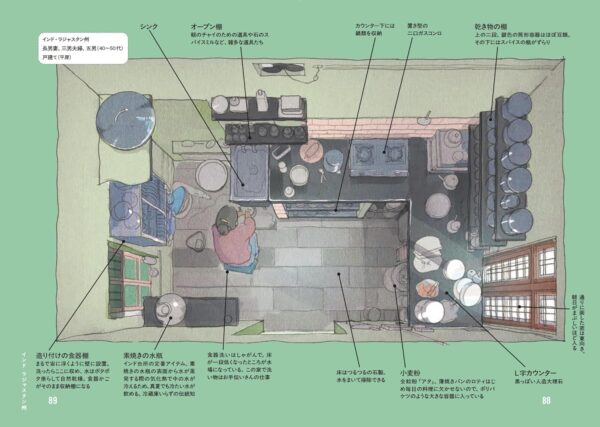2015年7月30日にサービスを開始し、10周年を迎えた『Fate/Grand Order』。
「TYPE-MOON作品がスマホで遊べる」という衝撃にくわえ、圧倒的なテキスト量、歴史上の人物を基に独自の解釈をくわえた多様なサーヴァントたちなど、本作は多面的な魅力で数々の「マスター」を生み出してきた。
そんな本作のこれまでの歩みを祝し、TYPE-MOONエースVOL.17では、数々の10周年記念特集が掲載されている。
総監督である奈須きのこ氏とリードキャラクターデザイナーの武内崇氏による2万5000字超えの対談を始め、FGOスタッフへのインタビューや、記念漫画などを多数収録、キャメロットのバルーンが付録として付属するなど、まさにてんこ盛りの「お祝い号」だ。
本サイトでは特別に、奈須きのこ氏、武内崇氏による対談の冒頭約7500字を掲載。
開発のきっかけや魔神柱との戦い、ヴォーティガーンの登場など、ユーザーと共に歩んだ10年間の「旅」について振り返る。
奈須きのこ
全体構成・メインシナリオ・シナリオ執筆・総監督
千葉県出身。TYPE-MOON作品全般のシナリオを手掛けてきた。『FGO』ではメインシナリオ&総監督としてライター陣を牽引する。武内崇
リードキャラクターデザイナー
千葉県出身。TYPE-MOONの代表を務めるクリエイター。『FGO』ではリードキャラクターデザインとアートクリエイティブディレクションを務める。
さまざまな「財産」を与えてくれた『FGO』
──『Fate/Grand Order』(以下『FGO』)ローンチ当時、奈須さんにインタビューさせていただいた際に本作のテーマを「旅」だとおっしゃっていたのを覚えています。
あれから『FGO』と共に歩んだ10年は開発陣にとっても長い「旅」になったのではないでしょうか。
奈須きのこ氏(以下、奈須氏):
『Fate/stay night』をはじめとする一連のシリーズは、主人公たちがいるひとつの街の中だけで完結していました。でも『FGO』は、時代を越えてさまざまな場所を訪れる世界規模の話になる。人理を守るという大きな目的のために世界を巡るのは、それこそ「旅」なのだと、当時は考えていたんです。
それがまさか、自分たちにとっても10年にもおよぶ旅になるとは……。我々にとっても『FGO』の制作はそれまで経験したことのない未知の領域へ踏み込んでいく「旅」でした。
武内崇氏(以下、武内氏):
いざここで「10年」という言葉を聞くと、本当に長い間この作品に関わっていたんだなと改めて思います。ものすごく濃密な日々でしたし、あっという間に過ぎ去っていった感じがしますね。
『Fate/stay night』をはじめとするTYPE-MOON内部で作っていたパッケージ作品とは違って、『FGO』はシナリオライター陣やイラストレーターの方々、ラセングルの開発チーム、そして宣伝スタッフなど本当に多くの人たちの協力のもとで作り上げてきた作品です。そういう意味では、『FGO』の制作は行く先々で仲間を増やしながら歩んできた旅だったように思います。
奈須氏:
仲間が多すぎて、画面に入りきらない(笑)。社内で完結するパッケージ作品は、作ってしまったら残る財産はその作品だけ。でも『FGO』は制作の過程で「多くの人とのつながり」というとてつもなく大きな宝を得られました。『FGO』には関わってくれた多くの仲間たちの思いが詰まっている。
武内氏:
この10年間は我々にとって「旅」でしたが、ローンチ当時から遊んでくださっているユーザーのみなさんにとっても『FGO』と共に歩んだ「旅」だったのではないでしょうか。
その「旅」という点で、我々とみなさんはゆるやかな共感を得ている気がするんです。開発陣はそんな旅の「終着点」に向けての歩みを進めていますが、その気持ちがユーザーの方々にも伝播していくといいなと思っています。
──「旅」を続けていくうちに背負い込む「荷物」も増えた結果、身軽さがなくなってしまったような感覚はありませんか?
奈須氏:
『FGO』に関わったことで、自分の人生・運命は大きく変わりました。関わってよかったかどうかは正直なところ50/50かなと。『FGO』と出会わなければ、もっといろいろなTYPE-MOON作品を生み出していたかもしれない。でも、現状はそれを補って余りある「財産」を得ている。
それは売上や知名度、人とのつながり、そして多くの人の協力で生み出してきたキャラクターたち。これほどたくさんのキャラクターをひとつの世界観・作品の中で描ける経験はほかにありません。
そして「身軽さがなくなったか」という質問については、明確に「否」です。身も心もつねに軽いですよ。軽くしておかないと激流に飲み込まれてしまうから。発想は軽く、やることは濃くを信条にしています。「今度の期間限定イベントはこんなことをやってみよう」とか「今度はこの方にキャラクターデザインをお願いしてみよう」という発想は、柔軟さと軽さがないとできませんからね。
武内氏:
その時々で新鮮さがないと、作っている方も気持ちが前へと進みませんからね。奈須からたびたび提示される小さな目標は、我々がつねにポジティブな気持ちで新しいことを楽しみながら挑戦できるきっかけにつながっていたように思います。
──たしかに、期間限定イベントやエイプリルフール企画は、ユーザーを楽しませるのと同時に開発スタッフも楽しみながら作っているのが伝わってきます。
スマホゲーム開発という新たな地平へ飛び出して
──初めてのスマホゲームの制作に挑むにあたって、開発陣としてもさまざまな試行錯誤があったと思います。開発当初はどのような作品をめざしていたのでしょうか。
奈須氏:
そもそものきっかけは、本作のプロデューサーのひとりである岩上敦宏さん【※1】からの「『Fate』でスマホゲームを作りたい」というムチャ振りでした。
自分はコンシューマゲーム大好き人間なんですが、サンプルとして遊んだ『チェインクロニクル』【※2】が大変面白かった。魅力的なキャラクターたちが多数登場する物語が、随時更新されてユーザーを飽きさせずにグイグイ引き込んでいく。このフォーマットで『Fate』を作ったら絶対に面白いものになるから、まずはやってみようかと。それで2016年いっぱいまでスマホゲームの開発に尽力して、2017年はまた違う作品に臨もう、という意気込みでいたんです。
でも、実際にローンチしてみたら思いのほか多くのユーザーからいい反応をもらえたし、シナリオライター陣や開発スタッフが一丸となってひとつの作品を作り上げていくのは、いちクリエイターとして大変刺激になりました。
ただ、1年目の『FGO』はゲームとしてあまりにも未熟な点が多かったし、そのぶん伸びしろもあった。また、多くのクリエイターさんから素晴らしいキャラクターのデザインを預かっていたので、絶対にこの作品を駄作で終わらせるわけにはいかない。必ずみんなが面白いと思える作品へと成長させていかなくてはならないと、2015年末に強く感じていました。
※1:岩上敦宏…アニプレックス代表取締役。数々のアニメプロデューサーを務める。
※2:チェインクロニクル…2013年に配信開始したオンラインカードバトルRPG。
武内氏:
スマホゲームユーザーに、特に昔からのTYPE-MOONファンのみなさんに受け入れてもらえるのか、ローンチするまでは不安でいっぱいでした。でもふたを開けてみたら、驚くほどたくさんの方から反応をいただけて正直ホッとしました。
新しいことへの挑戦がいい結果につながって安堵したのもありましたが、改めて振り返ると最初の1年はものすごい勢いで駆け抜けたなという印象しかありませんね。
奈須氏:
本来、20代後半くらいにきてほしい人生の大きな転機が、まさか40代に差し掛かってからくるとは……。まだ体力がギリギリ残っている年齢でよかった。
武内氏:
目標に向かってひたすら突き進んでいたガムシャラ感は、『月姫』や『Fate/stay night』を作っていたころに近いよね。
──第1部の途中から、シナリオとバトルのバランスが変わったのを明確に感じました。制作途中でバトルの頻度やシナリオのボリュームに関して軌道修正が行われたのでしょうか。
奈須氏:
制作当初は、今のようなシナリオ重視のゲームを考えていたんです。でも、当時ディレクターを務めていた庄司(顕仁)さんから「スマホゲームユーザー層にあわせて、もっとバトルを楽しませるものにしてほしい」という要望をもらって、シナリオを細かく分割して、間にバトルを差し挟む形にしました。
でもいざ『FGO』がローンチされたら「もっとじっくりシナリオを読ませてほしい」という声がたくさん届いたんです。それですでに納品してあった第4章以降は、シナリオ中に無理にバトルを差し挟むのはやめようと。
第5章は担当ライターと自分とで半々くらい受け持ってシナリオを書き直しましたが、第6~7章は当初構想していたものはユーザーの期待に沿うものではないと判断してお蔵入りにしつつ、僕の方ですべて書かせてもらうことにしたんです。


武内氏:
第6~7章はほかのライターが担当だったんだっけ?
奈須氏:
そうなんですよ。第6章の主軸になっていたのはオジマンディアスだけだったし、第7章は「大怪獣VSワルキューレ軍団」だった。でもここまでの盛り上がりを考えると、第1部終盤にふさわしくもっと壮大で複雑なものにしないと、ユーザーの期待に応えられないだろうと。
それで第6章を自分がやるなら、せっかくだから「円卓の騎士」の話を中心に持ってこよう。そして第7章も敵が大怪獣だけじゃなくて、「三女神同盟」と戦うものにして、メソポタミアを治めていたころのギルガメッシュの話にしようと。今思い返すと、第7章は直感的にアイディアを出して、そこにいろいろな要素を肉付けして物語を組み立てていった記憶があります。
武内氏:
先行してデザインがあがっていたエルキドゥも組み込まなくちゃいけない、という課題もあったよね。
奈須氏:
そうだったね。当時は小説『Fate/strange Fake』の刊行も始まっていたので、『FGO』であまりエルキドゥを活躍させてしまうと『Fake』の立場がない。それで「『FGO』にエルキドゥを出さなくてはいけないけど、エルキドゥを出せない」という、とんち問答みたいな問題が発生したんです。苦肉の策として編み出したのが、「エルキドゥの姿をした別人」であるキングゥというキャラクターでした。
武内氏:
キングゥはエルキドゥとはまた違った魅力をもつ存在になりましたね。また、第7章は「大怪獣と戦う」ということは以前から聞いていたので、我々開発陣もこれまでと比べて最大規模の戦いになるように気合いを入れて臨んでいました。
──第1部といえば、やはり終章での魔神柱との戦いが思い出深いです。全ユーザーが一丸となって最後の戦いに臨むという構想は、どの段階で思いついたんですか?
奈須氏:
それに関しては最初から考えていました。『チェインクロニクル』にもレイドバトルがあったんですが、最初にあれを経験したときに衝撃を受けまして。自分もスマホゲームを作るなら、ラストバトルで絶対に大規模なレイドバトルをやりたいと思っていたんです。2016年末にユーザーのみなさんと一緒に盛り上がれたのは、僕にとってもいい思い出です。
武内氏:
あのレイドバトルはトレンドにも上がったし、盛り上がり方が異常だったよね。ちょっと怖かった(笑)。
奈須氏:
素材のうまさに惹かれたユーザーたちが「魔神柱を倒せ!」と殺到して、こちらが想定していた以上のスピードで魔神柱を狩り倒していましたからね。たしかにストーリー上、一番盛り上がるポイントではあったけれど、アイテムの配布も含めたゲームバランスの妙もあの盛り上がりの一助を担っていました。
それまでの戦闘やイベントで得られるアイテムの分量をきちんと管理していたからこそ、あのレイドバトルでの大盤振る舞いにみんなが喜んだんです。
ストーリーを楽しみたいエンタメ欲と、素材を集めたいという物欲、そして年の瀬というタイミングの三拍子が重なってあの異常事態が起こったのでしょう。ネット上で「あっちの魔神柱のほうが素材おいしいらしいよ」などとニセ情報を流して、ほかのユーザーを誘導しようとする情報戦が繰り広げられたのも面白かったです。
武内氏:
年末という絶好のタイミングだったからこそ、あのお祭り騒ぎに至ったというのも大きいです。当時、第1部第7章が12月7日開幕で終章はその2週間後の12月22日スタートという超過密スケジュールだったので、さすがに間に合わないんじゃないかと思っていました。
しかし、当時のディレクターの塩川(洋介)さんが「終章は年内に絶対に実装をする」と、強い意思で開発スタッフを引っ張ってくれました。塩川さんの剛腕と高いモチベーションで頑張ってくださった開発スタッフがいなければ、あの大盛り上がりは実現できなかったでしょうね。

奈須氏:
たしかにあの頃の『FGO』の制作は、塩川さんが剛腕でグイグイ引っ張ってくれたからこそ成り立っていましたね。メインストーリーの進行だけでも大変だったけど、そのうえで期間限定イベントもやらなくてはいけない。開発スタッフ全員が火の車状態でしたが、本筋のメインストーリーと、ワチャワチャした茶番劇を描くイベント、どちらも『FGO』には欠かせない大切な要素なんです。利益のことだけを考えたら、小さなイベントを乱発して新キャラをバンバン出しさえすればいい。
でも、そんな中身のないものはすぐにユーザーに飽きられてしまう。だから『FGO』の世界観を描くメインストーリーを一番面白いものにしなければならないし、だからこそそこに付随するイベントも輝く。塩川さんがそうした我々の思いを尊重してくださったのは、『FGO』の方針を定めるうえでとても大きかったと思います。
武内氏:
塩川さんは「こういう作品を作りたい」という奈須の意思を制作の中心に据えてくださいましたし、その方針は現ディレクターのカノウヨシキさんにも受け継がれています。
『FGO』がずっとブレずにストーリー重視の作品であり続けるからこそ、従来のTYPE-MOONファンがついてきてくれているのでしょうし、新しく『FGO』に入ってくれたユーザーが新鮮に感じる部分なのだと思います。
ライター陣が自由な発想で取り組んだ1.5部
──1.5部はメインストーリーからは外れた「枝葉の物語」でありながらも、各章それぞれコミカライズされるなど高い人気と完成度を誇っていました。この1.5部はどういった経緯で作られることになったのでしょうか。
奈須:
2016年の8月くらいに、第1部が終わっても『FGO』はどうやら続くらしいということがわかりまして。ただ、すぐに第2部に入るには、開発側だけでなくユーザーにとっても準備期間が必要だと思い、第1部と第2部をつなぐエピソードを作ることにしたんです。
第1部の制作ではライター陣に「この章はこの時代を舞台にして、このキャラクターを登場させて物語を作ってほしい」と大まかな構成を提示して、僕の方で統括して監修することで全体に統一感を持たせていました。
でも1.5部はメインストーリーから独立した話なので、各ライターの個性を存分に出して好きに書いてもらうことにしたんです。いわばシナリオ執筆における「ガス抜き」ですね。それで自分担当キャラの武蔵が主人公の「英霊剣豪七番勝負」が他ライターとの合作になった以外は、各ライターにお任せという形を採ったんです。
──1.5部ではサーヴァントの正体を伏せた状態で物語が進行する「真名隠し」という試みもありましたね。
武内氏:
第2部を制作するにあたって「なるべく『Fate』らしさを残したい」という目標がありながらも、やりきれなかったことがいくつかありました。「真名隠し」はそのひとつです。『Fate』の面白さの要素はいくつかありますが、7騎のサーヴァントの正体が物語の進行とともに明かされていくところも、大きな部分を占めていたと思います。
『FGO』でもあのワクワクを表現したいと思って「真名隠し」というシステムを導入したんですが、うまくハマる部分とハマらない部分があって、恒常的に採用される要素にはなりませんでした。
奈須氏:
新規サーヴァントの真名を全部隠したら、その正体を追っていくので物語の大きな部分を割かれてしまいますからね。それにせっかくピックアップ召喚に登場しても、「誰?」となりかねない。
でも武内のやりたいこともわかるし、現状に満足せず新しいものを盛り込んでいきたい、という思いもありました。それで1.5部限定で「真名隠し」を導入したんです。
武内氏:
奈須はユーザーに新鮮なゲーム体験を提供するため、たびたび我々に「手を抜かずに考えるのをやめるなよ」とプレッシャーをかけるんです。奈須が率先して大小さまざまなアイディアを提案しやすい場を作ってくれているから、TYPE-MOONスタッフからもいろいろな声が集まるのだと思います。
奈須氏:
『FGO』は10年前にローンチされたゲームではありますが、せめて発想だけは新しいものを追求しながら、つねにユーザーに驚きと充実感を与え続けたい。そしてシナリオライターとしては、ストーリーテリングでユーザーをワクワクさせ、ゲームを通して夢と希望を提供したい。そのことを自分の中のテーマとして制作に臨んでいるんです。
──「真名隠し」は定着こそしませんでしたが、その後も正体を偽っていたサーヴァントの真名が「真名熔解」という形で判明する展開で生かされていますね。
奈須氏:
第2部第6章でオベロンの正体が明かされるところですね。みんなが「真名隠し」を忘れたころにやったら絶対に面白いだろうと思って、プリテンダーが実装されるまで隠していたんです。
──オベロンの正体が判明したとき、非常に驚いたのを覚えています。よもや「ヴォーティガーン」の名をここで見ることになるとは!と。
奈須氏:
「ヴォーティガーン」という名前については、『FGO』から入ったユーザーは「第2部第6章で急に出てきたけど誰?」と思ったでしょうね。なんせ『Fate/stay night[UBW]』Blu-ray BOX上巻の特典小説「Garden of Avalon」を読まれた方しかヴォーティガーンのことは知らないわけですから。ヴォーティガーンは最後のブリテンの守護者であり、生前のアーサー王=アルトリアにとって最大最強の敵でした。
いつか『FGO』でなんらかの形で登場させようと思って、ひそかに仕込んでおいたんです。でもアーサー王とヴォーティガーンの対決を、高価なBlu-ray BOXを買わないと読めないものにしてしまったのは、じつに申し訳ないと思っています。
話題は第2部、奏章、そして「FGO」10周年とその先についても語られた。
このつづきは発売中「TYPE-MOONエースVOL.17」にてご確認ください。