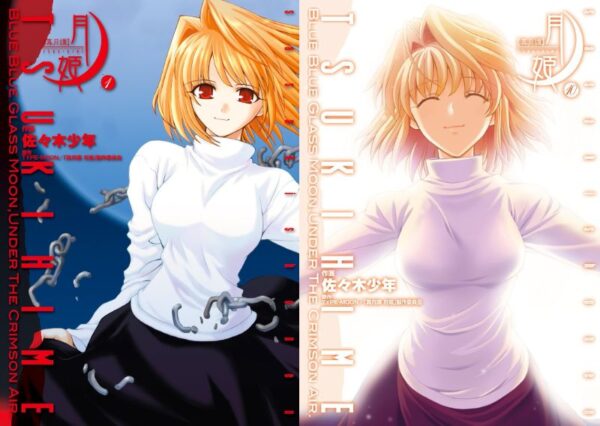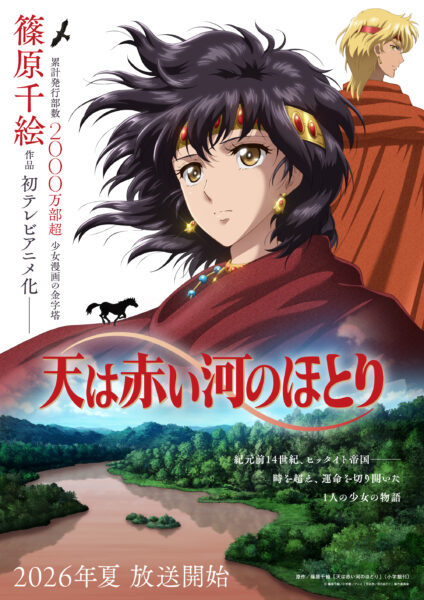マイクロソフトより10月22日に発売される、ハイスピードアクションゲームの『NINJA GAIDEN 4』。本作はTeam NINJAとプラチナゲームズがタッグを組んで開発が行われたことに加えて、シリーズとしても前作より約13年ぶりの新作ということで大きな注目を集めているタイトルだ。
最新のグラフィックや新たな技などの見どころも多いのだが、最も大きな変化は主人公がこれまでの「リュウ・ハヤブサ」から「ヤクモ」へと交代したところである。これにより、さらにアクションの幅も広がりつつも、これまでのシリーズの伝統をしっかりと受け継いだ作品に仕上げられている。
リリースに先駆けて、メディア向けの体験会が実施された。こちらでは、そのときに行われた開発陣へのインタビューとして、ディレクターの中尾裕治氏と平山正和氏、アートディレクターの西井智子氏、ステージディレクターの阿部雄大氏、リードコンポーザーの宮内雅央氏に直接お話を伺うことができた。こちらでは、その模様をご紹介する。
Team NINJA×プラチナゲームズだからこそ生まれたアイデアもあった──『NINJA GAIDEN 4』のディレクター中尾裕治氏と平山正和氏インタビュー
本稿で最初にご紹介するのは、『NINJA GAIDEN 4』のディレクターであるプラチナゲームズの中尾裕治氏とTeam NINJAの平山正和氏だ。

──13年ぶりに新作を作ろうとした時、最初に目指したところはどんなところだったのでしょうか?
平山正和氏(以下、平山氏):
どんな形であれ、『NINJA GAIDEN』らしさを感じていただくことが絶対に外せないポイントだと思っていました。これまでやってきたような理不尽と感じるようなシチュエーションであっても、超人アクションで乗り越えることができたり、多彩なアクションがプレイできたりするところは、一番大切にしていたところです。
今回は新主人公のヤクモが「鵺の型」を含めた、リュウができないようなアクションをできるようにしましたが、その中でも『NINJA GAIDEN』らしいフェアな攻防や超人らしいアクションは、絶対外さないように意識して作っています。
中尾裕治氏(以下、中尾氏):
『NINJA GAIDEN』らしさというところで言うと、前作から時間も経っていますし、我々プラチナゲームズが作るということもあるので、単に面白いアクションにするのではなく、すぐ手に取って『NINJA GAIDEN』だと感じてもらえるようなものを目指すという部分に関しては絶対に外さないと話し合いをした……というよりは、お互いに察したみたいな感じでしたね。
──ちなみに、『NINJA GAIDEN』らしさというのは、どのような部分をさすのでしょうか?
平山氏:
自分の中で特に感じているのはフルコントロール感といいますか、思った通りにキャラクターが動かせるところはすごく重要だと考えています。例えば、今自分がこういう風に攻めたいって思った時に思った通りの攻撃アクションが出るところもフェアな攻防だと思います。あとは忍者らしいグリップ感、手触りの良さみたいなところとかも、いわゆる自分の思った通りに動かせるからこそ実現できると思っています。
中尾氏:
それに加えて、アクションのサイクル部分がしっかりまとまっているというか、全ての行動に無駄がない。メリットデメリットがはっきりしており、それぞれどのようなシチュエーションでどのように使いこなしていくのかというところを緻密に設計されているのが『NINJA GAIDEN』です。そうしたところは、どんなに要素を追加したとしても外せない部分ですね。
──改めて13年ぶりに新作を開発することになった経緯やきっかけなどを教えていただけますか?
平山氏:
我々としても『NINJA GAIDEN』はすごく大切なIPとして考えています。Team NINJAとしても13年前からずっと作りたいと思っていたことは事実です。なかなか作るチャンスがなかった中で、弊社社長の鯉沼とプラチナゲームズ社長の稲葉さんが交流のある関係性だったということもあり、「一緒に作らないか」という話になったというのが始まりです。
その上でマイクロソフトのフィル・スペンサーさんからも声をかけいただき、3社でタッグを組んでやりましょうといったところがこのプロジェクトの経緯としてあります。『ベヨネッタ』シリーズや『ニーア』シリーズなどのアクションゲームを作っていることでリスペクトしているスタジオでもあったので、一緒にやりましょうという形で進めてきました。
──共同開発を行っていく中で新しく見えてきた点やメリットなどはございましたか?
中尾氏:
アクションを構築していくにあたり、それぞれ両者の強みが分かれているのかなと思っています。私の解釈としてTeam NINJAは、繊細なプレイフィールみたいなところを得意とされています。一方、プラチナゲームズはけっこう派手というか、ケレン味のある表現や気持ちよくなる動線の部分。抑圧と開放の仕組みが得意だと思っています。
そこが単にくっつくとバランスがすごく崩れてしまったり、『NINJA GAIDEN』らしさが薄れていったりするので、その組み合わせや濃淡の部分はいろいろ話し合って作っていきました。
平山氏:
我々が『NINJA GAIDEN 4』をTeam NINJAだけで作ったら、絶対出なかっただろうというアイデアは感じています。まさに、今おっしゃっていたダイナミックなケレン味みたいなところですね。今回でいうと「血楔」などは、なかなか我々だけでは出なかっただろうなと思います。
プラチナゲームズさんのそうした独創的でダイナミックなアイデアはなるべく取り入れつつも、『NINJA GAIDEN』シリーズとしてのシステムらしさが感じるようなポイントにしっかり落とし込んでいくことが重要だと考えました。
例えば鵺の型は、今までのリュウ・ハヤブサができたアクションではありませんが、実はそれを使うことによってより欠損しやすくなるというシステムがあります。鵺の型を使って欠損させて滅却して結界(旧作でいうエッセンス)が発生して絶技に繋げるといった、いわゆるシリーズならではのアクションサイクルは意識して協議しました。
──今回試遊した中で一番印象に残っているのが、難易度の幅が広くなっていたところです。こちらは両社の間で話し合いはされましたか?
平山氏:
前提としてですが、今回触ってもらった範囲は序盤のステージになので、後半になればなるほど『NINJA GAIDEN』らしい歯応えのあるバトルを感じていただけるようになっています。その上で、13年ぶりの発売というところもあり、初めて『NINJA GAIDEN』シリーズを触っていただくユーザーの皆さんもかなり多くいると思っています。
また、アクションゲームは好きだけど、当時は幼くてプレイしていなかったという方々も増えてきていると思っています。そのため、幅広い方に遊んでいただきたいということが方針としてありました。
今回は「NORMAL」の下の「HERO」という難易度を用意していますが、そちらは単純に簡単にするだけではなく、オートカードができる仕様が入っています。それがモードを通じてずっと有効というわけではなく、オプションでオフにすることもできます。
自分がちょっと上達してきたなと思ったら、オートガードを外して自分でガードするようにマニュアル操作にしてみようとか、プレイヤーがステップアップしていけるというような方針というのは実装しています。
幅広い人に遊んでいただきたいだけど、いわゆる『NINJA GAIDEN』らしい骨太のアクションや骨太のバトルも体験していただきたいので、あまり敬遠せず入っていただいき、ステップアップしてぜひ超人を目指していただきたいというのが、難易度設計としては考えています。
これまでのシリーズ同様でありますが、「HARD」以上の上位難易度もしっかりご用意しています。そちらに関しては、むしろ今までシリーズを遊んできた凄腕の皆さんでも歯応えが感じられるような難易度になっています。
──最高難易度の「MASTER NINJA」は難易度が途中で変更できないことに加えて、タイランの支援がないと書かれていました。この支援とは、死んだときにもらえるアイテムのことでしょうか?
中尾氏:
そうですね。基本的に高難易度になっていくと、タイランの支援と呼ばれているものはなくなります。よりハードになっていくことに加えて、難易度の違いとしては敵配置や敵AIの変更で、より強力な連携をしてきます。外側も内側の部分も可烈になっていくという形です。
──敵の攻撃もより狡猾になってくるんですか?
中尾氏:
そうなんです。
平山氏:
難易度が変えられないという部分に関しては、今回は専用ビルドとして最初からプレイできるようになっていましたが、ゲームを始めたタイミングでは「HERO」、「NORMAL」、「HARD」という3つのモードから難易度が選べ、これまでのシリーズとは異なり、道中で難易度も変えられるようにしています。
先ほどのステップアップの話に紐づきますが、チャプター1では「HERO」でやって、チャプター2では「NORMAL」で、チャプター3以降は「HARD」でやってみたいなことも、1周目でユーザーが上位難易度をチャレンジできるという仕組みを入れています。まず一周目はどんどん上達していただいて、クリアしてから最上位難易度にチャレンジできるような形になっています。そうした意味で、上位難易度の「MASTER NINJA」では難易度の変更できないといったのはそうした意図も含まれています。
──ちなみにステージクリア後にスコアと「下忍」などの評価が出ますが、あちらは何段階で決まるのでしょうか?
中尾氏:
あちらの評価は5種類です。
──主人公を新しく変えたのはシリーズ初心者に向けてのアピールも含まれていると思いますが、タイトルを『NINJA GAIDEN 4』にするのか、それとも全く新しいものにするのかといった議論はございましたか?
平山氏:
まず『NINJA GAIDEN 4』を作ること自体は決めていまいた。そうした中で、どんなタイトルにするのがいいんだろうというのが、どちらかというと入り口として近かったと思います。ヤクモを新主人公として出しましょうというのは、プラチナゲームズさんからアイデアをいただきました。我々としても、新規のユーザーに新しい気持ちでプレイしていただきたいというところがあり決めています。
ヤクモのアクションはリュウとは違う『NINJA GAIDEN』らしさが出ているようなところを感じていただけるように調整していくことは決めていました。今回はナンバリングとしてリュウ・ハヤブサがプレイできないのは違うだろうという気持ちもあり、ヤクモを新主人公にしつつリュウ・ハヤブサも登場させる、両軸でナンバリングとして挑戦していこうと決めました。
──リュウ・ハヤブサはシリーズの象徴のような存在ですが、過去作と今作で描き方などが変化した部分や、これまでの作品から継承してきたところはございますか?
中尾氏:
リュウ・ハヤブサはキャラクター的にいうと、すごく寡黙なイメージが僕はあります。リュウってこんな感じだったという印象自体は、今作においても崩さないようにしたいと思って描いています。
ただ、こだわったのはアクションで、これまでのリュウ・ハヤブサと同じ手触り感だけど、よりプレイしやすくするバランス感を整えるところにすごく力を入れています。一番大きな変化として付け加えたのが、ヤクモでいう「鵺の型」に相当するもので、「閃華状態」っていう新しい要素があり、そこでこれまでできていた忍法が自由に切り替えながらリアルタイムで出せます。あとは、超忍の奥義が繰り出せるようになり、リュウがさらにアッパーになっています。
──今回試遊した序盤では、リュウは敵対しているようなニュアンスでしたが、チャレンジモードではヤクモの代わりにリュウに切り替えて遊べるようになっていました。こちらは、ストーリーを進めていくことで、交互に操作できるようになるといった流れになるのでしょうか?
平山氏:
まずストーリーモードに関しては、後半に進んでいくとリュウを主人公としたチャプターがあるといったようなイメージが近いです。今回触っていただいたチャプターチャレンジは、クリア後に解禁されるモードになります。こちらは、ストーリーモードでヤクモが主人公のチャプターでも、全てリュウでプレイすることができます。なので、クリア後に全てのチャプターでヤクモとリュウの好きな方を選んでプレイできる要素が解禁されるというイメージですね。
──今回の試遊でどちらのキャラクターも触りましたが、リュウはアグレッシブに自分でガシガシ攻めていくみたいな操作性でした。一方、ヤクモはあらゆる状況に対応できるみたいな感じになっていました。それぞれのキャラクターの操作性やコンセプトで意識した部分はございますか?
中尾氏:
キーワードとしてアクション体験のイメージで考えていたのが、リュウはパワーでヤクモはスマートです。このふたつの対比を入れたいというのがひとつありました。全体的なプレイフィールはそこに集約されているかな、と思っています。
というのも、リュウとヤクモというふたりのキャラクターに対しては、世界観的な設定もそうですし、ルーツもそうですし、それこそ若くて未熟。それぞれ全体的な対比みたいなところを入れるようにしています。そこでヤクモの変化や、リュウはこんなキャラクターだよね、みたいなところを両方合わせて楽しんでいただければと思います。
両方に共通している部分もあって、それはキャラクター的なところでいうとクールなところや、寡黙であるところという、『NINJA GAIDEN』らしいところも備えています。アクションの体験に関しても、基本的なテクニック類は、両方に共通して使えるような状態にはなっています。
『NINJA GAIDEN』の原体験というか、プリミティブな体験を両方で味わってもらえる状態にしつつ、パワフルとスマートを分けているみたいな感じのイメージで作っています。
『NINJA GAIDEN 4』流の「血の流し方」とは? 白い衣装の敵を登場させることで「凄惨な状態にした」という達成感を演出
──『NINJA GAIDEN』シリーズというとゴア表現がありますが、今回は血しぶきが激しくなったような印象がありました。倒した時の爽快感や気持ちよさという部分で、どのようなこだわりがあったのでしょうか?
平山氏:
いわゆるバイオレンスな表現というのは、『NINJA GAIDEN』シリーズとしてハズしていないひとつの要素だと思っています。ただ、単純にグロテスクにするのはシリーズには全く合っていないと考えており、例えば切った時の斬撃の手触りの部分や、欠損した時のグリップ感みたいなところに紐づいたバイオレンスさが重要だと思っています。
プラチナゲームズさんの方から、血しぶきの部分に関してはこういうふうにしたいという提案をいただきました。それがまさに我々の考える『NINJA GAIDEN』らしいバイオレンスさに紐づくところです。斬撃した時によりスラッシュアクションらしい血しぶきの激しさや気持ちを繋げるところを伸ばしたいという話だったので、そこに関しては大きく意見がずれることなく、両社でそれを伸ばしていく要素として強化していきました。
中尾氏:
今回の血しぶきはすごく派手で、とにかく爽快なグロテスクさというかバイオレンスみたいなところを目指したので、そういう形の落とし込みになっています。その中でも、切った時の肉感やヒットの実体感をしっかりさせたかったので、攻撃を与えた時にヒットエフェクトはほとんど出さず、血や実際にあるもので表現し、必要であれば誇張してみたいなことをやって、より実体感を高めるような形でビジュアルに落とし込んでいます。
──序盤に出てくる敵は白い衣装を身につけているものが多く、戦っている時に血しぶきが付着して見えます。これはバイオレンスさを引き出すための工夫でしょうか?
平山氏:
そういう部分もイメージして作っています。バイオレンスさを強調したり、凄惨な状態にした達成感を出すために白くしていたりといった工夫はしています。
──アクションの手触り感の部分で、新しく技もいくつか追加されたかと思います。そうしたものを組み立ていくときにどのようなところにこだわって作りあげていったのでしょうか?
平山氏:
手触りに関しては、思い通りに動かせるように何度も調整をし続けることが重要だと思っています。このシチュエーションの時に入力が気持ちよくないというところを、どれだけ潰せるか。例えば、人によっての入力の癖みたいなのが結構あります。
着地した瞬間に何かボタンを押すというのを、同時に押せる人もいれば、少し遅れたタイミングでも押せない人がいます。そうした、ひとつひとつの部分を実機で触りながらやっていくことの積み重ねは、これまでのシリーズにあったアクションだけではなく、今回ヤクモで追加されたアクションでも達成しなければ『NINJA GAIDEN』らしさって出てきません。かなり地味な作業ではありますが、プラチナゲームズさんと細かい手触りの部分で協議させていただいたポイントです。
──それは、戦闘だけではなく、壁走りや飛鳥返しなど細かいアクション部分も含めてでしょか?
平山氏:
そうですね。あとは、スティックを少し入れた時に歩き出すのか? どのくらい倒したら走り出すのか? など、タッチ感みたいなところも大きく操作感に影響するところです。
中尾氏:
もう何から何までですね(笑)。着地の時の重力感もちょっと欲しいよね? みたいな話や、歩き始めのリアルな感じみたいなところを、スピード感の高いアクションの中でどこまで出せるかチューニングはすごくこだわっています。
──線路の上を移動するシーンがありましたが、これはどちらのアイデアで生まれたものなのでしょうか?
平山氏:
それこそまさにですが、やはりプラチナゲームズさんの独創的なアイデアだなと思うポイントでして、我々もあのレールは思いつかなかったなと思います。
中尾氏:
ちなみにあのレールアクションは、もちろん我々が入れたいなと思ったのもありつつですが、『NINJA GAIDEN』のこれまでの激しい戦闘の中で、戦闘と戦闘の間も道中で敵が出てきたり、どんどん強襲されていくシチュエーションというところがすごく止めどない感じがして、それが過去作の中でも良かった部分だなと思っています。それをさらに加速的にしていき、本当に息つく暇もない展開を表現したかったというところもあり、あのようなアクションを追加しました。
なので、プラチナゲームズっぽさを入れたいからレールを入れましたというよりも、そこがさらに『NINJA GAIDEN』ともマッチしてより面白くなるんじゃないかと考えて提案させていただきました。
──実際の東京をベースにしているところは存在しますか?
中尾氏:
実際の東京というよりは、『NINJA GAIDEN 2』に登場した東京魔天楼のエッセンスみたいなところは引き継いでいるつもりです。
今回、黒龍がムクロになって空に浮かんでいてみたいな流れなんですけど、その黒龍をどうにかしないといけないので、基本的には東京の中で行われる話になっています。ただロケーション自体はいろいろと用意しているので、実際の東京で言うと田舎の方みたい景色の違いは出しており、ずっと街中で戦っている感じではないので、そこはご安心いただければなと思います。
平山氏:
後半のステージは東京でありながら和風の神社っぽいステージがあったり、森があるステージがあったり、逆にちょっと地下の鬱蒼としたステージであったり、そういった感じでステージの変化は大きくなっていますね。
──中尾さんはシリーズ作品のファンとしても知られていますが、実際に自分が作る立場になって、率直にどのような心境ですか?
中尾氏:
発表する側としてこれを言うのもあれですが、「お待たせしました!」みたいな感じというよりは、僕も一緒に観客席に行って「来た!」という感じの気持ちですね。
往年のファンの方と同じような気持ちで、待ちわびていたものが作れるというところもあったので、緊張もありつつ、やはり自分の中で自信はありました。ファンとして深くやってきたというのがあって、そこは結構楽しく作れましたし、すごくいい経験になったなっていうふうに思います。ファンであるという熱意も伝えられたので十分です。
──ファンだからこそ大切にしている部分や本作において自分の中の『NINJA GAIDEN』の感覚を反映させた部分はございますか?
中尾氏:
今回は「絶技引導」が『NINJA GAIDEN 2』ぶりに復活していますが、いろんな過程を経てあれになったわけではなくて、まず軸足に据える作品をどれにしていくか決めるときに『NINJA GAIDEN 2』をベースにした仕組みやサイクルで考えていきたいと提案させていただいていました。
そうした元あったシステムでサイクルの中ですごく優れているものや、初代や『NINJA GAIDEN 3』からのいいところも入れたりして、とにかくプレイフィールドの中でファンとしてすごく良かったり好評だったりした部分は、どんどん取り入れてやっていくことを、ずっと意識しながら作っていました。それこそ、ほぼ毎日過去作を触っていたので(笑)。
──開発中で苦労されたところはどんなところでしょうか?
中尾氏:
手触りです。アクション面の手触りの部分は、もうずーっと話し合っていました。
平山氏:
ヤクモという主人公でリュウとは違うアクションがある中で、どういう風に忍者が遺伝らしさを感じてもらえるかというのは、すごくやりとりした部分でした。1年前のヤクモと現状だと、多分原型が無いまではいかないにして、もかなり別の手触りにはなっていますし、ここは本当に日々触りながらチューニングして合わせていったところですね。
中尾氏:
今作ならではの苦労の部分でいうと、『NINJA GAIDEN』はシリーズを重ねているタイトルであるため、ある程度アクションサイクルや仕組みは完成されているものかなという風に私としては感じています。その中で、今回の「鵺の型」やリュウでいうと「閃華状態」を追加するにあたり、ただアッパーにするだけでは限界が来ます。
それこそ『NINJA GAIDEN』特有の難しさや可烈な印象が薄れてしまうので、新しいシステムで楽しんでもらいつつも、元々あったサイクルの中に溶け込み簡単になりすぎない。逆に難しくなりすぎないみたいなところを目指していくのにすごく苦労しました。ここが一番時間かかったかもしれないですね。
平山氏:
今作の「鵺の型」は、ずっとあったアクションなんです。ただ開発初期段階で「鵺の型」を実装したときに、端的に言うとすごく猛威を振るっていた時代がありました。そうなってくると、『NINJA GAIDEN』らしい攻防剣撃で攻めて、滅却して、結界を出して攻めたり、体術的なものを使いながら多彩に攻めていったりするみたいなところが体験できなくなってしまっています。
「鵺の型」は振っていて面白いけど、『NINJA GAIDEN』らしいアクションかと言われると……という時代もあったりしました。「鵺の型」の良さは残しつつ、モードチェンジして戦えるのはアクションとして豊かな部分だと思います。その豊かな部分を残しながら、どのようにゲームサイクルに入れ込んでいくのかというところは、すごく時間かけました。
──ヤクモの武器をふたつ持たせるようにしたのは、アクションの幅を広げるためのものでしょうか?
中尾氏:
今回は過去作から進化して任意にリアルタイムで選べるようにしているのは、前作からすごく時間が経っているということもあり、プレイの幅広さを強化して進化させることが必須ということで、入れたものになりますね。
平山氏:
今回の試遊では専用ビルドとなっているので、2種類の武器のみの使用可能になっていました。ヤクモに関しては既に公開している棍やハンマーの武器種もありますし、それ以外の武器種も今後発表していければと思っています。
──久しぶりのシリーズ最新作ということで、これまでプレイしてきたファンだけではなく、本作から初めてプレイする新規ユーザーもいると思います。それぞれに対してどのようなアピールポイントがございますか?
中尾氏:
これから触っていただく方に対して伝えたいことは、やはりこの強襲されている苛烈さみたいなところです。本気で襲ってくる敵たちと本気で向き合うアクションゲームとしてのすごく磨かれたものを、『NINJA GAIDEN』は提供していきたいと思っています。
そうしたアクションゲームとしての質の高さみたいなところは、ぜひ触れていただきたいですね。アクション自体の豊富さや、選択肢の多さもウリのひとつです。本当の意味でプレイヤースキルを自由にカスタマイズしていきながら戦うところが、『NINJA GAIDEN』の面白さの際だった部分です。グリップ感のある気持ちのいいアクションができるところが、これからのユーザーに対してぜひ触って体験していただきたいですね。
『NINJA GAIDEN』という作品自体の間が空いてはいるものの、僕としては現体験みたいなところをすごく大事にして作ったつもりです。久しぶりに触っていただく方も、すぐにこれは『NINJA GAIDEN』だって思ってもらえますし、今回の「鵺の型」に関してもド派手なものとして追加はしていますが、『NINJA GAIDEN』らしい繊細さみたいなところはしっかりと守ったうえで入れているものにはなっています。
シリーズ経験者の方は、そういうところはご安心いただいて、『NINJA GAIDEN』のナンバリングとしてしっかり楽しんでいただければと思います。
──今回最高難易度の「MASTER NINJA」でボス戦を少しだけ遊ばせてもらいましたが、1回の攻撃で体力が8割ぐらい削られました。こちらは開発でクリアされた方はいらっしゃるのでしょうか?
平山氏:
そこはしっかりクリアしています。今回触っていただいたものは「MASTER NINJA」を開放していましたが、実際にプレイしていただくとアクセサリー的なもので防御力が上げられます。「MASTER NINJA」は2週目以降の解禁になるので、そうした部分も駆使しつつやっていただく必要があるというのが前提としてあります。
「MASTER NINJA」に関しては、ダメージ量での差別化は我々としても一番望んでいません。基本的にはクリアした後にプレイする難易度なので、アクション体験として変化がないと同じステージで遊んでいただくうえでも難しいと思っています。
詳細に説明すると「MASTER NINJA」に関しては、敵の強さだけではなく、配置される敵の種類と敵のAIみたいなのが変わっていきます。そうしたアクションの変化を楽しんでいただきつつ、より骨ごとなバトルができるところを目指して開発しています。
中尾氏:
一点補足すると、今回のプレイしていただいたビルドは、プレイヤーのHPがほどほどの状態ぐらいにしているので、最終的にHPの最大値を上げることができます。一撃で8割削られるのは、今回の体力ではそうですが、辛いことは辛いものの、実際はそうならないと思います(笑)。
平山氏:
探索要素で見つけたアイテムを集めることでHPの最大値を増やすことができるシステム自体はあるので、そういったことで育てていただいたうえで2周目以降に「MASTER NINJA」になるので、強化した状態でプレイしていただけます。
──最後に本作の発売を楽しみにしているファンにメッセージをお願いします!
平山氏:
十数年ぶりに『NINJA GAIDEN 4』というタイトルを発表できたことを、大変嬉しく思っております。今は誠意開発中ではありますが、ヤクモに関しましてもリュウとは違う手触りの中で、『NINJA GAIDEN』らしさをしっかり大切にして開発しています。もちろんシリーズならではのリュウも、プレイアブルとして遊ぶことができますので楽しみにしていてください。
また、アクションゲームが得意ではない方から超人の皆様まで幅広い内容で用意していますので、ご興味のある方は手に取っていただければと思います。
中尾氏:
手触りの部分は、本当に『NINJA GAIDEN』らしさを追い求めて作ったつもりです。我々プラチナゲームズが作りつつも、この作品が『NINJA GAIDEN』であることは始めから最後まで忘れずにやってきたので守れていたことでもあります
いろいろ追加された要素はありますし、間も空いて期待や不安がある方も多いと思います。全てにおいていえるのは、『NINJA GAIDEN』らしいものはしっかり作ってきました。触って早々に「あっ、『NINJA GAIDEN』久しぶりだな!」という感じになっていただけると思います。
──ありがとうございました!