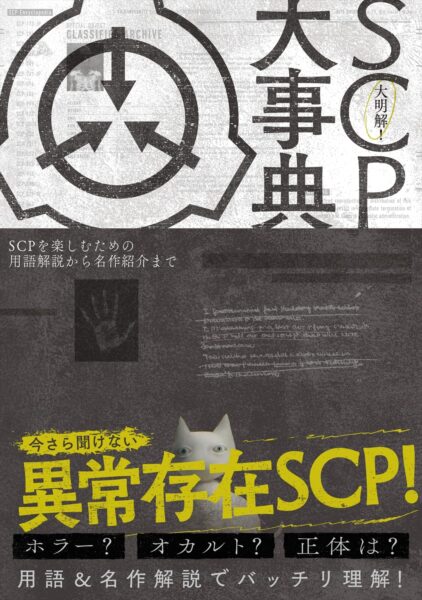佐藤さんという“目利き”
玩具業界紙から角川書店へ
鳥嶋氏:
ここまでKADOKAWAやライトノベルの話を伺い、マンガやアニメの話をしたけど、そろそろ佐藤さん本人の、編集者としての話を聞きたいな。
(略歴を見ながら)……佐藤さんの略歴って、変化に富んでいるよね(笑)。
佐藤氏:
ですか? ですよねえ(笑)。
鳥嶋氏:
僕はこの4分の1ほどで収まるからさ(笑)。
 |
──(笑)。そもそも佐藤さんが出版を意識したのは、いつでしょうか?
佐藤氏:
僕は出版社に入りたくていろいろ受けたんですけど、全部落ちたんだよね。時代のせいにするつもりはないんだけど(笑)。
鳥嶋氏:
いや、時代のせいにしようよ(笑)。厳しかったもの。
佐藤氏:
じゃあいいか(笑)。1976年に大学を卒業したんだけど、オイルショック(1973年・第一次)の余波で、当時は新卒を全然採ってくれない時代だった。名だたる出版社、それこそ集英社を含めて受けて、全部落ちてね。それでおもちゃの業界紙に入りました。
ちょうどそのころ、任天堂からカラーテレビゲーム15(1977年)がとても新鮮なおもちゃとして登場したんだよね。

そういうファミコン前夜の時代に、僕はおもちゃ業界にいた。アメリカでCES(コンシューマ・エレクトロニクス・ショウ)という家庭用の電気製品見本市があるとそこに行き、見聞してきたことを講演会で話したりね。
僕が前座でアメリカの情報を話すんだけど、メインは任天堂の山内溥さんだったりして。阪急百貨店でそういうものをやって、業界で結構大ウケだった記憶があります。
鳥嶋氏:
意外と高い会費を取るような?(笑)
佐藤氏:
そうそう(笑)。それがファミコン前年の1982年かな。その年に、トミーが“ぴゅう太”を発売してね。翌年にはバンダイがアルカディアやRX-78を出したり、ちょうどテレビゲーム戦争のさなかだったんだよ。それがその夏にファミリーコンピュータが出ると、数年かけて全部そこに収斂していくんだけど。

こうしてちょうどテレビゲーム機やホビーパソコンが過熱してきた時代を見ていたから、人に角川書店を紹介してもらったとき、ゲーム雑誌の企画書を出したんだよね。
鳥嶋氏:
繋がっているねえ。
佐藤氏:
そうなんですよ。それで「やってみるか」という話になった。
 |
鳥嶋氏:
すると佐藤さんは、書籍の出版社だった角川に雑誌の企画を持ち込んで入ったんだね。角川の本来の在りかたとは違うんだね。
佐藤氏:
ところがその1982年の角川は、ちょうど『ザテレビジョン』が創刊されたあと。雑誌を始めたところだったんです。
つまり春樹さんが映画を作っている一方で、先ほども言ったように歴彦さんが雑誌に夢を持って『ザテレビジョン』を始め、『コンプティーク』や『ニュータイプ』、それから『ビデオでーた』などを次々と創刊していく時代。その中で『ロードス島戦記』をはじめ、マンガやら小説なども手掛けられていく。
鳥嶋氏:
角川がメディアミックスで風雲児となったころだね。
佐藤氏:
角川の基本はやはりメディアミックスでしたね。僕はメディアミックスという手法をそこで学んだんでしょうね。
目利きとしての佐藤さんの凄さ
鳥嶋氏:
そう言えば訊きたいことがあって。角川書店がいろいろな会社を吸収合併していったのは、どうして? メディアミックスのため?
 |
佐藤氏:
偶然もあるんですけど、一緒になる相手には、自分たちの強い方面のメディアミックスをさらに強化する、映像とオタク系をやっぱり選んでいるんですよね。映画にしても大映であったり日本ヘラルドであったり。その一方で出版は、いちばん最初はメディアワークスだけど、アスキー、エンターブレインにメディアファクトリーでしょ。これらはどこもライトノベルとマンガをやってる出版社ですよ。逆に言えばそうじゃないと成功しませんよね。
鳥嶋氏:
のちに小学館の最高顧問を務めている白井さん(白井勝也氏)が、ある日、落ち込んでいたのよ。というのも、『ポケモン』のカードを展開していたメディアファクトリーを、首脳部とも知り合いだし、小学館で買いたかったんだって。そしていざメディアファクトリーが売りに出るのが決まったときにベットしたら、角川に負けてしまったんだって。
佐藤氏:
角川は、そのときもの凄く張ったんですよ(笑)。
張ったけど、結果的にKADOKAWAの中で見合うだけの重要な役割を担っていますよね。
鳥嶋氏:
そのあと、たとえばドワンゴとの知り合いかたとか、その後の関わりかたとか、ああいう佐藤さんの目利きや勘はどこから来ているの?
佐藤氏:
ドワンゴは……偶然ですよね。それこそドワンゴが株式公開する前、着メロの時代に、その中に友達がいたので、それで知り合っただけですよ。だからその縁で、監査役をやったり取締役をやっていたんだけど。
 |
もちろん、社長になってから、「『ザテレビジョン』や『東京ウォーカー』などで一緒に何かできないものか」と提案したことはありましたよ。
でもそれはやっぱり、何かが生まれてくるような新鮮さを、あのときのドワンゴは持っていて、実際に新しい才能も生まれていたし、紙の媒体にはないメディア力もあったから。
鳥嶋氏:
つまり、面白そうだった?
佐藤氏:
そう、面白そうだったんです。
──失礼な訊きかたになりますが、なぜドワンゴだったんですか?当時のドワンゴはとくに、まともじゃないじゃないですか。それなのに数あるIT企業の中で深くやり取りしようと思った相手がドワンゴだったというのは、何か理由があるだろうし、それはやっぱり佐藤さんの目利きだったのかなと思うわけです。
佐藤氏:
知り合ったのは僕だけど、ドワンゴをいちばん面白がったのは、じつは歴彦さんだったんだよ。
二次創作が生まれる場とか、UGC(ユーザーの制作したコンテンツ)とか、そういうものに対して彼は直感が働くんだと思います。「ドワンゴのニコニコの中に新しいものが生まれている!」というような。
鳥嶋氏:
その後の面倒くさいことを全部整備してるのは、この人なんだけどね(笑)。
──すると歴彦さんが川上量生さん(ドワンゴ創業者)と出会ったのは、ニコニコが成立した後ですか?
佐藤氏:
そう、ニコニコの後。
──佐藤さんがなぜドワンゴに注目したのかという話に戻るんですが……これは僕の仮説ですが、編集者の資質や本質のひとつって、その目利きじゃないかと思っているんです。佐藤さんは、マンガや小説の編集を直接手掛けるわけではないし、企画に具体的に専念するわけでもない。
だけども周辺にあるものが上手くいく。それって佐藤さんの才能というか、能力の本質のひとつなのかなと思っていまして。その編集者の嗅覚というか目利きというのを、もう少し言語化したいんですね。
佐藤氏:
うーん、おもちゃ業界紙時代の経験が、自分の中で凄く大きな資産だったとは思っていてね。
昔のおもちゃ業界って、ダッコちゃん、レーシング、ラジコンなどがヒットしても、そのメカニズムがわからなかったんです。

(画像はダッコちゃん 文化遺産オンラインより)
なんで売れてなんで消えていくのかがわからないから、おもちゃ会社の浮沈も激しかった。だからおもちゃメーカーは継続的にヒットを生む土壌づくりに腐心していたわけです。そういうところを見てきたのは大きかった。
鳥嶋氏:
業界の外から、内側を見続けてきたわけだ。
佐藤氏:
そこで継続的なヒットを生み出すために、タカラはリカちゃん、トミーはプラレールのような定番商品に行くんだけど、バンダイはテレビキャラクターの商品化を発明した。
それからサンリオのキティちゃんのキャラクタービジネスがあり、決定的だったのが1983年のディズニーランドの日本進出だね。ここでキャラクターマーチャンダイジングが本格的に日本で始まったんですね。
 |
そうしたキャラクターマーチャンダイジングは当時ひときわ新しく、角川のメディアミックスの手法と共通するところがあります。そうやっておもちゃ関連の会社から学ぶことは多かった。とくにキャラクタービジネスね。バンプレストにいた土屋新太郎という人から、ずいぶん教わりました。
凄い理論家の方で、のちに『キャラクタービジネス -その構造と戦略』という本を出しています。それを読むと、角川的なメディアミックスの手法もよく解ったんだよね。メディアミックスも継続的にヒットさせる仕組み作りだと。
鳥嶋氏:
僕から見た佐藤さんって、物事の見かたがフラットなんだよね。普通は出版社として物を作っていると、僕もそうだけど出版社の立場で物を見る。
でも佐藤さんは、先ほども話に出たアニメイトやバンダイなど、そういう出版でない企業との話に、わりとスッと入っていくんだよね。
僕などは、「彼らがどこにいて、僕がどこにいるか」、その在りかたを定義付けしてから入っていくから、ある部分でケンカを売ったりすることもあるんだ。でもこの人は、スッと脇に入っていく。
佐藤氏:
答えになってないかもしれないけど、そういう意味では、「キャリアが出版から始まっていないから」というのがあると思う。
──日本ファルコムと組んで、『ザナドゥ』や『ロマンシア』のマンガを出して25万部という数を売っていますよね。そうした入りかたややりかたに興味があるんです。
それぞれのゲームが人気なのは確かですが、「それをマンガ化したら売れる」などは、誰もやったことがないから判らない。その柔軟性やフットワークの軽さは、どこから来ているのでしょう?
鳥嶋氏:
横からの意見になるけど、ひと言でいうと“共感能力”なんじゃないかな。誰かが「面白い」と言ったものを、素直に「面白い」と思えるかどうか。これだと思うんですが、どうですか?
 |
佐藤氏:
あの当時の角川って、「ゲームをメディアミックスする」という大きなテーマがあったんですよ。歴彦さんが凄く奨励していましたしね。
それと、先ほどの例で言えば、日本ファルコムの加藤正幸さんが面白かったんです。「キャラクターというものを勉強したい」と言われ、僕はあの人に引き回され、ぬいぐるみの会社まで一緒に行ったりしてね。そうやってずいぶん付き合った(笑)。
【ゲームの企画書】激動のゲーム業界を“変わらないこと”で生き抜いてきた日本ファルコムのスゴさとは?【業界初、加藤会長×近藤社長対談】
佐藤氏:
そんな付き合いの中で、「マンガをやってみたい」、「音楽をやってみたい」と言うので、そのすべてにお付き合いしたんだ。そういう意味では、方々にそうした人間関係を普通に作っていたからかもしれない。コナミやタカラやバンダイにもいろいろと話を持ちかけたね。おもちゃ化やゲーム化を含め、メディアミックスの弾はいっぱい撃ったよ。イベントもたくさんやったし。
鳥嶋氏:
佐藤さんは出版人としてはめずらしく顔が広い人なんだよ。出版社から現れた名前の知られている編集って、意外と世界が狭い人が多いんだけど。
佐藤氏:
……あんまり納得できていない感じかな?
──いえ、納得できないということはないんですが……(汗)。
鳥嶋氏:
自分で不思議に思っていないものだから、説明するのが困難なんだよね(笑)。「なんで生きてるんですか?」と聞かれているのに近いと思うよ。
 |
──佐藤さんの凄さというものを、まだ誰もちゃんと説明できていない気がするんですよね。
佐藤氏:
いや、別に凄くないからね。
鳥嶋氏:
いやいや、凄いですよそれは。いまのKADOKAWAの実質を作っているんだから。
佐藤氏:
もういいじゃないですか、この話は(笑)。
鳥嶋氏:
いやいや、今日のテーマなんだから(笑)。
人が「面白い」と言ったものって普通は否定しがちで、それを素直に「面白い」と思えるのは、相当レベルの高い力だと思うんだよね。否定から入るのが打ち合わせだと思っている編集も多い。
──新しいものや面白いものがあったときに、それを「面白いよね」と話が通じる相手って、じつは少ないですよね。でき上がったものに対してはみんな共感するんだけど。
佐藤氏:
たぶんだけど、あの時代ってそういう面白さが塊として転がっていたんだよね。
 |
鳥嶋氏:
でも「塊としてあった」と言ったって、あのころに雑誌にいて、「ゲームが面白い!」と遊びながら物を作っていた人間なんて、私とあなたを含めてもどれだけいるか(笑)。
佐藤氏:
うーん、自分でも言うのもおこがましいけど、おもちゃをいろいろと見てきていたから、普通の大人よりは柔軟だったかもしれないね。
鳥嶋氏:
佐藤さんについてさっき“共感能力”と表現したけど、もっと踏み込んで言うなら、好奇心だと思うんだ。
新しいものが最初に来るときって、得体が知れず、やっぱり奇妙なんだよね。それを「面白いね」と共感できるのは、ある種の幅広いセンサーが働いているからで、何かが来たときにフラットに受け入れられる。
さっき佐藤さん自身は“遊び感覚”と言っていたけど、その心理的障壁が低いから“仕事感覚”にならないんだよ。
──そう考えると、佐藤さんの持つ性質が、KADOKAWAの雑食性やいろいろなものに繋がっていく感じはありますね。
佐藤氏:
あの当時は、雑誌を次々と創るから、いろいろな業界から人が入ってきたんだよね。雑食性と言ったけど、雑草みたいだよね(笑)。
鳥嶋氏:
角川がそういう形で頭ひとつ出てきたから、集英社も講談社も、ある部分で角川に削られたんだよ。いちばん削られて致命傷を受けたのは、たぶん小学館だね。
本来なら『少年サンデー』は、“オタク萌え”を取っていかないといけないのに、角川にがっつり持っていかれたから、立ち直れなくなった。
佐藤さんと鳥嶋さんの関係
──いまのお話で、「鳥嶋さんは佐藤さんのことをよく見ているなあ」と感じましたが、佐藤さんと鳥嶋さんの出会いについて聞かせていただいてもいいですか?
鳥嶋氏:
僕と佐藤さんは接近したり離れたりというような感じで、ある時期に同じように仕事を同じような業界でやっているけど、言うほどダイレクトに接触したことはなかったんだ。
深く話をするようになったのは、ここしばらくのことだったり。
 |
佐藤氏:
そうですね。直接はないですね。
鳥嶋さんは覚えていないと思うけど、その昔、僕は鳥嶋さんをバンダイで見かけたんですよ。当時は『ジャンプ』が押さえていたゲームの情報にいろいろ規制がかけられていたから、「あ、いた! 憎たらしいなあ」と思いながら遠巻きに見ていた(笑)。
──(笑)。つまりそれ以前から鳥嶋さんの存在を意識していたと。
佐藤氏:
おもちゃの業界紙にいたころ、『Dr.スランプ』にマシリトが出ていましたし、関連したおもちゃもいろいろと出ていましたから、そのころからですね。
鳥嶋氏:
『Dr.スランプ』は、時代のインパクトとしては、『ドラゴンボール』の10倍はあったからね。
佐藤氏:
『Dr.スランプ』はキャラクター商品としても新鮮で、たとえばアラレちゃん消しゴム【※】とかね。その業界紙の職場で「これ凄いなあ」と言っていた。ジャンボマシンダーや超合金、それから戦隊物とか仮面ライダーのような、ポピー【※】が作ってきた当時の王道だった流れとは、また違うんだよね。新しい風をおもちゃ業界に巻き起こしていてさ。だから業界紙のときに鳥嶋さんに気づいていたんだ。
以来、僕は結構鳥嶋ウォッチャーですね。
鳥嶋氏:
この人ね、僕よりも『少年ジャンプ』のことが詳しいし、好きなんですよ(笑)。
佐藤氏:
そんなことないよ(笑)。
 |
※アラレちゃん消しゴム……『Dr.スランプ』のキャラクターたちを象ったゴム人形。スーパーカー消しゴムや怪獣消しゴム、そしてキン肉マン消しゴムの文脈上にあるが、白眉だったのは物語の舞台“ペンギン村”の台座込みの建物が別売され、ペンギン村の光景がジオラマのように再現できる商品(「ペンギン村分譲中」)展開などもあったことが挙げられる。
※ポピー……バンダイから分かれた杉浦幸昌氏を軸に1971年に創業された玩具会社。仮面ライダーの「変身ベルト」、「ジャンボマシンダー」、「超合金」などキャラクターを利用した数々の大ヒット玩具を生み出した。1983年にバンダイに吸収合併され、以降、バンダイのキャラクタートイの礎となった。
鳥嶋氏:
すると佐藤さんはキャラクター商品というものの展開を、最初のころから見ていたんだね。それは凄く大きい。勘が養われているし、普通の編集なんかよりも視野が広い。始まりが出版社でないのは本当に重要で、それが佐藤さんを形作っているよね。
情報や人脈の広さや、視点のフラットさもそこから来ているんだろうなあ。
──では逆に鳥嶋さんが佐藤さんを意識したタイミングというのは?
鳥嶋氏:
僕はハッキリ覚えているんだけど、『ファミ通』が、レコード大賞のように「ゲーム大賞をやりたい」と言って、『Vジャンプ』を含め、さまざまなゲーム雑誌に声をかけたタイミングがあったんだ。
そこには『ファミマガ』編集長の山本さん(山本直人氏)や佐藤さんや僕もいて。そのときに「ああ、この人が電撃とかいろいろやってきた角川の佐藤さんか」と思ったのが最初。
ちなみにその集まりでは、僕は与したくないから、啖呵を切ってできるだけ早く帰ろうと思っていたんだけどね(笑)。
佐藤氏:
実際啖呵を切って帰っていったよね(笑)。
 |
一同:
(爆笑)。
『コロコロ』に挑むときと同じくらいの絶望感
鳥嶋氏:
当時は佐藤さんという名前は知らなくても、後になって振り返ると、同じ時期に同じような何かをやっている。佐藤さんが『コンプティーク』で『ゼビウス』を取り上げているとき、僕は“ファミコン神拳”を始めていたし。
【田中圭一連載:ゼビウス編】ゲーム界に多大な影響をもたらした作品の創造者・遠藤雅伸は、友の死を契機に研究者となった。すべては、日本のゲームのために──【若ゲのいたり】
佐藤氏:
僕は雑誌を始めるときに、結構あちこちへ勉強をしに行ったんです。そのとき『コロコロコミック』はチョロQを手掛けていた。
「チョロQの中を開けるとギアがひとつだけ赤い」とか「青い」とか、そういうものを読者に投稿させ、裏技みたいに取り上げていて、「こういうふうに仕掛けているんだ」と学んだんだよね。子ども向けのカルチャーを雑誌がどうやって扱うのかという勉強になった。
鳥嶋氏:
同じころ、僕も『Dr.スランプ』でチョロQブームにあやかるためにデザインを読者に募集して、鳥山さんがリファインして実際に作る企画などをやっていた。
 |
佐藤氏:
「本当は子ども向けの雑誌をやってみたかった」というのは自分の中にあったんだよね。でも、子ども向けでは『コロコロ』に敵わないから、当時は新しかったゲームに目を向けたわけで。
鳥嶋氏:
いやあ、『コロコロ』と同じことやったら死んじゃうよ! 当初、増刊の『Vジャンプ』を作ったときに「勝てない」と思った。「正面から対抗するのはすぐに止めよう」と。あれは無理。小学館の底力だよね。
佐藤氏:
ベタベタの付き合いと企画力、そして媒体力がないとね。
鳥嶋氏:
でも僕が常務や専務になったころ、「集英社もマンガだけだと厳しいからライトノベルに斬り込みたい」と研究したんだけど、『コロコロ』に挑むときと同じくらいの絶望感を感じたよね。「これは無理だろ、いまさら」って(笑)。どこも角川で真っ黒に埋まっているんだもの。「悪の帝国」と呼んでいたよ。「勝てないよ、自由軍は!」って(笑)。
だから、いつのまにかここまで佐藤軍が勝ち取ってきたというのは、本当に凄いよね。
佐藤氏:
僕に言わせたら、『ジャンプ』のように、自分たちの出版物に棚があることが羨ましくて仕方がなかったんだ。コンプレックスとまでは言わないけど、「ラノベに何とか棚ができないだろうか」というのは最初のころの大きなテーマだった。
『出版月報』なんかでは、「ライトノベルは一部のものを除いて消えてしまう商品」とか書かれていたり。そりゃそうだよね、だって棚がないんだもの(笑)。
 |
『ロードス島戦記』だって、棚がなかったから平台にしか置かれていなくて。その後に続刊が出るんだけど、まとめ買いをしてもらうには、やっぱり棚があることが大事になる。
コミックスもラノベも、棚と平台が上手く機能するから展開するわけで。『ロードス島戦記』の初期は、それがなかったから苦労した。
鳥嶋氏:
やっぱり「作って終わり」ではダメなんだよね。「どう売るか、どういうふうに進めていくか」と腐心した話を聞いていると、カバーの研究や『コロコロ』の勉強を含め、「これが必要だ」となったらすぐに実行する佐藤さんは、単なる編集じゃないんだよね。
現場のときからすでにひとりマルチでやっている。やらざるを得なかったのかな? 大手にいるとさ、普通はプライドが高いからそんなことできないんだけど、佐藤さんはそれをスッとやれるからね。
歴彦さんと佐藤さん
鳥嶋氏:
今日の対談でとくに面白かったのは、「KADOKAWAは出版社じゃない」というのと、「編集ということの在りかたの違いや視点の違い」が何か凄く大きなものに繋がっていくことですね。
佐藤さんが出版社の編集ではないところから始まってるから獲得した視点や物の見かたが、佐藤さんのその後の在りかたやKADOKAWAのある部分の在りかたを決めている。
佐藤氏:
そうですかねえ。
鳥嶋氏:
振り返ってみると、あの就職氷河期時代に、佐藤さんはおもちゃの新聞に行くべくして行った感じがするよ。もちろんその道を選んだのは佐藤さん自身なんだけど、それが角川へ来て、歴彦さんの狙いとマッチして、凄く活きていると思う。
──今回の話ではところどころで歴彦さんのお名前が出ましたが、佐藤さんにとっての歴彦さんはどういう存在なのでしょうか? 慕う理由をお訊きしたいです。
佐藤氏:
思考に「ああ、なるほどな」と思わされる論理がいっぱいあるんだよね。それこそ「角川は出版社じゃない」という認識や、袂を分かった兄貴が映像をやっていて、戻ってきたときにそれを否定せず、自分でも映像事業を始めたり。
 |
最初から集英社、講談社、小学館に敵わないことを解っていて、自分のスタイルを極めていく。そういったあの人のプロデュースの手法、経営の手法が解るんだよね。だからやっぱりね、尊敬していますよ。
鳥嶋氏:
佐藤さんの指針のひとつになっているんだ。
佐藤氏:
そうです。歴彦さんの考える会社の形の流れを追っていくと、ちゃんと理想があって……本人は言わないけど、たぶん根っこはアメリカにあるんだろうなと。
そういうものを勉強して歴彦さんのいまがあるし、まだ「できていない」と思っているから、まだ現場にいる。そういうことが見ていると解る。そしてそれは尊敬に値する。
鳥嶋氏:
だとするとさ、もし歴彦さんが退くようなことがあったら、佐藤さんはKADOKAWAに戻るべきじゃないの? そうじゃないと、KADOKAWAに指針がなくなるよ?
佐藤氏:
いやいや、そんなことはないよ。
鳥嶋氏:
えええ?(笑)
 |
佐藤氏:
少し話を逸らすと(笑)、講談社って、出版を、とくに雑誌は“面”として張っていくんだよね。あらゆるものをセグメンテーションして、ひとつひとつに雑誌を置いていく。
でも隙間があって、集英社や学研などが虚を突くようにそこに何かを出すと、潰しに来るんだよね(笑)。それで全面をまた支配するんだよ。それが彼らがおもに雑誌でやってきたことで、そうすると往時の角川を含めた中小は悲哀を味わうんだよね。
鳥嶋氏:
必ず対抗誌を出すからね。『Vジャンプ』のときも出してきた。
佐藤氏:
そういう戦いがかつてあった。つまりそれは中小が負け続けた歴史でもある。「その中で、どうやって生きていくのか」ということを、歴彦さんはずっと考えて実行してきたんだと思うんだよ。
鳥嶋氏:
その結果、KADOKAWAは肩を並べて戦えるところまで来たってことだよね。ある部分はすでに大手3社を抜いているわけだし。
佐藤氏:
それは、独自の道を行かざるを得なかった結果のひとつだよね。
 |
──そういった道を模索していく中で、フラットな視点を持った佐藤さんが入ってきて、いろいろなものを吸収して大きくなるというのが、角川が歩んだ1980年代から2000年代の歴史ですね。
鳥嶋氏:
だから佐藤さんは「歴彦さんがいて良かった」と言うけど、歴彦さんは「佐藤さんがいてもっと良かった」と思っているんじゃないかな。
佐藤氏:
いやいや、そんなこと(笑)。
──持ち上げますね(笑)。
鳥嶋氏:
この人はね、もっと自分を過大評価するべきだと思う。過小評価してるからね。普通の人間は過大評価が多すぎるんだけどさ。
今後のラノベ──そのとき編集者のやることは
鳥嶋氏:
そんな佐藤さんの視点だと、ライトノベルはこれからどうなりそうですか?
佐藤氏:
そんな難しい質問をされても、困りますねえ(笑)。
鳥嶋氏:
いいじゃないですか、もう無責任に言える立場なんですから(笑)。
 |
佐藤氏:
そうですね……いまは“なろう系”も傾向がラノベと同じようなものになってきているので、もう一回「ガラガラポン」があるんじゃないかなと思いますけどね。
鳥嶋氏:
何か新しい動きが起きるんじゃないかと。いまは閉塞感があるから。
佐藤氏:
閉塞感はあるんじゃないですかね。“なろう系”が想定している読者は年齢もわりと上で、一冊あたりの価格も高いので、限定した層を狙っているような印象ですし。だから間口を拡げるために低年齢層への策をKADOKAWAでもいろいろとやっていますよ。
 |
それから、さっきのアニメの話も関連してくると思うんだけど、昔、アニメ原作はマンガの独壇場だったものが、「ライトノベルからのアニメ」という流れが出てきたように、「なろう系からのアニメ」は現れているし、そしてそのつぎがまたきっと現れる。
鳥嶋氏:
そうやってアニメーションのバリエーションが増えたんですよ。そしてマンガというもののエッセンスを吸収する形で、もう一度、文字が、小説が復権したんだよね。それがラノベであったと。
──いま「マンガがダメになった」とか、「コンテンツが難しくなった」と言われる状況下で、「じゃあどうするの? もう一度面白いものを作ろうよ」というのはもの凄く正論なんですが、それだけだと、ただの精神論に聞こえてしまうわけで。
鳥嶋氏:
いま、マンガ編集者がやらなきゃいけないことって何かと言うと、「読者がどういうものに動かされるか」、「何を欲しいと思っているか」のリサーチを、具体的に作品を作りながらデータを取って、もう一度経験則として積んでいくこと。それしかないんだよね。
──たぶん編集者がやるべきことって、鳥嶋さんの言う原点の見直しと、もうひとつは、作ったものを見てもらえる場所を探すこと。それは昔でいう流通だったり、人が来る導線だったりを探すことだと思います。
いまはそれがTwitterやYouTubeなど、けっこうバラバラに散っているので、なかなかひとつにはできないんですが。
鳥嶋氏:
解る。そこでは子どもが鍵になるんだけど、彼らが携帯を持ち始めるのがいまは小学校の高学年あたり。安全面での保障とか、まわりの友だちとの兼ね合いで親は持たせざるを得ない。さらにもっと小さな子守の時点で、スマホそのものは触らせている。だけど子どもには、「お金は使っちゃいけない」という前提もある。
 |
あのとき漫画村が広がったのは、こういう現状が後ろにあることを見ておかないと理解できないよね。著作権教育だけの問題じゃないんだよ。
持っているから触わる。親の干渉を受けずに見られるものはタダのものしかない。だったらそれを見る。そういうものがいまはいっぱいあるよね。
佐藤氏:
そうですね。
鳥嶋氏:
あとはそういう時代に、「子どもどうしがコミュニケーションをどういう形で取るのか」とか。
──昔はそれこそ『ジャンプ』をお兄ちゃんが買ってきて、弟も読んでいた。ではいまそれをネットで再現できているかというと、できていない気がするんです。
影響力の復権を考えるなら、極論すると、どうするかはともかく、それは何らかの形でネットでも再現すべきことだと思いますね。
鳥嶋氏:
いまのところはLINEのようなものなんだろうね。ただああいうSNSはグループは作りやすいけど、本当の意味でのコミュニケーションになってないからな……。
媒体の発信力
──編集が今後を考えるなら、「昔あった雑誌の力強さとは何だったのか。何を失ったのか」というのを、ひとつひとつ分解して考えるのは必要な作業なのかなと思います。
鳥嶋氏:
雑誌が失ったもののひとつは、メディアとしての特性だと思う。いまはマンガ誌にマンガは載っているけど、マンガ自体に発信力がない。結果、雑誌としての発信力もない。
 |
以前だったら、そんなに選択肢があったわけでもないから、たとえば『ドラゴンボール』があったとき、子どもたちのあいだで「今週の見た?」と話題になった。キャラクターの動静や物語の進行が、いまの大人でいうとワイドショーのネタみたいに話題になっていたんだよね。
──それはいつも鳥嶋さんから伺っている話ですが、「雑誌とはライブであり、いま見る理由を必要とする」という話ですね。それがいつのまにか構造的に作品主義になり、単行本中心の売られかたとなり、当のライブ感はTwitterなどのSNSに奪われ、「雑誌をいま見る理由」もなくなってしまった、と。
佐藤氏:
雑誌がなんで売れなくなったかというのは、「雑誌を買わなくていい理由」が生まれたってことだよね。それにはさっきも言った通信費が大きく関わると思うけど、ほかにもいろいろありそうだよね。
鳥嶋氏:
そこは僕もよくいろいろ考えるんですよ。裏返して、「雑誌はなぜ生まれたのか」と考えたり。
もともとは雑誌に編集長という特定の強い個性があったはずなんですよね。それが先ほどの入広型雑誌の登場によって、滅びが始まったんじゃないかと思うんだ。個性だとか雑誌カラーだとか言われていた、専門性というか特異性というか、ある種の視点の傲慢さがなくなったんじゃないかな。
佐藤氏:
それ自体が求められなくなってしまった?
鳥嶋氏:
か、どうかはわからない……。
「エッジが効いている」という言いかたがあるけど、これは、「これがわからない人は読まなくていいですよ」という、“いい傲慢さ”だと僕は思う。電ファミのインタビューはある程度そうだもの。「これ、わからない人は読まなくていいです」という重さと長さ(笑)。それもひとつの記事の切り口だよね。
ふたりのこれから
──そろそろお時間になりました。今日の話を通じて、鳥嶋さんから見た佐藤さんの凄さや、やってきたことへの感想、佐藤さんから鳥嶋さんがどのように見えたのかなどを聞かせてください。
さらにそれを踏まえ、1980年代から2000年代にかけて日本のコンテンツ業界や出版界において大きな役割を果たしてきたおふたりが、これからどうされるのか、または今後の役割などについても語っていただければと思います。
鳥嶋氏:
佐藤さんの凄さについて改めて思ったのは、人の才能をフラットに評価できて、一緒に遊べる懐の深さだね。編集者って厳しかったり文句を言ったり、またはプロデュースすることが仕事だと思っている人が山ほどいるけど、そうじゃないんだ。今日の話を聞いて解ると、編集者の資質というのは、どれだけ作品や作者に「面白い」と思って寄り添い、理解して世の中に出してあげられるか。そんな“遊べる感覚”にあるんだよ。
 |
そのために必要なものを佐藤さんは持っていて、雑誌編集からではなく業界紙から入ってるから、偏見を持たずに才能に対しての評価ができる。非常に広い視点から偏見なく物を見られるのが、やっぱり凄いところだよね。
なおかつ、僕になくて決定的に関心する部分は、年上に対して尊敬の念が持てるところ。あり得ないね(笑)。
そういうポジショニングは違うけど、才能を評価して世の中に出したいという思いは一緒。佐藤さんと一緒に世の中の才能をもう一回発見して繋げて、新しいものを作り出せないか、それを最前列で見たいと思いますね。
だけどジジイだから、目利きがどこまで通じるか判らないけど、経験則だけはあるから、この数年で何かを一緒にやれたらいいなと本当に思います。
佐藤氏:
鳥嶋さんもそうだし集英社もそうだけど、僕からすれば巨人だったからね。ウォッチャーとして、アラレちゃんの時代も『ドラゴンボール』の時代も『Vジャンプ』のころも、それらを越えて『ジャンプ』に戻って必死に立て直してるころも、ずっと見てきたからね。どこかで記者的な感覚も残っているから──編集者的と言ってもいいんだけど、僕は鳥嶋さんを面白く見ているんだよね。
 |
いま「これから何か一緒にできたら」と言ってくれて嬉しいんだけど、マンガやライトノベルが間違いなく元気がなくなってきているこの時代に、新しい才能と出会えるようなことがあるなら、それはやっぱりやってみたい。
鳥嶋さんと同い年のジジイだけど、自分がまだそういうところに力を出せるかどうかを試してみたい。ジジイだからゆえ、9割がた絶望的な気もするけどね(笑)。でも、いまもマンガやライトノベルを楽しく読めるし、新鮮なおもちゃも大好きだし、イケるような気はする。
むしろ、長く社長をやりすぎた。管理する側にいすぎたので、現場にいたいね。
鳥嶋氏:
それはよく解る。「ここにいる場合じゃない」、と時間をロスした気持ちになるよね(笑)。
佐藤氏:
そう! もうちょっと自由な心で現場を見たい。現場にいなかったことでダメになったニューロンを再生させたいんですよ。
鳥嶋氏:
そうそうそう。3分の1くらいしか頭が動いていない感じがするよね。錆びているよ、本当に。
若い人たちと会って話をしていると、経営の話より面白いんだもの。僕が3年間社長をやって解ったのは、僕は勘が悪いわけじゃないから、社長業は人並にはできるけど、「本当に適正か」と問われると、「そうではない」ということだった。
足し算をしてコツコツ数字を構築していく仕事って、やっぱり僕の本来のスピード感と合わないし、ダメだね。勘で動くほうが僕にとってやっぱり面白いし、合う。社長は、もう少し辛抱強い人じゃなきゃダメ(笑)。
 |
佐藤氏:
(笑)。
鳥嶋氏:
それから、社長という仕事を何年もやっていると本当に人間がダメになるね。株式会社において代表権を持っている社長って、絶対的権力者だからね。「ああ、これはあと何年もやったら人間がダメになる」と思ったもの。
佐藤氏:
僕はメディアワークスから数えると、20年も社長をやってきたからね。ダメ人間の度が進んでいる。
鳥嶋氏:
ハハハハハ。
佐藤氏:
まあ、社長うんぬんはともかく、最近は素直にいろいろ感じられる心の自由さが大事だと思うようになりました。65歳を過ぎたころから、人生やり直したくなった。足腰鍛えてね。ワクワクするようなことをしたいなと思います。
──そうやって同時代を生きながらもやりかたがまったく違ったおふたりが、今後何らかのタイミングで組んで「面白いことに挑戦しよう」という展開になったら、それはもの凄くワクワクしますね。
そしてそれが、いまのコンテンツ業界や日本そのものを覆っている閉塞感を突破するきっかけのひとつになるといいなと思います。
鳥嶋氏:
僕は編集なので、才能ある人にはすぐに「一緒にやろうよ」って言いたくなるんだよね。「ほら、面白そうじゃない?」という悪魔の囁きをね(笑)。だから、もしそんなことがあったら、そのときは当然手伝ってくれるんだよね、平くん?
──ええーっ!?(了)
 |
今回の取材には、じつは大きな裏テーマがあった。
それは、筆者(TAITAI)が長らく持ち続けていた「編集者とは何か?」という疑問を探るというものだ。出版業界が斜陽になり、ネットメディアやSNSが隆盛を極めるなかで、作品はどう作られて、どう世に届けられるべきなのか? 作家個人が情報を直接発信できるいま、編集者という役割は本当に必要なのだろうか? ここ数年、その答えをずっと探り続けていた。
そもそもその答えが知りたくて、鳥嶋氏の話を佐藤氏と聞きに行ったり、ジブリ鈴木敏夫氏に半ばやり込められたり、今度は鳥嶋氏とともに佐藤氏に迫ったりと、じつはシリーズのような感覚で取材を続けていたのである。
今回の取材は、まさにその最終回とも言える内容だったと感じている。
思えば、佐藤辰男氏は、筆者にとって長らく”不思議な存在”だった。
大企業の社長にまで登り詰めた人物でありながら、その佇まいは柔和そのもの。いつも温厚な雰囲気を漂わせており、言葉を濁さずに言ってしまえば、品のいい月並みな壮年男性にすら見えなくもない。話す内容も、鳥嶋氏のような明敏かつ鋭利な論を発するわけではなく、要は「何がどう凄い人なのか」がいまいちよく解らなかったのだ。
しかし、その足跡を辿れば、記事中でも触れたような驚くほど大量の功績を残しており、佐藤氏の周囲を見れば、いつもそこに新しい人が集い、新しいものが生まれていたことが判る。それは決して、人並みな人間の成せることではない。
では、そんな佐藤氏の凄さとはいったいなんだったのだろうか?
それは要するに、目利きなどではなく、まして独自の編集理論でもない。
鳥嶋氏も認めた佐藤氏の凄さとは、何よりも作家に「共感する才能」であった。そして、それこそが編集者にもっとも求められる資質であり、最初に必要とされる感覚だったわけだ。
その共感も、作家と編集者という閉じた関係の中で響き合っているだけではどうにもならない。共感は、時代に対する嗅覚──佐藤氏ご本人の言葉を借りれば、「AppleIIでミステリーが楽しめることに驚愕した」だとか、「RPGというものが本当に目新しかった」──という感覚に裏打ちされている必要があり、その感覚がのちのラノベとの出会いなどでも働いているのだ。
言うまでもないが、編集者は、自身が何かを生み出すわけではない。編集者とは、他人の才能を引き出し、その才能を磨く職業だ。なればこそ、まず誰よりも最初に作家(才能)を認め、励まし、そのクリエイティビティに寄り添うことが、編集者には求められる。
編集者のもっとも根源的な部分とは、つまり、目利きと称して才能をふるい落としたり、技術的な指導をしたりすること(もちろん、これらも大事な才覚ではあるが)だけではなく、才能に「共感する」ところからスタートすべきなのだという、考えてみれば当たり前の、至極単純な結論であった。
思えば、前述の鳥嶋氏へのインタビューでも、それを「好奇心」という言葉で表現していた。いわく「才能は奇(稀)なるもの」、「まず奇(稀)なるものを面白がること」が重要だと。これに比べれば、作品そのものの目利きやプロデュースの巧さなどは、些細な能力に過ぎないのかもしれない。
その「奇(稀)なるもの」を目の当たりにしたとき、多くの人はそれをそのままでは理解できない。だからこそ、それを理解し、共感したときに得られる面白さを、広く人々に伝える「編集」という仕事が重要となるのだ。
今回の取材は、そうした編集者のもっとも根源的な部分が、心の底から納得できた&腹落ちしたという意味で、個人的にもとても意義あるものだった。
言うまでもなく、出版業界は、いま苦境に立たされている。
その苦境を脱するにあたって、出版社が問われているのは、まさに「編集者とは何か?」という本質なのではないだろうか。そして、それを踏まえた我々若い世代の編集者が向かうべき先はどんなものだろうか? 彼らの行ってきたことやその立ち振る舞いの中に、きっとそのヒントはあるはずだ。
自分がこれから10年20年と編集の仕事を続けていくなかで、時間が経ってから今日の取材を振り返ったとき、あらためて佐藤氏や鳥嶋氏の凄さを噛みしめる日が来るだろう。そのとき自分は、共感力をどれだけ高められているのだろうか。いま彼らが見ている広々とした景色を、自分も見られるようにならないといけない。そのためには、もっと頑張らないといけないなぁ……。そう思わされた取材であった。
 |
最後に。
しばらく日が経ってから鳥嶋氏と話をしているときに、氏がそこで語っていた言葉が今回の取材と併せて強く心に残ったので、その台詞を紹介して、本稿を締めさせていただきたい。
編集者と作家のケンカってのは、だいたい編集者が悪いんです。作家というのは腕一本で生きている。サラリーマンの編集とは覚悟が違う。ケンカだって覚悟を持ってしている。
でも同時に、作家というのはとても孤独なんです。編集者は、そうした作家の気持ちを理解しなきゃいけない。それこそ、新人賞を取った人や、デビューして10年経ったような人であっても、先行きが判らずに不安でいっぱいなわけで、真っ暗闇の中にいるのと変わらないんです。
それって喩えるなら……目を瞑ったままマラソンをしているようなもの。作家というのは、真っ暗な中を不安や恐怖と戦いながら走り続けなきゃいけないんです。だから編集者は、その作家の孤独や不安をいちばん解ってあげないといけない。
さらに言えば、編集者は世に出なかった才能こそ忘れちゃいけないんです。世に出た作家はね、お客さんが覚えてくれるからいい。だけど、世に出なかった才能は担当した編集しか知らない。だからこそ、その人のことを編集者が忘れちゃいけないんです。
そうした有名無名の才能の先を走りながら、鈴の音を鳴らして先導する役割──それが編集者なんです。
鳥嶋和彦
鳥嶋氏も登壇。“拡げる”仕事に転職したい人のための、キャリア相談会を実施します
佐藤さんと鳥嶋さんによる“頂上対談”はいかがだったでしょうか。作者やコンテンツの魅力を見出し、寄り添い、拡げる仕事の楽しさが見えた記事になったのではないかと思います。
そこで電ファミニコゲーマーでは、新たな取り組みとして、惚れ込んだ何かの魅力を“拡げる”仕事に転職したい人のための、キャリア相談会を実施します。
この催しは、Webメディアである電ファミニコゲーマー、出版社である白泉社、ゲーム専門のマーケティング会社であり、数々の実績を持つリュウズオフィスの三社で合同開催。いずれも“拡げる”仕事に携わるメンバーです。この三社で、ゲームをはじめ、コンテンツに関わる現場の生の声を転職を考える皆さんにお届けしつつ、皆さまの質問や疑問にお答えしようという試みです。
現在はこの相談会への参加者を募集中。詳細は以下のリンクからご確認ください。奮ってのご参加をお待ちしております!
・キャリア相談会 応募フォームはこちら
https://pro.form-mailer.jp/lp/b0c449b2160425
・キャリア相談会 告知記事はこちら
http://news.denfaminicogamer.jp/oshirase/181228b
【プレゼントのお知らせ】
佐藤辰男さん、鳥嶋和彦さん、それぞれ愛用の万年筆をセットで1名様にプレゼント! これで編集の頂点を目指したい!
詳しい応募方法は電ファミニコゲーマー公式Twitter(@denfaminicogame)をチェック!
【あわせて読みたい】
【全文公開】伝説の漫画編集者マシリトはゲーム業界でも偉人だった! 鳥嶋和彦が語る「DQ」「FF」「クロノ・トリガー」誕生秘話一体、伝説の漫画編集者とゲーム業界との関わりはどんなものだったのか? ほとんどメディアに姿を現さない氏に、長年の友人というカドカワ会長・佐藤辰男氏の紹介で我々が出会ったのは、とある都内の老舗ホテルの一室。
白髪頭におしゃれなブランド服の出で立ちで現れた鳥嶋氏は……確かにマシリトの面影がある。そして話し始めてみると、60歳を超えた人間とは思えないほどの俊敏な頭の回転で、カミソリのような切れ味鋭い言葉が次々に飛び出してきた。
──かくして我々はその日、『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』『クロノ・トリガー』など数々の名作ゲームたちが生まれるに至った、ゲーム業界黎明期における知られざるエピソードと人間関係の逸話の数々を、その中心人物の口から聞いていくことになったのであった。
【あわせて読みたい】
ジブリ鈴木敏夫Pに訊く編集者の極意──「いまのメディアから何も起きないのは、何かを起こしたくない人が作っているから」スタジオジブリの月刊誌「熱風」の仕掛け人である鈴木氏は、いまでこそスタジオジブリの“顔”として広く認知されているが、そもそもは徳間書店で「月刊アニメージュ」の創刊に携わり、二代目編集長を務めた人物。
つまり今回の取材は、ベテラン編集者に「メディアとは何か? 編集とは何か?」を訊くというものでもある。
取材中に“取材のまとめかたの善し悪し”を聞いてしまうなど恐ろしい展開にもなり、そこでは映画プロデューサーの顔とはまた違う、雑誌編集者としての鈴木氏を見ることができた。