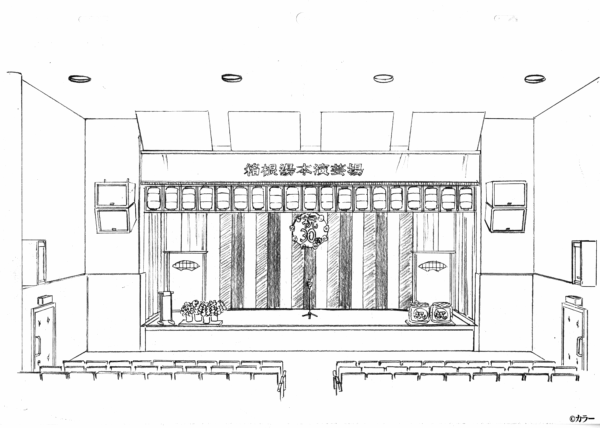去る8月30日から9月1日、パシフィコ横浜にて、ゲーム開発者向け技術カンファレンス「CEDEC 2017」が開催された。
だが、そもそも「CEDEC」というイベントの名前を聞いたことがない読者も多いのではないだろうか。このカンファレンスは、国内外から招かれたゲーム業界関係者たちが「セッション」を行い、ゲームに関する知識を共有するものだ。
当然、交わされる話題は専門的になる。先日行われた「東京ゲームショウ2017」を一般消費者向けの催しとするならば、「CEDEC」は生産者向けの催しと位置づけられるだろう。

正直なところ、昨年から本格的にゲームライターの活動をはじめたばかりの筆者も、不勉強ながら開催日直前までこの催しの存在すら知らなかった。不明なまま会場に入り、はじめて来場者の多さと彼らの熱気を目撃して、驚いたくらいだ。
多大な情報量のなかでめまいを起こしているうちに、パシフィコ横浜の無数の講演ホールは、ほぼ全室が三日間ぶっ通しで使用された。しかし、ひとりの人間として、参加し理解できたセッションには限りがある。そこで本稿では、あくまで筆者なりの切り口で、この催しの概要をレポートすることにした。
ここで交わされた知見は、開発者にはもちろん、プレイヤーにとっても意義深いものだった。たしかに話題はゲーム作品そのものについてではなく、開発部分に関するものが主だった――ただ、それだけに、いまだ見たことのないゲームの未来を、いわば遠望することができたのだ。

さて、「CEDEC 2017」の内容を大別すると、講演者によるスピーチ/ディスカッション形式の「セッション」と、講演者と参加者が直に会話しながら技術体験を共有する「インタラクティブセッション」に分けられる。
告白すると、筆者は参加したすべてのセッションの内容をよく理解できたわけではない。技術系カンファレンスに突然放り込まれた文系ライターの戸惑いも交えつつ、順を追って話していこう。
企業ブースで、ひときわ目を引いたのは…?
「藤田さんの目についたものを、とにかく自由に取材してきてよ」と、編集部から大変に気前の良い指示を受けた筆者は、初日の会場で困惑していた。移動中に前もって確認していた講演リストには、自分が理解できそうなタイトルが見つからなかったのだ。

仕方ない。とにかく筆者は鼻を利かせようとした――満員の会場のなか、人々が首から下げている入場パスには、ゲーマーなら一度は耳にしたことのある国内ゲーム企業の名前が記されている。
見渡せば会場の広々とした廊下には企業ブースが設営されており、Unity【※1】やUnreal Engine【※2】といった開発エンジン、アンチチートプログラムやクラウドデータベースなどを販売する企業の人々が微笑みかけてくる。

「あなたのソシャゲ、チートにお困りではありませんか? 弊社のアンチチートをどうぞ!
いや、おれは開発者じゃないんだ!
……そもそも、私はこのイベントについていけるのだろうか? 困惑が動揺に変わりはじめたころ、企業ブース群の奥に設置されていたひとつの展示が、筆者の目を奪った。
その展示とは――「砂場」である。
※1 Unity
ユニティ・テクノロジーズが開発したゲームエンジンの一種。開発が手軽であること、VRに積極的な対応をすすめているところから、VR系アプリケーションの多くがUnityで開発されている。スマートフォンからブラウザ、コンシューマーなどを問わず、複数のプラットフォームに対応しており、幅広く採用されている。
※2 Unreal Engine
Epic Gamesが、1998年に発売したFPS『Unreal』に実装したものに端を発するゲームエンジン。FPS、TPS以外にもさまざまなジャンルのゲームに使用されている。開発会社のEpic Games。
技術者たちを虜にする砂場、「流動床インターフェース」
筆者は、この小さな砂場に目を落とした。
※ものつくり大学の的場やすし氏と菅谷諭氏によるインタラクティブセッション、「流動床インターフェース:液体のように振る舞う砂を用いたインタラクションシステム」。なんだこれは?(筆者注)
よく見ると様子がおかしい。
砂場の表面に水の気泡のようなものがあらわれては消え、まるで沸騰しているかのようだ。コンテナの底部からは、コンプレッサーの音が聞こえる。ものつくり大学の的場やすし氏と菅谷諭氏に促されるまま、この砂場に手をつっこんだ瞬間、筆者は瞠目した。
 |
水のようなのだ。
差し込んだ手はどこまでも沈んでゆき、底がないみたいだ。歓声をあげると、的場氏は微笑みながら、スイッチを押した。すると――砂がとつぜん固まり、手を動かせなくなってしまった。
両氏によれば、このプロセスは、じつは基本的な自然現象を基にしているという。そもそも砂には、空気を送り込むことによって、まるで液体であるかのようにふるまう性質がある。液体のようになった砂場のなかに筆者が手を突っ込んだとき、的場氏が押したのは、砂場に空気を送り込むエアコンプレッサーのスイッチだった。
送風が切られたとたん砂はふだんの振る舞いに戻り、「手がしっかりと砂場に埋まった状態」に戻った。そこで、筆者の腕もいっしょに埋められてしまったのだ。

正直なところ、このインターフェースがどのようにゲームに応用されうるかは、筆者にはわからなかった。
しかし、この「砂場」の周囲に集ったエンジニアたちが、みな童心に帰ったように目を輝かせていたのは、じつに印象深かった。彼らは口々に言葉を交わしていた――
「VRにおける触覚デバイスとして使えるかもしれない」
「すべての砂粒に極小のセンサービーコンを埋め込めばコントローラーになる」
「流体のシミュレーションにもってこいだ」
このあたりで、筆者は「CEDEC」という催しの意義を掴みはじめていた。
居ながらにして世界を見る目、ドローン
つぎに目を引いたのは、ドローンのレースコース――いや、より正確には、ドローンのパイロット自身だった。
インタラクティブセッション会場のいちばん奥に、網で組まれた立方体がある。網の天井からは、コースを限定するリングがいくつも吊されている。その中心に奇妙なゴーグルをかけた男が鎮座し、微動だにせず、静かにコントローラーを動かしている――そして彼の周囲を、直径十センチにも満たない超小型ドローンが、精霊のように飛び回っている。

挨拶もそこそこに、筆者は彼が装着していたゴーグルを借り受けた。ゴーグルのなかには小型ディスプレイが埋め込まれており、そこに映し出されていたのは――筆者自身の姿だった。ドローンのカメラの信号が、無線でゴーグルのディスプレイに投影されているのだ。

インストラクションを受けて、それなりにドローンを飛ばせるようになったころ、筆者はふと考えた――「そうしようと思いさえすれば、このままCEDECの会場を居ながらにして見て回れる。マイクとスピーカーをつければ、会話すら可能じゃないか」――これはもはや、ゲーム的なアイデアが、現実世界で実現したと言っても過言ではない。
「Rainbow Six」シリーズ【※1】や「Watch_Dogs」シリーズ【※2】に登場していたドローン技術が、現実に登場したと言えるではないか。
※1 「Rainbow Six」シリーズ
Ubisoftによるタクティカル・シューター系の対戦型FPSシリーズ。同シリーズは、トム・クランシーの小説を原作にしており、1998年のWindows版がシリーズ初作。その後家庭用ゲーム機にも移植された。
※2 「Watch Dogs」シリーズ
Ubisoft開発のオープンワールド型アクションゲームシリーズ。2014年に初作が発売され た。「Central Operating System」(通称ctOS)と呼ばれるOSがインフラ管理をする都市で、主人公がハッキングして都市を操作していく設定である。オンラインプレイも、非常に高い人気を有している。
サイバーベイビーの誕生、VR子育てシム
つぎに筆者が見たのは、サイバーベイビーだ。もう一度言おう、サイバーベイビーだ。なお、名前は筆者がつけた。
ところで、筆者には子どもがいない。じつは、赤ん坊をこの腕に抱いたこともない。まだ見ぬわが子の存在は、遠い未来の出来事のように思える――しかし、そんな蒙昧さを打ち砕くようなインタラクティブセッションが、会場の一角に存在していた。

リアルな赤ん坊の重みが再現されたマネキンを両腕に抱いて、HTC Viveのヘッドセットを装着したとき、筆者は衝撃を受けた。ポリゴンの世界のなかで、どこか筆者自身を思わせる顔立ちの赤ん坊が、両腕のなかにいたからだ。
こちらの動作にあわせて、VRのなかの赤ん坊の感情が変わる。腕のなかにいるものはマネキンだとわかっているのに、ミルクを飲ませ、げっぷをさせ、寝かしつけているうちに、なんとも形容しがたい気持ちが湧いてくる。おそらく、愛に近い――じつに奇妙な体験だった。
 |
それまで子どもという存在に対して懐疑的だった人間が、かれの子どもを抱いたとたん、心の奥底からわき出てくる愛情にとらわれることは、よくある話だ。このセッションの要点は、そういった感情を覚える対象が「ヴァーチャル」であることだろう。
育児は過酷な仕事だ。もしかすると先進国における少子化の原因の一端は、人々がその過酷さを、想像しすぎるからかもしれない。しかし、自分の赤ん坊を抱くことによってしか体験できない感情が、その過酷さを乗り越える原動力となることも確かだ。
そして「Real Baby – Real Family」は、みごとにこの「赤ん坊を抱く」という体験をシミュレーションし、われわれ人類が普遍的に持っている「愛」を、擬似的ではあるが、強く惹起させた。
もしかすると、これはゲームが打ち出したもっとも効果的な少子化対策かもしれない。なにせ筆者はあれから、子どもについて、じつによく考えるようになったからだ。
(もっとも、ゲームにまつわるカンファレンスで子どもに関する気づきを得るなど、原稿にするとき、斜め上過ぎるのではないかと不安になったのも確かなのだが……)