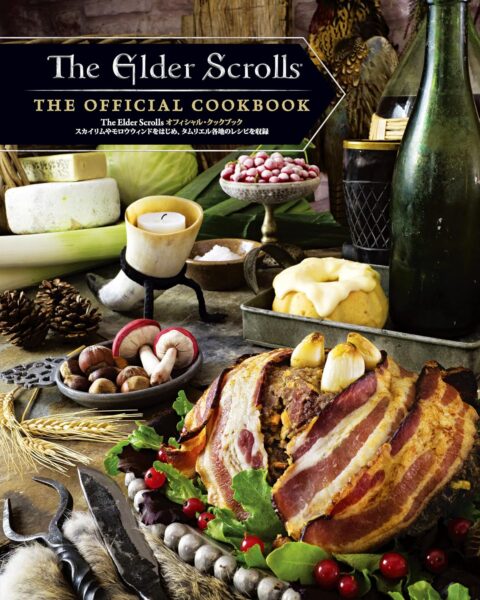いよいよセッションにも参加
二日目のことだ。初日のインタラクティブセッションの体験で気を良くし、浮足立っていた筆者は、とにかく目についた「セッション」に飛び込んでみることにした。
国内外のゲーム業界関係者が講演を行う「セッション」は、それぞれの講演室で同時多発的に行われた。おもな内容は、スライドを併用するスピーチや、パネルディスカッションなどだ。先日弊誌でレポート記事を掲載した、徳岡正肇氏の講演もここに分類される。
結果から言えば――筆者の突撃の結果は、散々なものだった。
取材ノートから引用してみよう。
「各ノードがタスク実行時に必要なコストをコアに返すよう設計する。このコストが1フレームの実行あたりに許可されたコストの閾値を超えると、そのフレームでの処理をコアに中断させ、次のフレームに持ち越す。これによって処理負荷が軽減され、スムーズなAIの動作が可能となる……」
これは、AIの設計に関するバンダイナムコスタジオの講演のメモだ。この文章の意味が理解できる方は、とりあえず来年の「CEDEC」に足を運んだほうがいい。理解できない読者は、安心してほしい。筆者にもわからないからだ。
この講演では、「Perception Tree」なる新奇なAIの内部構造がかなりのところまで明かされたが、筆者の専門性とまったくかけ離れているために、執筆は不可能だと判断するほかなかった。

スウェーデンのゲーム会社、Starbreeze社【※】が開発中のヘッドマウント型VRディスプレイ「StarVR」の講演についても、その開発意図やビジョンについてはよく理解できたものの、実際のスペックや製品構造に関する話題は、まったく理解できなかった。
レンズの屈折率から人間の視野角の問題まで、ありとあらゆる工学が取り上げられたが、データとその意味に話題が移ったとたん、筆者の専門から外れてしまうのだ。

※Starbreeze社
1998年設立されたスウェーデンのゲーム開発会社。2013年にリリースされた『PAYDAY 2』などが代表作。「StarVR」とは同社が開発している業務用のハイエンドVRヘッドセットのことで、5Kの驚異的な解像度や、210度の広い視野角が特徴。
このことは、現代のゲーム業界が、その内部で優れた魔法を用いている証左である。そして、魔法が魔法に見えてしまうのは、ひとえに筆者が文系であるためだ。おれも、理系ならよかったのに。そうすれば、このカンファレンスを心から楽しめたのに……筆者はすこし落ち込みながら、つぎの講演室に入室した。
すると、そこで登壇していたのは――「Call of Duty: Infinity Warfare」シリーズのディレクターだった。
できるだけ早く失敗せよ――欧米デベロッパーの開発哲学
ところで、筆者はPCゲーマーだ。十代のほとんどをPCに費やし、二十代半ばを越えた今でも、コンソールはひとつも持っていない。理由は単純だ――PCゲームがもたらす感動が、かつて筆者の心を完全に捉えたからである(……あと、金欠も原因のひとつだ)。
Infinity Ward【※】による2007年の作品『Call of Duty 4: Modern Warfare』は、筆者をPCゲーム界隈に引きずりこんだ作品のひとつだ。明快な一本道のFPSで、ハリウッド映画的表現を積極的に取り込んだ快作である。はじめてプレイしたとき、筆者はまだ高校生だった。
あの時のあのゲームを作った会社が、10年後のいま、目の前でゲーム作りについて語っている――その光景は、なんだか不思議なものだった。
※Infinity Ward
米ロサンゼルスに本社を置くゲーム開発会社。2002年設立。「Call of Duty」シリーズを手掛けている。
このセッションにおけるメインテーマは、「ディレクターシップ」。多種多様なスキルを持った人々が集まるゲームの開発現場にて、どのようにチームをまとめ上げるかだ。

そこで語られたのは、誰もが開発時に経験する「失敗」の重要性だった。Infinity Wardのディレクターはこう語っていた――
「開発の早い段階で、あるゲームが持っているポテンシャルを最大限発揮させるんだ。もちろん、そこで問題が発生する。しかし、そのタイミングが早ければ、それだけ問題を解決する時間が多くなる。できるだけ早く失敗すること――これが大事なんだ」
筆者にとって興味深かったのは、それぞれの会社を代表するディレクターたちの思想が、彼らのゲームに確実に反映されていることだった。「ディレクターの責務は、あるゲームがどうなるべきか明確にすること。目標への道筋を示すことだ」という発言からは、「Call of Duty」シリーズ【※】の明快さが、たしかに感じられたのだ。
※「Call of Duty」シリーズ
戦争をテーマとしたFPSゲームシリーズ。2003年に発売された初作『Call of Duty』以来、大ヒットを連発している世界的に人気のタイトル。
ベトナムと日本の共同開発から見えた中小企業の未来
このあたりから、理解できそうな講演をかぎ分けられるようになってきた。そう――格好良いからと言って、軽々しくAI関連の講演などに行くから、いけないのだ。
背伸びをせず、身近な言葉が入っている講演を選ぼう。そこで足を向けたのが、「日本とベトナムとで開発&PRしたSteam向けゲームの「反省と未来」」という講演だ。日本のゲームスタジオ「GIANTY」【※1】によるこの講演を選んだのは、ひとえに「Steam」という単語による。
メインテーマとなったのは、同社が開発したPCタイトル『GOKEN』【※2】と、その開発過程だ。

※1 GIANTY
株式会社GIANTY(ジャイアンティー)。日本のゲームスタジオ。2017年2月に「ICJ」より現行の社名に変更。代表作は『GOKEN』、『あやかし百鬼夜行』、『モンスター・ドライブ・レボリューション』など。
話のいきさつはこうだ。モバイルに注力している同社は、ガラパゴス化していく日本のマーケットに危機感を覚えていた。そこでPCゲーム市場に参入するべく、昨年末ごろからベトナムとの共同開発に踏み切った。
ベトナムを選んだ理由は3つ――「コスト」、「人材」、そして「技術」だ。ベトナムチーム運用にかかるコストは、日本の1/2 から 1/3。また、情熱を持った若い人材が多く、市場は技術革新とともに急成長を続けている。
海をまたいで手を結んだことで、開発はわずか10ヵ月で完了。結果として、10時間を超えるボリュームの作品を実現できたという。
しかし、なにもかもがスムーズに動いたわけではない。コミュニケーション、価値観の違い、スケジュール感の違いなどが、開発を進めるにつれて明らかになってきた。
日本とベトナムの差を対話によって認識し、よりよい環境を構築すると、ベトナムチームのパフォーマンスは目覚ましいほどに向上した――
「ベトナムの若者の、「良いゲームを作りたい」という情熱はすごい。単なるアウトソーシング先ではなく、共同開発の関係にまで踏み出したことで、すばらしいクオリティを実現できた」
とディレクターの三原龍磨氏は語った。

「いまの日本は、トリプルAタイトルしか売れない。ソーシャルゲームも、大手IPもの【※】がAppStoreの上位100位を占めている。この状況で大手企業と渡り合うために、日本であるという利点を考えていきたい」
※大手IPもの
IPとは「Intellectual property」、つまりは「知的財産」のこと。ここでは有名キャラクターを起用したゲームなどを指す。
これは偶然にすぎないかもしれないが、この10年間、筆者がPCゲーム(≒非国産ゲーム)ばかりをプレイしてきたのは、もちろん趣向にもよるが、ある意味で国産ゲーム(≒コンソール)全体の状況を表していたのかもしれない。
筆者がまだ幼かった90年代にもPCはあった。しかし筆者が本格的にPCゲームに熱中しはじめたのは、あきらかに2000年前後だ。そしてこの時期は、今年まで続いた日本ゲーム業界の低迷期と完全に合致する。
それはそれとして、低迷期のあいだにも戦っている人々がいたからこそ、私たちは長く暗い時代を終えることができたのだと思う。
その確かな兆しが、たとえば講演にあったような「はじめからSteamに向けて、コストを抑えるためにベトナムと共同開発する」という、「世界的にはごく普通だが、日本の中小企業には難しかった挑戦」の実現として、いま表れてきているのではなかろうか。
 |
さらに筆者は考える――中小企業によるさまざまな挑戦がようやく実を結び始めた遠因には、大企業である任天堂の「ある達成」によって、国内ゲーム業界が一気に活気づけられたことも大きいと。
そして大企業による「ゼルダの伝説」へ
今年3月に発売された『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』は、作品としての圧倒的な完成度でもって、私たちの横っ面を張り倒した。一般プレイヤーだけでなく、業界にかかわる人間もまた、同作の出来に驚嘆したはずだ。
その光景には、こんな言葉さえ浮かんでくる――「終わった」と思っていた日本のゲームが、暗い時代を終えて、野生の息吹を取り戻したのだと。
そのことを示したのが、すでに多くの読者も聞き及びであろう、任天堂の八つの講演だ。筆者が任天堂の講演に参加できたのは三日目、取材の合間をぬって、やっと一つだけではあった。

だが――この講演を聴講したとき、今回の『ゼルダ』は彼らにとって「まぐれ当たり」では全くないことが理解できた。これは極限まで効率化された開発環境を基盤に、狙った的を完璧に射抜いてみせた作品なのだ。その講演内容は、弊誌にて近日公開予定のhamatsu氏の記事にて、詳細に明かされるだろう。【※】
※hamatsu氏による任天堂講演レポートの前編にあたる、「任天堂のメディア発信の歴史」を考察した記事はこちらに掲載中です。(編集部注)
正直なところ、この任天堂の講演の内容に触れずに「CEDEC 2017」について語るのは、麺抜きでうまいラーメンを作るような仕事だ。
しかし、この鉢に盛られている具材はそれぞれに興味深いものばかり。砂場に技術者たちが回帰し、居ながらにして見るドローンが宙を飛び、VRで子育てを疑似体験する。欧米のゲーム企業の開発メソッドが明かされ、ベトナムと日本による共同開発が達成される――数々のセッションからは、ゲーム開発はもちろん、様々な分野へと波及していく技術のありようが伺えた。
ひとりのゲーマーとして、ゲームと、ゲームにまつわる技術が秘める可能性を心から味わう体験であったのだ。

「CEDEC 2017」で共有された知識は、やがて個別のコミュニティのなかで結実し、ゲームのみならず、現実をも変える技術として実現するだろう。ひとりのゲーマーとして、きたるべき明るい未来が、いまから楽しみだ。
【あわせて読みたい】
「戦争は、時間と空間のジレンマである」現代ウォーゲームが発見した“真実”——ゲームはいかに戦争の「本質」を捉えてきたか【徳岡正肇氏インタビュー】
本稿の著者・藤田祥平氏による、徳岡正肇氏のインタビューもあわせてお楽しみください。両氏の濃密なトークから、「ウォーゲーム」の魅力を改めて感じれる記事となっております。