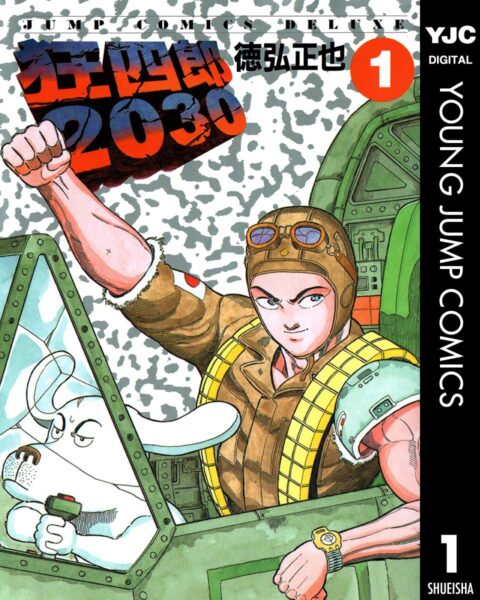『バイオハザード』というシリーズは非常に変わったシリーズだ。
『アローン・イン・ザ・ダーク』の影響を伺わせる、場面に応じてカメラポジションが瞬時に可変する洋館を探索する初代。
これまでの流れを断ち切りTPSというジャンル全体に大きな影響を与えた『バイオハザード4』。
そのあまりに偉大な功績にすら背を向けてとうとうFPSに舵を切った『バイオハザード7』、その流れを組む続編であり現時点における正統シリーズ最新作である『バイオハザード ヴィレッジ』。
そして2023年3月24日、シリーズ最大の転機作である『バイオハザード4』のリメイク作、『バイオハザード RE:4』が発売される。すでにmetacriticのスコアは93点を獲得するなど、そのクオリティについてはなんの心配もいらないだろう。
 |
私がここで考えたいのは『バイオハザード』とカメラの関係性の変化についてである。
『バイオハザード』シリーズほど、プレイヤーキャラクターとカメラの関係性が変わり続けるシリーズは無い、と言っても過言ではないだろう。
 |
なぜ『バイオハザード』はプレイヤーキャラクターと、それを映すカメラの関係性を、節目節目で大きく変化させる必要があったのか。
それは本シリーズが「アクション」であると同時に「ホラー」のゲームでもあったからだ、と筆者は考えている。
「アクション」のゲームであれば、ある種の定番やお約束のシステムをシリーズで踏襲し続けるということは悪いことではない。
だが「ホラー」ではそうはいかない。ゲームの世界にいきなり馴染んでもらっては困る。プレイヤーにはきっちりその世界に怯えてもらう必要がある。
「サバイバルホラー」というジャンルを提唱し、自ら「ホラー」という枷を自分にはめることによって『バイオハザード』というシリーズは、極めてユニークな道を歩んだシリーズとなっている。
『バイオハザード RE:4』が発売されるこのタイミングに、改めてシリーズのカメラとキャラクターの歩みについて振り返ってみよう。
文/hamatsu
※文中に『バイオハザード』シリーズのネタバレ、特に『バイオハザード7 レジデントイービル』と『バイオハザード ヴィレッジ』のネタバレが含まれますのでご注意ください。
キャラクターとカメラが分離したとき
ゲームが2Dから3Dになって大きく変わったこととして、キャラクターの操作とカメラの操作が分離した、ということがある。
『モンスターハンター』や、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』のような広大なオープンフィールドを駆け回るタイプのゲームにおいて、キャラクター操作と同時に、主に右側のスティックを用いてキャラクターの後方を追従してくるカメラを操作し、周辺を見渡すなどといった行為は、もはや当たり前のことといって良いだろう。

ゲーム空間におけるカメラの存在が明示化されたことで明らかになったことは、ゲームプレイヤーとは、映画でいうところの演技とカメラの両方を同時に行うという離れ業を当たり前のことのようにやってのけているという事実である。【※】
※さらにゲームの実況者とは、主演、撮影、さらに実況解説という、無声映画でいうところの活動弁士のようなことすら一人で行っているわけだ。
そして、キャラクターとカメラの操作が別々になることで改めて気づくのは、2Dの多くのゲームは「キャラクター操作とカメラ操作の両方をひとつのキー操作、主に十字キーやレバーの操作のみで行う」という極めて洗練された操作系を備えていたのだということである。
だが、3Dのゲームにもキャラクターとカメラが分離しないどころか、むしろ一体化したゲームジャンルが存在する。
FPSである。
FPSにおいてキャラクターを操作するということはカメラを操作することであり、そしてFPSにおける視線を操作するということは射線を操作するということとほぼ同義である。世界を「移動する」ことと「見る」ことと「撃つ」ことが、見事に融合したゲームジャンル、それがFPSである。
3Dのゲームの神様というものがもしいるのだとすれば、おそらくその神はFPSというジャンルを愛し、祝福している。
FPSというゲームジャンルが『Call of Duty』や『Apex Legends』のようなタイトルに代表される、現代においても定番の人気ジャンルであることは説明するまでもないだろう。しかし、そんな優れたFPSというジャンルだって万能ではない。キャラクターの視点とカメラを一体化することで失われたものだって存在する。
それは、プレイヤーが操作するキャラクターの身体である。
正確にはFPSだって特定のキャラクターを操作している以上、ゲームからプレイヤーキャラクターが無くなったわけではない、しかし、少なくともゲーム画面上からはキャラクターの手や持っている銃と言った一部を除いて、プレイヤーキャラクターは消えてしまっている。このことは決して小さくない意味を持っている。
「疑似物理フィードバック装置」としてのゲームキャラクター
ゲームをプレイしている最中に、「重さ」や「軽さ」といった感触を感じ取る人は多いのではないだろうか。
『モンスターハンター』でいえば、大きな「大剣」を振るう際には「重さ」を、軽量な「双剣」の操作に「軽さ」を感じるといった具合にだ。
基本的にはゲームコントローラには、「重さ」を表現する機能は備わってはいない。重い剣を振ろうが軽い剣を振ろうがボタンの重さが可変したりはしない。しかし、我々はしばしばゲームをプレイしていて、特に自身が操作するキャラクターの見た目や動作を通して「重量」を感じ取ってしまう。
 |
これがゲームキャラクターの持っている重要な機能のひとつ、「疑似物理フィードバック機能」である。
自身が操作するキャラクターの動きを三人称視点で「見る」ことで「重さ」を感じるというのは考えてみるとなかなかに不思議で興味深い現象だが、このキャラクター機能に着目したとき、FPSというゲームジャンルの持つ問題点も同時に見えてくる。
FPSが抱える問題点。それは、カメラとキャラクターをほぼ同一化してしまうことで、三人称視点のゲームであれば得られた、自身の分身たるプレイヤーキャラクターを「見る」ことで得られる物理フィードバック機能の多くが消失してしまうということにある。
FPSとはプレイヤーの身体感覚が希薄になりやすいゲームジャンルでもあるのだ。
とはいえ、それでもFPSというゲームジャンルのその基本構造が圧倒的に優れているという事実はそう簡単には揺らがない。
繰り返しになるが、キャラクターの視線と射線が自然な形で同一化出来ることからくる操作上のメリットは、そのデメリットを補って余りあるものだ。だからこそ、現在においても世界的に人気ジャンルのひとつとして存在感を保ち続けているのだろう。
今回、このような前振りから話を始めたのは、そうした「カメラと身体性」という観点から『バイオハザード』シリーズを改めて考えたいと思ったからである。
「カット割り」によって失われる方向感覚
1996年にリリースされ、国内外で大ヒットした初代『バイオハザード』だが、実は初期の『バイオハザード』はキャラクター操作とカメラ操作が分離していない。キャラクターの移動に応じてカメラポジションが瞬時に変化し、場所によってキャラクターの見え方が、引きの画にもなるし、アップにもなる。
『アローン・イン・ザ・ダーク』に明確な影響を受けた、背景を移動するたびにまるで映画のカットが切り替わるかのようにカメラポジションが瞬時に移動するこのカメラシステム──いわゆる「ラジコン操作」には大きなメリットとデメリットがある。
ひとつは既に述べたように、プレイヤーがキャラクター操作とは別にカメラ操作をする必要がないため操作系がシンプルであるという点だ。
プレイヤーはただ移動をするだけで自動的にカメラポジションが変更されるので、2Dのゲームとは明らかに違う臨場感が生じながら、3D化によって発生するカメラをプレイヤーが操作するという手間は省けているのである。3Dの良い点は引き出し、デメリットは省けているのだから素晴らしいというほかない。
だがこのメリットは同時にデメリットも孕んでいる。それは、プレイヤーの移動に応じて意図せぬカメラポジションに瞬時に変更してしまうことで、プレイヤーの方向感覚、操作感覚に狂いが生じてしまう、という点だ。
初代『バイオハザード』の固定カメラシステムは、その特性上、さっき前だったはずの方向が後ろに変わり、左だった方向が右に変わるという現象が起きてしまう(ゲーム中ではそこまでの極端な変化がおきないように配慮がされているものの、唐突に変化が起きることは避けようがない)。
だからラジコン操作とも言われる独特の操作システムを採用しているのだが、いわゆるアクションゲームとして『バイオハザード』を考えた場合、この操作やカメラのシステムはあまり適切なシステムとは言えない。
しかし、『バイオハザード』は「アクション」ではなく、「ホラー」のゲームなのである。「ホラー」として考えた場合、プレイヤーの方向感覚を狂わせるこのデメリットはむしろメリットに転じる。
敵から逃げようとしてドアノブに手をかけようとしながらも方向感覚が狂ってドアを開け損ねる瞬間などは、ホラー映画における「命からがら乗り込んだ車のエンジンが、かかりそうでかからない瞬間」をゲームというメディアで追体験したかのような感動すら覚えたものである。
 |
初代『バイオハザード』とは、3Dにまつわるデメリットを巧みに回避しながら、さらに癖のあるカメラワークや操作系というデメリットすらもホラーゲームにとってのメリットとして活用したゲームなのである。
しかし、歴史的な傑作である初代『バイオハザード』は一作目にして既に問題点もハッキリ露呈していた。ゲームの前半はあれほど怖かったのに、後半は怖くなくなるのである。
基本的には各種銃火器やナイフによってゾンビを始めとするクリーチャーを倒しながら進むゲームであるため、弾丸のリソースマネジメントに失敗さえしなければ、後半は余裕のある火力で圧倒出来てしまう以上それはしょうがないことであるとも言える。
そして『バイオハザード』がややこしいのは「怖くなくなったからと言って、ゲームとしてつまらなくなったわけでもない」という点である。武器としては若干心もとないハンドガンの残弾に気を配りながら常に周囲の警戒を怠らない必要に迫られる緊張感に満ちた「ホラー」として、後半は強力なグレネードやマグナムもバンバン使用しながら迫るクリーチャーを火力で圧倒していく「アクション」として楽しめるゲーム、それが『バイオハザード』というゲームだ。
そのことに作り手側も自覚的だったからこそ、『バイオハザード』というゲームは初代から周回プレイを前提とした作りになっているのだろう。3時間以内にクリアを達成し無限ロケットランチャーをゲットし屋敷を大火力で蹂躙するその時には「恐怖」は微塵も存在しない。
しかし繰り返しプレイすればするほどに「ホラー」とは別の側面の魅力があったことにも気付かされるスルメのようなゲームでもあるのだ。だからこそ加山雄三や鈴木史郎といった著名人にも何度も繰り返し遊ぶタイトルとして名前が挙げられるのだろう。
しかし、「ホラー」に対する「慣れ」は、『バイオハザード』における大きな問題点として多くのプレイヤーにすら認識され、そのことが『バイオハザード』というシリーズにマンネリや安住を許さず、大きな変化を促すきっかけとなっていくのである。そして『バイオハザード4』によってシリーズは大きく変化することになる。
ビハインドビューというTPSの「新しい標準」
なぜ『バイオハザード』シリーズはナンバリング第4作にあたる『バイオハザード4』で根本的な変化を遂げたのだろうか。
その一因としては、ゲームキューブでリリースされたリメイク版の『biohazard』がカメラ固定でラジコン操作のバイオハザードとして出色の出来だったからということがあるだろう。一度倒したゾンビが突如として蘇るクリムゾンヘッド(わかっていても滅茶苦茶怖い)などの新規要素を追加して登場した、この初期バイオハザードの完成形とも言えるであろうタイトルを出したことで、シリーズは次に向かわざるを得なくなったということはあるのではないか、と思う。
かくして『バイオハザード』は第4作にして「ビハインドビュー」というカメラシステムを自ら発明するのだが、このビハインドビューというカメラシステムの画期性とはどこにあるのか。
 |
ビハインドビューの画期性、それは三人称視点だから得られる、自身のキャラクターを客観的に見ることによって疑似的な重量の感触が得られる「身体感覚」の導入と、FPS的なゲーム中のプレイヤーの視線とカメラが一体化することによって得られる「臨場」の感覚の両立を成し遂げた点にある。簡単に言ってしまえばTPSとFPSの“いいとこどり”をしたのだ。
※ちなみにビハインドビューのルーツには『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の弓やパチンコを操作する際の三人称から主観視点に切り替わるシステム、『スーパーマリオサンシャイン』のポンプでの放水操作などがあるのではないかと筆者は考えている。この辺の任天堂のカメラの探求についてはまた別の機会に改めよう。
なぜ既存のTPSやFPSをそのまま踏襲する形にしなかったのか。それはやはり『バイオハザード』の根底には「ホラー」があるからだろう。
かつてのカメラとキャラクターに距離がある旧来のTPSでは、「自分自身の身体が危機にさらされる」という緊張感や臨場感に欠ける。それなら旧来のカメラ固定のラジコン操作の方がカメラアングルに変化が生まれる分、メリハリが生じている。FPSは非常に良くできたゲームシステムだが、危機的状況に陥り、時には容赦のない攻撃に晒され、傷つく「身体」に欠ける。
襲ってくる敵と正対し、的確な対応が出来れば打開可能で、それが出来なければ危機に陥る。このフェアな関係性から生じる緊張感、これが『バイオハザード4』は本当に素晴らしい。チェーンソー男やリヘナラドールといった強敵との対峙はその極致と言えるだろう。
 |
2005年に登場した『バイオハザード4』とビハインドビューというカメラシステムが如何に画期的な存在であったかは、それ以前と以降のTPSの在り様を比較すれば一目瞭然だろう。特に2004年にリリースされた『グランド・セフト・オート・サンアンドレアス』とその次回作である2008年リリースの『グランド・セフト・オートⅣ』のカメラシステムの違いなどはその顕著な例である。
さらに影響を与えた例としては、より対戦に特化した『Gears of War』シリーズ、今年リメイク版が発売された『Dead Space』シリーズなどが有名だろう。日本以上に海外のゲームシーンに対して大きな影響を与えているのである。
ゲーム単体の出来としても素晴らしく、後に与えた影響は絶大。おそらく2000年代におけるもっとも偉大なゲームのひとつ、それが『バイオハザード4』である。
その革新性とは、キャラクターとカメラの関係性の革新である。それはあまりに画期的でありながら、新しいスタンダードでもあった。そして『バイオハザード』というシリーズが本当にユニークなのは、そんな自身で確立した新しい標準にすら、安住は許されないということなのである。
 |
FPSによって生まれ変わる『バイオハザード』
画期的な一作となった『バイオハザード4』にも問題がないわけではない。それは、「あんまり怖くなくなった」という点だ。
いや、まったく怖くないわけではない。序盤の村やリヘナラドールといった特定の敵との対峙は非常に怖い。しかし、あまりにも汎用的で新しいスタンダードと言えるカメラシステムを発明し、ゲーム内容も非常に練られた本作は、「ホラー」というよりも、「アクション」としての側面が強くなってしまったように私は思う。
さらに皮肉なことだが、このあまりに良く出来た『バイオハザード4』によって、最も苦しめられたのは『バイオハザード4』以降にバイオハザードシリーズを作り続けなければならなくなった『バイオハザード』の作り手達だろう。
なぜなら偉大なオリジンである『バイオハザード4』は当然として、これを濃厚に意識して作られたフォロワータイトルすらも超えなければならないハードルとして立ちふさがることになってしまったからだ。特に日本発売はしていないものの、『バイオハザード4』の影響を明確に受けながら、「ホラー」としての側面をより強めた『Dead Space』はビハインドビューを採用したTPSタイトルの金字塔と呼ぶべき傑作である。
そのあたりの具体的な苦労や葛藤についてはユーザーである自分には想像することしか出来ないが、『バイオハザード』はシリーズ第7作『バイオハザード7 レジデント イービル』において、ついに自身で発明し、確立したビハインドビューを捨て、FPSとして生まれ変わることになる。
そして『バイオハザード7 レジデント イービル』にはFPSへとゲームシステムが変更されたと同時に、もうひとつ過去作との大きな違いが存在する。その変更とは、主人公イーサン・ウィンターズの顔をほぼ一切、画面中に写さないということだ。

これらの要素を採用した最大の理由は『バイオハザード7』がVR対応タイトルとして作られ、主人公とプレイヤーの一体感を高める上で効果的だと考えたからだろう。しかし、『バイオハザード』におけるFPSという形式の採用は、ユーザーとのシンクロ以外の別の効果を産むことに繋がっている。
すでに述べたようにFPSという形式は、3D空間でシューティングゲームを遊ばせる上で非常によく出来たシステムであるが、同時にキャラクターの身体感覚が希薄になりがちなシステムでもある。
そして『バイオハザード7 レジデント イービル』の主人公、イーサン・ウィンターズは、顔が一切映されない希薄化されたキャラクターである。そしてこのイーサンがゲーム中で次から次へとひどい目にあわされることになるのだが、ひどい目にあえばあうほどにひとつの疑問が湧いてくるのである。
「劇中で一番の化け物ってもしかして、この主人公イーサンなのでは?」と。
おそらく『バイオハザード7 レジデント イービル』の時点においてはイーサン・ウィンターズという主人公は匿名性の高い、プレイヤーとシンクロしやすい主人公として作られたのではないかと思う。
しかし、その続編である『バイオハザード ヴィレッジ』においては明らかに作り手側が意図的に、この顔も見えない主人公こそが劇中最大の謎であるという意図を込めている。FPSの欠点にもなりかねない希薄な身体感覚という特性を逆手にとって利用し、自分が操作するプレイヤーキャラクターに謎の根源を配置する。
そして疑念を抱かずにはいられないくらいに『バイオハザード ヴィレッジ』において、イーサンは手を切断され(その後サクッと縫合し)、やばい液体を浴びて皮膚が爛れまくるなどなど大変な目にあいまくり、そして何事もなかったかのように回復して次の戦いへと向かうのである。
なので最初から最後まで主観視点で進行する『バイオハザード7 レジデント イービル』と『バイオハザード ヴィレッジ』は、自分の分身たるこの主人公こそが一番やばいのでは?という疑念と共にゲームを進めることになる。
「自分の姿がほぼ見えない」というFPSという形式のもつある種の欠点が、むしろ本作においてはゲームの面白みであり、ゲームを進める推進力のひとつになっているのである。これは非常に巧みな作りだと思う。
恐怖は慣れてしまうが、疑惑は晴れるまで膨らんでいくからだ。この二作品をプレイした方が従来のシリーズとは違う妙な居心地の悪さを覚えたのだとすれば、その理由のひとつは「このどこか信用しきれない主人公の在り方」にあるのだと思う。そしてそれは作り手側によって意図されたものでもあるのだ。

『バイオハザード7 レジデント イービル』『バイオハザード ヴィレッジ』のFPS路線が単なる上辺のシステムの変化のみに終わらず、『バイオハザード4』以降の路線に行き詰まりを覚えつつあった本編に新しい風を吹き込めたのは、FPSという形式のもつ長所と短所を理解した上で、その短所すらも逆に活用するという設計の巧みさにある。
初代『バイオハザード』は固定カメラとラジコン操作によってホラー的な視覚効果と操作感覚を演出した。最大の転機作である『バイオハザード4』はビハインドビューの導入によって、自身の「身体」を晒しながらその場にいるかのような臨場感の両立を達成した。
『バイオハザード7 レジデント イービル』以降のFPS路線は、一体化しながらも自分で見ることができない自身の「身体」こそが一番不気味という──FPSにおける身体感覚の希薄さを逆手にとった手法により、既存のシリーズとは一線を画したプレイ感触を確立することが出来たのである。
「ホラー」に始まり「アクション」に終わる
2017年にリリースされた『バイオハザード7 レジデント イービル』、そして2021年にリリースされた正統シリーズ最新作『バイオハザード ヴィレッジ』と続けてFPSという形式を採用したが、同時に「RE」というリメイクシリーズもリリースされるようになる。
2019年に『バイオハザード RE:2』、2020年に『バイオハザード RE:3』、そしてこの度リリースされる『バイオハザード RE:4』。このREシリーズの特徴は、ラジコン操作でもFPSでもない、ビハインドビューを採用する形でシリーズをリメイクしている点にある。
 |
特に出色の出来と言えるのが『バイオハザード RE:2』だろう。TPSになることでアクション性が高まりホラー要素が薄れてしまうという『バイオハザード4』の時点で抱えていた欠点を、暗闇に包まれた閉鎖的な空間をか細いライトを頼りに進むという、プレイヤーの視界に制約を加えることで補っている。
それによって終盤まで緊張感が途切れなかった見事な設計は『バイオハザード7』とは別のアプローチで「ホラー」への原点回帰を感じさせる一作となった。
『バイオハザード』が『バイオハザード』である限り、「ホラー」という要素を完全に捨てることはないのだろう。時には「アクション」に寄せたタイトルが出たとしても、シリーズの原点には「ホラー」が存在し、常にそこに回帰しようとする。
こうなると久しぶりにラジコン操作の『バイオハザード』新作をやってみたいような気にもなるが、なかなか難しいのではないかと思うし、GC版の『biohazard』という高すぎるハードルを超えるのは並大抵のことではないだろう。
ここでひとつの結論を述べよう。『バイオハザード』とは、「ホラー」で始まり「アクション」に終わるゲームである。
一作目から定番のご褒美武器として「ロケットランチャー」が存在し、序盤ではプレイを続けることすらためらうほどの恐怖を覚えた相手を、最終的には一切の迷いなくヘッドショットを叩き込み、大火力で蹂躙出来るようになる。その「ホラー」から「アクション」へのふり幅こそが『バイオハザード』なのではないかと思う。
 |
「ホラー」の魅力を誰よりも理解しながら、同時に「人はやがて恐怖に慣れてしまう」という限界も同時にわかっている。だからこそゲームに慣れ親しみすぎて恐ろしさを全く感じなくなったとしても、そこには秀逸なアクションゲームとしての姿が立ち上がってくる。だからこそ繰り返し繰り返し遊んでしまう。それが私の考える『バイオハザード』というゲームだ。
このどれほど画期的な恐怖表現を確立したとしても、同時にそれが自身の力で打倒可能な「アクション」でもある限り、ユーザーはやがて当初感じていた恐怖にやがて「慣れて」しまうだろう。だからこそ、『バイオハザード』の作り手は常にゲームの在り方に根本的な変更を加える必要に迫られ続けているのである。
FPS路線の現時点における集大成と呼べそうな『バイオハザード ヴィレッジ』、TPS路線の原点回帰であると同時に到達点であろう『バイオハザード RE:4』以降のシリーズがどうなるかはまだわからない。もう一回くらいFPS路線を継続してもいいのではないかとも思うが、正直言ってそこに「慣れ」を感じつつあるのも事実だ。
『バイオハザード』はこれからもきっと「ホラー」であり続けるのだろう。その背後にある作り手たちの不断の努力に敬意を表しつつ、新しい『バイオハザード』、新しい「ホラー」をこれからも待ち望みたい。