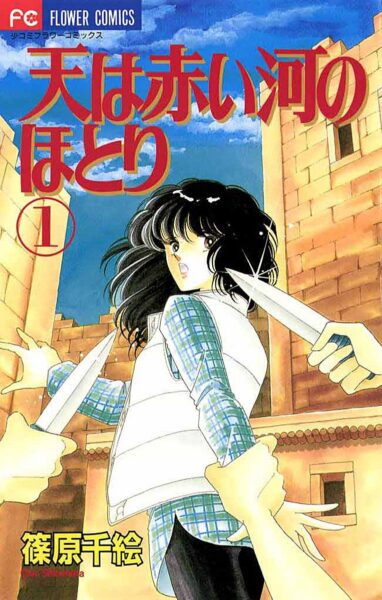9月27日、日本一ソフトウェアからあるタイトルが Nintendo Switch向けにリリースされた。タイトルは『ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団』(以下『ルフラン』)。いわゆる『Wizardry』系列のダンジョン探索ゲームだ。
ゲーマーならば3DダンジョンRPGをジャンルとして確立した『Wizardry』の名を知らない者はいないだろう。インスパイアされた後発作品は「ウィザードリィ・ライク」(以下Wizライク)などと呼ばれることもある。ゲームの内容としては、読んで字のごとく、3Dで描画されるダンジョンを一人称視点で探索し、戦闘し、装備を整えるなどキャラを強化し、より深くまで潜り、そしてボスを倒す。これがおおむね一般的なゲームフローだ。
さて、時節は夏が過ぎ去り秋の気配が濃厚であるが、じつは今夏、Wizライクのタイトルが複数リリースされていた。まず、コンパイルハートからはシリーズ続編『神獄塔 メアリスケルター2』。

スパイク・チュンソフトからは『ダンガンロンパ』チームが制作した『ザンキゼロ』。

アトラスからはシリーズのニンテンドー3DS最終作とされる『世界樹の迷宮X』。

一部プレイ意欲を維持するのが困難なものもあったが、それぞれに高い目標に向けて作られたであろうこだわりが見受けられ、遊ぶに値するものばかりだ。さらに11月29日には、今やファンらの熱気すら感じるようになった『ペルソナ』シリーズからのスピンオフ作『ペルソナQ2』がリリース予定。
※『ペルソナQ2』。なお初代はかわいらしいグラフィックと裏腹に、本格的『世界樹』であった。
そう、2018年後半戦は何故かWizライクタイトルが豊作なのである。けっしてメインストリームとは呼べないジャンルでこうした現象が起きるのはめずらしい。いちファンとしては嬉しい悲鳴をあげずにはいられなかった。
そんななかNintendo Switch向けに発売された『ルフラン』は、もともと2016年にPS Vita向けに発売され、その後PS4、PC(Steam)へと移植された。大雑把にいえば3度目の移植ということになる。いわゆる「底堅い人気」とゲームそのもの品質がなければ、なかなかおがめない光景である。
本作のタイトル名をご存知だった方はどれだけいらっしゃるだろうか。プレイ済み、さらにクリア済み、となると決して多くはないかもしれない。だが、本作はたしかにいくつか粗はあるものの、日本一ソフトウェアが挑戦したWizライク、そして新規IPとして、注目に値する快作だった。ダンジョン探索ゲームが多数リリースされている2018年だが、もっとも注目すべきなのは実は移植作である。そんな『ルフラン』の魅力を、いくつかの視点から紐解こう。
文/Yoichi Yumitori
引き込まれるストーリー
Wizライクでストーリー? と疑問に思われる方はおおいに正常だ。元祖『Wizardry』からして物語はゲームのフレーバーにすぎず、ダンジョンを探索させる動機づけにすぎず、そしてそれが基本形である。たとえば『世界樹』シリーズなどでは充分に引き立ったキャラクターたちが存在し、魅力的な掛け合いがある。だがしかし、それはあくまでも物語がリニアに展開される上で必要とされるパーツであるにとどまり、ゲームの根幹を成していると解釈するのは難しいところだ。
そこにきて『ルフラン』は特異なスタンスをとっている。主人公「ドロニア」とその従者「ルカ」を中心に織りなされるダークな世界は、その終着点まで着実に、しかしときによろめきながら、歩みを進める。サブキャラクターもそこに深く食い込み、あるいは掘り下げられる。それもごく自然な形で。

詳述するとネタバレになってしまいゲームの価値を激減させてしまう恐れがあるので避けるが、本作の物語を語る上で特筆すべき最大のポイントは、各ダンジョンに秘められたバックストーリーにある。通常のWizライクにおいて、ダンジョンとは踏破すべき対象であり、またはキャラを鍛え上げる場として設定されている。一方『ルフラン』も、同ジャンルの慣習どおり突拍子もないデザインのダンジョンが次々と登場するが、それぞれにきちんと存在意義が設けられているのである。
よほど意識してプレイしない限り、一周でその全容を把握することは難しい。もし既プレイでベストエンディングまで見た、という方でもぜひもう今一度プレイし、妙味を堪能していただきたい。そして初見の方は「なんとなく、そういうものだ」と認識しながらプレイすることで、一見脈絡のないダンジョンに、見えそうで見えない一本の線を感じ取ることができるかもしれない。

荒削りながらもプレイ衝動をかきたてられるダンジョンパート
3Dダンジョンの探索パートは比較的オーソドックスといってよい。しかし例外が2点存在する。「壁壊し」と「落とし穴」である。
「壁壊し」は読んで字のごとく、ダンジョン内の壁を特定のコストを消費することで破壊できるシステムだ。壊せない壁も多々あるが、それでもマップを一見しただけでは認識できないような意外なルート取りなど、最速最短の一本道をプレイヤーが積極的に発見する楽しさを埋め込んでくれている。

「落とし穴」は読んで字のごとくである。しかし、和製RPGの文法をあざ笑うかのように、そのペナルティはきわめて大きい。1階層分でも落下すればパーティー半壊、ゲーム中盤からは全滅する場所が多数ある。最初にハマったときは「これク……」という罵倒が脳裏をよぎったが、じつのところそんなに意地悪・理不尽なものではなく、”きちんと画面を見ていれば回避できる”のである。これはなるほどと感じたところ。そう、本来落とし穴というものはそのようなデストラップであったはずだ。

なお、バトルパートはオーソドックスなターン制。特徴的なのは、「カヴン」の存在である。これはいわゆる部隊、1戦闘単位として扱われる。カヴンには実際にバトルに参加するアタッカー枠が最大3枠、後方で様々なメリットをもたらすサポーター枠が最大5枠ある。戦闘に参加するのは5組のカヴンであることから、編成によっては15人ものキャラでバトルすることになる。
といっても毎回全員分の行動を入力するわけではない。原則的にはカヴン単位でしか指示は出せない。個別に細かい命令をしようとすると、特別なコストが必要になってくる。このため、「雑魚戦ではカヴン単位で戦闘、ボス戦のいざというときは各人に詳細な指示」という流れが美しくできあがっている。
日本一ソフトウェアらしくというか、バトルにかかわる要素(装備、隊列、職業等)が大量にあり、直感でプレイすると何がなんだかわからない大味なゲームに思えるかもしれないが、その実、突き詰めるとシンプルにしてディープなバランスとなっている。最初はぜひとも攻略サイトなどを読まずにプレイしてみてほしいところだ。
絵と音で迫るアートの力
これ以外にも注目すべきアートスタイルは、オブラートに包むと”独特”、直球を投げると”下品”だ。とりわけエネミーの造形は、性的表現を感じさせるものがきわめて多く、CEROの審査基準に対する猛烈な闘争心を感じずにはいられない。しかしこれが不思議と不快ではなく、そもそも陰鬱としている世界観に絶妙にマッチしているのだ。

音楽は佐藤天平氏が手がけている。楽曲数は多くない。サウンドトラックに収録されているのはわずか20曲。昨今のゲームミュージックのサウンドトラックのボリュームからすると少ないのは間違いない。しかしそれゆえに一般的に印象に残りがちなバトル曲以外にも多くの曲が耳に残る。少し聞けばイベントシーンがすぐに思い浮かぶ、そんなゲーム音楽は希少だ。とくにエンディングの曲は感動的ですらある。
なお、オリジナルサウンドトラックCDは限定版の特典だけで、現時点では単独で一般販売されていない。Switch版は、日本一ソフトウェアの直販やAmazon限定版などにも付随していない。商業的に難しい点はあるのかもしれないが、今後の展開に期待したいところだ。
※プレイしてから見ても味わいがある
『ルフラン』をWizライク完全未経験者におすすめするのはやや厳しい。複雑怪奇なゲームシステムがそこそこ高いハードルとして立ちふさがってくるからだ。しかし「昔ファミコンでちょっとだけ『Wizardry』やったな」、「そういえば無印『世界樹』やったっきりご無沙汰だ」、「最後にやったの『BUSIN』だわ」、そんな層に強くプッシュしたい。ほんの少しの下地か素養さえあれば理解するのは、じつはそこほど難しくない。
本作を充分にプレイし、クリアし、頭の中の3DダンジョンRPG純度を上げておき、しかるのちに『ペルソナQ2』を迎撃する。そんなスタンスも悪くないはずだ。