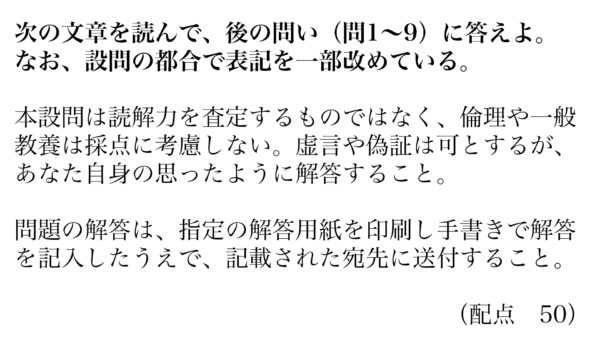「テキストアドベンチャーゲーム」と「小説」──媒体は違えど、どちらも“テキストを読ませて”我々プレイヤー/読者を楽しませてくれるエンターテインメントである。
このふたつのエンタメは、どちらも“テキストが主体”で、“ゲーム”と“書籍”というアウトプットの違いだけでしかない……と、想像してしまいがちだが、じつはさまざまな違いが存在する。
その違いとは、いったいどんなものだろうか?
今回、このテーマについて語ってもらったのは、ニトロプラスで活躍する実力派シナリオライター・下倉バイオ氏と、KADOKAWA在職時に『灼眼のシャナ』や『とある魔術の禁書目録』など数々の人気ライトノベルシリーズの担当を務めていた編集者・三木一馬氏(現在、編集/エージェント会社「ストレートエッジ」代表)のおふたりだ。

一見すると接点がないように思われる両氏による対談は、じつは過去に意外な邂逅があったことにはじまり、「ゲームシナリオ」と「小説」のそれぞれが持つ特色、そして“いじめ”といったエンタメにしづらいテーマに挑むスタンスについてなど、多岐に渡る内容となった。
このトップ級“シナリオライター✕編集者”対談で、「“物書き”とは、どのような人たちなのか」を垣間見ることができるはずだ。
13年前、じつは会っていたふたり
──下倉さんはゲームのシナリオライターとして、三木さんはライトノベルの編集者として、それぞれご活躍中ですが、“テキスト”を生業としているところに共通点があるものの、もちろん相違点もあるかと思います。
今回は、その“ゲームシナリオと小説の違い”について、話を伺うことができればと思っているのですが……じつは初対面ではないそうですね?
下倉バイオ氏(以下、下倉氏):
そうですね。2005年頃のことになるでしょうか。ボクはニトロプラスでシナリオライターになる前に、電撃小説大賞【※】ほか、いろいろな出版社の新人賞に応募していたことがあったんです。その頃、三木さんとお会いしたことがあって。
※電撃小説大賞
文庫の小説レーベル「電撃文庫」を刊行している旧メディアワークス(現KADOKAWA)が1993年に設立した小説の新人賞。毎年開催され、今年で25回を数える。第10回までの名称は「電撃ゲーム小説大賞」。同種の新人賞の中でも応募総数が一際多く、受賞作や選考落選作から多くの人気作家を輩出している。
──「選考に残っていますよ」、といったような連絡でしょうか。
下倉氏:
「見込みがあるから一緒にやってみないか」といった感じですね。電撃文庫のほかにも何件か編集部さんから連絡をいただきましたが、その頃ちょうど知り合いに声をかけられて、タッチの差でゲーム業界のニトロプラスに入ったんです。
三木一馬氏(以下、三木氏):
ゲームシナリオライターと並行して小説家になる、いわゆる「二足のわらじ」をしようとは思わなかったんですか?
下倉氏:
最初は「それもありかな」と思っていました。で、実際に「できるだろう」と思って、三木さんとも打ち合わせさせていただいた記憶があります。
ただ、やはりテキストを書く量がちょっと尋常じゃなくなるんですよね、「二足のわらじ」だと。当時、美少女ゲームはテキスト量が肥大化していた面もあり、1ヵ月に3~400KBだから……ライトノベルでいうと、文庫1~1.5冊くらいの量を書いていたんですよね。

その一方で、三木さんにプロットを出してやりとりをしていましたが、「これに応えるには、かなり集中してインプットする時間が必要だ」と思って……。それでゲームのほうに専念させていただいたという感じですね。
──では、電撃文庫の編集さんに何か不満があって身を引いた、というわけではなく……?
下倉氏:
それは違います(笑)。
──具体的には、どんな打ち合わせだったのでしょう?
下倉氏:
確か、何度か三木さんと打ち合わせした後に、「雑誌『電撃hp』【※】で開催されるコンペに出したい」といった話をいただいて、試験的に短編をひとつやりとりさせていただいた、という感じです。
※『電撃hp』
KADOKAWAの刊行していた小説雑誌。1998年から2007年まで刊行。電撃文庫で刊行されていた作品の短編小説や、書き下ろしの小説などが掲載されていた。実施していた新人賞『電撃hp』短編小説賞の受賞作もここで掲載されていた。後を継ぐ雑誌として『電撃文庫MAGAZINE』が現在も刊行中。
──まず『電撃hp』に短編が掲載されて、好評だったらそれを文庫で刊行、といったような形でしょうか。
三木氏:
そうですね。でも一方で、長編小説の打ち合わせもしていましたよね?
下倉氏:
長編は……確か、ボクから「魔女が空戦をやる」みたいなお話のプロットを出したはず。
で、当時、三木さんは似たようなジャンルを手掛けられていて「結果が出なかったのでどうしよう……」と考えていたようで、「(この作品)本当にやりたい? 本当にやりたいなら付き合うけど、苦労するよ……?」みたいな話をされた記憶があります。
──かなり具体的にやりとりを覚えてますね(笑)。
三木氏:
ボク、その頃の記憶が曖昧で申し訳ないんですけれども……下倉さんとのやり取りは、自然にフェードアウトしたような……?
間違っていたら注意してほしいんですけれども……ボクの場合、“原稿を読んだまま返事をしない”というのはないはずなんです。絶対に何かリアクションしているはず。

だから、その辺りで連絡が途切れてしまう理由は、ボクの指摘があまりにもたくさんあったり、作家さんが応えられなかったりとか……。
もしくは、ボクは“具体的な締切を設定しない”クセがあるのですが、“編集の指示があまりにもヘビーすぎて、作家さんから返事が戻ってこない”という流れで自然消滅するという可能性はあるな、と……どうでした?
下倉氏:
確か、自分のほうから正式に「ちょっとこのままだと、いまやっているゲームシナリオの作業がまずくなって、満足な仕事ができないので……」という内容でメールを差し上げた感じですね。
三木氏:
そうでしたか……それはよかった。覚えてなかったけれど……。
──その場合、無理に追いかけて書かせるのではなく、 “いい作品を書いてもらって本にしたい”という想いが、当時の三木さんにはあったのでしょうか。
三木氏:
あったはずです。懐かしいな……。あの頃、ムカついたこととかは言ってほしいです! いまから直しますから!
下倉氏:
いやいやいや、ムカつくことは全然なかったですよ、本当に(笑)。ただ、「三木さんって、やっぱりエネルギッシュだな、アグレッシブだな」と思いました。
あと、印象に残っているのは、原稿への赤入れ【※1】がスゴかったんですけれど、「『撲殺天使ドクロちゃん』【※q】の原稿には、もっとたくさん赤を入れているんです」と言っていました(笑)。

(画像はAmazon.co.jp: 撲殺天使ドクロちゃん (電撃文庫) eBook: おかゆまさき, とりしも: Kindleストア より)
※1 赤入れ
著者の原稿に間違いの指摘や変更の提案をすること。表記の由来は紙媒体で行う際は赤字で記入することから。「朱入れ」と表記することも。
三木氏:
それは事実です(笑)。それには理由があるんですよ。ギャグ小説は「ギャグのほうが、ストーリーがメインの作品よりもチェックに時間がかかって、修正する部分が多くなる」んですよ。
下倉氏:
たぶんそういう理由でしたね。ボクが投稿した小説もコメディ系でしたし。
当時、三木さんは「『ドクロちゃん』を担当していて、それで自分が下倉さんの作品の担当になった」といった話をされて、「あ、そうか」と。その話、すごく覚えています。
──ギャグというかコメディ系の作品で応募されていたので、当時『ドクロちゃん』を担当されていた三木さんが立候補した?
三木氏:
立候補制ですね。だから絶対ボクとしては引っかかるものがあって、ご連絡を差し上げたと思います。
──ということは、ライトノベル作家デビューしていた可能性も十分にあったのではないでしょうか。
三木氏:
ゼロではないですよ。あったと思います。
──当時の市場的には、その作品がヒットして人気作家になる可能性はどれくらいあったのでしょう。
三木氏:
ボクが担当したら100%ですよ(小声)。と、冗談はさて置いて。当時は、本当に軽い内容のものが受けた時期で。メタとパロディが多かったんですね。ただ、そのときの下倉さんの投稿作品には「萌え」が足りなかったんですよ。
あの当時もいまも「萌え」が大切なジャンルですが、ギャグのためにキャラを殺している描写があったんですね。なので、“ヒロインをもっと愛でることができるキャラにしていく”という作業を二人三脚で時間もかけてやっていたら……たぶんその作品は、あの当時にも読者のニーズはあったと思っています。
──「萌え」要素さえ加われば、人気になっていたかも……というわけですね。下倉さんとしてはある種の手ごたえや、「惜しかった」という印象はありましたか?
下倉氏:
いまだったら感覚は全然違いますが、当時はもう少しストーリー重視というか、真面目なものをやりたいなという思いもありました。まだ「萌え」というものに照れみたいなものがあったというのが、正直なトコロですね。
ニトロプラスのシナリオライターは、ほぼ放置されている?
──下倉さんは、ライトノベル作家としてデビューする可能性もありつつ、シナリオライターの道を進むことになったわけですが、シナリオライターになることを決断された決め手とは?
下倉氏:
んー、決断ではなく流れでなったというか……。中学生時代からライトノベルをずっと読んだり書いたりしていたので、「ラノベ作家になろう」としか考えていなかったですけれど(笑)。
で、地方出身のボクは大学を出たあとに無職のまま東京に出てきて、貯金を切り崩して投稿生活みたいなことをしていたんです。
──先ほどお話があった、電撃小説大賞ほかいろいろな出版社の新人賞に応募していた頃、ですね。
下倉氏:
当時、『ファウスト』【※1】といった雑誌のミステリ系の新人賞もあったので、「広い意味での“エンタメ系”で何か書けないかな」と思いはじめて創作を続けていました。
『ファウスト』が出たときに、その裏表紙をみたら確か『Fate/stay night』【※2】の広告が入っていて。「こういう雑誌の裏に、このような憧れるようなものが載っているんだ!」と思ったのが、強烈に印象に残っていますね。

2004年に発売されたPC用ノベルゲーム。『月姫』などの作品で人気を博した同人サークル『TYPE-MOON』が商業へと移行し発売した初の作品。同作のシナリオライターである奈須きのこが前述の『ファウスト』に小説を掲載していたことなどから、広告掲載が実現したと思われる。
(画像は「Fate/stay night」公式ページより)
※1 ファウスト
講談社の小説雑誌。2003年から2011年までの間、不定期に刊行されていた。ミステリ系の作品が多かった新人賞「メフィスト賞」受賞者(舞城王太郎、佐藤友哉、西尾維新など)と、シナリオライター(奈須きのこ、竜騎士07)による小説を掲載していた。
──ラノベ以外の選択肢が広がったんですね。
下倉氏:
そうですね。で、貯金を切り崩す生活も長くは続かなくなって「どうしようかな」というときに、当時のウェブ小説で知り合った、ニトロプラスの手伝いをしている仲間から声がかかりました。それで「わかりました」とニトロプラスに入ったのですが、エロに対しては多少の抵抗はありましたね。
ただ、ニトロプラスというメーカーが、エロだけにこだわるメーカーではない印象だったので「面白いものが作れるのならそれでOK」という感じで、ゲームのライターをはじめた形です。
三木氏:
当時、「18禁ゲームのシナリオライターってカッコイイ」という憧れがありましたよね。作品内容での上か下かではなく、世間の見方としてシナリオライターのほうがステージ的に上だったんですよ。
いまでこそ、ライトノベル出身の作家さんが文学賞を受賞したりとか、たくさんアニメ化したりとかで、若干ヒエラルキーに変化があるかもしれませんが、当時はエロゲ―全盛期で、そこで名を馳せるライターさんに対して、みんな一目置いていましたね。だから、シナリオライターになりたいという人も多かったし。
──ちなみに、賞に応募していた際の作品の傾向、投稿のペースは?
下倉氏:
2作品、応募していました。ひとつがパロディものというかすごくコメディ調のもので、もうひとつはバリバリのファンタジーで「竜に乗って郵便配達をする」みたいな内容でしたね。
ギャグものが二次選考まで行って、ファンタジーものが三次選考まで行ったんです。
──「一次選考で何度か落選」といった流れではなく、応募をはじめてすぐに高次の選考まで進んだのですか?
下倉氏:
それまではずっと一次選考落ちが続いていました。何が突然ハマったのかわからないですが、同時期に他のレーベルさんからも声がかかったりして、「さあ、これからラノベデビューを狙えるのではないか?」と思っていた時期に、ニトロプラスに入社したんです。
──下倉さんは、実際にはシナリオライターの道に進みましたが、もし作家になっていたら、どんな日々を過ごしていたでしょうね。
下倉氏:
それは少しの間、「二足のわらじ」をはいていたから、わかりますね。ライトノベルの作家は、編集さんと一蓮托生みたいなところがあるとすごく思います。
当時、別のレーベルの方に「(原稿用紙で)ひと月あたり400枚書いている」と言ったら、「その2倍書け!」と返されました(笑)。「いやいやいや、待て待て待て」と。
三木氏:
それは……その編集者が悪いのでは? もう少し意図や理由をしっかり伝えたうえで、編集者も一緒に頑張るような気持ちとセットで伝えないと、ただの暴言になってしまいますよね。
下倉氏:
それでも地方から出てきたばかりの立場からすると、妄信しそうになるトコロがあって「怖いな」と思いました。自分の場合はニトロプラスという居場所ができて、そちらでは気軽に作品の話ができる先輩のライターの方がいますし、かなり平静に、客観的に聞くことができましたね。
でも、もしカリスマ性のある編集者にそういうことを言われたら、どんな理不尽な命令でも「わかりました!」と言って全力を尽くしていたかも。それによって未知の領域を切り拓いて、何か得られるものがあったかもしれないな、と。
──しかし、編集者という存在は、まず作家さんに信用していただけないと何もはじまらないところがあるのでは?
三木氏:
そうですね。出版の話だと、まず編集者が読んで、その感想を伝えるんですよね。ですから、小説家は“誰かが見てくれる”というモチベーションが必ずありますし、そのやり取りから、信頼関係が生まれてくると思います。
ただ、ボクは文句もたくさん言いますから、作家さんは自信がなくなっていくかもしれませんが……(笑)。
──(笑)。
三木氏:
作家さんがすべての根幹なのは間違いありませんが、イヤな話“作家を利用して自分を存在証明させようとする編集者”も、一方でいるんですよ。
「作家をうまくコントロールしている俺」みたいな。ですから、被害を受ける作家さんもゼロではなかったと思います。
──なるほど。
三木氏:
これは、ボクの超個人的な意見ですが……2000年代後半より以前のラノベ編集者の編集能力自体は、そこまで高くなかったと思っています。もちろんボクを含めて、です。絶対に、大手出版社の人気の週刊漫画編集部にいる編集者のほうが優秀だったし、創作の真剣さなども全然違いました。
 |
でも、2000年代の後半になって「どうやらラノベは儲かるらしい」という話になって、複数の版元さんがラノベレーベルを創刊しはじめて、ラノベ編集者自体の数が増えてきた。そうすると、玉石混淆にはなりますが、優秀な編集者も生まれはじめます。
そうじゃない編集者の中には──いろいろな部署から異動してくる方もいたので──威張り散らすタイプの編集者もいたんでしょうね。これはなかなか難しい話で、「子が親を選べない」と一緒で、「作家も編集者を選べない」ので、チームとなる運の要素はあると思います。
──一方で、ゲームのシナリオライターの場合は、ディレクターであったり、チーフになるライターさんのような存在が、作品に対して指示を仰いだり、相談相手となったりするポジションになるのでしょうか。
下倉氏:
普通のゲーム会社は、たぶんそうだと思うのですが……ニトロプラスはそこら辺については放任主義なので……(笑)。
──チームという形態で、集団作業はしているのですか?
下倉氏:
部署としてはそうですね。日頃の悩みなどを話し合ったり、観た映画のココがすごくよくて、それが自分の作品のこういう要素に近い、といった話は、けっこうします。
ただ、作品については、基本的に最初に出すプロットについて反応をもらうだけで、あとはほぼ放置、です(笑)。
──「面倒見のいい先輩」がいる感じでしょうか。
下倉氏:
そうですね。雰囲気としては「お前が自分の力で1本をモノにしろよ」という状況で、シナリオを書いている感じです。
三木氏:
ニトロプラスさんで企画のGOが出る仕組みは、最初はチームやシナリオライターさんどうしで企画書を出し合って「これで行こう」と責任者が決めて、その後でシナリオライターやほかの開発チームのメンバーが集められる、という感じなのでしょうか?
下倉氏:
ウチの場合はちょっと特殊かもしれませんが……シナリオライターがやりたい「企画」を、社長と取締役に持って行き、OKが出たらシナリオを書き進めていく感じです。
三木氏:
「これやりたいです」と持って行っても、「ラインがいっぱいだからダメだ」と言われることもありますか?
下倉氏:
ウチの場合は、シナリオライターだけが先行して執筆していくという進め方が多いですね。ノベルゲームはお話ありきで、それに演出をつけていくという作り方が多くなりますから、先行してシナリオが積んである分には、むしろ好都合というか。
アクションゲームなどシステムも関わってくるストーリー作りだと、こういった作り方はできないと思うのですが……。
三木氏:
複数の企画をコンペにかけるというわけでもなく、1回ごとの企画提案なのですね?
下倉氏:
そうですね。1回ごとですし、それはライターが面白いとか企画のディレクターが面白いと思っているものを「わかった。じゃあ任せよう」みたいな関係性でやっています。