ニトロプラスでの下倉バイオ初仕事は、『月光のカルネヴァーレ』
──下倉さんが、はじめて「自分の力でモノにした1本」とは何だったのでしょう?
下倉氏:
2007年の『月光のカルネヴァーレ』【※】という作品ですね。そのときにはまだ、1本作るので精一杯でした。読み物としてきちんと作ろうという意識はあったのですが、「分岐を作ればいいんでしょ?」みたいな考えで、あまりゲームらしくなかったという反省があります。
「ヒロインを変えて、お話の結末を作ればゲームになるよね、ノベルゲームになるよね」というくらいの意識しかありませんでした。

たぶん、そのまま続けていたら、ストーリー中心にライティングを続けていたと思いますが、その後、ディレクターから「もっとお前の武器を活かす作品を」という話を受けて、企画を練って作ったのが2008年の『スマガ』【※】という作品です。
このとき、ようやくシナリオライターとして「ゲームのシナリオを書くことがうまくできたかな」と感じました。胸を張れる作品がようやくできた、と。

──『スマガ』は、作中の題材としてループ構造を扱っていました。小説でも“ループもの”といえるものは、すでにいくつかありましたが、ゲームとの親和性は高かったのでは?
三木氏:
そうですよね、やり直しができるから。
下倉氏:
だと思いますね。ちなみに、『スマガ』の企画の仮タイトルが“魔女イリヤ”でした(笑)。ボクも当時やっぱり『イリヤの空、UFOの夏』【※】“どストライク”の年代でしたので。
作家視点で『イリヤの空、UFOの夏』を読むと、後半に行けば行くほど、エンタメの作り方という“いやらしさ”と“悲劇的な展開”みたいなものが、すごく襲ってきたんですよね。

(画像はAmazon.co.jp: イリヤの空、UFOの夏 その1 (電撃文庫) eBook: 秋山 瑞人, 駒都 えーじ: Kindleストア より)
もちろん読者として、すごく心を揺さぶられたのですが、読んでいるときに「作り手の物語の扱い方って倫理的な何かが浮き出てくるよな」という感覚があったんです。
そこで、あからさまに用意された悲劇を“ループもの”としてストーリーの中に取り込むことで、「なぜそのような悲劇が起こらなければならないのか」という作者側の“業”みたいなものを取り込んだゲームができるのではないかと、当時のボクは考えたのだと思います。
──中身についてはぜひプレイして味わっていただくとして、作品のボリューム的にはどのくらいの分量になるのでしょうか。
下倉氏:
4メガバイトくらいです。
三木氏:
すごいですね。1.5メガくらいあれば十分長いシナリオですよね。
下倉氏:
そうですね。『Fate/stay night』などが出た後は、テキスト量もガンガン増えていて、ライターも複数人で担当して……というのが当たり前になったと思います。
メディアがDVDに移行して、容量を気にせずフルボイスにできたのも大きかったのではないでしょうか。
──小説だと、10〜13冊くらいのストーリーを考えることになるわけですよね。
三木氏:
ですね。でも、ヒロインごとにわかれているから、内容が重なる部分もあるのかな。だから一概には言えないですが、4~5冊分くらいの長さとすれば理解はできます。
あと、ゲームはいい意味で“演出を他者にも依存できる”と言いますか、声やBGMや背景といった要素がある。
 |
物語のジェットコースター的な部分で、レールがいろいろな方向に脱線してもいいんですよね。「こっちに行けば富士山が見えるルートがあるよ」とか。いい意味で、何もない演出をワザとしてもいいですし、物語を彩る描写を入れていってボリュームが増えるほうがいい、というところがあるのだと思います。
でも小説では、それがあると少し邪魔なんですよね。その点は、ゲームとの違いを感じます。小説は、全体的にひとりでまとめる作業になりますね。
下倉氏:
ゲームの場合、先にまずポンっと1本のパッケージに対してお金を払ったお客さんが「よし勝負だ」と触れるものなので、ある程度「最後まで読んでくれるだろう」という前提のもとにお話を作れるところがあります。
でも、たぶん複数冊のシリーズを前提とした続刊ものライトノベルだと、1巻で「え? これは……」みたいな印象があると、そこで詰まってしまうことがあると思うんですよね。
──三木さんが担当された作品で、最初から「全10巻構想」みたいな大長編パターンはありますか?
三木氏:
『ソードアート・オンライン』【※】というタイトルが……(笑)。最初から「あれ、どうすれば全部出し切れるんだ」と思いました。

(画像はAmazon.co.jp: ソードアート・オンライン1 アインクラッド (電撃文庫) eBook: 川原 礫, abec: Kindleストア より)
──ウェブ連載を経て、できあがっているものだったので、かなり特殊な例ですね。
三木氏:
基本的には、1巻ずつ積み上げていく方法が主流ですよね。
下倉氏:
その方法の場合、お客さんの反応によって、当初予定していた方向から大幅にズレていくことはあるのでしょうか?
三木氏:
もちろん、大いにあります。結局、物語の大筋は同じですが、過程が違いますね。その変化が、作家さんの“成長の証”だったりするので、リアルタイムでの面白さをとっていきます。
漫画の連載でもそうでしょうが、リアルタイムな物語のほうが、魅力的に描かれるんだろうなとは思います。
──ゴール地点が変わらない範囲で、読者の反応を見つつ臨機応変に「次はこういうことをやろう」と、作家さんと相談する感じでしょうか。
三木氏:
お話の展開よりも、キャラクターが大事ですね。「どのキャラクターの、どんなシーンを見たいか」という観点で予定を軌道修正することは多いかもしれません。
──三木さんの話を受けて考えてみると、下倉さんが行うゲームシナリオ執筆の場合、どのキャラクターにどれくらいの出番を与えるかというのは、事前に決めたら後から調整はできないということになると思います。いかがでしょうか?
下倉氏:
難しいところです。基本的に、ゲームはプレイヤーに選択権があるものなので、作り手の倫理としてはあまり“えこひいきできない”という感覚がすごくあります。
「自分はこのヒロインが好き」、「ボクはこのヒロインが好き」というユーザー全員が納得できるように、イベントCGの枚数やシナリオの内容、量をなるべくフェアに、公平に分けようという意識が強くあるんです。
──完成前、作品情報を発表したときの反響の大きさで、実際の仕上げのときにさじ加減を調整することも難しい?
下倉氏:
ゲームの場合は、フィードバックを内容に反映する時間がないと言えます。情報が出ている頃には作品のプロットは決まっていますし、お客さんの反応に耳を傾けても、まだ世間に出していない作品のプロットを変えちゃうだけの確信が得られるかというと、それは製品からの反応でないと難しいです。
ゲーム本編とファンディスクのように分かれていれば、その調整は利きますが、情報公開・宣伝時点でのフィードバックを反映させるのはリスクが高そうです。
小説は“二人三脚”で、ゲームシナリオは“集団”で作り上げるもの
三木氏:
ところで、いままで特にイラついたディレクションはありました? 「こんな指摘……なんだよこのディレクター」みたいな。
下倉氏:
「正直、この子、ぜんぜん可愛くないんですよねー」みたいなことを言われたことが(笑)。
一同:
(笑)。
下倉氏:
そんな感想だけを言って帰っていきます(笑)。
三木氏:
えぇー? 「ここはこう直そう」とかじゃないんですか。
下倉氏:
編集者的なコミュニケーションスキルがあれば言えるのでしょうが……スタッフの中にはできる人もいれば、できない人もいるので(笑)。でも、感想はやはり重要だと思います。
──読者目線での貴重な意見になりますしね。
下倉氏:
そうそう。
三木氏:
そういうのを、「バックネット裏でからあげクンを食いながら言うやつ」とボクはたとえています。
「お前は楽だよな! グラウンドに降りて来い!」って。
下倉氏:
(笑)。でも、作品を世の中に出すということは、そういう人を相手にするということなので……。
三木氏:
偉いですねえ、器がデカい。
下倉氏:
本来なら“バックネット裏”という遠くで言うようなことを、目の前で言ってくれる人がスタッフにいることは、すごく幸せなことだと思います。そういう人間はなかなか貴重です。
──小説家だと、編集者と打ち合わせをしている期間は作品が世に出ません。編集者にしか見せないため煮詰まることもあると思います。
一方で、ゲームは会社の中で何人かに見てもらう機会がある、と。編集者との二人三脚になる“小説”と、集団での制作になる“ゲーム”との違いですね。
三木氏:
ボクは、その作品完成までの過程の違いは、それぞれ一長一短だと思います。
アニメの脚本家がそうなのですが、いろんな人から好き勝手に言われることがあります。直列回路・並列回路みたいなもので、対応するには“意見の調整ができる脳みそ”が必要になる。同じ脳みそでも“創作で深く関わる脳みそ”とは違うものです。
 |
つまり、打ち合わせ内容をうまく取捨選択して自分なりに咀嚼したり、誰の意見に重きを置いて改稿したりするかとか、そういう部分を見極めるスキルを持てる人でないと、たくさんの人が参加する打ち合わせは難しいと思いますね。
ちなみに、小説の“作家と編集者の1対1形式”でも、「好きなようにやっていいよ」という編集者もいるので、作家の味だけで作れるときもあります。
──作家の個性を出したい場合は、1対1のほうが有用かもしれないと。下倉さんはそういった面での向き不向きはありますか?
下倉氏:
アニメ制作の場では、より人数が増えていろいろな人がいるでしょうし、そういった場でいままでと同じモノづくりをするのは大変だろうと思います。
三木氏:
でも、ゲーム作りを進めていくうちに、ディレクターさんなどから別の意見を言われたりしませんか?
下倉氏:
現状のニトロプラスの規模が、ディスカッションでも腹を割って話すことができるギリギリの人数かな、という感覚があります。
人が多くなるにつれて、「役割分担で権限のないところに口を出さないようにしよう」であるとか、「とりあえずここは目をつぶって通そう」といった駆け引きも出てくると思うのですが、いまくらいの人数でモノづくりの経験を積んでいると、きちんと「正直どう思う?」というやり取りがお互いにできて、納得してきちんと制作ができる環境なのかなと。というのも、同じ場所に顔が見える距離で集まって作っているので。
三木氏:
それができるのであれば、アニメの脚本もできますよ。大丈夫! この記事を読んでいるビデオメーカーのプロデューサーさんはぜひ下倉さんに(笑)!
──『スマガ』以降、お仕事の履歴としてはファンディスクの『スマガスペシャル』を経て、『STEINS;GATE』【※】と続きます。『STEINS;GATE』での参加形態をお聞かせいただけますか。

下倉氏:
『STEINS;GATE』は、企画初期に「構成補佐」で参加しています。『スマガ』で“ループもの”をやっていたので、その経験から「ここはこういう構造にしたほうがいい」といったことを伝えました。
ここでも最初のうちに腹を割って「こういう欲しいものがある」ということをお互いやりとりできたので、それで上手くいったのかなと思います。
──その後の、ニトロプラスで下倉さんが手掛けられた作品では、最初から最後までひとりで全部執筆されたということですか?
下倉氏:
『凍京NECRO<トウキョウ・ネクロ>』【※1】は深見真さん【※2】の原案がありましたが、基本的にはシナリオは自分が責任を持ってフィニッシュさせるという形でやらせてもらっています。

※2 深見真
小説家。脚本家。漫画原作者。富士見書房(現KADOKAWA)が主催していた富士見ヤングミステリー大賞を受賞し、2002年にデビュー。銃器、武器、格闘技などを題材にしたアクション作品を数多く発表。『凍京NECRO<トウキョウ・ネクロ>』では原案を担当。
──いわゆる「ヒロインAは下倉さん、ヒロインBは別の方」といった制作スタイルは、ニトロプラスさんのやり方として、あまりないことなのでしょうか。
下倉氏:
そうですね。それができたら楽なんでしょうけど(笑)。
──分担方式でやってみたいということはありますか? 共作という形になりますが。
下倉氏:
うーん、難しいですね。ヒロインを各ライターが分担することで生まれるメリット・デメリットはあると思っていて。ウチのゲームはまず、「キャラクターが第一にあるゲームではない」という感じがしています。
ストーリーの流れや全部プレイしたときのゲーム全体の要素が組み合わさったときの達成感であるとか、キャラクターとは別の要素がゲームとして働くように組み立ててあると思うので。
──確かに。2013年発売の『君と彼女と彼女の恋。』【※】は、ゲームならではのギミックが仕込んでありましたが、そこも含めて下倉さんの作品であるということでしょうか。
下倉氏:
そうですね。キャラクターの個性を出すところも頑張りますが、ゲームとしての仕掛けであるとか流れをきちんと描きたいなと思い、ひとりでやらせてもらいましたね。
──それは、シナリオライターという領分からはみ出ているかも?
下倉氏:
そうですね。最初は「テキストをライティングする仕事かな」と思っていたのですが、だんだんゲーム作品をスタッフと一緒に作っていくうちに、「ああ、それじゃダメなんだな」と感じました。
ゲームシナリオというものは、演出をアテにしなくちゃいけないし、音楽をアテにするところはストーリーを過剰に書く意味がないので省略しちゃってもいいですし……完成品としてうまく機能するシナリオを書くことに注力するようにしています。
──“監督”兼“編集者”兼“シナリオライター”くらいのことをやっておられるのですね。
下倉氏:
イベントCG(1枚絵)をどこに入れるかくらいまでは、シナリオライターが決めています。恐らくライトノベルでいえば「イラストレーターを誰にするか」、「挿絵をどこに入れるか」ということもシナリオライターに権限があるようなイメージです。
だから、電撃文庫に投稿していた頃は、挿絵などは全然感覚がわからなくて……「なんで電撃文庫は冒頭にこんなにカラーページが多いんだろう」と思っていました(笑)。
当時はストーリーにしか興味がなかったのですが、自分でゲームを作るようになると市販のライトノベルを読んでいるときに「なんでここに挿絵が入ってないんだよ」と怒るように(笑)。
──見せ方まで意識が行くようになったのですね。
下倉氏:
はい。そこはゲームを作ったことで、大きな変化がありましたね。
大学生時代の電撃文庫は、自分にとってすごくホットな存在だった(下倉氏)
──ゲームのシナリオライターは、編集者と二人三脚の小説家よりも、じつは孤独な作業なのかもしれませんね。独りで書いていて辛いと思われましたか?
下倉氏:
それまでもずっと書き続けて、新人賞に落ち続けていたので大丈夫でした(笑)。「世の中はまだ認めないかもしれないけど、俺の書くものは面白いはずだ」と、書くことへの精神的な耐性だけはすごくあったので、何年かの投稿時代の経験が役立った感じがします。
三木氏:
だいたい20年前くらいということでしょうか? 電撃小説大賞への投稿だと、第6回、第7回ですね……『僕の血を吸わないで』の阿智太郎さんとか、『天国に涙はいらない』の佐藤ケイさんとか、そのあたりですよね?
『僕の血を吸わないで』(KADOKAWA/1999)、『天国に涙はいらない』(KADOKAWA/2001)
(画像は僕の血を吸わないで (電撃文庫) eBook 、 天国に涙はいらない (電撃文庫) eBook|Amazonより)
下倉氏:
当時、大学生のボクにとって、電撃文庫はすごくホットな存在でした(笑)。書き出したのは中学生の頃からだったので、ずーっと長くやってはいたんですけれども。
本格的にやり出したのは、大学生になってインターネットで個人のサイトを持って、ネットでweb小説を発表してからですね。けっこう盛んにやっていましたよ。
三木氏:
当時のweb小説といえば、まさに黎明期の頃で、ご自身のホームページで掲載するパターンですよね?
下倉氏:
そうですね。まあ「ウェブリング」【※】とかがあって、それで極少数の人間がやっていました。投稿サイトも、いまの「小説家になろう」【※】みたいな大きなところがあるわけではありませんし。
※1ウェブリング(WebRing)
インターネット黎明期に開発された、似たジャンルのウェブサイトをつなぐためのサービス。個人サイトのURLを登録し、繋ぐことによって同好の士との連携を容易に行うことができた。
※2 小説家になろう
株式会社ヒナプロジェクトが運営している小説投稿サイト。当初は個人サイトとして公開されたが後に法人によるサービスに移行。2018年現在、日本でも有数の投稿者数、閲覧者数を誇り、掲載された作品が書籍化される事例も多い。
三木氏:
「Arcadia」【※】もありました?
※Arcadia
個人が運営していた小説投稿サイト。2000年頃からインターネット掲示板として公開されていたものが後に小説投稿に特化し、一時は『小説家になろう』よりも多くの作者と読者で賑わった。現在サイトは更新停止中。
下倉氏:
「Arcadia」はギリギリあったかな……。ただボクはどっちかというと「2ちゃんねる」の「創作文芸板」【※】などから発祥した「アリの穴」【※】とか、もっと殺伐としたところで投稿していたんです(笑)。
※1 「創作文芸板」
2017年に「5ちゃんねる」へと名称を変更したインターネット上の匿名掲示板「2ちゃんねる」。その中でも文章での創作活動についての話題を扱う掲示板のこと。作品の感想など読み手向けの話題ではなく、創作の悩み相談・新人賞の話題など、書き手向けの話題を扱う。
※2「アリの穴」
上記の掲示板から派生したサイトのひとつ。2002年~2013年頃までは小説の投稿が行われていたが、サイトは現在消滅している。個人運営との情報もあるが詳細は不明。トップページには「匿名投稿・添削できる修行場所。煽り・罵倒は覚悟の上で」と注意書きがあった。
三木氏:
あの当時は、確か富士見ファンタジア文庫さんのセールスが一番素晴らしくて、電撃文庫はその次くらいだった気がします。
下倉氏:
読んでいる小説の好みとしては、やっぱり富士見ファンタジア文庫ってメジャーなタイトルが安定して続きを出していて、メディアミックスもバンバンやって、っていうイメージがあった中で、小説が好きな人間が感じていた「何か新しいものが来るぞ!」という感覚は、電撃文庫のほうが強かったかな、と思っています。
三木氏:
なるほど! 電撃小説大賞は第何回ごろから投稿されたか覚えていますか?
下倉氏:
自分の投稿記録によると2004年に結果発表されたものに応募しています。
三木氏:
じゃあ、第11回ですね。
下倉氏:
その年の結果を見たら、ずっと「日日日さん」【※】の名前があって。いつも「この人、なんて読むんだろう?」と思っていた年です。
※日日日(あきら)
小説家。『ちーちゃんは悠久の向こう』(新風舎刊/のちにKADOKAWAにて再刊)にて第4回新風舎文庫大賞で大賞を受賞しデビュー。2005年ごろに複数の新人賞で入選を果たし、業界の内外で話題となった。直近では『あんさんぶるスターズ!』、『プリンセスコネクト! Re:Dive』などゲームシナリオの分野でも活躍中。
三木氏:
日日日さんは、電撃文庫でも一次選考通過されていました。
──複数のレーベルで受賞してデビューされました。
三木氏:
確か、一斉に別々の作品を投稿されていたんですよ。それで結果的には電撃小説大賞では受賞しなかったんですけれど、他の賞をたくさん受賞していて、すごく記憶に残っています。
下倉氏:
一次を通ったときから「また日日日がいるぞ」って、ボクら投稿者の間でもすごく話題になっていました(笑)。
──日日日さんの活躍はまるで漫画みたいな出来事でしたね。これが2004年頃のことですが、その頃、三木さんはどうしていたのでしょうか。
三木氏:
ボクは電撃小説大賞の第8回(2001年)から選考に参加しています。そこで、初めての担当作家さんである『A/Bエクストリーム』の高橋弥七郎さん【※】と出会ったので。
※高橋弥七郎
小説家。第8回電撃ゲーム小説大賞に応募した『エクスターミネーターA/B』が選考委員奨励賞を受賞。同作を改稿した『A/Bエクストリーム』にてデビュー。2002年から刊行された『灼眼のシャナ』は3度のテレビアニメ化に加え、劇場映画化やOVA化なども果たし、電撃文庫を代表する作品のひとつになった。
──のちに『灼眼のシャナ』で大ヒットとなる高橋弥七郎さんを見い出したんですね。
『A/Bエクストリーム CASE-314[エンペラー]』(KADOKAWA/2002)『灼眼のシャナ』(KADOKAWA/2002)
(画像はA/Bエクストリーム CASE-314[エンペラー] (電撃文庫) Kindle版、灼眼のシャナ (電撃文庫) Kindle版|Amazonより)
三木氏:
1作目は売れなかったんですけどね……。その後の第9回が、鎌池和馬さん【※】を担当させていただいたかな。でも鎌池さん自身は三次選考で落ちていますが……。
※鎌池和馬
小説家。第9回電撃ゲーム小説大賞に応募した『シュレディンガーの街』が三木の目に留まり、2004年に完全新作『とある魔術の禁書目録』にてデビュー。同作は、2度のテレビアニメ化と劇場映画化を果たし、2018年10月からは『禁書目録』テレビアニメ3期が放送される。スピンオフコミック『とある科学の超電磁砲』も2度テレビアニメ化されるなど、いま現在も『とある』プロジェクトは大きく展開されている。
──その頃から、受賞作ではない作品に対して作家さんに声がけなどをされていたのでしょうか。
三木氏:
していました。第9回は、その(鎌池さんの)落選作でしたし、第8回もハセガワケイスケさん【※1】が応募されていました。のちに『しにがみのバラッド。』をお書きになる作家さんです。
その当時、「電撃hp短編小説賞」という別の賞もありまして、そこでは『撲殺天使ドクロちゃん』のおかゆまさきさん【※2】も拾い上げという形でデビューしています。
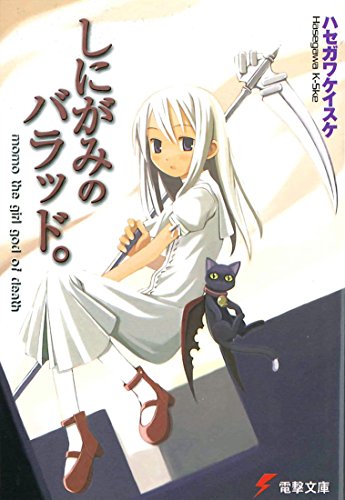
※2 おかゆまさき
小説家。本文中にもある「第2回電撃hp短編小説賞」に応募した『撲殺天使ドクロちゃん』が雑誌掲載を経てデビュー作となる。
──この頃、編集者としては「いいな」と思った作家さんは受賞するかどうかに関係なく、声をかけることはできたのですか?
三木氏:
そうですね。ボクが知る大きな分岐点となった事例が『キノの旅』【※】なんですね。『キノ』は受賞していないのですが、当時の担当編集が「この作品は面白いから、『電撃hp』に全部掲載しよう」ということで掲載して、のちに文庫として発売したら、すごく売れたんです。

(画像はキノの旅 the Beautiful World (電撃文庫) Kindle版|Amazon より)
──応募されていた下倉さんの側からは、そういう動きは見えておられましたか?
下倉氏:
そうですね。電撃文庫は大賞とかの受賞作以外からも、ちゃんと拾って来るという印象はすごくありました。ちょっと後の話ですけれど、『とある魔術の禁書目録』はすごくインパクトがあったかと。
三木氏:
当時は、いい時代でした……(笑)。というのも、各タイトルを読者が追っかけることができましたよね。いまなんて、あまりに新レーベルや新作が発売されすぎて、ラノベを追いかけきれないですよ。
下倉さんが仰るように「この作品は未受賞だけれど、発売されるんだ」とか、読者が調べる時間も十分にあったんですよね。でも、いまなんて全然ない(汗)。当時はよかったな……。
──まだ、あまりライトノベルレーベルの数も少ない頃でした。
三木氏:
少なかったですね。ボクが電撃文庫に入ったときは「MF文庫J」さん【※】がなかった。ファミ通文庫さん【※】もまだなかったんじゃないかな。入社時の2000年の頃は、角川スニーカー文庫さん、富士見ファンタジア文庫さん、電撃文庫と、数えられるくらいでした。
※MF文庫J
KADOKAWAから刊行されているライトノベルのレーベル。元々はリクルートのグループ会社であり、後にKADOKAWAが吸収合併することとなったメディアファクトリーが2002年に創刊した。
※ファミ通文庫
KADOKAWAから刊行されているライトノベルのレーベル。アスキーが1998年に創刊した。アスキーからエンターブレインに事業譲渡され、さらに後年にKADOKAWAがエンターブレインを吸収合併したため、MF文庫Jや電撃文庫などとは同一会社、別レーベルという形になっている。







































