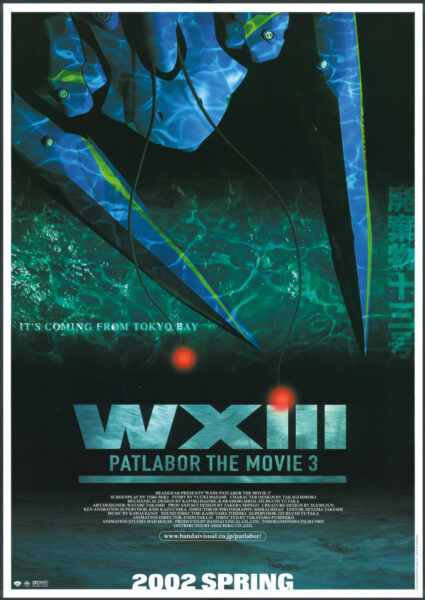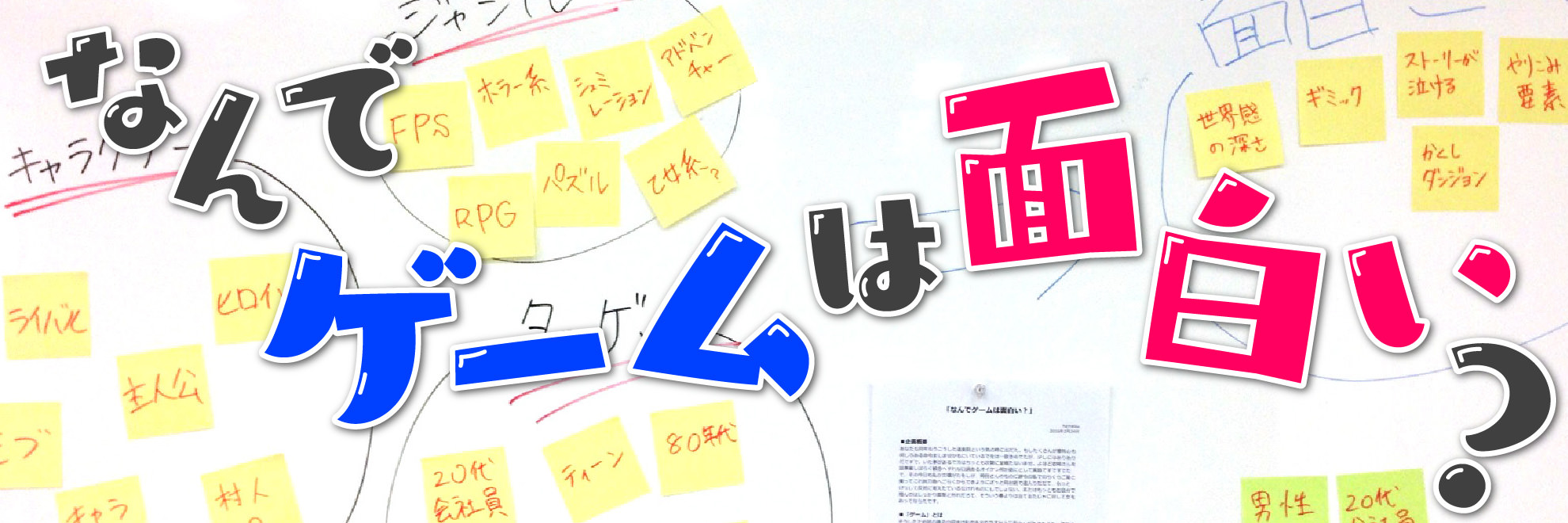 |
現代において最も世界的に大衆的支持を集めたクリーチャー、それがゾンビだ。
去る2017年7月に、そんなゾンビの今日に至るまでの標準形を作り上げた、「ゾンビの父」とも呼べる偉大な映画監督、ジョージ・A・ロメロ【※】が亡くなった。

(Photo by Getty Images)
彼がいなければ、言わずと知れた世界的大ヒットゲーム『BIOHAZARD』【※1】は生まれなかっただろうし、『Left 4 Dead』【※2】や『Dead Island』【※3】といった洋ゲーゾンビ作品群も存在しなかっただろう。
※1 BIOHAZARD
カプコンより発売されているホラーアクションアドベンチャーゲーム。初作は1996年に発売。ユーザーの口コミによって徐々に人気を獲得した。後にさまざまなプラットフォームに移植された。現在では世界的大人気タイトルのひとつに数えられている。
※2 Left 4 Dead
2008年に、『Counter-Strike』や『Half-Life』などを手がけたことでも有名なValve Corporationから発売されたFPSゲーム。襲い来るゾンビの群れに立ち向かう4人の「生存者」の戦いが、映画のように描かれている。
※3 Dead Island
2011年にリリースされたオープンワールド型ホラーアクションゲーム。Windows版、PS3版、Xbox 360版が発売された。キャラクター視点の戦闘が重点に置かれ、経験値でスキルや武器能力を向上させるなどのRPG要素も強い。
そして初代『BIOHAZARD』が存在しないということは、続編タイトルに当たる『biohazard 4』【※1】も生まれなかったということであり、「ビハインドビュー」という現代TPS【※2】の雛形となるシステムも誕生しなかったということだ。それはつまり、シューター系ゲームの歴史が全く別のものになることを意味している。

※1 biohazard 4
2005年に発売された「バイオハザードシリーズ」の6作目。ニンテンドーゲームキューブで発売されたのち、多数のハードにも移植された。本作は従来のシリーズとは異なり、TPSの要素がより強くなるなど「フルモデルチェンジ」として売り出され、高い評価を得た。
※2 TPS
Third Person Shooterの略。プレイヤーもしくは主人公を追うような、第三者視点で操作をするアクションシューティングゲーム。
ゲームの歴史に最も大きな影響を与えた映画監督、それはジョージ・A・ロメロなのではないだろうか。
今回は、そんな彼が世に送り出した不世出のクリーチャー、ゾンビはなぜ偉大な存在なのか。なぜゲームシーンに大きな影響を与えたのかについて考えてみよう。
ゾンビは「3つの時間軸」を表現できる
ゾンビとはなにか――それは一言で言うと、「現在」にいながらにして「過去」と「未来」に手を伸ばせる存在である。
ゾンビは大体、服を着ている。それは大体のゾンビはかつて人間だったからだ。ゾンビには「かつて生きていた」という「過去」が存在する。すでに人がいなくなった廃屋にゾンビがいれば、そこから「かつてここに住んでいた住人だった」という「過去」を類推することは容易い。
ゾンビがただただそこにいるだけで、その人、その場所の「過去」が見えてくる。
かつて『BIOHAZARD』を遊んでいたときに、ゲームが後半に差し掛かり、全く服を着ていない無限に湧くゾンビに遭遇した際に、怖さを超えてなんとも言えない「味気なさ」を感じてしまったことがある。

(画像はAmazonより)
なんでだろうと思いつつも、当時は特に気にもとめていなかったのだが、今ならそれがゾンビが当然持っているはずの「過去」が存在していなかったからなのだとわかる。
後にリリースされたリメイク版の『biohazard』【※】には「リサ・トレヴァー」という、もはやゾンビとすら言えないようなクリーチャーが登場するが、それに遭遇するたびになんとも言えない戦慄を覚えていたのは、その全身から発する「過去」におののいていたからなのだ。
※biohazard
2002年に発売された初代『バイオハザード』のリメイク版。対応ハードはニンテンドーゲームキューブで、のちにWii移植版(2008年)も発売された。初代に比してグラフィックなどが大きく向上したほか、ストーリーや武器にもさまざまな変更点が加えられた。
また、ゾンビには人を噛むことによって、その人間をゾンビにできるという強力な「感染力」がある。
噛まれることによって、人がゾンビになる。それはその人の「未来」が確定したということだ。ゾンビになる以外の選択肢は、その前に自分の頭を撃ち抜いて死ぬ、くらいしか存在しない。時間は妙にあるのに、選択肢はほぼ無いというあたりが、またなんとも言えないゾンビ映画独特のキャラクターの死、もしくは変質の描写になっている。

ゾンビとは、「噛みつく」というシンプルなアクションによって周囲の人間の「未来」を確定させる存在である。
そしてなにより、ゾンビは基本的に人間を見つければ襲いかかってくるので、ゾンビがいる「現在」には、それに対応するかたちでのアクションが生まれる。つまりゾンビとは、ただそこにいるだけで「現在」「過去」「未来」という3つの時間軸を、そこで生まれる描写やアクションによって表現できる存在なのである。
“世界”を変容させるゾンビの「感染力」
次に、ゾンビの持つ重要な機能、「感染力」について再度考えてみよう。
単体ではさほど戦闘能力が高くなく、対応することがそれほど困難なわけではないゾンビがそれでも厄介な存在であり続けるのは、その持ち前の「感染力」によって爆発的に個体数が増えるからだ。
そこにゾンビがいるということは、その周辺一帯にもゾンビがいることを示唆する。ゾンビが存在する世界において、人の気配のしない空き家ほど緊張感に満ちた空間はない。そこには常にゾンビがいるのではないかという「可能性」が生まれるからだ。

(画像はIMDbより)
ゾンビが世界に存在するということは、その「感染力」を背景に、あらゆる空間にゾンビが存在する「可能性」が生まれるということである。ゾンビとはその「感染力」によってあらゆる空間に対して影響力を持つ。
街中にゾンビが溢れているということはその街の壊滅を示唆する。そして途絶える交通、絶える各種インフラは、より大規模なレベルでの危機を暗示する。人を襲い、その数を増やし、大量のゾンビが街中を闊歩するという「状況」を映すだけで、その背後にある「世界」が破滅に向かっていることを示せる存在、それがゾンビだ。
「現在」「過去」「未来」を映す存在であると同時に、存在するだけで、なんならそこにいなくても「空間」の持つ意味を変えてしまう。ゾンビとは、目の前の「空間」以上のより広い「世界」が変容したことを想起せざるを得ない、我々の想像力に侵食してくるタイプのクリーチャーなのである。
実は相性が良い「ゲームとゾンビ」
「時間」と「空間」を表現するメディアである映画と、「時間」と「空間」を股にかけることができるゾンビは相性がいい。だが、ゲームとゾンビもまた非常に相性がいい。
なぜなら、ゲームとはプレイヤーキャラクターや敵キャラクターの「機能」の発揮によって駆動するメディアだからだ。そしてゾンビは、「感情」や「意思」のクリーチャーではなく「機能」のクリーチャーなのだ。
今更な説明ではあるが、作品によって様々なバリエーションや差異があるとはいえ、ゾンビには基本的に感情はない。ただただ本能的にその「機能」――人を見つけたら食べる、食べられた人もまたゾンビになる――などの発揮に努めている存在だ。このシンプルな原理に基づく行動は、ゲームのルールをシンプルなものにしてくれる。

そしてゾンビには、「現代」に自然な形で登場させやすいという非常に大きなメリットもある。
実は現代を舞台にしながら、「ひたすら単純明快に、プレイヤーに襲いかかってくる敵がいる状況」をつくるのはなかなか難しい。プレイヤーが銃で武装などしている場合はなおさらである。なぜなら、ある程度の知能がある存在であれば銃を恐れて警戒するからだ。その点ゾンビは、銃を構える相手を前にしても臆さずこちらに向かって直進してくれる。
ゾンビは、複雑な現代の現実世界を極めてシンプルなルールに塗り替えてくれる。だからゲームとゾンビは相性が抜群に良いのである。
ホラー映画から考えるゲームキャラクターの本質。傑作ホラー『ドント・ブリーズ』は何故“ゲーム的”映画なのか?:「なんでゲームは面白い?」第六回
※本連載のホラー映画を扱った回では、ゲームキャラクターを「特定の機能を有した機能体」だと位置づけ、ホラーに登場するクリーチャーとの類似点を指摘している。
「走り出した」ゾンビの隘路
映画とゾンビは相性が良かった。ゲームとゾンビもまた相性が良かった。それは先程述べた通り、ゾンビはこっちが攻撃する気満々で銃を構えても臆さずこちらに向かって来てくれるからだ。
だが、それは同時に、ゲームとしては次第に物足りない存在になるということでもある。初代『BIOHAZARD』においても、ゾンビが活躍するのはやはり序盤においてである。そしてその序盤においてすら、最も脅威となる存在は高速移動が可能な犬ゾンビだったりするのだ。
すでに述べたように、ゾンビが魅力的なのは、それがやはり過去に人間であり、その過去を引きずった状態で目の前に現れるからではないかと思う。
『BIOHAZARD』において中盤以降から登場する「ハンター」は、それはそれで怖く驚異的だが、ゾンビに比べるとどこか「味気なさ」が感じられることは正直に述べざるを得ない。

(画像はAmazonより)
『28日後…』【※1】や『ドーン・オブ・ザ・デッド』【※2】という作品以降になるだろうか、全力疾走で走るゾンビが一般化し始めた。それはつまり、ゾンビがその「機能」を発達させ始めたのである。
※1 28日後…
2002年公開のSFホラー映画。人々の凶暴性を引き出すウィルスが蔓延し、壊滅した28日後のロンドンが舞台。
※2 ドーン・オブ・ザ・デッド
2004年公開のホラー映画。ロメロ監督の『ゾンビ』(1978年)のリメイク作品にあたる(双方とも原題は“Dawn of the Dead”)。ゾンビ映画のB級イメージを払拭し、各キャラクターの人物像にも焦点が当てられ、さらに「走るゾンビ」という設定が加えられたことで、話題となった。
なぜゾンビが走り始めたのか、なぜそのようなゾンビが大衆に受け入れられたのかについては諸説あるだろうが、ゾンビを題材としながら「より強い刺激が欲しい、より展開をスピーディなものにしたい」という単純明快な観客の要望に基づくものであることは間違いないだろう。そしてこの流れは当然のようにゲームにも波及する。
走るゾンビを題材としたゲームの代表といえば『Left 4 Dead』があげられるだろう。このゲームにおけるゾンビの動きの軽快さには、かつての牧歌的な面影はない。油断すれば一瞬で間合いを詰められ、襲いかかられてしまう。さらにこのゲームでは、一度に尋常でない数のゾンビが登場するため、どれほど重装備で待ちかまえようとも全く安心できない。
リメイク版の『biohazard』にも走るゾンビが登場する。それも、すでに倒したはずのゾンビを放っておくとそれが「クリムゾンヘッド」としてより強くなって復活するというかたちでだ。この「クリムゾンヘッド」は本当に怖い。倒したゾンビがずっと廊下にいる状況がそもそも禍々しく不気味だが、そこから突如立ち上がって襲いかかってくる恐怖は、やってない人には是非一度体験してもらいたい。ゲームにおけるゾンビ表現に「時間」を導入したという点においても画期的な存在である。
なぜ初代バイオハザードは怖くて、バイオ4は怖くないのか?:「なんでゲームは面白い?」ホラー特別回
※本連載の「バイオハザード」シリーズを扱った回では、空間への恐怖を煽る好例として、このクリムゾンヘッドを取りあげている。
ゲームの中のゾンビは、走り出すことによって単なる序盤のザコ敵に留まらず、ユーザーに脅威を与え続ける存在になった。『Left 4 Dead』も『biohazad』もどちらも名作である。個人的には走るゾンビ映画にも走るゾンビゲームにも好きな作品は多い。

(画像はAmazonより)
ゾンビを題材とした作品がここまで幅広い支持を受け、様々な作品が作られる以上、ゾンビが高機能化、高性能化するという流れ、ゾンビ機能のインフレ化は止められない必然的な流れだったと言えるだろう。ゾンビは高速化することで、現代のエンターテイメント作品としてその存在をアップデートさせたとも言える。
だがそれは、すでに述べたような、ゾンビがただそこにいるだけで表現できる「過去」や「未来」を味わいにくくしてしまうこともまた事実なのだ。なぜなら、全速力で群をなして襲いかかってくるゾンビはただただそれだけで充分すぎるほどに驚異だからだ。
そこには、単体のゾンビであればちょっと突き飛ばす程度でも危機回避できてしまっていた頃のどこか呑気な風情や、余裕をこいて油断していたらいつのまにか取り囲まれて詰んでしまったような不条理な絶望感は存在しない【※】。

(画像はスプラトゥーン2 新要素「サーモンラン」発見報告映像より)
ゾンビは単体では確かに弱い、低機能なモンスターだ。しかし、単純にその機能を高性能化することによって、本来持っていたはずの「時間」「空間」に影響を与える機能性が弱まってしまっては、本末転倒というものではないだろうか?
高性能なゾンビを活かす『新感染』のレベルデザイン
その点について現在、公開中の映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』【※】は一つの回答を示している。
ここに登場してくるのは全速力で疾走し、群体として襲いかかってくるという今日的な「走る」タイプのゾンビだ。この映画が面白いのは、高速で移動する列車内に舞台を限定することで、高性能化したゾンビの機能をある部分では抑制し、ある部分ではより助長することに成功しているところだ。
※新感染 ファイナル・エクスプレス
2016年制作の韓国ゾンビ映画(日本では2017年9月1日より劇場公開中)。ソウル発・釜山行きの高速列車に娘とともに乗りこんだ主人公が、車内で伝播するウイルス感染により次々とゾンビと化していく乗客たちから逃げ回るサバイバル・パニックアクション。カンヌ映画祭で上映されたほか、多数の映画祭で賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を得ている。
列車の中だから外界に対しては文字どおり距離を置くこともできる一方で、列車内でゾンビが発生すればそれは脱出不可能な地獄が生まれることにもなる。そして何両も連結されているため、安全な場所と危険な場所の区分けが明確にできる。
非常にレベルデザインの行き届いた空間機能が、ここで何かが起きたであろう「過去」を、これから起こるであろう「未来」を、そして崩壊していく「世界」を観客の目の前に映し出し、よりゾンビの本質を浮かび上がらせることに成功している。
これは、ゾンビの「本質」を絶妙にとらえて、高性能化するゾンビへの要求に応えた表現であると思う。
逆に言えば、海外ドラマ「ウォーキング・デッド」シリーズ【※】においてゾンビが走らない理由は、ゾンビの本来的な機能の発揮に主眼が置かれているからだろうし、このドラマシリーズが面白い理由も、やはりゾンビの本質的な機能を連続ドラマならではのたっぷり長い時間をかけて、じっくりと見せてくれるからだろう。

(画像はFOX公式サイトより)
そう――どれほどゾンビが高機能化しようとその本質はおそらく変わらない。そして今後もその本質を継承した作品が支持され、愛されていくのではないかと思う。それは映画においてもゲームにおいても同様である。
ゾンビを知りたければ『ゾンビ』を見ればいい
ゾンビはそこにいながらにして「過去」「現在」「未来」を映す。ゾンビを通すことで目の前の「状況」を超えた「世界」が見えてくる――。
我ながら大げさなもの言いをしているなと思う。明確な意思や感情を持たずに、人間を見ればとりあえず襲いかかってくる極めて単純なモンスターを題材に、本当にそんな表現が可能なのだろうか。
そう思うのであれば、ジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』【※】を観ればいい。
そこにはただただ目の前の状況に翻弄され続ける人間の「現在」が、確かにかつて人間だったという全てのゾンビが等しく持っている「過去」が、ゾンビに噛まれてしまったことで次第にゾンビになっていく人間の「未来」が、そして決してスケールの大きな大作ではないにも関わらずゾンビに支配されてしまった奥行きを持った「世界」と、遠からず滅びの道を歩んでいくであろう「世界の行く末」が映し出されている。

(画像はAmazonより)
こうやって『ゾンビ』という映画を解説していると、単なるゾンビ映画ではないとかジャンルの枠組みを超えたとか――みたいな言葉で形容したくなってくるが、この映画はどこまでもゾンビ映画だし、B級ホラー、B級アクションと呼んでしまっても差し支えのないようなチープさも同時に備えている。現代のCG満載の映画になれた視点で観たら、その印象はより強まるだろう。
だからこそ『ゾンビ』という映画は素晴らしく、なんとも言えない愛嬌を持った映画になったのだとも思う。深読みしても面白いし、ポップコーン片手に気楽に見ても面白い。
そんな、映画のみならずゲームにも多大な影響をもたらした偉大なる機能体「ゾンビ」を生み出した「ゾンビの父」ジョージ・A・ロメロに敬意と哀悼の意を表してこの文章を終わりたい。

文/hamatsu
【あわせて読みたい】
なぜ初代バイオハザードは怖くて、バイオ4は怖くないのか?:「なんでゲームは面白い?」ホラー特別回
本連載「なんでゲームは面白い?」の特別回では、hamatsu氏によるバイオハザード論を掲載中です。「音響表現」、「カット割り」などの切り口から、初代『バイオハザード』に深く切り込んでいます。