『弱虫ペダル』のようにアキバ通い
──さて、ここからは宮路さんがその後プロデュースされた、『シルフィード』など数々のゲームについて訊ねていきたいんですが……ちょっとその前にお伺いしたいことがありまして。
というのも宮路さんって、麻雀仲間の遠藤雅伸さんをはじめ、エイゲ会の人脈もそうですし、何よりも21歳の若さで弟の宮路武さんらとゲーム アーツを立ち上げらています。ゲーム アーツといえば、パソコンゲームの黎明期を切り拓く一翼を担っていた「技術の会社」としての存在感がものスゴく、どういう経緯で会社を立ち上げられたのかが知りたくてですね……。
宮路氏:
ああ……それは僕らの出自が、秋葉原のパソコン少年だったからですね。
三宅氏:
それはゲーム業界にとって重要なオーラルヒストリーになりそうですね。
宮路氏:
いまからおよそ40年近く前のことですかね。当時僕は川越付近に住んでいた中学生。ちょうどその学校を卒業するかしないかというときに、インベーダーゲームが現れたんですよ。
もちろんインベーダーの前にもピンボールなども置かれていたゲームセンターはあったんですけど、インベーダーで初めてコンピューターゲームの面白さに触れ、当時すさまじい衝撃を受けました。
 |
とはいえ、当時の中学生に1プレイ100円は高かった。するとある日、友達のひとりが「秋葉原に行くとタダでゲームができる」という情報を仕入れてきたんですよ。
というのも、秋葉原のショップの店頭にはパソコンが置いてあって、そこでコンピューターが触り放題だったんですよね。当時はそういう店が、人が寄り付かない変な雑居ビルの片隅などにあったんです。
──いまのような“オタクの街”になるまえ、当時、世界有数の電気街として知られていた秋葉原の風景ですね。……それにしても、お金がないなかで秋葉原までの足代ってどうしていたんですか?
宮路氏:
自転車ですね。秋葉原までだいたい片道45キロぐらいを漕いでいました。

──よ……45キロ!?
三宅氏:
完全に『弱虫ペダル』と同じじゃないですか。【※】
※『週刊少年チャンピオン』に連載中の『弱虫ペダル』の主人公にして、二次元オタクの小野田坂道は、千葉県佐倉市より片道45キロ離れた秋葉原まで自転車で通っていたというエピソードを持つ。
宮路氏:
当時、ブラウン管にテレビ番組以外のものが映っていることが本当に衝撃だったんですよね。ましてやそこでゲームが動いているわけで。
そうしたパソコンショップには、プログラミング言語の本も置いてあって。「面白そうだ」と見よう見まねでいじっていたらコードを覚えてしまって。
三宅氏:
そのお店って、パソコンを売るためのお店だったんですよね(笑)?
宮路氏:
まあ当時、僕らみたいな“パソコン少年”って秋葉原にたくさん出入りしていたんですよ。だいたいメンツが決まっているので、そのうちに仲良くなってみんなでゲームを作り始めたんですね。
 |
正確に言うと、当時の僕らはゲームは二の次で、ただただパソコンがいじりたかっただけなんですよ。でもプログラムって何か目的がないと作れないので、ゲーム作りってちょうどよかったんですね。
──確かに、往年のゲームクリエイターのインタビューなどを読むと、当時のゲームって、まだ“パソコンという夢の箱”の一部と捉えられていた節がありますよね。
宮路氏:
そんなことをしているうちに、ある日お店の人から「お前らゲームを作ってくれよ」とお願いされたんです。
当時著作権などが曖昧な時期だったので、ゲームセンターで新作が出るたびに「あの『ラリーX』みたいなのできない?」などと声をかけてきて。作ってみるとデキはよくないんですけど、売れていた。やっぱりニーズがあったんですよね。
だから僕の高校3年間は、ひたすらゲームを作って、メディアがカセットテープの時代ですからダビングをして、ラベルを貼って、納品して、納品書と請求書を書く日々でしたよ。
──高校生でプログラムから卸しまで。もう完全に自営業者ですね……。
宮路氏:
しかも、新機種のパソコンが出るたびに「アプリケーションを移植してほしい」と言われ、それらのハードを全部貸してくれていたんですよ。
ですから貧乏だった我が家に、当時のほとんどの新作パソコンが揃っていました。親子三人の六畳一間に、当時100万円を超えるパソコンが5〜6台置いてありましたね(笑)。
──マンガのような話です(笑)。それが1970年代の終わりでしょうか。
宮路氏:
ええ、それまでパソコンと言えば“御三家”と呼ばれるApple II(アップル・1977年)、PET 2001(コモドール・1977年)、TRS-80(タンディ・コーポレーション・1977年)でしたが、当時やっと秋葉原でシャープのMZ-80K(1978年)、NECのPC-8001(1979年)などの日本製パソコンが出始めてきたころでしたね。
シャープ MZ-80K(左)とNEC PC-8001(右)
(画像はMZ-80 – Wikipedia、NEC | パーソナルコンピュータ | KCGコンピュータミュージアム(分散コンピュータ博物館)より)
三宅氏:
ちなみに当時のパソコンって、いまのような巨大なOSが入ってない、裸の状態ですよね。
宮路氏:
そうそう。「OSなんて自分たちで作る」という発想だったので、当時はみんなマシン語を使うのが普通でしたね。
だからハードとソフトの両方の勉強ができて、それがその後の仕事に繋がっていると思います。まあ勉強というか、本当に遊びまくっていたら、いつのまにか身に着いたという感じですが……(笑)。
──マシン語ベタ打ちなんて、いまそんな芸当を見せてくださる人はほとんどいませんよね……。
高校生でゲーム本を出版。浪人兼プロデューサー生活へ
──そこから、どのようにしてアスキーに繋がっていくのでしょう?
宮路氏:
そんなふうにたくさんゲームを作っていたら、高校3年生のときに「そのゲームを本にしたい」という話を出版社さんからいただいたんですよ。というのも当時、ゲームのプログラムが書かれた“プログラムブック”というものが売れていて。
それらの本の執筆を始めたら、3年生の2学期から学校に行けなくなっちゃったんです。先生に「来い」と言われるんですが、「いや、締め切りがあるから」みたいな(笑)。
──かっこいい(笑)。
宮路氏:
まあ、全部成り行き任せだっただけですけどね。そうこうしているうちに受験シーズンになり、ある日、学校が集めていた願書を取りに行ったら、「お前のぶんなんてあるわけないだろ」と言われて。幸い卒業はできたんですけど、受験にチャレンジすることもなく浪人しました(笑)。
 |
それでしかたがないからパソコン販売店でバイトをしていたら、たまたまそこの店長がアスキーの取締役になることが決まったんです。
当時、アスキーって憧れの雑誌を出すめちゃめちゃかっこいい会社だったので「行く行く!」とついて行ったら、当時26歳だった塚本慶一郎さん【※】が現れ、いつのまにか翌日からバイトをすることになっていました(笑)。
※塚本慶一郎
1957年生まれの編集者・実業家。西和彦氏、郡司明朗氏とともにアスキーを創業し、出版部門を統括。副社長まで務め、1991年に退社後、翌92年に郡司氏とインプレスを設立。現在はインプレスホールディングスの最高相談役を務める。
──塚本さんですか。それは話が早いですね(笑)。アスキーではどんな仕事をされていたんですか?
宮路氏:
『テープアスキー』というゲーム付きブックのようなプロダクトを手がけてました。いまでは考えれられませんが、ソフトバンクさんが大きく扱うまで、当時は(PC)ゲームの流通そのものが細かったんです。
そんななか、「出版としてゲームを出す」ということを、おそらくアスキーが日本で初めてやったんじゃないかなと思います。しかもそこの部署は僕ひとりしかいなかったので、秋葉原の仲間連中を集めていろいろなプロデュース仕事を始めたんです。
──仕事ぶりが凄まじいですが、当時って単に浪人中のバイトの身分ですよね(笑)。受験勉強の進みはどうだったのでしょう?
宮路氏:
もうすっかり仕事のほうが楽しくなっていましたよね。
夏ごろに「ヤバい。願書を出さなきゃ」と思い、当時のアスキーに近い場所で調べたら青山学院があったのですが、すでに締め切られていて(笑)。結局、國學院の法律学科に進みました。ところが……。
──ところが仕事と麻雀に明け暮れて、大学は中退されてしまうわけですね(笑)。
六法全書を読解して定款を作った
──そこから会社を作られたと。
宮路氏:
ええ。そんなふうに3年ほどが経ったころ、「組織が大きくなってきたので、会社としてちゃんとピラミッド構造を作りたい」という話が出たんですね。すると僕らはバイトなのに、新入社員の人たちよりも仕事ができちゃうわけですよ(笑)。
 |
ですから「これを期にアスキーに入りたいです」と仲間のひとりが言ったら、「お前らは扱いづらいし、会社を作りなよ」と言われてしまって。当時はもう「えええー!?」という感じですよ(笑)。
──扱いづらい(笑)。ひどい話ですね……。
宮路氏:
というわけで、就職先を自分たちで作らないといけなくなったんですよ(笑)。おりしも、たまたま僕は法学部だったので、六法全書を読み込んで、ワープロ専用マシンを使って手製の定款を作ったんです。
でもこれは後から知ったのですが、当時すでに法務局に出すためのフォーマットが文具店で売られていて。ですから当時、わざわざ六法全書を読解して定款を作ったのって、たぶん僕ぐらいですよ。20回くらい法務局にダメ出しを喰らいましたから(笑)。
三宅氏:
法務局も教えてくれたらいいのに(笑)。
 |
宮路氏:
それで21歳のときに仲間7人と作ったのが、ゲームアーツという会社でした。最初はバイトで稼いで、六畳のアパートを借りて開発室にしたりして。あまりに狭くて、トイレの蓋で仕様書を書いてるやつとかいましたね(笑)。
そこで作ったパソコン向けのゲーム『テグザー』(1985年)が、最初に驚くほど売れたんです。当時、パソコン向けゲームというものがほとんどなく、ちょうど同じ時期にスクウェアとエニックスが出て来始めて、そうした市場ができつつあった時代でした。
ゼロからアニメ制作した『ゆみみみっくす』
──なるほど。マシン語ベタ打ちでゲームを作っていた天才少年時代に始まり、最先端の技術通が集った当時のアスキーを経て……と、その出自を踏まえると、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』も含め、ゲームアーツのその後の作品の系譜にも納得感がある気がします。
たとえば、1993年の『ゆみみみっくす』のアニメーション映像技術って、当時としてはかなり革新的だったと思うんですよね。
(画像はゆみみみっくす|製品情報 | ゲームアーツより)
宮路氏:
当時はCD-ROMが登場した時代でしたね。CDって、創業以来、容量と闘ってきた僕らにとって夢のような大容量だったわけですよ。
それで“映像型のゲーム”ができないかと考えたのが始まりでした。普通にアドベンチャーゲームはありましたが、そういう映像型のゲームって、当時はまだ誰も作っていなかったんです。
そこで、まずうちの社員の薦めで、竹本泉先生にオリジナルのストーリーのペラを3枚ぐらい作ってもらったら、これが面白くて。もう直感で、「これで行こう」とGOを出したんです。
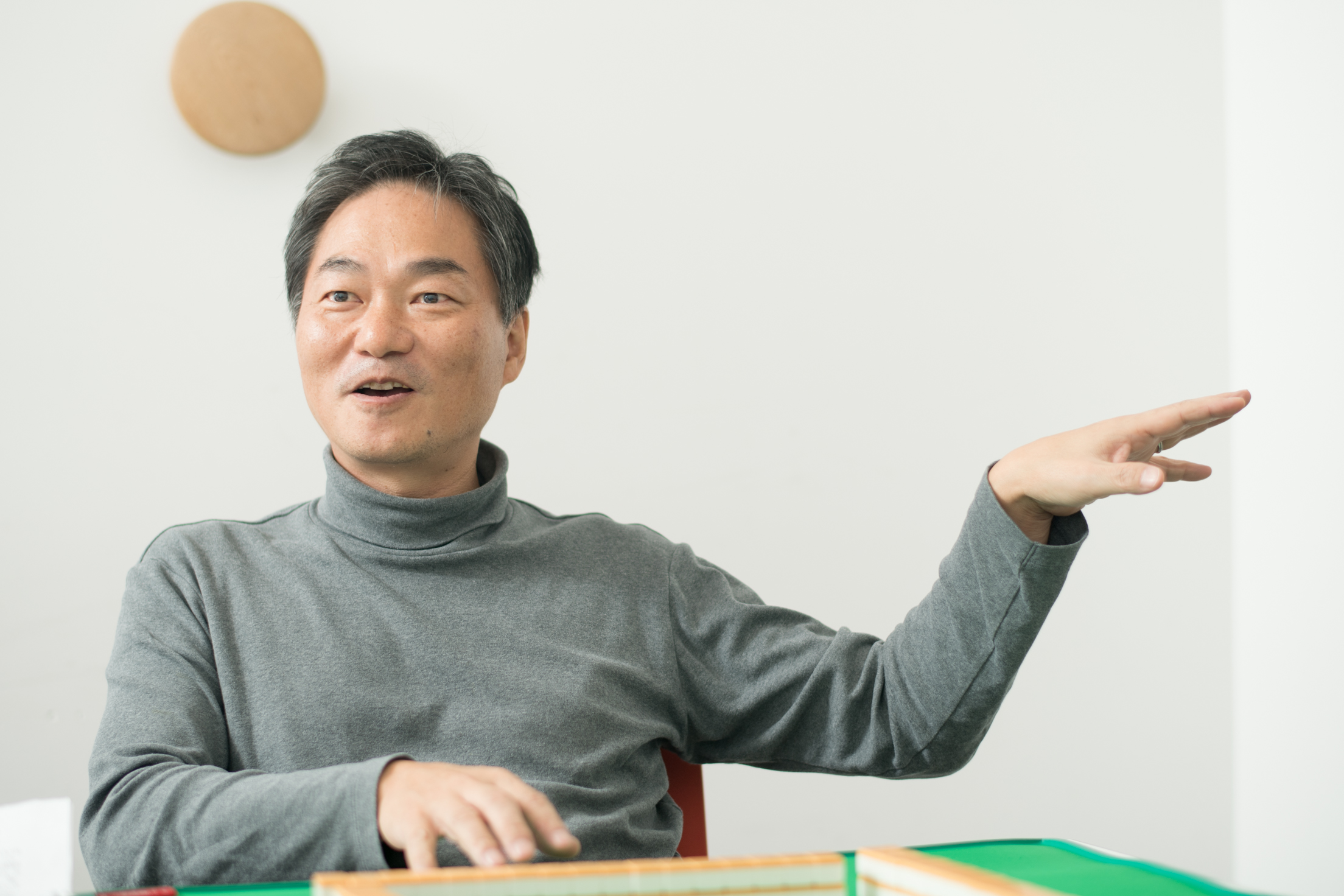 |
ただ、最初は簡単にできそうだと思っていたんですが、そこからが大変で。当時MPEGの規格もなかったので、高速でペイントして描くアニメ型のものを作るしかない。
でも、アニメなんて作ったことがないから、原画マンも必要、動画マンも必要ということになり、結局何室もマンションの部屋を借りてアニメスタジオを作るはめになって……。
──簡単だと思ってたら、ゼロから真面目に作ることに……既視感がありますね(笑)。
宮路氏:
(笑)。いまだったらそんなバカなことはせず、「アニメ会社に頼めばいいじゃん」と言うんだけどね……そういう間違ったことをいっぱいやっていますよ。
最先端のポリゴン表現に混ぜた“ウソ”
──興味深いのが、1986年発売の『シルフィード』では、当時最先端だった3Dのポリゴン技術をウリにしていることです。
とりわけ、『ゆみみみっくす』と同じ1993年に発売されたメガCD版でも、ポリゴン技術をウリにしており、同じ時期に、アニメーションと3Dポリゴンの両方に取り組んでいたというのが面白いなと。
(画像はシルフィード|製品情報 | ゲームアーツより)
宮路氏:
あれは当時うちの弟(宮路武氏)【※】がポリゴンにこだわって作ったものなんですよ。ただ、当時はポリゴンをゲームに用いるのはスゴく大変なことで、たとえばポリゴンの四角が10個も表示されれば、もう処理スピードの限界が来ちゃうんです。
※宮路武
1965年生まれのゲームクリエイター。15歳でアスキーに参加。19歳で兄・洋一氏らとともにゲームアーツを旗揚げ。『シルフィード』をはじめ、『ガングリフォン』シリーズや『グランディア』シリーズなどをディレクターやプロデューサーとして手掛けた。2000年にはジー・モードを設立。2011年に45歳の若さで逝去している。
──当時のCPUだとそうですよね。
宮路氏:
だから、あれは3Dのくせに大半が二次元の絵になっているんですよ。自機などはちゃんとした3D描画ですが、じつは背景はムービーを同期させているだけ。
 |
他社のプログラマーからは「インチキだ!」なんて言われましたけど、ユーザーさんはそんなの判らないので、「スゴい! 3Dだ!」と思ってくれましたね。いち早く「3Dでこんな映像ができるんだよ」という体験をしてもらいたかったんです。
──当時プレイして、「こんなことができるんだ!」と本当にビックリしました(笑)。
宮路氏:
そうした経験がひとつに繋がったのが『グランディア』(1997年)なんです。
あれはおそらく、世界で初めて背景が360度完全にポリゴン空間になっているRPG。ですがすべてポリゴンは厳しいので、今度はキャラクターを2Dアニメーションにしたんですよ。
(画像はグランディア|製品情報 | ゲームアーツより)
そうした三次元の背景に馴染むキャラクターを描くとなると、今度は原画マンクラスの超トップクリエイターが必要になり、もうあらゆるアニメーション会社に頭を下げて頼んで回りましたね。
しまいにはジブリにも行きました。まあ……断られましたけど(笑)。
──なんと、そんなところにまで。
宮路氏:
それらのゲームを作るなかで学んだのが、“アニメーションの表現とポリゴンの表現の違い”でした。
ポリゴンというものは、やっぱりある意味シミュレーターなので、ウソをつけないんですよ。逆にアニメはウソの塊。
たとえば『カリオストロの城』の冒頭のカーチェイスの、ルパンたちのクルマが崖を登っていく表現などがそうですよね。あのシーンって、ウソなんだけど、あれで前のクルマを追い抜くからこそ面白いわけです。
三宅氏:
物理シミュレーションをしたら、絶対に登れませんからね(笑)。
ゲームでも、たとえばプレイヤーがピンチのときに仲間のキャラクターは、仮に気付かない距離にいても気付いたふりをして助けに来ないとダメですよね。
 |
シミュレーター的に考えたら、遠くにいるんだから判るわけがない。でも、ユーザエクスペリエンスとしては、そのほうがリッチな体験になるわけですから。
汎用的な会話なんて面白くない
──少し蛇足になると思いますが、これまでの話を踏まえたうえで不思議なのが、『機動戦士ガンダム ギレンの野望』のエグゼクティブプロデューサーをされていますが、これはどういう経緯だったのでしょう?
宮路氏:
あれは本当にプロデューサー業をしていただけでした。いまはスクウェア・エニックスにいる浪川真治くんが作ったんですよ。彼が本当に優秀で、ほとんどゼロからデザインしたものです。
 |
僕はテストプレイをして、「極めてよくできているな」と思った。もう本当に何も言うことがありませんでした。僕の手柄はほとんどない。もう浪川くんの努力です。
──『ガンダム』でシミュレーションという企画をされたのは宮路さんですよね?
宮路氏:
もちろんそうです。お金を集めるのとコンセプトを決めた程度。だから手柄は3%ぐらい(笑)。
──『ガンダムネットワークオペレーション』も宮路さんですよね。
宮路氏:
そうです。バンダイの鵜ノ澤(伸)さんに言って。「『ガンダム』のオンラインゲームを作って、それで引退しよう」なんてことを思っていましたね(笑)。
まだ当時はインフラも弱く、そこにオンラインゲームなんて、サーバーのコストだけでも何億など、とてつもなくお金がかかるわけですよ。
だから僕が思ったのは通信量が多いものはダメということと、あと『ガンダム』のファンは20~30年来の人が多く、働き手としても結構中堅になっているということ。
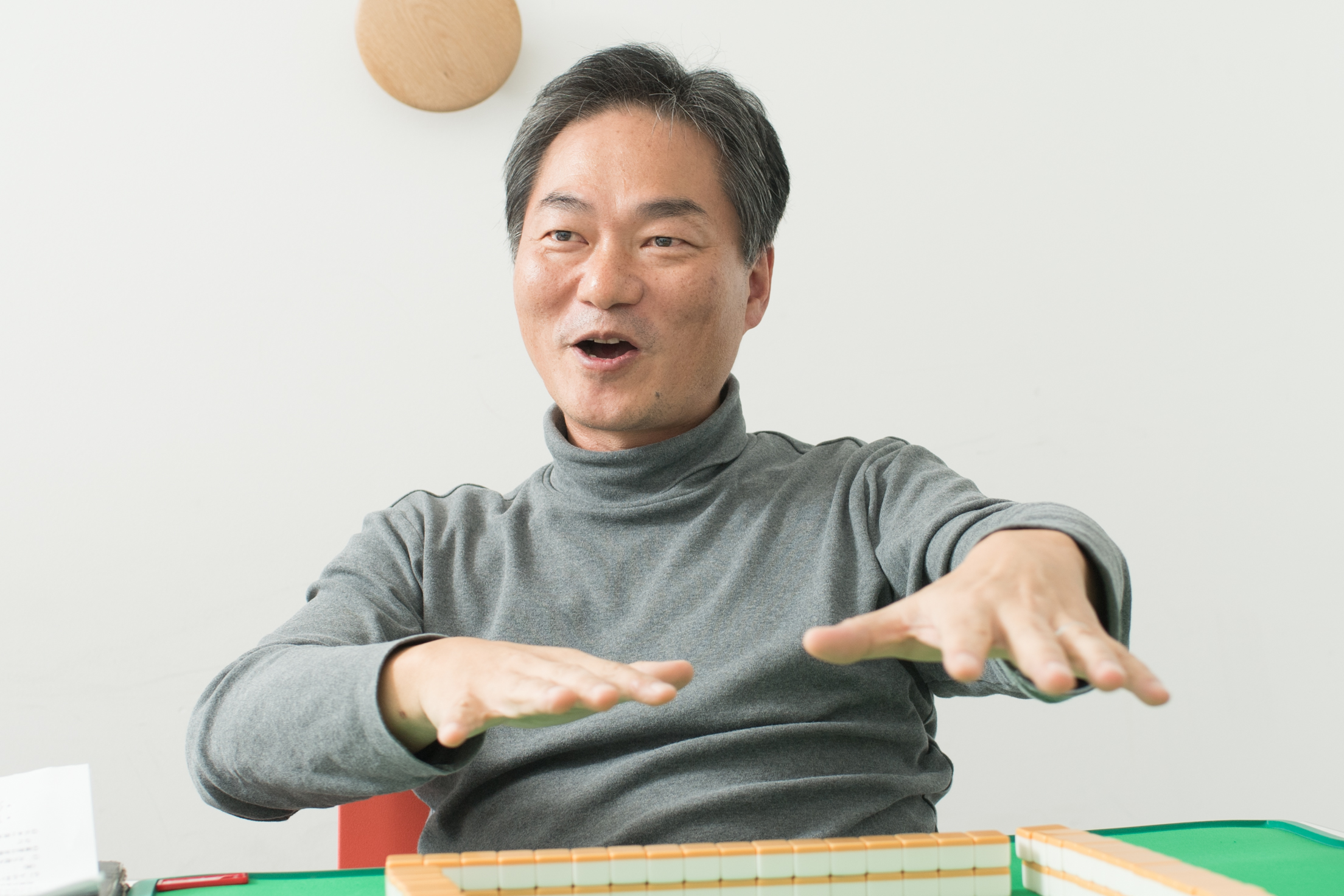 |
そこから僕が考えたのはひとつだけで、「朝にセッティングをしてぶん投げておいて、帰ってきたら結果が判るオンラインゲームを作ろう」ということだったんです。それならコストが少なくて済む。
それが『ガンダムネットワークオペレーション』なんですよ。これが非常に上手くいきました。当時のサーバーの環境を考えると、ゲームデザインとしては適切だったと思います。それにライフスタイルにも合っていたと思います。
──1日が楽しくなりますね。
宮路氏:
そうそう。いまのソーシャルゲームもそれが当たり前のロジックでしょう。いまから20年前のアイデアですから、まあそこは褒められるんじゃないかなと(笑)。
三宅氏:
やっぱり早いんですよね、そういうことを思いついて実行するタイミングが。
──(笑)。ここまでの話を伺っていると、ゲームアーツの歴史というのは、最先端の技術に寄せる理想に対して、ずっとCPUのパワーが足りない……という状況との格闘の歴史のように思えてきますね。
その過程で「ツモに偏りをもたせよう」、「3Dに見えるアニメを作ろう」というウソの要素を入れていったところに、今日の話の本質があると思います。
宮路氏:
まあ「ウソをつけ」と言っているわけじゃないのですが(笑)、「ユーザーにどういうエモーションを与えるか」を最優先で考えて作れば、いまのAIの技術の幅ももっと広がるはずなんですよね。
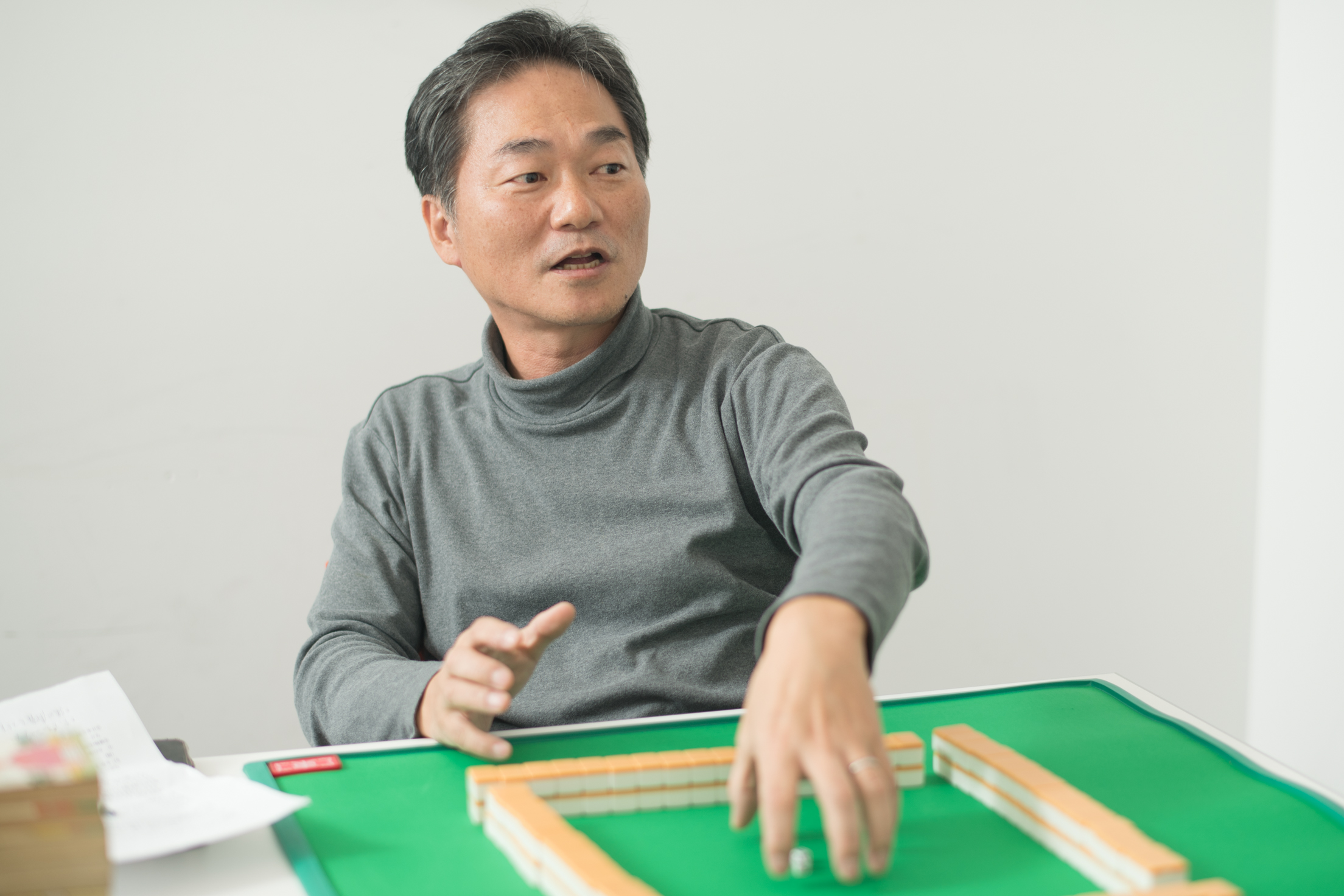 |
最近その問題をもっとも感じたのが“会話型AI”ですね。あれって、真面目にシミュレーションして汎用型の会話をさせるから、とんちんかんな答えしか返ってこないんですよね。
見ず知らずの趣味も合わない人といきなり会って、「こんにちは」と言ったっきり、重い空気が流れていくときのような感じがしますよね(笑)。
──確かにああいうAI相手には、何をしゃべっていいのかわからない感じはあります。
三宅氏:
会話って、「いつに誰とどこでどういう意図を持って話す」という言外のシチュエーションが重要なので、汎用的な会話から学習させようとしても、必ず破綻しますね。
宮路氏:
逆に、テーマを絞り込めば会話はできるんですよ。たとえば、話す相手が初音ミクだったら、好きでよく知ってる人なら話すことがある程度決まってきますよね。
会話がある程度絞り込めさえすれば、あとは総当たりで検索しちゃえば、かなり筋のいい返事ができるはずなんですよ。
──実際は総当たりで調べているだけでも、ユーザーにはそんなことは判らないというわけですね。
三宅氏:
1999年の『シーマン』で「なぜあんなに自然な会話ができるのか」という話を開発者の斎藤由多加さんから聞いたんですが、まさにエンターテイメント的な作りかたをしていました。

「どんな会話だとユーザーが面白がるか」から逆算して、分岐を含めた答えを大量に作っていったんです。科学者たちが必死に「いいAIを作れば、いい会話ができるはずだ」という発想で研究しているのに対し、アプローチが完全に逆なんですよね。
※参考サイト
シーマンは来たるべき会話型エージェントの福音となるか?:斎藤由多加インタビュー(人工知能学会 AI書庫)
宮路氏:
僕は汎用的にいろいろなものに使えるAIのようなものって、基本的にまだ使えないものだと思っています。むしろ特化型にしたほうがゲームには向いていますよね。
三宅氏:
実際、アルファ碁も囲碁のAIでしかないし、いまあるAIの9割ぐらいが特化型ですね。アクションゲームのような、何が起こるか判らないものには汎用型として作るんだけど、それも完全にはうまくいってません。
ただ、今後世界の至るところがデジタル空間になり、多くの人がAIと向き合うようになったとき、「それをユーザーはどう面白がりますか?」ということが必要になるわけです。そのとき蓄積があるのは、この30年間それを探求してきたゲームしかないわけですよ。
じつはゲームで積み重なっている知見は、これからゲームの枠を超えて広がっていく可能性があると思いますね。
AIとゲームデザインが絡み合うために
──ここで三宅さんに改めて伺いたいのは、今後のゲームAIの開発に、今日の宮路さんのお話ってどのように生かされ得るかということです。
三宅氏:
最近、AIを勉強してからゲーム開発に入ってくる人が多いのですが、そこで自分が学んだ技術を使おうとしちゃうことが多いんですよね。
本当は、技術とゲームデザインのバランスが大事なのですが、いまその両方について深く解っている人は本当にいないんです。
 |
だから今日のお話を聞いて、「『ぎゅわんぶらあ自己中心派』がうまくいった秘訣は、宮路さんがその両方をできる人だったからだ」と思いました。初めて作ったとは思えない完成度のAIと、ユーザー体験を重視した作りかた。
その両方が、麻雀という土台の上でちゃんと繋がっているんですね。
実際、宮路さんに限らず1990年代までのゲームAI開発者の話を聞いていくと、ひとりの人間の頭の中でその両方のバランスが取れているパターンがじつに多いんですよ。
──逆に、いまはなぜそのバランスが崩れているのでしょう?
三宅氏:
やっぱり分業制になっちゃっているからですよね。するとコミュニケーションがうまくいかず、エンジニアとゲームデザイナーが喧嘩しちゃうことも多いんです。
 |
たとえば、僕が10年以上前にパス検索【※】をゲームに入れるのに「一週間ください」とお願いしたとき、「いま俺が一個一個、点のデータを打てば一瞬で終わるんだよ」と言われたことがありました。
とはいえパスって無限に存在するので、いまはパス検索が効率的で、導入するのは当たり前になっていますが、10年前はなかなか理解を得られなかったんです。
確かに、スタート直後は10倍くらいの時間が作業にかかっちゃうんです。でもAIはとくにゲームデザインと非常に絡み合うので、後半になってどんどん活きてくるんですよ。
むしろ表面だけ繕うと、後がどんどん苦しくなってゲームデザインの幅も狭まってしまう。
※パス検索
3Dのフィールド上に置いて、自律的に移動するキャラクターがたどる移動経路を検索する技術。ナビゲーションメッシュと呼ばれる座標軸をフィールド上に設定し、まずプレイヤーキャラクターの位置や対象キャラクターの可動範囲を検索し、必要に応じて目的地への最短経路や予想経路を計算する。
──まさに今日宮路さんに伺ったお話が、その具体的な例だったと思います。
三宅氏:
僕はそういう話をこの10年ずっと言ってきたつもりなんですが、なかなか解ってもらえなかった。やっぱり実例を見せないとダメだったんですね。
 |
すると1987年の時点ですでにそれを体現した仕様書があって、そこから学べることはやっぱりものすごく多かった。今日、「この仕様書が1987年のゲーム業界に広がっていれば、日本のゲーム産業はものすごく変わってたのに」と話を伺いながら思っていました。
──ゲームAIの歴史が変わっていたと。
宮路氏:
でもいまって、ベースのいちばん大変なところは、すでにいろいろな人が作ってくれているし、API【※】も公開しているので、昔より楽勝で作れるはずなんですよね。それらを使いこなした先に、さまざまな面白さのゲームがあるんだと思います。ゼロから作らなきゃいけなかった時代とは、見違えるほどに状況は違うはずですよ。
※API
アプリケーションプログラムのインターフェースの仕様。ソフトウェアの機能の一部をウェブ上などで公開し、共有することで、ユーザーはサイトに関係なく同じ技術を利用できる。InstagramでFacebookアカウントの情報が使えるなどアプリケーションどうしの連携が可能なのはその例。
三宅氏:
それに、ゲーム業界ってAI技術を無視して演出に流れていた時期が続いていたので、エンターテインメントに応用していない昔の技術も、案外山のようにあるんですよね。
それっていま、ある種の宝の山のようになっているので、その技術をゲームデザインにまで落とし込んでいかなきゃいけないと思います。
宮路氏:
ゲームって、つねに新しい体験を求めてきたと僕は思うんですね。2Dが3Dポリゴンになったのもそうだし、VRもそうですよね。
じゃあいまAIが注目を集めるなかでは、「AIを使うといままでにないこんな体験ができるんだ」というアイデアから、まったく新しい形のゲームが生まれると思うんです。
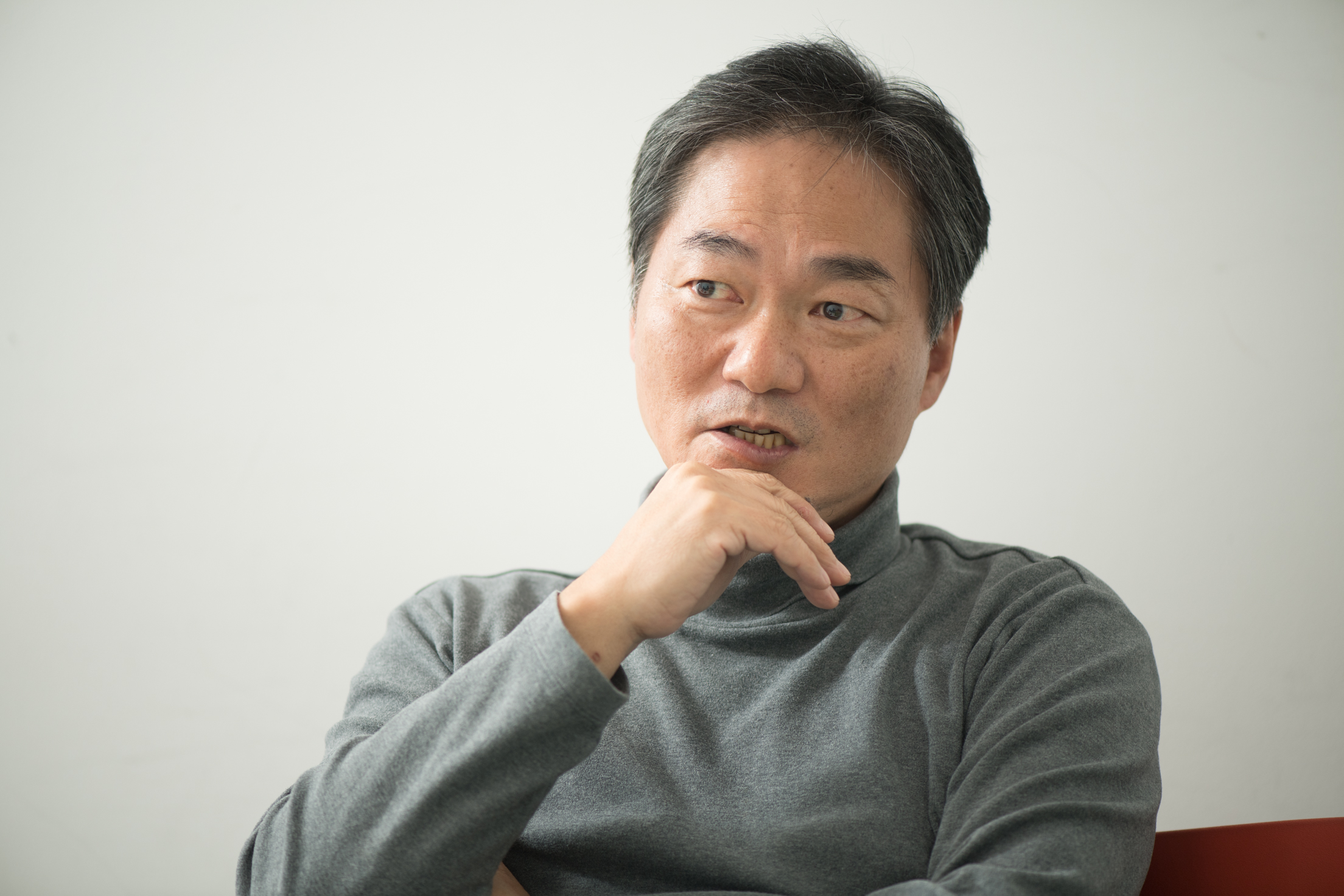 |
そしてプロデューサーをしていて思うのが、そうした新しいAIのような技術は、最初のコアのアイデアを固めるときに決めるべきなんですね。いきなり100人でバンと制作を始めてからだと、100人という重しができるので、ゲームのコンセプトよりもマネジメントを優先させちゃいますから。
そこがいまの日本では難しいのかもしれません。
三宅氏:
たとえば『ポピュラス』や『ブラック&ホワイト』、『Fable』などで知られるピーター・モリニュー氏の開発って、小さいプロジェクトを回せるようなシステムになっているんです。
(画像は2008年発売のニンテンドーDS版、ポピュラスDSより)
2〜3人のチームを組ませてひとつのAI技術を使い、たとえば「かわいい犬の仕草をひたすら作る」みたいなプロジェクトをいっぱい立ち上げるんですよ。『ブラック&ホワイト』シリーズに犬が出てくるのはそのせいみたいですが(笑)。
いずれにせよ、そんなふうに実験的なエクスペリエンスが上手くいったら大型ゲームに実装する……というサイクルができている好例だと思います。
宮路氏:
そのやりかたは完全に正しいね。
僕はゲーム業界を長らく見てきて、そうした新しい技術によるプロジェクトがイノベーティブなゲームを生むと思っていますよ。ただ注意しなきゃいけないのが、イノベーティブなゲームって、最初は大勢には理解されづらいものなんですよね。
僕自身いっぱい過ちを犯しています。たとえば当時仲良かった友人の作った『シムシティ』のプロトタイプなんかも、最初全然解りませんでしたしね……。
『シムシティ』が理解できなかった
──友人って、あのウィル・ライト氏ということですよね。……ちょっと気になるので、その話、詳しくお聞きしてもいいですか?
宮路氏:
じつは1980年代、ウィル・ライトとは年末年始は毎年一緒に過ごすぐらい仲良しだったんですよ。レイク・タホーのスキー場にある別荘にApple IIを持ち込み、スーパーボールを見ながら過ごしたりしていて。
そんなある日、彼が開発中の『バンゲリングベイ』のマップエディターで『シムシティ』のプロトタイプを作っていたんですよ。「こうやって街を育てていくんだよ」というのを見せてもらって。
 |
でも正直に言って、当時アクションゲームが主流のなかで、それの何が面白いのかさっぱり理解ができなかったんです。それから2年ぐらい経ったころかな、Amiga版の『シムシティ』のサンプルをもらったときに──凄まじい衝撃を受けました。
そのとき、「本当に新しいことは理解しにくいんだ」と身をもって知りましたね。
──ファミコンしか知らなかったただの子どもとしては、『シムシティ』に触れて、「ああ、こういうものもゲームになるんだ」と世界が拡がった感がありました。
宮路氏:
その見極めは、『バンゲリングベイ』の版元のブローダーバンドもできていなくて、ウィルが『シムシティ』完成版のデモ持って行っても、最初は「売れない」、「だから扱わない」という判断だった。
そこで彼はマクシスという会社を作り、蓄えかから何から自費を注ぎ込んでパブリッシュしたんですが、やはり最初は全然売れなかったんです。
 |
ところがノーベル賞学者がこれを遊んだらしく、News Weekか何かの全国紙に「これはスゴい」というコラムが書かれたところ、それで爆発的に売れるようになったんです。
そうしたら任天堂が「買いたい」とやって来てスーパーファミコンで発売されることになった。そういう動向を見て事の大きさに気づいたエレクトロニック・アーツがマクシスの株式を買って……というようなことがあったんですよ。
三宅氏:
その後の『シムピープル』(原題:『The Sims』)なども、言ってしまえば家具を買って街で暮らすだけのゲームですからね。それがいまシリーズ累計で2億本近く売れている。
あれって、最初にウィル・ライトが300行ほどのプログラムを持ち込んで始まったんですよね。核となる部分は、最初からそこに全部入っている。
そのAIでは、人間の生理的な欲求のシミュレーションをしていて、いまの日常系のAIの基礎にもなっています。
宮路氏:
ウィルって、いわゆる科学少年なんですよ。アカデミックな方向に行きながらゲーム的なものを作り続けている。『シムアース』なども“宇宙創生”がテーマじゃないですか。
──小さいころの夢が、「人口が増えた地球を救うためのスペースコロニー設立」だったらしいですね。
宮路氏:
懐かしいな……久しぶりにウィルに会いたいものですね。
当時、別荘の近くにギャンブルができるところがあって、みんなでブラックジャックの確率計算なんかをしていると、ウィルも参加してきて「必勝法はこうだよね」って考えてくれて。あのときもみんなでハマったりしていましたねえ……(笑)。
麻雀とは“人生の縮図”
──そこでも相当ギャンブルをやられていたわけですね(笑)。
宮路氏:
ギャンブルって、その人の生きかたや考えかたが如実に表れるのが面白いんですよ。
それこそいろいろなプロ雀士の方たちと出会い、いろいろな打ちかたを見てきましたが、皆さん巧いんですが、個性が全部違うんですね。無謀な打ちかたをする人もいるし、計算に忠実に打つ人もいる。
 |
麻雀をやる仲間はみんな言うんだけど──そこに人生を見るんです。人生ってツイてるときもあれば、ツイてないときもある、判断力が試されることもあるし、仲間たちとのコミュニケーションもある。
そうした人生の縮図みたいなものが、“この一局”の中に入っているんです。
──なるほど。
宮路氏:
それに将棋や囲碁などは、強いやつが強いじゃないですか。でも麻雀って、究極に強いAIを作っても全然意味がない。だって弱い奴でもツキがあれば勝てるわけだし、勝敗よりもコミュニケーションが面白いわけですよ。
麻雀という遊びを知っていれば、知らない人でも相手の意思が手から読めるし、それって立派なコミュニケーションですし、それを経て仲良くなれることもある。これだけ娯楽が溢れかえるなかで、いまだに優れたゲームだと思います。
──だからこそ今日の麻雀の話は、ゲームAI全体の話に広がる余地があったんじゃないでしょうか……と、オチっぽいものがついたところで、そろそろ時間となりました。本日は長時間、ありがとうございました。
宮路氏:
いえいえ、こちらこそ。それではちょうど4人いますので、続きは卓でも囲みながら……(笑)。(了)
 |
さて、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』開発秘話、そしてゲームアーツを巡る宮路氏の逸話の数々、いかがだっただろうか?
今回のインタビューはまずもって早過ぎる“麻雀AI”誕生の謎に迫るものだが、印象的だったのが宮路氏の職人芸のようなゲームの作りかただ。AIで基礎を作ったあとは、もうひたすらに膨大なテストプレイを繰り返し、徹底的に手触りや面白さにこだわっていく。
そうして「バグをあえて残す」、「評価値に“揺らぎ”を持たせる」などの判断をしていった結果生まれたものは、なんのことはない、いまようやく最先端のゲームAIの設計思想がたどり着いたものと響き合っていた。そのことに、まずはこの取材の意義がひとつ垣間見えたのではないかと思う。
また、10代にしてゲーム制作からプログラムブックの出版まで手がけた若き日の氏の活躍もさることながら、技術の会社として最先端の技術に取り組み続けたゲームアーツの話も貴重な歴史的証言であった。
そしてそうした技術的制約のなかで、ユーザー体験を最優先させ、技術と“インチキ”のバランスを突き詰めていく──それこそが宮路氏のゲーム制作であり、さらにはエンターテイメントのひとつの本質であるようにも思えた。
取材中、三宅氏はゲームデザインとAIが絡み合うことの重要性を再三にわたり指摘していた。
電ファミでは今後、『がんばれ森川君2号』、『アストロノーカ』など、早い時期から人工知能を取り入れたゲームを世に送り出している森川幸人氏のインタビューの公開などを予定しているが、こうしたまだ分業制になる前のゲームAIの歴史を通じ、ゲームデザインとAIの両立の秘密について解き明かしていければと思っている。
同時に、冒頭でも述べたように、この記事と時を同じくして、三宅氏の監修によるゲームAI用語辞典なるwikiページを開設した。これは前述のAI記事群を読むときに、知りたいと思った言葉の意味やこれまでの歴史に始まり、実用例など理解を深めるために用意したものだ。ゆくゆくは研究者たちも集い、ソースコードなどもやりとりできる場になればと願っている。
そしてこうしたゲームAIにまつわる記事や用語辞典などで得た知見が、両氏の言うように、これから私たちの未来の生活でその真価を発揮していくことを願ってやまない。
(C)片山まさゆき/講談社・ヤングマガジン Ⓒ1987 GAME ARTS/YELLOW HORN
(C)片山まさゆき/講談社・ヤングマガジン Ⓒ1987,1988 GAME ARTS/YELLOW HORN
(C)1992 竹本泉,GAME ARTS
(C)1993 GAME ARTS
(C)1997 GAME ARTS/ESP キャラクターデザイン/草彅琢仁
【あわせて読みたい】
21世紀に“洋ゲー”でゲームAIが遂げた驚異の進化史。その「敗戦」から日本のゲーム業界が再び立ち上がるには?【AI開発者・三宅陽一郎氏インタビュー】このインタビューでは、大手ゲーム会社で第一線のエンジニアとして働きながら、日本デジタルゲーム学会理事を務め、さらには『人工知能のための哲学塾』や数々のAIの啓蒙書を執筆してきた、AI開発者・三宅陽一郎氏を迎えた。
そこで語られたのは、21世紀に「海の向こう」で驚異の進化を遂げてきた、ゲームAIの歴史だ。それは同時に、日本のゲーム産業が3Dゲームの発展の中で、世界市場の「蚊帳の外」に追いやられていく十数年の歴史でもある。
90年代、日本のゲームクリエイターは、素晴らしい職人芸と独創的なゲームデザインで、世界のゲーム市場を魅了していた。
そこに21世紀、欧米のゲーム開発者たちは「サイエンス」の力でいかに挑み、ついには桁違いの巨大産業へ育て上げたのか──まずは、彼らの成し遂げた、そのイノベーションの歴史を見ていくことから始めよう。















































