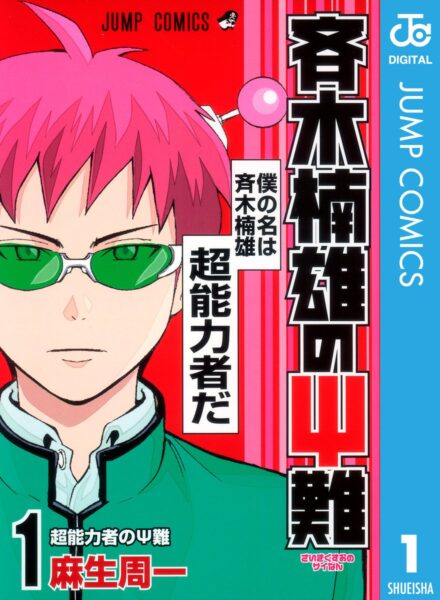「メトロイドヴァニア」は、なぜこれほどまでゲーマーの心を引き付けるのだろうか。
メトロイドヴァニアは、横スクロール2Dアクションゲームのひとつで、マップを探索し、能力を手に入れながら行動範囲を広げていくものを指すことが多い。現在はゲームジャンルのひとつとなっており、Steamストアでもジャンルとしてカテゴライズされている。
2025年7月17日にはバンダイナムコゲームスよりパックマンをモチーフとしたメトロイドヴァニアタイトル『Shadow Labyrinth(シャドウラビリンス)』が発売(Steam版は7月18日発売)。大手パブリッシャーもメトロイドヴァニアへ参入する時代となっている。
「メトロイドヴァニア」という造語の由来は、1986年に任天堂から発売された『メトロイド』と、1997年にKONAMIから発売された『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』(英題: Castlevania: Symphony of the Night)のふたつのゲームに由来している。
2000年代の初頭、ゲームのメインストリームが2Dから3Dへと移る中、一瞬時代から忘れられた2Dアクションというジャンルの空白に滑り込むようにして急拡大したこの言葉は、その後20余年の間に多くのゲーマーを虜にしてきた。
フリーゲームとして出発した『洞窟物語』や、Steam上で大きな人気を博した『Hollow Knight(ホロウナイト)』など。メトロイドヴァニアの発展の歴史は、個人や小規模チームによるインディー開発の発展とともにあった。「メトロイドヴァニア」はインディー開発者たちに愛され、今日でも多数の作品が発表されている。
今回電ファミ編集部では「メトロイドヴァニア」の始祖のひとりであるArtPlayの五十嵐孝司氏をお招きし、さらに同ジャンルを手がける総勢6名のゲーム制作者にお集まりいただき、メトロイドヴァニアの魅力に迫る座談会を企画した。
お集まりいただいたのは、『Bloodstained』シリーズを手がけ、新作『Bloodstained: The Scarlet Engagement』を発表したばかりのArtPlay五十嵐孝司氏。そして『Shadow Labyrinth』開発スタッフである、バンダイナムコスタジオ 原田勝弘氏、高橋徹氏、バンダイナムコエンターテインメント相澤誠吾氏、エンジンズ福井智章氏。最後に、team ladybug制作のメトロイドヴァニアタイトルを複数プロデュースされている、ワイソーシリアス斉藤大地氏にお越しいただき、メトロイドヴァニアの歴史や特性などを、さまざまな視点から語っていただいていた。

、原田氏、高橋氏。
座談会では、「ゲーム中の移動速度」や「セーブポイントの頻度」などからメトロイドヴァニアを考察する意見が出たり、同ジャンルとは切っても切れないインディー開発との関わりや市場の変質などについて指摘する発言など、さまざまな意見が飛び交った。
「自分でもクリアできるアクションゲーム」が作りたかった
──本日はお集まりいただきありがとうございます。『シャドウラビリンス』開発陣の人数が多いので、まず『シャドウラビリンス』スタッフの皆様から自己紹介をお願いします。
相澤誠吾氏(以下、相澤氏):
プロデューサーを務めている相澤と申します。よろしくお願いします。
高橋徹氏(以下、高橋氏):
『シャドウラビリンス』の制作プロデューサーをやっています高橋です。『シャドウラビリンス』の統括というか、「どうしてもこれが作りたかった」っていう企画立案者です。よろしくお願いします。
原田勝弘氏(以下、原田氏):
僕はちょっと特殊な立ち位置なんですけど、全体のコーディネーター的な役割を務めています、原田です。仕事としてはプロデュース側のグローバルマーケティングの展開にも口を出すし、ゲーム自体の内容にも口出しして整合性をとるような、そんなことをやっています。
福井智章氏(以下、福井氏):
株式会社エンジンズという、大阪のデベロッパーに所属していて『シャドウラビリンス』のディレクターを担当させていただいています。もともとはSNK、そのあとはカプコンで働いていました。
──読者のために説明を加えさせていただくと、福井さんの経歴は本当にすごいですよね。大阪芸大卒業後にSNKにデザイナーとして入社し、『サムライスピリッツ』シリーズを手がけ、その後『星のカービィ 鏡の大迷宮』のディレクターも務められていて……。
高橋氏:
子どものころに『ザ・キング・オブ・ファイターズ』や『サムライスピリッツ』が好きだったので、2Dアクションを作るならそのプロの人って思って、福井さんにお声がけしたんですよ。「絶対に『サムスピ』の人とやりたい!」と。
斉藤大地氏(以下、斉藤氏:):
僕は『星のカービィ 鏡の大迷宮』が大好きでして……。
五十嵐孝司氏(以下、五十嵐氏):
海外だと『鏡の大迷宮』が知名度高いですよね。

高橋氏:
今回の座談会では「『シャドウラビリンス』はこんなすごい人が作ったんだ!」っていうところもバンバン伝えたいですね(笑)。
──(笑)。さて、今回はメトロイドヴァニアを手がけていらっしゃる作り手の皆さんにお集まりいただき、メトロイドヴァニアの魅力について座談会形式で語り合っていただきたく、この場を用意させていただきました。
原田氏:
じゃあ最初は、『シャドウラビリンス』が『悪魔城ドラキュラ』と『ブラッドステインド』【※】をどれぐらい参考にしたのかを言えばいいですかね(笑)。
※『Bloodstained: Ritual of the Night』
五十嵐氏が代表を務めるArtPlayが2019年にSteamでリリースしたメトロイドヴァニアタイトル。現在シリーズ新作の開発が進行中。
高橋氏:
たくさん勉強させていただきました(笑)。
福井氏:
もうほんまに90%くらい、設定以外のところは全部参考にさせていただいています(笑)。
──まずはメトロイドヴァニアの魅力というものをできるだけ言語化するところから始めたいと思っていまして、最初のテーマとしては「なぜみなさんはメトロイドヴァニアを作るのか」というあたりから進めていければと思います。
みなさんがメトロイドヴァニアを意識されることになったきっかけや感じた魅力などをお聞かせください。
五十嵐氏:
僕がメトロイドヴァニアって言葉を初めて聞いたのは、『ブラッドステインド』のキックスターターキャンペーンをやっているときだったんですよね。
最初は「メトロイドヴァニアってジャンルになってるの⁉︎」という感想でした。「『メトロイド』って任天堂さんの商標でしょ、そのまま使うのはダメじゃないかな」と(笑)。
原田氏:
(笑)。うしろの「ヴァニア」はギリギリ大丈夫そうですけども。
五十嵐氏:
「ヴァニア」はね……まあ「トランシルヴァニア」って地名もあるし、いいだろうとは思うんですけど、『メトロイド』はさすがにダメだよね、という話になって。そのときに「じゃあ、我々はIGAvania(イガヴァニア)って呼びます」みたいな話が出て、非常に迷惑しているんですけども(笑)。
造語のもとになった『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』(以下、『月下』)ですけど、僕がなぜこういった内容のゲームを作ろうと言ったかというと、いわゆる「ステージクリア型のアクションゲーム」をもっと長く遊べるようにしたかったっていうのがひとつ。もうひとつが、自分でもクリアできるアクションゲームを作りたかった、というのがあります。
当時、『悪魔城ドラキュラ』も含めて面クリ型のアクションゲームって横スクロールが多かったと思うんですけど、うまい人だと2時間くらいでで終わっちゃうんですよね。でも価格は5800円とか、6800円ぐらいするわけです。これをもうちょっと遊べるようにしたいなというのがありました。
原田氏:
僕にとってもメトロイドヴァニアって、昔のアーケードゲームとか、もしくはX1、PC88、PC98の初期ぐらいによく出ていた面クリ型のアクションゲームの系譜なんですよね。あのころの系譜がいまに繋がっているという認識です。
──五十嵐さんももともとそういったジャンルのゲームがお好きだったんですか?
五十嵐氏:
横スクロールもアクションももともと好きですね。好きだったんですけど、なにせ下手くそなんで、クリアできないんですよ(笑)。
でも、クリアできるアクションゲームもあって、それが『ゼルダの伝説』でした。『ゼルダの伝説』はクリアできたんですよ。それで「自分でも最後までできる横スクロールアクション」を作りたいなあと。
あと『悪魔城ドラキュラ』の世界観が好きだったのもありますね。ずっと制作に関わりたいと思っていました。『悪魔城ドラキュラ』のチームに入ったときに「探索しながらやれるアクションゲームにしましょうよ」という話をして。
ですので、いちばん最初は探索型アクションゲームを自身が携わりたいと思っていた『悪魔城ドラキュラ』で、っていうところでした。ただ、じつはそれができるようになったのって『ときめきメモリアル』のおかげなんですけども。
原田氏:
『ときめきメモリアル』のシナリオに関わられてたんですよね。
五十嵐氏:
『ときめきメモリアル』のオリジナルであるPCエンジン版のスタッフのひとりです。ご指摘のとおり、シナリオを担当していました。
原田氏:
脚本畑からエンジニアというのは変わった経歴ですよね。
五十嵐氏:
もともとはプログラマーなんですけど、僕のような例も含め、いろいろなスタッフがシナリオを書くこともあったんですね。
僕は大学ではSF研究会で映画を撮っていたので、一応脚本を書いたことがないわけじゃないのもあって『ときめきメモリアル』のシナリオを書くことになったんです。『ときめきメモリアル』が爆発的にヒットしてくれたおかげで、ちょっと融通が利くようになって……。
──わがままが言えるようになったんですね(笑)。
五十嵐氏:
PCエンジン版の『悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』を作っていたころ、僕は隣りで『ときめきメモリアル』を作っていたんですよ。「いいなあ」って指くわえながら。
原田氏:
あれやりたいなあと(笑)。
五十嵐氏:
『ときめきメモリアル』のシナリオを書きながら『ドラキュラ』チームに遊びに行って触らせてもらったり、息抜きの場にしていたんですよね。その後、いろいろあって『月下』に携わらせていただいて……。ちょっと話がそれちゃいましたけど。
原田氏:
『ゼルダの伝説』シリーズはもともとファンだったんですか?
五十嵐氏:
めちゃくちゃファンですね。『メトロイド』も好きなんですけど……『メトロイド』って難しいじゃないですか。
原田氏:
そうですね、難しい。こういうことを言うとファンに「いや難しくはないだろ」って怒られるんで、あまり言わないようにしてるんですけども(笑)。
五十嵐氏:
『悪魔城ドラキュラ』を探索型にして経験値のシステムを入れたのも、時間をかければちゃんとクリアできて、エンディングを見ることできる、という想いからだったんです。値段分は遊んでほしいなあって。
ただ『月下』はマルチエンディングを採用していたので、最初のエンディングを見ただけでソフトを売りに出してしまった人がいて(笑)。
高橋氏:
あるあるですね(笑)。
五十嵐氏:
ちゃんとエンディングを作っちゃったので……ゲームオーバーにすべきだったかも……。
原田氏:
メトロイドヴァニアが昔のアーケードゲームとかと決定的に違うのは、「プレイごとにお金がかかる」ことと、「技術を上げない限りクリアできない」っていうのを崩したところなんですよね。
このふたつってアーケードゲームのビジネスモデルとしては絶対的なルールだったわけですが、『月下』のRPG要素がそれを打ち崩したんですよね。
原田氏:
キャラクターが強くなったりとか、ゲーム中にポーズかけて回復薬が飲めちゃうとか。これってアクションゲームをクリアできない人への救済なんですよ。「好きだけどクリアできない」っていう、まさに僕みたいなのがターゲットなんですよね。それで、世の中にそういう人が結構いるってことなんですよね。
斉藤氏:
めちゃくちゃわかります。僕もスーパーファミコン版の『悪魔城ドラキュラ』を子どものころにやって、怖すぎて難しくて、夜に夢を見ましたからね(笑)。難しいし怖いしクリアできないよ、みたいな。
高橋氏:
あの聖水の瓶が割れることも怖いし(笑)。
斉藤氏:
全部怖かったですよね。自分もそんなにアクションゲームがうまいほうじゃなかったので。『月下』は「時間をかければクリアできる」っていうのがすごくうれしかったです。
五十嵐氏:
当時、ゲームを遊んだ方からうれしいお便りをもらったことがあったんです。30代の女性から「パケ買いしたんですが、初めてアクションゲームをクリアできました!」というお手紙をもらったことがあって、「ああ、作ってよかったな」と思いましたね。
原田氏:
それぐらいアクションが苦手な人まで広がったってことですよね。
五十嵐氏:
そうだと思います。まあ、パッケージのビジュアルもよかったんですよ。
高橋氏:
パッケージのアルカードが幻想的でイケメンでしたね。
原田氏:
女性がちょっと惹かれる感じのね。
五十嵐氏:
あれはもとの『悪魔城ドラキュラ』が「ヴァンパイアがテーマなのに、なんで筋肉マッチョ推しなんだよ」っていうのもあったんですよ(笑)。
メトロイドヴァニアの探索の醍醐味とは?
──さきほどキャラクターの成長要素の話題がありましたが、プレイヤーとの距離感と言いますか、作り手側としてゲームの難易度と親切さのバランスをどのように考えているのでしょうか?
プレイヤーに「おもしろさ」を感じさせる難易度バランスを、どう設計されているのかをおうかがいできればと思うのですが……。
高橋氏:
『シャドウラビリンス』では『Hollow Knight』(ホロウナイト)をかなり参考にさせてもらっています。私が『ホロウナイト』をプレイしててびっくりしたのが、Steamのアチーブメントを見たときに、クリアしてる人が10数パーセントだったということ。
といっても私も下手でクリアできてないんですけども、私はあの難度が好きだったんですよね。ですので、『シャドウラビリンス』ではあの難度を維持したまま、ゲーム中の成長要素でクリア率をもっと上げようと考えました。
難易度自体は『ホロウナイト』を軸にしつつ、プレイヤーの装備を銅の剣から銀の剣にして……というやり方でクリア率を上げることを目指しました。

五十嵐氏:
ウチのやり方のひとつですが、「その敵は何発で倒せるのか」をベースに設計を組み立てていると聞いてます。序盤の簡単な雑魚は最初2発でとか、後半のボスは何発ベースでとか、割と普通のアクションゲームと似てるかもですね。
あとは適正レベルをだいたい決めていて、その適正レベルを超えれば少し楽になれるよ、という設計にしていますね。
福井氏:
それは『シャドウラビリンス』でも同じですね。1回のコンビネーションが4発で、普通のザコ敵なら4発当てれば死ぬけども、ちょっと強い敵ならあと1発必要になるというバランス。そこでレベルをひとつ上げたら、あと1発必要だった敵もワンコンボで倒せる、というものですね。
先日、デモ版を体験していただいた、いろいろな方のプレイを見たのですが、いまのゲーマーはみんなうまいっスね。「その技、そんな使い方できるんや!」とこちらが驚きました(笑)。
原田氏:
でも、彼らに合わせたらダメなんですよ(笑)。うまい彼らに合わせたら、ゲームのすそ野が小さくなっちゃう。
高橋氏:
(笑)。
斉藤氏:
メトロイドヴァニアにおける親切さとかプレイヤーの距離感で言うと、ひとつずっと考えてることがあるんですよね。それがメトロイドヴァニアのマップについてなんですけど、要するに探索する際にプレイヤーが好む「迷い」があるんじゃないのかと思ってるんです。
僕はアクションゲームの戦闘とかに関してはちょっとわからないところが多いんですけど、マップの塩梅に関しては明確にメトロイドヴァニアユーザーの好む「彷徨う速度」があるんじゃないかって思っているんです。言語化するのは難しいんですけども。
たとえばteam ladybugの作品って、ものによってはマップがリニア(直線的)だったりするんですよね。簡単に言えばメトロイドヴァニアっぽくない。昔、あるゲームでステージ追加型のようなアーリーアクセスをやったことがあるんですけども、それは一般的なメトロイドヴァニアよりも横スクロールアクションに近いマップだったんです。
でもプレイヤーのみんなは、その作品をメトロイドヴァニアだと思ってプレイしているんですよね。じゃあ、ユーザーは何をいちばんメトロイドヴァニアだと思っているんだろうと考えたときに、team ladybugの設定するゲーム中の移動速度とマップを彷徨う速度と『月下』をはじめとする名作たちがとても似ていることに気づいたんですね。
そこで思ったのが、もしかしたらユーザーはこのマップを行ったり来たりする速度のことをメトロイドヴァニアだと思ってるんじゃないか、っていうことなんですよ。
意外かもしれませんが、team ladybugはダッシュ移動を絶対に入れないんですよ。とても以前「ダッシュ移動を入れようよ」と相談したら「このテンポが大事なんです」と断られて。「ユーザビリティが…」といったら「それはまやかしのユーザビリティです」って(笑)。
──名言ですね(笑)。
斉藤氏:
結局そのときは、あとからアビリティでダッシュを追加してくれたんですけど、「最初からは入れちゃダメなんです」とladybugは言っていました。だから僕はこの速度が、プレイヤーとメトロイドヴァニアのマップとのあいだに通じている距離感なんじゃないかと思ってます。
ただ、ladybugでも最新作はいわゆる「どこでもワープ」を入れてみたんですけど、意外と体験を損なわなかったですね。行ったり来たりのテンポがちゃんと良くて、しっかりおもしろかったです。
──プレイヤーからすると、テンポを重視しているとは思います。
斉藤氏:
じつはメトロイドヴァニアのプレイフィールでいちばん大事なのって、移動のテンポなのかもしれないですね。いま売れているメトロイドヴァニアのタイトルを見てると、結構それを感じます。
とくに近年のメトロイドヴァニアでは「探索をしている」という状況それ自体が重視されていると思っていて、とにかく背景であるとか舞台設定とか世界観といった「没入感」に関与する要素が求められる傾向にあると思います。でもそのときに移動のテンポが早すぎると、周りに目が向かなくて、頭が回らないんだと思うんですよ。
原田氏:
難しいですね。僕は「速度」ではないんじゃないかな、と思います。とくに五十嵐さんが作っているタイトルを遊んだときに感じることなんですけど、メトロイドヴァニアたらしめているのって「セーブポイントの場所と頻度」なんじゃないかと思ってます。
斉藤氏:
あ~、それもわかります。
原田氏:
メトロイドヴァニアの探索って、「どこまで進むのか」という緊張感がつねにあるんですよね。「この先まで進むのか、やめて1回戻るのか?」という。僕はやっぱりそのリスク・リターンがゲームの基本になってるんじゃないかと思っています。
たとえばそれが昔のゲームだと、そのふたつのバランスがかなり極端で、「すべてを失うか、プレイヤーがうまくなるか」しかなかったんですよ。
『ブラッドステインド』をプレイしても感じるところなんですが、先に進むのか戻るのかっていうプレイヤーの選択は、キャラクターのアクション的な速度ではなくて、レベルデザインとしてのセーブポイントの場所と頻度によってコントロールされてるんじゃないですかね。
五十嵐氏:
いまはもうクイックセーブが増えて、すぐ再開・再戦できるようになってますよね。でも昔は「死んだらセーブポイントまで戻る」というのが一般的でした。入手したアイテムはもちろん全部放棄というレベルデザイン。その点『シャドウラビリンス』は取ったアイテムはちゃんと残してくれていますよね。
原田氏:
優しいですよね(笑)。僕らの世代なんてPCがカセットテープの時代、たとえば『ハイドライド』なんかはA面に戻して40分待ちとかでしたもんね。
※『ハイドライド』
1984年に当時のT&E SOFTがPC-8800シリーズなどに向けて販売したPCゲーム。
福井氏:
『シャドウラビリンス』でも最初はデスペナルティありで、「死んだらゼロ」というデザインにしてみたんですけど、テストプレイをしたスタッフから非難囂々で(笑)。
原田氏:
いまはもうダメなんだよね(笑)。
高橋氏:
プレイ時間を大幅に戻すのって、悪い意味で心が折れるタイミングになっちゃいますよね。「もうこのゲームやめよう……」って思うタイミング。死んで大幅に戻されちゃうと、ゲームプレイが楽しくなくなってしまう。
私なんかはかなり辛いと思うんですけど、福井さんは「それが楽しいんだ!」っていうところがあり、結構揉めました(笑)。
五十嵐氏:
意見がわかれるところだと思いますよ。でもいまのユーザーはどちらかというと、死んだときに失うものが多いというのはあまり好きじゃないですよね。
原田氏:
大嫌いですよね。
斉藤氏:
僕も辛いですね。でもそんな中でも『Escape from Tarkov』【※】が流行っていたり……。
※『Escape from Tarkov』
リアリスティックなゲームプレイを特徴としているFPS。他プレイヤーとのレイドで死んでしまった場合、身に着けていたものやそれまでの入手品を(一部の例外を除いて)すべて失ってしまう。
原田氏:
そうなんですよね。
斉藤氏:
ミスったら全部台なしになるっていうのは、ゲームの根源的な快楽のひとつだとは思うんですよ。
原田氏:
僕もどちらかというと「死んだら最初から」くらいのほうが緊張感を持ってプレイできるんですよね。なので根っこの部分では、ゲームには高いリスクがあったほうがいいと思っているんです。だけど最近の若い人にそれを言うと、「冗談じゃない」という反応をされちゃうんですよね。
現在のトレンドだと、クロスプラットフォームが当たり前でコンソール機で遊んだゲームの多くがPCで遊べるようになっていますし、中断してもすぐ続きから始められてパッパッと短時間で遊べるような、そういうスタイルですよね。
福井氏:
うちの息子が20代後半のゲーマーなんですけど、いまの若い子たちはいろいろなゲームを遊んでいるので、ひとつのゲームに時間を取られるのを嫌がるんですよね。
死んだからゼロみたいなゲームだと「え、じゃあこの5分とか10分、下手したら30分が無駄になるってこと⁉︎」となってしまう。
斉藤氏:
ゲーマーの中でも、ゲームへの比重が高い人はあまり気にならないみたいなんですよね。死んだらゼロみたいなことがあっても「そういうこともあるよね」と受け取ってもらえる。そういった尊敬語としての「ゲーマー」という存在が、僕はあると思ってます。
原田さんみたいな「ゲームが人生だ」と思っているコアゲーマーの人数って、たぶん昔とそんなに変わっていないんじゃないでしょうか。現代でそうじゃないゲーマー層が浮かび上がってきてるのは、それだけゲームが外側に広がったということじゃないかなと。
福井氏:
僕らの若いときってネットはなかったじゃないですか。でも、いまはもうネットが当たり前で、つねにボイスチャットを繋いで、という遊び方です。なのでそういう感覚っていうのは、昔とだいぶ違うとは思いますね。
五十嵐氏:
やっぱりいまの時流に合わせていくのがつねなのかな、とは思うんです。「死んだら全部なし、なんていまどき流行らないですよ」という声は多いですからね。