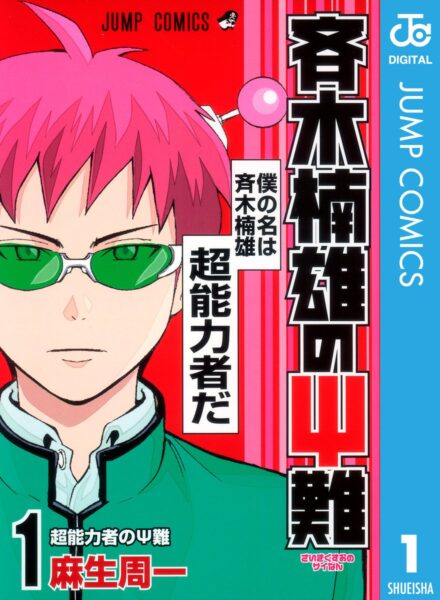最近はアクションゲームにも「物語」が求められるように
──五十嵐さんは先日新作の『Bloodstained: The Scarlet Engagement』を発表されました。お話できる範囲で、『ブラッドステインド』シリーズで何を目指しているのかなど、意気込みを聞かせていただけますか?
五十嵐氏:
もともと『ブラッドステインド』は、2D横スクロールアクションゲームがなかなか商売にならなくなってしまったっていうのが遠因にあるんですよね。
当時、このジャンルのゲームは携帯機でおもに展開されていたのですが、利益を出していくのが難しくなってしまったんですよね。プライスプロテクションがどうにもできない時代だったんです。要するに開発費がかかるんだけど、ゲームの価格を上げられない。「フルプライスでいいじゃん」と提案しても、「そんなことはできない」と言われてしまって……。
それから少し経つんですが、ちょうど『Mighty No. 9』【※】がクラウドファウンディングを実施してうまくいったタイミングで、その仕掛け人の方の祝賀会に呼ばれていったんですけど、そこで耳元で「辞めるならいまですよ」って囁かれて。
※Mighty No. 9
『ロックマン』シリーズで知られる稲船敬二氏が、インティ・クリエイツとともに開発した2D横スクロールアクション。2013年、クラウドファンディングサイトのKickstarterで出資を募り、380万ドル(約4億円)を集めて話題となった。
──(笑)。
五十嵐氏:
ちょうど出資したいと言ってくださった会社もあったので、「じゃあ『ブラッドステインド』を作ろう」と会社を辞めたんですよ。でも出資予定だった会社の状態がちょっと怪しくなり、クラウドファンディングをやることになったんですね。
初代『ブラッドステインド』のコンセプトは、「あの楽しかったゲームをもう1回やれる」なんです。ものすごく懐古主義っぽい考え方なんですけども、初代『ブラッドステインド』はユーザーが期待してくれたとおりのものを提供できたと思っています。
いま作ってる『Bloodstained: The Scarlet Engagement』は初代とは違うコンセプトなこともあって、企画立案からディレクター(SHUTARO氏)に頼りっきりです。だから、そのディレクターの想いがすごくこもっている、チャレンジングなタイトルになってます。ふたりのキャラクターを入れ替えながら戦っていくゲームになっていて、ジョブシステムとか、閃技システムとか、いろいろと新しいことをやっています。
原田氏:
「閃技システム」って何ですか?
五十嵐氏:
アクションの最中に特定の条件を揃えて技を出したりすると、新しい技がひらめくというシステムですね。ひらめくことでその技を使えるようになると。
原田氏:
初代の『ブラッドステインド』を開発していたときに、いちばん大きかった学びや反響ってどんなものでしたか?
五十嵐氏:
これはけっこう前から言われていたんですけど、「ストーリーとかキャラクターをもっと深く掘り下げてくれ」という意見が多いんですよね。
原田氏:
なるほど〜、そっちなんですね。
五十嵐氏:
これは僕のスタイルというか癖みたいなものなんですけど、アクションゲームだったらシナリオはゲーム性をジャマしない程度の最低限に留めておくのが好きなんですよね。『ときめきメモリアル』のときに考察本がいろいろ出たこともあって、ゲームで表現されていないところはユーザーさんが想像力で勝手に埋めてくれればいいという考えなんです。
もしその後に続編を作ることがあるとすれば、そのときに「これが公式だ」として、空白を埋めればいいと思っているんですよね。でも、いまはそこをもっと深く掘ってほしいと。
そういうこともあって『The Scarlet Engagement』ではシナリオを書いていないんですよ。初代は僕が書いていたんですけど、僕が書くと簡素化しちゃうので(笑)。今作はディレクターがみずから執筆しているのですが、これがすごくおもしろいんですよね。
原田氏:
僕は初代『ブラッドステインド』の「懐かしい感じ」が好きでした。キャラが急に帰りだすとか(笑)。
五十嵐氏:
ご都合主義がいっぱいあります(笑)。
原田氏:
なにかを説明し始めたところで「じゃあ、私は先に行きますんで!」という展開があったり。いやいや、それは都合がよすぎるんじゃないの、と思いましたから(笑)。
五十嵐氏:
『月下』のときも、「お前、ここどうやって入ったんだよ」というのがありましたから(笑)。
原田氏:
でも確かに格闘ゲームでも、いまはストーリーが重視されているんですよね。格ゲーのストーリーってなんてもともとご都合主義だし、昔は「必要ないだろ」と言われていたんですよ。
でも21世紀に入ったあたりから世の中がけっこう変わってきましたよね。ストーリーモードが入っていない格ゲーは、統計的に見てもあまり売れない。ストーリーモードにしっかりとお金をかけているタイトルのほうが圧倒的に売れるんです。『鉄拳』がぐわっと伸びたのもその影響が大きかったんですね。
『鉄拳』とか『モータルコンバット』って、ものすごくお金をかけてストーリーモードを作っているんです。昔と比べると客層が圧倒的に変化していて、この変化は若い人だけに限ったことじゃないのかもしれません。ナラティブを求めるお客さんって、いまのトレンドなんですよね。
斉藤氏:
ナラティブは難しいですよね。ゲームのシナリオだから、短いほうがいい。でもユーザーはストーリーにも多くを求めだしているので、短すぎると不評になるかもしれない。ゲーム体験と合っていれば、長くても短くてもいいんですけど、それはものすごく難しい。……。
原田氏:
ずっと解説されても困る、っていうのがありますよね。
福井氏:
僕ら世代のゲームって、容量の問題などもあり、そんなに演出ってなかったじゃないですか。
原田氏:
「『覇王翔吼拳』を使わざるを得ない」【※】という演出もありましたが……。
※「覇王翔吼拳を使わざるを得ない」
SNKの格闘ゲーム『龍虎の拳』の主人公、リョウ・サカザキのセリフ。ジョン・クローリー戦前のデモシーンで流れる。全文は「武器を持った奴が相手なら、『覇王翔吼拳』を使わざるを得ない」。
福井氏:
いや、あれは使わざるを得ないんですよ(笑)。
──元SNKスタッフの方からのツッコミ、ありがとうございます(笑)。
福井氏:
でもまあ、いまのナラティブはすごいですよね。
原田氏:
みんな求めますよね。ゲームプレイの達成感とかおもしろさだけじゃなくて、そこに体験としてよさを入れてくれ、って求めてるんですよ。
──単にストーリーを語るのではなくて、システムやゲーム性などで感じさせる、体験させるという物語表現が増えている感じがありますね。
相澤氏:
『パックマン』ってもともとシナリオやストーリーがほぼないんですよね。設定としては彼女がいるとか、ちょこちょことはあるけども……。
原田氏:
というかあるわけがない! あの時代に生まれたゲームにそんな深い話があるわけがない(笑)。
相澤氏:
いろいろと派生作品みたいなのが出てきたときに、ちょっとした設定が生まれたりはするんですけど、どうしても根幹となるシナリオはないんですよね。だから何か新しいものを作り出すっていうのが難しいんです。
今回メトロイドヴァニアというジャンルで作ると決まったときに「やっとストーリーを入れられる」とよろこんで(笑)。やはりストーリーがあるといろいろと展開がしやすいんですよ。
高橋氏:
たとえば『ホロウナイト』だと、物語はちょこちょこっとしか見せませんよね。まさに感じさせる内容になっている。『シャドウラビリンス』でもそういうやり方を目指してはいたのですが、そうは言っても今回はパックマンIPを使っていますから「なぜパックマンがここで戦っているのか」というところをちゃんと描かないといけないんですよね。
そのため、開発過程の中でストーリーが多くなり、さらに私が以前手がけた『New Space Order』に関連した歴史の話も入ってきたり、さらにはUGSF(銀河連邦宇宙軍)【※】の世界観を使っているので、整合性もとらないといけない。ですので、メインのストーリーのほかに、ゲーム中で拾える手記をアイテムとして登場させて、より深い話がわかるように補完しています。
※UGSF」(銀河連邦宇宙軍)
ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)のゲーム内に共通して登場する架空の軍隊、および登場する一連のタイトルを指すシリーズ名。初出は1984年『ギャプラス』に登場した「銀河連合軍」。
福井氏:
それが人員も予算もすべて決まったあとでさらに増えたので、もう現場は壊滅状態でした(笑)。
高橋氏:
いや、違うんですよ。「俺たちの好きにやらせろ」みたいなことを言ってたじゃないですか(笑)。
福井氏:
僕もどちらかというとゲームに演出はそんなにいらない、物語の隙間は自分の心で埋めろ、というタイプの人間なので、最初はそのつもりだったんですよ。
でも、物語の設定みたいなものが膨らんできたときに、現場は「ええ……」という空気になっていたんですが、そんなことを言いながらもみんなノリノリで作業をしていました(笑)。
斉藤氏:
ちなみに、僕はプロデューサーとしてシナリオは一応見ますが、「ゲーム体験とのシンクロニシティがあるテキストにしてね」とはずっと言っていますね。
ladybugの新作『ブレードキメラ』も、ツリー形式でスキルを習得していくシステムなんですけど、この部分もストーリーと連動させています。
記憶をなくした男がスキルを思い出すたびに記憶も取り戻し、ストーリーも進んでいく。そうすることで、プレイヤー自身もゲーム内のキャラクターが思い出したことを追体験していく感じになるわけですから。
「おもしろいだけ」ではもう足りなくなってしまった
──斉藤さんは先ほどメトロイドヴァニアのトレンドみたいなところをお話されていましたけど、時代性的な気づきなどはありますか?
斉藤氏:
時代性というか、Steam市場ではメトロイドヴァニアの数がとにかく増えましたよね。一時期は「メトロイドヴァニアで一定のクオリティのものなら100%買う」というユーザー層が一定数いたんですよ。「メトロイドヴァニアこそ最高のゲーム」と思っている層が確実にいましたよね。
でもいまって、そういう層ですらやりきれないぐらいメトロイドヴァニアがあふれちゃっているんですよ。こうなってくると、もう良いだけでは厳しいんですよね。
原田氏:
結局はマイナーなジャンルであっても、それが確立してしまうとメジャージャンルと同じ苦しみを背負うことになってしまう。そうなると作っている人の知名度とか、IPであったりとか、そういうものがほしくなるんですよね。
いまは、ゲームがおもしろいというのは当たり前になっちゃっている。Steamって1000円、2000円のゲームが相当おもしろいじゃないですか。実際におもしろくて評価も高いんだけど、あまり売れていないというタイトルもいくらでもあって、マーケティングが足りてないんですよね。
世間が気づいたらみんなが評価するんだけど、気づいてもらうにはパブリッシャーだったり、IPだったりのパワーが必要になる。差がつかなくなる市場的な苦しみが、メトロイドヴァニアというジャンルにも出てきちゃったってことですよね。
斉藤氏:
近年はボリュームを求めるユーザーがSteam上で明白に増えましたよね。僕もSteamレビューで「ボリューム」っていう単語が出てくるようになったのを観測していて、本当に成熟期だなと感じています。
原田氏:
ボリュームそのものというか、価格に対してシビアなんですよね。
斉藤氏:
そうそう、そうなんですよ。
原田氏:
値段が8000円に設定されていたら見方もシビアになるけど、2400円だったら許してやるか……となる。海外だと、$19.99なのか、$29.99なのか、$39.99なのかでだいぶ求められるものが違うんですよ。
斉藤氏:
3~4年前くらいまでは、もうちょっとユーザーもおおらかでしたよね。価格もボリュームも、おもしろければ目をつぶるよ、っていうおおらかさがあった。
原田氏:
AAAのゲームも遊んで、メトロイドヴァニアもサブ的に買ってるような人たちが、メトロイドヴァニアを主食にし始めているのも影響としてあるんじゃないですかね。それで余計にみんなが欲張りになっているんじゃないかな。
そういった状況の中、今度はバンダイナムコのような会社が手を出してくるわけで(笑)。余計にそれが加速するんでしょうね。
相澤氏:
そういうところはあるでしょうね(笑)。
高橋氏:
『シャドウラビリンス』も当初はクリアまで20〜30時間だと思って作り始めていたんですけど、だんだんボリュームが増えていき、私自身が最終面まで行くのに、だいたい60時間くらいかかるんです。ここまでのボリュームになると、評価の見方もシビアになりますよね。
斉藤氏:
いまって、何かがよければいいってわけではないですよね。アートも設定もアクションもナラティブも全方位で優れていて、かつプレイタイムもある程度にまとまっていないといけない。だからとても難しいですよね。
高橋氏:
……じつは気になっていたことがひとつありまして、「私たちがメトロイドヴァニアに行っていいのかな?」とずっと思っていました。メトロイドヴァニアって、ある意味インディーの聖地みたいなところじゃないですか。そこに行くっていうことが失礼にならないかなと。
「我々の楽園に潤沢な資金を持って入ってくるな」と思われてるのではないか……。ですので、インディーファンというか、メトロイドヴァニアファンの皆さんには怒られるかもしれないですが、こんな奴らが作っているので許していただければと……。
原田氏:
あはははは(笑)。
斉藤氏:
そもそもの話、インディーってゲーム業界のルネッサンスなんですよね。別にゼロから始まったムーヴメントではなくて、メトロイドヴァニアというジャンルも、もともとはKONAMIさんや五十嵐さんをはじめとした開発スタッフ、任天堂さんと『メトロイド』のスタッフさんたちが作り上げたものがあったからこそのものですから。
原田氏:
巨大なパブリッシャーが作ったものですよね。
斉藤氏:
ゲームの技術が進歩して、2Dという場所が一瞬ゲームのメインストリームから取り残された瞬間があって、その空白部分にルネッサンスとして復刻するような形で作られてきた運動だと僕は思っているんですよね。
その場所で新しく尖ったものをやろうとしていたアーティストのようなインディークリエイターたちは、またつぎに行く場所を探すんじゃないのかなと思います。Steamというプラットフォームは、昔はインディー開発者にとってとてもいい場所だったと思います。でも、その場所に「大手が入ってくるな」というのは逆に傲慢になってしまいますからね。
五十嵐氏:
『ブラッドステインド』はよくインディーと言われるんですけど、僕は特段インディーだとは思ってないんですよね。インディーに対して失礼だと。別にメトロイドヴァニアはインディーだけのものではありませんから。
僕の中でのインディーは、爪に火を灯しながら「自分の好きなものはこれなんだ!」ってコツコツ作っているようなものなんですよ。『ブラッドステインド』はクラウドファンディングで支援を得ているし、パブリッシャーから出資も得ているし、さすがにそれをインディーと呼ぶのは、ちょっとインディーに失礼だろうと僕は思っています。
原田氏:
わかります。僕もそのイメージです。まさにインディーズバンド的なね。
高橋氏:
同人誌的なノリ、って言うんですかね。
斉藤氏:
僕もまさにインディーレーベルの社長で、クリエイターは基本的に1〜2人とか4人くらいの少人数チームをプロデュースしています。とはいえ、インディーの定義は難しいんですよね。ユーザーからすれば、さきほどおっしゃられたとおり、価格とクオリティー以外、関係ないんですよ。
原田氏:
そうなんですよね。尖ったアートワークで2000円〜3000円くらいのものをインディーゲームだと思っているんですよね。
斉藤氏:
ある種マーケティング的にインディーゲームをやってるところもありますよね。
ただ、少数で、身を削りながらインディーゲームを作っているクリエイターさんたちもいて、これは本当に尊敬されるべきだと思いますね。アメリカの『kenshi』というタイトルの開発者さんのインタビューを読んだんですけど、あれはすごかった。
初期は、夜警のバイトをしながらゲーム開発をやっていると。「なんで下請け仕事をしたりパブリッシャーからお金をもらわないんだ」と尋ねられたら「インディペンデントであるというのは、何物にもかえがたい宝物だと思っています。」って答えていたんですね。
原田氏:
なかなかすごいですね。
斉藤氏:
アメリカのインディークリエイターだな、と感じました。国民性もある気がしますね。ヨーロッパの方たちは、むしろ結構もらう印象があるんですよ。多分ヨーロッパだと伝統的に映画とかで比較的ディレクターに自由さがあるから、お金をもらってものを作ることをそんなに恐れていないんじゃないか、と愚考しています。
一方、日本のインディーゲームはインターネットの産物だと思っているんですよ。インターネットと、Unityと、RPGツクール的なツールの発達によって、個人でもニコニコ動画で動画を投稿するようにゲームを作れるようになったという。インターネットクリエイターの一種として発生したのだと思っているんですね。
原田氏:
なるほど。
斉藤氏:
まあそれはさておき、メトロイドヴァニアっていうのが、個人や小規模チームでも作りやすいジャンルであったことは間違いないと思いますね。
原田氏:
いまやそれもなかなか難しくなってきましたよね。今日ここまで話を展開して思ったのは、ぜひゲームの2周目の要素として、五十嵐さんが解説するオーディオコメンタリーを副音声で入れてほしいですね。BGMの代わりに「ここは結構苦労していて……」とか、「このキャラのバックストーリーはじつはこうで」とか、「予算がなくなってこのステージはここで終わっています」みたいなものがあると、「このゲームのことを深く知りたい」という方にはよろこばれると思うんですよね(笑)。
しかもゲーム業界初になるかもしれない……。これ、いいこと言ったんじゃない(笑)。
一同:
(笑)。
──原田さんが最後に和ませてくれましたので、座談会はここまでとさせていただきます。皆さん、本日はありがとうございました!(了)
ユーザーの間から自然発生的に生まれた「メトロイドヴァニア」というものは、かつてはそれを生みだしたインディーの聖地だった。けれどそれも今や確立されたジャンルとなり、インディー開発者だけでなく、大手のパブリッシャーなども参入する人気ジャンルのひとつとなっている。
これまでメトロイドヴァニアは、多くの人がクリアできるアクションを作りたいというジャンルの原点から、暗く内省的な物語や、探索するというプレイそのものにまつわる不安感、そして世界観を楽しませるためのゲームテンポなど、多くの独特な要素を発展させてきた。
けれど多数の作品が生まれる豊かな土壌となったメトロイドヴァニアは、それゆえにいま大きな変化の時期を迎えているのかもしれない。もはや「おもしろい」だけで足りないのだ。より深い物語体験がなければ、現代ではユーザーを十分に満足させることはできない。たとえばIPというものに注目が集まっているのもそのひとつだろう。
「パックマン×メトロイドヴァニア」という異色の組み合わせも、一見するとそうした話題性的なIP利用にも見えてしまう。だが、今回の座談会の中で浮かび上がってきたのは、それよりはるかに強力な「おもしろいメトロイドヴァニアを作りたい」という、メトロイドヴァニアの魅力に取りつかれた開発者たちの誠実な挑戦だった。
一方で、パックマンという明るく健全な雰囲気のキャラクターが、メトロイドヴァニアという内向的な暗さを持つゲームの中でどのような変化を遂げることになるのかは、興味深いポイントでもある。かつてほとんどナラティブを持たなかったキャラクターは、感情の内面へ内面へと向かうゲームと融合することで、より深い奥行きを持つキャラクターになるのかもしれない。
メトロイドヴァニアはいま成熟を迎えている。といっても、成熟は停滞を意味しているわけではない。積み重ねてきた過去の蓄積をどうやってもうひとつ超えるのか。新たな問いを重ねることによって、過去の形式をどう超えるのかが求められているのだ。迷宮を彷徨うパックマンは、その問いに答えを見つけ出せるだろうか。