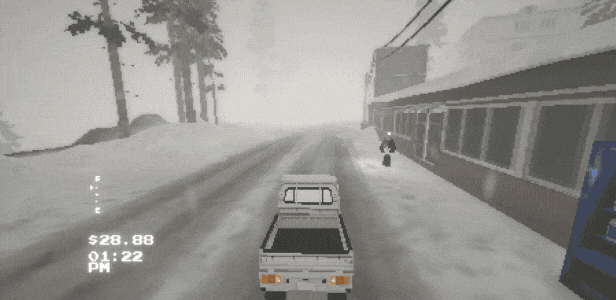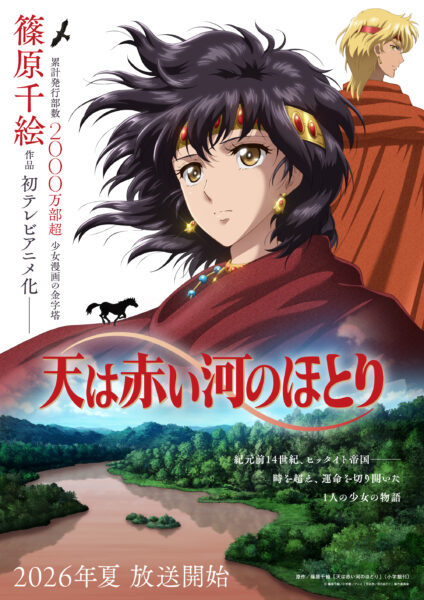タイトル名:『Easy Delivery Co.』
プラットフォーム:PC(Steam)
開発元:Sam C
発売日:2025年9月18日
価格:1,499円
概要:
『Easy Delivery Co.』は、のんびりとしたドライブゲーム。あなたは猫の配達屋となって、雪山の山間の町でドライバーとして仕事をこなしていく。なお、報酬は最低賃金に満たない。
他者の実在の確信について
先日、車に荷物を積み、三時間の道程を往復した。
あるところで、わたしはふと、ひとりだった。
わたしのほかに運転手はおらず、視界はモノクロで、ひとりぼっちの信号機の寂しげな赤色が、霧に滲んでいる。
十字に区切られた新田の交差点が、雨に煙っている。
わたしは妄想した──人間は、みんな滅んでしまったのだ。
むろん、妄想である。
しかし、わたしたちの現実には、これが妄想であると断定するための手がかりがない。
わたしのほかの人間が、魂をもたない自動人形かもしれないという推理を、論駁することは不可能だ。
他者は、魂をもっている「ふり」をしているだけかもしれない、という疑いは、どんな理論によっても晴らすことができない。
だから、わたしの他者の存在の信じかたは、直感的だ。
わたしには、他者は、論理的な思考によっては感じられない。
わたしが他者の実在を信じられるのは、誰かを抱きしめたり、会話をたのしんだり、いつか誰かとそうしたことを、思い出しているときだけだ。
だからわたしが遭遇した、あの霧の交差点の情景は、わたしのなかの他者の実在の確信をうしなわせた。
(むろん、いまは回復している)
こうしたヴァイブスは、遍在している。
都会でも田舎でも、人がいようといなかろうと、ある魂がほかの魂をもとめて満たされないとき、わたしたちはそれを感じる。
このヴァイブスはアンニュイで、メランコリックで、エモーショナルだ。
半径数キロメートルにだれもいない、山奥の小屋で、冬ごもりをしながらこれを書いていると、ますますそんな気分になる。
とても単純なゲームプレイなのに、ビデオゲームの魔法がかかっている
あなたは猫で、配達屋だ。かわいい軽トラを所持している。あなたはそれに乗り、荷物を配達する。
配達があなたの仕事だとわかるためには、他者の助けがいる。
犬が、雪に閉ざされた町のなかでたき火をしながら、あるメロディーをハミングしている。
彼はあなたに仕事のやり方を教え、ぼくの山小屋にあたたかいコーヒーを飲みにおいで、と言う。ただ、山小屋へつづくトンネルが落木で閉ざされているので、軽トラをはしらせるには、燃やしてしまうほかないだろう。
あなたはライターの代金30ドルをもとめて、配達の仕事をする。業務を発注してくれるのは、地元の商店の、店主の猫たちである。
彼らはあなたに荷物を預けながら、びっくりしたように言う。
「きみは、セブにそっくりだね。まえの配達員さ。いなくなっちゃったのだけれど。元気にしているかな。」
とうぜん、あなたはセブのことを知らない。
あなたは荷物を積み込み、軽トラを走らせ、指定された位置まで荷物を届ける。町と町のあいだは離れていて、ふつうに道を行けば、現実時間で三分くらいかかる。
エナドリやコーヒーを飲み、軽トラの燃料を補給しながら、ラジオから流れるかすれた音楽に耳を傾ける。しばらくやれば、こつはつかめる……。
とても単純なゲームプレイなのに、ビデオゲームの魔法がかかっている。
この魔法は、言葉にすると消えてしまう。初代プレステのようなローポリがいい。ほかにドライバーの姿を見かけない。すべてが雪と雲にとざされて太陽がない。
荷物を落としたり、崖から転落しても、ビデオゲーム的な都合で、車道のうえにリスポンする。
肩肘を張る必要がない。とてもイージーだ。
そういえば、すべての地元の商店の名前には、Easyの名がついている。イージーマート、イージーオート、イージーカフェ……。もちろんこのゲームの名前であり、あなたの仕事の内容も、イージーなデリバリーだ。
鳥たちがあなたを見ている、日が暮れたり風が吹いたりする。コーヒーを飲もうと招いてくれた犬の山小屋に行くと、このあたりは積雪がひどいから、スタッドレスにするといいと言う。それを履いたら、ふもとの漁村まで来てくれとも。
あなたは100ドルをがんばって稼ぎ、あたらしいタイヤを履く。
店主の猫たちは、それぞれの店から出ようとしない。だが、すべての町の、それぞれのチェーン店に偏在する。イージーベーカリーの店員はあの猫、イージー燃料の店員はこの猫……。
彼らは外に出ているようすもないのに、どうしていつもおなじチェーン店の、別の建物にいるのだろう……コンビニの店員さんが、みんなおなじひとで、北海道にも沖縄にもいたような感じで……。
まあ、ゲームだから、そういうものか。
彼らはNPCだ。
だが、だからこそ、存在しようとしている。
かすれたラジオからえんえんと、おなじ音楽が流れている。
漁村を封鎖する鋼鉄の隔壁の前で、犬があなたに語る。
かつて、この漁村はとても栄えていた。だが、企業が──イージーの名を冠したすべてのものを経営するコングロマリットが──ここに来てから、住民たちはしだいにこの村を捨てた。その時期になにがあったのかを探るために、湖の果てにあるダムのコントロール・センターに潜入してほしい。
「ところできみは、ほんとうに」と彼は言う。「セブに、よく似ているね。」
「無言の主人公」であるあなたは、フェンスを破壊するためのバンパーを配達の仕事で手に入れ、うらぶれた山裾の寒村にふさわしくない、巨大なダムの建物へ潜入する。
とても高くて遠いところにかかった、霧のなかの線路を、荷物を満載した貨物列車が走っていく……。
捨象、抽象、Abstract
ちょっと、まわりくどい話をする。
捨象、という言葉についてだ。
しゃしょう、と読む。
この言葉は、近代化のあと、明治期に、英語からむりやり作られた。
その語源をたどってみよう。
捨象は、英語で、Abstractという。
Abstractから、接頭辞Ab-を抜いて語幹を残すと、Tract(ひく、ひっぱる)になる。
Tractという単語には、いろんな接頭辞がつく。
At-(のほうへ)tructでAttract(惹く)。
日本語でも「ひかれる」という。おもしろい。
Con-(共に)tructでContract(契約)。
仕事の契約をするとき、「ひきあいがあった」という感じだ。
Ex-(外に)tructでExtract(抽出する)。
「ひきだす」だ。ものをいれる引き出しは、古くは「抽斗」と書いた。
では、Ab-(離れる)にTractを足すと、「捨象」になるのは、なぜか。
自然の現象世界から、ある一部を抽きだし、ほかは捨てることをいうからだ。
「抽く」ことを強調したいときは、「抽象」という。「捨てる」ことを強調したいときは、「捨象」という。
どちらも、Abstractの訳語だ。
「抽象画」は、ごぞんじだろう。
あれは、Abstract Artという。
ためしに、「抽象画」を「捨象画」と呼んでみよう。
ちがうものに見えてくるはずだ。
*
さて。
あらゆる芸術は、自ずから捨象する。
ビデオゲームも、例外ではない。
たとえば、マリオはものすごく高くジャンプできる。
その理由は、説明されない。
また、されなくてもかまわないと、わたしたちは無意識に思っている。
なぜなら、彼がとても高くジャンプできることも、その理由も、捨象されているからだ。
わたしたちはその捨象を、「ビデオゲームだから、そういうものだろう」と、無意識に思う。
イェスパー・ユールという研究者が、ふと気になって、「どうしてマリオはとても高くジャンプできるのでしょう」と、友人たちに聞いてみたことがある。(これは『ハーフリアル』という本に書いてある話だ)
ほとんどの人が、そんなことは考えてもみなかった、と前置きしてから、
「これは、ゲームだからな」
と説明した。
「そういうものだろ、ゲームって」
よく考えてみれば、ただの配管工があんなに高くジャンプできることは、おかしい。
だけど、わたしたちはその表現を、「そういうものだ」と見ている。
ある表現を「そういうものだ」と見ること。
これが、捨象を受け入れることだ。
すると、人類が現実を描写したものは、すべて捨象されていることがわかる。
たとえば、いらすと屋さんの画に描かれる人間は、二頭身で描かれる。おまわりさんも、パン屋さんもだ。
しかし現実の人間の大半をしめる大人は、まあ、だいたい七頭身くらいだ。
なのに、わたしたちは二頭身のおまわりさんの絵をみて、「これは人間のおまわりさんだ」と思う。
大人の人間がだいたい七頭身であるという現実から、べつに二頭身であってもいいか、と要素を抽出し、七頭身の部分を捨てること。
これがAbstract、「抽象/捨象」だ。
(だからアブストラクションはイチゼロではなく、濃度だ。無限大にアブストラクトされた表象は幾何学の点で、無限小はこの世界そのものだろう)
*
ビデオゲームにおいては、非常にたくさんのものが捨象される。
どんなものが捨象されるかは、作品によってことなる。
犬や猫がしゃべるのはおかしいけれど、「そういうものだ」。犬や猫にしては直立歩行で、首と胴体がつながっていないけれど、「そういうものだ」。この軽トラックはいくら横転しても傷一つつかないが、「そういうものだ」。
だが、エナドリやコーヒーを飲まないと倒れるし、寒いところにいると気絶してしまう。夜になると暗くなるし、気温が下がる。これも「そういうものだ」が、わたしたちの現実とそんなにちがわない。
あるひとは、そのことを、リアリティ(現実味)がある、と表現するだろう。
こたえて言おう。
ビデオゲームのリアリティは、作品の数だけある。
わたしたちがビデオゲームを遊ぶのは、いろんなリアリティをさわって、知りたいからだ。
現実のわたしたちは、壁にさわって、それをすり抜けられないことを知る。
しかし、ビデオゲームにおいては、人間が壁をすり抜けてもかまわない。
『テトリス』のリアリティは、われわれの現実とおなじように、下向きの重量が働いているところだけではなく、横一列を並べたらブロックが消えるところにも、ある。
それはテトリスに固有だが、テトリスのリアリティだ。
「現実では、積み木を横一列に並べても消えないのに、どうしてテトリスにおいては、横一列に並べたらブロックが消えるのだろう。いずれにも、下向きの重力が働いているのに?」
という問いには、
「これはビデオゲームという、べつのリアルだから」としか、答えようがない。
「ビデオゲームだから」に理由をつける
さて、回り道が長くなった。『Easy Delivery Co.』に戻ろう。
この作品のすばらしいところは、「ビデオゲームだから」という理由で、ふだんみんなが納得してくれるすべての捨象に、しっかりと、作品世界内で設定をつけていることだ。
これは、夜道で背後から刺されかねないレベルのネタバレだから、捨象しつつ話す。たとえて言えば、「どうしてマリオはあんなに高くジャンプできるの?」という問いに、ちゃんと答えている。
しかも、そのやり方が物語的で、とてもエレガントなのだ。
「どうしてすべては、ほかのどのようでもなく、こんなふうになっているのか?」
のんびりと配達をこなしながら、さまざまなキャラクターたちと話をしていくうちに、徐々に、ゆっくりと、この根源的な問いへの答えが、明らかになっていく。
キャラクターのダイアローグだけではない。木々や、雪道や、配達という行為や、配達される物や、吹雪の空のなかで寂しげな赤い航空障害灯をともしているラジオ塔、凍りついた湖、空、大地、イージー関連のチェーン店が、語っているのだ。
プレイしているうちに、だんだんと、その声が聞こえてくる。
すべては、はじめからそこにあり、ずっとその答えを語り続けていたのだ。
この作品においては、すべてが問いへの答えなのだ。
わたしは西田幾多郎を思い出した──
「物が汝の呼声となるのである、物が我々に呼びかけることによって私は汝を知り汝は私を知るのである」
(『汝と私』という作品のことばだ)
余話だけれど、「諦める」は、「明らめる」だ。
わたしたちがなにかを「諦める」ということは、そのうえでなお、なにができるのかを「明らかにする」ことだ。
キリスト教徒の天国のイメージは、まったき光だという。
わたしたちは、死ぬとき、すべてを「諦める」。
そこでは、すべてが「明らか」になっている。
だとしたら、『Easy Delivery Co.』は──天国みたいに明らかな作品だ。
(それにしても、わたしたちの現実は、いったいなにから捨象されたのだろうか。そもそもこれは、なにかから捨象されたものなのだろうか……。)