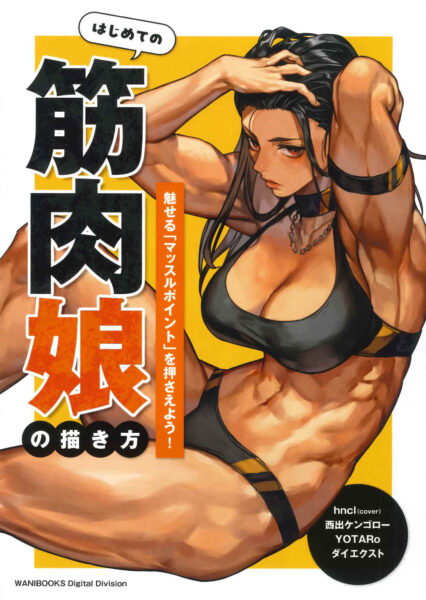7月16日、ゲーム内の表現や事象を専門家と共に探求する「ゲームさんぽ/よそ見」にて、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の建築物を解説する動画シリーズの第2回「【隈研吾/伊東豊雄/永山祐子】スター建築家たちのパビリオンはそれぞれどこが凄いのか|万博建築#02」が公開された。
動画では、建築史家の倉方俊輔氏が前回から引き続き出演。隈研吾氏、伊東豊雄氏、永山祐子氏といった“スター建築家”たちが手がけたパビリオンの「凄さ」について、専門的な視点から深く掘り下げている。「ゲームさんぽ/よそ見」の公式YouTubeチャンネルおよびニコニコ動画で視聴可能だ。
今回の動画は、大阪・関西万博に点在する各国のパビリオンやシグネチャーパビリオンを、建築という切り口で巡る内容だ。単なるデザインの美しさだけでなく、その建築が持つ歴史的・文化的背景や、建築家の批評的なメッセージ性、さらにはコストや工期といった現実的な側面まで含めて、それぞれの建築の多面的な価値を解き明かしていく。
(画像はYouTubeより)

動画ではまず、大阪・関西万博で4つのパビリオンを手がける隈研吾氏の建築について解説された。マレーシア館の竹を用いたデザインや、ポルトガル館のロープを垂らした大胆な外観などを例に挙げ、倉方氏は隈氏の建築の本質を「早く理解できて、安い素材で、映える」と分析する。
一見すると批判的にも聞こえるが、その「割り切り」や、あえて構造の裏側を見せるような「誠実さ」あるいは「図太さ」こそが、隈氏の建築家としての批評性であり、歴史に残る所以だと論じている。


動画の中ではほかにも、1970年の「太陽の塔」へのオマージュとして設計され、規制を想像力で超えようとする伊東豊雄氏のパビリオンや、ドバイ万博から部材をリユースしてサステナビリティの新たな可能性を示した永山祐子氏の建築など、大阪・関西万博を多角的に楽しむための様々な視点が語られている。