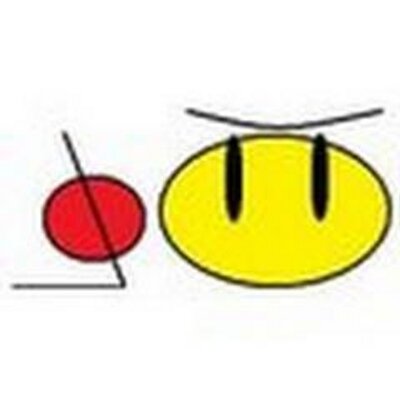『ポケモンGO』開発者の思想を考える
──そろそろ『母性のディストピア』の議論に戻ると、この本は最後の方で、まさにその『ポケモンGO』【※】についてかなり本格的に論じられていますよね。

(画像はApp Storeより)
宇野氏:
『ポケモンGO』って正直に言って、ゲームとしてはつまらないんだよね。『Ingress』も、僕は始めてから2ヶ月で散歩の習慣ができたら、単に自分の興味で街中を散歩する方が面白くなってやめてしまった。
でも、そこを批判することには、何の意味もないと思う。
 |
だって、別にあれって「彼氏と一緒にピカチュウ捕まえに代々木公園に行きました」みたいな「自分の物語」を楽しむことこそがメインであって、ピカチュウを捕まえるというゲームそのものの面白さなんて、どうでもいいからね。むしろ、単純であればあるほどいいんだよ。
で、これは実は『Ingress』の思想でもある。だって開発者であるジョン・ハンケは結局のところ、「人間が外の世界の豊かさに気づきさえすれば、それでいいんだ」と言ってるからね。
──それ、凄い割り切りですよね。ちなみにジョン・ハンケさんって、宇野さんの中ではどういう人なんですか?
宇野氏:
インタビューを読む限り、かなり正統にニューエイジ的なヒッピー文化を引き継いでいる人だと思う。
基本的に、ハンケは世界は美しくて豊かなものであると思っていて、でも人間はその歴史情報や自然情報の豊かさを、自然状態では受け止めることができないんだと思っているんだよね。
そこで彼が考えたのは、Googleが世界を情報化して歩きやすくしてあげて、人間と世界の距離を縮めてあげるということだった。

(画像はAmazonより)
そしてハンケはGoogleマップの担当者として、その後ゲーミフィケーション【※】を取り込んで『Ingress』を作っていくことになる。
要はハンケにとっては、「人間を外に連れ出して散歩させて、世界の豊かさに気づかせたい」というのが本質で、その口実として「ゲーム」というものが使われているだけなんだよ。
だから『Ingress』の日本人スタッフにインタビューしたときにも、「2ヶ月で散歩の方が面白くなった」と言ったら、「それでいいんですよ」という話になっちゃったんだよね。
※ゲーミフィケーション
ゲームデザインの技術やメカニズムをはじめとするゲームの考え方や動機づけの方法論を、ゲーム以外の領域に利用すること。顧客ロイヤリティの向上から企業の組織マネジメント、フィットネスまでその応用分野は多岐にわたる。
──彼からすれば、リアルの豊かさを楽しむ能力を身につけたのなら、もうこのゲームはクリアしてしまったようなもんだよね……という感じでしょうか。
宇野氏:
いずれにせよジョン・ハンケは今、確実に世界最強のゲーム作家の一人だよ。
「政治と文学」を結ぶ物語装置としての劇映画が崩壊していくなか、もう個人が結ばれるべき世界というのは、国家からマーケットに取って代わってしまい、その二つを結ぶ回路として今や「他人の物語」よりも、「自分の物語」の演出としてゲームを用いることの方が上手くいっている。古くから「政治と文学」と言われてきた比喩が、「市場とゲーム」に置き換わっていると僕はずっと主張してきたけど、ジョン・ハンケはそのことを、あまりにも鮮やかに象徴していると思う。
なぜ今、黎明期のオタク文化に着目するのか
──ただ、ちょっといくつか疑問を差し挟んでもいいですか? まず、正直なところ人間が完全に「自分の物語」に耽溺していくとは思えなくて……実際、莫大な売上を上げるAAAタイトルがストーリー性を高めていたり、ピクサーのような映画が世界的に大人気だったりするわけじゃないですか。
宇野氏:
それでも、この二十年で「自分の物語」の側にずいぶんとパワーバランスが傾いたのは明白でしょう?
そりゃあまだ大きな勢力は保っているよ。だけれど相対的には「他人の物語」の側は衰退し、「自分の物語」の側が拡大している。
 |
昔から、この「自分の物語」と「他人の物語」のバランスは変化し続けていて、今はその転換期なんだと思う。ただ、ここから21世紀のかなり長い時間、「自分の物語」の方へと文化の重心が傾いていくのは間違いないんじゃないかな。そもそもツールの発達で生産力が上昇して、生活の自由度が上がって自己決定力も上昇すれば、そりゃ「自分の物語」が優位になっていくのは、当然の流れだと思うしね。
そして──僕は別にそれでいいと思ってる。だってハンケの思想にしたって、代々木公園にピカチュウを取りに行くことによって、偶然性に導かれて他人の物語にぶつかる可能性を引き上げることができる、という言い方も出来るわけじゃない。
──確かに、そうですね。プレイヤーが「自分の物語」を追求する結果として、他者に出会えたら、それでいいじゃないかという話ではありますね。
宇野氏:
そういう意味では、この『母性のディストピア』という本も、僕みたいな「他人の物語」にどっぷり浸かってきた人間が、現代の「自分の物語」優位の時代にそのノウハウを今後どう応用したらいいかを意識しながら書いた本なんだよ。
──ただ、個人的にはある種の淡泊なつまらなさや危険性も、『Ingress』や『ポケモンGO』のような娯楽には感じていて……というのはプラットフォームで個人が世界に直に接続するというのは、ある種「政治性の欠落」が起きた世界でもあると思うんですよ。別に『Ingress』のプレイヤーがサリンを撒くかもしれない、とかそういう話をしたいわけじゃないんですが(笑)、こういう場所から富野さんのような才能が登場することってあるのかな………と。
宇野氏:
それ、暗に富野がサリンを撒くような人間だと言ってると思うんだけど(笑)。
もちろん、ほとんどの人間の考えることや生活は凡庸なので、ネットワークに吐き出される「自分の物語」もまた凡庸だよ。FacebookやTwitterに吐き出される人々の「意見」にほぼ価値がないのと同じようにね。ただ、彼ら自身はそう思っていないし、思えるわけがない。
ただ、ジョン・ハンケはそれでいいのだと開き直っていると思う。グローバルに何十億人を対象にそれを仕掛ければ、確率の問題として何百万人に1人の凡庸ならざる「自分の物語」を引き出すことも、それを一瞬で世界中にシェアすることもGoogleには可能だと思っているだろうからね。
でも僕の考えは少し違っていて、やはり「自分の物語」を求めて遊んでいるうちに事故的に「他人の物語」に出会えるような仕掛けにしておくほうが面白いと思う。だからこうやって「他人の物語」の時代の遺産のうち、何が有効かを検証する仕事に人生を費やしているわけだけどね。
あとはまあ、そういう意味ではまさに「政治的な成熟」が、今のシリコンバレー企業が拠ってるカリフォルニアン・イデオロギーには欠けてるんだと思うよ。その問題は、もうフェイクニュースなど色々な形で噴出しているよね。

(画像はUber公式サイトより)
ただ、さっきの富野の話のときに「ニュータイプ」という発想が、実は革命への挫折の中で生まれたニューエイジ的なものと、同時並行的に登場した概念だったという話をしたじゃない。やがてコンピューターカルチャーというものが世界を大きく変えていき、市場が国家に匹敵する巨大な存在として我々の生活を規定していく予感は、あのとき先進国の若者層にはあったはずなんだよ。
それがアメリカにおけるギークで、日本ではオタクだったんだと僕は思ってる。
──カルフォルニアン・イデオロギーと日本のオタク文化は、異なる場所で産まれた「双子」のような存在だった……という感じでしょうか。確かに『母性のディストピア』の最後の方を読んで、黎明期のオタク文化に可能性を見いだしている印象はありましたが。
宇野氏:
おそらく、この日本の「失われた30年」で一番可能性があった政治的主体は、あの頃のオタク──具体的には「新保守派」なんて言われていた頃の、リアルポリティクス系の言論を発していた時代の彼らだったんじゃないかと思うんですよ。
──読者に補足すると、本の中では『シン・ゴジラ』に登場した官僚たちの姿に、宇野さんはその「実現しなかった理想」を見てましたよね。
宇野氏:
まあ、『シン・ゴジラ』での庵野さんの描き方自体が、かなりアイロニカルなものなんだけどね。
当時のオタクが持っていた「新保守」の倫理というのは、世界をイデオロギッシュな「物語」としてではなく、ある意味で技術主義的に世界を「情報の束」として見るものだったんですよ。

(画像は『シン・ゴジラ』予告より)
だから、過剰に専門化する行政にも、イデオロギー的な政党政治にも正しく距離を置くべきだし、しょせんは政治なんて「手段」でしかない以上、「是々非々」で正しくコントロールしていけばいいと割り切れた。当時、冷戦が崩壊した中でそういう意識は知識人の態度として正当である、というコンセンサスがあったんだよ。そこには 「総合知識人としてのオタク像」みたいなものが、確かにあったと思う。
──この本で面白いのは、そういう政治に対してクールに向き合う主体が日本で育った背景には、実は70年代後半から80年代前半くらいにでてきた「月刊Newtype」をはじめとする当時のアニメ雑誌やゲーム雑誌があったんじゃないか、と書いていることですね。

(角川日本文化図書資料館 蔵)
SF・模型・特撮・パソコン・TRPGなどを縦横無尽に横断していく雑食性と総合性を兼ね揃えた当時の新しいサブカルチャーには、そういう情報論的な教養体系の萌芽のようなものがあったのではないか、と。そして富野さんが「ニュータイプ」という概念をポジティブなものとしてアニメファンに提示した頃、当時の彼の目に映ったファンたちは、そんな新しい人間たちの姿だったんじゃないか……と。
宇野氏:
でもニュータイプは残念ながら「失敗したカリフォルニアン・イデオロギー」になり、富野由悠季も結局はニューエイジ的な「虚構の時代」の精神から離陸できなかった。
それに、この本の最後で『シン・ゴジラ』をかなりの分量で論じたけど、特撮みたいな技術へのフェティッシュに規定されるオタクというのは諸刃の剣でもある。『風立ちぬ』の堀越二郎のようなもので、イデオロギーへの警戒心にも繋がる一方で、それは政治的な無垢さにも繋がっていた。
 |
実際、その後この世代のオタクたちこそが、ネトウヨの温床になっていった歴史もあるわけじゃない? 僕はその零落の歴史を思春期と同時に見てきているから、それが生半可なことじゃないことは分かってる。
だけど、カリフォルニアン・イデオロギーが現代の世界を覆っていく中で、今の情報環境における理想的な主体を、富野が「ニュータイプ」に見た理想を更新することで考えることができるんじゃないか……そんな風に思うんだよ。要するにイデオロギーに対して無免疫な技術主義から免疫をもった批判的技術主義の可能性を、当時のオタク文化の一部の再評価から考えたい、というわけ。
戦後サブカルチャーのゆくえ
──なるほど。冒頭で語られたような70年代後半~80年代にかけてのサブカルチャーを、いま語る政治的な意味というのが、かなり見えてきた気がします。では、ここで議論の方向性を変えて、コンテンツという面ではどうでしょうか。今後の日本の戦後サブカルチャーについては、どう思っていますか?
宇野氏:
ちょうどこの本を書いてる途中に『シン・ゴジラ』【※1】と『君の名は。』【※2】が上映されて、「ああ、もう戦後的なサブカルチャーは本当に終わるんだな」と思ったんだよね。

※2 君の名は。……2016年公開のアニメ映画。新海誠監督の第6作目にあたる。都心に暮らす男子高校生・瀧と岐阜県の田舎町に暮らす三葉の二人の身体が、ある日突然入れ替わるという物語。公開から間もなく爆発的な動員が見られ、邦画としては『千と千尋の神隠し』(2001年)に次ぎ2作目となる興行収入200億円を突破する、歴史的な大ヒットとなった。日本だけでなく、中国をはじめとするアジア圏でも空前の人気を誇り、世界125の国・地域での公開が決定している。画像は『新海誠監督作品 君の名は。公式ビジュアルガイド』書影。
(画像はそれぞれAmazonより)
──確かに、あの二つには新しいサブカルチャーの胎動を感じた人が多いと思うんです。
ただ、少し個人的な話をしてしまうと……一つ気になったのは、あの二つの作品が海外に出たときに、全く違う評価を浴びてしまったことなんですよ。一言で言えば、『君の名は。』は色んな国で大ヒットした一方で、『シン・ゴジラ』は決して比較して好い興行成績とは言えなかったじゃないですか。
宇野氏:
なるほどね。
──その理由は、震災以降の日本という国への「距離感」だったと思うんです。『シン・ゴジラ』が海外でパッとしなかったのは、厳しい言い方をすれば「日本がいかに二流国になったか」という現実を徹底的なリアリズムで描いた結果、普通の先進国では「なんで行政機関がこんなグダグダの行動を取ってるんだ?」と鼻白まれてしまったからだと思うんです。

(画像は『シン・ゴジラ』予告より)
一方で『君の名は。』は、まさにこの本が鋭く指摘しているように、3.11を意識している内容なのに、集落ごと破滅させる隕石の光景を見て、良くも悪くも主人公と一緒にその美しさにうっとりするような作品だった。
こういう状況って、今後あらゆるジャンルのコンテンツで起きていく未来だと思いませんか? 今の日本という国の文脈に付き合うことが、もはやあまりグローバリゼーション下では世界にとって大事な意味を持たなくなっていくんだな……というのが実感された出来事でした。
宇野氏:
まあ実際、『シン・ゴジラ』って、ここ20~30年の日本政治のグダグダに対するアイロニーが分からないと、まったく面白くない映画だと思うよ。そして、僕は『シン・ゴジラ』の方が圧倒的に好きだけど、今後『君の名は。』のような作品が台頭していく世界になっていくのも仕方ないと思っている。
でもそこにかつて僕が愛したものの遺伝子が残っていて、面白いものがあればいいなとは思う。
──ただ、もう決して遠くない未来に、日本のコンテンツ産業が内需だけで今の規模を維持するのが立ちゆかなくなりだすのも見えているじゃないですか。
ニーア、ペルソナ等の人気ゲーム開発者が激論! 国内ゲーム産業を支える40代クリエイターの苦悩とは【SIE外山圭一郎×アトラス橋野桂×スクエニ藤澤仁×ヨコオタロウ】
※日本のゲームクリエイター4名を招いた上記の座談会では、まさに日本のゲーム業界が世界市場でポジションを失っていった経緯などにも触れられている。
実際、大型ゲームではとうの昔にそれは起きていて。00年代に本格的なグローバル市場がゲームに登場したとき、日本のゲーム業界はほとんど対応できずに世界市場でポジションを失った経緯があって……Netflix【※】みたいなグローバルプラットフォームにアニメが乗っていくことは、同様の事態が他のジャンルでもどんどん生じる始まりのようにも思うんです。
※Netflix
米オンライン動画配信サービスの最大手。1997年にオンラインDVDレンタルサービスとして創業。2007年に2012年にかけてレンタルサービスを廃止し、ストリーミング配信に一本化。やがて既存作品だけでなく、オリジナルコンテンツの制作・配信にも乗り出し、大ヒットタイトルを量産している。全世界のユーザー数は1億人を超える(2017年12月現在)。
宇野氏:
それでいいんじゃない? 文化なんて、そういう形で発展していけばいいと思う。僕も今後、確かにNetflixのようなプラットフォームに日本のアニメが「荒らされてしまう」状況はあると思うよ。
でもさ、日本が生んだアニメーションに影響を受けたインドネシアとかの作家なんかが変なものをつくって、それが今後の世界を結果的に面白くしていけばいいんじゃないかな。
──まあ、それもそうなんですけども(笑)。
宇野氏:
正直なところ、僕自身はグローバリゼーションで日本が沈んでいくことなんて、本音では結構どうでもいいと思ってるから。
だってグローバル競争で格差が広がってるのは先進国の内部だけであって、国際格差でいえば急速に縮まってて、この間まで汚い水を飲んで死んでたような地域の人たちの生活がドンドン向上しているわけでしょ。そんなの、圧倒的に「正義」であるに決まってるじゃない(笑)。
※上記の動画は、グローバリズムによって世界は「フラット」になりつつあるという事実を、ヴィジュアライズされた人口の推移データを用いて説明し話題を呼んだもの。20世紀以降、国家間の経済格差、平均寿命の格差は小さくなる方向に向かっていると説明している。
そうね……ただ、IPが作れなくなるときって「一瞬」だったりはするみたいだね。
例えば、香港なんて昔はIPを作れたけど、もう作れなくなっている国なんだよ。カンフー映画もジャンルとしては崩壊してしまって、かつて映画をあれだけアイデンティティにしていた国が、今は本当に金融しかないエコノミックアニマル都市になってしまった。そのことは、やはり一部の香港人にとって忸怩たるものがあると聞いたことがある。
──その意味では面白い話があって……今なお欧米のゲームクリエイターで日本人にリスペクトを払う人は多いようです。というのは、やはり日本のゲームには圧倒的にオリジナリティがあるからだと言うんですね。
しかも、こういうのはゲームに限った話ではありません。海外のコンテンツ企業と話をすると、とにかく日本人のIP創出能力の高さはうらやましがられます。実はIPを生み出せる人材が出てくる国家って、欧米の一部の国と日本くらいで、非常に希有な土壌だと言われたこともあります。

(画像はGoogleより)
そういう中で最近、戦後の日本が発揮したこういうクリエイティビティの条件って何だったのだろう……と考え込むことが多くて、実はそれが今日の取材を『母性のディストピア』の筆者にしてみたかった理由でもあるんです。
宇野氏:
それは大塚英志が論じてきたような、とても大きなスケールの問題だと思うから難しいよね。
もちろんクレバーな回答をするんだったら、ベビーブームがあって、戦後中流階級が生まれたから……みたいな解説は普通にできる。
やっぱり戦後日本の繁栄の中で分厚い中間層が登場したことは大きいよね。
日本はホリエモンとフリーターが同じマンガを読んでいるような特殊な国で、それによって小さい子どもからティーンエイジャー、ひいては大人まで文化的なものに触れる機会が非常に多くて、こういう独自の文化が発展した面はあると思う。
ただ、やはりコンテンツやIPの話となると、こういう戦後中流文化の文脈だけでは語り切れない部分が出てくるのは事実だよね。
──それこそ「憲法九条」に始まる戦後日本の特殊な環境が、彼らのクリエイティビティを生み出した経緯というのはあるんじゃないでしょうか。実際、日本の戦後の製造業の発展なんかも、そもそも他国なら軍需産業に行くような水準の頭脳が、憲法九条があったことで、民間で大活躍したことにあったりしたわけじゃないですか。
宇野氏:
普通は軍需産業に行くはずの優秀な人間が民間に出て行ったことで、軍事兵器の代替物として選ばれたのがハード面では「自動車」で、ソフト面では疑似戦争としての「虚構」だった……というのは言えるかもしれない。
実際、加藤典洋【※】や大塚英志っぽい話をすると、日本が現実で戦争せずにバーチャルの世界で戦争し続けていたのは、そうだよね。そこに何かしらの必要があった結果、一種の副産物としてこういう文化が生まれた側面はあるのかもしれないね。

(画像はAmazonより)
村上春樹よりも、日本文学史的に正統な作家たち
──その辺の話を考えていくと、冒頭の話に戻るようですが、この三人のような作家を生み出した背景とは何だったのかを、最後に聞いておきたいんです。
宇野氏:
そもそも、僕はあの三人は村上春樹【※1】なんかよりずっと正統に、日本文学の作家だと思ってるんですよ。
実際、かつて戦後アニメーションという歪なジャンルが、この戦後日本の中で最も射程の長い表現であることを確信していたオタクたちがいて、彼らが『新世紀エヴァンゲリオン』【※2】以前から注目していたのは、やはり高畑勲とこの三人だった。

(画像はNHKアニメワールドより)
この辺は、それまでアマチュアのアニメシーンから出てきた天才アニメーターが好きにやってたイメージの庵野秀明【※3】が『エヴァ』以降、「あ、これは宮崎、富野、押井に続く巨匠の候補なんだ」となった理由でもある。その辺は、同時代の人間にしか分からない感覚かもしれないけれども……。

(Image by Dick Thomas Johnson . Licensed under the terms of cc-by-2.0.)
※1 村上春樹
1949年生まれの作家。1979年に『風の歌を聴け』(講談社)でデビューし、群像新人文学賞を受賞。1987年に上梓された『ノルウェイの森』(講談社)は、累計1000万部を越すベストセラーとなり、一世を風靡する。その後も精力的に執筆を続け、現在も国内外ともに大きな影響力をもつ作家である。代表作は『ねじまき鳥クロニクル』(新潮社/1994〜1995年)、『1Q84』(新潮社/2009〜2010年)など。翻訳家としても知られ、海外文学の邦訳も多数。近著は『騎士団長殺し』(新潮社/2017)。
──ちなみに、どういう部分であの三人を日本文学の正統な嫡子だと思うのですか?
宇野氏:
端的に言えば、彼らは近代以降の、日本人男性の自意識の問題を極めて直接的に扱ってきた作家なんですよ。
そもそも、日本という近代化がなされてない国において、日本人というのは成熟した西洋近代的な個や市民への心理的成熟が困難であるという問題が、ずっとあったでしょ。しかも戦後日本となると、サンフランシスコ体制のような問題もあって、ますます自立した個として振る舞うのが難しい国になっていく。
当時の日本というのは、世界史的にも異常な「飼い殺し国家」として、経済的に発展していくという状況になってしまったわけじゃない。
──戦前であれば『こころ』の夏目漱石だし、戦後であれば『金閣寺』の三島由紀夫に、『飼育』の大江健三郎に……という感じで、まあ高校の現代国語の授業で教わるような大作家たちが、既にそうですね。男性的な実存が上手く保てない苦悩を、延々と日本社会の未成熟の問題に結びつけて書いてるというか……。
夏目漱石の『こころ』は1914年、三島由紀夫の『金閣寺』は1956年、大江健三郎の『飼育』は1958年に発表された。書影は左から2013年オリオンブックス刊のKindle版、2003年新潮社刊の文庫版、1959年新潮社刊の文庫版のもの
(画像はそれぞれAmazonより)
宇野氏:
そうした時に、日本の男性インテリたちは「さも近代化できてるかのように」演じてきたのだけど、常にそのコストを女性に依存してしまうという問題があり続けてきたんですよ。
その典型は、文学者の江藤淳【※】だよね。有名な話だけど、彼は外ではさも西洋近代化された市民であるかのように振る舞って文章を書きながら、家庭では奥さんを殴りつけていた。
村上春樹の作品も、それは一緒だよ。『ねじまき鳥クロニクル』に象徴されるように、ポストモダン的な価値の宙吊りから抜け出すための正義を実行するコストを、自分ではなくて奥さんに背負わせていく。

(画像はそれぞれAmazonより)
こういう自分の不能性に対してのアイロニカルな自覚が、女性への依存モデルとして描かれてきた問題が日本文学史にはあるのだけど、ここで取り上げた三人の作家は見事にその問題を扱ってきた作家たちだと思う。
──その辺は、この『母性のディストピア』という本で存分に論じられている内容ですね。ガンダムであればシャア、宮崎駿さんのアニメであれば『風立ちぬ』の堀越二郎、そしてその構造を裏側から見た作品としての、押井守さんの『ビューティフル・ドリーマー』のラムみたいに、有名なアニメーション作品が日本文学の名作群と通底するテーマでバンバン切れてしまうのは、痛快でした。
宇野氏:
でも、こういう問題は戦後日本社会にも同じ構造としてあるんだよ。だって、そもそも昭和のサラリーマン文化なんて、専業主婦がいなければ成立しないでしょ。
東京で言えば、戦後の都市開発は都心部から西へ西へと発展していった経緯があって、当時の東京のホワイトカラーは田園都市線の沿線なんかに住んで、都心のオフィスに長時間かけて出勤したりして、しかも深夜まで飲み会をして帰宅したりしていた。こんなの、自分の身の周りを奥さんに全て押しつけなければ成立しない生活だよ。
それこそ、シャアみたいなものだよね。外では見栄を張ってるけど、内では妻を母と見なしてその腕の中で甘えているという。
──「ララァは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ!」ですね。この『母性のディストピア』を読むと、まさに三人がその問題に鋭く向き合ってきたことが見えます。もちろん三者三様で、この本の中では宮崎駿さんはある種の「天然」でその構造を描きだして、富野由悠季さんは抗いながら敗北していき、押井守さんはその構造の告発を延々と続けて……という感じでしたが。
宇野氏:
そして、この三人の源流にある高畑勲の仕事というのが、まさに本質的だよね。何度も繰り返すように彼はそんなイミテーションとしての近代を、アニメーションという純度100%の虚構だからこそ描ける自然主義的リアリズムで描く可能性を提示した人なんですよ。
──そう聞くと、高畑勲さんの重要性にも納得がいきますね。ただ、また話を戻してしまうと、こういうふうに文学史的な水準の主題に迫っていく才能が、なぜこの時期に登場してきたのかというのが気になっていて。
宇野氏:
そういうのは量的な問題なので、これから世界中の国がコンテンツを作っていく中で、それこそ一定の確率で才能は登場してくると僕は思うよ……ただ、君が言いたいのは、要はクリストファー・ノーラン【※】は出てくるけど、もしかしたら富野は出てこないんじゃないか、ということだよね?
※クリストファー・ノーラン
1970年生まれの映画監督。21世紀最大の映画作家のひとりとしばしば目されている。イングランドの生まれだが、アメリカ国籍ももつ。長編2作目の『メメント』(2000年)で注目を集め、『バットマン』の新三部作の監督に抜擢。『ダークナイト』(2008年)はシリーズ最大の記録的興行成績を収めた。ほかにも『インセプション』(2010年)、『インターステラー』(2014年)、『ダンケルク』(2017年)といった作品で知られる。
──そうです。
宇野氏:
それについて言えば、押井もそうなのだけど──とりわけ富野由悠季という人間は、新しいジャンルが勃興するドサクサの中で出てきた人間なんだよね。黎明期のアニメの現場にいた連中というのは、実は根っからのアニメーターでも何でもなくて、いわば映画産業が斜陽だから、しかたなくアニメに来たような人たちも多いんだよ。
──でも、それって80年代~90年代のゲーム業界のレジェンドたちが、まさに一緒ですね。取材してみると、驚くほどみんな「本当はゲームなんてやる予定じゃなかった……」という人たちばかりでした。正直なところ、子供の頃からゲームで育った後続のクリエイターたちの方が、よほどゲームへの愛を饒舌に語るし、能力も全方位で高い人たちも多いから、なんだか不思議な気持ちになるんですよ。
 |
宇野氏:
だって、どんなジャンルであれ究極的には新しく勃興する瞬間にしか、富野由悠季のような巨人は現れてこないから。そして、もはやアニメは既に確立されたジャンルである以上、富野がここから再び生まれてくるのは厳しいと思うよ。むろん、この先エンターテイメントがどんどん変わっていって、色んなジャンルが生まれてくる中で、そのジャンルの巨人は出てくると思うけどね。
僕としてはそこに富野のような、ヘンなものを生み出す人間の遺伝子が残っていればいいなと思ってる。
戦後のアニメから持ち帰るべき「遺産」
──巨大な才能というのは、黎明期にしか登場し得ない、と。では、最後に聞きたいのですが、戦後サブカルチャーからコンテンツという意味で、僕たちは具体的に何を持ち帰れるのでしょうか?
宇野氏:
僕としては「映像の世紀」が終わってしまった状況で、もし持ち帰るものがあるとすれば、彼らの示した思想や美学しかないと思う。僕が『母性のディストピア』で書き残したかったのも、まさにそういうことだしね。
例えば、これから先にすべての文化が広義のイベント化していく中で、たとえば僕はアートの大衆化が起きるんじゃないかと思ってる。その中で、戦後サブカルチャーの持っていた思想とか美学って、結構活きてくると思うんだよ。
──それは面白い予測ですね。実際、チームラボ【※】がシリコンバレーや新興国で、20世紀の現代アートの文脈なんてすっ飛ばして、とんでもない人気で引っ張りだこになっている状況なんて、わかりやすくそうですよね。
※チームラボ
2000年に設立された日本のデジタルコンテンツ制作会社。デザイナー、エンジニア、建築家、数学家など、情報の表現のスペシャリストで構成され、数多くの作品やインスタレーションを世に送り出している。上記動画は2014年に発表された『追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点 – Light in Dark』。なおこの作品には、アニメーターの板野一郎が得意とした「板野サーカス」と呼ばれる空間のデフォルメ表現が応用されている。
宇野氏:
そういう意味では、押井守の最近の作品で数少ない傑作が、愛・地球博のパビリオンの『めざめの方舟』【※1】だったのは面白いよね。
あれは、押井守版の『百億の昼と千億の夜』【※2】みたいな感じでさ、パンという人間の顔をしてるけど、明らかに人間じゃない神のような存在がいて、その横に竹谷隆之【※3】がつくった顔が鳥や獣になっている像がずらーっと並んでいる。そこに押井守の考える、チームラボみたいな感じの自然のインスタレーションが大きなパビリオンに存在している。

(画像は「愛・地球博」公式サイト内、『めざめの方舟』制作発表のプレスリリースより)
※2 百億の昼と千億の夜
光瀬龍が1965年〜1966年にかけて『S-Fマガジン』(早川書房刊)で発表したSF小説。阿修羅王、イエス、釈迦、プラトンなどが時空を超えた戦いを繰り広げ、そのスケールの大きさからしばしば日本SF史上の傑作とされる。萩尾望都による同名の漫画化作品(秋田書店、1977年〜1978年)も有名。2010年に発売された新装版では、押井守が解説を寄せている。
※3 竹谷隆之
1963年生まれのフィギュア造形作家。1980年代後半からキャリアをスタートし、雨宮慶太監督作品の造形美術を数多く担当。特にメカやクリーチャーといった主題を得意とし、国内外で精密な造形と独創的なデザインが評価されている。庵野秀明とも関係が深く、2012年公開の『巨神兵東京に現わる』では巨神兵の造型を、『シン・ゴジラ』(2017年)ではキャラクターデザインを担当した。
──行ってなかったですが、それは面白そうですね。
宇野氏:
実は押井守が「ネットワークの世紀」の物語を描こうとしたとき、どうも彼は自分の身体が浸食される感覚の「面白さ」を描こうとしていたように思うんだよ。
「他人の物語」に感情移入するのは、あくまでも理性的な精神を通じた感情の操作でしかない。でも、なにがしかの媒介を通さずに、直接にAとBの身体が繋がってしまったとき、人間の身体はまったく別ものになってしまう。どうも、その感覚を当時の押井は面白がっていた気がする。
でも、それってある種『ポケモンGO』でハンケが目指した、「自分の物語」を欲望として追求したときに、偶然に「他者」と出会って身体が浸食されていくような体験に似ている気がするんだよね。とすれば実は押井守がかつて描こうとしていたことは、むしろ今の時代の方が分かりやすいんじゃないか。
あの作品が示唆していたのは今後、そんな風に戦後アニメーションが培ってきた様々な美学や思想というものが別の形で活きてくるんじゃないか……という予感だったように思う。
──それは結構楽しみな未来ですし、むしろ身体を用いたリアル連動型のゲームなんかにこそ、彼らの二次元で表現してきた思想や美学が活かされそうで、ワクワクします。では、そろそろキリがいいところですので、最後に今後の活動の予定を教えてもらえますでしょうか。
宇野氏:
今後……いきなり話は変わるけど、実は『観光しない京都』というタイトルの京都本を考えてる(笑)。
──一気に話が変わりました(笑)。
宇野氏:
というのも僕は学生時代から社会人の最初の期間までを京都で過ごしていて、今も大学の講義で京都には春学期に隔週で通ってる。そこで知った「単に過ごすだけの町」としての京都の面白さを、描きたいんですよ。何人か京都に詳しい人を誘って、フォトエッセイみたいな感じで書きたいなと思ってて、できれば表紙は横山由依ちゃんにしたい(笑)。もうしばらくは、眉間に皺が寄ったようなものを書きたくないんだよね。
──でも、これだけガッツリとしたものを出したあとだと、さすがにそうですよね。
宇野氏:
ただ、これはあながち適当に言ってるわけでもなくて、今日、押井守やジョン・ハンケについて話したことでもある。
どうしても批評言語って「〜〜ではない」という話になっちゃうのね。だから、『観光しない京都』はタイトルこそ「〜〜しない」というものだけど、中身を絶対に「〜〜である」というものにしようと思ってて。
「こうすると面白い」、「こうした方が楽しい」とかを、バンバンこう書いていって、切断的なものではなく、接続的な言語でものを伝えられないかと思うんだよ。
──その一方で、「小説トリッパー」で新しく批評の連載を始めていますよね。

(画像はAmazonより)
宇野氏:
あっちの方は、コツコツやろうと思ってる。ジョン・ハンケ、猪子寿之、吉本隆明の3人を並べて、『母性のディストピア』で書ききれなかったような、日本人のサブカルチャーの専門家が見たカリフォルニアン・イデオロギー論みたいなものにもっと踏み込もうと思ってます。これは1年くらいかけて、ゆっくりとまとめようかなと思ってます。
他にも、高校生向けの本を書かないかという話も来ていて、若い人たちに向けて今日話してきたような文化から自分が学んできたものを何かしら語りかけられたら……なんてことも思ってますね。(了)
【あわせて読みたい】
『ポケモンGO』を語ることが、社会を語ることよりも重要になる!? “ゲームを語る”ことの難しさと、これからの「ゲーム批評」の話をしよう宇野常寛氏主催の「PLANETS」副編集長を務める中川大地氏に、ゲーム批評の歴史を語っていただきました。2016年に『現代ゲーム全史――文明の遊戯史観から』(早川書房)を上梓した同氏が読み解く、ゲームと批評の関係とは?
関連記事:
「電王戦」5年間で人類は何を目撃した? 気鋭の文化人類学者と振り返るAIとの激闘史。そしてAI以降の“人間”とは?【一橋大学准教授・久保明教氏インタビュー】
『君の名は。』監督・新海誠がゲーム業界を駆け抜けた日々 ~『イースII』リメイクOPから『ほしのこえ』誕生まで 【ゲーム語りの基礎教養:特別回】