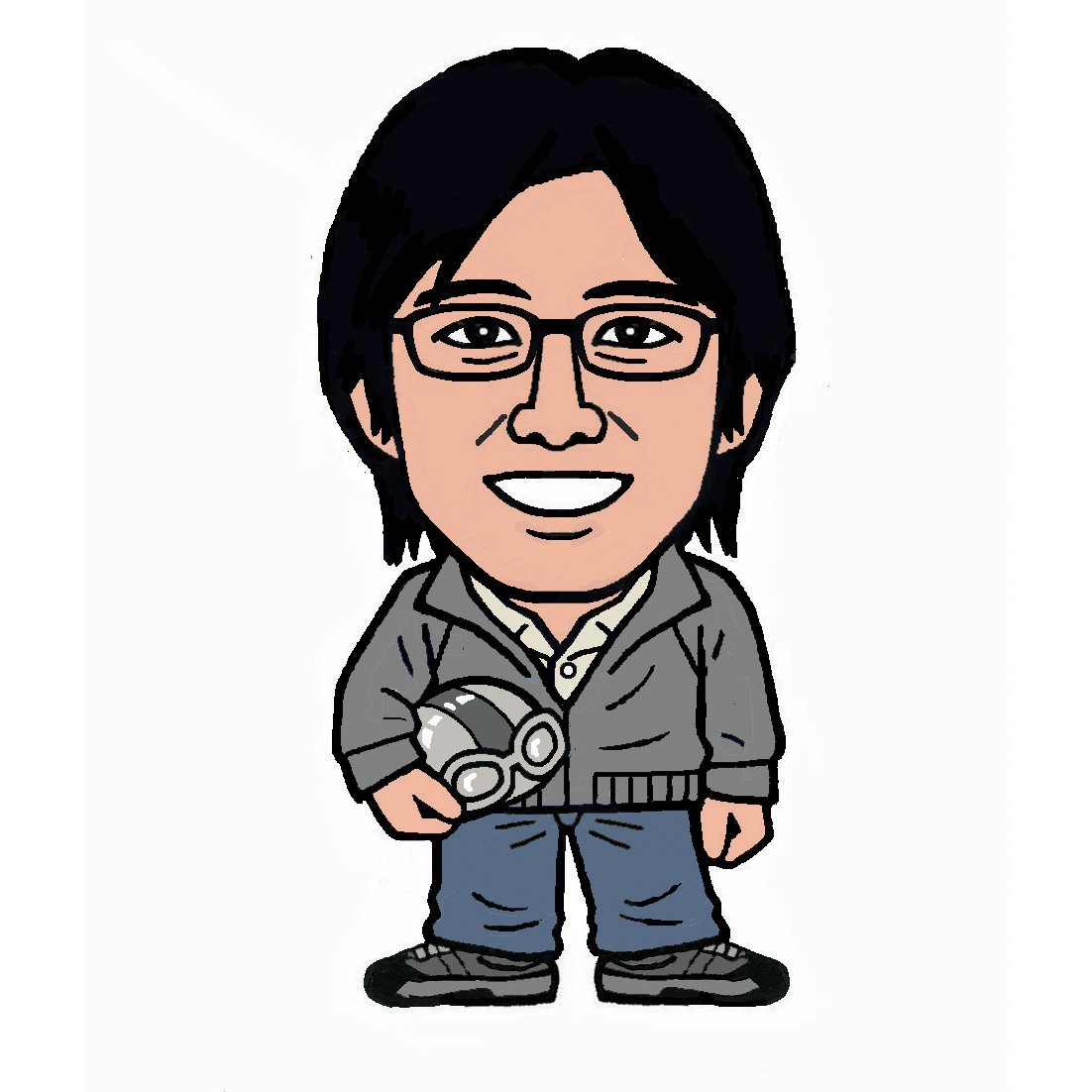2018年3月17日に、東京・吉祥寺のスターパインズにて、ゲームデザイナー須田剛一氏率いるグラスホッパー・マニファクチュア(以下、GhM)の創業20周年を記念するイベントが開催された。
当日は氏の出世作であるアドベンチャーゲーム『シルバー事件』とその続編にあたる『シルバー事件25区』をまとめてプレイステーション4用ソフトとしてリメイクした『シルバー2425』の発売イベントも兼ねており、会場は熱心な須田ファン&GhMファンで満たされ、Tシャツ1枚で過ごせるほどのひとかたならぬ熱気を孕んでいた。
 |
さまざまなトークショウや限定ライブなども行われたイベントのリポートは他のメディアに譲るとして、電ファミ取材陣が注目したのは、『killer7』の開発者が集まって催された座談会と、イベント終了時の挨拶で須田氏が、「(現在は)あまり遊べる環境にないんですけども、近い将来、『killer7』のリマスターを実現したいと思っています。そのあとには『花と太陽と雨と』も」、と『killer7』および『花と太陽と雨と』のリマスター製作を口にしたことだ。
沸き立つ来場者を前に「今日お越しいただいた皆さんとの約束にしたいと思いますし、ちゃんと、あの……10年以内に実現したいと思っています」とオチを付ける須田氏だったが、「カプコンさんも応援してくれているので」という添えられた言葉に遠くない実現性を感じた。

現在はゲームキューブ版とプレイステーション2版が中古として出回っているだけで、なかなか遊ぶ環境を整えるのも難しい『killer7』。
最新ハードやSteamなどでもし登場するのであれば、当時業界内外に衝撃を与えたこの伝説のタイトルがどう衝撃的であったのかを、ひとりでも多くの読者に知ってもらい、リマスターに挑んでほしく、まず作品の概要を解説するとともに、ストーリー以外の部分から衝撃の理由を(極めて筆者の主観であるが)列挙していこうと思う。
ストーリーについては、ぜひリマスターをプレイして、その色あせないシャープさに向き合い、眩暈を覚えてほしいものだ。
文・写真/小山太輔
“車椅子に乗った老齢の多層人格の殺し屋”が主人公のゲームを見聞きしたことがあるか?
『killer7』は、『シルバー事件』の須田剛一氏によるディレクションとシナリオ、『バイオハザード』シリーズの三上真司氏によるプロデュースと監修にて、カプコンから2005年6月9日に発売されたゲームキューブ用アクションアドベンチャーゲーム。ゲームキューブで唯一の18歳以上対象ソフトとなっている。
車椅子に乗った老齢の多層人格の殺し屋が主人公。その主人公の中に眠る7つ(以上)の人格を切り替えつつ、バトルやアドベンチャーパートを乗り越え、物語を進めていく。
 |
バトルパートはTPS(プレイヤーキャラクターの背後にカメラがあるシューティングゲーム)の体裁で進み、実際にシュートするときにはキャラクターの視点となる。
のちにプレイステーション2版が発売されているが、暴力的・性的な表現が一部抑えられている。
トゥーンシェイドの洗練によってセンスで闘えることを示唆した【なぜ衝撃的だったのか#1】
『killer7』のオリジナルであるゲームキューブ版が発売された当時(2005年)は、3Dポリゴン描画ができるようになった32ビット機(ニンテンドウ64、プレイステーション、セガサターンなど)が新世代機(ゲームキューブ、プレイステーション2、ドリームキャスト)にひととおり切り替わり終えた時期にあり、よりすぐれた映像表現を求めて各メーカーとも手法を模索していたタイミングにあたる。
表示可能なポリゴン数が増え、よりリアルな方向へと舵が切られることが普遍的であったそうした状況下で、『killer7』のコントラストを突き詰めたハイキーかつスタイリッシュなシェーディングは、たとえ物量に任せられない中小のデベロッパーであっても、センスひとつで大きなメーカーと闘えることを示唆したものとなった。
 |
これは須田氏の前々作にあたるプレイステーション2用ソフト『花と太陽と雨と』(2001年)での表現をより突き詰めたものと思われ、2000年のセガ『ジェットセットラジオ』などとともに一種の発明に近いものだった(イベントでは、かなり早い段階からこのシェードの方向が決まっていたことが当時のプログラマである渡邉和寿氏から明かされていた)。
翌2002年に登場した任天堂『ゼルダの伝説 風のタクト』や同じカプコンの通信レースゲームゲーム『アウトモデリスタ』などを経て、トゥーンシェイドはゲーム業界全体で、あるいはアニメ業界など親和性の高い界隈を巻き込みながら発展を遂げ、今日の『アイドルマスター』シリーズやアニメ『けものフレンズ』などのように、とくにその点を拾い上げて語られることもないほど普遍化している。

だが、その中にあってもいまだ『killer7』のように、フラットかつシャープな陰影で、圧倒的なセンスを見せつけるものは、モノクロで彩られた『MAD WORLD』など、数えるほどしかない。
そしてこの表現も、章によっては表現の方向を作為的に変え、プレイヤーをはぐらかし続ける悪趣味さだ。
タイポグラフィへのこだわり【なぜ衝撃的だったのか#2】
独特のシェーディングとともに衆目を集めたのは、イベントシーンで画面下部に脈動するテキストだろう。
かなと漢字で大きさを変え、規則的な揃えかたをせず、脈打つようにゆらゆらとアニメーションする文字群は、“殺”、“死”などの特定の文字に込められた血のような効果、そして「ヒャクパー(100%)」、「トル(殺す)」など須田氏独特のドライブ感のあるルビ表現とあいまって、潜在的な浮遊感や酩酊にも似た恍惚感をプレイヤーに与えた。
 |
さらに言えば、物語を細部までロジカルにつかもうとするプレイヤーの奮闘をするりとかわす、氏独特の難解な(あるいは3周ほどして深いことは何も考えていない)ストーリーテリングに、妙な説得力をもたらしていた。
心情をマップで表現する手法【なぜ衝撃的だったのか#3】
電ファミ記事“ゲームの企画書”の『零』、『SIREN』を開発者が語るホラー回で、『零』シリーズをずっと手がけているコーエーテクモゲームスの柴田誠氏がこう語っている。
柴田氏:
その意味では、マップの長さや曲がり方で、プレイヤーの感情をコントロールすることは出来るんですよ。(中略)「零」では廊下の長さが異常に長かったり、変なところで曲がったりしていているマップは、感情をコントロールするために「間」を設けているんですね。
──ああ、ホラーゲームでよく意味もなく、部屋と部屋の間に何も出てこない「連絡路」みたいなのがあって、ちょっと必要性が疑問だったのですが、それも「間」なんですね。
柴田氏:
そうですね。部屋の場合は、「よし。さぁ調べるぞ」となって、自由に動き回ってしまう。ところが、廊下は前に進むしかないので、「目の前のドアには何があるんだろう」と考える時間が生まれるじゃないですか。
でも、このマップによる感情のコントロールは、ホラーゲーム以外のクリエイターは、皆さん意識されていないと思います。ジャンルは違うんですが、『killer7』がやっていて、マップの長さで間を作ることをホラーゲーム以外で拘る人がいるとは、と思いました。
こう語られるように、須田氏のゲームのマップは攻略本などで見るような図面として表すと、とことんイビツなときがあり、それがゲームの魅力を引き立てることにひと役買っている。
ほかのゲームであれば、各種の演出やマップの構造によって決戦などのイベントシーンは盛り上がる方向に誘導されがちなところ、須田氏の作品の場合、この『killer7』にしても、前述の『花と太陽と雨と』にしても、そして『NO MORE HEROES』にしても、道のりの長さでプレイヤーの心情を盛り立てる表現をすることがある。
柴田氏の発言を汲んでこれを考察すれば、この形は隅々まで作り手の意図が込められた作品の見えかたにプレイヤーを否が応でもはめ込むものであり、とりわけ『killer7』においては、プロデューサーの三上氏が須田氏の作品の本質──つまり作家性そのもの──あるいは須田氏という人物そのもののインナーワールド──をゲームの鍵と見極めて、そこへとプレイヤーを誘導したものとも思われる。
 |
これは、簡単モードにあたる“敢闘”モードを選んだときに、シューティングの照準が自動になることからも明らかで、ゲームに対するプレイヤーの腕前を楽しんでもらう以上に、それで挫折し作品の全容を見届けられなくなるくらいなら、難度から生まれるゲーム性は抑えてでも「須田氏の世界を味わって欲しい」という意志の表明そのものだ。
さらに付け加えるなら、須田氏のゲームメカニクスの異質さ、プレイヤーが戸惑いを受けるメカニクスの代表例として、ボタンを押して進む、いわゆる“レール移動”を挙げておこう。「テキストベースのゲームが好きなお客さんも遊べるための入力装置」と氏が語るように、テキストアドベンチャーではボタンを押してコマンドを選択していたゲームの進行を、アクションゲームでもボタンを押すことでキャラクターがレール上を移動することに変換しているのだ。
露悪的な表現とユーモアがひた隠すものは
つまるところ『killer7』は何かと言えば、須田氏の混沌とセンスの顕現であり、いまではメジャータイトルではほとんど見られなくなった“作家性”の塊なのだ。この塊の喉ごしは人を選ぶこともあるが、飲み込めば誰にとっても確実に忘れられない味となる。
ではその須田氏の作家性とは何か? これは須田氏の核にあるものをユーモアと露悪的な趣味で包み隠し、プロレス的なショーマンシップで煙に巻いたものという、とんでもないシロモノと思われる。
 |
ここまでして氏が隠し通しているものは、テキストの端々に匂い立つ叙情性──おそらく須田少年が遠い日に感じていた、ブリティッシュポップのセンシティブさにも似た叙情性だ。これはたいていの場合、プロレス好きという言い訳の裏側に隠されている。
その照れ隠しは、氏がイベントに登壇するとき、たとえば2002年の『killer7』発表時にルチャのマスクをかぶって現れたり、つい先日も海外記者たちを前にニンテンドースイッチ向けの『NO MORE HEROES』の新作を発表したとき、レスラー武藤敬司の真似で同時通訳を大混乱に陥れたりなど、さまざまな形で確認できるが、ともあれ『killer7』が須田氏のインナースペースを具現化したものであるならば、氏の内側を読み解くのもまた、たいへんに困難を伴うものであることは確かだ。

リマスター版『killer7』や『花と太陽と雨と』リリースの暁には、またあらためてストーリーを含めた作品論、須田氏論などができればと思う。
(c)grasshopper manufacture Inc. 2005
(c)CAPCOM CO.,LTD. 2005 ALL RIGHTS RESERVED.
【あわせて読みたい】
ホラゲにゲームデザインの常識は通用しない!? Jホラーゲームの第一人者『零』×『SIREN』開発者が語り合うホラーの摩訶不思議(柴田誠×外山圭一郎)【ゲームの企画書第八回】電ファミでは、『サイレントヒル』や『SIREN』の開発者・外山圭一郎氏と『零』シリーズの開発者・柴田誠氏の対談記事も掲載しております。ホラーの不安感を作り出すために必要な要素を、余すところなく語り合っていただきました。