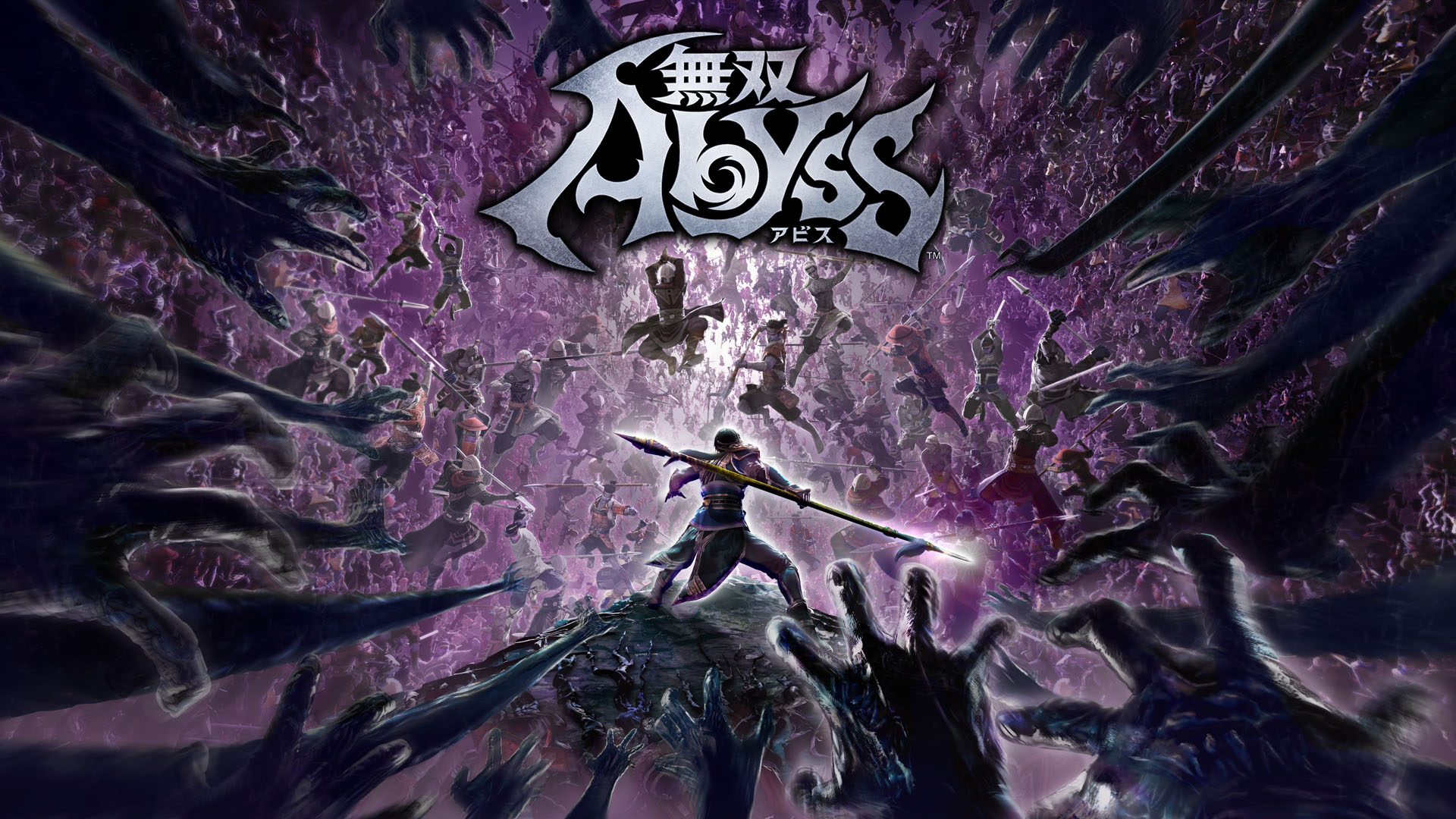ゲーム作りは、予算も時間も人手もかかる。
ゲーム環境の発展とともに予算がどんどん拡大し、ひとつのゲームに対して数十億円規模のお金がかかってしまうことは現在ではよくある話だ。そういったタイトルは開発期間も長いため「作っているあいだにトレンドが変わってしまう」ということもめずらしい話ではない。
一方で、インディーゲームは一芸に秀でた低価格なタイトルがどんどん出ている。既存のシステムであっても作家性が強く出ていたり、プレイ時間が短くても深く刺さる物語であったり、「1本の映画を観る」くらいの気軽な気持ちで遊べるタイトルが非常に多い。
こういった市場の盛り上がりはゲームファンとしてたいへんありがたいが、大手ゲームメーカーは参入しにくいのが現状だろう。なぜなら会社が大きければ大きいほど、リスクを避けるために尖った企画は通りにくいからだ。
そんななか、コーエーテクモゲームスから『無双アビス』という新作ゲームが発売された。
本作は「低価格」「少数精鋭のチーム」「ローグライト」という、これまでのコーエーテクモゲームスとしてはもちろん、大手ゲームメーカーとしては異例のタイトルになっている。しかも、企画から発売まで約1年という短いスパンだったそうだ。
これはゲーム業界に風穴を開けるかもしれない。しかしなぜこの企画がコーエーテクモゲームスで通ったのだろうか?
そこで今回電ファミは、本作のプロデューサーを務める平田幸太郎氏に「異例だらけの新作ゲームが『無双』の名を冠するにいたるまで」をうかがった。企画を落とさないための、平田氏ならでは作戦とは?

最初に語られたのは、同氏の『Slay the Spire』に対する愛情。ローグライト好きだからこその視点と企画。本稿では、『無双アビス』の企画が実現するまでの経緯や「手軽に楽しめる作品を作りたい」といった作品に込められた思いについてお届けしていく。
『Slay the Spire』は「4つのハード」で購入するほどライフスタイルに浸食
──まずは『無双アビス』の企画が立ち上がった経緯についておうかがいさせてください。「低価格」「少数精鋭のチーム」「ローグライト」といったこれまでと異なる企画が、なぜコーエーテクモゲームスという大きな会社で通ったのでしょうか?
平田幸太郎氏(以下、平田氏):
これは話すと長くなるのですが、ディレクターを務めた『WILD HEARTS』の開発が落ち着いたときに「自分で新規の企画を立ち上げたい」と思い、ローグライトをテーマに企画書を書いていたんです。それは、単純に私がローグライト好きであると同時に「気軽に手に取って楽しめるタイトルを作りたい」という思いがありました。
というのも、昨今は開発するタイトルがどんどん大型化していますよね。そういったゲームを作ることができるのは大手企業ならではの強みだと思う一方で、「コンパクトなタイトルもコンシューマーゲームに求められている時代なのではないか」と思ったんです。
──重厚なタイトルだけでなく手軽なゲームも求められているという分析のなかで、ご自身の好きなローグライトがマッチすると考えられたわけですね。ローグライトあるいはローグライクでいうと、これまでどういうタイトルを遊ばれてきたのでしょうか?
平田氏:
古いところだと小学生のころに遊んでいた『トルネコの大冒険 不思議のダンジョン』や『風来のシレン』シリーズです。大人になってからは『HADES』や『Vampire Survivors』に触れたとき「すごく市場性のあるジャンルだな」と感じました。
ただ、個人的にダントツで好きなのは『Slay the Spire』です。
──あっ、そのひと言で平田さんがゲーマーということがよくわかりました(笑)。
平田氏:
『Slay the Spire』はコアゲーマーほど響く作品ですよね(笑)。私の人生で5本の指に入るタイトルです。4つのハードで購入して遊んでいるゲームは、『Slay the Spire』くらいですから。
──たしかに『Slay the Spire』はさまざまなプラットフォームで遊べますが、どうしてそんなことになったのでしょうか?
平田氏:
初めて『Slay the Spire』を遊んだのはPS版でした。当時は『WILD HEARTS』を開発していたころで忙しい時期だったにもかかわらず、「なんだかおもしろそう」と思って遊んでいたら知らぬ間に朝の5時とかになっていたんです(笑)。
すごくおもしろいので精神的には充実していたのですが、肉体的にきついと思って(笑)。寝ながら遊べるようにNintendo Switch版を購入しました。
ただそれでも遊び足りないので、スマホで遊べるようにiOS版を購入して……という具合に、どんどんライフスタイルに浸食していってしまって。最近Androidに機種変更をしたので、それが4ハード目です。
──(笑)。平田さんが生粋のゲーマーだということがよくわかりました。
平田氏:
それでいうと、私はずっとゲームセンターでゲームをしてきたので、対戦格闘ゲームもすごく好きです。はじめはスーパーファミコン版の『ストリートファイターⅡ』を遊んでいました。
でも、しばらくして『ストリートファイターⅡ』がゲームセンターで遊べると知って、試しに対戦してみたらボコボコにされてしまいました。「世の中にはすごい人がいるんだな」と(笑)。そこから『THE KING OF FIGHTERS』シリーズや『GUILTY GEAR』シリーズなど、当時対戦が盛んなタイトルにハマっていったという感じですね。
──対戦格闘ゲームのうまくなっていく過程であったり、お金の使わせ方であったり、勝っても負けても対戦したくなるような調整の仕方は、ローグライトに通じるものがあるかもしれませんね。
平田氏:
そうですね。そういう意味では、ローグライトは自分の中でシンパシーを感じるジャンルだと思います。何回も挑戦することでプレイヤーとしての経験値やスキルが高まり、より高い壁に挑戦できる。そういった要素が刺さったのかもしれません。
──対人かそうでないかの違いはありますが、プレイヤー側のスキルを高めていく点は格闘ゲームもローグライトも共通していますね。
平田氏:
『Slay the Spire』は、おそらく500時間から1000時間くらいは遊んでいると思いますが、それでもまだ「わからないことがあるな」と感じるタイトルなので、本当にすごいと思います。
そのうえで、ローグライトのゲームは「合う」「合わない」があるとも感じました。ただひと口にローグライトといってもアクションもあればカードゲームもありますから。間口の広さがありつつ、自分に合ったものを選択できるのがジャンルとしての強みだと思います。
コーエーテクモでは異例づくしの企画を “2択作戦” で突破
──新しい企画を模索するなかでローグライトを作る方向性になったとのことですが、当初の企画内容はいまの『無双アビス』に近いものだったのでしょうか?
平田氏:
じつは最初、『無双アビス』とは別のローグライトの企画を作っていました。というのも、予算を取るためにはまず経営陣に企画を持って行く必要がありまして、そのときにただ企画を持って行くだけでは説得力がないと思ったんです。
そこで考えたのが、「対案となるB案も一緒に持って行って “どちらがいいですか?” と聞く」という、詐欺師のような作戦でした(笑)。
──どちらかを選ばせる状況を作り出したわけですね。
平田氏:
はい。「マルですか、バツですか」と聞いたら「どちらかといったらバツ」と言われてしまう可能性があるため「A案とB案どちらがいいですか」と聞くことでどちらかの可能性は残せるだろうと思いました。
そのときB案として考えたものが、『無双アビス』の前身の企画です。
──最終的にB案である『無双アビス』が採用されたのは、どういった経緯があるのでしょうか?
平田氏:
企画が通ったときのことを考えて「将来的にどう肉づけしていくか」というのを、A案でもB案でもあらかじめ考えていたんです。そうしたら、不思議なことにB案のほうがいろいろとアイデアが湧いてきて。
「こういったことができるな」とか「こういう試みはまだ行われていないな」とか「既存のアイデアでも、うちの強みを活かせるかも」といった勝ち筋のようなものがB案には多かったんです。
──ちなみにA案の方はどういった内容だったのでしょうか?
平田氏:
A案はどちらかというと「ちゃんとしたアクション」で、自分をビルドアップしていくような企画でした。
一方で『無双アビス』の前身は “B案” ということもあって、それとは対極の強みを出していこうと考えたんです。そうしているうちに「キャラクター数の多さでも勝負できる」といったローグライトとの相性のよさが見えてきました。
最終的に社長の鯉沼へ正式に相談するときには、『無双アビス』の前身のB案だけを持って行って「この企画をやりたいです」と伝えました。
──その時点でのB案の骨子はどういったところだったのでしょうか?
平田氏:
決めていたのは「クオータービューで最高の爽快感を出す」というところでした。
ローグライトのビルドの部分などは、企画を煮詰めていくなかでどんどん深みが増していく部分だと思うのですが、最初に考えたのは「画として引き込まれるものがあるか」という点です。これはもう『Vampire Survivors』を初めて見たときに痛感したポイントで。
──『無双アビス』の「一斉召喚」のシーンなどは『Vampire Survivors』のステージ後半のような、パッと見で「おっ」と引き込まれるものがあります。
平田氏:
私は格闘ゲームプレイヤーのライブ配信をよく見るのですが、あるとき「格ゲー以外のゲームをやっているぞ」と思って配信を開いたら2Dドット絵のゲームをプレイされていたんです。それが、『Vampire Survivors』でした。
正直なところ最初は「なにがおもしろいんだろう」と思って、仕事をしながら配信をつけていたのですが……。仕事が落ち着いたころに見直してみたら、画面がものすごいことになっていたんです(笑)。あのインフレ感のようなものが必要だと思っていたので、企画の最初の軸として意識していました。
──『無双アビス』は、『無双』シリーズのさまざまなタイトルからキャラクターが参戦していますよね。それも最初からのコンセプトとしてあったのでしょうか?
平田氏:
はい。『無双』のキャラクターを使うとなったときに、シリーズとして親しまれているキャラクターを使った方がいいだろうと考えました。
最初は『真・三國無双』シリーズのキャラクターのみに絞ろうと考えていたんです。しかしながら『無双アビス』のいちばんの特徴である「ビルドの多様性」というところを表現するうえで『三國』だけに限定せず『戦国』のキャラクターも入れることにしました。
──参戦キャラクターの幅もそうですが、100体という数の多さにも驚かされました。
平田氏:
100体というキャラクター数は、ビルドの多様性を確保する最低限の数を考えたときに出てきたものです。最初に「100体登場させる」と言ったときは周囲から「できるわけがない」とすごく言われました(笑)。
──ということは、100体というのも構想の初期段階からあったのですね。
平田氏:
企画の途中段階で増減はしましたが「100という数字を遵守することでセールスポイントにしたい」という思いもあり、がんばりました。
──「できるわけがない」と言われた企画を企画会議で提案したときはどういった反応があったのでしょうか?
平田氏:
私としては「怒られるかもしれない」と思って企画を持って行きました(笑)。
というのも、「税込み2970円の低価格」「少数精鋭のチーム」「ローグライト」というのは弊社として新しい挑戦になります。異例だらけの企画なので、どんな反応があるのか読めませんでした。
──実際の反応は……?
平田氏:
それが……奇跡的にめちゃくちゃ理解があったんです(笑)。
──(笑)。
平田氏:
じつは税抜きで2700円という価格もプロデューサーの立場として「3000円くらいにしたほうがいいのかな」と考えたこともあったのですが、社長の鯉沼(久史氏)に価格変更を止められたんです。
私の立場から「何様だ」と思われるかもしれませんが、「社長、わかってらっしゃる!」と思いました(笑)。
──鯉沼さんを含めたコーエーテクモゲームスの上層部にも、平田さんと同じような問題意識といいますか、「なにか変えなきゃ」といった思いがあったのでしょうか?
平田氏:
いや、私もその真意まではわかりません。ただ、すごく応援してくださったので、そのおかげで新しい挑戦ができました。
──いちゲーマーとしての意見になってしまうのですが、コーエーテクモゲームスからこういったゲームが出てきたことに驚かされました。世間でインディーゲームなど小規模開発のゲームが話題になっていても、大手メーカーさんほどその流れに乗りにくいと思っていて。しかし今回、コーエーテクモゲームスがその競争に参入されたことで、変わるきっかけが生まれるのではないかと。
平田氏:
ありがとうございます、そういった話題は周囲とよく話していたりしますね。たいへんありがたいことに、『無双アビス』に関しても社内でよく「注目しているよ」と言っていただけます。
──少数精鋭のチームで作ったということでしたが、開発期間としてはどれくらいだったのでしょうか?
平田氏:
社内の企画会議を通すような段階では、ディレクターと私のふたり体制くらいの、ごく少人数で動いていました。チームとしては現行のプロジェクトのなかでいちばん人数が少ないと思いますね。
プログラマーを加えて実際に作り始めたのは昨年の2月か3月だったと思うので、約1年ほどで世に出すことができました。
──なるほど。そう聞くと「どんどん出してほしい」といった気持ちになりますね(笑)。
平田氏:
そのスピード感を求めていました。いまのゲーム開発は1本に5年くらいかけることもよくある話になってきています。しかしそうなると、なにかしらのトレンドがあったとしても乗り遅れてしまったり、テイストが変わってきてしまうところがありまして。そこに対するなにかしらのアプローチをしたいとずっと考えていました。
「コーエーテクモのゲームはこういうものである」といった先入観がない
──『無双アビス』のジャンル名は「ローグライト無双アクション」とのことですが、「ローグライト」「ローグライク」というジャンル名は、しばしばその定義が議論になります。その点に関して平田さんはどうお考えですか?
平田氏:
そうですね、定義づけは難しいですよね。ただ、本作に関しては「ローグライクではなくローグライトだ」と、開発チームによく話していました。
私としては「『Rogue』がもともと持っていたゲーム性の一部の要素だけを持ってきている」というのがローグライトなのかと思っており、くわえて「ローグライト」という言葉には「気軽さ」も込められていると思っています。
──「ローグライト」という言葉に、制作側として「気軽に遊んでほしい」という意味合いを込めていると。
平田氏:
やりたいこととしても、「正統派のローグライク」というよりは、「『無双』としての新しいかたち」のようなイメージだったので、それもあって「このゲームはローグライトだ」と考えています。
──『無双』ファンだけではなく、より幅広い方々へのアプローチを考えたわけですね。
平田氏:
プラットフォームに関しても、現行の機種すべてに対応しているのはそれが理由です。
PS5、PS4、XboxSeriesX|S、Switch、Steamと、「このゲームが気になった全員がアクセスできるようにすべてのプラットフォームで出しましょう」と言いました。しかしこれに関しては苦労もあったので、スタッフには恨まれているかもしれません(笑)。
──『無双』シリーズは『真・三國無双 ORIGINS』が発売されたばかりです。『無双』シリーズの制作経験が豊富なスタッフは『ORIGINS』に参加されていたのではないかと思うのですが、『無双アビス』開発スタッフはこれまでどういったタイトルに携わっていたのでしょうか。
平田氏:
いままで『無双』をずっと作っていたようなメンバーは少ないです。しかしそれがいい面でもありました。当初は『真・三國無双7』や『戦国無双4』からモーションやエフェクトを持ってきたのですが、どうしてもクオータービューの『無双アビス』には合わなかったんです。
同じモーションでも「カメラが俯瞰的になることによってもっさり見えてしまう」といった問題があったのですが、手を入れることに対して躊躇がなかったのはよかったと思います。
──「『無双』シリーズはこういうものである」といった先入観がないぶん、新鮮なものができあがったのですね。
平田氏:
最初は控えめなところから手を入れていたのですが、「怒られてもいいからやりきっていいよ」と言ったら「本当ですか!」と、いまのようなかたちとなりました。本作を作るにあたって、クオータービューアクションとしての気持ちよさはゲームに対する入り口としてかなり意識した部分になっています。
ただ、最終的にこのゲームを繰り返し遊んだとき「どこに魅力を感じるか」というと、やはりビルドの部分だと思うんです。どれだけこのゲームを遊んだ人であっても「まだこんなシナジーがあったんだ」という気づきがある状態を目指しました。
──本作は「実況映え」するゲームになっていますよね。100回やれば100回違った動画内容になるので、ゲーム実況者の方からするとすごく「取れ高のあるタイトル」になっていると感じます。
平田氏:
個人的には実況動画よりも解説動画のほうが作りやすそうな気がしています。いまって攻略の最先端がユーザーさんだと思うんですね。
『WILD HEARTS』を作ったときも「この難関をクリアするには3週間くらいかかるだろうな」と思っていた箇所が、1〜2週間くらいで「ノーダメージクリアのお手本動画」みたいなものが上げられていたりして(笑)。
いまの時代はそういった「ユーザー発信の攻略」が重要だと思っています。本作は「よーいドン」でみなさんが攻略を開始することになるので、自分の気づきを発信していただけたらうれしいです。
100体のキャラクターのなかから「ひとりの操作キャラと仲間になる6人を選ぶ」。これは単純計算でも160億通り以上あるわけです。そういった可能性のなかで「俺はこれが最強だと思う」とか「俺はこのビルドが好きだ」といった情報共有をしてもらえれば、すごく楽しい関係になるんじゃないかと思います。
『無双』アクションの爽快感がローグライトの「インフレ要素」で突き抜ける
──本作はこれまでの『無双』シリーズとは異なり、クオータービューで360度から敵が迫ってくるというのが特徴的です。視点が変わったなかで、アクションの爽快感はどのように肉づけされていったのでしょうか?
平田氏:
クオータービューにした理由は、サードパーソンカメラでは表現できなかった「敵が360度から迫ってくる」というところです。それを「ひとりのキャラクターが爽快に吹っ飛ばしている」という絵面を作りたいと思いました。
しかしそうなると、同時に出現する敵の数も重要になってきます。たとえば「画面の中に1000人の敵を登場させる」となると……。プログラマーには悪いことをしたと思っています(笑)。
──(笑)。
平田氏:
俯瞰のカメラの中でその数の敵がいたら価値になると思ったので、そこは譲れませんでした。あれだけの数の敵が出るなかでマルチプラットフォーム対応もしないといけなかったため、プログラマーはとても大変だったと思います。
また、演出面でもクオータービューだからこそできるものがあったと思っていて。ひとつは「無双乱舞」や「無双奥義」を打ったときに、敵が吹っ飛んでカメラに衝突する演出です。そういった「敵がドッカンドッカン吹っ飛んでいく」という絵面は、クオータービューの強みですよね。
あとは、「仲間を召喚する」というシステムもサードパーソンカメラだとあまり効果的ではなかっただろうと思いました。俯瞰のカメラにすることによって、「仲間の攻撃がどれだけ作用しているか」が視覚的にわかりやすいんです。
──たしかに、サードパーソンカメラで味方を召喚したとしても、カメラの後ろに回り込んでしまったらなにが起きているのかわかりませんね。
平田氏:
目指したのは、「インフレ感」でした。普通のゲームの場合、制作側の「こうやって強くなっていきます」というレベルデザインを、比例的に超えていくような仕組みになっていると思います。
しかし、ローグライトの気持ちいいところは、その強さの上昇の仕方にスパイクがあるところだと思うんです。そこでいかにプレイヤーに「できた!」と思わせるかが重要だと思うので、絵作りとしてそれを演出するのはかなり意識しました。
──先行プレイをさせていただいたときに「ちょっとボスが強すぎるんじゃないか」と感じたところがあったのですが、これまでの平田さんのお話から、そういったインフレは織り込み済みの調整だったとわかりました。
平田氏:
たぶんビルド次第で解決すると思います。ただ、じつは序盤のボスに関しては狙いがありました。
本作のザコ戦の部分は、うっかり油断すると体力を削られることはあってもこれまでの『無双』のような感覚で進められます。一方でボス戦は「味変」というわけではありませんが、「相手の攻撃にも注意しようね」といったバランスに調整しました。
とはいえ「無双乱舞」や「一斉召喚」で一気にダメージを与える部分は残したかったので、ボスの行動の隙に攻撃を当てることで、本作の気持ちいいアクションを体感できるシステムにしています。
しかしこうしたバランスはインフレする前の話。極端な話、ビルドが完成しきった暁には、「プレイヤーが一歩も動くことなくラスボスを倒す」こともできると思います。
──そこまで強くなれるんですか!?
平田氏:
はい。ビルドを突き詰めれば、それこそ『Vampire Survivors』でインフレしたときより楽に戦えると思います。
──ちなみにそれって、どのようなビルドなのでしょう。
平田氏:
「動かないで済む」でいうと、召喚技のなかに「光の弾が画面内を跳ね回る」といった種類のものがあり、その技をもった英傑を6人揃えて威力や弾の数や持続時間を強化する、といったものです。
「一斉召喚」のボタンを1回押すだけで画面が弾で覆いつくされ、ずっと攻撃判定が持続して敵が溶けていくという(笑)。召喚技に設定されているクールダウンもビルド次第で「0」にできたりもします。
──(笑)。本当に、アイデア次第でなんでもできるゲームですね。
平田氏:
コンボ攻撃の最終段階で発動する召喚技をコンボの途中で発動できるようにできる「クイック召喚」というシステムがあるのですが、それらを組み合わせることによって、□→△→R1とボタンを連打していくだけで、英傑がバンバン出てきて攻撃してくれるようになるんです。
そのうえで「特定の属性の英傑をまとめて召喚する」といった特性を持った英傑がいるとボタン連打で6人の英傑が延々と召喚できるようになったり(笑)。
──(爆笑)。
平田氏:
いま言った例でいうと、「ねね」という英傑は「自分が召喚されたときにほかの豊臣家のキャラクターを全員召喚する」ことができるんですね。ですので、「ねね」のクールダウンを0にして、ほかを豊臣家のキャラクターで埋めると……。
──聞けば聞くほど、バランス調整が大変だったと思うのですが、「1年で作りました」というレベルではないですよね。
平田氏:
めちゃくちゃ大変でした。開発チームのチャットに「雑談チャンネル」があるのですが、「このビルドが強い、弱い」といったやりとりが行われているんです。そのなかでずっと「こいつは壊れてます」「こいつも壊れてます」ってログが流れてきて(笑)。
──(笑)。
平田氏:
でも私は「いや、壊れているのは悪くない」と言いました。なぜなら、ローグライトのおもしろいところとして「 “もうこれ勝ち確定やん” という状態に持って行ける可能性がある」というのが重要だと思っているからです。それ自体はぜんぜん悪くないことだと思うんですよ。
なので調整で重要視したのは、気持ちよさのスパイクを作るための戦略性と少しの運要素ですね。「より勝ちやすいビルドを構築していく」といった戦略性は考えてほしいところなので。実際に調整した点としては、「このビルドは成立しやすいからみんながこれを目指してしまう」といった場合などですね。
──なるほど、特定のビルドが簡単に作れすぎてしまうと「楽だから毎回これでいいや」となってしまいますね。
平田氏:
そうなんです。「このビルドを目指していたけどキーとなる諸葛亮が手に入らなかったから次善の策を取ろう」とか「いつもは手に入らなかったから諦めていたけどたまたま呂布が手に入ったから呂布を中心としたビルドにしよう」というような広がりを作りたいと思いました。