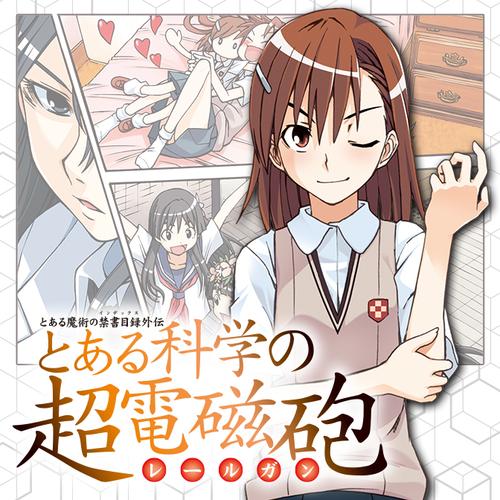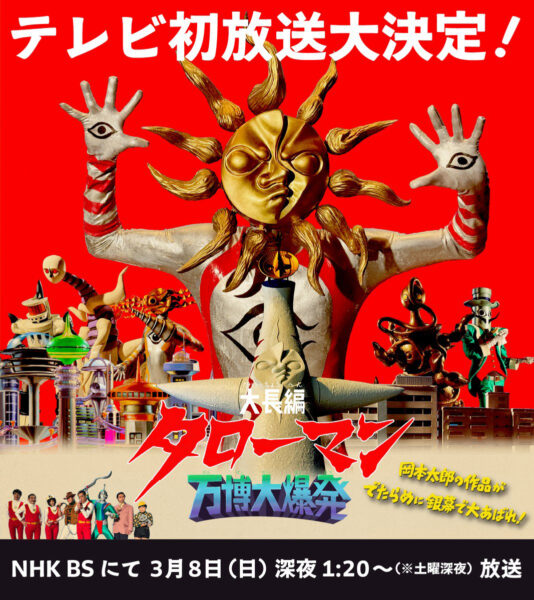人はなぜ荒廃した世界に佇む女の子にグッとくるのだろう。
この件について熱弁を振るうディレクターと、困惑するディレクターがいた。熱弁を振るっているのは『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』(以下、エンダーリリーズ)や『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』(以下、エンダーマグノリア)のディレクターを務める岡部佳祐氏。そして困惑しているのは『ニーア オートマタ』のディレクターを務めるヨコオタロウ氏。

なぜ上記のような状況になっているのかはぜひ本文を読んでいただきたいのだが、両氏が手がける作品は「荒廃した世界で戦う可憐で儚げな雰囲気の女の子が出てくる」という共通点がある。
「終末世界×女の子」は昨今のゲーム作品において人気のモチーフとなっており、火付け役となった作品といえばやはり『ニーア オートマタ』ではないだろうか。機械生命体に占拠された地球で戦うアンドロイドたちの物語を描き、主人公「2B」の鮮烈なビジュアルやヨコオタロウ氏の紡ぐシナリオが大きな話題を呼んだヒット作だ。

一方、岡部佳祐氏といえば1月23日に探索型2DアクションRPG『エンダーマグノリア』が発売されたばかりだが、その前作にあたる『エンダーリリーズ』もまさに『ニーア オートマタ』の影響を受けているとのこと。か弱い少女「リリィ」が、死ぬに死ねない屍と戦い「浄化」をしていく物語だ。

そこで今回は、ゲームにおける「女の子の在り方」についておふたりに対談形式で語り合っていただいた。
両氏の作品はパッと見の雰囲気やアートスタイルが魅力的でありながら、実際のゲームプレイの手触りやアクション部分の丁寧な作り込みも評価されている。アイデアを実際のゲームに落とし込むディレクターの仕事論や苦悩、20歳ほどの年齢差がある両氏の「ゲーム業界今昔」といった話題にいたるまでお届けしよう。
『エンダーリリーズ』を開発する怪しい会社(?)について
──本日はよろしくお願いいたします。『エンダーリリーズ』は『ニーア オートマタ』からも影響を受けているそうで、岡部さんから「ぜひお会いしたい」とリクエストがあり、ヨコオさんにお越しいただきました。
岡部佳祐氏(以下、岡部氏):
よろしくお願いします。ヨコオさんには以前からお会いしたいと思っておりました。
ヨコオタロウ氏(以下、ヨコオ氏):
よろしくお願いします……。

──ヨコオさんどうされました?
ヨコオ氏:
いや、事前にスタッフの皆さんと名刺を交換したのですが、社名が「Live Wire(ライブワイヤー)」と書かれているものと「BINARY HAZE INTERACTIVE(バイナリーヘイズ)」と書かれているものと2種類あって、それぞれデザインが違うんですよ。
岡部さんからいただいた名刺はライブワイヤーとなっていますが、岡部さんはそちらに所属されているんですか?
岡部氏:
はい。どちらも「ADGLOBE(アドグローブ)」という会社の子会社で、ライブワイヤーがゲームの開発会社、バイナリーヘイズがパブリッシングブランドのような役割を担っています。
ヨコオ氏:
えっ、また新しい名前が出てきた。つまり、アドグローブさんの中にバイナリーヘイズというブランドがあって、実際の開発はライブワイヤーが担当していると。
岡部氏:
いえ、実際の開発はアドグローブやライブワイヤー、ほかグループ会社も協力して行っています。
ヨコオ氏:
社名がいくつもあったり、ひとつの住所に複数の会社が入っていたり、なんだかすごく怪しいんですけど……。
──(笑)。それで言うとアドグローブさんは会社の経緯も少し変わっていて、代表の小林宏至さんが「いきなりゲーム会社を作るのではなくいったん別業種で会社を成功させ、そこから得た利益でゲームを作る」という手法を取っているんです。
ヨコオ氏:
えっ、ますます怪しい……。アドグローブさんの本業はなにをされているんですか?
岡部氏:
アドグローブは、もともとシステム系の開発を担当する総合IT会社として立ち上がりました。そこから徐々に会社の規模が大きくなっていって、10年ほどかけてようやくゲーム制作に投資ができる段階になったので、ダークファンタジーを専門で手がけるブランドとしてバイナリーヘイズを作りました。
そこで最初に生まれた作品が『エンダーリリーズ』になります。

ヨコオ氏:
じゃあ、アドグローブさんでシステム開発をしている人たちは「俺たちが稼いだ金をゲームで無駄遣いしやがって」みたいに思っているかもしれないということですか(笑)。
岡部氏:
「あいつら遊んでるんじゃないだろうな」という見えないプレッシャーはありますね(笑)。
「女の子を助けたい欲」が結果的に独自性へとつながっていた!?
──おふたりの作品には「荒廃した世界で儚げな雰囲気の女の子が登場するアクションゲーム」という共通点があると思いますが、同じジャンルのほか作品と被らない「隙」のような勝ち筋が見えていたのではないでしょうか。こうした点についてはどうお考えですか?


ヨコオ氏:
僕の場合は「隙が見える」というより、具体的に言うと「既存ゲームに対する不満」がかたちになっていると思います。決してほかのゲームの悪口を言いたいわけではないのですが、満足するタイトルがあれば別に自分で作る必要はないので。
岡部さんもおそらく、既存ゲームに対する「こうしてほしい」という気持ちが作品になっているのかなという気がします。
岡部氏:
まさにそうですね。それもあって、自分でゲームをプレイすることは本当に大切だと思っています。自分でゲームを遊ぶなかで「ここがいい」「ここが悪い」といった判断基準が形成されますし、「もっとこうだったらいいのに」といった不満やエゴから自然と作りたいものが生まれてくるので。
ヨコオ氏:
そういった不満が『エンダーリリーズ』に現れたわけですよね。
岡部氏:
それで言うと、「女の子を助けたい」みたいな欲求ってあるじゃないですか。
ヨコオ氏:
……ん? えっ? そんな、いきなり共有意識みたいに言われても(笑)。
一同:
(笑)。
ヨコオ氏:
そんな日常的に「女の子を助けたい」とは思いませんよ(笑)。岡部さんは普段からそう思っているんですか?
岡部氏:
たとえば、檻の中に女の子が入っているパッケージのゲームがあったとして、その主人公が自分だったら、「その女の子を助け出して、あわよくば自分のことを好きになってほしい」と思いますよね。
ヨコオ氏:
いや、ちょっと途中から岡部さんのオリジナルの味が強すぎて、どこに同意したらいいのか難しいです(笑)。
でもたしかに『エンダーリリーズ』に出てくるような女の子は「弱者の象徴」なので、弱者が理不尽な目に遭っている場面を見せられると「助けたい」という欲求が刺激されることはありますね。

でもそこから先の、付き合いたいかどうかは人によるので(笑)。か弱い少女じゃなくて、強い女性が好きな人もいるので(笑)。人によるんじゃないかな。
──いったん「女の子を助けたい欲」が存在するとしましょう(笑)。
岡部氏:
はい、存在するとして(笑)。ただ、それをゲームで表現しようと思うと、「女の子」というのはゲームシステムのなかではけっこうジャマになりやすいんです。たとえば、キャラクターAIの完成度が悪かったら勝手にあちこち動いてしまってストレスになるし、かといって女の子をギミックのような扱いにしてしまうと愛着が湧かなかったりします。
「いい感じに助けられてほしいけどシステムのジャマにはなってほしくはない」という塩梅が非常に難しいんです。
ヨコオ氏:
ああ、なるほど。
岡部氏:
最終的に『エンダーリリーズ』は「少女を操作して戦闘は召喚されたキャラが行う」という、折衷案のような形に落ち着きました。
なので、ヨコオさんと同じように「既存ゲームに対する不満」はありつつも、もっと根底の欲求としては「女の子を助け出して、あわよくば自分のことを好きになってほしい」というところから発生していると思います。それが結果的に「隙」に入り込んで独自性につながっているのかもしれません。
ヨコオ氏:
……だいぶ岡部さんのリビドーの根源が見えていい。いい感じなんじゃないですか、これは(笑)。
『ICO』はゲームにアートを持ち込んだエポックメイキングな作品
──「女の子を助けたい」というモチーフの元は、やっぱり『ICO』【※】のような作品になるのでしょうか?
岡部氏:
そうですね。『ICO』は大好きな作品です。でもその一方で自分のエゴが出てしまって。女の子の喜ばせ方や悲しませ方について「もっとこうしたい」と思ってしまいます。
【※】『ICO』:2001年に発売されたアクションアドベンチャーゲーム。のちに『ワンダと巨像』『人喰いの大鷲トリコ』などを手がける上田文人氏の作品で、主人公の少年「イコ」が霧の中で出会った謎の少女「ヨルダ」と手をつないで連れ歩くアクションが特徴的。

──まさに『ICO』はけっこう絶妙で、少女はジャマと言えばジャマで扱いが難しいと思うんです。一緒に手を引っ張っていかなきゃいけないけど、 襲われたりして「お荷物」になってしまうこともある。そんな中で『ICO』がゲームとして成立している理由ってなんだと思いますか?
ヨコオ氏:
『ICO』は全体としてのメッセージ性がすごく強い作品ですよね。正直なところ「女の子の手を引いて連れていく」というのは、ゲームの快適性という点ではネガティブな要素です。
たとえば『ICO』が、「女の子ぐらいのサイズの大きなスーツケースを運ぶ」というゲームだったら、面倒くさいゲームの極みのような作品になっていたと思います。そこを女の子にしたところに発明があるんですよ。
──どういうことですか?
ヨコオ氏:
つまり、それまでは「画面内のオブジェクトをすべてただの箱に置き換えてもおもしろいのがいいゲーム」と言われていた時代だった。でも、そこから1歩進んで「ゲーム性としては既存のものと同じ、あるいはネガティブな要素もあるけど、そこにテーマや意味がある」ということを提示したのが『ICO』という作品だったと思います。
──なるほど。要するにそれまでの時代は、遊びのシステムをまず成立させていたんですよね。任天堂さんがよく言っていますが、丸や三角のモックだけでもおもしろいと思える遊びがまず先にあって。
ヨコオ氏:
そのアプローチだと絵柄や世界観はあくまで「飾り」になりますね。
──絵はあくまで飾りであって、「遊びのシステムをいかに作り込むか」という考え方が主流だったと思います。
ヨコオ氏:
そんな中で『ICO』はまずアートや雰囲気が存在して、そこにゲーム性が従属し、テーマやメッセージを表現しているように見えます。すごくエポックメイキングだと思いましたね。
──確かに。「遊びのシステムが既存のものだったとしても、アートやお話が違えばそこに生まれる感情も変わってくる」ということを、明確に示したのが『ICO』だったと。
ヨコオ氏:
そう思います。その後、『LIMBO』【※1】や『UNDERTALE』【※2】のような作品たちが、ゲームアートにおける最初の発明を生み出したような時代があって、そこからワッとゲームの表現幅が広がりましたよね。『ニーア』シリーズもそうした作品からの影響を受けています。
【※1】『LIMBO』:2010年に発売された横スクロールアクションゲーム。モノクロの世界で描かれるミニマリズム的な表現が特徴的。
【※2】『UNDERTALE』:2015年に発売された、トビー・フォックス氏によるインディーゲーム。「誰も死ななくていい優しいRPG」がキャッチコピー。
また他方では、『ファイナルファンタジーⅦ』のころから生まれた「ビジュアルの力で押していくこともゲームの魅力のひとつ」という潮流もあって。そうした流れはいま発達しきっていて、当たり前のようになっていますよね。
ゲーム性もアートもよくなければいけない。ゲームのなかのさまざまな要素が発達しきったのが現在の世代だと思います。岡部さんは「発達しきったゲームの次の世代」として台頭されているわけですが、そんななかで「ゲームを作るうえでフォーカスすべきもの」があるとしたらどこだと思いますか?
岡部氏:
「システムもストーリーもアートも音楽もよくなければいけない」というのは、まさにその通りだと思います。『エンダーリリーズ』や『エンダーマグノリア』も、そこを満たせるようにがんばりました。
結局のところは、ゲームに感情移入してもらうことが肝心だと思うので「すべての要素に対して納得ができるかどうか」が重要なのではないでしょうか。そのうえで、ゲームシステムにストーリー的な意味が持たせてあったりするような作品を遊びたいですし、自分でも作りたいと思っています。
ヨコオ氏:
それを満たしているゲームって、あまり世に出ていませんか。
岡部氏:
うーん、少ないかもしれません。ストーリーについていけなくなったり、システムなどに落ち度を見つけてしまったりすると、単調で飽きてやめてしまうことも多いです……。
──『エンダーリリーズ』や『エンダーマグノリア』に「遊びやすい」という声が多いのは岡部さんが感じた不満に対する改善が反映されているからなんでしょうね。