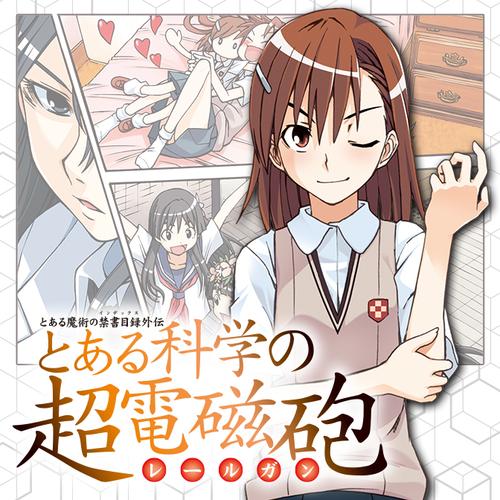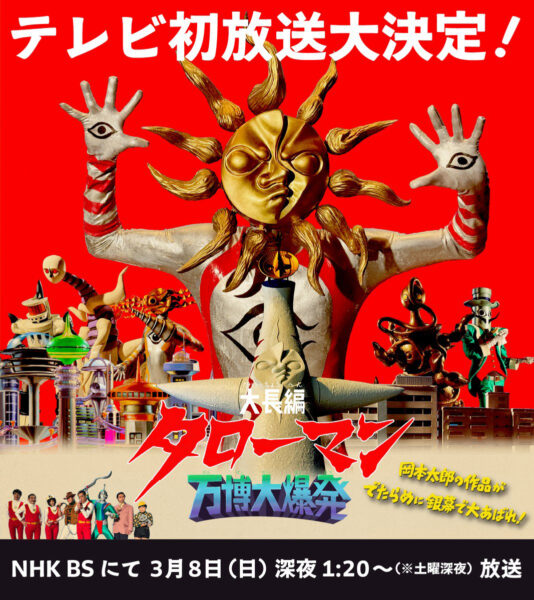制作規模や環境などの違いからくる、それぞれの苦労について
ヨコオ氏:
岡部さんは『エンダーリリーズ』『エンダーマグノリア』とリリースされて、つぎの作品についてはなにか考えているんですか?
岡部氏:
『エンダーマグノリア』は『エンダーリリーズ』での反省や、前作でやれなかったことを出し切ろうという思いで作りました。そのうえで、メトロイドヴァニアもそうですが、横スクロールのアクションゲームでできることの幅がもう残されていないと思うんです。
──ゲームとしてできる「新しいアクション」を発明する余地が限られてきているということですか?
岡部氏:
はい。新しい体験を求めていくと、『CARRION』【※】などのように、「主人公がエイリアンで触手を伸ばして壁に這わせて進むゲーム」といった、よりトリッキーなことをしないといけません。
加えて、ああいうミニマムな作品は我々の予算感ともマッチしないという事情もあります。なので、結局同じようなゲームになってしまうのであれば、つぎは3Dのゲームを作ってみたいという気持ちがありますね。ただ、見た目の部分で言うと2Dの絵が好きなので「3Dだけど見た目の雰囲気は2D」という作品に挑戦してみたいです。
【※】『CARRION』:2020年に発売されたアクションアドベンチャー。プレイヤーが触手の生えた怪物を操作するのが特徴的。
ヨコオ氏:
それって、「HD-2D」のような2Dの見た目を拡張したものなのか、3Dゲームではあるんだけど見た目のトーンが2D調ということなのか、どちらですか?
岡部氏:
後者ですね。見た目の部分でまだ追及できることがあるのではないかと考えています。あとは、自分がどうしても作りたいジャンルで言うと「コマンドRPG」にも挑戦したいですね。
ヨコオ氏:
えっ、コマンドRPG!?
岡部氏:
はい。きちんとお話を書くRPGを作りたいという夢があるので、次回作でできるかはわかりませんが「死ぬまでにはどこかで作りたいな」と思っています(笑)。
ヨコオ氏:
『エンダーリリーズ』のようなアプローチのアートで、3DのコマンドRPGを作るとなるとけっこうコストがかかりそうなイメージがします。
岡部氏:
そうなんです。アセットにかなりコストがかかるので難しくて。ヨコオさんの作品もそのあたりのコスト面はかなり考えて作られていると感じます。
ヨコオ氏:
いちばんお金がかかるのは背景なので、そのあたりのやりくりをどうするかは課題でした。今後、アート面でのブレイクスルーなどがあってローコストで実現できるアプローチが出てきたらいいですよね。
岡部さんは、AAAぐらいの予算をかけて作るような座組を考えたことはないんですか?
岡部氏:
それに関しては、単純に自分の想像が追いついていない部分があるのと、あとはどうしてもその規模になってきてしまうと「自分が作ったもの」にはならない気がするんです。
僕はシナリオを専門としているのかというと、意外とそうでもなくて。デザインや音楽、アートやシステムなど、満遍なく口を出したい人間なんです。そう考えたときに、その規模でのゲーム作りはどうしても現実的ではないように思うんです。
逆にヨコオさんにお聞きしたいのですが、AAAや大きな規模のタイトルにおいてディレクターが好きな方向性で制作したり、心に思い描いたゲームを作ったりするときに大事なことってどんなことなのでしょうか? あるいは、「そもそもそれが可能なのか」といったことをおうかがいしたいです。
ヨコオ氏:
『ニーア』シリーズはAAAではありませんが、実際のチームによっても体制は変わると思います。ディレクターの仕事ってそのチームにいるメンバーによって変わってくるじゃないですか。
岡部氏:
なるほど。
ヨコオ氏:
極論として、たとえばチームにアートがめちゃくちゃ強い人がいるのなら僕自身がアートを見る必要はないと思うんです。
ただ、「アートが強い」というのがどういうことかというと、単に「絵がうまい」わけではない。「コンセプトに合っているか」「音楽やほかの要素と調和しているか」といったように、全体を俯瞰して見ることができないといけません。
これがなかなかたいへんで、ディレクターというのはこういった「だれかが作ったものを叩いて直して調和させる」という仕事だと思うんです。
しかしそれを経て100%自分の思い通りになるかというと、そうはなりません。自分の手では作っていないですし、自分にその能力もないですからね。ただ、製品として出すうえで、少なくとも70点くらいのものにはしようと思っていろいろがんばっているのが実情です。
だから、岡部さんが自分のコントロールできる範囲内でやられているというのはうらやましいです。
岡部氏:
僕は少数精鋭のチームの力のおかげでゲームを制作できているのですが、これがAAAだったりヨコオさんの作品のような規模感になったらどうなるんだろう、と。100名以上は関わっていらっしゃいますよね?
ヨコオ氏:
延べ人数はそれくらいになります。ただ、現実的にコミュニケーションを取れるのは20人くらいなので、コアメンバーの人数だけで言うとそんなに変わらないかもしれません。
僕はどちらかというと、スクウェア・エニックスさんのようなパブリッシャーさんのもとで下請けのデベロッパーとしてやってきたので、その点でままならないことが多かったんです。予算の問題であったり、人員的な問題であったり、そういう悩みが尽きなくて。
岡部さんの場合、アドグローブさんはパブリッシャーとデベロッパーが一体になっている会社さんなわけですよね。そうなると、僕が抱えていたような苦労みたいなものは少ないのではないですか?
岡部氏:
そうですね。僕も過去の経験上、ヨコオさんのおっしゃるような気苦労がありました。「がんばって作ったのに発売できない」といったことを目にしたり、周囲から聞いたりしたことがあります。そういった悩みがないのがいちばんのメリットですし、『エンダーリリーズ』や『エンダーマグノリア』をリリースできた理由もそこにあるかもしれません。
ただこれは「自分が優秀だったからリリースできたんだ」という話ではなくて、そもそもそういった土壌のある環境が少ないということなんだと思います。予算は比較的低くてもある程度の人数のコアメンバーでパブリッシャーと一貫してゲームを作れる環境が少ないから、いいゲームが出にくいという側面はあるかと。
遅咲きだったヨコオ氏と若くしてヒット作を送り出した岡部氏
──おふたりそれぞれの世代で、ディレクターとしての在り方や勝ち筋のようなものも変わってくると思います。岡部さんの世代でのし上がるためにはどういったことが必要なのかというのも気になりますし、ヨコオさんも同世代の中で台頭されるにあたって苦労されたのではないでしょうか?
ヨコオ氏:
僕の世代の話をすると、同い年に野村哲也さんや上田文人さんがいて。パブリッシャーに所属するディレクターの存在が大きかったんです。そんななか僕はかなり遅咲きで、しかもたまたまディレクターになったという。
『ニーアオートマタ』の音楽を担当した岡部啓一さんと「僕たちはだいぶ歳を取ってから売れたのがよかったよね」と、よく話します。『ニーアオートマタ』がヒットして、もしこの先20年くらいゲームを作ることになっていたら、そのあいだ必死に落ちないようにがんばらないといけないけれど、「僕たちはもうあと10年くらいで死ぬから大丈夫だよ」って(笑)。
そういう意味だと、岡部さんは30代で『エンダーリリーズ』というヒット作を生み出したわけで、これから先の人生がすごく大変なんじゃないかと思います。
いま30代ということは、ゲーム業界にいる限りこの先あと30年近くはゲームを作ることになるわけですよね。『エンダーリリーズ』や『エンダーマグノリア』は、やりたいことをできる範囲でやりきったプロダクトだと思うんです。そういった作品を作り、「もうやりきってしまった」状況からつぎのアイデアを絞り出していくことになるので、そういった苦悩があるんじゃないですか?
岡部氏:
はい、まさにそういうところがありまして……。今回のテーマでもある「ダークファンタジー×少女」に関しても、もうやりきってしまったようなところもあるんです(笑)。
ヨコオ氏:
えっ、バイナリーヘイズさんはダークファンタジー作品のブランドだけど、岡部さん的には「もうダークファンタジーはやりたくない!」みたいな!?
岡部氏:
やりたくないと言うとちょっと語弊がありますけど(笑)。ダークファンタジーはかなり広義のジャンルなので、そういう意味ではまだまだやりたいことはあります。
ゲームやジャンルに対するアプローチを変えながら続けていきたい気持ちはぜんぜんあるので、そういった逃げ道を用意しながらこの先もゲームを作っていきたいです。
あとは、ひとつの作品を作るための開発期間を、これ以上は長くならないようにしたいです。1本に5年くらいかけていると、当初作りたいと思っていた熱量も変わってきてしまいますし、プレイ時間的にも2~3年の開発で作り切れるくらいのボリュームにしたいのですが、なかなか難しくて。
ヨコオ氏:
僕としてはもう4~5年もすれば、ゲームエンジンの機能やAIのアシスト技術などの発展によって、工数の問題は徐々に解決していくのではないかと思っています。ただ、開発が楽になったらなったで、参入障壁が下がって、クリエイターの数はどんどん増える。もう真っ赤っかのレッドオーシャンになってしまって、商売にならなくなってしまうような未来が来るのではないかと予想しています。
岡部氏:
たしかに。なんだったら、すでにそうなっている部分もありますよね。とくに3D調のゲームは、アンリアルエンジンで作ったらどれだけシェーダーなどの表現をがんばったとしても「アンリアルエンジンのゲーム」とわかるようになってきています。
そんななかで僕が2Dのゲームを作ったのは、ビジュアル面での差別化が図れるだろうという狙いもありました。今後、いざ3Dのゲームに挑戦してみたらそういった問題も出てくるかもしれませんね。
『ドラッグ オン ドラグーン』の “無茶振り” すぎる発注内容
ヨコオ氏:
『エンダーリリーズ』は、インディーゲームのなかで見るとすごく成功しているタイトルですよね。
インディーゲームの成功って、売り上げの面でもそうですけど、プロダクトの個性やカラーを売り込むという点も大切で、そういう意味でも『エンダーリリーズ』は成功していると思います。そして続編の『エンダーマグノリア』を出すことによって、それがより強固になっていく。

ただそうなると、岡部さんやバイナリーヘイズさんのブランドカラーのようなものがどんどん固くなっていってしまって逆にそこから外に出るのが難しくなるとも思うのですが、そのあたりはどう思いますか?
岡部氏:
そうですね、それに関しては小林社長も言いたいことはあると思いますが、僕自身はジャンル的にも固くなっていく感じはしています。「あと何本出せるのかな」という気持ちにはなりますね。
ヨコオ氏:
それは、モチベーションやアイデアという意味ですか?
岡部氏:
個人的なモチベーションですかね。自分のやりたいことであり、求められていることでもある「ダークファンタジー」「美しい世界」「荒廃した世界と少女」など、そういった自分のリビドーのようなものを消費している感じがしていて、同時にそれが尽きていくのも感じています。
僕はギャグも好きなので、「もっと笑えるゲームを作りたい」と思うこともあります。目の前に作るべきものもあるなかで「未来はどうなっていくんだろう」という不安でいっぱいです。
ヨコオ氏:
僕は受託仕事が多かったので、まず「こういうのを作ってくれ」という前提があるんです。その前提ってだいたいダサいんですけど(笑)。そのダサい前提をなんとか自分なりに納得できるようにしようという気持ちでお仕事をするので、なかなか飽きないんです。
『ドラッグ オン ドラグーン』のときに最初に言われたのは、「『エースコンバット』と『真・三國無双』をくっつけたゲームを作れ」でした。「そんなの作れるわけないじゃん!」というふうに思いながら、それでもお金はいただいているので、自分にどう折り合いをつけるかということばかり考えていました。

岡部氏:
えええええ!
ヨコオ氏:
僕はうわっつらの要件を満たすのは得意なので(笑)。本質はぜんぜん捉えていないけど「言われたことはやったよね」みたいな。
岡部氏:
そう考えると、『ドラッグ オン ドラグーン』はだいぶ要件を満たしていますね(笑)。それを聞くとちょっとまた違った感動を覚えます。
ヨコオ氏:
でも、そういったことを繰り返していると、自分がなにを作りたかったのかわからなくなるところがあるんです。だからいざ「前提なしで好きなものを作れ」と言われると困ってしまって。そういう意味では、岡部さんはわりと好きな事をやれているのでうらやましいですね。
──ヨコオさんのようなスタンスでありながら「個性的なクリエイター」として認知される例って、かなり珍しいのではないでしょうか?
ヨコオ氏:
そうかもしれませんね。ひとつ思うのは、諦めちゃうのはよくないと思うんです。「ヨコオは納得できないかもしれないけど次回作で好きなことをやらせてもらえるようにひとつ我慢してよ」みたいなことを何回も言われるなかで、そのたびに僕は「つぎなんかねえよ」って言っていました(笑)。でも、そういうことを言われると呑んでしまう人はたくさんいると思います。
すべてを否定する必要はないと思いますが、そういう要求を呑んでいくうちに角がとれていって、なにを作っているのかわからなくなることはある。なので、作品のコアになるところにはちょっかいをかけられないように、「そこでくじけない厚かましさ」みたいなものがあるといい気がしますね。
その点、岡部さんは理解者が近くにいらっしゃって、うまくやれているような感じがします。僕が言われたような理不尽な要求のようなものはないのでは?
岡部氏:
そうですね。そういう意味では、理解者に囲まれた環境でゲームを作れていると思います。ありがたいことに、一緒にやってくれているスタッフは10年来の付き合いがあるので、そこに助けられている部分はありますね。とくに「この人はこれができる」とわかっているスタッフがいることが大きいので、逆にコアメンバーが変わってしまったらなにもできなくなってしまうと感じています。
でも、僕がもし「『エースコンバット』と『真・三國無双』をくっつけたゲームを作れ」と言われたら、普通に「できません」と言ってしまうような気がするので、そこはまだまだ甘いのかもしれません(笑)。
ヨコオ氏:
スタッフさんは大事ですよね、わかります。僕はどちらかというと、うまくチームを作れなかった側なので。そう考えると「僕ってチームがない割にはがんばっているな」と思いました(笑)。
岡部氏:
チームがないのにヨコオさんのカラーが作品に出ているというのがすごいですよね。
ヨコオ氏:
『ニーア オートマタ』がヒットしたことによって、みんながわがままを聞いてくれるようになったんです(笑)。それまでも同じようなことは言っていたんですが、みんなが言うことを聞いてくれなくて、「乱暴な暴君」という感じでした。
岡部氏:
『ドラッグ オン ドラグーン』のころから、そのスタンスは変わりませんか?
ヨコオ氏:
そうですね、なんなら僕はディレクターになる前からそういった文句を言っていた人間なので(笑)。『ニーア オートマタ』が当たってラッキーでした。
──逆に、開発メンバーの方たちがヨコオさんの言うことを聞きすぎてしまって、ストッパーがいないような状況にはならないのでしょうか?
ヨコオ氏:
あっ、それに関してはある程度の解決策を見出していて。たしかに、みんなが僕の言うことを聞きすぎてしまうという問題はあるんです。
ですが、そこに対して「ヨコオの言っていることをすべて鵜呑みにしていたら、いつまでたっても完成しない」という量を言うんです(笑)。そうすると、だれかがどこかで止め始める。自然とプロジェクトマネージャーの側からコントロールしてもらうような形になっていきました。
ゲーム作りってこんなに楽しいのにお金までもらえるから狂ってる
ヨコオ氏:
僕はゲーム以外だと、舞台やマンガの原作などをやっているのですが、岡部さんはゲーム以外のメディアを手がけてみたい気持ちはありますか?
岡部氏:
じつは昔、マンガを描いていたことがあるんです。賞にも応募していました。ただ、「いちばん好きなことは仕事にしないほうがいい」という言説ってあるじゃないですか。実際にマンガ家になったらマンガが好きなあまりに病んでしまいそうだと思ったので、マンガ家を目指すのはやめました。
ヨコオ氏:
えーっ! そうなんですね。
岡部氏:
はい。当時2番目に好きだったのがゲームだったので、ゲーム業界に入ったんです。
あとは、ゲーム業界が昔に比べてブラックではなくなってきているというのもありました。マンガ家はいまでも博打のような側面があるので、親に止められがちというか。ゲーム業界は僕の時代でも「ギリギリ社会人扱い」という感じだったので、選択肢に入ったところがあります。時代が違っていたら、もっと別の仕事をしていたかもしれません。
ヨコオ氏:
ゲーム業界もまともな人が増えましたね。いまは会社に泊まることも禁止されていますし、すごく「時代が変わったな」と思います。
岡部氏:
若い人は本当に真面目ですよね。グラフィックやアート関係だったら、ゲーム業界はいちばんの選択肢に入ってくるんじゃないですかね。
ヨコオ氏:
あとは「ビジネスとして成立している」ところもありますよね。僕はいつまでこの「景気がいい状態」が続くのかわからないと思っていますけど。
岡部氏:
(笑)。最近はどうなんでしょう。
ヨコオ氏:
昔から思っていることなのですが、ゲームを作るのって楽しいじゃないですか。「こんなに楽しくて趣味みたいなことをやっているのにお金をもらえている世界はおかしい、どこか狂っている」と思っていて。「この世界はいつかどこかで滅びる」と思っています(笑)。
一同:
(笑)。
ヨコオ氏:
労働ってもっとなにかしらの代償を差し出さなければいけないはずなのに、僕たちはお菓子を食べながら楽しくゲームを作っているわけです。あとになって時代を振り返ったとき「あの時代は狂っていた」って言われそうだと思っています。
岡部氏:
享楽の時代ですか(笑)。でも、なにかしら捧げているものはあると思いますけどね。
ヨコオ氏:
僕から見たら30代の岡部さんは若手のクリエイターですけど、岡部さんから見た10代や20代のクリエイターって、どういう感じに見えていますか?
岡部氏:
若手の子たちはまず真面目で、ゲームが本当に好きな子が多い印象です。ひとつ思うことがあるとすれば、彼らが通ってきたゲームのタイプが僕たちの世代のゲームとは異なってきているということです。
僕はギリギリファミコンを通ってきた世代のため『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』も遊んでいますし、なんとなくゲームの歴史や変遷を体感してきた感じがあるのですが、若手の子たちが通るゲームと言えば『マインクラフト』や『Apex Legends』で。
『マインクラフト』なんて、あれ以上はない極みのようなゲームです。各ジャンルにおいて「一生それだけ遊んでおけばいいじゃん」というような、完成度の高いゲームをいきなり遊べるような環境が用意されているので、「そこから自分がなにかを作りたくなるような気持ちが生まれるのだろうか」とは思います。
ヨコオ氏:
僕も岡部さんも既存ゲームに対する不満が自身のゲーム作りにつながっているという話をしましたが、「若い子たちにはそういったストレスがそもそもない」と。
岡部氏:
そうですね。いまはいいゲームしか生き残れないし、遊ばれない時代ですよね。競争を勝ち抜いたゲームだけやっていればいいというのは、ゲームを探しやすいというメリットもあります。
ただ、僕たちの幼いころは、予算も限られた中で中古ゲームショップでゲームを探して遊んだ時代でしたし、時には「クソゲー」と呼ばれる作品に出会ったりもしました。そういった経験のない子たちが、いまどういう思いでゲームを作っているのかは僕も聞いてみたくなることがあります。
ヨコオ氏:
採用面接などをしていると、岡部さんの世代の人たちは、「賢い人が増えたな」という印象があると同時に「おとなしい人が増えたな」とも思います。これってインターネットなどで、ちょっとはみ出したことをするとすぐ叩かれて炎上するような風潮の影響なのかなと思っているのですが、岡部さん自身としては、ご自身の世代をどう捉えていますか?
岡部氏:
インターネットの影響に関しては、自分よりもう少し若い30代前半くらいの世代から大きく現れていると思います。SNSの「監視社会感」みたいなものが強くて、悪目立ちはできないような意識があると。
ヨコオ氏:
僕らの世代もそうだし、僕らより上の世代もそうでしたが、ゲーム業界は「目立ったやつが勝ち」みたいな業界だったので、岡部さん以下の若い世代がこれからいい世界に変えていってください(笑)。
岡部氏:
そういうところにおもしろさもあったと思いますけどね(笑)。でもいまは自宅で簡単にアンリアルエンジンを触れるのもいいですよね。
ヨコオ氏:
そうですね。僕たちの世代は自宅で3Dモデルに触れたりするのはほぼ不可能でしたからね。そこはうらやましいと思う反面、いまの時代に僕が大学生だったらゲーム会社には就職していなかったと思います。
家でゲーム制作がすべて完結するから、人付き合いをしなくて済むような仕事を探して、ひとりでコツコツとインディーゲームを作ったり。その結果、チームビルディングも大ヒットも望めないような生活をしていたような気がします。
そう考えると、不自由な時代に無理やり就職したことは、僕個人としてはよかったと思います。でも個人的には、こんな無理のある業界はもうすぐ滅ぶと思っているので(笑)。お菓子を食べながらできるような仕事は間違っている(笑)。
岡部氏:
えっ、まさかの「ゲーム業界が終末世界になる」というオチですか(笑)。
ヨコオ氏:
はい。「現実世界の終末世界で岡部さんのような若い世代ががんばっていく」ということですね。これからもがんばってください……ッ。(了)
ゲームのなかのさまざまな要素が発達しきった現在。そこから「新しい遊び」を見つけることは至難の業なのではないだろうか。しかし、『ICO』がそうであったように、遊びのシステムが既存のものだったとしても、そこにテーマやメッセージが存在するから意味がある。
両氏の作品は「荒廃した世界で戦う可憐で儚げな雰囲気の女の子が出てくる」という共通点があり、テーマ性が濃い作品だ。レッドオーシャンなジャンルのなかでほかにない独自性を確立している理由は、既存ゲームに対する「もっとこうしたい」という気持ちだという。
たしかにその気持ちがなければ自分でゲームを作る必要はない。岡部氏の「女の子を助けたい欲」はヨコオ氏を困惑させるほど熱いもので、その欲求が『エンダーリリーズ』を生み出し、続編『エンダーマグノリア』へとつながっているのだろう。
また、ヨコオ氏の「ゲーム作りが楽しい」という発言も印象的だった。「『エースコンバット』と『真・三國無双』をくっつけたゲームを作れ」なんてことを言われたら、普通は「ゲーム作りって難しい……」と自分の作家性を見失ってしまうのではないだろうか。しかしヨコオ氏は『ドラッグ オン ドラグーン』を完成させ、『ニーア オートマタ』という大ヒット作を生み出している。
チームを持たないヨコオ氏のスタンスで「個性的なクリエイター」として認知される理由を聞けたところも本対談の大きな聞きどころだった。