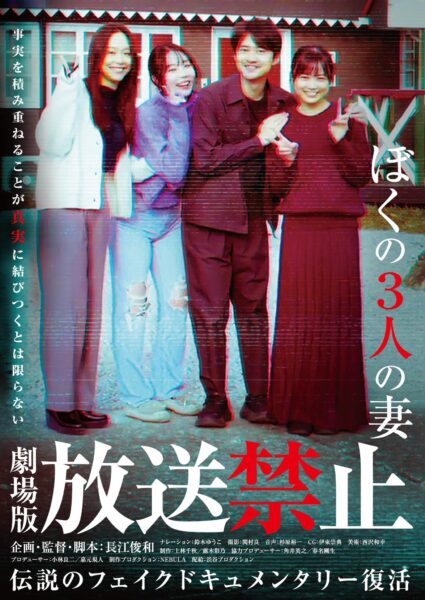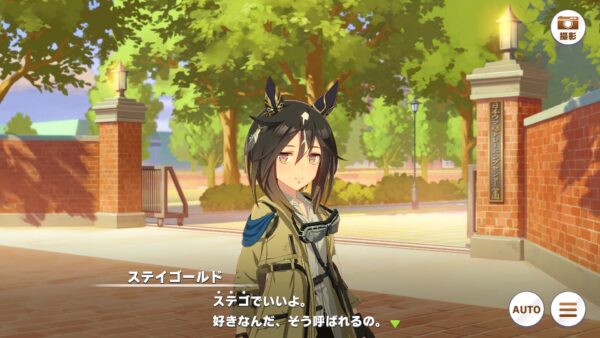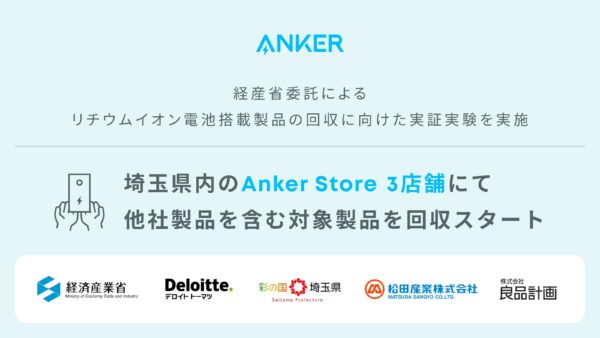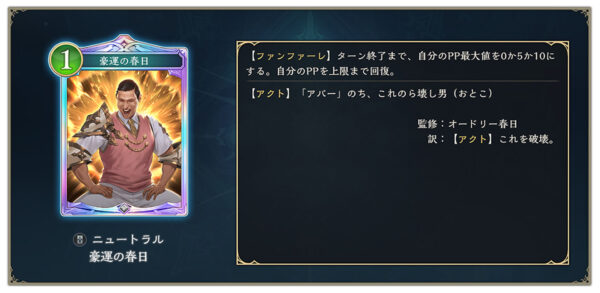あの衝撃から5年。「ゴースト」が再び帰ってくる。
2020年7月に発売された『ゴースト・オブ・ツシマ』は、世界中で大きな驚きと、それ以上の喜びをもって迎えられたタイトルだった。
同作は“元寇”という、世界的には決してメジャーとは言えない出来事を取り上げ、13世紀・鎌倉時代の侍たちが抱えていた「誉」という価値観を見事に描き出した。
そして2025年の10月。サッカーパンチ・プロダクションズは新たなる「ゴースト」の物語を世に送り出そうとしている。
それが、シリーズ最新作『ゴースト・オブ・ヨウテイ』だ。舞台は17世紀初頭・蝦夷地(現在の北海道)。主人公・篤(あつ)は、自身の家族を殺した復讐のため、「羊蹄六人衆」と呼ばれる謎めいた存在を追って、北海道の各地を旅する。
そんな『ゴースト・オブ・ヨウテイ』の発売を10月に控えるなか、電ファミニコゲーマーは『ゴースト・オブ・ヨウテイ』開発陣へのインタビューという大変貴重な機会を得た。
アメリカの開発会社であるサッカーパンチ・プロダクションズが、日本的な人物像、その心の機微、「侘び寂び」のような価値観にいたるまでを、これほどまでに高い水準でゲームへ落とし込めた理由はなんなのか?
また、前作から続投となる「黒澤モード」に加え、『十三人の刺客』など数々の名画で知られる三池崇史氏をモチーフとした「三池モード」や、『サムライチャンプルー』『カウボーイビバップ』を手掛け、国内外のアニメファンを魅了した渡辺信一郎氏にフィーチャーした「渡辺モード」を収録するなど、日本のカルチャーに対するその並々ならぬこだわりは何から生まれるのか?
弊誌では、そうした日本のプレイヤーが誰しも抱くであろう質問をぶつけてみた。
その質問への回答は次のようなものだ。いわく「専門家やアドバイザーとの綿密なコミュニケーションを積み重ねた結果である」、そしてなによりも「本シリーズの制作は日本の時代劇・映画・アニメへの感謝の旅のようなもの」なのだという。
本稿ではほかにも、「最新作の舞台としてなぜ“17世紀初頭の北海道”が選ばれたのか?」「重要な仲間として紹介されている狼と、どのようなコミュニケーションが取れるのか?」など、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』に関する多数の質問を投げかけている。
前作に心動かされた方、そして新たな物語に大きな期待を抱いている方は、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いである。
〇インタビュイープロフィール
ネイト・フォックス氏……サッカーパンチ・プロダクションズ クリエイティブディレクター ジェイソン・コーネル氏……サッカーパンチ・プロダクションズ クリエイティブディレクター
「『ゴースト・オブ・ツシマ』シリーズの開発は、時代劇、映画、アニメへの感謝を示す旅である」
──『ゴースト・オブ・ツシマ』はナラティブ、アクション、アートといった目に見える部分はもちろん、人物の機微や「侘び寂び」といった日本人でも表現することが難しい内容にいたるまで、驚くべきクオリティで描かれていました。
アメリカのゲームスタジオであるサッカーパンチ・プロダクションズが、いかにして鎌倉時代の日本への理解を深め、圧倒的クオリティーでゲームとして表現できたのかをお聞かせください。
ジェイソン・コーネル氏(以下、コーネル氏):
私たちとしても、世界中のプレイヤーに『ゴースト・オブ・ツシマ』を楽しんでいただけたことを光栄に思っていますし、特に日本の皆様に歓迎していただけたということは非常に嬉しいことだと考えています。
『ゴースト・オブ・ツシマ』の成功は、文化面をはじめとした各方面でのアドバイザーからの知識や考証が大きく寄与しています。神道や仏教といった宗教面はもちろんのこと、対馬の地理や文化。日本独自の振る舞い、所作。戦闘に関してもそうですし、歴史的な考証も含まれています。
皆様に喜んでいただけるものができたのは、そうした各方面について、さまざまな方の助けを借りることができた結果ではないかと思います。これは『ゴースト・オブ・ツシマ』だけでなく、最新作である 『ゴースト・オブ・ヨウテイ』についても同じことが言えます。
──先日公開されたState of Playの映像のなかでは、ゲーム中の画面効果や演出が変化する特殊モードとして、前作に引き続いて「黒澤モード」の収録が発表されたほか、あらたに「三池モード」と「渡辺モード」の存在が明らかとなりました。
アニメ『サムライチャンプルー』などの監督である渡辺信一郎氏にフィーチャーした「渡辺モード」に関しては、ゲームジャンルに留まらず、多くのアニメファンからも多くの反響がありました。これらのモードを本作に収録しようと思ったきっかけはなんだったのでしょうか?
コーネル氏:
前作である『ゴースト・オブ・ツシマ』も含め、本シリーズの開発は日本の時代劇や映画、アニメなど、「私たちが影響を受けたジャンル・作品に対する感謝の気持ちを示す旅」のようなものだと考えています。
そうした想いを表すひとつの方法として、前作では「黒澤モード」を、今作では新たに「三池モード」と「渡辺モード」を追加する形で、ゲームのなかにそれらのエッセンスを盛り込みました。そのため、ファンの皆さんにこれらの新しいモードを楽しみにしていただけているというのは、我々としても喜ばしい限りです。
──それぞれのモードの特色を教えてください。
コーネル氏:
前作をプレイした方なら分かるかもしれませんが、「黒澤モード」の大きな違いはそのビジュアルです。もちろんサウンドにも違いはありますが、モノクロ時代の黒澤映画の雰囲気を再現するというのが、このモードの特徴になっています。
「三池モード」は、血のなまぐささ、血の表現が強化されることから、戦闘の臨場感をより一層楽しんでもらえると思います。前作『ゴースト・オブ・ツシマ』の頃から、『十三人の刺客』の戦闘シーンに大きな影響を受けていますので、本作ではさらに強くそういった要素を体感していただけると思います。
「渡辺モード」において特徴的なポイントは音楽です。もともと、アニメジャンルとゲームジャンルはファン層に共通する部分があると考えています。『ゴースト・オブ・ツシマ』でも、開発チーム内で楽曲のローファイリミックスを作って遊んでみたことがあり、「ローファイとゲームは意外と相性がいい」ということを発見しました。そこで、本作では正式にローファイな楽曲を聴きつつゲームをプレイできるようにしたんです。
狼は仲間ではあるがペットではなく「蝦夷の大自然の象徴」。絆を育むことで“新たな協力方法”がアンロックされる
──本作では、篤の重要な仲間として一匹の狼が登場していますね。この狼は戦闘面で頼もしい活躍をみせてくれそうですが、戦闘以外の部分でも篤と狼の交流はおこなえるのでしょうか? 具体的には、一緒にご飯を食べたり、その体を撫でたり、ともに温泉へ浸かったり……といったことは可能ですか?
ネイト・フォックス氏(以下、フォックス氏):
本作に登場する狼は、まさに蝦夷の大自然の象徴とも言えます。私たちも狼は大好きですが、注意して欲しいのは、この狼は篤の仲間ではあっても、彼女のペットではないということです。

State of Playの映像でもすこし映っていましたが、本作では狼とのストーリーを進めていくなかで、彼との絆を深めていくことができます。それにともなって、狼との「新しい協力方法」もアンロックされます。
この新しい協力方法が具体的にどういうものなのかは、この場では伏せさせていただきますが、「野生動物としての狼との交流」を楽しんでいただけるものになっていると思います。
──State of Playの映像では、美しい自然のなかに佇む侍たちや地蔵など、和人【※】的な要素やモチーフが数多く配置されていました。篤の幼少期の記憶からも、彼女やその一家が和人の文化圏で暮らしていたことがうかがえます。
一方でPSブログ上では、開発チームの皆様が北海道でおこなった現地リサーチについても公開されており、先住民族・アイヌに関する展示を撮影した画像なども掲載されていました。当時の蝦夷地に暮らしていたアイヌの人々やその文化は本作のなかでどのように表現されているのでしょうか?
※和人
アイヌの人々と対比して、日本列島本土に暮らす人々を指す言葉。
コーネル氏:
ストーリーという点では、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』の物語は完全にフィクションであり、メインストーリーである篤の復讐の物語に、アイヌの人々が直接的に関わってくることはありません。ただ、ゲーム体験の一部として、アイヌの人々やその文化が登場することになります。篤はアイヌの人々との出会いを通じて成長していきますし、篤とアイヌの人々との交流のなかで、アイヌの美しい文化も垣間見えるようになっています。
実のところ、本作の舞台を北海道にしようと決めた時点では、私達はアイヌの人々のことを詳しく知っているわけではありませんでした。しかし、作品を作っていくなかで、その存在に対してより詳しく知っておく必要があると考え、アイヌのコミュニティと接触し、交流を図りました。

また、専用のアドバイザーに文化的な監修をお願いしたほか、質問にもあったように現地へ実際に出向いて、貴重なお話を聞かせていただき、博物館の展示なども通じて当時の文化を学びました。
作品を作る上でも現地の方と相談を重ね、そうした文化を「ゲームのなかでどのように表現するのがよいか」については何度もフィードバックをもらいながら、ゲーム内に要素を盛り込んでいきました。
当時の人々にとっての“フロンティア”としての北海道を描きたかった
──過去に実施されたインタビューのなかで、開発チームの方が本作を「日本の時代劇と西部劇の融合」と表現されていました。先述の「黒澤モード」を始め、本作の“時代劇”としての側面はすでに数多く紹介されていますが、本作の“西部劇”としての側面はまだあまり語られていない印象です。
本作の西部劇的な要素としては、どういったものが存在しますか? また、時代劇と西部劇を融合させることで、作品にどのような効果をもたらしているのか、お聞かせください。
コーネル氏:
本作は、日本の地の果てである広大な蝦夷地というものにインスパイアされる形で、制作がはじまりました。
そのうえで、「時代劇と西部劇の融合」がゲーム内で感じられる部分としては、楽曲が挙げられます。日本の伝統的な楽器である三味線や箏、尺八を使いつつも、どこかウェスタンな、西部劇的なテーマも組み合わせています。

そもそも、時代劇と、ジョン・フォードなどを始めとする西部劇には、非常に多くの共通点があると考えています。たとえばふたりのキャラクターが決闘をおこなう際の緊張感は、どちらのジャンルでも広く見られるものです。
西部劇と時代劇は、シネマの歴史において半世紀以上にわたって、相互に影響しあってきました。ゲーム内では主に時代劇の影響が色濃く出ているのですが、そのなかでも西部劇のテイストも少し楽しんでいただける作風になっていると思います。
──『ゴースト・オブ・ツシマ』では元寇という形で異文化と対馬の接触がテーマとして描かれました。最新作である『ゴースト・オブ・ヨウテイ』では、和人による蝦夷地開拓という形ではありますが、やはり異文化と日本の接触点が舞台となっています。
日本の歴史にはさまざまな出来事が存在しますが、そのなかでも異文化と接触する時代や場所がシリーズの舞台として選ばれているのには、なにか理由があるのでしょうか?
フォックス氏:
確かに、『ゴースト・オブ・ツシマ』は、フィクションではありつつも、元(モンゴル)による対馬侵攻という歴史的な文化衝突からインスピレーションを得ています。しかし、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』は文化衝突の物語ではありません。
『ゴースト・オブ・ヨウテイ』で描かれるのは、篤による羊蹄六人衆への復讐の旅です。その旅の途中で出会うアイヌの人々は敵ではなく、彼らと主人公・篤との間に育まれるのは敵意ではなく友情です。
本作が蝦夷地をゲームの舞台として選んでいるのは、ひとつにはこの場所がこれまでビデオゲームであまり取り上げられることのなかった場所だからであり、そしてここが当時の侍にとっての危険で美しいフロンティアだったからです。
本作の舞台となる1603年は、関ケ原の戦いが終わり、徳川幕府のもとで一定の平和が訪れた時代です。しかしその結果のひとつとして、多くの侍が職を失うことにもなりました。そこで彼らは新たなチャンスと生活を求めて、北を──すなわち蝦夷地を訪れた、というのが本作が描く世界観です。
当時の蝦夷地はまだ人も少なく、和人にとっては幕府のような公権力の及ばない、言ってみれば無法の土地です。多くの野生動物が闊歩する、美しくも厳しい手つかずの自然が色濃く残されている場所でもあったでしょう。私たちとしては、そうした当時の厳しい自然の世界を、フィクションとしてのオープンワールドで表現したかった、というのが最も大きな理由です。
本作は歴史にインスパイアされたフィクションであり、そうした経緯も踏まえつつ、当時の人々を生き生きと描けるように努力しました。北海道は息を呑むほど美しく、険しく、また1603年においては危険な荒野でもありました。みなさんにも私たちが描いた蝦夷地の雰囲気をじっくり味わっていただければ嬉しいです。
もちろん、これまでの質問のなかでもお伝えしているように、和人だけでなくアイヌの人々との交流も、ゲーム内では体験することができます。そういった部分もふくめて、本作を楽しんでいただければと思います。
コーネル氏とフォックス氏へのインタビューのなかで強く伝わってきたのは、「日本文化」への多大なリスペクトだ。
さまざまな方面でアドバイザーと連携し、必要とあらばゲームの舞台となった土地へ直接出向き、現地の環境や文化を取材する。それに加え、映画やアニメといった創作文化に対してのリスペクトとして「黒澤モード」、「三池モード」、「渡辺モード」を用意したというのだから、その情熱は並々ならぬものだろう。
そういったリスペクトや情熱を糧として描かれる美しく、険しい北海道を舞台に、篤の復讐の物語はどのような展開を経て、いかなる結末に辿りつくのか。ぜひ読者の皆様も、筆者とともに期待に胸を膨らませながら、本作の発売を待ってほしい。
『ゴースト・オブ・ヨウテイ』は2025年10月2日より発売予定。対応プラットフォームはPS5となっている。