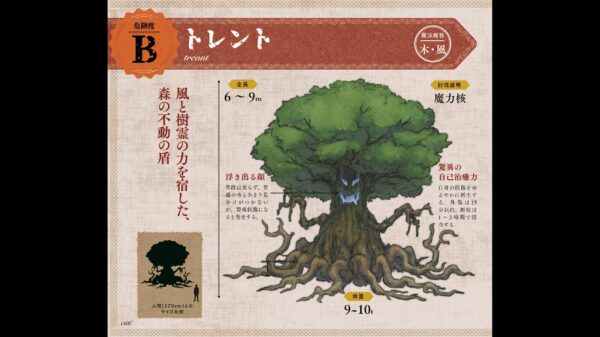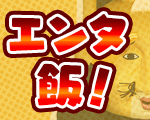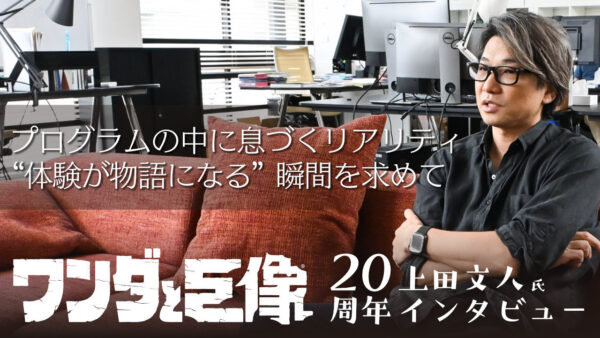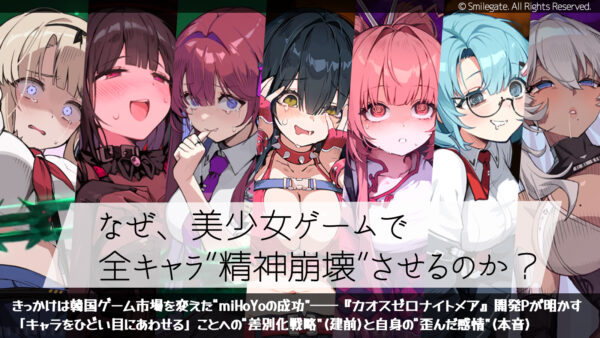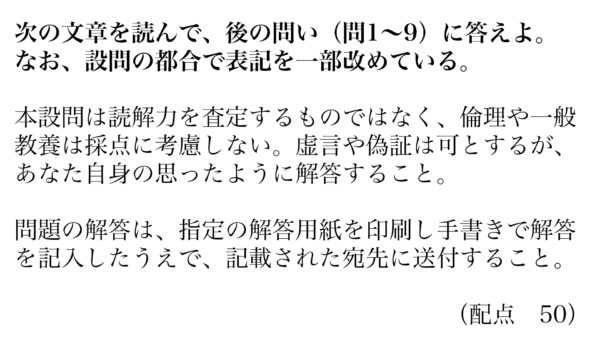『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズを遊ぶことは、「ゲーマーが健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のうちに含むべきだ。
それくらい本シリーズはおもしろいし、プレイできること自体が尊い。
筆者は第1作である『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』のリリース当初から本シリーズをプレイしているが、20年弱経過した今も前作をそれなりの頻度でプレイしている。
致死的な空間異常(アノマリー)がはびこり、ミュータントが跋扈し、さまざまな派閥の陰謀が渦巻くあの恐ろしくも美しい「ゾーン」の空気と、本シリーズならではのハードコアなゲームシステムの調和から得られる体験は、ほかのどんなタイトルにも代替できないからだ。

『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズは「ハードコアFPS×オープンワールドRPG」路線の元祖と言えるのではないだろうか。
部分的に近い要素を持つタイトルは当時から複数存在したが、物語を逸脱して略奪しまくることもできるオープンすぎるワールドと、スキルやステータスの概念がなく簡単に死ねるFPSが同居している例は『S.T.A.L.K.E.R.』以前を探してもなかなか見つからないだろう。
筆者は今回、11月20日に発売予定のPS5版『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』を2時間ほどプレイする機会をいただいた。結論から言うと、やっぱり “神ゲー” だ。
読者の皆さんにはぜひとも遊んでいただきたい。PS5を持っていない方は、なんとかして手に入れていただき、さわっていただきたい!
1点だけ正直に申し上げると、筆者はコントローラー操作にはまったく慣れていないため結果として、2時間の中で30回くらい死ぬことになった。しかし、それがむしろ「非常に楽しめた」ということは特筆したい。これは筆者があまりにもゾーンに毒されてるせいかもしれないが、それだけではないはずということを本稿では釈明させてほしい。
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、前作の正統な続編としてプレイできるだけでありがたい
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』(以下、S.T.A.L.K.E.R. 2)は、過去の3部作『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』、『S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky』、『S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat』の続編である。物語はこの3部作の後日譚に当たるため、シリーズを知っているとニヤリとする要素しかない。
しかし、前提知識がなくても十分におもしろいので気にしなくていいだろう。でも、気になったらぜひ遊んでほしい。本作が熱狂的に支持されている理由のひとつは重厚なストーリーにあるからだ。
本シリーズは原子力発電所の事故により奇怪な変貌を遂げた「ゾーン」と呼ばれるウクライナのチョルノービリを舞台に、そこでしか手に入らない希少な「アーティファクト」を求めて不法に侵入したストーカーたちの生活が描かれる。タイトルにもなっている “ストーカー” は「密猟者」といった意味合いだ。
『S.T.A.L.K.E.R. 2』の主人公ものっぴきならぬ理由がありストーカーとなるのだが、前作に増して謎の多いスタートになっていた。常識に反するヤバいものを手に入れ、さまざまなものを失い、そこから物語が始まる。詳しくはぜひともプレイして確かめてほしい。
今回の体験会ではニューゲームのセーブデータとゲーム中盤のセーブデータでそれぞれプレイさせてもらえるという至れり尽くせりの内容だったが、序盤はストーリーの開示とチュートリアルがメインだ。プレイ面でいえば、ピストル一丁でゾーンに放り込まれるので「サバイバル感」が非常に強い。まさに洗礼を受ける瞬間と言える。
いきなりミュータントの群れが襲ってきたり、闇夜に紛れてバンディットが襲撃してきたりする。カジュアルに存在するアノマリーも、難易度設定や装備次第で触れただけで焼けたり感電したりで軽く死ねる。
ここで言いたいことはひとつしかない。
これが、いい。
本作の魅力はこういった困難に対して適応しながら、まさにストーカーとして成長していくことにある。ゲームの中で強くなるのは装備だけで、経験値を獲得して “成長” するのはプレイヤーなのだ。逆にいえば装備が多少弱くても、ウデマエさえあればなんとかなる局面も多数ある。ウデマエに自信がなくても、敵を罠にはめたり迂回したりと知恵を活かすチャンスもある。
そのことを、筆者は今回の体験プレイを通して改めて感じることができた。
というより、痛感したかもしれない。
なので、無理は禁物だ。本作では前述したように難易度設定ができる。筆者はストーカー自信ニキだったので、コントローラーでのAIMに慣れていないにも関わらず真ん中の難易度を選んだのだが、いま振り返るとやや早計だった。じっくり遊ぶならそれでもいいし、なんなら最高難易度でもいい。ただ、2時間という短い時間で本作を堪能するのであれば、恐れず難易度は下げるべきだったかもしれない……。
『S.T.A.L.K.E.R』シリーズは、プレイヤーの成長も重要というハードコアな仕様だからこそ救われる
先述のとおり本作は序盤からちゃんとハードなのだが、筆者はもうひとつの中盤からのセーブデータでとにかく死にまくった。
本作では装備が整ってくるとサバイバル感はそのままに、戦闘の味が濃くなってくる。より効率的に敵を倒せるようになる一方で、やっぱり死ぬときはあっさり死ぬ。
中盤のセーブデータでは「沼地」という名前そのままのフィールドで、4カ所のビーコンを停止させるため拠点を攻略するミッションをプレイできた。当然攻略する順番も攻め方も自由だ。
手元にはゲーム終盤まで通用するような現代的なアサルトライフルと、ミュータント相手に効果てきめんなショットガンがあり、インベントリにはワンマンアーミーかというくらい弾薬と回復キットが満載だ。体験プレイでここまでもてなしてくれることに心躍ったが、実際のところはここからノンストップのデスループが始まった。
筆者が苦戦したのは多数のゾンビがはびこる放棄された基地の攻略だ。本作のゾンビはシリーズ伝統だが、なんと銃を撃ってくる。走らないのだけが唯一の救いだ。といっても正直、ゾンビだけならまだなんとかなる。精神攻撃を仕掛けてくるミュータント“コントローラー”までセットになっていたのが、かなりキビシイ。
本来ならNPCのバンディットとミュータントは敵対関係にある。そのため、バンディットとミュータントの大乱闘が発生し、労せず戦利品を手にできてオイシイなんてこともゾーンを散策していると起こりうる。生態系のシミュレーションが成されているのも本作の魅力のひとつだ。
しかし、ゾンビとミュータントは友達だった。
ミュータントの精神攻撃に対しては「視界に長く入らない」「薬剤で耐性を付ける」といったさまざまな対処方法がある。しかし筆者は震える新兵よろしく手元がおぼつかないので、戦闘中に適切な対処がぜんぜんできない。
攻める方向を変えようだとか、とにかく突っ込んでミュータントを最初に始末しようだとか、いろいろ策を巡らせるのだが、自分が下手すぎて死ぬ。それでもトライを重ねるごとにルートも最適化され、AIMもあったまってきて「なんかやれそう、でも最後の一手が足りない……! でも届きそう……!」と没頭しているうちにハッとした。
本作ではゲームオーバー画面で死亡回数がカウントされるという親切機能(?)が搭載されているのだが、気づけば20回を超えていた。
「記事を書くために来たのに、同じ場所で何十回も死んでいるだけでは何も書けないぞ」と思い至りその場を離れた結果、しばらくして高性能なスナイパーライフルを手に入れることができた。しかし、「こいつで遠距離から一方的に狙撃すれば攻略できるかもしれない」とウキウキで舞い戻っている最中に体験会の終了時間。
ということで、1敗である。
悔しい思いを胸に帰宅してPC版を起動したが、果たしてこれはリベンジになるのだろうか?
同じ拠点に夢中になっていなければ、適切な装備を早期に入手できてもっとあっさり攻略できたかもしれない。急がば回れ、そういうこともあるだろう。一方でゴリ押し続けていても、攻略できたかもしれない。ちゃんと上達はしていた……。
もちろん、通常のプレイであれば、拠点に帰って装備選択からやり直すという手もある。インベントリいっぱいにグレネードを詰め込んで爆撃なんて戦術もナシではないだろう。めちゃくちゃいい装備を手に入れるまでずーっと寄り道するのもイイ。結局、本作において重要なのは「いかにして戦うか」なのだ。
また、本来のゲームプレイでは銃弾が有限なだけでなくアーマーや武器も損耗するため、修理費や経費などといった現実的な問題と戦うリソースマネジメントも必要になる。
しかし考えを巡らせなくても上手くやれば「安く済む」し、そうなると敵から奪った物資で「利益が出る」ので、総体的にウデマエを高める意義がデカい。ここを突破すればオイシイ思いができると信じてありったけを投入する賭けに出るのもまた一興。
どういうスタイルでプレイするか、自分自身がどう成長するかを本作では自由に選ぶことができる。これほど恵まれていることはない。
本作はハードコアだからこそ自由でおもしろい。このあたりは昔から変わっていない。昨今だと特に脱出シューターをプレイしている人にとってはおなじみの要素かもしれないが、そのジャンル自体が『S.T.A.L.K.E.R.』に影響を受けているということは否定できないはずだ。
ちなみに、慣れ親しんでるPC版を遊んでいても筆者はちゃんと死ぬ。でも、ロードすればいくらでもトライはできる。どちらかというと、拠点に帰ってから収支が赤字になってることに気づく方が怖いので、世知辛い。
でも、やっぱりそれもおもしろい。これはもうひとつの人生を歩むに等しいと言いたい。レベル制ではない「ハードコアFPS×オープンワールドRPG」だからこそのおもしろさだ。これは全人類に知ってもらいたい。そして、その本質はプラットフォームに左右されない。
狂った世界が好きな人にはぶっ刺さる、そんなゾーンに一生浸っていたい
本作が、1972年のSF小説『路傍のピクニック』に強く影響を受けているのは有名な話である(後に『ストーカー』の名で映画化もされている)。「ゾーン」が登場し、「ストーカー」がいて、致死的な空間異常があり、貴重な遺物が存在したりと、ゾーンの場所と発生の原因は異なるものの多くが共通している。
なぜチョルノービリが舞台となっているのか、原子力発電所事故との関連性は一体なんなのかといった本シリーズのオリジナル要素は前3部作で語られている。終盤でゲームの中の謎が一気に解消されたときのキモチは今でも思い出せるが、なんともいえない。これはもう、“味わい” と表現するほかないだろう。
物語としてのテーマをひとつに絞ることは難しいが、俯瞰すると本作は多様な価値観を持つ人々が未知に挑む群像劇のようでもある。それが超常現象を中心に回っているので、個人的には最近だとシェアードワールドの『SCP財団』っぽさもあると感じている。
ポストアポカリプス、サバイバル、ミリタリー、ゾンビ、ミュータント、超常現象、ミステリー、陰謀、巨大遺構……など、筆者の好きなものをサッと思いつくだけ挙げてみたが、だいたい『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズに詰まっている。たぶんもっとある。
これはむしろ青春時代に『S.T.A.L.K.E.R.』に出会ってしまったせいでそうなったのかもしれない。
少しでも琴線に触れるものがあったら、ぜひ本作をプレイしてほしい。PS5をお持ちの方はもうすぐだ。