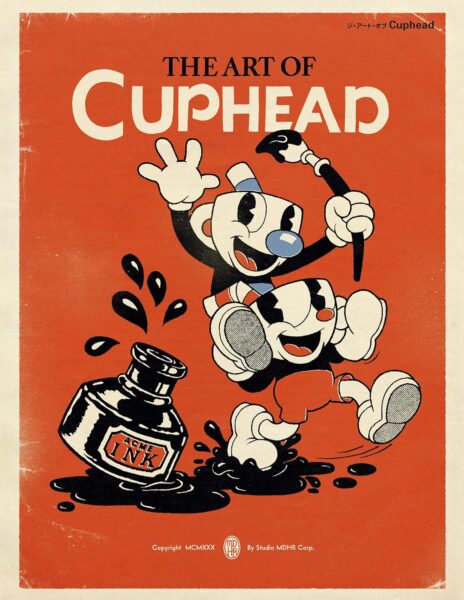戦国時代のVRコースターができるまで
――プログラムは外注とのことですが、ソフトはどのように作られているのですか?
襟川氏:
ソフトに関しては私を含めて誰も、実はVRのことをあまりよくわかっていないところからのスタートだったんです。
だいたい、これから作ることになる社員がまだ、VRを見たことも触ったこともなかったんですから。ちょうどバンダイナムコさんがVRの施設【※】をやっていたので、そこへ見に行きなさいとか、ウチの社員でOculus Riftを持っている人間がいたので借りて、これをすぐ買いなさいとか、とにかくVRと名のつくものはなんでも見てきなさいと。
※VRの施設
バンダイナムコエンターテインメントは、VRアクティビティ体験施設「VR ZONE Project i Can」を、東京・お台場において2016年4月〜10月の期間限定で運営していた。その後、新宿・歌舞伎町で常設施設となる「VR ZONE SHINJUKU」を、2017年7月14日よりオープンしている。
ただ私の頭の中には、VRでこういうものを作りたいというのはすでにあったので、ここで何が出てきて、ハードのほうはどんな動きをするのかという情報カードを作成し、みんなに説明しました。ソフトの作り方を全員で共有するための、フォーマット作りです。
ジェットコースターは、VRならどこでもよく見かけます。女性も好きなものだし、これは絶対に作りたいんだけど、他のコースターと同じなら当社でやる意味はありません。コーエーテクモらしく戦国時代を舞台にした、他のどこにもないジェットコースターを作ろうと。

あとはやっぱりホラーも欲しいですよね。外部の方からホラーのストーリーができてきたので、それをどんどん手直しして、人手不足なのでキャラクターやセリフも自分で作って、VRならではの要素を詰め込んでいったんです。ムカデが頭の上のほうからチョコチョコとやってきて、プレイしている人の頭の上に、実際にバサッと何かが落ちてくるとか。

私自身はホラーなんて怖くて怖くて、大嫌いですけど、仕事ですからそこは切り換えて。好きじゃないからこそ、どういうものが怖いのかというのがわかります。ただバッと驚かすだけじゃなくて、心理的にあおり、恐怖の絶頂で思い切り驚かすとか。
人気ゲーム群のVR版ができるまで
――すでに発表されているタイトルには、コーエーテクモさんの人気タイトルのVR版もありますね。先ほど話題に出た『真・三國無双』【※1】もそうですし、競馬ゲームの『ジーワンジョッキー』【※2】も。
襟川氏:
『真・三國無双』はラッキーでした。おっしゃるように既にVRデモ版がありましたので、これはなんとか社内で作らせれば早いと。でも襟川(陽一氏)たちにバレたらうるさいので、探りを入れました。まず現場に行って、「ねぇ、無双のVRのことだけど。あれちょっと直せば商品になるけど、どう思う? 30%の利益は保証するから、2〜3人をひと月でいいから誰かいない〜!」と。

なんと、聞いてみるものです。「次の作業まで1〜2ヵ月なら人を出せます」とプロデューサーのありがたいお言葉を聞いたからにはこっちのもの。「よし! あちこち気に入らないところを絶対直して、私の思い通りに作り直させよう。ひと月分増えたって知〜らないっと」、ということにして。
何回も現場にはりつき、できあがったら、まー社内外の評判が良いこと。「ヤッターッ」と思いました。チームの皆様、利益が出たらたっぷりロイヤリティをお支払いいたしますからね。
※2 ジーワン ジョッキー SENSE
騎手になりきって競走馬を乗りこなすアクションゲームをVRで再現。実際に馬の背中に乗っているかのようなリアルな振動や風を感じながら、激しいデッドヒートを繰り広げる。
――『ジーワンジョッキー』の開発についてはどうでしたか?
襟川氏:
私は以前、競走馬をゲームの研究のために持っていました。馬主としては襟川(陽一氏)ですが、自分でも動物が好きですからよく馬にも乗っていたことがあります。そういう本物の感覚を知っているので、これは絶対にVRでも活かしたいと思ったんです。
そもそも競走馬を買ったのは、競馬ゲームを作っていたからなんです。競走馬がどんな暮らしをしているのか。調子が悪くなってきたら笹針を打つとか、そういったことをゲームに活かそうと思って、馬を飼い始めたんです。そうしたら、初めて買った馬がいきなり優勝してしまった。その後に買った馬も重賞レースで優勝して、牡馬で1位になるなど、たくさん賞金を稼いでくれましたが、レースはほとんど見に行けませんでした。
それに競馬ゲームなら、すでに開発用の素材はありますから。VRのチームに、たまたま競馬のゲームを作っていた社員がいたのも幸運でした。

でも最初に競馬のゲームができた時は、ヘンなものができちゃって(笑)。ゲームを作っている社員は、実際に馬に乗ったことがないんです。馬って意外と大きいんですよ。なのに、馬が小さくて「こんな迫力がないのはダメ! もっと大きくして!」って。
それから今度は、風や雨や雪を降らせたいと。扇風機を持ってきて風を出してもらい、イスを動かしたら、これがいい臨場感なんですよ。そんなこんなで、色々と試行錯誤しながら作っていったんです。
男性のプッシュで実現した『DEAD OR ALIVE Xtreme Sense』
襟川氏:
そうやってゲームを作っていたら、襟川(陽一氏)が「『DEAD OR ALIVE Xtreme』がすでにVRであるんだから、アレも入れれば」って言うんです。他の社員もそう言うんですけど、「冗談じゃないわよ!」って。品がなくてふさわしくないと、断ったんです。

――えっ!? それはもったいないですよ。
襟川氏:
男性はみなさん、そうおっしゃるんですよね(笑)。
その後、この業界とはぜんぜん関係のないお客様がいらしたんです。建設業界だったかコンサルタントだったか、とにかく紳士然としたお二人で。背広をバリッと着て。その方とVR センスの話になって、「水着姿の女の子がブランコに乗ったり、綱引きでバストが揺れたりするソフトを入れたい」という社員にダメと言ったと話すと「えっ、それがいちばん売れそうですよ」とおっしゃるんです。
ゲーマーでもない紳士然とした方々がそんなことを言うんですから、もうビックリしちゃって。目から鱗ですよ。こんなジェントルマンまで言うのなら、これは本当だろうと。この歳になって男性目線と女性目線の違いを認識するなんて遅すぎました。頭を切り換えて「『DEAD OR ALIVE Xtreme』やる!」とチームに伝えました。
※「やわらかエンジン」版と通常版の比較検証資料。
――それで『DEAD OR ALIVE Xtreme Sense』が、ラインナップに加わったんですね。では、今後はVRでどんなソフトを作ってみたいと思われますか?
襟川氏:
何人かで対戦するVRのゲームも、すごく面白いと思います。男性のお客様向きです。開発が大変ですけどね。でも自分でそれを遊びたいかというと、そうじゃないんです。対戦でバンバン撃ち殺したりするのは、あまり好きじゃないですから。
自分で遊んでみたいのはジェットコースターやスキューバーですね。あとは『金色のコルダ』【※1】や『ときめきレストラン☆☆☆』【※2】のキャラクターと一緒になって、その空間を楽しめるようなものも作ってみたいですね。

ルビーパーティーが手がけるネオロマンスゲームの1つで、クラシック音楽を題材にした女性向け恋愛・育成シミュレーションゲーム。2003年に第1作が発売されて以降、これまでにナンバリング4タイトルとソーシャルゲームがリリースされている。最新作『金色のコルダ2 ff』が12月21日発売予定。
(c)Konami Digital Entertainment
(c)コーエーテクモゲームス

『ときめきメモリアル Girl’s Side』シリーズと同じ「はばたき市」を舞台に、レストラン経営と男性アイドルたちとの恋愛を楽しめる、iOS/Android用の女性向け恋愛シミュレーションゲーム。KONAMIから2013年3月にリリースされたが、2014年8月よりゲームの運営がコーエーテクモゲームスに移管されている。
©Konami Digital Entertainment
©コーエーテクモゲームス
始まりは1〜2分で書いたメモだった
――お話を聞いていると、かなり精力的にVRゲームづくりをされていますよね。
襟川氏:
ソフトもハードも何もかも一緒に作っていますから、飽きないです。頭の中ではゲームを考えながら、椅子をデザインし、外部の方に発注しながら、ビジネスモデルも作成する。全部同時進行です。
VRというのは、モニターで見ているのと実際にVRで見るのとは、ぜんぜん違うんです。何回も調整が必要ですから、時間がかからないシステムを考案したり。
でも、私は他にも仕事があるわけです。業界団体の仕事もあるし、経営会議もあるし、さらにはファイナンスの責任者ですから。親や家庭のこともある中で新機軸を打ち出すには、いかに短い時間で即断、即決、行動するかにかかっています。アドベンチャーゲームです。ですが、社員もよくついてきてくれます。
――ハードもソフトも、本当に襟川さんご自身がかなり主導されているんですね。
襟川氏:
「なんで私が?」って、みなさんそうおっしゃるんですけど、私はもともと美大を卒業してデザイナーをやっていましたから、昔からいろんなものを自分で作っていたんです。オリビア・ハッセーさんと布施明さんが結婚するきっかけになった新しい口紅のディスプレイ台も、全国のデパートに使用されますから偏光板を使って大変な思いをして作りました。【※】

(画像は布施明のFacebookページより)
私は経営者であり、デザイナーです。自分の頭に描いたものを形にして、推進していくのが仕事です。VR センスを始める際には、メモ帳に筐体のラフスケッチを1〜2分で描いたんです。このラフスケッチが、最初の出発点ですね。

VR センスの筐体を作っている中国に行った時は、ノコギリください、紙ください、セロテープとハサミくださいって、その場で直しました。VR センスのロゴが必要なのでロゴを作って、位置なども決めましたから、仕事は早かったです。数時間で終わりました。
――ノコギリまでご自身で扱ったんですね(笑)。
襟川氏:
会社としてネットワークゲームを作り始めた時は、私が自分でやろうとは思いませんでした。その時は社員がやってくれたので、襟川(陽一氏)もいるし、別に自分がやらなくてもいいわけですよ。女性向けのゲームの時は、他に誰もやる気がなく、やる意義があったので、自分でやりました。今度のVRもそれと同じですね。
まして、みんなが反対しているから(笑)。反対しているということは、今後VRが本格的に普及してしまったら、後から遅れてのこのこ出て行くことになりますよね。それでは遅い。
高齢者にVR旅行を楽しんでもらいたい
――今回のVR センスは、筐体をゲームセンターなどに設置して、そこでプレイするという形です。襟川さんとしては家庭でVRを楽しむよりも、アーケードなどのロケーションビジネスで展開するほうが、より可能性があると考えているのでしょうか?
襟川氏:
私はそうではありません。むしろ家庭にこそ入れたいと思ったんです。なぜかというと、筐体を家庭に入れて個室にしてしまうの。そうするとVRもできるし、カラオケルームとして中で歌を歌ったり、楽器を練習したりもできるし、たばこを吸う世の父親がホタル族にならなくて済みます。ドアも付けられますから。
ところが社内のアーケードゲームを運営している人たちに、扉を付けちゃいけないと言われたんですよ。なぜなら安全性の点検ができないし、中でお客様がどうなっているのかわからないと。私もそのとおりだと思って、しょうがないから扉を取ったんです。でもいずれは、家庭の中で個室として利用でき、VRも楽しめるというものも作りたいです。
――そうなんですね。では、当面の販売先として想定されているのはなんでしょう?
襟川氏:
当面はゲームセンターやショッピングモールになるでしょうね。あるいは遊園地やテーマパークといった娯楽施設もいいでしょうし。そういった施設では、雨が降ったら屋外のアトラクションが楽しめなくなるので、屋根のある場所にVR センスを設置すれば、お役に立てます。
あとはホテル。一度お部屋に入ってしまうと、空いている時間がたくさんあるので、ちょっと体験していただいたら、楽しいと思いますよ。ほかにも空港に置いて飛行機の待ち時間にちょっと体験してもらうなど、可能性はありますよね。
VRに興味はあるんだけど、まだ本体をお買いになっていない方は、たくさんいらっしゃると思います。そこでまず、ゲームセンターなどでVR センスを体験していただいて、それで面白ければ、VRの本体を買っていただいたり。
また、VR センスで開発したソフトは、しばらくしたら一般のPlayStation VRのソフトとして、販売を行う予定です。それを体験した方が、より五感に訴えるVR センスで遊んでみたいと思われたなら、ゲームセンターなどにいらしていただいて、実際に体験してもらえればと。ぜんぜん違う感覚を味わうことができますから。そういう形での循環サイクルが生まれたら嬉しい限りです。
――かなり幅の広いビジネスモデルを、考えておられるんですね。
襟川氏:
考えるだけならいくらでも夢は広がりますが、第一はお客様が何回も楽しく遊んでくださり、購入してくださったお店に利益を出していただかないと。夢を追って、VR センスの本体が売れないうちにソフトをたくさん作ってしまうと、大赤字になってしまいます。なんとしてもこのビジネスを成功させたいですけれど、一方では予算管理を徹底しないといつまでも赤字になって、社員がかわいそうなことになってしまいますから。初期投資できる予算の範囲の中で、最高の品質にします。
当社はゲームを作っていますけど、VRは必ずしもゲームである必要はないと思うんです。なかなか行くことのできない外国の街を、そよ風に吹かれながら歩いたり、スキューバーで美しい海中を見たりしてね。キレイですもんね、海の中って。そんなふうにVRには、いろんな可能性がありますよね。
 |
実はVRでいちばん作りたいものがあるんです。私の二人の母が高齢者の施設に入っていて、入居者には以前は海外に旅行したり、ご主人と温泉に行かれたりしていたのに、もう足が動かなくて外出できない方もいらっしゃるんですね。
そういう方たちがVRのマシーンに座って、昔行った温泉に行くことができるとか、スキーを楽しんだり、パリの街やモンマルトルでシャンソンを聞いたり、リラの香りを楽しみ、若かりし頃の思い出にひたれば、嗅覚が刺激され、脳が活性化されて、食欲も出ますから。
高齢者の方だけではなくて、病院で長期療養中の方もいらっしゃいますよね。1年、2年と病院から外に出られないとか。そういうところにもVRは有効だと思うんです。夢は無限に広がります。