8000部の希少さが世界に届く価値になる
TAITAI:
「熱風」って、いま何部ぐらい刷っているのか聞いていいものでしょうか?
鈴木氏:
いいよ。
田居氏:
8000部ですね。
 |
TAITAI:
8000部。「熱風」は書店での無料配布と、購読料を払って定期購読する形があるわけですが、その比率は?
田居氏:
3000部と5000部くらいですかね。
TAITAI:
3000部が書店に置いてあって、5000部が送付分ということですか。
田居氏:
逆ですね。書店に取りに来る人のほうが圧倒的に多いんです。
TAITAI:
その中でフラっと手に取る方というのは、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか? それとも毎号、同じ人が取りに来るのでしょうか?
田居氏:
たぶん、同じ方のほうが多いと思いますね。特集によっても変わります。
たとえば最近私が担当した記事で言うと、奈良美智【※】さんの特集(2017年10号)がいい例で、そういうときには奈良さんのファンの方たちが「熱風」を手に入れたくて、「書店に行ったけどないんです」と突然電話してくるなどがあります。
※奈良美智……1959年青森県生まれ。画家、彫刻家。挑戦的な眼差しでこちらを見つめる子どもをモチーフとした絵画が広く知られており、日本のみならず国際的に高く評価されている。
(画像はそれぞれAmazon|奈良美智 全作品集 1984-2010 Yoshitomo Nara: The Complete Works、スタジオジブリ出版部| 小冊子『熱風』2017年10月号の特集は「奈良美智 ロング・インタビュー ”絵に描かれるもののために”描く。」です。より)
TAITAI:
素朴な疑問で恐縮なんですが、「熱風」って無料で配布しているものじゃないですか。だったら、たとえば記事をネットで公開してみるなど、そういう話ってこれまでに持ち上がらなかったんですか?
鈴木氏:
えっ?
TAITAI:
というのも、「熱風」って「この記事がネットに載ったらものすごい反響があるだろうな」と思えるようなものが、本当にたくさんあるんですよ。それをあえてネットでやらない意図が気になるんです。
鈴木氏:
ネットでもやろうっていう話は何度もあったんですよ。でも、最初の糸井さんのひと言が大きかったんでしょうね。形があるのってやっぱり贅沢なことだと思うんですよ。希少価値が生まれます。
吉川:
希少価値かあ……。
鈴木氏:
それだけの部数しか刷られていないというのはね、読者の皆さんもなんとなくわかっていると思うんですよ。でも「そういう人のところへ届けばいい」と僕は思っているんですね。
 |
それに本当に必要なものはね、誰かが勝手にネットに載せてくれるんですよ。さっきのiPadに関する宮崎駿へのインタビューで僕は実験したんです。「熱風」が発信したものがどこまで届くかということに興味があったんですよ。
TAITAI:
結果はどうだったんですか?
鈴木氏:
すごいところまで届いた。「ニューヨーク・タイムズ」まで。
TAITAI:
えっ!?
鈴木氏:
「ニューヨーク・タイムズ」のコラムで扱われました。これは嬉しかったですね。
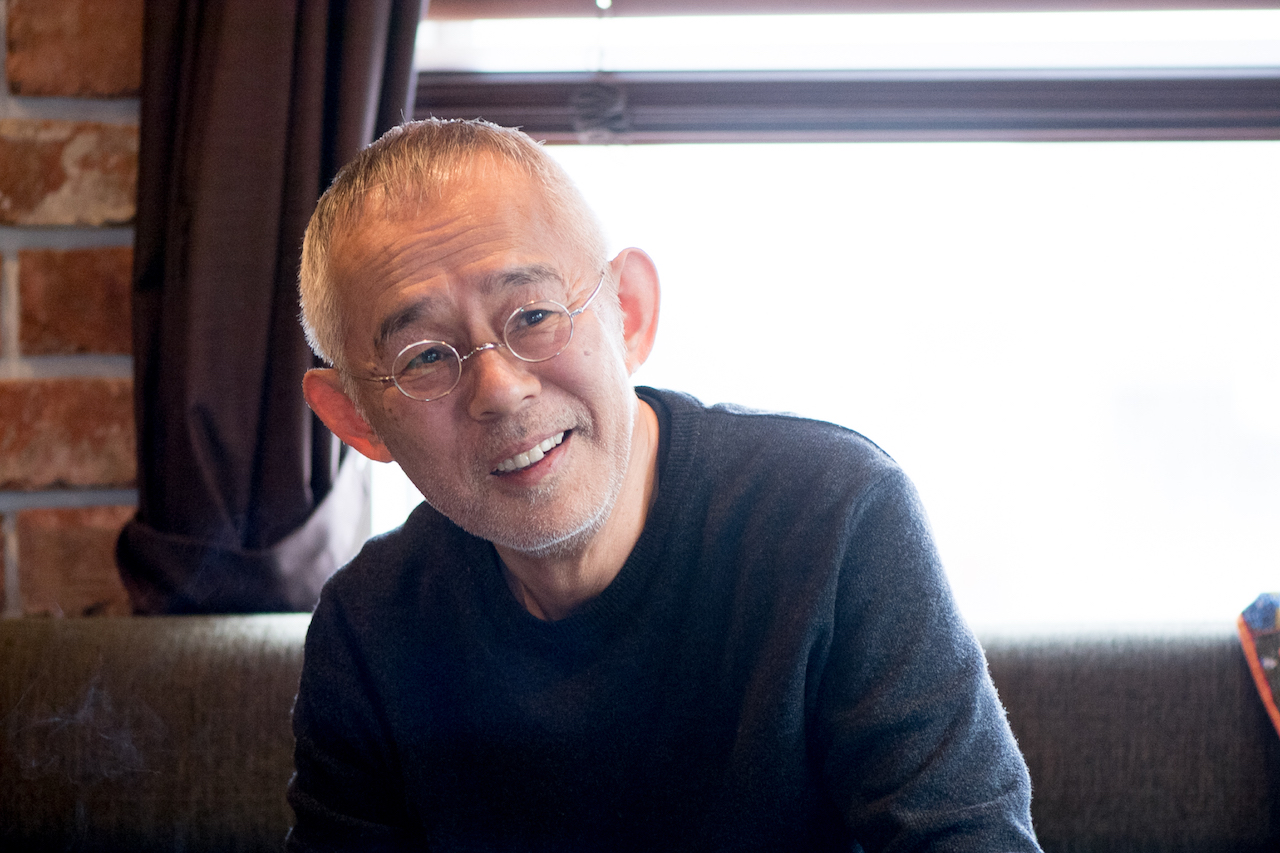 |
吉川:
へえ~。
鈴木氏:
やっぱりメディアってそういうもんなんですよ。あの発言が、アメリカで宮崎駿という人が注目を浴びた大きな要因のひとつになったかもしれない。でも発信元は8000部の「熱風」なんですよ。
TAITAI:
それは最初の発信に稀少性があって、狭い出口からポロッとそういう情報が出てくるからこそ、圧が高まってそこまで届くということですか?
鈴木氏:
そう。途中でネットでワーッと広まったらダメなんですよ。
 |
TAITAI:
メディアの価値や発信力みたいなものを考えたときに、たとえば8000部という「熱風」の部数を10万部に引き上げるという考えかたもありますよね。
鈴木氏:
それはね、読者の要望次第だと思っているんですよ。「熱風」は、もともと社会還元のひとつだと思っていたから、読者からそういう熱い声が届くなら、それは増やしていかざるを得ない。
じつを言うと最初はもっと少なくて5000部から始めたんだっけ。それが8000部まで増えた。「このぐらいの部数がちょうどいいんだろうな」と思っているんです。
だから別にいま、こちら側から「増やそう」という考えはないですよ。「部数が出りゃいい」というものじゃないもの。
「いいか悪いか」ではなく「好きか嫌いか」で何事も決めたい
TAITAI:
でもメディアの指針というか価値のひとつとして、「多くの人に読んでもらえる」ということもありますよね。でも「熱風」はあえてそうじゃなくて、クローズドに近い形でやられているわけですよね?
鈴木氏:
多くの人に読んでもらうとなると、記事の内容はある種の過激さを失うでしょ? 少ないほうがね、言いたいことを言えるんですよ。その環境を失いたくないですよね。
TAITAI:
先ほどの気配りの話ですね。予防線や配慮が必要になって、雑誌としての尖り具合がなくなると。
鈴木氏:
そうですよ。僕が「アニメージュ」を作っているとき、おかげさまでどんどん売れ行きが伸びていったんです。だから途中でね、言いたいことを言うために部数を減らそうと思ったんですよ。
TAITAI:
ええっ!?
鈴木氏:
それで大実験だったんですけれどね、半分に減らしましたよ。そうしたら精神衛生上、気分がとてもよくなったんですよね。
TAITAI:
いったいどうやって半分に減らしたんですか?
鈴木氏:
簡単ですよ、売れない記事をやればいいんだから(笑)。
どういう記事が喜ばれて、どういう記事をみんなが厭がるかって、自分で作っていればわかるでしょ。ちなみにこれはね、いろいろなところで言ってきたんですけれど、みんなが厭がる記事って、宮崎駿特集ってのがそうなんです。
 |
一同:
(爆笑)。
鈴木氏:
だって当時は宮崎駿なんて誰も知らないんだもの。でもあの特集をやったことによってスッキリしたんですよね。だから雑誌としては以後良くなったと思うんですよ。
TAITAI:
「人気作よりも、内容で戦うほうがいい」という確信を得たんですか?
鈴木氏:
そういうことじゃない。「いいか悪いか」という判断よりね、「好きか嫌いか」で何事も決めたいんです。僕はそう思います。ましてやね、「売ろう」と考えるのはつまらない。
 |
TAITAI:
「好き嫌い」は、「面白く思う、思わない」だと思いますが、その判断基準は?
鈴木氏:
自分ですよね。
TAITAI:
鈴木さんは何を面白いと思うのでしょう? どんなものがアンテナに引っかかるんですか?
鈴木氏:
それはもういろいろな基準があるから。美しいか醜いか、いいか悪いか、好きか嫌いかって。そんなのは理屈よりも直感で決めたほうがいいですよね。
TAITAI:
そういう好き嫌いを軸に「稀少性の価値で戦う」というような考えかたをする方って、いまの世の中にそんなにはいない気がします。もちろん雑誌を貫く軸として「好き嫌い」は重要ですが。
田居氏:
でもいま世の中は、いろいろなものがそういう方向に向かっていませんか?
 |
「たくさん刷って」とか、「たくさん作ってたくさんの人に渡す」というものよりも、“すごくいい大切なもの”を作って、それを手に入れる過程でメディアならメディア、物なら物が注目を浴びるという仕組みですね。私はそういう時代にどんどんなってきている気がします。
鈴木氏:
宮崎駿が表紙になった原発特集のとき(2011年8号)なんか、なにしろ新聞が大々的に取り上げたりね、やっぱりああいう手応えが面白かったね。世間を騒がすきっかけになる。

憲法特集(2013年7号)なんかもね、あれも僕が中日新聞の人に「憲法について話して」と言われたのがきっかけでね、「じゃあ高畑さんにもしゃべってもらうか」、「宮崎駿もしゃべらせるか」って思ったんです。
そういうときに「熱風」が本当にいい場所になるんですよ。こんなに規模が小さくても、そういう機会を提供できる。何もそんなにね、偉そうにものを言おうと思っているわけじゃないんです。でも、面白いんですよ。
人数を増やして役割分担をするから、ダメになる
鈴木氏:
やっぱり編集向きなんだね。昔から何か騒ぎを起こすのが好きなんです。だから雑誌なんでしょうね。
TAITAI:
ご自身としては、記者ではないというイメージですか? あくまで編集者であると?
鈴木氏:
そんなもの同じですよ。そういうことにこだわっちゃいけないんです。
記者と編集者の境界線なんてない。両方やればいいんだもの。自分が「アニメージュ」を作っていたときにも、みんなにそれを要求したし。
田居氏:
今日のようにひとつの取材にいろいろな役割の方が【※】おいでになるということが、私が「アニメージュ」にいたころには本当になかったので。いてもカメラマンと自分ぐらいでしたから。
 |
※いろいろな役割の方
当日の電ファミ取材陣は、カメラマン含め5名だった。
鈴木氏:
僕らのときはね、さっきの“気配”を鍛えるためにね、たとえば対談記事の収録でも、僕はいつもひとりだったんですよ。
そうすると、司会をして写真を撮って、なおかつ速記もしなきゃいけないんですよ。それで取材から帰ると、その日のうちに原稿を書いちゃうんですよね。これには鍛えられましたねえ。
だから僕はテープ起こしってしないんです。いちおう機材は持って行きますよ。だけどしたことないですね。そんなことをやったら勘が鈍くなるから要らないもの。
額田氏:
鈴木さんはレイアウトまで引くんですよ。
鈴木氏:
白夜書房【※】ってあるじゃない。昔さ、仲良くなったヤツがいたんだけれど、「写真時代」などいろいろな雑誌を出していた当時のあそこは、ひとつの雑誌をひとりで作っていたんだよね。
その友だちがいろいろと送ってくれて読んでいたんだけれど、どれも無茶苦茶面白かった。しかも、ひとりひとりの編集者の個性が活きたうえで記事の使い回しがない。だから、出ているいろいろな雑誌がまとまってひとつの大きな雑誌みたいな気分だったんだよね。
※白夜書房
1975年設立の出版社。1981年~1988年に発行されていた「写真時代」を筆頭に、1980年代にはアダルト系写真雑誌やコミック雑誌を多数発行していた。ヌード写真やアダルトコミック中心の各誌面には、加えてサブカルチャー的な記事が数多く掲載されており、のちのサブカルチャーの担い手を多数輩出した。なお、現在の白夜書房はパズル雑誌、芸能雑誌、実用書などを発行しており、アダルト系雑誌は取り扱っていない。
額田氏:
アダルト系の出版には、わりとそういうところが多いですね。と言っても別に何か崇高な理念があるわけじゃなく、単にお金がないから人を雇えないんですけど。
鈴木氏:
いやでもね、僕らの時代も雑誌にはやっぱりお金がなかったんだよ。だからひとりで全部やらなきゃいけない。「アニメージュ」の創刊編集長だった尾形という人は、じつはひとりで広告まで集めているんですよね。
田居氏:
そうですね。
鈴木氏:
挙げ句の果てには、書店まわりまでやるんです。
TAITAI:
広告営業と販売を、編集業務と同時にやれる人って本当に稀有ですよね。
額田氏:
そういうことを覚えると、結果として面白くなるんですよね。
鈴木氏:
そう。だからいまは「役割分担を決めて、それに徹する」ということをやり過ぎていますよね、たぶん。
 |
TAITAI:
耳が痛いですね……。
吉川:
昔、私がやっていたテレビ番組【※】なんかも、4人ぐらいで作っていましたよ。いまは30人ぐらいのスタッフがいるでしょ。だから人件費だけでたいへんなことになる。
※やっていたテレビ番組
じつは吉川は、日本テレビのプロデューサーとして、『世界まる見え!テレビ特捜部』、『恋のから騒ぎ』、『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』、『特命リサーチ200X』などを手掛けている。
鈴木氏:
そうなんですよね。映画もね、人数が増えてからダメになったんですよ。
昔の映画って4~5日で撮るでしょ。スタッフは5~6人。それがいまはだいたい10倍になるんだよね。1時間半の映画を作るのに60人でゾロゾロと。そうしたらもう、つまらなくなるに決まっているもの。
TAITAI:
役割で分業するとダメになるのは、感覚としてよく解るんですが、いったいなぜなんでしょう?
鈴木氏:
だって、全体を解っていたほうがいいに決まっているじゃないですか。
どこの業界でも、そういうのってあるんですよ。たとえば映画の世界でもそう。
僕も映画の製作に関わっているけれど、どういう映画なのか解っているから、宣伝を考えるのが無茶苦茶に楽なんですよ。
ところがいまの映画の世界を見ているとね、どんな映画なのか全体を知らない人が宣伝をやっている。上手くいくわけがないですよね。
 |
『ナウシカ』でアニメーションを始めたときは面白かったですよね。実製作の最後のほうで追い込みになったとき、僕ね、真似っこして動画を描いたりしていたんですよ。そうすると宮さんが寄ってきてね、「うん、動画の線としてはいいかな」とか言って寄越したりね。
一同:
ははははは(笑)。
鈴木氏:
それからセルに色も塗ったんですよね。だって監督の宮さんだって塗っているんだもの。そうするとね、そこを担っている人たちが何をやっているか解るようになる。逆にそういう経験を踏まないと、解りませんよね。
TAITAI:
なるほどなあ……。




































