座談会なんて、いい加減な話でいい
吉川:
先ほど、総合雑誌に興味があった残滓が「熱風」に至ったと仰っていましたが、「文藝春秋」や「中央公論」などの総合雑誌も、オピニオン誌も、僕らとしては「なんだか読みづらいな」という感じがしちゃって、なかなか手が伸びない部分があるんです。
鈴木氏:
でも昔の「文藝春秋」などを読むと、本当に面白いんですよ。僕が書く座談会のまとめなんてね、昔の「文藝春秋」の真似ですもの。ところがいまは、みんなその方法を知らない。失われた技術ですよね。
TAITAI:
失われた座談会のまとめかたって、どういうものなんでしょう? すごく気になります。
鈴木氏:
些末なところへ話題を持っていくんですよ。すごく細かいところへ。
昔の「文藝春秋」の座談会を読むとね、みんなが集まってくるところから始まるんです。「なんで遅れてきたんだよ」ってところから始まるんですよ(笑)。
吉川:
それが活字になっている(笑)。
鈴木氏:
いまはそこを全部省くでしょ。だからつまらないんですよ。僕がラジオでやっている「ジブリ汗まみれ」【※】は、だいたいその手法なんです。
出演者がスタジオに入ってきて、挨拶からそのまま雑談になるでしょ。それをそのままラジオで流しちゃうんですよ。すると「えっ、もう本番が始まってるんですか?」となる(笑)。
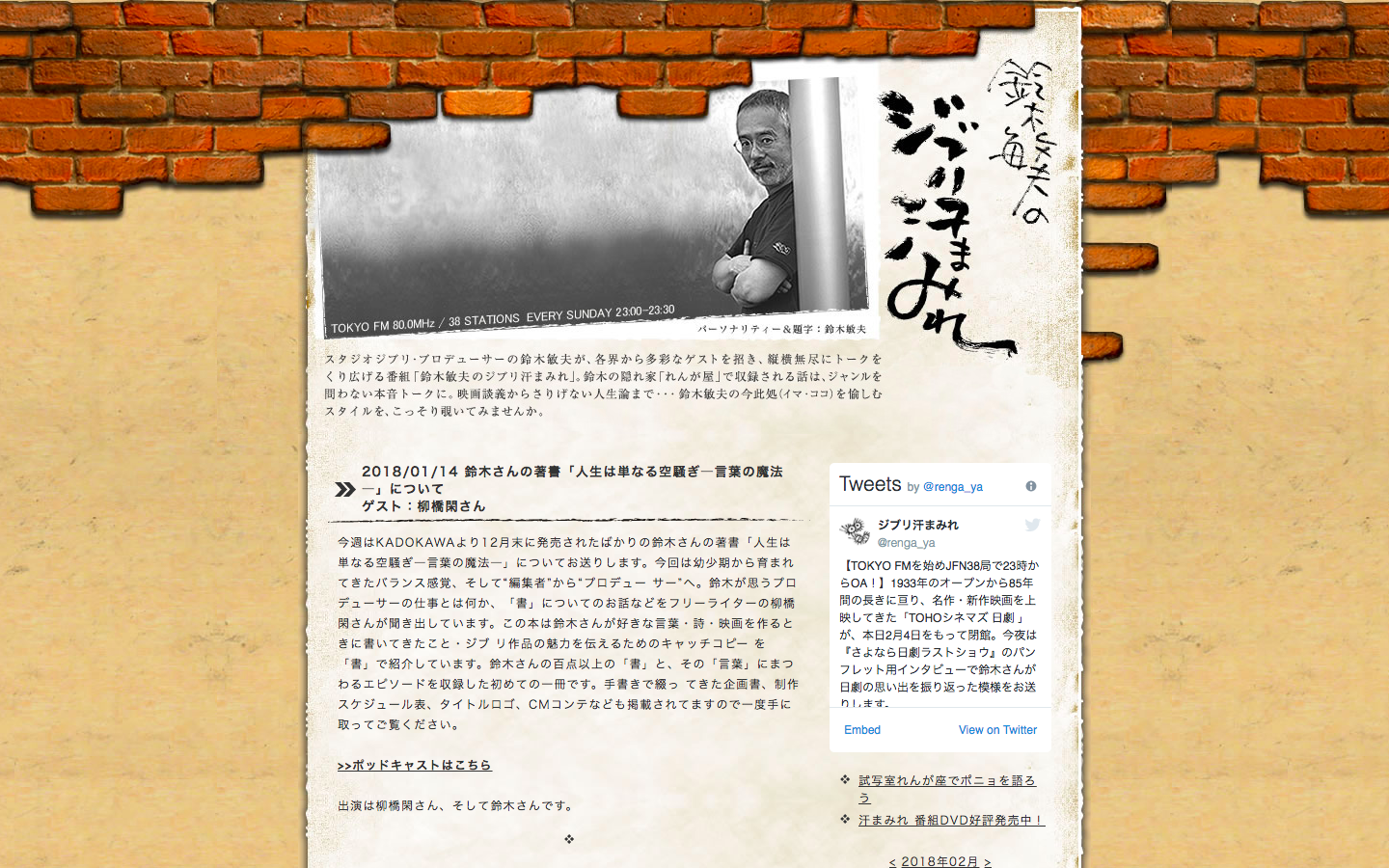
(画像は TOKYO FM 80.0MHz| 鈴木敏夫のジブリ汗まみれのスクリーンショット)
吉川:
先日ゲストで呼ばれていた、日本テレビの土屋(敏男氏)【※】がビックリしていましたよ(笑)。
※土屋敏男
1956年静岡県生まれ。日本テレビでバラエティー番組の演出やプロデューサーを数多く担当。なかでも「進め!電波少年」のT部長として、視聴者にも広く知られている。現在は日本テレビ放送網株式会社 日テレラボ シニアクリエーターを務めている。
鈴木氏:
いまは、話したことのエッセンスだけ引っ張り出そうとするからいけないんですよ。会話がある結論やある考えにたどり着くには時間が必要で、その経緯が面白いはずなのに、その面白さをぜんぶ取っ払うんですよ。
TAITAI:
その傾向はありますね。
鈴木氏:
生涯に1回だけ、高畑勲、宮崎駿、僕で座談会をやったことがあるんです。
3人が集まるような場では、ふだんはね、高畑さんがいちばん早く着くんです。僕が2番目で3番目が宮さん。ところがそのときは僕と宮さんが先に着いて、高畑さんが遅れやってきた。これはめずらしいことなんですよ。そうすると、僕ならそこから書きたくなるわけ。
「ふだんは時間どおりに来る高畑さんが、なぜか今日は遅れている。なんと30分遅れて登場」とかね。
吉川:
なるほど。
鈴木氏:
この座談会は、『風立ちぬ』を作り終えた後で宮崎駿が引退を発表したんですが、そこから2ヵ月ぐらい経ってからの話。会場に着いた高畑さんの第一声が大きな声で「宮さん!」。ふたりは久しぶりに会うんですよ? 「引退するって本当なの!? 止めたほうがいいよ!」って(笑)。
すると宮さんがなんて答えたか。「あっ、あっ、あれは鈴木さんの陰謀だよ」。
一同:
わはははははは(笑)。
鈴木氏:
こんな面白いところが、いまのやりかたでは省かれがちになる。
大事な話をしなきゃいけないと思うんでしょうね。でも座談会なんて、いい加減な話でいいんですよ。放談しているだけだから。
TAITAI:
座談会記事では、よく「現場ではあんなに盛り上がったのに、テキストにするとぜんぜん面白くない」ってことが起きがちなんですよね。
鈴木氏:
だから「rockin’on」の渋谷陽一さん【※】がテープ起こしをそのまま掲載するようなインタビューをやったでしょ。あれはあれで問題もあるんですけれど、でもやっぱりある種の面白さが出ていますよね。
※渋谷陽一
1951年東京都生まれ。株式会社ロッキング・オンの代表取締役社長として、みずから創刊した音楽雑誌「rockin’on」や、インタビュー雑誌「CUT」などを統括している。宮崎駿氏や鈴木敏夫氏には、幾度もロングインタビューを行っている。
TAITAI:
僕はテープ起こしをそのまま掲載というのには否定的なんです。現場で口頭だと阿吽の呼吸でお互いに分かったことが、文字に起こしても第三者に伝わらない場合がけっこうあるので。
鈴木氏:
それは説明を挟んじゃえばいいんじゃない? 「なんでこんな阿吽の呼吸が成り立ったのか」って、3行書けば終わりなんだから。なんでも書いちゃえばいいんですよ。「たぶんこういうことだと思う」とか。
TAITAI:
確かに、「どうしてそこで伝わったのか」という解説を入れるのはすごく面白いですね。
鈴木氏:
「と言ってたけれど、私はそこに立ち会って、実際はどうなんだろう? と思った」と入れたっていいんですよ。あとで本人たちに訊きに行って、「訊いてみたらこういうことだった」と入れてもいいし。
書きかたっていろいろあるんです。僕は対談でね、「小説風に書くと、こうか」なんて書いたりもするんですよ。以下、小説の口調で書いちゃうんです(笑)。記事にはそういう柔軟性が必要。
 |
僕はもともと「アサヒ芸能」【※】の記者でしたが、そのときからそういう手法を多用したんです。だって、いっぱい任されるんですよ。
たとえば正月特集で対談を10本掲載するって言って、そのうち6本が僕のとこへ回ってきたことがあって。それを2週間で終わらせなきゃいけないんだもの。
※アサヒ芸能
1946年に「アサヒ芸能新聞」として創刊。1956年にB5サイズの週刊誌「週刊アサヒ芸能」となった。芸能スキャンダルを中心に、スポーツや社会事件などを取り扱っている。
田居氏:
それは……たいへん。
鈴木氏:
でしょ。だったら「ああでもない、こうでもない」ってともかく書いちゃうんですよ。でも、それが勉強になったんですけれどね。
TAITAI:
たとえばインタビューだと、何かを言われて言葉に詰まった表情をしたりなどありますよね。こういうときって、言葉そのものは何も話していない。でも、これを記事でどう表現するかって、とても大事な部分なんですよね。
鈴木氏:
その場でそこまで含めてメモを書いておくんですよ。だからテープ起こしじゃダメなんです。
人間の記憶力って、いろいろ話しても次の日に憶えていることは半分に減るんです。その次の日には、また半分になる。1日ごとに半分ずつになるなら、十日も経てば全部忘れますよね。だからすぐ書かないといけないんです。
 |
「愚図(グズ)」っていう言葉があるでしょ。これが象徴的でね、昔はもたもたしていると「このグズ!」って怒られたんですよ。いまはこの言葉は消えたけれど、やっぱりグズはダメですよね。とくに雑誌など、こういう商売をやる人はスピード感が必要。
TAITAI:
そうですね。
鈴木氏:
僕はともかく記事を書くのが好きなんですよ。
去年、週刊誌(女性セブン)で連載をやってみたんですけれど、担当の編集者が内容を見て「週刊誌の記事みたいです」って言うから、「俺はもともと編集なんだ」って言ったりして(笑)。
僕は週刊誌を作るほうだったから、「週刊誌に連載をするというのは、こういう面白さなのか」と思ってね。
TAITAI:
どういう面白さですか?
鈴木氏:
まず、一週間前に自分で何を書いたか憶えていないという面白さ(笑)。編集者とは必ず打ち合わせをしてね、すると「それ、このあいだの原稿に書いてありますよ」と言われるんです(笑)。
いろいろ協力してもらいながら、そうやってしゃべっていると、次に何を書いたらいいかのネタを思い付くんですよね。いまはその連載を単行本にしようとしていてね、ちょっと楽しみなんです。
面白さの判断には、広い意味での教養が必要
TAITAI:
今日、鈴木さんからお伺いしたような考えかたや方法論は、額田さん、田居さんのおふたりも参考にされているのでしょうか?
額田氏:
僕はけっこう参考にしていますね。先日、あるカメラマンさんのインタビューをすることになったんですが、普通はカメラマンのインタビューなら、だいたい写真論の話になりますよね。
そうしたら鈴木さんが「いや、お金をどうやって稼いでるのか聞きなさいよ」と(笑)。
 |
一同:
ははは(笑)。
額田氏:
「広告などの儲かる仕事をしていないカメラマンって、いったいどうやって生活しているのか、そこを聞くべきだよ」と。そういう発想はすごく刺激になりますね。
田居氏:
実際に聞いたら面白かったよね。
TAITAI:
鈴木さんはなぜ、「それを聞いたらいい」と思ったんですか?
鈴木氏:
素朴に思えば、自然と湧く疑問ですよね。「いい写真を撮っているかもしれないけれど、これじゃ売れないだろうな」と思ったから(笑)。
「アニメージュ」でもそういう記事をやったことがあるんですよね。『クラッシャージョウ』【※】というアニメーションが映画化されてね、それに携わっているアニメーターの7、8人を、毎月追いかけたんですよ。「アニメーターの生活と意見」という名で。
「描いているものの派手さの裏で、どうやって毎日暮らしているのか?」って(笑)。
※クラッシャージョウ
高千穂遙氏原作の人気SF小説を、1983年に劇場アニメ化した作品。原作小説のイラストを描いていたアニメーターの安彦良和氏が演出を手がけており、安彦良和氏自身の初監督作品でもある。
額田氏:
週刊誌的な発想ですよね。
鈴木氏:
やっぱりみんな、すごく身近に感じたみたいですね。生活と意見って面白いんですよ。
TAITAI:
肝心なのは、そういう発想が「編集者から出てくるかどうか」ですね。
先ほどの座談会のさまざまなまとめかたもそうですが、「本質的にそこが面白いと思えるかどうかって、どうやって体得していくものなんだろう」とよく思うんです。
鈴木氏:
それには教養が必要ですよ。教養というのは、広い意味での教養ね。
 |
同じものを見て「面白い」と思う人と、「面白くない」と思う人がいるでしょ? それはたいがいね、つまらなそうにしている方には教養がないんだもの。
勉強不足なんですよ。いろいろな物を読んで、いろいろ見聞して、「何が面白いものなのか」というのをね、やっぱり自分なりに勉強しなきゃ。
TAITAI:
知れば知るだけ、なんでも面白くなってくるということですね。
田居さんは、そうした鈴木さんの考えかたを参考にしたり、影響を受けたりするところはあるのでしょうか?
鈴木氏:
田居さんとはね、「アニメージュ」以来だから42年の付き合い?
田居氏:
そんな数字、言わなくていいです(怒)。
一同:
(笑)。
田居氏:
鈴木さんがどういう考えかたをする人かは、42年間も一緒にやっているので解るので。
鈴木氏:
自分では言うんだ、数字を(笑)。
いや、解るならその42年を見ていて「俺は何か変わった?」と訊きたかった。
田居氏:
変わっていませんよね。
鈴木氏:
変わっていないんだ。
田居氏:
進歩がないんじゃないのかな(笑)。
一同:
(爆笑)。(了)
 |
いまでは、アニメ映画のプロデューサーとして名を馳せている鈴木敏夫氏。今回は、そのもうひとつの顔である“編集者”としての鈴木氏に迫ってみたインタビューであったが、いかがだっただろうか。
正直、自分がつね日ごろ感じている悩みや疑問を、ストレートに鈴木氏にぶつけてみるという体になってしまった今回の取材だったわけだが、ことごとく筆者の予想を超える──それでいて、芯を喰っている──受け答えをされていたのは、さすがのひと言。宮崎駿という才能を見出し世の中に仕掛けた、鈴木敏夫という人の凄みや面白さが垣間見える内容になったのではないかと思う。
なかでも、「最近は、雑誌から何かが生まれることが減っているのではないか?」という問いに対し、それは「何かを起こしたくない人が雑誌を作っているから」だという鈴木氏の指摘は、我々の世代が重く受け止めるべき言葉なのかもしれない。
数値に追われ、生産性や効率性を追い求めるなかで、現代のメディア人が失いがちな何かが、そこには含まれている気がするからだ。
「追うのではなく、起こす」。
編集者たるもの、その気概を持たないといけないなあ……と、改めて身が引き締まる思いであった。
編集者のキャリアパスや可能性というものを考えたときに、「その“行き着く先”とはなんなんだろう?」と思うことがある。その手腕でもって出版社内で役職を上げていく、あるいはみずから出版社を立ち上げるなど、それはさまざまだとは思うが、そんななかでも、自身の目利きを信じ、「出会った才能に賭ける」という方向性もまた、ある意味もっとも“編集者的なもの”だと思った次第。
今回の取材を通して、電ファミ、ひいては自分自身の目指すべき方向性が見えたような気が・・・・・・しないでもない。いやあ、頑張らないとなあ。
【あわせて読みたい】
【全文公開】伝説の漫画編集者マシリトはゲーム業界でも偉人だった! 鳥嶋和彦が語る「DQ」「FF」「クロノ・トリガー」誕生秘話電ファミでは、伝説の漫画編集者マシリトなる鳥嶋和彦氏と、カドカワ取締役相談役・佐藤辰男氏との対談も掲載しております。『Dr.スランプ』や『ドラゴンボール』、『ONE PIECE』や『NARUTO』、『テニスの王子様』など、数々の名作を世に送り届けたその“編集”の技とは?


































