問い直された格闘ゲームの価値
──先ほどはアーケード全体の話が中心でしたが、ここで少し格闘ゲームに絞ったビジネスモデルをお伺いしてもいいでしょうか。基板の話もありましたが、パッケージとの売り上げの比率は、どういうバランスだったんでしょう?
原田氏:
家庭用は販売枚数が数百万枚と大きいので、売上高は大きく見えますね。ただ当然、アーケードビジネスから見れば薄利多売です。比率は当然時代で変わっていきましたが、1990年代~2000年代初期は純利益で言えば、じつはアーケードと同じくらいの水準でした。
アーケードは、当時はある意味堅実で確実でしたね。実際にはBtoBのビジネスですから売り先が決まっているため、だいたい台数も見えて投資額も決めやすい。そして単価も高いので、売れたときの利益確保も早い。インカムで稼ぐのはお店の方々で、我々は基板をお店に売った時点で、基本的にはビジネスとして成立してしまいますから。
──いまと違い、アーケードはネットワークサービスが付いた“継続ビジネス”ではなかったですしね。
原田氏:
ええ。昔は売った時点で利益回収でしたね。だから格闘ゲームは足が速く、立ち上がりのいいビジネスだったはずです。

しかも、開発期間もそんなに長いわけではない。当時のRPGは2~3年かけて作っていましたが、格闘ゲームは長くても丸1年。『鉄拳3』は長いほうで2年近くかけましたけど、開発期間としてはじつはアーケードゲームは1年かからないくらいで作ってしまって販売する。
そしてプロモーションもほとんどいらないんです。比較で言うと、たとたとえばいまのゲーム、とくにモバイルに代表されるものは、下手をしたら開発費よりぜんぜん広告宣伝費のほうが高いです。
──そうですね。開発・広告宣伝・運営の三位一体ですから。
原田氏:
しかも、その三つは後半に行くにつれて、圧倒的にたいへんになっていったりする。
でもアーケードビジネスは、店舗そのものがプロモーションの場でしたので、広告宣伝はほとんど要らなかったんです。となると、もともと回収サイクルも早いうえ、いいものさえ作れば長く稼げた。いま思い返せば当然ですが、このビジネススキームこそが、昔のナムコやセガが大きくなったひとつの要因だと思うんですね。
 |
ちなみに、家庭用も初代プレイステーションが出たばかりのころは、ポリゴンのゲームが何でも爆発的に売れる時代でした。
質はともかく、国内でも100万枚オーバーのゲームがたくさんあった。家庭用への移植はたいへんなんですが、ブームのまっただ中ですから、アーケードで面白さを確保できているものや、ある程度人気が出ると判っているものが、爆発的に売れたんです。
非常にいいビジネスチャンスでした。それでも1990年代当時の家庭用の収益は、アーケードとだいたい五分五分だったわけです。
──なんというか、聞けば聞くほどアーケードが当時の業界にとって基幹ビジネスであったということが解ってきますね。
原田氏:
だから『鉄拳』も、「しっかりアーケード展開を継続していこう」と言っていました。
その後も欧米からは「なぜアーケード先行ビジネスをやるんだ? あり得ない!」と言われていたんですが、実際には開発費を回収したうえで利益もしっかり得られてました。そうすると、簡潔に言えば家庭用に回せる開発費も増えるわけじゃないですか。実際のところアーケードで先行していないと『鉄拳』の家庭用版をあれくらいの規模で作ることはできませんでしたよ。
──モードの充実などは、アーケードの先行ありきなんですね。
原田氏:
たとえば『鉄拳』シリーズを過去から順に見ていくと、他の格闘ゲームより明らかにプレイモードやムービーのボリュームが、その時代の競合タイトルに比べて多いと思います。
ああいう開発ができていたのは、やっぱりアーケードがあったから。アーケードは『鉄拳』というフランチャイズにとって重要な足場だったんですよ。
──その状況で、どうやって家庭用ゲーム機しか残らなかった欧米のビジネスを維持したのでしょう? 実際に維持しなかったり、維持できなかったメーカーもあるわけですよね。どう維持しようと考えたのか、それに必要なものはなんだったのかを教えてください。
原田氏:
そうですね。先に言っておくと、ここからの話は言いかたを間違えると、ゲーマーの皆さんが怒ってしまうような内容です。いろいろな側面があるので、エモーショナルな部分は一旦置いて、あくまで客観的にひとつの側面として捉えてほしい話です。
僕も開発者として、若いころはクリエイティブな側面だけで仕事をしてきましたが、格ゲージャンルの暗黒の10年を生き残るあいだに、あらゆる側面から格闘ゲームというものを冷静に見直す必要に駆られたんですよ。そしてそこから学ぶことも多かったんです。
いまからお話をするのは、そうした暗黒時代を生き抜くために必要だった俯瞰的な視点での話です。
──それはいったいなんでしょう。
原田氏:
まずアーケード版でなくなるということは、ビジネス業態が変わり、“遊び放題の時代”が来るということなんです。当時、「そうなったときの“格闘ゲームの価値”って何だろう?」ということを考えていました。
──格闘ゲームの価値?
原田氏:
日本では、プレイするたびに1回100円を入れていました。負けたら100円が取られます。ですが勝てば10回、20回と遊べる。これがアーケードで格闘ゲームが成り立っていた理由じゃないか……と思っていたんです。
 |
ですので、コインを入れる環境を失った時点で、とくに欧米での格ゲー文化は「廃れる可能性がある」と当時、仮説を立てました。まあここまでは周囲の皆も同じようなことを言っていたはずです。
──なるほど。アーケードで格闘ゲームを楽しんでる方には、ある種の勝敗に伴う緊張感があって、それを楽しんでいるのだと。しかしアーケードがなくなることで、その魅力を実感できない人が現れたわけですね。
原田氏:
そうです。現在でこそYouTubeなどの動画サイトもあるので、他人のプレイを見て熱狂したり、勉強したりもできます。しかしあの過渡期……ここが暗黒時代と呼ばれる所以なんですが、1990年代後半から21世紀に入ったころは、ちょうど時代の移り変わりで、そんな動画やストリーミング配信やSNSなんてものはなかった。
ですからアーケードがなくなると、スーパープレイを見る機会もない。格闘ゲームの強いスーパーヒーローたる人物もわからない。そうして地域コミュニティが消滅していった。
そうなると、家庭用市場における格闘ゲームの価値というものは、アーケードとの比較論で言えば、おそらく「かなりのレベルで失われた、もしくは失われたように映った」はずなんです。
──魅力の伝道師たちが不在になったと。
原田氏:
そしてそれを証明するように、アーケードがなくなったと同時期に消えていった格闘ゲームタイトルもいっぱいありました。
皆さん知らないだけで、欧米のアーケードだけでリリースされていた格闘ゲームタイトルがたくさんあったんですよ。
あれだけブームだったのに、当然ですが、家族でやるゲームではなくなってしまったんですね。当時はまだ、インフラも整わず、オンライン対戦も厳しかった。
 |
これが、世界市場における格闘ゲームにとっての、アーケードも動画掲載もストリーミングもSNSもオンライン対戦もない、空白の暗黒時代です。
──そこで質問は原点に立ち返ります。そこでなぜ『鉄拳』だけが抜きん出られたのかと。
原田氏:
『鉄拳』プロジェクトは、そうしたインフラなど環境の問題が解消される時期を、当時は「恐らく10年後」と予想していました。要は、世界のインフラが全部光ファイバーに変わるころと目していたんですね。
「その時代が来れば、格闘ゲームは新時代を迎える可能性がある」と言っていたんですが……でも、当時の僕らから見れば、その待ち時間は長過ぎたんです。
「そう言ってるあいだにIPが消えてしまう」。「いつか解決されるから」なんて言ってないで、「この10年をどう超えるか」、つまり欧米アーケード文化が消え、オンライン時代にも完全移行できていない暗黒の10年との向き合いかたを考えなければいけませんでした。
待っていたらこのジャンルは消えてしまう。事実、先に述べたように周囲はどんどんシリーズを断念し、凍結させていっていたわけです。
──そうですよね。
原田氏:
だからといって、安易に「よし、もう欧米は家庭用ゲーム機ビジネスの時代になる」と判断して「じゃあ家庭用を頑張ればいい」という話でもなかった。先ほどのビジネスモデルの問題や価値観の話もあって、プラットフォームを問わず格闘ゲームには暗黒時代が来る可能性が待っていて、やっぱりというか現にそれは起きたわけです。
……ここで、「格闘ゲームの価値ってどこにあるのだろう」という話に戻るんです。
「格闘ゲームだから買う」というメンタリティをある意味期待しなかった
──その問いに結論は出たのでしょうか?
原田氏:
ええ。まず僕らが目を付けたのは、「そもそも3D格闘ゲーム、もしくは3Dポリゴンブームは、なんでやって来られたのか」ということの再定義でした。

日本もそうかもしれませんが、欧米はとくに「テクノロジー的に最先端をいくもの」が、非常にいい地位を占めます。まずこれは見えていたんですよ。
最先端のものは憧れられるし、「ひと目見てみたい」と思ってもらえる。あくまでも喩えですが、クルマで言えば、『バーチャファイター』や『鉄拳』はアーケードゲームにおける大衆車でなく、スポーツカーのような価値を持つものとして当時は通用したんです。
──ある意味、技術の見本市であったと。
原田氏:
いまの若い世代の人には「何を言ってんだ?」と思われそうですが、当時あの「異常な関節数と異様ともいえる膨大なアニメーション数を持つ人体2体を制御できる」というのは、稀なノウハウで、マネできる会社もそこまでなかったんです。
正確には初代プレイステーションやプレイステーション2の時代に、恐ろしい数の3D格闘ゲームが生まれたんです。でも、みんなあらゆる制御が上手くいっていなかった。猫も杓子も格闘ゲームを作っていましたが、やっぱりいいものはなかなか生まれなかった。
人体という高難度かつ永遠のテーマ、肌や服のシェーダー表現、布や髪の揺れ、間接をつなぐエンベロープ技術やスキニング、ライティング、エフェクト、膨大なアニメーション制御と補完技術など、当時は最先端の技術が集結していたジャンルのひとつでしたから。
──つまりポリゴン格闘ゲームには、ハイエンド商品のベンチマークとしての価値があったわけですね。いわゆる、プレイステーションのロンチのたびにリリースされる『リッジレーサー』のような感じで。
原田氏:
そうです。当時は、格闘ゲームがグラフィック的にも有利だったんですね。キャラクター2体ぶんしかポリゴンが登場しないので、あらゆる処理を人体の表現として緻密に割けるわけです。先に述べたような最先端のグラフィック技術を投じやすく、開発力が見られる一大ベンチマークジャンルでした。
それらを踏まえたうえで、僕らは2000年代から始まる暗黒時代に対して販売戦略も変えていったんです。
そこで、僕らはそのとき、『鉄拳』はあくまで1対1の対戦格闘ゲームでありながらも、「格闘ゲームだから買うという層だけを狙った路線をやめよう」と言ったんです。謎かけのようですが。
──客層の想定を変えていったと。
原田氏:
アーケードのビジネスモデルが生んだ格闘ゲームって、対戦の面白さでもあるんですけど、現実的に見てみると「敗者を生み出すゲーム」という側面もあるわけです。それは統計的には勝ち越してる人間のほうが少なくて、多くの人間は「負けて悔しい思いをしているゲーム」という形で現れる。そういう意味では結構シビアなもの。
つまり敗者を作りやすい格闘ゲームは、その構造自体がブームを去らせた理由のひとつとなるのは皆さんも理解できると思います。
だからゲームの内容を“闘うこと”に特化させた場合、「本当にみんなが幸せになれるか」と言ったら、「ちょっと難しいんじゃねぇの」と思ったんですね。
おそらく2~3割のコア層は、「格闘ゲームだから」という部分を動機に買ってくれている。だけど残りの7~8割のお客さんは、必ずしも“ガチ対戦”を目的に買ってはいない。もしかすると「格闘ゲームだから買う」という層じゃないところまで広がっているわけです。
先ほど話したとおり、この言いかたは一部誤解が生じるかもしれませんが、暗黒の10年で格闘ゲームが失ったビジネスモデルとゲームとしての価値を思い返してほしいんですね。
皆の好きだったIPやシリーズはここで消えたり凍結されたりしてしまったんですよ。それは、暗黒の10年を突き破っていける光明が見出せなかったからです。
僕らはそこで賭けに出た。「うちは対戦格闘ゲームでありながら、格闘ゲームとしてだけでは売らない」と。
 |
──具体的にはどういうことですか?
原田氏:
「格闘ゲームとして面白い」と思ってもらうには、まず手に取って触ってもらわなければいけませんよね? その結果、10人にひとりが「これは面白い」と気づいてくれたら最高です。
でも、我々が暗黒の10年で想定していたのは、“格闘ゲーム”という理由だけでは「手に取ってすらもらえない」という状況でした。ここがキモです。
「ゲームの対戦部分が面白い」という以前に、その面白さがわかるところにたどり着く人は、エンターテインメントを求める旅人100人のうち何人なのか……。
だったらまずは「その旅に出たい」と思わせる映像を見せたほうが絶対いいんじゃないか。そこで手に取ってもらうための作戦として考えたのが、ベンチマークとしてのグラフィックだったとも言えるんです。
──なるほど。あるころから『鉄拳』は、いわゆるキャラクタークリエイションやアーティスティックな部分へのエネルギーのかけかたが、明らかに変わっていった印象を受けます。
あれはベンチマークを意識していたからなんですね。コアな格闘ゲームファン以外にも訴求できる方法として、グラフィックやCGムービーにも力を入れたと。
原田氏:
ええ、まずは価値をそちらに持っていったんです。たとえば人の真心やその人の本質なんてものは、出会ってみっちり付き合えば、その価値を理解してもらえますよね。だけど多くの人はまず外見で判断してしまう。
多くのコアゲーマーの皆さまは当然「何を言ってんだ、格ゲーとして勝負しろよ!」と仰ると思いますが、そもそもその本質部分の勝負に関しては、僕らも好きが高じて格闘ゲームを作ってるわけですから、ずっと挑戦し続けていますし、本質がそこにあることはもちろん理解しています。

だけども、その本質を覗く以前にそのドアを開けてくれる人がいないとしたら、僕らは「まずその門構えから変える必要がある」と考えたということです。
──門構え。
原田氏:
たとえば、当時いわゆるプリレンダリングCGムービー【※】と言われる手法を真っ先に格闘ゲームに入れたのは『鉄拳』でした。「これCGムービーがすごいらしいよ」、「このゲーム、綺麗なグラフィックのCGが見られるんだよ」というのは、確かに格闘ゲームとしての本質的な価値ではありません。
※プリレンダリングCGムービー
あらかじめCG映像を作製(プリレンダ)し、それを動画として再生するムービー。対になるものにリアルタイムレンダリングムービーがあり、これはプレイの当該場面で、演算によってCGが描写され、ムービーの体をなすもの。
いまでは「プリレンダのCGかよ」と言われますが、当時は“きれいなCG”自体に価値があったんですよ。そういう時代でした。
そういう経緯で、『鉄拳』はあるときからオープニングムービーにやたら力を入れているんです。シリーズを追うごとに、だんだんオープニングムービーが長くなっていったりして。
──過去にはSIGGRAPH【※】でも、ナムコのプリレンダCGが賞を取りまくっていましたよね。『鉄拳』や『ソウルエッジ』がシアターで大々的に流され、「日本から出ているCGのトップだ」ってずっと言われていました。
なるほど、そのあたりの話といまの話がきれいにクロスしますね。それはベンチマークを目指していたからなんですね。
※SIGGRAPH
アメリカコンピュータ学会のCG分科会として始まった国際会議で、過去から現在に至るまで、CGに関する最先端の話題はここで発表・議論される。とくに1990年代末までは、SIGGRAPHで開催されるElectronic Theaterの価値がきわめて高かった。公募をくぐり抜けた作品が上映されるが、当時はYouTubeもなく、最新のCG作品をまとめて見る機会も少なかったため、非常に“特別な場”とされていた。ナムコは1997年に『ソウルエッジ』(正確には、その海外版の『SOUL BLADE』)オープニングムービーでElectronic Theaterに入賞して以降、幾度となく入賞を果たしている。
原田氏:
はい、その側面は確実にありました。
逆に格闘ゲームの競技性の面だけで言えば、『ストリートファイター』や『バーチャファイター』に「いつ追いつくんだろうこれ……」というくらい、正直に言えばゲームシステムの構築という点で我々は遅れていました。
いまでこそ『鉄拳』も、競技を志向した格闘ゲームとしてe-Sports化されていますが、もともとは対戦の競技性がまだまだ弱かった。少なくともお客さまからはそういった評価を受けていたことは否めません。
ですが、僕らが対戦格闘ゲームとして熟する時間も欲しかったし、予見された暗黒の時代を生き残るためにも、一般に訴求できる戦略に舵を切ったんです。
もちろんそのやりかたは、広くアプローチできるけど、浅いですよ? 浅いですけど、そういう入り口に価値を見出さないと、「格闘ゲームは恐らく生き残れないだろう」という予想があったことは、先に述べたとおりです。
世の一般のお父さんお母さんが、クリスマスやブラックフライデー【※】に「話題のこれを息子に買って行ってやろう」、「このCG一緒に見よう」と思うくらいじゃないと、生き残れないはずという仮説は持っていました。事実、当時それは当たりましたね。
※ブラックフライデー
11月第四金曜日のこと。とくにアメリカでは、祝日である感謝祭の翌日にあたり、感謝祭向けセールスで残った製品の一掃バーゲンが行われることが多く、「もっとも小売店でものが売れる日」とされている。現在は年末商戦がスタートする時期としての意味合いが強い。
FPSに奪われた「ベンチマーク」のポジション
──それが『鉄拳』がいまに至る転機になっていると。
原田氏:
ところがそれも長くは続きませんでした。さらに時代が変わり、対戦格闘ゲームに代わって今度はPCで動く海外のFPSが、いわゆる開発総合力、技術力のベンチマークになっていくんです。
──あー。いわゆるワールドシミュレーターとしてのFPSですよね。
原田氏:
最先端の要素が何拍子も揃ったのがFPSというジャンルになりました。家庭用ゲーム機からではなく、最初はすべてPCゲームからですが、『メダル・オブ・オナー』あたりに始まり、『バトルフィールド』や『コール オブ デューティ』が一時代を築いたときには、彼らがいろいろな意味で最先端になっていたんですよ。

──しかも、大量のプログラマーやデザイナーを同時に動かし、アセットのマネジメントもきちんと整備してですね。そもそも格闘ゲームのころって、そこまで大量のアセットを外部で調達する必要はなかったと思うんですよ。
ところが、FPSに求められる物量作戦になった瞬間に、アセット製作や調達のピラミッドを作らないとできなくなってしまって……。
原田氏:
そうそう。僕らはそれを“大戦”に喩えていて、本当に物量戦争の時代に入ってしまったんです。
僕らは伝統工芸的に、性能にキャップのあるハードウェアで、ひたすらリッチな人体を2体動かすというノウハウは作りました。セガやナムコはポリゴンに関する特許技術も多く持っていていましたし、そういう“刀の道”を宮本武蔵の如く歩んでいたんです。
ところが戦場が、「鉄砲、弓、槍なんでもあり。戦艦も戦車も戦闘機もあり」という大戦化をしたときに、「これは近いうちに技術だけじゃなく、補給・バジェット・そのファンディングも含めて負け始めるぞ」となったと。
──こういってはなんですが、非常に既視感のある敗けかたのようにも思います。それにしても、その物量戦はなぜ始まったのでしょうか?
原田氏:
そもそも昔からCGの技術については、最先端という意味ではハリウッドのほうがゲーム業界よりはるかに進んでいました。ただ、ハリウッドのさまざまな映画を作ってる一流の人たちが、日本のゲーム業界に恐れおののいた瞬間が、1990年代に一瞬だけ存在したんです。
絵の凄さじゃなくて「このレベルのCGをリアルタイムで動かして、しかもこの値段なの!?」という、コストパフォーマンスの点でです。日本人の匠の技術とコスト、とくにリアルタイムのCG描画においては、当時は少なくとも日本のゲームがすべての最先端でした。
 |
ただ、それが世の若者の目を奪っていくのを目の当たりにした、ハリウッドを含めた西海岸の人たちが、「ゲームはわりと儲かるぞ」と理解してしまったんですよ。
その結果、「最先端の映像をここに導入するべきだ」と判断し、彼らの資金と人材が動いたとき、格闘ゲームがベンチマークだった時代が終わったんです。
──ベンチマークとしての価値がFPSに奪われたのは、だいたい2005~2006年ごろですかね。
原田氏:
結果的に、僕らがベンチマークとして評価されていたのは、ギリギリ『鉄拳5 DARK RESURRECTION』(以下、『鉄拳5 DR』)まででしょうね。2006年あたりでしょうか。もともとの『鉄拳5』がプレイステーション2ベースのタイトルで、『鉄拳5 DR』はPSPへの移植、つまり下位互換移植技術の高さなどが欧米で高く評価されていたころです。
そして1990年代からPCゲーマーだった私自身も最新のものが好きなので、そのころには完全にFPSをあらゆるベンチマークとしていましたね。
──その過程で、次なる活路を見出す必要があったはずですよね。
原田氏:
当時、開発として生き残る道がいくつか社内でも語られていました。
ひとつは“メガゲーム”です。これはいわゆる『Grand Theft Auto』シリーズのようなゲームや、もしくはFPSのようなものを、大量に開発費を投じて大量の人間で作ることです。「社内の各タイトルに分かれているチームが一緒になれば、すごいことができるんじゃねえの?」と思ったわけです。
たとえば、当時の『リッジレーサー』チームや『エースコンバット』チームと『鉄拳』チームが一緒に作る、というようなメガゲーム的な発想のタイトルの開発もできるんじゃないかと。これは、どこのメーカーも一度は考えたはずです。
──でもどこも実現できていない。
原田氏:
ここではたと気付くんです──それぞれの開発部はこれほどいろいろなゲームを作ってきたのに、共通しているノウハウがないんですよ。
「当時のナムコは優秀な開発者を生み出す」ところとして業界でも著名だったんですが(笑)、そういう喩えとして「ナムコは道場である」と思ってたのに、じつは看板が1枚の道場ではなく、開発チームごとに「俺は鎖鎌」、「僕は鉄砲」、「俺は居合切り」というように流派が違いすぎていた。
あるいは同じ格闘家だと思っていたのが、じつは芸術家だったりしたという。「これは恐ろしい流派の違いだぞ」、「組織文化と流派が違うぞ」と。
 |
しかも組織文化のあいだを繋ぐ、もしくは境界を溶かすためのミドルウェアやエンジンを持っていない。共通の言語を持っていなかったんです。この時点で、すでに一部の日本のメーカーは自社内で共有できるエンジンを持っていましたが、我々はそうではなかった。
だからそういう風にチームをひとつにするやりかたはできなかった。結局、ノウハウは開発全体のものでなく、個々のノウハウでしかなかったんです。
先に述べたように、各チームがイチからスクラッチで作る文化でしたからね。かといって、我々が格闘ゲームという自分たちの得意分野を捨て、急に「FPSをやろう」といっても無理……というループに陥る。
──確かにそうですよね。「『リッジ』チームと『鉄拳』チームで何かを一緒にやれ」といわれてもパッと想像がつきません。ビジネスとしての規模感も見当つきづらい。
原田氏:
それで言うなら、「どのくらいの量を投資してどのくらい回収するか」という判断も問題でした。初代プレイステーションのころは、日本が大きな投資で挑戦といいますか、「賭け」に出られた最後の時代だったと、いまになれば理解できると思います。何が当たるかまだわからない時代ですから、各社こぞって最新技術に投資したり、新しいジャンルで賭けに出られた。
「久夛良木が面白かったからやってただけ」 プレイステーションの立役者に訊くその誕生秘話【丸山茂雄×川上量生】
でも一大事業化して、収益手段がある程度安定してしまうぐらい所帯が大きくなったら、どうしても大きな賭けに出にくくなった。これは日本のゲーム業界全体に言えたことだと思います。
──ところが、欧米はそこにガンガン投資していくわけですね。
原田氏:
欧米には当時から、CTO(チーフテクニカルオフィサー)という職業が存在していました。これは“最先端のテクノロジーを理解したうえで経営判断をする人間”というものです。
エンジニア出身の場合もあるし、クリエイター業出身の場合もありますが、簡単に言えば「最先端の技術の勘どころ」があって、それの価値が理解できて、そしてそれにどれくらいお金がかかるかがわかる。そして何より「そのテクノロジーによって時代がどうなるか?」を予測したり、ビジョンを見出せたりするような人材です。
最先端テクノロジーが理解できるから、4、5年先が読める。読めるから、投資の判断ができる。
たとえばミドルウェアやエンジンの開発って、それ自体ではお金を産まないですよね。それ自体を売るなら話は別ですが、我々のようなゲームメーカーは基本的にはそれ自体を売るわけじゃない。だから投資の種類の中でも、こうした研究費みたいなものが「どれぐらい費用対効果があるのか」などは見えにくい。
でも、もしテクノロジーに対するリテラシーやアンテナがもっと高ければ、「プログラマーを50~100人と並べる時代だったり、AIや物理演算を多用する開発や効率化が求められる時代が来たりしたときには、それに対応するエンジンとミドルウェアを作っておかなきゃ」という判断はピンとくるわけですし、当時欧米のメーカーにいたCTOの人たちは、少なからずそういう投資判断をしていた。もしくはここが理解できたエンジニアがその立場へのキャリアパスを歩んでいた時代だったんですよ。
アメリカ、とくにハリウッドを含めた西海岸は、時代を読んでいろいろなことやり始めるわけですから、判断も早ければ投じるお金も多い。そうやってやっぱり向こうが先行したわけです。
──日本は、なぜその判断ができなかったのでしょうか?
原田氏:
これは私見ですが……やっぱり、我々日本のゲーム業界は、ある意味で若かったんだと思います。急に一大産業化した業界だったので、経営層にはCTO的な存在も当然いない。まあ、現在でも日本の業界にはCTO的なポストが確立されているようには見えませんが。
 |
その一方で、北米のシリコンバレーなどは当時すでにエンジニアが起こした会社も多かったし、後のIT業界の経営者にはエンジニア出身が多く、ゲーム業界の外からもそうした人材が多く流入していましたからね。
そもそもエンジニアだったりテクノロジーに対する知見や勘どころが高い人の地位は、日本よりは高いし、重宝される風土がありましたね。
当時、日本では自分たちの得意なことを曲げてでも欧米の真似、いわゆる大量開発ゲームというものにシフトしようとした時期もありました。
でも結局「その選択肢は厳しかろう」ということになりました。失敗もありましたし、実際に膨大な開発費を投じたけれど、陽の目を見なかったタイトルもあります。
──メガゲームへの道は容易なことではなかったと。
原田氏:
時代の象徴だったりベンチマーク的な存在として求められたりするものは、時代とともに変化するのでしかたない。FPSとて、いつか地位を奪われる可能性はありますから、そこにこだわってはいられません。
そういうわけで、我々はメガゲームではない道を探すことになります。それが『鉄拳』の歩んだもうひとつの道──徹底した“アナライズ”を踏まえた海外展開でした。
調査してわかったヨーロッパ・アメリカ
──徹底したアナライズ。具体的にはどう進めたのでしょう。
原田氏:
まず「格闘ゲームはどういう受け入れられかたをしているのか」について、いわゆる市場調査をしました。
21世紀に入ってからですが、当時のナムコでは初めての試みでした。調査と言っても、いまほど洗練はされていないし、あくまで徹底してデータを集めるところから始めたんです。
でも、それまでは顧客データと言えば売り上げ本数しか見えていないわけですから、「市場、つまりプレイヤーからどう受け止められているか」は、じつはまったく解っていなかったんです。
たとえば家庭用ソフトだけで言えば、じつは『鉄拳』ってヨーロッパがいちばん売れるんですよ。『鉄拳7』まで合わせて、『鉄拳』は家庭用のシリーズで累計4600万本売れてるんですが(2017年7月末時点)、なんと半分以上がヨーロッパなんです。
その次がアメリカ。一国で考えるとアメリカはいちばん大きいのですが。アメリカの次はアジアや南米やオセアニア、日本は全体の5%あるかどうかという分布なんですよ。
でも、当時はこれも「なんか欧米でやたら売れるね。とくにヨーロッパで売れるね」という感じで、その理由は解っていなかったんですよ。
ですから「これはまずい」と、どの国で、どういう年齢層が、どういう遊びかたをして、どういう見かたをしているのか……ということを調査し始めました。
──結果はどうだったのでしょう?
原田氏:
当時の調査だけでも、いろいろなことが判明して面白かったですよ。
まず、ヨーロッパで売れてた理由のうちのひとつが面白かったですね。
当時、ヨーロッパだけは自社でパブリッシングしておらず、当時のソニーグループが扱っていたんですよ。つまり、「『鉄拳』って日本のソニーのやつでしょ?」、「父ちゃん、ソニーのプレイステーションと『鉄拳』買ってきたよ」というような認識で買う人が多かったんです。ソニーグループのブランドイメージは強くて、これは『鉄拳』のブランドイメージを1ランク押し上げていたところは少なからずあったというのが見えてきたんです。
さらに調べると、ヨーロッパはさまざまな国があるので国によっても違うんですけど、わりと家庭的な感じで受け入れられていることも判って、学校帰りに友達をひとりふたり家に連れ込んで対戦したり、会社帰りに集まって遊んだりという、ちょっと昔の日本のファミコン時代の遊ばれかたに似ていたんです。
──それは面白いですね。
原田氏:
とにかくヨーロッパでは「ソニーパブリッシングの格闘ゲーム」という認識が持たれている時代があった。
「『パックマン』のナムコだよ」と言いたくなるところですが、海外では「『パックマン』はMidwayのゲーム」と誤解してる人さえいましたからね。パブリッシングや流通の強みが地域に大きく影響していた事例ですね。
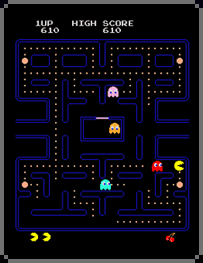
(画像はパックマン ウェブ PAC-MAN WEB|WHAT IS PAC-MANより)
そうすると、たとえばヨーロッパでソニー製品のように認知されて売れているなら、「パブリッシャーはずっとソニーがいいんじゃないの」という判断もできたりするわけです。
あるいは、ソニーのイメージを分析すると、ほかの格闘ゲームと売れかたが違うということに気づく。すると「これは絶対にストーリーや最先端のCGムービーなどの価値観を盛り込むことが必要だ」となるわけです。
結局、僕たちは『鉄拳6』からヨーロッパでもパブリッシャーになるんですけどね。そんなわけでじつはそれまでのヨーロッパにおいては『鉄拳』ブランドはかなりソニーグループに育てられた部分がありました。
──なるほど。アナライズの結果、打ち手が見えてきたと。
原田氏:
あとは、キャラクターの人気と役割なども見えてきました。人気は地域ごとに違い、それぞれ必要な役割がある。日本でもアメリカでも人気じゃないけど、ヨーロッパのここで人気のキャラクター……のようなものが見えてくるわけです。
たとえば、ヨーロッパではよく吉光がポスターでメインで使われていたりしました。
私たちのイメージだと「メインは風間仁にしましょうよ」と思うじゃないですか。当初は「なんでやねん、意味わからん」と思ったんですが、ヨーロッパではそういった部分でもアートに対する意識が違うんですね。パッケージの色使いや広告宣伝の手法もまるで違っていた。
左から『鉄拳3』、『鉄拳5』、『鉄拳7』の吉光。時代に合わせてデザインもどんどん変化していく
英語の表記も、別にかっこいいと思っていなかったりして、民族のいろいろな思いが反映されているんです。「欧米」ってよくひとくくりにしますが、ヨーロッパに足を運んで現地の文化を学べば学ぶほど、「アメリカと全然違うじゃん」と思いましたね。
調べるうちに分布が見えてくるので、「デザインはある程度全方位にカバーできるように作らなきゃいけない」となるし、「キャラクターのターゲットも分けよう」という話になる。
ちなみに、よく「開発者があのキャラを嫌っている」など言われたりしますが、それは皆さんの思い込みです。真面目な話、キャラクターが30人いたら、30人のキャラ全員が自分たちの息子や娘みたいなもんですよ。
しかも嫌な言いかたをすれば、娘息子がある意味で稼ぎに出ているわけですよ。そうなると本当は全員がいちばんであってほしいんです。でもよく考えると、全員がいちばんになるのはあり得ないんですよね。だから、個々にターゲットする地域や層を与えて、役割を担ってもらうわけです。
──確かに、『鉄拳5』、『鉄拳6』、『鉄拳7』あたりのキャラクターを見ると、過去の作品とは分布がまったく違いますね。
原田氏:
『鉄拳3』以降を眺めると、こうした兆候があることに気づくと思います。シリーズを追うごとに地域を意識した戦略から、各種のコミュニティ層へ展開していくのがわかりますよ。
あ、当然僕の思い付きのようなキャラクターもいますけどね。そこは別ものということで(笑)。
「アナライズ」だけが自分たちに残された武器だった
──それにしても、いきなり海外の調査、そしてある意味で現代的なマーケティングをやろうとして、成果を上げていったのはすごいことですよね。原田さんは、もともとそうしたマーケティングをやられていたわけではないですよね?
原田氏:
……僕は、うーん、これを僕の立場で言うと誤解や怒りを買うかもしれませんが、じつは本来……正直、マーケティングというキーワードは嫌いだったりするんですよ。「殺し文句」にするにはあまりに意味が広い言葉なんですよね。
だから僕がやってるのはあくまで仮説を立てたあとに、それらを分析や検証してというプロセスなので「アナライズだ」と言い張ってるんです。昔、社内でも調査に基づいたマーケティング手法が多く語られていたんですが、それともまた違うんですよね。とにかく、あまり前面に押し出して掲げるのは本来好きじゃない。
──それは、作ってる人たちの感覚からすれば、そこに引っ張られてしまうからでしょうか?
原田氏:
うーん、それもあるかもしれないけれど、もっと違うところですね。
 |
たとえば過去の日本のこの業界には、マーケットやらなんやらのことを考えずにアイデアを産み出し、素晴らしいカリスマでチームを引っ張る超クリエイティブな天才が何人もいたわけですよね。と言いますか、多くのゲームがそうやって生まれてきたことはじつは誰も否めないはずです。
その人たちは、いわゆる調査だとかマーケティングなんてやる必要がなかったんです。「あらゆる分野が未開拓だった」、そういう時代だったということもあります。
当時はたとえば、格ゲーで言えば鈴木裕さんもそうだし、『ストリートファイター』を作ったアリカの西谷亮さんをはじめとする人たちなど。私は何度も皆さんと話していますが、アプローチがやっぱり僕らの世代とは全然違う。そもそも時代背景が違う。
『ストII』で格闘ゲームを生んだ伝説の男、西谷亮が挑むジャンルの再構築──『FIGHTING EX LAYER』にアリカが社運をかけて臨む理由【聞き手:「鉄拳」原田勝弘】
きっと、あれは1960~70年代にUFOが来襲して、どこかの宇宙人から「ピッ」って何か信号が送られて受け取った人だけが作れたゲームだと思うんですよ。
当時僕が大好きだった『ダブルドラゴン』を作った人々や、『ウルティマ』シリーズ作ったリチャード・ギャリオットは、絶対に宇宙人から、お腹にいるときに何かをされているんですよ(笑)。少なくとも学生時代にはそう感じていた……というのがあって。
──1980~90年代半ばまでエースの方々って、ネジがどこか飛んでいますよね(笑)。
原田氏:
皆さん言わないだけで、僕はああいう天才は人類じゃないと勝手に思っています(笑)。
そして、誰しもそうだと思いますがもちろん僕にも、そういう人たちへの憧れがやっぱりあります。「こうありたいものだ」……という思いがどこかにあるんでしょうね。だから「マーケティングだとかアナライズだとか、アイデアには関係ねえよ」と本当は言いたい、言い切りたいところがあるんでしょう。
だから、キーワードとしてもあまり好きじゃないというのがあるんだと思います。そもそもマーケティングというもの自体、かなり細分化されるべきもので、ひと言では語れませんからね。
 |
ただ、暗黒時代を乗り切るために、彼らのような天才が生み出した『ストリートファイター』や『バーチャファイター』に対して、ちょっと頭を捻ったアイデアや模倣で勝負していると、「まったく追いつかない……追いつかないどころか、『鉄拳』というIPはあと数年で消えてしまうだろう」と、その当時はそうやってすべてを受け入れて認めることにしたんですよ。
でも、一方では「追いつきたい」、「追い越したい」と思うわけです。そうなると当然、彼ら天才世代のクリエイターとは違う武器が要りますよね。
──その武器こそがマーケティングもといアナライズだった。
原田氏:
そうです。とはいえ僕の初期の唯一の武器は、たとえばとても低レベルなところから始まったんです。当初は「ソフトに封入されていたアンケートはがきを片っ端からすべて読む」とかだったんです(笑)。
あとはアーケードのデータですね。死にそうになりながらあらゆるプレイデータを集めて、統計データを積み上げ徹底的に分析して、自身の仮説やアイデアだけでなく、当時ようやく普及し始めたインターネット掲示板で、「いちユーザーが言っていることが、大局的に本当に言われていることなのか」の分析や検証をするわけです。
僕は足し算引き算が嫌いなんですけど、それでも地道にやった。当時は若かったし、真夜中にそんなことばかりしていた。休日も好き勝手にやっていましたからね。
そしてデザイナーやプログラマーに「どうする?」と訊かれたときに説得力を持たせてアイデアや意図を伝えられるように備えていたんです。
 |
そうすると、他人から集めたデータを分析した結果から導き出した答えを、まるで自分の中からアイデアが湧き出しているように言えるわけじゃないですか(笑)。とにかく僕には武器が欲しかった。それがアナライズだったんです。
──アナライズの考えはどこから出て来たものだったんでしょう?
原田氏:
もともと、大学で心理学をやっていたというのもありました。僕のやっていた臨床心理実験では「有意な差が認められるか」を仮説を立てて検証していくのですが、統計的な根拠が必要なだけに、いわゆるオカルトが許されない世界です。
たとえば人格や性格的な特徴を見出す場合、実際臨床心理的に統計を出していくと、身長の高低などによる有意差は認められるんですが、いわゆる日本でよく言われる血液型の4タイプだと統計的に有意差が認められないんですよ。
血液型占いなどが語られますが、こうして大規模に統計データを集めて分析していくと、少なくとも現在の科学的な定義では、一般にみんなが言っていることと現実には随分と乖離があると判るんです。
──そうなんですか(笑)。
原田氏:
そういう客観的な事実を知ったときの衝撃ってあるじゃないですか。そうすると、ものの見えかたが変わってきますよね。
ただ、何でもそうですが、盲信というか思い込みの力は怖くて、間違った方向に舵を取ることが開発の中でもあったんです。「第三者評価はすごい重要だ」と思って躍起になってデータを集めてアナライズするんですが、胸に刺さる痛さを伴うこともいっぱい出てくるんですよ。まあ、それがいまのSNSにも繋がるんですけど。
統計データをアナライズしていると、その世界を俯瞰して見られ、あらゆる事実が可視化されていくのがたまらなく面白いし、物事の基準としてかなり合理的だし、民主主義的だと感じるのですが、それに憑りつかれると何故か自分の心がどんどんフラットになっていくんです。モノづくりに対する“熱”さえもが統計データに吸い込まれるような気がして。
──かなり興味深い示唆です。
原田氏:
その反動もあり、数年前からSNSで個々の意見に耳を傾けて自分の心を刺激に晒すようにしたんです。たとえば“ノイジーマイノリティ”と言われる極端に偏った意見なども、ときにはいい意味で心に刺さりますからね。統計的な根拠や民主的なものとはまた別のところで「腑に落ちる」ということがある。
 |
とはいえ、あの暗黒の10年を生き残るために、そしてトップシェアを得るためには、あらゆるデータを読み取ることで「格闘ゲームがどう売れているのか」を当時の僕らが知る必要があったのは間違いありません。そしてそれを知ったときに、「それがひょっとしたら、ゲームの仕様にまで落ちてくるかもしれない……」と思ったんですよ。
──調査・分析されたデータから入念に傾向を読み解くとともに、一見反目しそうな声量の高い叫びや勢いのようなものも丁寧に拾い上げていく。それらを納得のいくバランス、お言葉を借りれば「腑に落ちる」ところまで融合させていったと。それが『鉄拳』がいまも続く鍵になっているわけですね。
どのように調査を行ったのか?
──先ほど、「いまほど洗練されていない」と仰っていましたが、調査自体はどのように進めたんでしょうか?
原田氏:
従来からやっていたマーケティングやアナライズもいちおうあって、それらの統計データを僕らはゲームの開発に役立てていました。ゲームセンターの基板の中に入っている、キャラクター使用率や勝率を含めたあらゆる操作データなどの実プレイデータを蓄積した“ADSデータ”というものです。
日本全国のアーケード店舗から400店舗をピックアップして、そのADSデータをFAXしてもらったり、海外のデータも熱狂的なファンやマニアにお願いして送信してもらったり。
いまは世の中がオンライン化されていますが、当時はとにかくデータを集めるのがたいへんな時代でした。
それに加えて先に述べたアンケートはがきなどですね。あとは、言える範囲で言えば海外ではしっかり予算を使って調査会社は使いましたね。それからコミュニティにディスカッションしてもらう手法とか。
その数年後に、僕のやっていたアナライズの流れとは無関係で手法も違いますが、社内でもこうした調査ブームのようなものが起きたこともありました。そのときによく言われていたのが、「ほかの業界ではこうした調査やいわゆるマーケティングは当然のように行われてきた」という話でした。
──確かに、ほかの業界ではよくあることです。
原田氏:
そもそも、ゲーム業界も昔はさほど調査する必要なかったんです。アーケードマシンが市場の中心という時代であればゲームセンターに行けば、少なくとも最先端のゲームの遊ばれかたというのは見られたので。
自分たちがゲームセンターへ行って、「おー、このゲームをまさかの横並びでやるんだ」というように観察していました。そこにはちょっとした気づきもありますよね。「あ、どの格闘ゲームでも投げばっかりやってる人は嫌われるんだな……」など。調査としてはかなり低レベルではありますが。
──僕もアメリカで『バーチャ』をやったとき、がんがん投げを使っていたら、「ヘイ!」って言われて台を蹴られました(笑)。
原田氏:
投げって上段ガード不能じゃないですか、3Dの世界で言えばね。「なんか卑怯だよ」と言われる(笑)。いまはまた違いますが、当時は「一般人は投げを嫌う」という傾向はあったんですよ。
 |
それからとくに欧米では“リングアウト”のシステムが嫌われる傾向にありましたね。「俺のほうが体力で勝っていたのに、最後に押されただけでなんで負けんだよ」というフィードバックが日本と比較したときに圧倒的に多いというのは当時から気付いていました。
だから『鉄拳』にはその後もリングアウトは入れず、どちらかというとどんどん壁で囲むなどオクタゴン的なシステムを特化させていったんです。
──ああ、そういう理由があったんですね?
原田氏:
でもそういうお国柄や地域コミュニティ文化の違いって、プレイヤーの皆さんに家庭に引っ込まれると見られないじゃないですか。
だからゲームセンターが海外で崩壊し始めたとき、日本やアジアではまだプレイヤーのプレイを直接見られたり、ADSデータも収集できたりするけど、欧米での遊ばれかたが「家庭に完全に閉じちゃって見えなくなる。マズい」と慌てたんです。
それは何度も述べているように、当時はまだ全世界的にオンラインのインフラも整っておらず、家庭用ゲーム機にもネットワーク機能がなく、あっても接続率は異様に低かったですから、家庭に閉じられてしまうとプレイデータが収集できなくなるので。
それで「家庭用で閉じられた海外の遊ばれかたをなんとか調べよう」となり、調べてデータを並べてアナライズしてみたら、捉えられかた、売れかた、遊ばれかた……全部が地域や国によって意外に違っていたというわけです。





































