「観戦」それ自体から収益を得るのは難しい?
──では、ここからは最後に「今後、格闘ゲームはどう収益を上げていくか」をテーマに伺っていきたいと思います。海外まで見越してビジネスを行っている『鉄拳』が、どんなふうにそれを考えているのかは、とても興味があります。
そこで重要になるのは、現況を考えるとeスポーツになりそうですが、ただ、いまeスポーツの状況を考えると、行方にはふたつの道があると思うんです。
ひとつは買ってもらうためのイベントとしてのeスポーツで、もうひとつは、完璧に興行としてのeスポーツ。いまは、後者が新興勢力になっていて、「ゲームって買ってもらわないと儲からなかったけど、もしかしたら遊ばない人からもお金を集められるんじゃないか」ということで、経営層などは興味を持ち、団体などを作っているんだと思います。
昔ながらのゲーマーは、いわゆるEVOのような、ゲームプログラムとしてのeスポーツを連想するんだけど、「いま注目されているeスポーツはそうじゃないよ」というのは、一般の人は知らない状況じゃないでしょうか。
原田氏:
そうですね。新しい世代の人たちは、わりと見たり応援したりも好きで、ただ応援するだけじゃつまらないから自分もちょっとやって、そこで解ってくるともっと面白い……という盛り上がりかたをしていますね。
昔だとこうです。ゲームセンターで、たとえばブンブン丸が戦っているとしますよね。それを見て、「ああ、あいつは〇〇って技を単に当てに行ってるんじゃなくて、こういう場面では置いてるんだな。なるほど、この技はこんな風に予想して置いときゃいいんだ! やったぜテクニック(セオリー)を盗んだ!」というものだったんですよ。
高橋名人×ブンブン丸×ウメハラ:eスポーツ座談会──名人ブームの影響からプロライセンス発行の本音まで
現在でも、こういう観点で観戦する側面や客層は当然いますけど、格闘ゲームに限らず、明らかに新しい動きはあります。たとえば有名な選手のプレイを観て「すげー! つえー! もう少しで優勝だ、頑張れ、頑張れ!」と興奮して、「泣いてる、負けて泣いてる悔しそう!」と感情移入して、「畜生、いつかあの人が世界大会で優勝してほしい! 頑張って!」とSNSで応援する。
そして、「彼がやっているキャラクターやゲームをもっと知れば、もっと楽しめるんじゃないか」と思ってゲームを買ってくる。そして「ええ!? こんな難しいことをやっているんだ」と改めて知る。これがいまですね。昔と方向が違うんです。
──いま、将棋の女性ファンがすごく増えていますが、完全にその入りかたですね。
原田氏:
メジャー化するってそういうことなんでしょうね。
 |
──とはいえ、「じゃあゲームはどうやって売ればいいんだ」という話になってきますよね。観戦を入り口にしてゲーム本編を買ってくれる人はいるにしても、本質はそこじゃない。
すると今度は、お金をいただくポイントを変えていくという話になります。たとえば野球だったら、昔はそうやって憧れてグローブを買ってもらったわけですが、いまはそうでもないですよね。
原田氏:
そうなんです、昔は、ミズノとかZETTとかが力を入れてたのはそこじゃないですか。いまは明らかに違って、ドリンクだったりしますもんね。
──この先、格闘ゲームのマネタイズを考えると「興行で儲ける」ことも視野に入れざるを得ないと思うんです。そうした魅せる要素を、どうビジネスの中に組み込んでいけばいいのでしょうか?
原田氏:
EVOをESPN【※1】が中継していて、『ストリートファイター』などは視聴された実績がありますよね。
また、『鉄拳』もアメリカのTurnerが放映するeスポーツテレビ番組『ELEAGUE』【※2】でシリーズ放映され、番組史上1位2位を争う視聴数となっています。このように、これらの番組は、スポンサーなどを含めた周囲の経済がわかりやすく賑わったひとつの例となったはずです。
ただ現時点で言うと、これらは特殊な例で、格闘ゲームに限れば一部でしか起きていない現象であって、まだまだ一般化しているわけではありません。
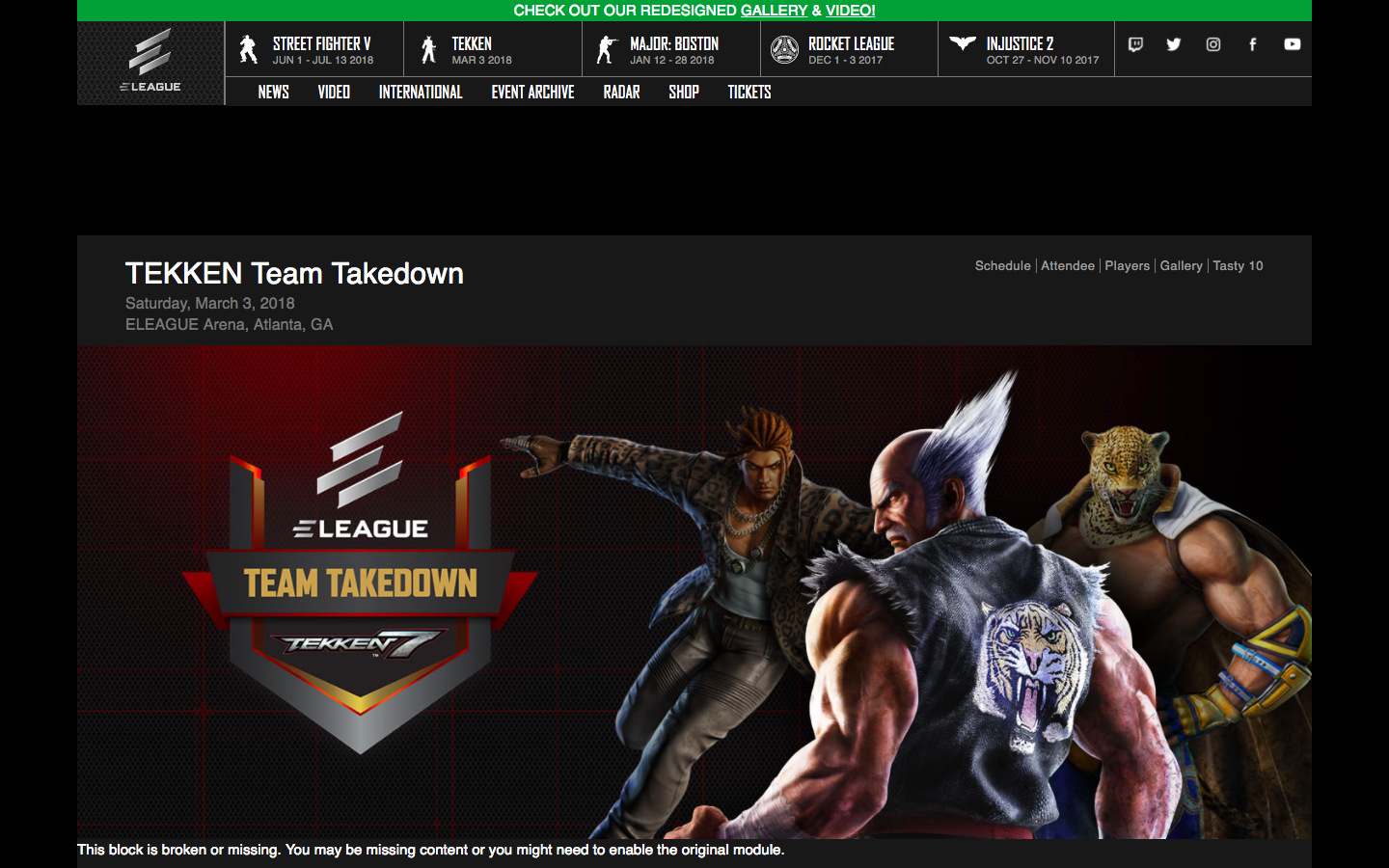
(画像はELEAGUE|TEKKEN Team Takedownのスクリーンショット)
※1 ESPN……Entertainment and Sports Programming Networkを略した、アメリカのスポーツ専門チャンネル。1979年開設。ウォルトディズニー傘下。NFL、MLB、NBAやモータースポーツなどメジャーなものから、ビデオゲームやマインドゲームなどまでを含めたさまざまなスポーツ中継を行っている。
多くの場合は、たとえば配信関連会社そのものだったり、食品会社や飲料メーカーがスポンサードして中継している。ある意味、企業広告の域を出てない……というと語弊がありますが、そのレベルで起きている話です。
これもカプコンの小野さんともよく話すんですが、じつは格闘ゲームというレベルで言うと、eスポーツはここのところ大きな変化はあったものの、いわゆるeスポーツというものが、世に言われるキーワードほどの状態になっているかというと、理想にたどり着くまでには、まだまだ大きな段階がありますよね。
eスポーツによって起きる経済効果が、我々ゲームパブリッシャー側にどういう利益をもたらすかは、現状だとまだまだ非常に計算しづらい。こうした広告宣伝は、費用対効果がどう顕在化したかの指標や分析が難しいんですよ。
──そうでしょうね。
原田氏:
たとえば飲料メーカーは非常に判りやすくて、10~20年かけてブランドを作って世に定着させるものなので、宣伝に使えるバジェットは新製品開発の開発費よりはるかに多い。バジェットの8割から9割が広告宣伝費に使われるらしいですね。
ゲーム業界は、ゲームの面白さの賞味期限もあり、飽きられたら新しいものを作らないといけない。飲料などに比べると、短期のマーケティングでどう売るか、もしくは買ってもらった1本のソフトをいかに長く遊んでもらって、たとえば追加コンテンツに投資してもらえるか、という課題があるんですね。
ビジネスの見地で言えば、ゲーム本編以外にマーチャンダイズなどで別途の売り上げがあればなおいい。そこにeスポーツという新しい注目株、間口が登場したので、業界が色めき立っているという現在があるわけです。
こういう動きは、広告宣伝用の出口を探してる企業にとっては非常に喜ばしいことですよ。プレイヤーに、スポンサーからの契約料やTwitchのドネーション機能による収入が集まるのもいいことです。大会を開催する側にお金が集まるのも喜ばしいです。
──ゲームメーカーとしてはどうなんでしょう?
原田氏:
仰るとおり、そこは「パブリッシャーやデベロッパー側は、どうなの?」という話に最終的にはなってくるんですよ。生臭い話をすると、我々パブリッシャー側で「eスポーツ単独でバッチリ儲かってます!」と胸を張って、堂々と言える状態のところはごく少数の例を除いていま現在ではほぼないと思いますね。
とくに格闘ゲームの界隈だと、eスポーツそのものによる直接収入はじつはまずないわけで、現時点ではプロモーションの域を出ていない。
 |
極端な話ですが、eスポーツからの直接収入によって、次の格闘ゲームが作れるぐらいの収入、要はパッケージやデジタル配信でゲームを売って儲けたお金と同じくらいの興行収入が得られるかというとそれはまずない。
我々はゲームを売った利益を株主と社員に分配し、残りを次の施策やタイトルに充てることでこれまで回って来たわけですから。このサイクルの中にeスポーツというものが入ってこれるのかどうかはひとつのエコシステムの指標になるかもしれませんが、じつはそうならない可能性もまだあるわけで。
──なるほど。思っているよりもシビアだと。
原田氏:
とくに日本だと法律の問題もあったので、自分たちから仕掛けるのが難しかった。
団体の設立などありますが、日本では少なくとも現状から大きく変わらないことには「これはファンイベントである」と割り切るしかありません。
eスポーツは、プレイヤーや配信する側だけでなく、当然メーカーやパブリッシャーが得られる利益もないと、最終的には回らないところもあって、メーカーやパブリッシャーが積極的にサポートしていきたい反面、環境面で言うと、なかなかビジネス化できないよね……と、他のメーカーさんともよく話しています。そういう漠然とした状態ですね。
格ゲーの立ち位置はIPへ
──ではeスポーツに対して、収益という意味では可能性は残されていないのでしょうか?
原田氏:
eスポーツに周囲が色めき立っているのは、先にも少し触れたとおり、eスポーツが遊びかたや遊びによって生まれる“付加価値”が増えたように見える“象徴的存在”だからだと思うんですよ。
生活の中でモバイルやネットワークの価値が高まって、昔は存在しなかったライブストリーミングなどが生まれてきた。そのタイミングで観る価値を持つeスポーツが、「これは新しい間口になるぞ、何か商売になるぞ」という実感をもってバズワードとしてハマったと言えるでしょうね。
昔はゲームや映像もすべて物質的な価値だったじゃないですか。カートリッジが入ったパッケージだったりテープだったりしたわけで、それがだんだん光ディスクのような安価な媒体になり、ついにはフィジカルなものではなく、ネット配信になり、ソフトウェアのデータに、つまりデジタルコンテンツに価値がある……ということになった。つまり物理的には存在しないはずのデジタルアイテムに価値が生まれてきた。
──価値を認められる部分がどんどん遷移していると。
原田氏:
かつては物理的なパッケージを売ることだけで一生懸命に利益を生み出してたわけですが、今度はライブイベントで攻められるようになった。たとえば弊社の『テイルズ オブ』シリーズだったら、“テイルズ オブ フェスティバル”などでアリ—ナを満員にできるわけですよね。

あとは『アイドルマスター』が、すごい付加価値を生み出したいい例ですね。『アイドルマスター』って本編のゲームはタイトルごとで何本売れるかというと、これはみんなが知ってることですが、10万本や15万本という規模です。この数字を聞くと「それだけ?」となりますが、いやいやいや、そういう話じゃないんですね。

この『アイドルマスター』というIPを中心に携帯ゲームだったり、周囲へ広がっているライブイベントだったり、グッズ展開だったり、そちらが本編以上のすごい広がりを見せているわけです。ゲーム本編はコミュニティのコアで中心地であっても、必ずしもそのIPの収益の中心とは限らないわけです。
──「IPとしてどう展開していくか」という考えかただと。
原田氏:
ゲームから生まれたIPは、アニメやグッズ、スピンアウトのゲームなど、いろいろなところに広がっていけます。
単なるゲームだけだったタイトルをIP化することが、いかに価値が高いか……ということをこの業界は20~30年かけて学習してきたわけですよね。すると「ゲームがどうか」という話だけじゃない、総合エンターテインメント事業になっていきます。
──要は、これまではIP=キャラクターだったのが、キャラクターがないものでもIPができる、ということですね。「対戦を見る」という行為そのものがIP化するというか。
原田氏:
そうそうそう。YouTuberもそうですが、視聴されることであれほどお金がもらえるなんて、昔は誰も思っていなかった。あれで億万長者が生まれるなんて、思いもしませんでしたよね。すると、ひょっとしたら我々にも「応援する」、「観る」という形で、野球みたいに「観客が付加価値にお金を払う時代」が来たんじゃないのか……これは誰でも思いますよね。
ただそこにはいろいろなハードルがある。「構造的にスポーツと違うぞ」というところは見えていて、パブリッシャーから直接、「eスポーツから得る利益が多いようにして」とは、なかなか言い出せない状況にある。
──そうですよね。いずれにせよ、従来のゲームビジネスとはだいぶ毛色が違う話になり出しているように思います。
原田氏:
結局、昔は「エンターテインメントといえばこれ」、「ゲームといえばこれ」、という作品性の強さや個性だけで勝負できていたんですが、いまのようにゲーム以外のエンターテインメントを含んでしまうと、群雄割拠どころじゃない。
その中で、自分たちのタイトルだけを、いや、ゲームだけを手に取らせるようにするのは難しくなってきています。
だからある意味で、これはゲームメーカーどうしの闘いじゃなくなっているんです。昔で言えばゲーム会社どうしがライバルであり敵だった。「打倒○○!」みたいなね(笑)。しかしいまはそういう争いじゃない意識レベルです。
ゲーム業界の、40代半ばでそれなりの役職を務めている人が集まるコミュニティがあるんですが、そのけっこう有名なクリエイターも含めた集まりでときおり出てくるのが、「このメンツで飲み会をするなんて、昔は考えられなかったね。正直「殴り合うんじゃないか?」と思うくらいのライバルだったし」という話なんです(笑)。
結局、「いまやライバルや敵はゲームメーカーじゃないよね」ということなんです。それこそ、あらゆるデジタルプラットフォームや総合的なエンターテインメントでシェアを広げているところは、すべてライバルになってくるわけですから。
ゲームタイトルどうしとか、ゲーム機シェアの取り合いやテレビ画面の取り合いのときは過ぎて、いまやあらゆるものとの「時間の奪い合い」であり、IPの闘いなんですね。
──もはや勝負のポイントがIPへと移行しているのだとすれば、特定のメディア内での勝負の重要性は下がりますからね。
原田氏:
ずっとゲーム市場のコアにいるお客さんにとっては、いまの話なんて言うのは「しゃらくせえ」ぐらいに思えるでしょう。
「俺たちは自分自身でいいものを見つけられる目を持っている」。もうそれでいいんです。そういう人たちはそれでいいんですよ、ありがたい存在です。
でもいま、そうしたコアなファン層から一般的に広げるのはすごく難しくなっているんですよ。スマッシュアイディアやスマッシュヒットは出るんですが、それをほぼ恒久的な大きなIPまで持っていくには、あいだに大きな溝があるんですよ。
その溝を超えるためにものすごいお金もかかる。単に「twitterやfacebookのアカウントを作って話題を拡散していけばいいんでしょう?」みたいな時代ではまったくなくなった。もっと高次の付加価値を生む仕掛けがあちこちで必要になってきたんです。
「発売後にどう売るか」を考える
──そうした総合的なIPとしてのゲームの運用は、日本よりも海外のほうが長けているんでしょうか?
原田氏:
それはまさにそうで、海外市場を長年にわたり見てきて気付いたのは、欧米の人たちは、ブランディングを日本よりもかなり早い時代から専門的にやる部署があったり、専門的に取り扱う会社やエージェント会社があって、しかも製品を企画する段階から、売れかたと売った後のバズの作りかたまで、かなり意識してやっているということです。
つまり「売れているビジョンを全員で先に見ながら、それをゲームの仕様にまでどう落とし込むか」という長期スパンのプロジェクトを起こせるようになっている。
 |
たとえばちょっと前までこの業界は、日本の場合だとゲームの発売2ヵ月前から、ガーッと宣伝をして、発売後の1~2ヵ月でひとスパンが終了というものでした。
しかし欧米は以前から違っていたんですよ。リリース前の広告宣伝的な動きは無論ですが、「リリースしてからの広告宣伝イベントや、話題のスパイクの曲線をどう作るか」という部分で違っていた。
発売前2ヵ月と、発売後2ヵ月が勝負ではなく、欧米の場合は市場性の違いから、最初から「1年売るぞ」という意識でいた。これが近年が「2年売るぞ、3年売るぞ」になってきてる。「育てるぞ」と。
──それはマーケティング技術の問題なのか、それとも嗜好を含めた問題なのでしょうか? これはあくまで僕のイメージですが、「出した瞬間の成果がすべて」という意識が、ハードウェア含めて、日本の商品全体に多いんです。
ところが、とくにアメリカがそうですが、「出したあとにどう売るか」を考える人々がきちんとリスペクトされているように思います。
原田氏:
それは根本にあると思いますが、もうひとつ理由があると思っています。それはじつは経済格差の側面や、価格に対する価値観の違いです。
日本は中流階級が多いので、みんなは定価のあいだで新作をバッと買っちゃう。少なくとも他国に比べるとはるかにそれができてしまう層が厚いのは間違いない。
欧米でも、当然最初から定価で買うのが気にならない人が最初に買います。でもそうでない人々は、値下がりやセールの時期にようやく「欲しかったあれが買える」んです。そして、所得階層が上から下まで深い多層構造になっているわけですよね。
 |
それから面白いのが、もちろん海外にもトレンドもあるし、「オワコン」に近いキーワードもありますが、それでも日本ほど「みんながやってないからもうやらない」という焦燥感のようなものが少ないこともある程度影響しています。
海外では、「いいものは時間がある程度経過しても、時代を経ても長く売れ続ける」というのは比較論として間違いなくありますね。
──それは、コミュニティができたことも関係してるんですかね?
原田氏:
あるかもしれませんね。コミュニティの中で世代交代するので、その世代の中でまた買い直しが起きたりして長く売れます。『鉄拳3』なんて、リリースした1年目で、国内130万本、ワールドワイドで430万本だったのが、2002年まで5年かけてなんと830万本まで伸びました。その時期まで初代プレイステーションの扱いがあったこともすごいと思いますが。

(画像は『鉄拳6』公式サイトより)
『鉄拳6』も、最初の1年で350万本売れて3年経過後にどうなっているのかを調べたら、累計枚数400万枚突破、500万枚突破……と、どんどん伸びていて驚きですよ。発売後数年経過して、なおそのペースで売れるというのは……。
──すごいですね……。そんなコミュニティの形は、日本国内では機能していませんよね。
原田氏:
とにかくこんなに足の長い売れかたは日本ではまずありえない。商習慣だけでなく市場性も違うので、売りかたや戦略も変わってくるわけですね。
売り始めからどこまで伸ばせるかが勝負
──そうした「長く売る」IP戦略を考えると、ゲームをリリースするリズム感も変わってくるのではないでしょうか?
原田氏:
「巨大IPを毎年世に出す」というパターンはちょっと崩れてきていて、2~3年に一度などになってきますね。『コール オブ デューティ』でさえ、毎年出すことを止めたじゃないですか。ふたつも開発ラインを抱えているのに、2年に1回ですよ。つまり、ひとつの開発ラインだった場合、3~4年に1回のペースになるわけですよ。
裏返せば、1本で2~3年は稼ごうという時代になった。元のゲームのファンに対して、どれだけゲームのパッケージ以上の付加価値を認めてもらうかが重要になっているんです。
これまた面白いデータがあって、ひとりあたりの購入本数は落ちても、1本あたりのプレイ平均時間は昔よりはるかに長くなっているんです。
──それは興味深いと言いますか、これまでのお話を裏づけるデータですね。
原田氏:
昔はパッケージを売って終わりの商売ですから、ある意味「手離れが悪いゲームは、いつまでもアップデートが必要なのでしんどい」みたいな言いかたをされていたんですけれども、いまは逆ですよね。
売り始めからどこまで伸ばせるかが勝負です。必然的に、ゲームの内容や提供されるコンテンツに変化が現れるわけですが、そこでゲームの運営ノウハウやマーケティングのノウハウ、コミュニティのマネジメントなどが重要になってきますね。
 |
そういう意味でいうと、スマホのゲームが運営の力で長くひとつのタイトルを保っているというのは、そのモデルのある意味典型例なんですよね。
──そう考えると、日本が持っていた従来の家庭用ゲーム機でのビジネスのノウハウは、死んでしまうのでしょうか?
原田氏:
やはり従来の、たとえば大きなゲームパブリッシャーがたとえば年間に100本ものゲームタイトルを発売して、とにかく短期でパッケージを売って儲ける……ということはちょっと難しくなっていますね。
本当にIPのファンであるという方たちにしっかり買っていだたいて、それを長く愛してもらわなきゃいけなくなってきています。
ゲームの遊ばれかたとしても、「いま流行りの携帯ゲームで遊ぶ」という生活習慣は、我々がいわゆる家庭用ゲーム機系のコアなエンターテインメントと呼んでいた「テレビの画面の前に座って、時間をしっかり取ってガッツリ遊ぶ」ものとは違う。
昔のしっかり遊ぶ時間を確保できる若い世代が多ければ、まだまだ「じっくり座して遊ぶ」スタイルは伸ばせるのかもしれませんが、一方で日本の場合、今後の若い世代の人口減少も考えると、なかなか難しいんではないかとは思います。
ただ、たとえばサウジアラビアやインドネシアなどには20代の若い世代がとても多いので、世界に目を向ければ、これから期待が持てる国がいっぱいあるのも事実です。
──今後、いわゆるアメリカ・ヨーロッパと、中東や東南アジアのような地域、さらに日本というのは、ある程度分けて考えないといけないわけですね。
『鉄拳』はどうあるべきか
──そんな状況下で『鉄拳』はどうされていくんですか?
原田氏:
いまに始まったことではないんですが、『鉄拳』もこの日本と海外市場とのギャップが激しいタイトルなので、もろもろの点で難度は高いです。

『鉄拳』の場合、アーケードはいまやアジアだけのビジネスになっています。一方で家庭用の場合は、いまやなんと売れる枚数の95%以上が海外になっているわけですから。
海外からすれば、『鉄拳』のように1タイトルごとに300万本以上売れるのであれば、「開発費はいまよりもっとかけていい」という判断になるわけだし、「より広げる方向にしていきたい」という方向性になる。しかしそうなると日本と構図が逆転してしまうわけです。
──なるほど。
原田氏:
もはやゲーム業界は、ゲームの面白さ、つまりアイデアや技術力ですべてが決まっているかというとそうではないんです。
昔みたいに「天才ひとりの素晴らしいアイデア」があって「素晴らしい天才プログラマーがひとり」いれば売れるという時代ではない。そういう時代もあったかもしれないし、事実ありましたが、いまは違います。「ゲームが面白くても売れない」ということも大いにあり得る。
たとえば面白いかどうか以前に手に取ってもらうまでのハードル、「売れた」という状況に至るまでに必要なビジネスやマーケティングの要件は、昔に比べて確実に増えている。
ですので単純に面白いゲームを作ればそれで確実に売れて、確実にフランチャイズとして何年もシリーズが継続されるなんてことはあり得ない。そんな中で、こうした投資や正しい評価もそのフランチャイズの継続に大きくかかわってくる要素になってしまってるんですよ。
そんなことを語ると必ず「原田氏が言う方向性は間違っている。もっといいゲームを作り、顧客満足だけに集中しろ。時代や環境の話を持ち出すな」と言われることもあります。
でも、ゲームのビジネスはそういうことだけじゃなくなってきているんです。一大事業化してマーケットがこれだけ大きくなったいま、もはやゲームだけじゃないこのデジタルエンターテインメントの業界全体での競合、時間の奪い合いです。マクロな視点で物事を俯瞰することが必要な業界になってきました。これは僕みたいな、もともとピュアに物づくり、いわゆるピュアな開発をしていた方や、ピュアなゲーマーには受け入れがたい部分もあるわけですよね。もっと世の中シンプルなはず、シンプルだったはずだと。
──そうした状況では、いったい何が必要なのでしょうか?
原田氏:
もちろん、ゲームを面白くするアイデアやタレントは必要なんですけれども、そういった才能に合わせてマーケットを読める人や最先端の技術に合わせた投資判断ができる人がいる、というそれぞれの役割が果たせる人たちが最初から集まったチームで、ビジョンを作り上げる必要があります。
ゲームの生みかたの難しさは、ずっと変わりません。ただ、売りかたの難度は圧倒的に上がっているわけです。「すごいものができました。どう売りましょうか」じゃもう駄目なんです。
作るとき、作っている段階からどう売れるかを考え、いわゆる開発系の人間と、マーケティング系の人間が「このゲームがヒットしているビジョン」をちゃんと描いて、そのために必要な要素やゲームの仕様やニーズに対する答えを開発時から盛り込んでいく必要がある。
そして、発売までのマーケティング&PRキャンペーンのロードマップが当然あって、「この構図なら勝てる」という状況でタイトルを生み出していかないと、勝てないという時代になりました。そこには、「売れる前から売れると運命づけられた」かのような広告戦略、企業の取り組みが必要なんです。
──なるほど。原田さんから見て、それをうまくやっているメーカーやタイトルはありますか?
原田氏:
私見ですが、日本で言えば現時点(2017年末)で恐らくワールドワイドで700万本は売っているであろう、『ファイナルファンタジーXV』でスクウェア・エニックスの田畑さんのチームは、相当な仕掛けをされているように見えました。明らかに過去にないペースと規模で売れている。

あれは明らかに、ビジョンがあって逆算して考えられて設計された側面がゲームにも垣間見える。「こうじゃないと勝てない」というビジョンから組まれた基礎設計がね。
出たあとにはいろいろなコラボレーション施策が待っていたわけですが、あれとて相当前から仕込んでいないと絶対にできないことですよね。売れていくさまを最初から描けているから、それにしっかり乗ってくる第三者も企画当初から現れるわけです。
──仰るように、開発の段階で売りかたを仕込んでいると。
原田氏:
そんなふうに、「ゲーム開発側とマーケティング側がビジョンをひとつにして設計していく」という体制を作りながら、ゲーム設計時に始まり、発売、発売後の展開を5年間ともにしている、というプロジェクトチームの回しかたが必要なんです。
まさに最先端の技術と、最先端のマーケティングと投資が三位一体になって出来上がっている、というやつです。
今後は本当にそういうことが必要なんですが、当然スクエニさんですら全部のタイトルでできているわけではないだろうなと思います。
欧米メーカーも全部できているわけじゃないですけど、エレクトロニック・アーツさんや、アクティビジョンさん、ユービーアイソフトさんなどの大きな企業は、やっぱりかなりのレベルで先に挙げたプロジェクト体制を仕掛けることができています。
──たとえば?
原田氏:
たとえば、『Destiny』や『オーバーウォッチ』は、売られる前からしっかり市場は温まっていて、「売れると信じられている」状態が作られていましたよね。
あれは明らかに、ゲーム開発だけでないマーケティングと一体化した数年越しのプロジェクトチームが成せる業です。加えて、西海岸の優れたエージェントたちがあらゆるタレントを使っていろいろなことを仕込んで、広告宣伝上「絶対に売れる戦略」を組んだうえで、満を持して出てきたタイトルです。
もちろん、ゲーマー視点で言うと、ゲームの良さだけでこの仕事を語りたいんですよ。でもね、「一大事業化、大きな産業になるというのはこういうことなんだな」という時代の変遷を目の当たりにしましたね。「ああ、そういう時代になったんだな……」って思いますよね。
格ゲーのビジネスモデルの試行錯誤
──ただ、偶然かもしれませんが、日本にはいくつか格闘ゲームの強いIPを作る会社があって、世界でミリオンを売る実力がある。ならば、そこで最新の手法を使って世界に売るしかないのでは、とも思います。
原田氏:
それは当然あります。
ただ、最新の手法といっても、格闘ゲームにはジャンル自体が持つ限界が当然あると思っています。
たとえば「Free to Play化したらどうだろう」というのは、『鉄拳』でもやってみましたが、すごい数の人が集まるわりに、アイテム購入などで収入が大きくなるかというと、そうでもないんです。
当たり前ですが、プレイヤーは「何かを装着する」などにはお金をかけず、結局「プレイするため」のアイテムがいちばん売れるわけです。
──格闘ゲームファンは、キャラクターのアバターを飾るところにお金をかけなかったわけですか。
原田氏:
あまりかけませんね。カスタマイズ的な遊びは、当然遊びの主体ではないので。かといってキャラクターの性能を「アイテムでどんどん変えられる」というのは競技性の本質からは外れてしまう。
そうなってくると「Free to Playでいろいろなアイテムをつける」とか、「性能変更アイテムをを買ってもらう」というのは、なかなか難しかったりするんです。
──確認しておきます。アーケードゲームにおいては、ワンプレイ100円を積み上げてきましたよね。それが家庭用ゲームやPCで「パッケージを買ったら遊び放題」になりました。
さらにそれをFree to Playにして、100円を入れてもらうのと同じように何かにお金を払ってもらうというゲームシステムは、結局成立しなかったんですね?
原田氏:
プレイしてもらうひとつの手法としてある程度成立しても、じゃあパッケージビジネスや昔のアーケードのように儲かるかというと、そうはならなかったですね。
少なくとも、単純に「アーケードビジネス的な手法を、家庭用のFree to playになぞらえて導入する」という試みだけでは足りないんだろうなと思います。
──たとえばアーケードがなくなった海外において、Free to Playは、アーケードの代わりになる大きな収益を得る状況を作り得なかったのでしょうか?
原田氏:
そうです。ビジネス的な規模では代替手段にはなり得ませんでした。そういう意味で言うと、ものすごい数の人は集まるので、とてつもない広告効果はありますが、メインのビジネススキームになるかというと、少なくとも格闘ゲームにおいては、シンプルなFree to Playは難しいでしょうね。
『デッドオアアライブ』の早矢仕洋介君とも話したんですが、『デッドオアアライブ』のやった手法は、Free to Playの形はとっているものの、「キャラクター単位で購入もできますよ」という新しい形の販売方法でもあるし、同時に本編を買ってもらうための導線となっているわけですよ。
ですので買いかたの間口は増えているんですが、「Free to Playがメインのビジネススキームかどうか」で言えばメインではない。
自社と他社の例から見ても、現状だと根本的なところの「格闘ゲームの基礎パッケージを一度買っていただく」というところがメインであることは変わっていないんです。それを補完する、補強する仕組みとしてFree to Playが機能している部分はありますが。
──なるほど。すると完全に新しい形のビジネスモデルの模索は、思うほどうまくいっていないと。
原田氏:
ただ、たとえばいろいろなジャンルでも起きている事象ですが、格ゲーで言えばカプコンさんは初めてシーズンパスの2年目を展開されましたよね。
ああいう感じで、1年2年というスパンで遊ぶようになって、昔みたいにゲームを買い、1週間で遊んでクリアしたら次のゲームだ……じゃなくなってきているという事例はあります。
 |
ほかのエンターテインメントとの時間の取り合いがある中で、「年間に買うのはこれだけ」と自分のお気に入りのIPを決まったものとして買って、長く遊ぶという時代になったので、そこは変わりましたね。ただ……そこは変わったけど、じゃあ根本的なビジネススキームをひっくり返すものになるかというと、そうでもない。
「なるほど、やっぱりゲームってビジネスモデルに起因する形で、構造が形成されているところは大いにあるなあ」と、いまさらだけど思いますよ。
──そうなんですよね。スマホゲームもいろいろ言われますが、あのビジネスモデルの中でやっぱり楽しいゲームですから。
原田氏:
だからヒットしてるし、楽しいんだけど、あれをPCや家庭用ゲーム機にそのまま持っていくのは、なかなか難しかったりしますよね。
それは当たり前で、薄々知っていたし、解っていたことだけど、やっぱり格闘ゲームみたいにアーケードというビジネスモデルで古い歴史を持つジャンルは輪をかけて難しいです。
──だからこそeスポーツに期待……という話に戻るわけですが、開発元には意外と利益が入ってこないみたいな状況があるわけですね。
原田氏:
だから、あのー……あらゆるゲームのすごく大きい大会とかで、年間何回も優勝したある選手の年収を見ては、小野さんと僕とで「俺ら選手になったほうがいいんじゃないか」と冗談で言っています(笑)。腕が追いつきませんので完全に冗談ですけどね。
でも、そういう意味ではいい時代になったとは思います。プレイヤーが大金を稼ぐという状況は、ひと昔前なら考えられなかったわけですから。
──昔のいわゆる名人・鉄人という人たちは全然儲かってはいませんからね。スタープレイヤーになった人たちが、きちんと一流のスポーツ選手と同じような扱いになっているということは間違いなく進化だなと思いますね。
原田氏:
全員が全員じゃない、わずかですけどそういう人々が出てきたのは、面白い構図かなと思いますね。
ただ、プロがプロたる所以という定義が、いまやっぱり混沌すぎて。ライセンスの話題に始まり、「少しでもスポンサー企業がつけばプロなのか」とか、「年収いくらからがプロなのか」とか、明確な規定はないわけで。自他ともに認めるプロは、やっぱり圧倒的に少ないですね。それはちょっと、僕らも無責任ではいられないと思います。
格闘ゲーム市場を「継続」するために……
──最後に、格闘ゲーム市場の今後についてお伺いしたいです。
原田氏:
何よりも、市場を、IPをちゃんと継続しないといけないですね。
たとえばeスポーツという新しい切り口から見ても、サッカーや将棋と違って、「ゲームはやっぱりメーカーが作らなきゃ始まらない」ということなんです。
つまり我々が投資をして、競技の基礎フィールドを作るところから始めないといけない。そうしたことを継続したり拡大したりしていくためにどうすればいいのか、ファンコミュニティの未来とエコシステムの連動を考え続けないといけません。
──コンピューターゲームという柱からできた視聴型のエンターテインメントを確立するには、まだどんなブロックを積めばいいかを考えないといけない段階なんですね。もしかすると『オーバーウォッチ』などの、ブリザードの人とは接点が見つかるんじゃないかなという気はします。
原田氏:
あの人たちも、じつはマーケティング側も強いから、ああいうことができているというのはありますからね。
──しかも最近のブリザードは、日本のテイストも理解してコンテンツ作りを始めているじゃないですか。
原田氏:
そうなんですよ。そうなってくると「日本の強みってどこにあるの……」という話になりかねない。そこは脅威ですよね。
 |
極端な話ですよ、新しいアイデアに加えていまの時代に合う、しかもマーケティングやアナライズも込みで設計して作った格闘ゲームが生まれるなら、結構面白いものが出てくる可能性を秘めていますよ。
格ゲーとて、はっきり言っていまとなっては技術的ノウハウはそんなに優位性にもならない。単に「作りかたに慣れているかどうか」などはありますが。
ただ、200~300万本じゃ済ませず、「1タイトルで単体1000万本クラスを目指すんだ」という話なら、「じつはストイックな格闘ゲームはそんなに魅力的なジャンルじゃない」という側面がありますよね。
──以前、電ファミの座談会でも、原田さんと同世代のクリエイターから同様の言葉がありましたが、この規模のところの“中間のゾーン”にほかは入って来ないので、格ゲーはそこでまだ頑張りたいということでしょうか。
原田氏:
そうですね。もう欧米の真似をしようとしてもなかなかできないジャンルがけっこういくつかあるので、格ゲーはまだ頑張れるのかなと思います。
ところが、「欧米の人に日本の真似は出来ないだろう……」と思っていたら、できるところも増えているので、そこの危機感は凄いわけです。もはや格ゲーだって真似なんて誰でもできるわけですから。
当然我々日本のメーカーも頑張ってますから、そういう意味ではお互いの境界がだんだん溶けていくという側面もあるんでしょうけれどもね。
最後は、そんな状況の中で「我々はどこに向かうべきか」ですね。(了)
 |
テクノロジーの進歩はプレイヤーの生活環境の変化を促し、生活環境の変化は嗜好の変化を促す。
こうしてビデオゲームの黎明期より活況を呈していたアーケードビジネスは2000年前後を境に崩壊に向かった。
このとき、坐して待つのではなく、“アナライズ”によってプレイヤーたちの要望に耳を傾け、積極的にブームに左右されない広い客層の獲得、すなわち“魅せるゲーム”への舵取りをしたことで暗黒の10年を生き存えた『鉄拳』シリーズは、決して楽な闘いではなかったが、気づけば孤高の存在となり、ジャンルの中でトップの地位を築き上げていったのだ。
これは、対戦格闘ゲームという、もともと日本が得意としていたジャンルで、先人たちの知見の積み重ねのうえに成立していた分野であればこそ、継続できた側面もある。だが、日本はエンジンやミドルウェアの開発による効率化と、大量に人をマネジメントしてアセットを量産し、大きな作品を生み出す部分で立ち後れていた。
『鉄拳』はその中であっても成功した希有な例だ。冒頭のグラフ分析に紐付ければ、WiiやニンテンドーDSの全盛期にもその先を見据え、地道なアナライズを重ね、IPの醸成を怠らなかったことが成功に繋がっていると言えるだろう。
同時に『鉄拳』の歴史は、アーケードゲームというビジネスモデルに紐付いた面白さに支えられていたゲームが、時代の要請に合わせ姿を変えつつも面白さを提供し続けた、変化の歴史とも言える。
話を伺うほどに、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』しかり、『モンスターハンター:ワールド』しかり、つぶさにその成立の過程をたどることによって、同様の足跡が見えてくるのだろうと感じた。これもまた追って丁寧にヒアリングしたいところだ。
そして今後。
次回も『鉄拳』同様に、全世界を相手に奮闘するタイトルや人物を取材することで、日本のゲームの世界での存在感がより強く意識される示唆を得られればと思う。
繰り返しになるが、前回記事のような不備のないよう、あらためて誠心誠意に反省するとともに、編集部ともども気を引き締めてこのテーマを掘り続けていければ幸いだ。
【あわせて読みたい】
米欧日の家庭用ゲームソフト市場は5:4:1の比──なぜ日本のゲームメーカーは世界で戦えなくなったのか【西田宗千佳:新連載】西田氏による連載序文も合わせてお楽しみください。時代の変化のさなか、日本のゲーム業界はどのような戦略をとっていったのでしょうか?


































