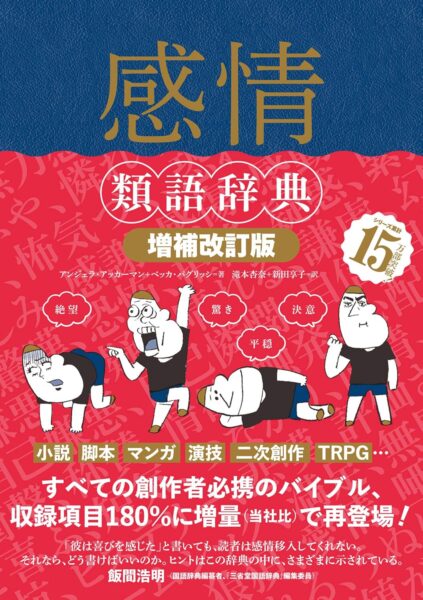2021年9月30日に、TooKyo Gamesとアカツキによる共同プロジェクト『トライブナイン』の詳細が発表された。これは、『ダンガンロンパ』などでおなじみの小高和剛氏を中心としたTooKyo Gamesのクリエイターたちと、有名IPのスマホゲーム化で数々のトップセールスタイトルを生み出しているアカツキがタッグを組んで、完全オリジナルの新規IPを生み出すプロジェクトだ。
 |
この『トライブナイン』は、2020年初頭に概要とコンセプトムービーが発表されていたものの、今回の発表でスマートフォンゲームやアニメといったメディア展開の全貌や、キャラクターをはじめとする世界観の細部が明らかになった。
『トライブナイン』では架空の東京を舞台に、23区それぞれを拠点としているアウトロー集団が抗争を繰り広げていく。この抗争がユニークで、野球をモチーフにした「エクストリーム・ベースボール」によって決闘が行われる。東京の街中をバイクで疾走したり、殴り合いのストリートファイトが展開されたりと、まさにエクストリームなバトルになっている。
 |
発表会では2022年1月よりTVアニメ放映が行われることに加えて、スマートフォンゲームの開発が本格的に開始されることが明らかにされた。ゲームはスマートフォン向けながら、高品質な3DCGを駆使したアクション要素が採り入れられているとのことで、どのようなゲームプレイが楽しめるのか、いまから気になるところだ。
電ファミニコゲーマーでは、この『トライブナイン』を生み出すふたりのキーマンに、2週連続でインタビューを行うことにした。第1回目に登場いただくのは、本作の世界観やシナリオ制作を担っている、TooKyo Gamesの小高和剛氏だ。
本作におけるアクの強いキャラクターたちや、エッジの利いたエクストリーム・ベースボールの設定は、じつに小高氏らしいテイストだが、そこにはどのような狙いがあるのだろうか。完全オリジナルの新規IPという「ゼロからイチ」のアイデアを生み出す発想法や、スマートフォンゲームでは異例とも言える膨大な量のシナリオを作成するための体制作りなど、今回の取材では『トライブナイン』を通して、小高氏による創作の根幹に迫ってみた。
 |
※取材に際し、写真撮影時以外はマスク着用、換気とパーテーションの設置等、感染症対策を徹底したうえで実施しています。
※この記事は『トライブナイン』の秘密にエクストリームに迫る、アカツキさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。
自分の判断を押し通すには、クリエイティブでほかのスタッフを圧倒する必要がある
──小高さんと言えば、『ダンガンロンパ』シリーズに象徴されるように、非常に個性的な作風で知られているクリエイターだと思います。今回の『トライブナイン』も、やはり相当ユニークな世界感ですし、なんというか、とても“ケレン味”がありますよね。
小高氏:
ありがとうございます。
 |
──そこで今回の取材では、そもそもこの“ケレン味”とはいったいなんなんだ? これを生み出すには何が必要なんだ? というところに、小高さんへの取材を通して迫れればと思うんです。
というのも、ゲーム制作は基本的に、チームで行うものですよね。でもチーム制作や会社という組織でモノを作るによって、作品としては失われるものがけっこうあると思っていて。そこに対して、小高さんやTooKyo Gamesが持つケレン味だったり、ある種の狂気を注入しようというのが、このプロジェクトの本質のひとつだと感じているんです。
小高氏:
モノ作りについてのインタビューを、これまでにもちょくちょく受けてきたんです。でも、ふとしたときに自分の記事を見つけて読み返すと、言っていることが毎回違っていて、正直ブレブレなんですよ(笑)。でも自分としてはウソを言っているつもりも、その場を取り繕って言っているつもりもないので。「なんで毎回ブレてるんだろう?」と。
よくよく考えてみたら、一個の気持ちでモノを作っていないというか。
作家性を出したいとも思っているし、みんなに受け入れられたいとも思っているし。自分だけのものを追求したくもあるし、チームのみんなの意見を採り入れたかったりもするし。そういういろんな思いで作っているんです。
ただその中で毎回変わっていないのは、「オリジナリティ」というか「この作品の存在意義」みたいなところ。その根っこの部分は毎回変わっていないと思っていて。
じゃあオリジナリティってなんなんだろう? と思ったときに気がついたのは、僕がクリエイターとして育ってきた環境は、大企業の大きなチームに所属して、優れた人たちが周りにいて、先輩から仕事のやり方を教えてもらって……といった状況にいたことが一回もないということなんです。
スパイクに入って企画を通そうというときも、大きな予算がつくことはまずなくて。でも、完成したゲームは大作ゲームと同じ値段で出すわけじゃないですか。そうすると予算でも敵わないし才能でも敵わないから、アイデアで勝負するしかない。当時のスパイクは『喧嘩番長』【※】とか、「なんだこれは?」っていうゲームが多かったころなので(笑)、そういう企画をいっぱい作って、出して、というのを繰り返していたんですけど。
でも、その経験があるからこそ、まずアイデアで特徴を出さないと、売れる売れないよりも先に、作るためのテーブルにすら載らないなというのがあったんですね。
※『喧嘩番長』
2005年にスパイクよりPS2用ソフトとして発売されたアクションアドベンチャーゲーム。番長のキャラクターを操作して街中を闊歩し、他の不良とケンカを繰り広げて「男気」を上げていく。好評を得てシリーズ化されて、ナンバリングタイトルが6作を数える人気作となった。
──でも、個性的であることやオリジナリティがあることと、奇抜なことって、若干違うものですよね。小高さんの作るものは、あえて奇抜さを出しているところもきっとあると思うんですけど、一方で、そうじゃない「確かさ」みたいなものが根っこにあるなと思っていて。そこの部分がたぶん、ほかとの差なんだろうと感じるんです。
これは僕の勝手な定義ですけど、モノを作っている人には、判断の軸を自分の内側に持っている人と、外側に持っている人がいると思うんです。つまりいまの流行であるとか、データに基づく分析によって判断するというのは、判断の軸が外側にあって自分の内側にはない。一方で本当にクリエイターとして尊敬されている人は、判断の軸を明らかに自分の内側に持っていると感じるんです。
小高氏:
確かに周りを見ていると、内側と外側の判断の違いというのはあるなと思ってますね。
──小高さんから見て、自分の内側に判断軸があることと、クリエイターの資質というのは、何か関係があると思いますか?
小高氏:
いまから10数年前に、わりと大勢のゲームクリエイターが会社を辞めて独立していったんですけど、その中には自分の内側で判断できない人が、けっこういたんじゃないかと思うんです。大きな会社にいるディレクターとかプロデューサーって、自分の内側で判断していたと思っていたら、じつは周りがうまいことフォローしていたっていうのも、往々にしてあったんだろうなと。そういう人が独立しちゃって、そこで初めて、会社に守られていたことに気がつくっていう。
僕自身は最初に言ったみたいに、判断自体がけっこうブレブレというか。このときは外側で判断しちゃっているし、このときは自分がやりたいだけだったり。ただそれでも僕が、自分の内側でも「これだ」と決めることができるのは、自分でシナリオを書いたり、自分の頭の中でモノを作っていたりするからでしょうね。
ディレクターでもいろんなタイプがいると思いますけど、僕はシナリオを自分で書くし、ヨコオタロウさんも自分で作れる人だし。そういうふうに自分で何かできる人じゃないと、スタッフを打ちのめさせることができないというか、ひれ伏せさせることができないというか。「ひれ伏せさせる」って言い方はおかしいですけど、そこはスタッフ内でも勝負ですから。
──スタッフ内での勝負というのは?
小高氏:
ゲーム開発の現場では、たとえ自分の内側に判断の軸を持っていたとしても、周りのスタッフに自分の言うことを聞かせられるか・聞かせられないかのほうが、よほど重要だと思っていて。とくにコンシューマゲームの場合、ゲーム開発が頓挫する要因の半分ぐらいがそこにあるのかなと。言ってしまえば、「ゲームクリエイターと名乗っているけど、あいつのどこがスゴイの?」とみんなが思ってしまったら、誰も言うことを聞かないじゃないですか。言うことを聞いたとしても10のうち5ぐらいしか聞いてくれない、というのがあるんです。
チームで作るといっても、ひとりひとりみんながクリエイターなので。その人たちと向き合うには、最終的に「この人はスゴイんだ」と思わせないといけない。僕の場合はシナリオを書けるというのがあったので、自分の判断を押し通せた。でもそういうのを持っていない人だとすると、どんなにおもしろいアイデアを持っていたとしても、周りのスタッフが実感を持って聞いていいかどうかわからないんです。
まったく絵が描けない人が絵に関するすごいアイデアを出してきたとしても「ホントなのか?」ってなってしまう。実際に優れた絵を描く人が同じことを言ったら「たしかに」みたいな感じになるので。結局、その人がクリエイトするモノを見せないと、言うことを聞かないかなと思うんですよね。そこらへんがむしろ大事というか。
嫌われるゲームプロデューサーのイメージってあるじゃないですか。フラッと現場に来て、無理難題を言っていなくなる、みたいな。それも日に日に言っていることが変わるっていう。でもそれって、やってることは自分とあまり変わらないのかもしれないと思っていて(笑)。
でも、僕も思いつきでこのあいだと違ったことを言うけど、僕の中ではスタッフにあまり嫌われていない気がしていて。それはやっぱり、自分が作るものがあるから。そこの差なのかなと。
ほかの作品から受けた「感動」を、こねくり回して新たな形に変えていく
──今回の『トライブナイン』だと、たとえばアウトローをテーマにするという意味では外側の要素として『HiGH&LOW』【※】とか、不良ものが流行ってるよね、みたいな話がある一方で、小高さんの内側には「でもオレならこうする」みたいなものがあると思うんですよ。「これだったら自分にとっての勝ち筋になる」だとか。
※『HiGH&LOW』
EXILE TRIBEによる総合エンターテインメントとして企画され、2015年に放映されたTVドラマを軸に、映画や舞台、ライブなど多岐にわたる展開が行われたプロジェクト。5つのグループが抗争を繰り広げる架空の地区を舞台に、不良たちの友情とバトルが描かれる。略称は“ハイロー”。
小高氏:
正直言って「勝ち筋」みたいなことは考えていなくて。それは売る側のことなので。ただ、いちばん最初に企画を持っていくときには、そのときに自分がいちばんおもしろそうだと思っているものを持っていきますよね。
『トライブナイン』の企画を考えた当時、たしかに『HiGH&LOW』は好きだったし、アウトロー物も好きですけど、いろいろとこねくり回していますから。誇張しすぎた東京23区同士がバトルするという内容に、はたして『ハイロー』のテイストが残っているのか、よくわからなくなっているんですけど(笑)。ただ、自分が「これならおもしろそうだ」と思ったものを持っていって、それが実際に仕事になったということは、どこかで「これなら売れる」という判断が入ったということだと思うんです。
そこからは話し合いをしながら、「こうしたらもっと売れるんじゃないか」と考えて作品を伸ばしていく場合もあるし、「もっと作品として尖らせたい」という理由でこうしたいという判断を下す場合もあるし。だからやっぱり、評価軸は一個じゃないですね。こねくり回しながら、って感じです。
──いちばん最初の「おもしろそう」と判断するのは、直感なんですか? それとも、多少なりとも何らかのロジックがあるのですか?
小高氏:
うーん、ブレンドですね。作っているときもそうですけど、ロジカルに考えすぎると詐欺師くさいというか(笑)。「その論理が本当なら絶対に成功するはずだろう」となっちゃうのは変じゃないですか。結局は「これ、おもしろいでしょ?」と持っていくしかないですよね。
売れる・売れないは時の運もあるし、ゲームって作り出してから3〜4年はかかっちゃうから、出るときには時勢だって大きく変わっている。「いまこれが流行っているからこれを作ろう」とやったところで、出るころにはそれが売れるとは限らない。
とにかく、関わっているみんなが「おもしろそう」と思ってくれることがいちばんの軸かなと思っていて。その「おもしろそう」を広げたり深めたりするために、いろいろ要素を付け足していくことが多いですね。そこがケレン味みたいなところにもつながってくるのかなと。
──自分の内側での判断について、もう少し伺いたいのですが。若いころには、自分の内側の判断を根拠なく信じられる時期がきっとあって、それで作れていたと思うんです。でもベテランの方からは、経験を積んでいくと逆に迷うようになるという話もよく聞くんです。小高さんの場合はいかがでしたか?
小高氏:
そうですね……。上田文人さんやヨコオタロウさんの場合は、自分のワールドを作るというのが内側の判断ポイントになっている気がしていて。本当の意味でのゼロイチですよね。
それに対して僕自身の作り方は、「あの作品のあのシーンを見た感動」だとか「あのゲームを遊んだときのおもしろさ」だとかがベースにあって……。
──基になるモチーフがある?
小高氏:
モチーフというよりは、自分が感じた気持ちの積み重ねというか。たとえばパズルゲームを作っているときでも、『ワンダと巨像』で巨像を倒したときのような、あの感覚を達成したいとか思うんです。じゃあパズルゲームであの感覚を達成するにはどうしたらいい? といった形で判断することが多くて。
 |
だからゼロイチというよりは、いろんなものをハイブリッドにつぎはぎしているというか。自分ならではのワールドを作りたいというよりは、「ここはあのときのあの感動」とか、そういう形で作っていることのほうが多いですね。だから広い意味では真似ているのかもしれない。その最初の感動がなければ、原動力にはなっていないので。
──でもそれは、作っているものが元ネタと近いか遠いかだけの話だと思うんです。上田文人さんにしても、ご自身の中に何の感動もなくやっているわけではないでしょうから。それが絵画なのか、実際の遺跡なのかはわからないけれど、何かに感動したときの想いがあって。その感覚をゲームに落とし込もうとしているんだろうなと、完成したゲームを遊んでいると思うんですよ。
だからここでポイントになるのは、縮小再生産になっているか、なっていないかだという気がします。
小高氏:
確かに。そこはそうかもしれませんね。
──あとは、自分自身は「これはイケてる」と思うものでも、それがはたして「お客さんにまで届くんだろうか?」と思うこともあるじゃないですか。「自分としてはイケてると思うけど、ちょっとニッチだな」とか、「これはニッチじゃないから届きそうだ」とか。そこの判断とか肌感というのは、どういうものですか?
小高氏:
そうですね……「これは他人に見せられる行為かどうか」という判断だと思います。
たとえば、ギャルゲーがめちゃくちゃ流行っていて、ギャルゲーを作れば売れるっていう時期に、ギャルゲーをあまり知らない僕が真似て作ってみても、それは小手先のものになってしまう。これは、あらゆる要素がそうかなと思っていて。
──自分の中にちゃんと持っているもので戦わない限りは、ほかの人にも届かないという意味ですか?
小高氏:
そうですね。さっきの話で言うと、僕のアイデアのスタートには「『スターシップ・トゥルーパーズ』の虫がいっぱい押し寄せて来たときのピンチ感を味わせたい」だとか、「『鬼滅の刃』の鬼舞辻無惨みたいなヤバいキャラにしたい」、だとか、他の作品から受けた感動があって。だからこそ、それをそのまま真似てしまってはいけないから、いろいろとこねくり回して変えていくんです。
でもスタートにあるのはその感覚なので、つねにいろんなものを吸収するようにはしています。ゲームもたくさんやるし、映画も見るし、マンガも本も読むし。それをやらなくなったときが、もう何も湧いてこなくなるときかなと思っているので。
──ということは、映画を見たりマンガを読んだりして、それについて仲間内でしゃべったりしているのですか?
小高氏:
いや、それはあまりしないですね。
──あくまで自分の中で消化していくんですね。
小高氏:
悪口のときはけっこう他人に話したりしますけど(笑)。逆におもしろかったときは「おもしろいなぁ」で終わるので、あまり話さないかな。「あの作品は良かったよ」という情報交換のほうが多いですね。「『オッドタクシー』はおもしろかったよ」、「じゃあ見てみよう」みたいな。
感想は自分の中に貯めておけばいいというのと、あとは『テネット』みたいな映画にしても、別に理解したいとは思わないというか。僕はさっき言ったようになんでも手広く見るほうで、逆に深くハマったことがない。「『テネット』を見たあの感覚」というのがわかりさえすれば、難解な感じをやろうと思ったときにああいう感じを思い出せればいいかなっていう。
──でも、それをいざ自分でやろうとしたときには、ある程度解析というか、読み解かないといけないと思うんですけど。
小高氏:
そこはでも、いろんなものをたくさん見ていて、なおかつ自分で作った経験もあれば、だいたい読み解けちゃうというか。
野球という体裁を取れば、どんなに無茶なものでも入れられる
──『トライブナイン』の場合、広げたり深めたりする作業は具体的にどういったものだったのですか?
小高氏:
僕は『ハイロー』に限らず不良物が好きで、不良物で群像劇をやりたいというのがまずありました。ただ、不良物で普通に○○高校とかを作っても「それって『喧嘩番長』だよな」と思ったので、そこから「東京23区をそれぞれ誇張していったらおもしろいんじゃないか」と考えて、今回の世界観ができたんです。
 |
最初は普通のバトルでもいいかなと思っていたんですけど、単なるバトルじゃ地味だと思って。それでバイクとかを使おうと思ったんですよ。まだアカツキさんに持っていく前だったと思いますけど、小松崎類君とかしまどりる君とかに、いろんなバイクデザインをお願いして。ロボっぽいのもあったり。いろんなデザインとかアイデア出しをやってたんです。でも「バイクも意外と普通じゃないか」みたいな話になってきて。
そうしたときに打越鋼太郎さんが「街中で野球をやっちゃえば、なんでもできるんじゃない?」と言い出して。一塁と二塁のあいだをバイクで走ってもいいし、ベースの上でバトルしてもいいわけだし。そこは「野球をやりたい」というよりも、野球という体裁を取れば何でも入れられる、というところで。そこで『地獄甲子園』とか『アストロ球団』みたいなものが頭をよぎって「それはおもしろいね」と。ただ、ああいうマンガみたいにバタ臭くなるよりは、もうちょっとファッショナブルな方向でやっていこう……という感じで企画がスタートしました。
──小高さんが思う不良物のおもしろさやカッコ良さというのは、言語化するとどういうものですか?
小高氏:
不良物のおもしろさって、やっぱり「キャラ立て」じゃないですか。とくに『疾風伝説 特攻の拓』【※1】とか『カメレオン』【※2】とか、僕がハマっていたころの不良マンガだと、新キャラが登場してきた時点ですごくキャラが立っているんですよ。ほかのジャンル、バトル物やファンタジー物よりもキャラが立っている印象があって。やっぱりちょっと狂ったキャラクターが多いので、そこに惹かれたところはありますよね。
※1 『疾風伝説 特攻の拓』
1991〜1997年に『週刊少年マガジン』で連載された、佐木飛朗斗氏原作、所十三氏作画の暴走族漫画。いじめられっ子の浅川拓は、暴走族で名を馳せる鳴神秀人に憧れてツッパリデビューするが……。
※2 『カメレオン』
1990〜2000年に『週刊少年マガジン』で連載された、加瀬あつし氏によるヤンキー漫画。中学校でイジメを受けていた矢沢栄作は、高校進学を機にヤンキーデビュー。持ち前のハッタリと悪運で周囲の不良たちに認められていく。
──ヤンキー物ならではのキャラの立たせ方というのは、どういうものでしょう?
小高氏:
ヤンキー物ってSFやファンタジーと違って、舞台がリアルじゃないですか。だから見た目とかであまり差が出せないし、変身するだとか、そういう特殊なキャラにもできない。あくまで思想とか口調とか行動とかでキャラを際立たせる。だから「こいつはヤバいヤツだ」というのを描きたいなら、ヤバいことをどれだけやらせるか、みたいな感じになっているところがグッときますよね。
──極論すれば人を殺しちゃうヤツがいちばんヤバいのかもしれないけど、ヤンキー物ってそうじゃないですよね。別に人も殺していないのに「こいつはスゲェことをやっている!」って思わせるのには、何かテクニックがあるのでしょうか?
小高氏:
そこはけっこう言語化しづらい感覚でしかないですけど、言葉とか伝聞でそれを説明するよりも、リアルでそれを見せるのが早いですよね。『特攻の拓』の一条武丸みたいにツルハシを持ってガガガッ!って現れれば、「こいつはヤベェ」っていうのが一発で出せるので(笑)。そこは絵の力もあるかもしれないですね。
──「これ、カッコイイよね」、「これ、いいよね」と思っても、言語化できないものってたくさんありますよね。そういうときにTooKyo Gamesの仲間内であれば、その伝達効率はかなり高いと思うんです。
小高氏:
そうですね。
──だけどそれがアカツキさんとやり取りをするとなると、伝達効率がけっこう大変になるんじゃないかと思うんです。言語化できないものをどう落とし込むかについて、小高さんが困難に直面したことはありますか?
小高氏:
ウチには絵を描ける人間がいるので、その絵力がかなり大きいと思います。とくにキャラクターや世界観に関してはそうですね。誇張しすぎた東京23区の例として「オオタシティってこんなところなんだよ」と口で言ってもピンと来ないけど、絵を描いて「こういう街なんです」とやれば、「あぁ、なるほど」と思ってもらえるので。
そこはやっぱり、僕らが仲間内のチームでやっている利点のひとつです。だから開発会社とやり取りする段階で「伝わらないなぁ」と思ったことはないですね。むしろそこはうまくやるようにしています。
それでも絵とかキャラクターは伝わるんですけど、『トライブナイン』の「エクストリーム・ベースボール」みたいなものはやっぱり、「街の中で何をやるのかわからない」というのが出てくるので、最初にティザーPVをTooKyo Games主導で作ったんです。あれを見てもらえば一目瞭然で、スタッフさんの側にもプロモーションの側にも伝わるようになる。
そういう意味では、伝わるように自分たちでも努力しているので、そこの部分で困ったことはないですね。もちろん細かい部分で伝わりづらいこと、たとえばこの『トライブナイン』という作品はどういうカラーなんだとか、『トライブナイン』というゲームのUIはどういったものであるべきなのかといったところに関しては、結局は実際に試しながらやっていくしかないので。
──その場合、最初の叩き台みたいなものは、小高さんが用意するんですか?
小高氏:
僕が、というかTooKyo Games側で用意して、それを伸ばしていく形ですね。その過程でアカツキさんから新たな要素を提案される場合も、もちろんあるし。
僕らのやり方はどうしてもクラッシュ&ビルドというか、2歩下がって3歩進むみたいな感じなんです。ひとまずこういう感じで出してもらって、それをもとにまたやり取りする、みたいな形で進めることになりますよね。向こうのスタッフの方たちが「この人たちはこういうやり方なんだな」と理解してくれて、それについていってもいいと思ってもらえたら、そこはうまくいくかなと。
逆に「最初から決めてくれよ」、「言ってることが前と違う」となってしまうと、それは厳しいかなと思います。幸い、いまのところはそういうことはないですね。ひょっとしたらアカツキさんの内部では言われていて、こっちに伝わってこないだけかもしれないですけど(笑)。
──そういった進め方は、最初のミーティングである程度の合意が得られていたのですか?
小高氏:
「こちらの言うことを聞け」というパターンだったら、不満が出ていたかもしれないですけど。僕らとしては、相手からも意見を出してくれる人のほうが合うと思っていて。最近は開発会社さんと組むときに、最初にそれを伝えていますね。「そういう人じゃないと無理だと思います」みたいに。
 |
──逆に、開発会社側にある程度まで委ねる部分というのは、どういうところなんですか?
小高氏:
たとえばUIだとか、UIの挙動の部分ですよね。あとは、大まかにゲームで達成したい部分はあらかじめ言いますけど、それを実現させるためのゲームシステムは、まず最初にアイデアを出してほしいと思いますね。
こっちで全部決めるのも「やれ」と言われればできるけど、それだと自分の想像の範疇でしかないので、小さくまとまっちゃう気がして。それよりは「こんなとんでもないものを考えてきました」というのを見てみたいですね。『アンリミテッド:サガ』みたいに「なんでここをルーレットにしようと思ったんだろう」という感動がほしいというか(笑)。