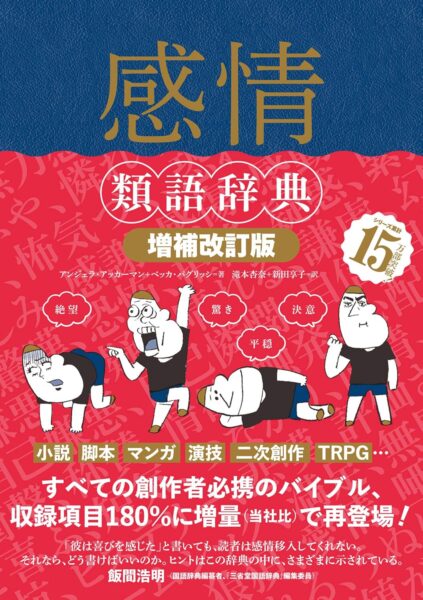最初からジャンル付けすると、ゴールが決まってしまって創作にブレーキがかかる
──これは素朴な疑問なんですが、ヤンキー物って主人公は弱いんだけど、ものすごく強い仲間や敵に食らいついていく話が多いですよね。たとえば「なろう系」の作品などだと、主人公がひたすら「俺TUEEE!」って無双するところに快感を覚えるわけですが。それに対して『特攻の拓』とか『東京卍リベンジャーズ』【※】だと、主人公がひたすら耐える。耐えているところに味方がやってきてなんとかしてくれて「ありがとう」っていう構図が多い。これって、いったいどこが共感されるポイントなんでしょうか?
※『東京卍リベンジャーズ』
2017年より『週刊少年マガジン』で連載中の和久井健氏による漫画。ヤンキー漫画に、タイムリープによる過去改変といったSF要素も加わったユニークな作品。2021年にはTVアニメ化や実写映画化が行われて大ヒットを記録した。
小高氏:
群像劇というのが大きいかな思っていて。群像劇である以上、敵のスゴさや仲間のスゴさを表現しなきゃいけないので、そうすると成長しない主人公だとか、主人公本人は敵に太刀打ちできなくて仲間が助けに来るっていうパターンが扱いやすいのかなという気がしますね。
ただ、それってけっこう特殊ですよね。バトル物だと主人公がちゃんと強くなって自分で何とかするけれど、ヤンキー物は仲間が何とかしてくれる。このパターンが成立するのはおもしろいですよね。
──一方で、『トライブナイン』はどういうところにユーザーの共感だとか、感動を置いているのですか?
小高氏:
『トライブナイン』は、アニメとゲームのほうでちょっと違うんですけど。ゲームのほうでもともと考えていたのは正直、ヤンキー物ではなくて『ONE PIECE』なんです。ある島に行って、敵と戦ったり交流したりして、また次の島に行くっていう、麦わらの海賊団みたいな構成を考えていたので。『ONE PIECE』の島にあたるのが、東京23区なんですけど。
だからある意味、連作短編みたいな感じになればと思っていて。ひとつの区ごとにカラーが大きく違って、ミステリーになったり恋愛物になったりサスペンスになったりという、いろんな要素の入ってくる物語になればおもしろいかなと。そういう意味では、ヤンキー物だからといってヤンキー脳で考えることもしていないというか。
もともとスタートの時点で、それぐらいの振り幅が取れるようにしているんです。最初からジャンル付けしてしまうと、わかりやすくはあるんだけれど、ゴールが決まってしまう。そうするとクリエイティブなところでも、ブレーキがかかってしまうんですよ。逆に、ある程度幅を広げておけば、なんでもぶち込めますから。『トライブナイン』に限らず、どの企画であっても、振り幅を大きく取っておくことが自分は多いですね。
ただ、それが一方では、売るときのわかりづらさにもつながるんですけど。それは『ダンガンロンパ』のときから言われますね。「どう売っていけばいいのかわからない」って。
──さっき話していた「尖り」とか「ケレン味」って、理屈では生まれないものだと思うんです。直感的というか、瞬発力としてのおもしろさをたぐり寄せていくのが、少なくとも小高さんのスタイルだと。
小高氏:
そうですね。さっき平さんがおっしゃったように、これは「なろう系」だとか、これは「タイムリープヤンキー物」だとかいったジャンルを、企画を考えるときには重視していないんです。むしろ「それも入れちゃおうよ」っていう、なんでも入る受け皿を作ることが優先で。それもあるから、自分は広く浅くでやっているのかもしれないですね。
たとえば「ロボット物」という一個のジャンルを深く掘り下げて、そのファンの心理だとか、話の作りのロジックだとか、「これがロボット物のあるべき姿なんだ」みたいなことがわかったうえで作るようなことはしないんです。初見でなんとなく「こうなっているんだな」と感じたことを、「じゃあ、ほかのジャンルではどうなっているんだろう」と、もうちょっと手広くやって、それを自分の作品に活かす、みたいな。ちょっとコラージュ的な感覚が近いのかもしれないですね。
──最近、『BEASTARS』というマンガの作者の方に話をうかがう機会があって。完結した物語全体を見るとすごく整合性があるんだけれど、じつは連載のときには一切考えていなかったと。毎週引きがあって、「つぎはどうなるんだろう?」とドキドキさせることだけをひたすら考えていて、それが結果的に全体のクオリティにつながるんです、とおっしゃっていて。
小高氏:
天才ですね(笑)。小説家の方にもいるんですよ、「一回書いた原稿は読み直しません」という方が。『デュラララ!!』の成田良悟さんなんですけど。「編集者に“間違っている”と言われたら、そこは直します」とおっしゃっていたんですが、たぶんそれまでに頭の中で、相当に練っていると思うんですよね。
僕は自分の書いたものを何十回、何百回と見直しているので、「ライブ感」なのかと言われるとそうでもなかったりするんです。第一稿を書いているときはライブ感で書くし、第二稿ではそれを客観的に見直すし。客観的に見ながらも、ふと思いついたことを新たに採り入れたりもするし。瞬発力で書くところと、論理立てて考えるところをごちゃ混ぜにしてやっているので、その論理すらも体系化されていないというか。
逆に言うと、僕は体系化されていないものを見たときに、いち観客として感動するところがあるので。「なんでここでこういうことになったんだろう?」という、予想がつかない演出だったり、予想がつかないゲーム性だったりにすごく感動するので。そこを目指しているから、あえてスタイルを作らないというか。
──さっきの『BEASTARS』の作家さんの話は、チーム制作と個人制作の対比という文脈で出てきた話なんです。先のことを何も考えずに、毎週毎週を盛り上げる形で描いていったにも関わらず、なぜ物語の整合性が取れているかというと、それは「ひとりの人間がやっているから」だと言うんですね。それはなるほど、と思ったんです。
それで『トライブナイン』の場合、小高さんおひとりで完結しているのは、いったいどういったところまでなんでしょうか?
小高氏:
世界観だったりキャラクターだったりというのは、TooKyo Games内のチームでの共同作業ですね。『トライブナイン』ってまずシナリオ量が膨大で。「こんなにあってどうすんの?」と思うんですけど、まぁそういうゲームもあっていいだろうと思っていて。「スマホゲームとはこういうものだ」という時代でもなくなっている気もするし。
 |
とにかく、ふだんの僕らが作るゲームと同じぐらいのシナリオ量があるので、それを今後も続けていくと想定すると、自分ひとりではとてもじゃないけどできないので、TooKyo Gamesのみんなで手分けして書けるような体制にはしています。
そういう意味では僕だけで完結しているところなんて、ないに等しいかもしれません。キャラクターデザインにしたって、小松崎類君やしまどりる君が僕の言うことを100パーセント聞くかと言ったら、そんなことはなくて。勝手にぜんぜん違うものを上げてきたりする(苦笑)。でも、僕もそれで良ければいいと思っているんです。それはアカツキさん側の作業のところもそうだし、僕が良いなと思えば、それでいいんですよね。
──では、その最終判断の軸を小高さんが持っている形ですか?
小高氏:
そうですね。ただ今回はスマホゲームなので、僕が考える以外のビジネス的側面であったり、「スマホゲームのユーザーはこういうふうに楽しむ」みたいなものは、アカツキさん側の意見も取り入れながらやってますね。
ゲームプレイによる体験も、すべてはシナリオのための演出
──『トライブナイン』はスマホゲームだけではなくTVアニメ化も行われますが、このアニメ化というのは企画のどの段階で持ち上がってきたものなんですか?
小高氏:
けっこう最初じゃないですかね。
今回はバトル物、それも街中を駆け巡りながら戦うというものなので、それをスマホゲームでどこまで表現できるのか、最初のころはわからなかったんです。だったら、まずはそれをアニメで見せたほうが、より広がるんじゃないかという話になったんです。あとはTooKyo Gamesの特色として、ゲームとアニメの両方をやっているところもあるので、それを活かしたいというのもありました。
──アニメとゲームのエンタメとしての違いを、どう使い分けていくのでしょうか?
小高氏:
アニメは、TVもそうだし配信に関してもちゃんと整備すれば、触れてもらうための敷居が圧倒的に低いですよね。すごく簡単に見てもらえる。それに対してゲームは、たとえスマホであってもやっぱり敷居は高いかなと。ダウンロードするのがまず面倒だし、容量を気にしたりもするし。そういう意味では、アニメの敷居の低さを利用しつつ、もっとこの世界を味わいたいという気持ちをゲームで深掘りするのがいいかなと思っています。
──小高さんとしては映像の強さやおもしろさについて、どういった認識でしょうか?
小高氏:
アニメって結局アクション、つまり動きなんですね。アニメでは言葉の力って、それほどないと思っていて。アニメから流行る名言は、けっこう簡単なフレーズが多いんですよ。マンガだとけっこう長いフレーズでも大丈夫なんだけど、それをアニメでやっても、あまり頭に残らない。アニメはどうしても動きがメインになるので、それを想像したうえで考えるほうがいいと思っています。
僕の場合、ゲームであってもシナリオをいちばんの主軸に置いているんですよ。はっきり言ってゲーム性もなにもかも、シナリオのための演出だと思っていて。もちろん、ゲーム性を大事にするクリエイターがいるのは承知のうえですけど、僕の場合はすべてシナリオをおもしろくするための要素という形で作っています。
──たとえばマンガにしても、シナリオやプロットを重視する人とキャラクターを重視する人の二大派閥みたいなものがあって。それで言うと小高さんは、キャラクターを重視する人に見えなくもないと思うのですが、そうではないと?
小高氏:
たとえば『ダンガンロンパ』で言うと、プレイヤーが犯人を自分で指摘しなきゃいけない。そのときにはもう犯人はわかっているんだけど、その指摘しなきゃいけない相手がめちゃくちゃいいキャラクターで、でも指摘した瞬間に処刑される……っていうこの気持ちを作るために、キャラクターを良くしなきゃいけないな、というところがあって。
僕がおもしろいと思う瞬間って、けっこう無理筋というか、「ここでこの展開っておかしくないか?」みたいなことが多かったりするんですけど、それってキャラクターの性格でごまかせるんです。普通の人はこっちを選択するんだけど、こいつはこういう性格だからあっちを選択するんだ、という。そのためにキャラクターを立たせているというのはありますね。
──小高さんは「シナリオを最重視」とおっしゃいますけど、いまの『ダンガンロンパ』のシチュエーションなんかは、やっぱりもうちょっとゲーム的な“体験”の部分に近いと思うんです。
小高氏:
そうですね。ただ「ゲーム体験としてのストーリー」を作っている部分が大きくて。そういう意味で僕は、ゲームは小説とかマンガとかアニメよりもスゴいと思っています。物語を表現するうえで全部を内包できる。さっき言ったように「このキャラクターを殺すのか?」という葛藤までプレイヤーに提供できる。お話を作るうえではいちばん挑戦しがいのあるメディアですよね。
それもあるからいろんなゲームをやって、「こういうゲームプレイがあるんだ」というのを勉強したほうがいい。たとえば『The Last of Us』をプレイして、「こういうシーンでこういう作り方があるんだ」と感じたことを、また別のところで再利用できる。すべては、物語をプレイヤーの心に刺すために作っていますね。
──同じ物語であっても、プレイヤーの能動的な行動をともなう受容の仕方と、そうじゃないものでは、どこがどう違うのでしょう?
小高氏:
うーん……ただ「自由度が高い・低い」という話でもないんですよね。そこが難しいところで。「ゲームにおけるシナリオとは何か?」という質問に、答えを出せる人はまだいないのでは、と思うんですよ。
 |
たとえば、『The Last of Us』も、1作目だと主人公の行動とプレイヤーの気持ちが、まだわりと一致するストーリー展開になっていたじゃないですか。それが『The Last of Us Part II』だと、後半の「なんでこういうことをするの!?」っていう「主人公=自分」じゃなくなる瞬間で、僕は逆に冷めちゃったというか。
──『The Last of Us Part II』は、プレイヤーの気持ちと主人公の気持ちがかなり離れている状態で操作しなきゃいけないシチュエーションを意図的に用意することで、違和感を持たせる作りになっていますよね。それが効果的だったかどうかの評価は、それこそプレイした人によって分かれるんですけど。
小高氏:
ただあれは、感情移入する・しないの問題なのかというと、そうじゃない気もしていて。
──『The Last of Us Part II』のあの体験が気持ちよかったかどうかはともかくとして、「記憶に残った体験かどうか」でいうと、間違いなく記憶には残ったと思うんですよね。
小高氏:
そうなんですよね。だからそこは、ゲーム性と物語の組み合わせがいかに強いのかという証明でもあると思うんです。
まあでも、自分の気持ちと一致するかどうかって意味では、『ライフ・イズ・ストレンジ』をやっていても「最短ルートはこっちだな」っていう、よこしまな気持ちで選択肢を選んだりもするので(笑)。何がゲームにとっての正解か、というのは難しいですよね。
──普通に考えれば、ゲームの主人公とプレイヤーが一体となる体験が良いものだというふうに、おそらく定義されがちだと思うんです。でもいまの話だと、それすらも使い方ということですよね。
小高氏:
そうですね。シーンによって違うんじゃないかとは思っていて。『ドラクエ』は基本的に主人公=自分だけど、『FF』は違う。でもどちらのシリーズも人気があるわけで。プレイヤーって正直そこまで気にしていないというか。「感情移入できる=良い作品」とも限らない。ただ「ここは感情移入させてあげよう」、「ここは主人公のキャラクターを立てて引っ張っていこう」という、そのさじ加減なのかなとは思いますね。
FPSの場合は別ですけど、カメラをどこにでも置けちゃうのがゲームの良いところだと思うので。感情移入させるようなカメラの場面もあれば、あえてカメラが離れちゃう場合もあって。さらには、急に別のキャラにもなれる場合もあるし。従来の物語理論というか、ほかのメディアの物語論をゲームに持ち込むことはできないかなと思っています。
マンガの場合はとにかく主人公をカメラの近くに置くとか、アニメの場合はとにかく動きで見せるとか、メディアによってそういう鉄則があるんですけど、ゲームの場合はそういった鉄則すらないというか。自分のペースで進められるわけだし、カメラも自分で動かせたりするので。「こうあるべき」という理論がいまだに解明されていないのが、ゲームのシナリオだと思うんです。
──ゲームシナリオの鉄則が、いまだに解明されていないのはなぜなんですか?
小高氏:
いままではギャルゲー以外、シナリオを書く人がゲーム開発のトップではなかったからじゃないですか。「シナリオだけやってます」みたいな請け負いの人のほうが多くて。
逆にゲームのグラフィックって、ヨコオタロウさんもそうだし上田文人さんもそうだけど、ゲーム開発のトップに立っている人も多いですよね。だからゲームにおけるグラフィックだとか、ゲームにおけるプログラミングはすごく研究されているけど、ゲームにおけるシナリオはまだまだ研究されてない気がする。プランナーなりディレクターから言われたことをちゃんとやるという人は多いと思うけど、ゲームの混ぜ方としてもっとこういうことがあるんじゃないか、というのを考えられるポジションにいた人が、あんまりいなかったというか。
──シナリオを書く人がゲーム開発の中心にいるというのは、最近の例だと『Fate/Grand Order』の奈須きのこさん。あとは『十三機兵防衛圏』も、ディレクターの神谷盛治さんがシナリオも含めて全部やったからああなった、というところがかなり大きかったとは感じるんですよね。
小高氏:
ディレクターに言われて作るタイプのシナリオだと、『十三機兵防衛圏』のあの作りにはなっていないですよね。物語をバツッと分断させているのは、ディレクターがシナリオを書けるし、それでも伝わるという自信があったから、あの作りになったんだと思う。
須田剛一さんもそうですよね。シナリオを書ける人がゲームメカニクスまでちゃんと見ているというか、提案までしている作品がもっと増えてくれば、ゲームシナリオのメカニクスも解明されていくと思うんですけど。
──それこそ、『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんは、まさにそこを開拓してきた先駆者でもあるんですよね。
小高氏:
いまはAAAの作品になると、そういうことが成立し得ないので。僕が携わる作品はそこまで大規模なものがなかったおかげで、お話なり世界観なりにドリブンして、そこの尖りで勝負するというゲームプレイが成立し得たというか。これが大会社になると、「ゲームプレイはあくまでシナリオのための演出なんです」なんて言っても、許してくれないだろうなと思うので。
──その意味で言うと、今回の『トライブナイン』は、シナリオを書く人がトップというか、ある程度ハンドルを握って運営する大規模プロジェクトとして、けっこう珍しい事例のひとつになるんじゃないですか?
小高氏:
それはどうでしょうね(笑)。
 |
ユーザーが「エクストリーム・ベースボール」のルールを気にするようなら、負けだと思う
──今回は小高さんが『トライブナイン』というIPのコアを作るわけじゃないですか。IPのコアを作るというときに、それこそ漫画家さんがIPの軸になることもあれば、映像から入ることもあれば、いろんな起点があると思うんです。
今回は小高さんというゲームを作る人が起点となったときに、IPを作るとどうなるのかを聞いてみたくて。たとえば奈須きのこさんの『Fate』は、すごくゲーム的だと思うんです。サーヴァントを召喚するルールがカチッとあって、登場するサーヴァントにもステータスみたいなものが決まっていて。「こいつらがバトルを繰り広げたらいったいどうなるんだろう」というシミュレーションに近いノリがあるというか、ゲーム的な設計や趣向というのが随所にあって。いわゆる小説家が考えるものとは、雰囲気がかなり違うと思うんです。
今回の『トライブナイン』も、そういうものになっているのですか?
小高氏:
なんていうのかなぁ……。ゲームってたいていは、ルールを決めていくものですが、僕の場合はそのルールを逸脱したときにおもしろさを感じてしまうというか。そこもシナリオ主導で考えているところの影響なんですけど、優れたルールを作りたいとは思っていないんです。それはどうでもよくて、とにかくこういう感動を与えたいと。そのためにはキッチリとしたルールが必要かもしれないし、べつにルールはあと出しでもいいんじゃねぇか、とも思うので。
たとえば『ダンガンロンパ』の学級裁判もそうですけど、ルールがあるようでいて、よく逸脱するんです。そこをプレイヤーが気にならなくなればいいかなと。そこを楽しませたいわけでもないので。
──さっき『Fate』の話をしましたけど、じゃあ『Fate』の物語上でルールが遵守されているかというと、そんなことはなくて、すぐ例外が出てきたりするんですよね(笑)。『Fate』の物語としての驚きには、最初に提示されていたものをどんどん裏切っていくというのも、ひとつあるなと。
小高氏:
奈須さんと僕ではタイプ的にぜんぜん違いますけど、僕は奈須さんの作品を見ておもしろいと思うし、奈須さんも僕の作品をおもしろいと言ってくれるのは、結局そこの部分が似ているというのがあると思います。
──ちなみに『トライブナイン』の「エクストリーム・ベースボール」にルールはあるんですか?
小高氏:
ルールはありますけど、そのルールをバババッと説明したところで、誰が楽しいんだろう? というのがあって(笑)。さっき平さんが言ったように、脳内でシミュレーションをやる人もいるかもしれないけど、それってけっこうしっかりした人しかやらないじゃないですか。もっとお気楽に楽しめるようにしたいなと思っているので。
一応はルールを作っておかないと作り手が不安になるけど、それをユーザーが気にならないようにするっていうところに、むしろ重きを置いていて。
昨今よく、仕事でシナリオを書いている人たちが陥りがちなのが、「なんでこいつはこういう行動をしたのか」という説明をすごく大事にしてしまうことだと思うんです。というのは、受け手からツッコミを入れられることに怯えてしまっているんです。でも、その説明をしたらたしかに納得できるけど、読んでる側はどういう気持ちでいればいいの、と思うんですよね。要は、その説明はじゃあおもしろいのか? ということです。
カットしたら、こいつがなぜこうしたのかはわからなくなるけど、そのほうがダイナミックでおもしろいじゃん、っていう。
むしろそこを気にさせないようにする、というのを『トライブナイン』では大事にしたいなと。
──ということは、野球がベースにはあるんだけど、点を取って9回が終わったら勝ち、みたいなわけではないと?
小高氏:
そうですね。野球をベースにしたのも、なんでもありにしたかっただけで。バイクを使ってもいいし、どんな道具を使ってもいいし。
──状況そのもののおもしろさとか、テキストを読み進めていくテンポ感とかで引っ張っていきたいわけですね。「そんなのを使って盗塁するのかよ!」みたいに。
小高氏:
ルールと言えば「なんでもありにするためのルール」にしようと。ホームランとかスタンドインとかもありませんから。あるのはランニングホームランだけで。
でもそれをババッと書いても仕方ないので。ホームページには載せておこうか、ぐらいで。むしろ気にしたら負けだと、ユーザーさんに思わせたい。「これは野球としてアリなの?」と思われてしまうようではダメだと。そこは『アストロ球団』を見習って(笑)。
でも、ユーザーさんはライブ感で見れるけど、作る側はじっくり考える時間があるので、だんだん不安になるときもあるんですよね。「これってツッコまれるんじゃないか」とか思ってしまうんです。でも自分は、ツッコまれてなんぼでしょ、と思っています。というわけで、ルールはあるけど、そこを気にされたら負けかなと。
──ということは、ルールとかシステムではなくて「体験性」みたいなところが、小高さんの中の「ゲーム的なもの」というか。
小高氏:
そうですね。あまり頭でっかちにはならないようにしようと。理論立ててモノを作ることはあえてしないし。じつは考えていたりもするんだけど、それをあえて言語化しないというか。
『ヤングマガジン』で連載されていたバレーボールのマンガ(『工業哀歌バレーボーイズ』)がバレーボールをぜんぜんやってなかったみたいに、エクストリーム・ベースボールをまったくやらない『トライブナイン』もアリだと思うし。そういう小ネタをいっぱい入れられる器という意味では、『トライブナイン』はいい器なんじゃないですかね。
──少し話が飛びますが、一回ヒット作を当てると、仕事としてもファンからも同じ味を求められがちじゃないですか。小高さんはそういう悩みに直面したことはあるんですか?
小高氏:
たとえば僕で言うとデスゲーム、極論を言えば『ダンガンロンパ』の続きなのかもしれないですけど。でもそれをそんなに欲しているのかな、というのもちょっとあります(笑)。
 |
──今回の『トライブナイン』でアクションを重視するというのは、小高さんのこれまでの作品とはまた違う色を出したいのかな、とも思ったのですが?
小高氏:
そういう考えでもないですね。『ダンガンロンパ』はスパイク・チュンソフトのものなので、僕がどうこうできる話ではないですけど、「もうデスゲームは作らないのか?」と聞かれても、作らないとも言い切れないし。『トライブナイン』のアクションに関しても、前がこうだからどうとかではなくて、単純に作りたいものの一個でしかないんです。
前とかぶる・かぶらないも気にしないし、自分の作風とかキャラクターもそんなに気にしないというか。「毎回同じようなキャラクターだね」と言われても、それも気にしないし。前と無理に変えても、ユーザーからすれば変える必要があるのかと思うし。それよりは自分の100パーセントの力を出すべきなのかなと思っていて。
キャラクターのデザインまでいっちゃうと、さすがにかぶりを気にしますけど、シナリオの風味とかは気にしていないですね。はたしてユーザーがどこまで気づいているのかというのもあるし。
シナリオのボリュームは正直、割に合わないぐらいがんばっています
──今回はアカツキさんとの共同作業になるわけですが、いっしょにお仕事されてみて、いかがでしたか?
小高氏:
もともと僕の中で「絶対にスマホゲームを作りたい」というよりは、『トライブナイン』というコンセプトを何かの形にしたいというのが、まず第一にあって。それをいくつかの会社に見てもらったんですけど、その中でアカツキさんと会って思ったのは、「ゲーム好きな人たちだな」と。それは僕が会った人たちだけの話なのかもしれないけど、とはいえほかの会社に行くと、ゲーム好きなのかどうかもわからない人たちが出てくることもあるんですよ。
──それはゲーム会社であっても、ですか?
小高氏:
そうですね。アカツキさんはゲーム好きなのと、あとは「野心」と言ったらヘンですけど、あまりギラギラしたところが良い意味でなくて。
最初に僕がアカツキの社員の方と会ったのは、飲み会の席なんです。打越鋼太郎さんと飲みに行ったら、そのお店に打越さんの作品を好きだという人がいて。名刺交換をしたらアカツキの社員の方だったので、そのときに初めてアカツキという会社を知ったんです。
そのあと、僕らが独立をしようというときにはもうアカツキさんが大きくなってきていたので、「今度企画を持っていくので見てください」という経緯だった気がします。
飲み会スタートだったからかもしれないですけど、ゲーム好きでフレンドリーな会社だというのが第一印象ですね。いっしょにお仕事するようになっても、その印象はあまり変わらないです。
──『トライブナイン』のために新たに開発チームを作るというのを聞いて、どう思いました?
小高氏:
やる気だなぁ、と思いました(笑)。
僕らはIPを作ることに長けているというか、むしろそれしかやれていない会社なのですが、みなさん「IPを作りたい」という話はよく聞くんですけど、はたしてみんなどこまで本気なのかはわからないんですよ。べつにIPなんかわざわざ作らなくたっていいわけで。集英社と組んで人気マンガをゲーム化したほうが、むしろよっぽどお金になるかもしれない(笑)。
ただ、アカツキさんはかなり本気だなというのが伝わってきて。タイミング的にも良かったなと思いました。
あとは「普通のものを出してもしょうがないよね」というところが一致できているので、そこはやりやすい部分ですね。「やっぱりファンタジーやRPGのほうが目に留まるんじゃないか」という人もいるかもしれないけど、僕自身は「そんな普通のことをやってもしょうがないでしょ」と思っていて。そこはアカツキさんも「そうですね」という感じなので。
──いま言われた「普通」とか「普通じゃない」の定義って、もう少し具体的に言語化すると、どういうものですか?
小高氏:
「尖る」とも違うんですよね。「尖らせたい」とか「ケレン味を出したい」というポイントも「普通じゃない」と言うんだけど、いま言った「ファンタジーやRPGではない」という意味での「普通じゃない」とは、また違う意味で。
さっき言った「普通じゃない」というのは、「いちばん売れているもの=普通」ですね。その真似をするのは嫌だよねとか、それは良くないというのが、「普通じゃない」だと思うんです。
クリエイターとしてそれはダサいかなと思うし。歴史上、二番煎じがそこまで売れたことはないと思うので。そういうものってそこまで売れないんじゃないかなというのが、アカツキさんと僕のあいだで一致しているから、「普通のものを出してもしょうがないよね」と言えると思うんです。もしこれが、ビジネス的に二番煎じでいいんだよというのが確立されていたら、「普通でいいんだよ」って話になるんですけど(笑)。
──そのへんは時期的なものもありますよね。スマホゲームやガラケーでは、二番煎じで良かった時代というのもたしかにあったわけで。
小高氏:
時期と、あとポジションもあると思うんですよね。立場によって言うことが変わるというか。家電の大企業だったら、小さい会社がアイデアを考えた製品に対して、もっとすごい二番煎じを作っても勝負できるでしょうし。そういうポジションだったらそれはアリ……クリエイター的にはナシなんですけど、ビジネス的にはアリでしょうから。
だからそのへんはアカツキさんがIP作りを実現したい立場も影響してくるから、「普通じゃダメだよね」が一致するというのは、めちゃくちゃ貴重なことだし。そうじゃなければ、そもそも僕らを選んでいないと思うので。
──そのあたりの経緯や事情については次回のインタビューで、アカツキ側の総合プロデューサーである山口修平さんに直接お聞きしますので。
小高氏:
「ほかの全員に断られたので、仕方なく」とかだったらイヤだなぁ(笑)。
 |
──では最後に、『トライブナイン』の意気込みを聞かせてください。
小高氏:
「今後のスマホゲームはこうあるべきだ」みたいな考え方はべつにないんですけど、シナリオにこれだけ力を入れているスマホゲームというのは、ほかにないかなと思っていますね。
本当にアニメのシナリオみたいに、みんなで集まってダメ出しをして。7稿、8稿、もっとかな。どんどんいっちゃって。オリジナルのアニメの作り方とまったく同じようにやっています。外部のスタッフだとあまりに期間が長くて割に合わないと思われるので、それもあってTooKyo Gamesの社員を増やしたんです。そこまで入れ込んでいるゲームは、ほかにないと思うので。
しかもそのシナリオを、ユーザーは無料で読める。無料でシナリオを読めるというのが、僕らとしてすごくやりたかったことで。スマホゲームだと、キャラクターのセリフやテキストだけがフレーバー的に使われるものが多かったりするんですけど。起承転結があるシナリオを無料で読んでもらえるというのは、僕らとしてはうれしいところだし、そこはぜひ楽しんでほしいなと思っています。
──アニメの脚本のようにシナリオの読み合わせをずっとやっているとのことですが、これまでのアドベンチャーゲームでは、そういった作業はなかったのですか?
小高氏:
『ダンガンロンパ』でもやっていますけど、『トライブナイン』に関しては「続く」ということも想定して、僕が全部やっていくスタイルだと絶対に途中でおかしくなると思っていて。僕としては毎週配信したいぐらいの気持ちで、ハイペースで作らなきゃいけないというのがあったので、最初から分業しないとダメだと。その分業を確立させるための体制構築もやっていますね。
──運営を見越したうえでの体制作りとしてやっているわけですか?
小高氏:
そうですね。いまのところ出来上がっているシナリオだけでも、『ダンガンロンパ』1作分ぐらいの量があるんですけど、リリースまでに2作分ぐらいはストックしておきたいと思っています。当初は「1ヵ月に1話考えるぐらいのペースでシナリオをやんなきゃね」と言ってたんですけど、ぜんぜん終わらなくて(笑)。
──それはスゴイですね。
小高氏:
そのぐらいの物語のうねりとかキャラクター数を作っていくと本当に時間がかかるので、なかなか割に合わないと思うんです(笑)。「スマホゲームにここまでシナリオをがんばりますか?」ってことを考えると、ほかの会社はたぶんやらないだろうなと。
──それは『FGO』や『ウマ娘』が出ているいまなお、自信を持ってそう言えるわけですか?
小高氏:
『FGO』の場合はやっぱり、奈須さんっぽさがあるじゃないですか。奈須さんの作家性で攻めて、ほかのライターたちも奈須さんのテイストをなぞっていく形になっていて。それに対して『トライブナイン』はもうちょっと幕の内弁当というか。ミステリー回があったり、ちょっとコメディ要素の物語があったり、恋愛があったり、いろんな要素が入っているので。「さぁコメディ回はどうしようか」という形で作っているから、より時間がかかってしまいますね。
そういう意味で、こんなスマホゲームはいままでにないし、実装はこれからなんですけど、はたしてどう実装していくのかなと。僕らもコンシューマゲームをやっているから、どうしても演出的に「文字だけじゃなくて動かしてほしい」とか「一枚絵にしてほしい」とか、要望がすごく多くなっちゃって。これがうまく実装できればスゴい武器にはなるし。割に合わないがんばり方をしている可能性はあるけれど、そこがいいところかなと思います。
──「割に合わないがんばり方をしています」というのは、ユーザー側としては非常に期待できるフレーズですね(笑)。それでは、ゲームの完成を楽しみにしています!(了)
東京23区の街の特徴をデフォルメした街やアウトロー集団、彼らが繰り広げる「エクストリーム・ベースボール」の設定など、『トライブナイン』の世界観は非常に小高和剛氏らしいエッジの利いたものになっている。それだけに、この作品が小高氏個人の創作というイメージを持つ人は少なくないかもしれない。
だが今回のインタビューで語られているように、『トライブナイン』は小高氏以外のTooKyo Gamesのメンバーをはじめ、開発を担当するアカツキのスタッフとも打ち合わせを重ね、多くの人のアイデアが集積されたものだという。それでもなお、受け手の側が小高氏のカラーを感じるのは、そここそが「創作の妙」なのかもしれない。
今回のインタビューではふだんの取材ではなかなか聞きづらい「ゼロからイチ」を生み出す創作の根幹について、可能な限り迫る形となった。それだけに、ふだんよりも慎重に言葉を選んで回答してくださった、小高氏の姿が印象的だった。
次回のインタビューでは、『トライブナイン』の総合プロデューサーを務めるアカツキの山口修平氏に、小高氏やTooKyo Gamesのスタッフたちが生み出したコンセプトを、ゲームとしてどのように具体化していくのかをうかがっている。そちらもぜひ注目してほしい。