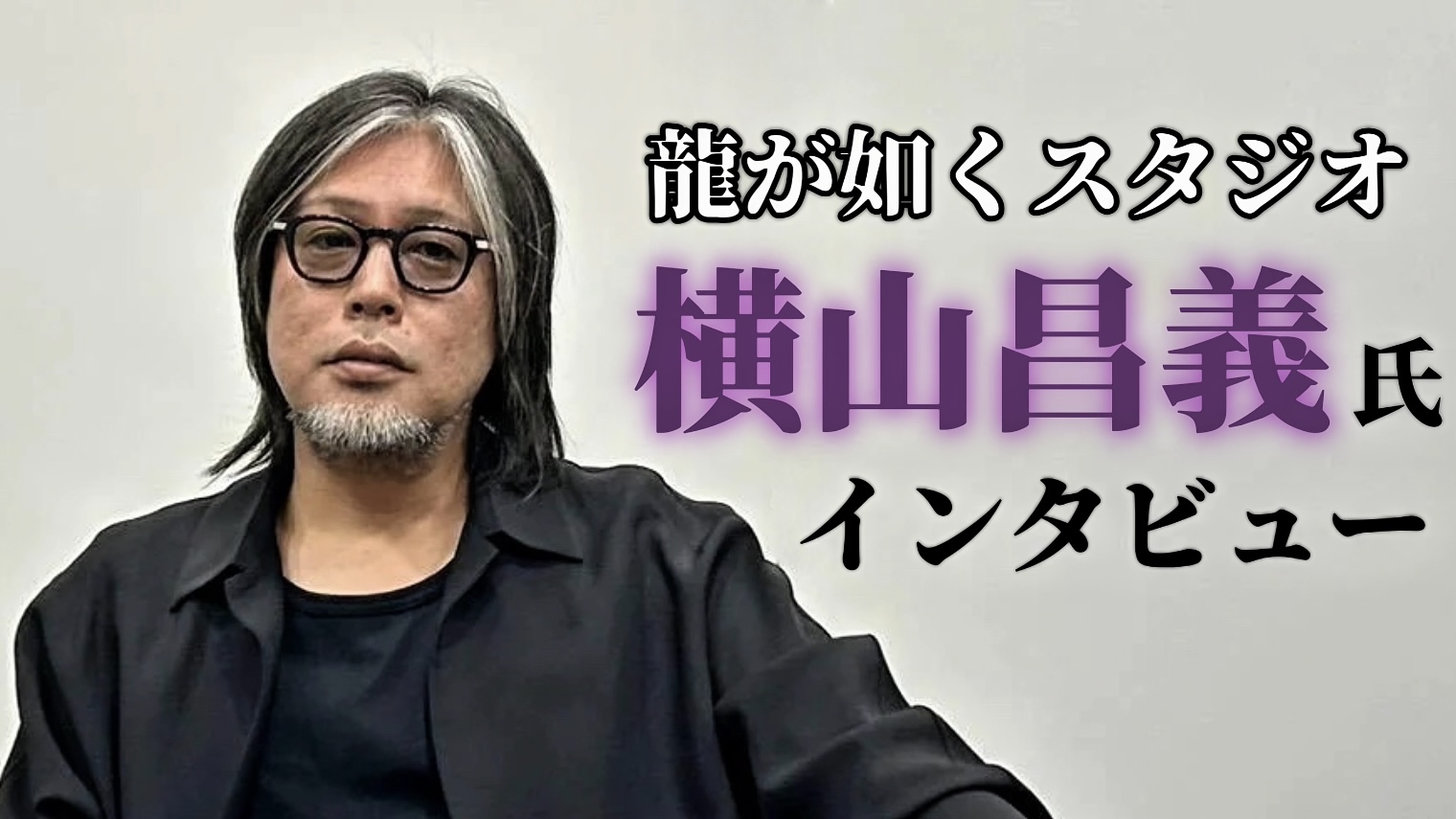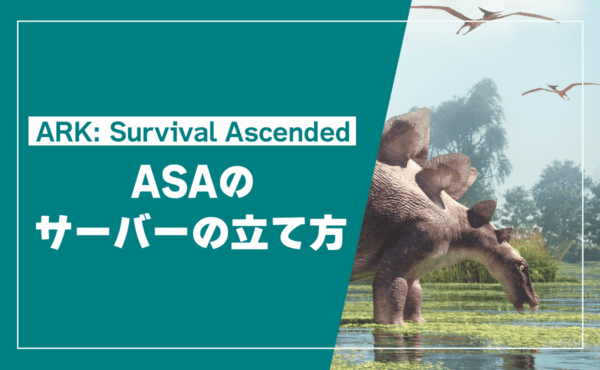「信頼しないし、任せない。でも責任は取る」横山氏の上司論
──お話を聞いていると横山さんは開発メンバーの自主性に任せていると感じました。
横山氏:
そうですね。僕は1から10まで全部自分で決めたいタイプではないので。
どうしても自分で決めなければいけないこととか、どうしても僕にやってほしいということはやりますが、それ以外は必要最小限で、口も出さないですね。
これは管理する立場にある人たちに聞いてほしい話なんですが、よく「部下のことを信頼して任せろ」と言われますよね。でも、その人のことをよく知らなきゃ信頼なんかできないし、任せることもできないと思うんです。
そうじゃなくて、信じなくてもいいし、任せなくてもいい。ただ、責任だけはしっかり取ればいいんです。「これはあいつがやったことだから」と責任逃れをしないことが重要なんです。
──「責任は持つからやってみろ」と。
横山氏:
自分の負荷を下げたいのであれば、人にやってもらうしかない。ただ、信頼していないと仕事を振れないというわけでもないということですね。
僕はむしろ「信頼してからじゃないと任せられない」と言っている人のほうが狭量だと思っていて。信頼できるかどうかを判断できるほどその人のことを知っているのかと言ったら、必ずしもそんなことはないんですよ。
だから、そういう意味でも僕はあまり人をコントロールするタイプではないですね。人を疑いつつ、でもよい仕事を期待する。期待通りでないときは徹底的にフォローするというのが正しい表現でしょうか。
──それが結果的にいい方向に向かっているわけですね。
横山氏:
ただその分、チェックミーティングなどでは遠慮なく、ストレートな言い方になってしまいます。ダメなものは何がダメなのか指示もかなり具体的なので、そこから先の自由度は低くなりがちですが。
──経験則でいえば、なにがダメなのかをはっきり言ってくれたほうが物事はスムーズに進むと思います。
横山氏:
そうかもしれませんね。ただ「自分はかっこ悪いと思ったけど、そう思っているのは自分だけかも」と感じたときは、ほかの人の意見もすぐに聞くようにしています。
何人かに聞いて、否定的な意見のほうが多かったら「じゃあ多数決でやめとこう」とか、「これはこれでアリだと思いますよ」と言われたら「そういうのもあるんだな」とOKを出したりする感じです。
とはいえクリエイティブの現場に公平性はなかなか持ち込めないのが実情です。上に立つ人のセンスに作品が寄っていくのは事実としてあるんだと思います。
──横山さんに認められることを目的化してしまうのはよくないということですね。
横山氏:
だから、良いものは何がよいのか、悪いものは何が悪いのか、好き嫌いの領域であっても理屈で説明するようにしています。それがどんな屁理屈であっても、とりあえず理由がないのはダメ出しされるほうも嫌でしょうから。
あとは新人研修などではよく「僕や上司に認められて喜ぶのではなく、お客さんに認められて喜ぶようになりなさい。それがプロです」とは言ってますね。
誰に認められるのがゴールなのか? その目線が合うと仕事が一気にやりやすくなるとは思います。それでいうと、僕自身はいまの社長とすごく合っていると感じますね。
──たしかに。内海州史社長と横山さんは合いそうな気がします。
横山氏:
内海は、少年のような心を持った頭のいい人。自分の知らないことをどんどん取り込んでいける人なんですよ。
たとえば若い人の中で流行っているスマホアプリなどを、自分で使うわけではなくとも「これは知っておいたほうがよさそうだ」と思ったら、どんどん取り込んでいく。その感覚はすごいと思います。自分の知らないことでも飲み込める。だから内海の感覚や経験に基づいた指摘や指示はすべて理解できなくても納得できるし、それを具現化することも苦じゃないんですよね。
彼に「世界を獲ってこい!」と言われたら、なんか近づけそうな気もしますし、実際にそう思って施策を練ると案外近づいていたりするんです。
やっぱり知っていることのみを取り入れていくだけでは目標に限界があるんですよね。僕自身は知らないことをやるのが苦手で、たとえば仮想通貨なんかには手を出せないタイプなんですよ。「すべての仕組みを理解してからでないと手が出せない」と思ってしまう。
でも、僕の周囲で仮想通貨で利益をあげた人たちって、あまり仕組みを理解しないまま買ったような人が多いんです。
──「よくわからないけど、流行っているから買ってみた」という方が多いですよね(笑)。
横山氏:
仕組みを理解していないと踏み込めない感覚の人も多いと思うんですが、それを超えたような感覚は、時には必要なんだろうなと思います。「新しいものに対する拒否感がない」ということが大事なんでしょうね。内海はそれを常に意識させてくれる経営者だと思っています。
「映像作品としての『龍が如く』」に魅力を感じたスタッフが増え、カメラワークや配色のセンスも進化した
──近年の『龍が如く』シリーズは、映像表現の面でも進化を続けていますよね。『8外伝』もですが、カメラワークをかなり意識していると感じました。
横山氏:
そこに関しては、最近入ってきた若いスタッフの力が大きいですね。もともと映画を作っていたり、映像の勉強をしていたようなスタッフが増えてきていて、彼らがすごくうまいんです。
『龍が如く』というシリーズが続いていく中で、映像作品としての『龍が如く』に憧れを持って、映像やストーリー推しの作品に携わりたいと思って入ってきてくれたスタッフたちが多く、映像関係の知識やセンスがある人が増えてきているんですよ。

──映像表現を突き詰めたいという動機は目から鱗です。たしかに、ビデオゲームは映像技術の最先端ですもんね。
横山氏:
『龍が如く』が立ち上がったときは、ゲームが専門だったチームがたまたまこの手の作品を制作したという流れだったので、そもそもの入り口が違うんです。僕自身も映像関係の出身ではありませんし。
映像関係の出身だったり、映像の勉強をしてきた人たちが本気でゲームを作りたくて入ってきてくれているので、彼らのセンスが存分に発揮されているんだと思います。『7』以降はとくにそれが顕著ですね。
──色味のセンスなどからもそれを感じます。
横山氏:
画面の色味に関しては、僕がけっこうタガを外しているところがあって。僕自身、極端なコントラストや色味の画が好きなので、「いじっちゃっていいよ」と言っています。『7外伝』なども、かなりコントラストを強くして、そこから徐々に落としていくような手法を取りました。
いつも迷うことなのですが、ゲームとしての視認性と、映像としての見た目のインパクトのどちらをとるか、という問題があります。そこに関してはわりとインパクト重視の方針を取っていますね。
──『8外伝』のメインカラーは紫色ですよね。紫って、すごく使うのが難しい色だと思うのですが、あれほど違和感なく使っているのは見事だと思いました。
横山氏:
ポスターの真島なんかはちょっと顔色が悪いですけどね(笑)。おっしゃるとおり紫色は使うのが難しいので、いろいろなところで「大丈夫かな」と思うことはありました。それに関しても、スタッフのセンスの賜物ですね。
──UIのレスポンスの良さであったり、色味やオシャレさも『8外伝』の素晴らしいところだと感じます。1作目からプレイしている身としては、ちょっとガサツで無骨な感じが『龍が如く』シリーズのイメージだったのですが、最近のタイトルでそれが覆りつつあるなと。
横山氏:
まさしくあれがスタッフたちのやりたかったことなんだろうな、と思いますね。ある意味で『龍が如く』の枠からはみ出したいというか。
似たような感覚は僕も持っていて。たとえば、以前の『龍が如く』は、極太の筆の字であったり、明朝体のフォントが多かったですよね。
──『仁義なき戦い』的なフォントですよね。
横山氏:
そういったオマージュ的な要素があったわけです。そこから『7』で、タイトルロゴをゴシック調に変えたわけです。ここがひとつの転換期だったと思っていて、『7』からRPGになったというのもありましたが、あれからずっとゴシックに近い書体を採用しています。
また、『龍が如く』と言えば題字の背景に筆で描いた赤い円を想像される方も多いかもしれませんが、『7』で変えてからは意識して戻さないようにしています。それくらい頑なに貫かないと、スタッフも「変えよう」という意識にならないんですよね。
プロデューサー、ディレクター陣がそういう姿勢を貫くことで「自分たちも変えていっていいんだ」という意識を彼らに伝える。それによって、『龍が如く』の世界観のギリギリのところで、「どこまで挑戦できるのか」といったトライをしてくれているんだと思いますね。
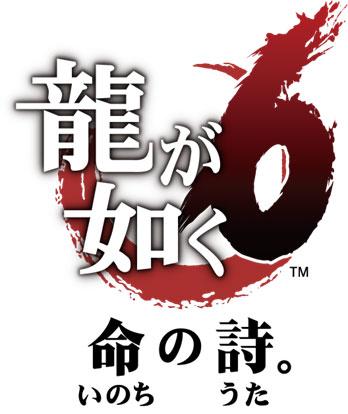

──実際に言葉として「変えていこう」といったことを言われたりもするのでしょうか?
横山氏:
「とにかくダサいものは作るな」というのは、つねづね言っています。「ダサい、ダサくない」の判断基準って、時代によって移り変わるものなので。
すごく参考にしているのが、僕はときどき10数年以上前に録画したドラマを見ることがあるんですよ。それで何を見るかというと、当時のCMを見るんです。
というのも、CMで使われているフォントがものすごくダサいことがあるんですよ(笑)。「何年前はこうだったな」とか、確認する意味でCMも飛ばさず見るんです。
おもしろいのは、2011年以降、テレビのテロップなどのフォントってほとんど変わっていないんですね。おそらく、10数年に1度のペースでそれが劇的に変わる瞬間が訪れていて。そのタイミングで、「古い、新しい」のセンスが更新されていると思うんです。
一方で音楽の分野では、昔流行ったものが回帰する流れもありますよね。そういったカルチャーって巡っていくものですし、昔のものを見ても「いまの時代にはないな」というものがあったりするんですよ。
──なるほど。ファッションの流行に近しいものがありますね。流行は進化をともなった螺旋だと……。
横山氏:
都内某所にある“とあるミュージックバー”ですが、お客さんがリクエストした曲を流すときに曲のMVではなく、昔の歌番組の映像を流してくれるんです。
いろいろな年代の人が訪れたり歌ったりしていて、すごく楽しいお店なんですが、映像を見るといまではぎょっとするようなフォントを使っていたりするんですね。
でも、それがかえってオシャレに感じられることもあって。そういったものに影響を受けている人ってたぶん多くて、僕もうちのメンバーを連れて行くことがあります。
──若い人にとっては、自分の中にない常識が出てくるような感覚なのかもしれませんね。
横山氏:
そうですね。そこからいろいろなエッセンスを取り込んでくれればいいなと思っています。
「1年に数回」レベルのイベントが「週に15回」起きるのが『龍が如く』の制作チーム。シリーズ1作目からの激動の20年間を振り返る
──『龍が如く』は2025年に20周年を迎えます。2011年に龍が如くスタジオが設立されて14年。2021年に新生「龍が如くスタジオ」となって4年が経ちますが、これまでを振り返ってみて、『龍が如く』というタイトルの業界内の立ち位置の変化であったり、チームの成長などについてお聞きできればと思います。
横山氏:
『龍が如く』に関わる前、僕は『ジェットセットラジオ』というゲームを作っていたのですが、すごく思い出深いできごとがありました。それは、「初めて外出した日」のことなんです。ゲーム作りって、基本的に内勤じゃないですか。
ずっと会社の中で仕事をしている中で、モーションキャプチャーの撮影をするために初めて交通費を使って外出することにすごくワクワクしたんですよ。五反田のスタジオに行って、朝からモーションキャプチャーの段取りを整えたり、台本を作ったりした日のことをいまでも覚えているんです。

──『ジェットセットラジオ』は25年前の作品ですから、よほど横山さんの中で思い出深い日になったんですね。
横山氏:
なぜそれほど鮮明に覚えているかというと、それが自分の中で年に数回しかないような一大イベントだったからなんですよ。
それで、『龍が如く』の話をすると……。そんな一大イベントが「週に15回」訪れるのが、『龍が如く』チームなんです(笑)。
──密度がおかしい(笑)。
横山氏:
声優さんの収録なんて、『ジェットセットラジオ』のころだったら一大イベントだったわけですが、龍が如くスタジオでは毎日起きているんですね。逆に言うと、何もなかった日のほうが「今日はすごく暇だったな」と、よく覚えているくらいなんですよ。
時間に対する経験の密度がぜんぜん違いますし、人生で何回も訪れないようなイベントをたくさん体験できたのが、これまでの20年でしたね。
『龍が如く』は現代劇の作品で、いろいろなタイアップを行ってきたじゃないですか。対象が街の中にあるものすべてなので、飲食やアパレルなど、さまざまなジャンルと関わりますよね。
タイアップするにあたって、お相手の業界の方とお会いすることも多く、それをゲームに落とし込むにあたって、その業界のことも深く知る必要があるわけです。
なので、作っているのはゲームだったとしても、感覚としてはコンサル会社のような知識を得られたような気がしています。コンサル会社の方って、もともとその業界のプロというわけではありませんが、業界に入って経験を積むことで知見を得ていくような側面がありますよね。

──相手方の業界に入っていって、経験を積んでいくと。たしかにそういった体験ができるのも『龍が如く』ならではですね。
横山氏:
純粋にゲームを作るというところから、これだけ逸脱してさまざまな知識を得られたというのは、『龍が如く』というタイトルだったからこそだと思います。
それは僕だけでなく、『龍が如く』チーム全体としてもそうです。『龍が如く』という作品に携わることによって、いろいろな知見が得られた20年間だったと思います。
──『龍が如く』の懐の深さのようなものが、ゲーム制作者としてのキャリアにも影響があったと。
横山氏:
「人間はいくつになっても、経験を積むことができる」んです。この20年で、人生何周分もの異常な経験を積めました。それは『龍が如く』というタイトルの特異性が生み出したひとつの結果なんだろうと思います。セガ社内で見ても『龍が如く』チームがいちばんいろいろなことを経験し、知っていると思いますね。
──『龍が如く』チームならではの経験で言うと、ほかにはどういったものがあるのでしょうか?
横山氏:
たとえばテレビCMを打つときに、放送するのに適切な動画かどうかをテレビ局が調査する「CM考査」という仕組みがあるんです。『龍が如く』はCERO:Dの作品なので、落ちる可能性は充分あり得るんですね。
これが『ソニック』や『ぷよぷよ』であったとしたら、落ちる可能性はほとんどありません。僕たちは考査に落ちる可能性の中でギリギリを攻めることになるので、CMの作り方ひとつをとってもアプローチがまったく違ってくるんです。

──『龍が如く』というタイトルならではの経験やトラブル対策のようなものがチームとして蓄積されていっているわけですね。ほかにも著名な芸能人を起用したり、『北斗の拳』のようなIPものとのコラボもあったり。そのうえで年に1作品のペースで新作を発売しているわけですから、ほかのタイトルではありえない経験量なのだと思います。
横山氏:
演者の方との出演交渉なども『龍が如く』ならではですよね。出演者の方によって、「何をもって『龍が如く』の仕事を引き受けたくなるのか」というニーズも異なります。だから、「ゲームを作っている」というより「『龍が如く』を作っている」という感覚のほうが近いですね。
「世界で5本の指に入るゲームスタジオになりたい」龍が如くスタジオが目指すこれから
──最後に、シリーズ20周年を迎えるにあたって、龍が如くスタジオとしての今後の展開であったり、目指しているところなどをお聞かせください。
横山氏:
本当の意味で「世界の中ですごいゲームスタジオを挙げろ」と言われたら、5本の指に数えられるようなスタジオになりたいと思っています。
「20年存続する」という点だけを見れば、それを達成しているゲームスタジオはたくさんありますが、毎年新作を出し続けてきた『龍が如く』の20周年は、一段と重みが違うと思うんですよ。
──『龍が如く』は20年間、途切れることなく走り続けてきた稀有なシリーズです。
横山氏:
そういったところも含めて、もう4〜5年もすれば確固たるブランドが確立されるんじゃないかと思うんですね。
そうなったときに、「すごいゲームを作るスタジオ」として、ワールドワイドで上から5つの中には入っていきたいという思いがあります。実際に、そう言ってくれる人もかなり増えてきている感覚もありますから。
──英語圏のSNSアカウントを見ても「RGG(龍が如くスタジオ)」という単語が浸透してきているのを感じます。
横山氏:
でも、まだまだ「RGG」と言っても伝わらない人はたくさんいるわけです。これはRGGという言葉に限らず、僕たちのロゴを見たときに「ゲームスタジオのロゴだ」と認識してもらえるとか、そういったところも含めて広めていかなければならない部分ですね。
同時に、そこに若干手がかかりつつあることも感じています。『8外伝』は、とくにヨーロッパでの売れ行きがよくて、これまでの作品と異なり、日本より海外のほうが強いんです。

──ヨーロッパは各国の嗜好が異なるので、難しい市場ですよね。
横山氏:
海賊文化の影響なのかはわかりませんが、とくにイギリスで売れているんです。僕たちからしたら「本気の海賊ゲームを作った」というよりは「『龍が如く』の外伝を作った」わけですが、そういったジャンルの作品として評価してくれている人もいると思うので、チャレンジはしていかなければいけないんだなということを痛感しました。
──海戦という新たな挑戦をしたからこそ、これまでとは違った層にリーチできたわけですね。
横山氏:
これは発売前から言っていたことなんですが、『8外伝』はどの部分がお客さんにヒットするかがわからない作品だと思っていたんです。蓋を開けてみたら、ウケた部分が人によってまったく違った。たとえばこのインタビューではストーリーのラストを褒めていただきましたが、『龍が如く』のシリーズ作として認めてくれた人もいれば、海戦の部分が大好きだという人もいます。
結果として『8外伝』は、いろいろなネタを取り込むことで、さまざまな可能性が見えてきたタイトルになりました。海戦を作ったスタッフたちには「俺たちにもこれまでと違ったものが作れるんだ」という自信も芽生えたでしょうし、本作は僕たちが作るこの先のタイトルに影響を及ぼしていくような作品になりましたね。
いずれにせよ、まだ世界的に大ヒットしているというわけではありませんが、大失敗するリスクもあった中で『8外伝』はすごく可能性を広げてくれたタイトルになりました。そういう意味でも大成功でしたね。
「『龍が如く』はカレーのような作品」と評する横山氏が、さまざまな挑戦を盛り込んでいった結果「今後の作品にすごく影響を及ぼしていくことになる」と語った『8外伝』。
懐の深いゲーム性の中で「サッカーのポジション」や「映像関係を志す若手」の話のように、スタッフがそれぞれの個性や得意分野を発揮できる。
そのうえで、「責任を取る」というリードメンバーの姿勢の元『龍が如く』という作品への熱量をぶつけられることが、チャレンジングでありながら、クオリティや満足度の高いゲームを作ることに繋がっているのかもしれない。
20周年を目前にして、まだまだ勢いを増す『龍が如く』シリーズ。今後の展開にも注目していきたい。