2021年7月19日の0時に「少年ジャンプ+」にて公開されるやいなや大反響を呼び、次々と熱のこもった批評、感想がネット上に次々アップされ、すでにひとつの「現象」と化しつつある、『チェンソーマン』の作者、藤本タツキ待望の最新作『ルックバック』。

連日のように力のこもった充実した新作が公開され、ネット上でバズることがもはや当たり前の出来事のようになりつつある、「ジャンプ+」の中でも『ルックバック』の反響は群を抜いている。本稿執筆時点で閲覧数は500万を突破しており、はてなブックマーク数は3000を超えるほどだ。
週刊少年ジャンプ誌上において始まりから第一部の完結まで絶えず異彩を放ち続けた『チェンソーマン』の作者の最新作ということでも公開前から期待を集めていた『ルックバック』は、なぜこんなにも多くの読者の心を揺さぶるのだろうか?
公開された直後に読み、「心を揺さぶられる」を通り越して完全に“ノックアウト”された人間として、この作品についての私なりの考えを述べてみたい。
文/hamatsu
※以下『ルックバック』と『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のネタバレが含まれますのでご注意ください。
※2021年8月2日、少年ジャンプ+編集部より『ルックバック』の一部表現を修正したとの発表がありました。本稿は、この修正版以前の表現をもとにして執筆されたものです。なお、この修正に関する筆者の追記は本文末尾に記しています(編集部)。
※2021年9月3日の単行本発売に伴い、以前修正された一部表現が再び修正された件について追記しました。(編集部)。
ねじれた成長物語としての前半部
この140ページを超える、短編というにはボリュームがあり過ぎる本作にとって不幸だったのは、後半のとある展開にまつわる部分があまりに強い反響を呼ぶあまり、前半部の素晴らしさを語る言葉が、少なくとも現状においては霞んでしまっていることにあるように思う。
『ルックバック』の前半部、藤野と京本という熱意も能力もあるふたりの少女が漫画を通じて出会い、共に歩み、そして袂を分かつまでを過不足なくテンポよく描くこの前半部は本当に素晴らしい。この前半のみで完結した短編として提示されたとしてもそれはそれで大きな反響を呼んだのではないだろうか。
この漫画の前半部の面白さ、それは、あまりにねじれた形でひとりの漫画家の才能の覚醒を見事に描いた点にある。
クラスで発行されている学年新聞で小学生にしてはけっこう、というか大分良くできている絶妙なクオリティの4コママンガを連載し、周囲から上々の反響を得ていることに満足を得て、それがプライドにもなっている小学校4年生の藤野。その藤野の前に不登校のため姿は見せないものの、小学生離れした圧倒的な「画力」で構成された4コマ漫画を藤野の眼前に突き付けてくる京本。
この京本、というか京本の創作物との衝撃的な出会いによって、天狗の鼻をへし折られた藤野は大きな挫折感を味わい、京本以上に絵が上手くなるために一心不乱の努力を開始する。
そして、その周囲を顧みない姿勢は、小学6年生になるまで続き、やがてクラスメイトや家族の間に溝を生じさせ、その軋轢の果てに、さまざまなものを犠牲にした必死の努力によってもなお埋めがたい「画力」の差を痛感した藤野は、自身の才能に見切りをつけ、漫画を描くことを辞めてしまう。
ここまでの説明だと、圧倒的な天才とそれにどう頑張っても追いつけない秀才という、いわゆるモーツァルトとサリエリ的なこれまで何度も繰り返されてきたタイプの物語だと思ってしまうかもしれない。しかし、実は『ルックバック』はそんな物語では全くない。
努力し着実に向上しているとはいえ、藤野が京本に及んでいないのはあくまでも漫画を構成する一要素に過ぎない「画力」なのであって、コマ割りやストーリー、キャラクター造形などの漫画全体を構築する上で必要な「漫画力」においては、実は物語の開始当初から藤野の能力は京本を圧倒している。そして年月を重ねるほどに藤野の「漫画力」は恐るべき速度で成長すらしているのである。
小学4年生から6年生になるまでの間に、藤野の「漫画力」が向上し続けていることは、作品中に掲載される実際に藤野が描いた4コマ漫画を見れば一目瞭然だ。
4年生の時は、「小学生にしては良くできている」という作品だったものが、6年生になった時に描いた、それが自身がマンガを辞めるきっかけにもなってしまった4コマに至っては単純に漫画として面白い。実際、私はこの6年生の藤野が描く「真実」という作品が大好きで、読んでて普通に笑ってしまった。
それにしても漫画家の漫画家としての成長の過程を、「実際の劇中作の作品のクオリティとその変化具合によって示す」という、藤本タツキという漫画家の剛腕ぶりである。己の漫画家としての力量に相当な自信のある作者でなければこんな芸当はできないだろう。
この前半部で興味深いのは、クラスメイトや家族など周囲の誰もこの藤野という漫画家の圧倒的な才覚と止まることのない成長ぶりに、藤野本人を含めて気付いていないところだ。
そしてクラスメイトの若干デリカシーに欠ける感じの男子生徒がやたら「絵」に言及することがまた興味深い。現実においても、面白い漫画に対して相応しい言葉が浮かばないからとりあえず「絵が上手い」って言っちゃうことってないだろうか。
京本という存在が現れるまで、藤野の漫画はたしかに支持を集めていたが、それは非常につたない言葉の、つまりは漫画に対する解像度の低い、批評性に乏しい賞賛でもあったのである。(まあ小学生なんだから、その辺はしょうがないのだけれど。)
藤野と京本が面と向かって出会い、その状況は一変する。
担任のナイスな横槍によって、不本意ながら、京本の自宅を尋ねる機会を得た藤野は、そこでも漫画家としての才覚を発揮し、何気なく京本についての4コマ漫画を描いてしまう。 そしてこの4コマがまた、ほんの気の迷いでサラっと4コマを描いただけなのに、いい塩梅に力が抜けのびのびした描線が好ましい良い4コマなのである。すでに継続的に漫画を書くことを辞めているにもかかわらず、藤野の漫画家としての才能は成長を止めない。
そんな漫画モンスターのふとした気の迷いとちょっとした偶然が重なることで、ついに藤野と京本のふたりは出会う。
素晴らしい作品を受け取り、どうしようもなく突き動かされてしまうという衝動
引きこもりの京本が部屋から出ることができた理由、それは彼女が藤野の漫画の猛烈な、ちょっと危険なレベルのファンだからだ。
学年新聞に掲載される藤野の漫画をひとつも漏らさず読み続け、好きな回も即答できるほどの藤野の漫画のファンである京本の発言によって、実は藤野は3年生から6年生の途中で漫画を描くことを辞めるまでの間、「一回も原稿を落とさずに毎週掲載を続けていた」という事実が判明する。
京本の自宅を藤野が訪れた際、彼女の自宅の廊下に積み重なったスケッチブックの山を描き、それを、藤野が親に「捨てて」と頼んだスケッチブックの束と対比させることで、京本の常軌を逸した努力を「画」によって藤野と読み手に伝えるという構成は、映画的で鮮やかだ。
しかし、ある種野暮ったい京本の長台詞で説明されるのは、毎週発行される学年新聞に掲載される漫画を、「画力」では上回る京本は、原稿の制作が間に合わず何度か落としているのに、「藤野は一度も落とさずに安定して長期連載を継続している」ということだ。
これはつまり、可視化された努力の量ではなく、「世に出たアウトプットの量(とひとつの作品を完成と判断する決断の回数)において藤野が京本を上回っている」という非常に重要な事実を示している。
しかし、小学3年生から6年生の漫画を描くことをやめるまでの期間、一度も休まず、質も落とさず(というかむしろ上がっている)原稿を描き続けるとは、藤野……商業漫画家としての資質があり過ぎる……。
本来であれば自分の誇りでもあった「絵」を描くという特技を奪われた因縁の相手である京本に「漫画」の才能を激賞されることで、藤野という漫画家の才能はついに覚醒する。
ちなみに、細かい部分だが、何気に重要な事実として、京本は藤野の熱狂的なファンではあるが、盲目的なファンではない。その証拠に京本は藤野の好きな漫画として5年生と6年生の時の漫画は全て好きと言いつつ、4年生の時は1月から3月まで連載していた「佐々木」シリーズと3年生の時に至っては8月第二週の一作しか好きな作品に挙げていない。
つまり京本は作品ひとつひとつをきっちり吟味した上で評価をしているのである。この的確な批評眼こそが藤野の才能を覚醒を促しているということは、本作において非常に重要な点である。
京本との会話中はそっけない素振りをして、「次回作の構想はすでにできている」などハッタリをかましていた藤野が帰宅する途中でいつの間にかスキップをし、恍惚の表情で天を仰ぐ見開きで描かれるコマが素晴らしい。
この時、藤野を取り巻く世界には土砂降りの雨が降り注いでいる。映画において「雨が降る」のは「そのキャラクターの悲しみを表現している」なんてことはよく言われることだが、少なくともこの時の藤野は悲しみを抱いてはいるようにはとても見えない。『ルックバック』の世界は、キャラクターの感情に安易に寄り添うようにはできていない。
だが、ひとりの漫画モンスターの誕生を祝福するには、この土砂降りの雨こそがふさわしいようにも見える。前半部のねじれた成長の物語のクライマックスを飾る、見事なシーンだろう。
ここまで、藤野は漫画家として非常に高い能力を持っているにも関わらず、そのことにほとんど自覚が無く、なんだったら若干見当はずれな方向にコンプレックスを抱いて、方向違いの努力をしてしまう。実はこのエピソードって、「案外似たようなことが現実に起きているのではないか」と私なんかは思うのだ。
要は「自分の資質と志向のミスマッチ」についてのお話なのだけど、自分では職人的な個人作業を黙々とすることに向いていると思ったら案外、人を束ねて全体を仕切る仕事に本来の適正があったり、学生のころは全く向いてないと思っていたのに、会社人としての生き方が性にあってしまったり。
またはその逆も含めて、いろいろな人が生きていく中で出会い、経験するという、けっこう普遍性のあるお話なのではないだろうか。
話を戻そう。そうして自身の本来の資質に目覚めた藤野は、帰宅するやいなやずぶ濡れのわが身も省みず、4コマではない新作マンガのネームにとりかかる。そして見事に45ページの短編マンガのネームを仕上げてしまうのだから、やっぱり彼女の漫画家として才能は尋常ではない。
そんなこんなで藤野がネームとキャラクター作画、京本が背景作画という分担作業で青春の時期をほぼ漫画制作に注ぎ込み、ふたりが17歳になるまでに7本の読み切りを掲載させる。
そのひとつひとつの漫画を仕上げていくシークエンスが非常に美しく、一作ごとの作風があまりに違いすぎる箇所などいろいろな面白みに溢れて素晴らしいのだが、そんな輝かしい日々を経て、ふたりは高校卒業のタイミングで連載の提案を貰い、そこでふたりの進む道が枝分かれしはじめる。
ちょっとした口論にはなりつつも、結果的に互いを尊重する形でふたりは袂を分かち、藤野は漫画誌での連載を開始し、京本は美術を学ぶ大学へ進学するというところまでがおおよその区切りとなって前半部は終わる。
『ルックバック』の前半部を簡単に説明するならば、藤野と京本というふたりが、それぞれ自身を激しく揺さぶる衝撃的な創作物と出会うことで、“暴走”と言っていいほどの激しいアクションを起こすその顛末を描いた話である。
実はこの漫画はふたりで漫画を協力して作る話というより、「お互いがお互いの作品に触発され、どうしようもなく突き動かされてしまう」という衝動にまつわる話なのである。
「送り手」と「受け手」の話とも言えるだろうし、一見すると創造者ではないようにも思える受け手から返ってくるフィードバックによって、送り手もまた大きく動かされるという話でもある。そしてこの「何らかの創作物を受け取った受け手の暴走」という前半部の主題は、後半部にまで至る、本作全体を貫く主題でもある。
だから藤野の漫画以外に自身を衝き動かす「絵」に出会ってしまった京本は、その衝動にしたがって美術の学校に進学を決意する。
そして藤野はひとり連載を開始し、着実に巻を重ねるが、なぜか11巻から先が続かず11巻が積み重なるという、「停滞」を示唆しているかのような若干の不穏さを漂わせ始めたところで後半部へと物語は進む。
あり得たかもしれない可能性を巡る後半部
『ルックバック』の後半部は衝撃的な事件から始まる。
起きた場所、犯行の手法などが違っているとはいえ、本作が公開された2021年7月19日というタイミングなどからして、多くの読者が、この2019年7月18日に起きた、京都アニメーション放火殺人事件を想起するであろう。劇中のこの事件によって、12人の命が失われ、京本もまた犠牲者のひとりとなる。
この悲劇的な事件を転換点として、本作の世界の描き方には大きな変化が起きる。
前半部において登場した藤野と京本という主要キャラ以外の人物、担任の先生や、妹を心配して空手の誘う藤野の姉、あんまり漫画に興味がない藤野のクラスメイトといった周辺に存在し、それ相応に藤野に関わってくる人物は、後半部ではほぼ登場しない。
本来であれば、登場してもおかしくないであろう京本の両親や親類、大学のクラスメイト等といった存在は後半部においては描写されず、藤野という個人に焦点を当てた、極めて主観的な、パーソナルな物語として構成されているのである。
京本の自宅を再訪し、誰よりも京本と身近に接してきたはずなのに「一度も見たことがないであろう制服を着た京本の遺影」という一種の創作物を見た、藤野の心は大きく揺れる。
かつて自身の部屋に閉じこもっていた京本を衝き動かした、藤野の手による4コマ漫画が未だ大事に保管されていることを確認し、「京本の死を招いたのは自身の責任ではないか」とすら思いつめ、自身が創作行為を行なう理由と意味を見失ってしまう。
そこから、鮮やかに展開される「もうひとつの世界」。
この展開に映画『ラ・ラ・ランド』や今年放映された日本のドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』の9話、そしてなによりクエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を想起した人は多いのではないか。
この「もうひとつの世界」において、明確な役割と人格、台詞を与えられて描かれるキャラクターは3人しかいない。藤野、京本、そして凶行に及んだ「犯人」だ。
あれほど劇的で運命的のようにも見える出会いを果たした藤野と出会わなかったとしても、なんらかの形で部屋から外に飛び出し、自分を衝き動かす「絵」と出会い、美大へと進学する京本。そして、結局小学6年生で学年新聞に掲載する漫画を描くことを辞めて、姉に進められた空手のトレーニングを続けているものの、なんらかの理由があって再び漫画を描き始めた藤野。
これが元々の世界と共通する部分はありつつも、あくまで異なる別世界として描かれる「もうひとつの世界」におけるふたりの姿だ。
この元々の世界で運命を変えられたように見えた京本が、実はどのルートを通っても結局部屋を出て「絵」の道を歩んでいたであろうということ。
漫画執筆に没頭しとにかく京本の「画力」を超えることしか頭になかったころには唾棄すべき提案にしか聞こえていなかったであろう空手の道が、そっちの道に進んだら進んだでそんなに悪いものではなかったこと。
そしてなにより、結局藤野は漫画の道にまた戻り、ふたりはまた別の形で出会ってしまうということ。
「もうひとつの世界」を読むことで感じとれるのは、当時は運命的な出会いのように見えて後から考えると実はそうでもなくて、当初はトゥルーエンド一直線だと思った道から脱落したとしても「そっちはそっちで別に悪いもんではなかった」という、あっけらかんとした風通しの良さだ。
そしてそれは前述した映画やドラマといった先行する作品群にも共通する美点でもある。『ルックバック』はそういった現在の最新の物語トレンドの中のひとつとして位置づけることも可能だろう。
だが、本作の「もうひとつの世界」にはもうひとりの主要人物がいる。そう、凄惨な犯行を企て実行しようとする「犯人」である。
「フィクションの力」は世界を変えるのか?
この「犯人」の描写は、すでに何人かの論者から問題を指摘されており、本作においてもっとも物議を呼んでいる部分でもある。私自身、そういった指摘から初めて気付かされる部分はあるし、検討するに値する論点だとも思う。
この描写があることで作品自体が抹消される、もしくはその部分の修正は必須であろうという考えについては簡単には同意しかねるが、そのような指摘が起きること自体は重要だし、こういった声が上がることは歓迎すべきだと思う。
だが、本作の「犯人」の描写については、表層的な言動や振る舞いだけでなく、また別の方向から捉える必要があるとも考えている。
本作のこの「犯人」とその後の展開は、すでに多くに論者が指摘しているように『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の終盤の展開をモチーフにしている。『ルックバック』の最後のコマに『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のパッケージらしきものが描かれていることからも、これは明確にそうだと言ってしまっていいだろう。
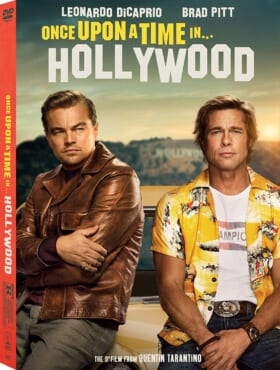
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の終盤において登場する犯人グループは、史実に沿って考えれば、現代まで語り継がれるおぞましい凶行に及んでいたであろう人物だ。しかし、彼らは意外にもブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオ演じる主役ふたりと犬に完膚なきまでボコボコにされ、燃やされ、死ぬ。
本作の意外かつ最高に爽快な終盤の展開と、これ以上ないほど見事にシャロン・テートを演じたマーゴット・ロビーの好演によって、これまでどうしても振り返るたびに悲惨な結末を反射的に想起せざるを得なかったシャロン・テート事件と、その犠牲者である女優シャロン・テートへの印象は、大きく塗り替えられた。
私個人としてはあまり好きな言葉ではないのだが、「フィクションの力」というものを実感として体験させてくれる映画、それが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』である。
『ルックバック』はこの作品を明確に意識しており、ある程度は同じ道を辿りつつ、しかしまた別の道を模索しようとする。
「もうひとつの世界」において別の可能性を提示されるのは藤野と京本だけではない。「犯人」もまた、取り返しのつかない行為に至る寸前のところで、偶然通りがかった藤野の見事な飛び蹴りによって、犯行は(器物破損や不法侵入を除けば)未遂に終わり、元々の世界とは別の可能性を提示されるのだ。
藤本タツキは、なぜこのような選択をしたのだろう。
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のように、「それっぽいことを言ってるようで、結局のところは救いようのないクズ」として犯人を描いた上で爽快にオーバーキルすることだってできただろう。
事実、『チェンソーマン』には一片の同情の余地もないようなクズな殺人者だって登場するのだから、そのようなキャラクターを創造することは、藤本タツキの力量があれば、造作もなくできることだ。
だが、『ルックバック』ではそれをしない。
完璧なタイミングで京本を助けに飛び込んでくる藤野の見開きのコマは『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のように、見る側の「これを待っていました!」という爽快感を存分に味わわせてくれる。
しかし一方で、元の世界においては12名の命を奪い逮捕され、おそらくは死刑になるであろう「犯人」に同じ道を歩ませることをしない。
なぜなら、それは「もうひとつの世界」の原理に反するからだ。この世界では藤野、京本、そして「犯人」は「もうひとつの可能性を提示される」という点において平等に扱われる。
なぜなら「犯人」もまた、その数少ない台詞や劇中の説明からも察せられるように、なんらかの創作物の「受け手」になることで暴走的な行動に駆り立てられてしまう、藤野や京本とその根本の行動原理において共通している人間だからである。
この「犯人」は過去の来歴や背景は描かれないが、実はそれは藤野に出会う以前の京本だってそうなのだ。劇中で京本は「人が怖くて部屋に引きこもっていた」と言っているが、それ以上の詳細な理由や家族との関係性などについては微かに存在が示唆されはするものの、ほぼ描かれてはいない。
「背景の無さ」という点について、京本と「犯人」はほぼ同じ水準で描かれる。両者に差があるのだとすれば、それは藤野と出会って以降の、漫画を描くことを通してさまざまな世界に触れていく京本を、藤野と我々は知っているということだ。
「犯人」もまた、「もうひとつの可能性」を提示される
ここからは私の推測になるのだが、『ルックバック』は、あまりにドラマティックで凄惨な事件の中心にいる「犯人」をできる限り「劇化」しないように、できる限りフラットに描こうとしたのではないかと思う。
「犯人」を描くひとつひとつの繊細な描線、どこにでも居そうなのにヤバそうでもある表情、攻撃的ではあるがひとつとして格好良くはならない所作、差し込む光に照らされて定まりきらない輪郭、汗とも涙ともとれそうな頬を伝う雫……。
どのコマをとっても、ひとつとして「過剰に格好良くも過剰に格好悪くも描かない」ということに関して一切の手を抜いていない。
おそらく作者は「犯人」にあらゆる意味においての「特権性」を剥ぎ取ることに全身全霊を注いでいる。これは相当難しい作業であったのではないかと察せられる。
この「犯人」は、本作において決して同情などはされない。しかし、決してこの世界から排除されているわけでもない。殺人が未遂で終わった彼は、元の世界とは別の道を「もうひとつの世界」の中で生きていくことになるのだろう。
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』が「フィクションの力」によって実在した唾棄すべき犯罪者を容赦なく処刑し悲劇を上書き更新したのだとすれば、『ルックバック』は同様の手法を取りつつ、「犯人」を凡庸のなかに位置付け、劇的な大量殺人事件という悲劇の物語の中心に「犯人」が鎮座することを許さず、別の可能性の中で生きさせようとする。
物語の主要な登場人物として登場させ、物語中における非常に重要な役割を担わせつつも、過剰に不快な人物としても、逆に魅力のある人物としても描かない。私は、その徹底して丁寧でありながら同時に突き放した描写の在り方に作者なりの「抵抗」を見る。
繰り返しになるが、それでもこの「犯人」の描き方に問題点が全くないとは私も思わない。作者の手癖が出てしまった側面が無いとは言えないだろう。しかし、問題は無いが安易でもある表現に落ち着くのではなく、現代の先端的な表現のさらにその先に挑もうとした作者の挑戦的な姿勢を、私は積極的に評価したいとも思う。
だからこそ、この漫画については安易な賞賛一辺倒になるのではなく、批判的なものも含めて言葉が交わされることが重要だろう。
そして念を押して言っておきたいのは、いくつかの瑕疵は存在するとはいえ、藤本タツキは少なくとも「犯人」を「もうひとつの世界」から排除するという選択をしなかったということだ。私は『ルックバック』という物語をそのように読む。
「もうひとつの世界」は、「元々の世界とは別の並行世界である」という解釈や、「衝撃的な事実に打ちひしがれた藤野が妄想した世界」という解釈など、さまざまな捉え方があるが(個人的には後者ではないかと思うのだが)、このような「別の世界もまたあり得る」という考え方は、元の世界の藤野が陥りかけていた「京本を間接的に死に追いやったのは自分ではないか」という、過剰な責任感からくる自責の念を、ある程度は中和してくれる。
しかし、それでも漫画家としての藤野は救われない。自分が漫画を描こうが描かなかろうが世界は変わらないし、自分の居る世界には、最良の相棒である京本はもう居ないのだから。
そんな打ちひしがれる藤野の前に、かつて自身の描いた4コマ漫画が京本の目の前に届いてしまったことと対を成すかのような形でひとつの4コマ漫画が現れる。
この4コマ漫画が、「もうひとつの世界」から届いたのか、すでにあった4コマがたまたま風に吹かれて目の前に現れたのか、これまた解釈が分かれるところだとは思うが、ひとつ言えるのはどのルートを通ったとしても、この4コマ漫画は「描かれたであろう創作物である」ということである。
かつての京本は、不意に現れた憧れの藤野先生作の4コマ漫画を見て、引きこもっていた部屋から外の世界へと飛び出し、藤野との出会いを求めた。そして現在の藤野は、不意に現れた4コマ漫画に導かれるように京本の部屋へと入り、かつてそこに居たはずの京本の姿を振り返ろうとする。
藤野が京本と始めて出会い、自身の才能に気付かされ、漫画家として覚醒した時、土砂降りの雨が藤野には降り注いだ。そして京本を失い、その京本の部屋で、亡くなる寸前まで藤野の漫画の読者であり続けた京本と過ごした日々を振り返る時、悲しみに満ちているはずのその場所には雨は降り注がない。
悲しいからといって、都合よく雨が降り注いでくれるとは限らない。しかし、藤野の頬を伝う滂沱の涙は、ふたりが出会わなければ始まることもなかったであろう連載漫画『シャークキック』11巻の最後のコマに降り注ぐ。そして、その涙に濡れたコマの中で躍動する主人公(シャークマン?)はこんなことを言う。
「シャーク様の出番だぜ!」
これまで繰り返し述べているように、『ルックバック』とは、何らかの創作物の送り手と、それを受け止める受け手の関係性についての物語である。
圧倒的な画力の京本の漫画に出会ってコンプレックスを暴走させ、本質を見失った努力に奔走する藤野。
崇拝と言っていいほどに敬愛する漫画家である藤野の4コマ漫画に触れることで、閉じこもっていた部屋から外の世界へ飛び出すほどの衝動を沸き起こす京本。
美大に陳列されている作品からなんらかのメッセージを受け取り、それが凶行への引き金になってしまう「犯人」。
そして奇跡なのか偶然なのか、京本が描いた4コマに不意に受け止めることで、自分が漫画を描く原点を再確認する藤野。
やがて藤野は立ち上がり、また漫画家としての自分の仕事場に戻る。そして、一片の4コマ漫画が描かれた原稿用紙を自身の机の正面の窓に貼り付ける。本作において、物語の序盤の暴走を除いて、藤野は一貫して送り手の側に立ち続けていた。
しかし、京本の4コマを自分の机の目の前に貼り付けることで、藤野は一方的に送り手の立場に立ち続けるのではなく、京本の漫画の受け手でもあろうとする。藤野が受け手であり続ける限り、漫画の送り手としての京本はこの世界に残るからだ。
藤野はこれからも漫画を描き続けるだろう。目の前に貼られた京本の4コマ漫画がある限り、藤野が漫画を描く理由を見失うことはないのだから。
「2021年7月19日」に公開するということ
最後に、本作を考える上で、外せない要素である「2021年7月19日」にこの漫画が公開されたことについても触れておこう。
「2019年7月18日」におきた京都アニメーション放火殺人事件から2年と1日を経てこのような、事件との関係性を強く意識させるこのような漫画を公開するということについては、意見が分かれるところなのではないかと思う。
それは、まだ記憶に生々しく残る凄惨な事件を、直接的ではなくそれ相応の翻案や抽象化がなされていたとしても「漫画の主題として取り扱う」ことであり、それを明確に受け手に想起させる「2021年7月19日」という狙いすましたタイミングで公開するということの是非についてである。
そこにいわゆる「エモさ」を感じてより心動かされる人もいれば、そこにある種の「仕掛け」や「不遜さ」を感じて鼻白む人がいたとしてもおかしくはないだろう。
私は藤本タツキという漫画家は、純粋に作品のクオリティを追及する「アーティスト」としての側面と、自身の作品をいかに効果的にアピールし、広めることができるかを考えて仕掛けを打つ「興行師」の側面が共存し、両立しているクリエイターなのではないかと考えている。そして、そんな両面性を含めて藤本タツキという漫画家を「面白い」とも思っている。
また、藤本タツキとデビュー当初からコンビを組んでいる編集者、林士平という「興行師」としての側面を濃厚に持ち合わせた「編集者」の存在も見逃せないだろう。
現在、「6組の新人漫画家と編集者のタッグが、競い合いながらデビューを目指す」という文字通り漫画制作を「興行化」した番組『MILLION TAG』にも参加している林士平。

そして彼が現在所属する「ジャンプ+」という主にネット上で展開される漫画プラットフォームという「興行の場」が無ければ、『ルックバック』という物語が発表され、発表されて一晩も立たずにセンセーションを巻き起こすということも無かったのではないだろうか。
そして、そのような「アーティスト」と「興行師」という異なる2つの側面とは、ネットで作品が流通し、“作品を発表するやいなや、即座に反響が返ってくる”ようになった現代の環境を自明の前提として生きている若い世代の作家や編集者にとって、当然のように持ち合わせている感覚なのではないかとも思うのだ。
たとえば『ルックバック』が掲載された媒体でもある「ジャンプ+」(と「週刊ヤングジャンプ」)にて連載されている『推しの子』の作者である赤坂アカと横槍メンゴは、担当編集者も交えたインタビューにてこんな発言をしている。

──ちなみにおふたりは、エゴサーチをするタイプですか?
赤坂・横槍 します!
赤坂 基本的にはかなり耐性があるほうなんですけど、自分自身でも気にしているところを改めて刺されると、思いのほかダメージを受けたりもしますね。
横槍 私はもともとそういうのに弱いタイプなので、完全に匿名の場所はあまり見ないようにしていて、基本はTwitterを見ます。Twitterは表現もマイルドであまり傷つかないので(笑)。
赤坂 いずれにしろ、なんとなく確認はしたくなっちゃうんですよね。
(中略)
赤坂 まあやっているうちに麻痺していって、最後には何も感じなくなるのかもしれないですけどね。僕の場合もそうで、今ではほぼ何も感じなくなりました。中傷も誹謗も完全なる日常の一部です。
横槍 ああ、たしかに。私も最初の頃に比べたら感じなくなったかも。でもそれはそれで人間味を失っていくようで、少し寂しいなとも思っちゃいますね。
漫画『【推しの子】』赤坂アカ×横槍メンゴ×担当編集・サカイ(前編)/描きたいのは「芸能界の闇」ではなく、しがらみや圧力の中でもがく人々|ライブドアニュースより引用
このように、現代の若い作家や編集者にとっては、「日課の如くエゴサーチをし、自身の発表された作品の反響を即座に受け止め、さらに次の作品へと向かう」というサイクルはもはや当然のこととなりつつあると言っていいだろう。
彼ら彼女らにとってみれば、今現在、目の前で起きている大きな反響を呼ぶ出来事や、自身にとっても切実な関係のある事件や諸問題を、「作品で取り扱わない」ことの方がむしろ不自然なことなのではないかと思うのだ。
これはもちろん私の個人的な推測だが、藤本タツキもおそらくはエゴサーチをゴリゴリにするタイプなんじゃないかと思う。そしてそんな作家であれば、自身にとって切実なことを描いた作品を、それを最も強く思い出す日に公開するということもまた自然なことなのではないか。
2019年7月18日に起きた京都アニメーション放火殺人事件とは、創作物を作る送り手を、受け手の側の、それも「一度は送り手の側にもなろうと志した人間」が破壊しようと企て、実行されたという点において、非常に衝撃的な事件だった。
この事件で逮捕され、自身も重度の火傷を負いつつ、辛うじて一命をとりとめた青葉真司容疑者に関しては、事件から2年を経ても未だ初公判の見通しすら立っておらず、事件の全貌は未だ把握されてはいない。
『ルックバック』という作品は「送り手と受け手の関係性を巡る物語」であるということは、すでに述べた通りだ。なぜ本作は間接的な形ではあるにしろ、京都アニメーション放火殺人事件を下敷きにこのような物語を描いたのか。
それはこの事件が送り手と受け手の関係性を、他でもないその送り手と受け手というサークル内部の人間が、それを制作する送り手が集うスタジオごと破壊しようとした事件だからである。【※】
※青葉真司容疑者は自身で小説を執筆しており、「その内容を京都アニメーション側に盗作された」という供述を逮捕後に行っている。彼の執筆した小説は京都アニメーション主催で毎年開催されていた「京都アニメーション大賞」に応募されていたとみられている。その後、京都アニメーションは同賞の開催を当面休止すると発表した。
いまさら説明するまでもなく、「フィクションの力」は人を変え、人を動かす。それが想定しうる最悪の暴力として表出してしまったのがこの事件なのだとすれば、ここから導き出される「フィクションは、人を破滅へと導くトリガーとなりうるのか?」という問いはあまりにも重い。
だからこそ、『ルックバック』は送り手と受け手という関係性が本質的に孕む危うさすらも内包する形、それも「受け手に湧き上がる衝動によって駆動する物語」として描かれた。それゆえ、本作は「2021年7月19日」に公開されたのではないかと私は考える。
漫画的な誇張や擬音表現などを極力排し、非常に静謐な作品として描かれる本作は、このあまりに重い問いかけに対する、現状考えうる限り最も誠実な「答え」であり、藤本タツキという漫画家だからこそできる、失われたものへの最大限の敬意に満ちた「追悼」である。
好き好んで追悼をする人などいない。しないで済むならこんなに楽なことはない。でも我々は追悼をする。残された我々にはそれをする必要があるからだ。
『ルックバック』という重層的、かつ多面的な物語を描くという行為そのものが、藤本タツキという作家にとっての追悼だったのだ……とまとめてしまえば陳腐になるが、おそらく藤本タツキは「この漫画を描く」ということを必要としていたのではないだろうか。
とはいえ、それでも今回のこの一連のやり方に、あざとさや一種の露悪性を感じる人もいるだろうし、そのことに対する違和感を表明する動きもまたあって当然だとも思う。
だが、私個人としては、このタイミングで一歩間違えれば総スカンを喰らってもおかしくないセンシティブな内容の漫画を全身全霊で(そうでなければ143ページなんて狂ったボリュームの短編を描かないだろう)投げつけてくる藤本タツキの漫画家としての覚悟と、そこに込められた決意に首を垂れる思いである。
私はこれからも度々『ルックバック』を読み返すだろう。この作品は、一時のバズで盛り上がって消費して忘れるような漫画ではないからだ。
この『ルックバック』を経て、まもなく開始するであろう『チェンソーマン』の第二部を、そして藤本タツキというまだまだ発展途上の作家のこれからを「受け手」のひとりとして見守りたい。
2021年8月2日に発表された内容の一部修正に関して
2021年8月2日、一部読者の指摘を受けて、『ルックバック』はその内容の一部を修正するとの発表があり、公開されている内容の一部が修正された。
「一度発表した作品を後から修正する」ということは、決して軽いものではなく、相当な熟慮の末の決断であったことは容易に察せられる。まずは、修正の判断を下した編集部側の意志を最大限尊重したい。
そして、私が確認する限り、修正がなされている箇所は、劇中の新聞での事件報道を除けば後半部の「もうひとつの世界」に集中しているということに着目しよう。
『ルックバック』という漫画が、あり得たかもしれない「もうひとつの可能性」を描いた漫画なのだとすれば、今回の修正版は、さらなる可能性を描いた「もうひとつのルックバック」として読むことも可能だろう。
本作における重要な要素の一つである、創作に対する「外部からの冷たい視線」というものが行き着く果てを描いたのが、今回の修正版であるとするならば、これはこれでひとつの作品としてまとまっているとも思う。
しかし、私のこの長い文章で指摘したように、修正前の本作は「犯人」を、なんらかの創作物の「送り手」であり「受け手」の側である可能性を示唆することで、京本や藤野寄りの人間として描き、惨劇を引き起こす「犯人」すら世界の一部として決して疎外せず、内包して描いていた。
こうしたかつての『ルックバック』が持ち得ていた「創作によって暴走する者を決して疎外しない」という視線は、修正後の『ルックバック』からは、おおきく後退してしまっていることもまた、私が受けた率直な感想として残しておきたい。
修正版においても「犯人が創作者側であった可能性もある」という解釈も出来なくもないが、今回の修正によって「犯人」はより「外部」の存在としての側面が強まったと私は考える。
そして、すでにこの世の中からは、少なくとも正規の手段では確認することが出来なくなってしまったかつての『ルックバック』が、確かにこの世に存在していたひとつの証言として、この文章は内容は修正せず、この追記を補足することのみに留めることとしたい。
2021年9月3日の単行本発売に伴う内容の再修正について
9月3日に『ルックバック』の単行本が発売され、それに伴い以前修正された箇所が再び修正されることとなった。
藤本タツキ著『ルックバック』については、発表後、8月2日に内容を一部修正いたしましたが、9月3日発売のコミックスにおいて、著者の意向を受けて協議のうえ、セリフ表現を変更している部分がございます。
— 少年ジャンプ+ (@shonenjump_plus) August 27, 2021
ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
少年ジャンプ+編集部
具体的な内容については、実際に単行本を読んで確認して頂きたいのだが、一度目の修正によって、この物語の主題ともいえるなんらかの創作物の「送り手」と「受け手」の関係性の外側に配置されてしまった「犯人」は、今回の修正によって再びその関係性の内側に戻る形となっている。
一度目の修正に批判的だった読者の間でも、今回の修正は概ね好評に受け止められているようだ。
私個人としても、以前の追記でも述べたように一度目の修正版『ルックバック』がそれはそれでひとつの作品になっているとは評価したものの、やはり本作は「送り手」と「受け手」の関係性が到達しうる最悪の事象まで射程に含めていることが非常に重要であるとも考える。そのため、初回版で指摘された問題点は回避しつつ、物語の主題は捻じ曲げない今回の修正を歓迎したいと思っている。
しかし、今回のこの二度にわたる修正はまた別の問題点も浮上させている。
それは、『ルックバック』はこれまで二度修正されているが、すでに我々は「正規の手段でその修正される以前の姿を見ることが出来ない」ということだ。
初回から紙で出版されていたのであれば、少なくともその出版されたモノは残る。しかし、ネット上で発表された漫画は、その時点でデータとして手元に残すなどしなければ、修正された時点でもう二度と元の状態を確認することは出来なくなる。
漫画を発表する主戦場は今後よりネット上に移行していくだろう。その過程において、今回と同様に修正の判断が迫られる局面は増えていくのは間違いない。
一度発表した創作物を後から修正するという行為は決して軽いものではない。それが物語の主題に関わる箇所であればなおさらだ。
だが、指摘された問題点に対して「送り手」の側が納得し、同意する部分があるのであれば、修正という判断に至ることもまたやむを得ないのではないかとも思う。「修正しない」ということは、「自身でも認識している目の前の問題を放置する」ということでもあるからだ。
この二度の修正を行なうに至る過程において、「送り手」の側がどのように考え、行動したのかについては、我々「受け手」の側からその全てを伺い知ることは出来ない。
この度、出版された『ルックバック』の単行本には、ジャンプの単行本であればよくある表紙裏の作者コメントや、巻末コメントなどは一切含まれていない。とにかく「作品の内容のみで語り切る」という意志で貫徹されている。
潔いとも言えるし、ある種素っ気ないともいえるこの単行本の在り方に、不必要に読者サービスをしない、ある種の「閉じた」姿勢を感じる人もいるかもしれない。
だが、『ルックバック』が出版される過程において、二度の重大な修正が加えられたという事実、つまり近年稀に見るほどに「送り手」と「受け手」が作品や言葉でやり取りし、互いにコミュニケーションをした末に今回の出版に至っているということは、本作を2021年を代表する作品として考える上で、忘れてはならない重要な事実なのではないかと思う。
「受け手」の言葉に対しても耳を傾け、自分のやるべきことをやろうとした「送り手」、それが藤本タツキという漫画家であり、そんな彼だからこそ『ルックバック』という漫画が描けたのだ。私はそのように考える。
今回、改めて紙で読む『ルックバック』はこれはこれで味わい深く、良いものだった。既にネットで読んだ人にも、最初の修正に憤慨した人にも、まだ一度も読んでない人にも、広くオススメしたい。


































