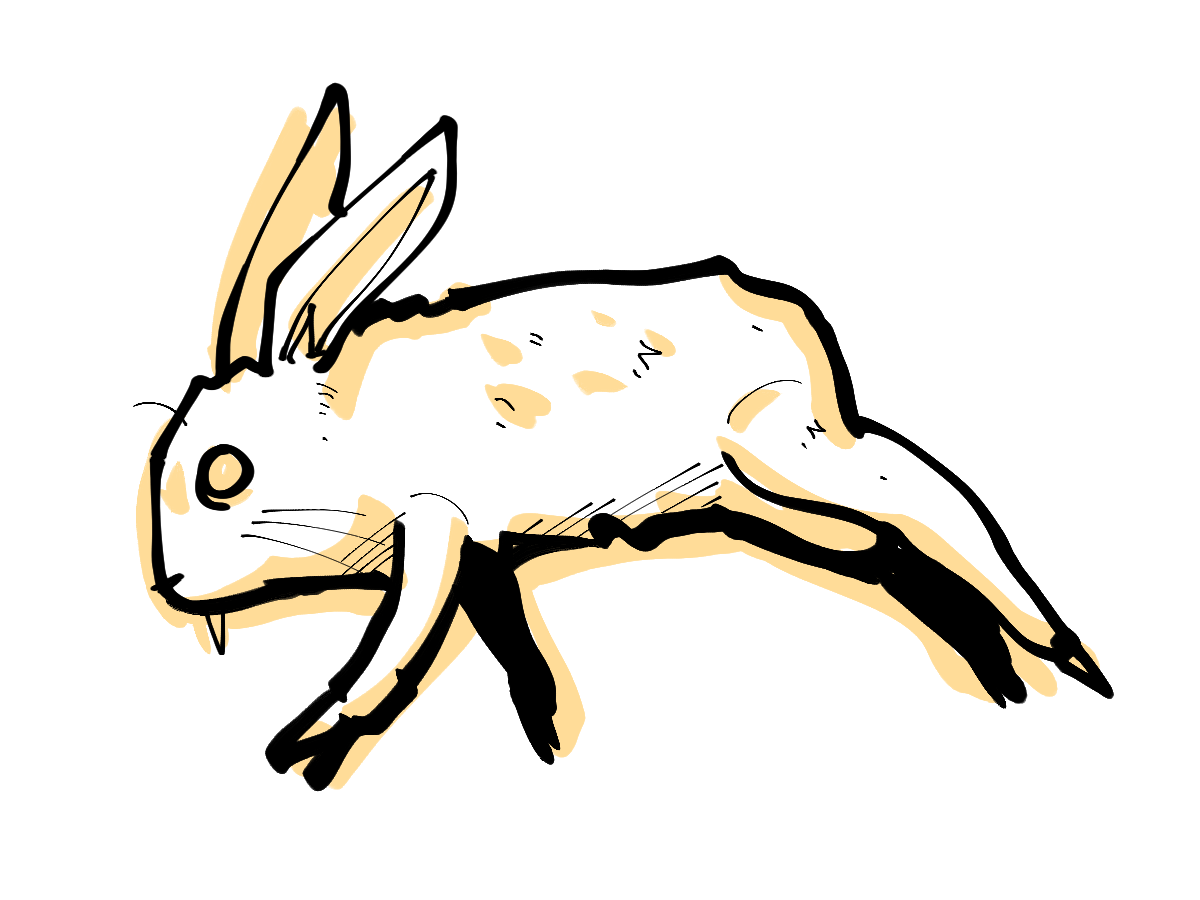ゲームをプレイするうえで「雑魚敵の死」に注目したり心が揺さぶられたりすることはありますか?
よほどマニアックなプレイスタイルでない限り、気にしないと思います。というのも、そういった立ち位置のモンスターなどは基本的にやられてナンボの存在であって、なぎ倒したら素材だけ回収してさっさと次へ進む──それが普通の感覚ではないでしょうか。
でも、『七つの大罪:Origin』はそんな雑魚敵の死に思わず目が留まってしまうゲームでした。
なぜなら雑魚敵なのにやたら死ぬまでの姿がじっくり表現され、まるで “見せ場” かのように作り込まれていたからです。
そこで限られた時間ではあるものの、さまざまな “散り方” を探るべく雑魚敵たちや周辺にいた生物の死にざまを調査してみました。調べた結果、大きく分けて2パターンの死に方をしていることに気が付いたので、紹介させてください。
ただし掲載できる画像に限りがあったため、要所要所で読者の皆さまの想像力をお借りできますと幸いです。
※この記事は『七つの大罪:Origin』の魅力をもっと知ってもらいたいネットマーブルさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。
ギャグ漫画のズッコケ風から映画のワンシーン風まで。個性的すぎる雑魚敵の死亡モーションの数々
本作は鈴木央氏原作の大ヒット漫画『七つの大罪』を題材としたマルチプレイ型オープンワールドRPG。広大なフィールドを見たらまずは駆け回りたくなるのが人間の性、ということで草原をあてもなく歩き回りながら景色を楽しんでいると、近くに敵の群れを発見しました。
早速戦ってみますか!どんなバトルなんだろう!
と近付いてみたら、なにやら盛り上がっていて無視されました。何事かと思ったら、雑魚敵の群れ同士がバチバチに戦闘中。どうやら縄張り争いをしているようです。
(武装したクマとウルフが戦っている姿を想像してください)
雑魚敵としてただウロウロしながら主人公サイドを一方的に襲ってくるのではなく、こうしてちゃんと自然な生態系が作り込まれていると「ああ、こいつらにもこいつらなりの事情があるんだな……」と妙な愛着が湧いてきますね。
などと思いながら抗争を眺めていたら、巨大なクマ型の敵である「ウェアベア戦士」のコミカルな死に方がふと目に留まりました。
バク宙に失敗したかのようにひっくり返って、後頭部を強打したまま固まるのでとてもシュール。ギャグ漫画でしか見たことがないような見事なズッコケ方です。

しかも、やられてから消滅するまでに若干の猶予があるため、尻を主張したこの個性的な死にざまをじっくり観察することができます。
ひっくり返ったまましばらく消えないので、雑魚敵が死んでも消滅しないタイプのゲームなのかと思いました。
さらによく見てみると、このズッコケクマさんと戦っている狼のような敵「ウェアウルフ戦士」も死ぬと「うっ!」と胸を大袈裟に抑えたあとにガクリと倒れ込むという、舞台俳優さながらの情感たっぷりな死に方を見せてくれました。
ただの群れでいる雑魚敵のはずなのですが、物語の重要人物としか思えないような散り方です。
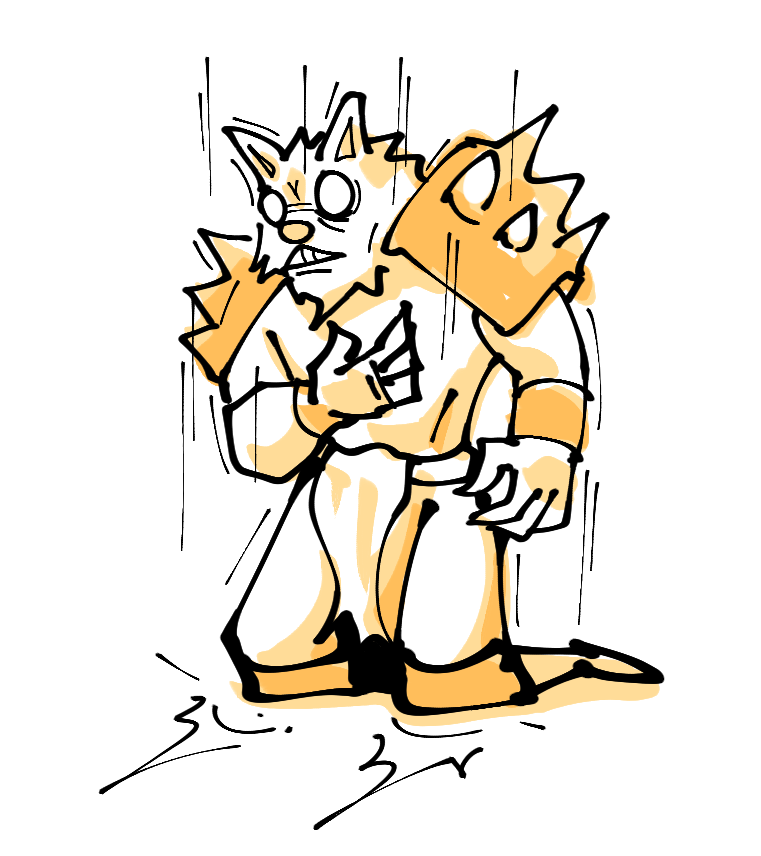
死に方のバリエーションはコミカル方向だけではない。対抗勢力のように存在する“生々しい死亡モーション勢”
こうなるとほかの雑魚敵たちの死に方も気になるので、周辺生物の「死に方鑑賞ツアー」という狂気のツアーを催行してみることに。
広大なフィールドを駆け巡り生物を見つけ次第倒してみると、どの敵にもそれぞれ異なる “こだわりの死亡モーション” が用意されていて、細部にいたるまでの作り込みを感じました。
フィギュアスケーターのような超速スピンを披露しながら吹っ飛んで死ぬ狼、逆立ち状態で足をバタバタさせて元気に死ぬ鳥、スローモーションのようにバラバラに砕け散るゴーレム……と、どいつもこいつも倒れ方に一癖二癖あって「敵の数だけ見どころがあるな~」とつい感心。
(どうにか想像してください)
よく見ると「死ぬ直前に頭に咲いていた花が萎んで引っ込む」みたいなモーションもあったりするので観察のし甲斐があります。カニさんはジタバタしていて可愛い。
(ジタバタしているカニを想像してください)
そんな中、人相の悪いウサギを発見。こいつはどんなコミカルな死亡モーションを見せてくれるんだろう? 跳躍力をいかしたトリプルアクセルとかしてくれるのかな? などと予想しつつ意気揚々と倒してみたところ、
力尽きるようにバタリと倒れ、足を伸ばす形で死亡。いや急にリアルすぎる。
あまりにもリアルすぎて、昔実家で飼っていたウサギの最期をそばで見届けたときのことを思い出して妙に感傷的な気分になりました。
重要人物とかボスキャラとかではなく、広大なフィールドをウロついているだけの雑魚敵のはずなのにこんなにリアルで丁寧な死亡モーションが用意されているとは思いませんでした。オーバー演技のコミカル劇団員だらけかと思いきや、こういった生々しい死亡モーションの雑魚敵もいるなんて!
“一体一体にちゃんと命がある” ということを強調するかのような演出に思わず見入ってしまいましたが、なんだか心にきたので逃げるようにその場から退散。
しかし気を取り直して雑魚敵狩りを再開してみると、同じように “リアリティを感じさせる最期” を見せてくる敵が、ほかにもちらほらいることを発見。
ツノから葉っぱが生えた鹿やバッファローのような敵、ミーアキャットのような敵も「力尽きてぐったりと倒れ込む」という生々しい死に姿で、例によってその死に姿も割とじっくり見せてくれるのでその度に「あっ…」と心がざわざわしました。
こんなマニアックなところに注目する変な遊び方をしているのは自分自身だけど。
雑魚敵にもそれぞれの生活がある。観察することで垣間見える彼らなりの日常と “生きている感”
新しい生き物を求めて歩き回っていると、テントが複数張られ松明が灯された場所を発見しました。どうやら敵の野営地のようなのですが、肝心の敵はおらずもぬけの殻です。
「おかしいな」と思ったのですが、よく考えてみるとこの場所は先ほどクマと狼が縄張り争いで抗争を起こしていた場所の目の前。恐らくはこの野営地を拠点にしていた者たちが縄張り争いに敗れ全滅してしまい、誰の気配もない寂しい空間へと変わってしまったものだと思われます。
(空っぽのテントを想像してください)
というかじつは争いの最終局面あたりで筆者も突然参戦して、数の減った両軍をド派手スキルで一網打尽にしていた(試し打ちしたくなった)ため、野営地の主たちはみんな死んでしまっているとみて間違いなさそうです。
そのときは「わあ、スキル強え!よし俺のひとり勝ち!こいつらおもしろい死に方してんな!」といった感じでまったく気にしていなかったのですが、改めて主を失った野営地をじっくり観察してみると、生活の痕跡がしっかりと感じられてなんとも言えない気分になりました。
投擲の練習をしていたのか、的に刺さった斧がそのままになっていたのがいちばん心にグサッと来ました。ああ、来る日に備えてコツコツ頑張ってたのに死んでしまったんだ……(殺したの俺かもしれないけど)!

まさか雑魚敵の死で「命の重み」を考えることになるとは思ってもいませんでしたが、それほど細部にわたって作り込まれているゲームでした。
今までアクションゲームで雑魚敵を倒したときは死亡モーションには目もくれず、ただ俺TUEEEEしながら散らばる素材を夢中で集めていただけだったけど、これからは雑魚敵一体一体の生きざまにも散りざまにも注目してみようかな。
雑魚敵にもこれだけの作り込みがなされている本作、原作にちなんだプレアイアブルキャラたちの動きや演出がどれだけ丁寧に作り込まれているのかは、言うまでもなく相当なものになっていると思います。
というのも恥ずかしながら筆者は原作についてざっくりとした理解しか持っておらず、それゆえにド派手な技のエフェクトなどを見ても「うおおめっちゃ綺麗!!」「超強いぞ!!」などといった価値ゼロ感想しか出せないのですが、原作ファンの方であればキャラたちの一挙手一投足から設定の裏側や感情の機微まで受け取れるはずで、より深く作品を楽しめると思います。
ともあれマルチプレイ型オープンワールドRPGとしての完成度の高さと心揺さぶる演出のパワーは、原作ファン・未読者問わず必見です。ご興味のある方はぜひ!
©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ⒸNS,K/TSDSFKAP
© Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.