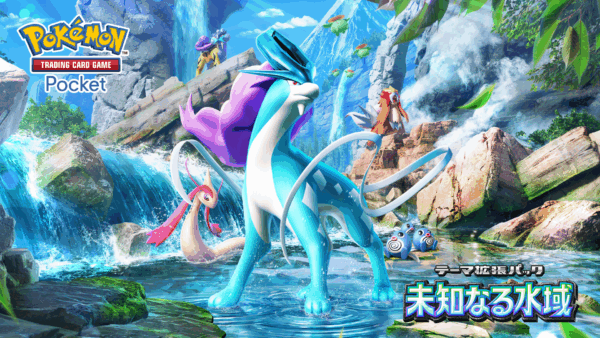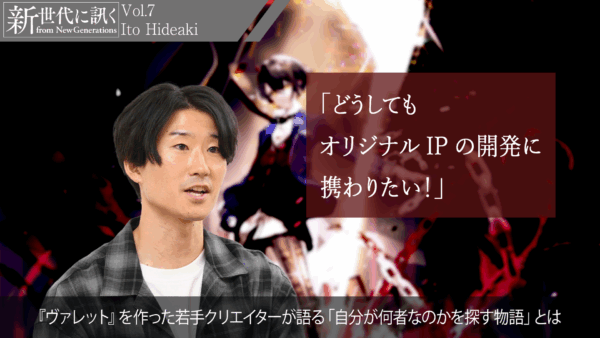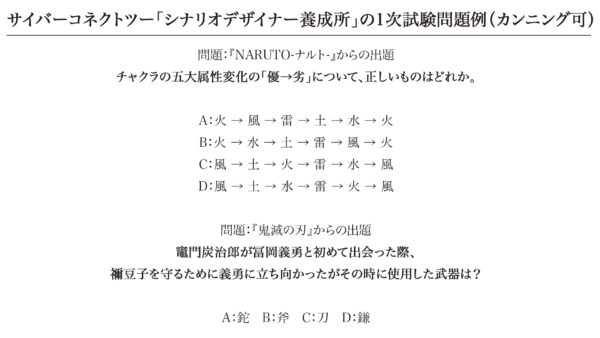ディレクターが語る『零』シリーズ全作品の制作秘話
最後に講演の冒頭で、ディレクター柴田氏が語った、『零』シリーズ各タイトル制作の動機などをお届けしよう。

『零』シリーズを作るまえは、館にトラップを仕掛けて訪れた敵を倒す『刻命館』というシリーズを作っていました。そのシリーズの終わりごろ、2000年くらいに「つぎの舞台は和風の館にしたら?」と考えついたんですが、開発には至りませんでした。初代のプレイステーションだとスペックにも限界があり、なかなか複雑な構造の建物は作れなかったんです。
その後、当時は夢のマシンのように感じられたプレイステーション2での開発を始めるころになり、「このハードなら作れるんじゃないか」と、和風の怖ろしげな屋敷を夜中に探索し、敵として幽霊が現れるというホラーゲームを作ることにしました。私自身、たまに幽霊を視るような体験もしていたので、「この体験をゲームに落とし込めたら、とても怖いものになる」と思ったんですね。当時は『バイオハザード』だったり『サイレントヒル』だったり、ホラーゲームの全盛期。「ちゃんと怖いものを作れば、けっこうイケるのでは?」というようなことを考えてスタートさせたんです。
それまでのホラーゲームの場合、武器を使って敵を倒すのが定番だったのですが、『零』ではこれをカメラにしました。霊と写真であれば、心霊写真を思い起こすと思いますが、“撮る”という行為は“撃つ”という行為に近かったので、これはゲームとしての相性もいいと気づいたんです。おもしろかったのは、相手が幽霊とはいえ、撮るとなると、よりいい写真を撮りたくなっちゃうんですよね。「そのへんがゲーム性にもなるな」と。
幽霊という、すごく怖い、見えないものを敵として表現しようとしました。当時はプレイステーション2には夢のような機能があると信じていたので、「見えないものを表現できるんじゃないか」と思って作ったのが1作目です。ただ“本当に怖いゲーム”を目指しました。

こうして作った1作目は、「とても怖いね」という評判をいただいた一方で、「怖すぎてやる気が出ない」という声もけっこういただきました。怖さは人によって変わります。「ぜんぜん怖くないよ」という人もいましたし、「訳が判らないほど怖い」という声もありました。その中でも、「怖すぎて最後までプレイできない」というプレイヤーのため、続編を作るときには、「つぎはもっと怖いんだけど怖くなくしてくれ」というハチャメチャな要求が出されまして、どうしようかと思ったんですね(笑)。
1作目にもストーリーがありましたが、それ以上に、怖い状況や演出によって、何かがいそうな、誰かに見られているような空間を描写することに力を入れましたが、2作目の『零 ~紅い蝶~』では、それに加えて「話の続きが気になるから先に行く」という作りにすれば、「もっと多くの方に最後まで楽しんでいただけるな」と、ストーリーを前面に出すことにしました。
主人公は双子の女の子。お姉ちゃんが取り憑かれたようになって、ふらふらと怖い村の奥へと行ってしまいます。プレイヤーは妹を操作し、「お姉ちゃんを助けなきゃ」と、どんどん村の奥へと入っていきますが、じつはその村では過去に双子にまつわる儀式が行われていたことが判り……と、過去の儀式と主人公の双子の話が交錯していきます。これらの結果、おそらくゲームの前半は1作目より怖くなくなっていますが、「最後までプレイできた」という人が増え、ホラーとゲームのバランスがいいと思ってもらえたのではないかと感じました。
また、この当時はゲームに主題歌を付けることが流行っていました。主題歌があることでストーリーのあるゲームとしてバリューがあると感じてもらえると思ったのです。その影響もあって『紅い蝶』から主題歌をお願いしています。歌っていただいたのは天野月子さん。ストーリーを体験したあと、ゲームの世界に合った歌が締めとして流れることで、“感情のまとめ”ができると思ったんです。

当時、物語のあるゲームのムービーは、「ゲームを進めると観られる」というご褒美のような位置付けのものが多かったのですが、『紅い蝶』のエンディングは“最高のバッドエンド”か、“最悪のハッピーエンド”しかないという、ある意味ではホラーらしい形になっていたため、「がんばってプレイしたのに、ご褒美がこれ!?」というお声をいただいていました。それを受けて3作目の『零 ~刺青ノ聲』は、バッドなオープニングだけど、グッドなエンディングになる設計にしようと思いました。
シリーズ1作目や『紅い蝶』は、「横溝正史が描くような日本の古い村へ行って、怖い目に遭う」という、旅や観光のような側面がありました。心霊スポットなど非日常的な場所に行く怖さですね。一方、よく耳にする怪談では、寝ていたり、シャワーを浴びていたり、夜に家に帰った瞬間だったりと、日常生活の中で怖い目に遭うものが多いんです。CGで作ったゲームは、そうした日常の中で起きた怖さを描くのがあまり得意じゃないと思っていたのですが、3作目はそれにチャレンジしようと思ったんですね。
日常の怖さだけですと、ゲームとしてこじんまりしたものになりそうでしたので、ふたつの軸を作りました。「主人公の日常生活で怖いことが起こる」という部分と、「眠ると夢の中でこれまでのシリーズのような和風の館へ行く」という非日常の部分。それらふたつの軸を行き来しながら話を進めていきます。日常で起きる怖さを取り入れつつ、“恋人が死ぬ”という最低の状態から始まった主人公が、どのようなエンディングを迎えるのか、というストーリーにしたのです。

プレイステーション3が登場した同時期に任天堂のハードがWiiになりました。このハードはコントローラーが独特で、テレビのリモコンのようなコントローラーと、ヌンチャクというサブのコントローラーがあり、これらを繋いで両手で遊ぶというスタイル。それを見て「アトラクション的なホラーゲーム向きだ」と思ったんですね。プレイヤーが屋敷の中に入って、懐中電灯で照らしながら探索する感じを味わえる。さらにリモコンに振動機能やスピーカーが付いているのもおもしろい。「これはとても新しいホラーゲームのプラットフォームになる」と思って任天堂さんとお話をした結果、共同でホラーゲームを作ろうということになりました。
同時に、グラスホッパー・マニファクチュアという会社を率いる須田剛一さんと会う機会があったんです。そのときに須田さんが「すごく『零』が好きなんですよ!」という話をしてくださいました。そこで「つぎに『零』を作るとしたらどんなゲームにしたらいいですか?」と尋ねたら、「カメラをもっとキャラクターに近づけましょう!」とすごい熱さで返ってきたんです。「彼女の匂いを嗅ぎたいんだ」と。その瞬間に「この人は信用できるな」と思ったんですね(笑)。自分の嗅覚でゲームを作っている人なんだと。よくよく考えてみると、須田さんはゲームキューブで『killer7』というゲームを作り、Wiiでも『ノーモア☆ヒーローズ』というゲームを作っていました。つまり任天堂のハードでの開発に慣れている。さらにプレイステーション2で『michigan』というホラーゲームも作っていて、“任天堂ハードでの開発”、“ホラーゲームを作った経験”というふたつを満たしていたのです。「ほかの会社と組むとしたら、グラスホッパーさんはベストなのかもしれない」と思い、けっきょく3社共同開発となりました。
『零』シリーズは、基本的には血やグロテスクさのない怖さを目指しているのですが、1作目と『刺青ノ聲』には残虐な描写を、あえてスパイスとして入れています。『月蝕の仮面』は血やグロテスクさのない幻想的なものにしようと思いました。ストーリーとしては、幼いころの記憶のない、つまり過去のない女の子がいて、その子がもう一度過去に住んでいた島にある病院を探索し、自分の過去に何があったかを思い出していくというものです。人が死んでいたり、血が出たりというよりも、“記憶が蘇っていく怖さ”のようなものにフォーカスしました。
というのも、Wiiのコントローラーを握って進めば体感度が増すことで、そのスパイスが必要なくなると思っていたのです。『零』の1作目から『刺青ノ聲』までは、主人公が歩いていくと、決まったポイントでパッとカメラが切り替わる、映画のようにカットが割れるカメラなんですが、『月蝕の仮面』は、サードパーソンビューといいまして、主人公の少し後ろあたりをカメラがずっと付いてきます。この視点だと、主人公と半分程度はプレイヤーの気持ちが一体化するんですよね。これにより、場所の空気や見えないものの気配などで美しいホラーゲームができると思っていたのです。しかし、この視点の変更によって、それまでの怖さの演出が使えず、この視点ならではの怖さを作るという、別の苦労がありました。イチからホラーに対する考えかたを見直し、試行錯誤に時間がかかったタイトルです。

つぎの『眞紅の蝶』は発売元が任天堂さんとなる共同タイトルで、再びプラットフォームがWiiです。『月蝕の仮面』でコントローラーや視点変更の“怖さ”というものをイチから見直しましたが、その方法論がひとまず完成したと考えたんですね。そうであればその仕組みを活かして「別のタイトルをもうひとつ作ろう」となったと。そのとき、たまたま「『紅い蝶』の世界を『月蝕の仮面』の視点で歩いたらどうなるんだろう」という話が出ました。当初は「設計がまったく違うから、当て嵌めるのはムリだろう」と思っていましたが、試してみたら思ったよりも違和感がなく、別の怖さの感覚が得られたんです。「だったらこれでひとつやってみましょう」ということになりました。
旧作の『紅い蝶』と基本的なストーリーラインなどは似ていますが、視点がサードパーソンになったことを踏まえ、ゲームのバランスや恐怖を演出するタイミングをもう一度考え直しています。その結果、細かい演出の変更やタイミングの調整が行われ、演出やエンディングの追加もあり、単純なリメイクではなくなったタイトルです。

このタイトルはWii Uで作ったんですが……皆さんご存知だと思いますが、コントローラーに画面が付いているんですよね。これをテレビ画面に向けると完全にカメラです。最初にハードを見たときは、「これはどう考えても作らざるを得ないだろう」と思いました。いろいろな方からも「作るんでしょ?」と言われるんですよ(笑)。ですが、いざ作るとなるとけっこうこれはこれで難しいんです。Wii Uパッドをカメラに見立てるという遊びは成立しているし、それはプレイヤーの皆さんも想像がつくとは思いますので、なんとかそれ以上のものを作るというのが課題でした。試作や実験を重ねた結果、『濡鴉ノ巫女』には、これまで私がホラーゲームでやったことのない要素をいろいろ詰め込むことができました。
たとえば、アクション要素と言いますか、プレイヤーの皆さんに能動的にやっていただく要素ですね。Wii Uパッドを構えるということで、見回したり傾けたりと、よりカメラを使っている感覚になっていただきたかったのと、プレイヤー自身が霊と対峙している感が出ると思いましたので、「霊に関与していただけるように」と増やした要素もあります。
ただ皆さんからも質問をいただいていますが、怖いゲームを作るときに、プレイヤーの関与が増えれば増えるほど、もしくはプレイヤーがコントロールできる範囲が増えれば増えるほど、怖さは減っていくんですよね。その代わり、幅広く楽しんでいただけるようなゲームらしさを入れることもできる。そのバランスをどうするかで、ギリギリまで紆余曲折を重ねたタイトルでした。
柴田:
シリーズの紹介はこれで終わりです。今日のこの場には、ホラーゲームに詳しい皆さんもいらっしゃいますし、そうでない方もいらっしゃるでしょう。“幽霊が出てくる和風ホラーアクションアドベンチャーゲーム”は、数少なく特殊なものですが、皆さんのゲーム作りに少しでもご参考になればと思います(笑)。
関連記事:
「おもしろいゲームが売れないときはプロデューサーがヘボい」──『ケイオスリングス』、『ミリオンアーサー』、『鈴木爆発』安藤武博氏に実況者ksonが訊く、プロデュースのノウハウ “ニコニコ自作ゲームフェスMV作~る放送”第3回
本当に知りたい“怖さ”や“お金”の話──『クロックタワー』、『NightCry』河野一二三氏によるホラーゲーム制作のヒント解説──実況者ksonも登場の“ニコニコ自作ゲームフェスMV作~る放送”第二回
名作アドベンチャーゲームの構造はこうなっている──『428』イシイジロウ氏によるアドベンチャーゲーム制作のヒント解説 “ニコニコ自作ゲームフェスMV作~る放送”第一回
ホラゲにゲームデザインの常識は通用しない!? Jホラーゲームの第一人者『零』×『SIREN』開発者が語り合うホラーの摩訶不思議(柴田誠×外山圭一郎)【ゲームの企画書第八回】