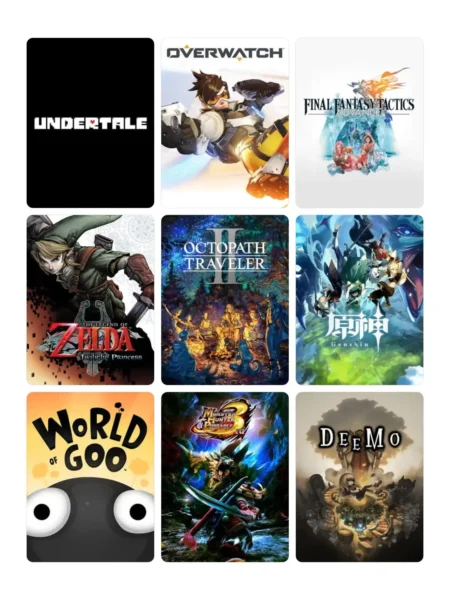「受託病」という言葉を聞いたことはあるだろうか。ゲーム開発会社のあいだで、「納期さえ守ればいい」という考えが蔓延し、モチベーションが低下する現象のことである。
そもそも受託病という言葉は、『ぎゃる☆がん』などで著名なインティ・クリエイツの社長である會津卓也氏(@t_aizu)が、2017年に「Tokyo Sandbox 2017」で行った講演「ゲーム開発とデジタル販売の実態:経験を元に」で使い、話題となったもの。
参考:デベロッパを蝕む「受託病」,その特効薬は“ガンヴォルト”。會津卓也氏が登壇した「ゲーム開発とデジタル販売の実態:経験を元に」聴講レポート(4Gamer.net)
同社はカプコンからリリースされた「ロックマンゼロ」シリーズなどの開発を担当し、国内でも有数の横スクロールアクションゲームメーカーとして知られているが、受託を続けるあまり、2012年に受託病に陥ってしまう。
この状況に危機を感じた會津社長は、自主的に好きなものを楽しく作れるゲーム――すなわち初の自社パブリッシュ作品のリリースを決意する。それが『蒼き雷霆 ガンヴォルト』というタイトルだった。

この『蒼き雷霆 ガンヴォルト』はダウンロード専売ではあったが、全世界累計で18万DLを突破するヒットを記録。ライブ開催やアニメ化、続編の制作、パッケージ版の発売など、幅広い展開を遂げ、受託病を克服する特効薬となった。
――この受託病はインティ・クリエイツに限った話ではない。“最も評価の割れたサバイバルホラーゲーム”としてギネスに登録された『レッド・シーズ・プロファイル』。この作品を手掛けたゲームクリエイター・SWERY氏(@Swery65)もまた、この受託病と闘っていたひとりだ。
SWERY氏は、SNKで『月華の剣士』などを手掛けた後、2002年にアクセスゲームズを設立。受託を行う一方で、自社IPの創造に力を入れ、『D4:Dark Dreams Don’t Die』などをリリースした。現在はWhite Owlsの社長を務めている。

両者は共に海外での知名度が高く、インディーズ方面での活動も行っているなど、受託病以外にも共通点が多い。そこで電ファミでは、ゲームデベロッパーに蔓延する「受託病」に迫るべく、會津氏とSWERY氏による対談を企画。
受託病の実態やデベロッパーならではの苦悩、そして自社IPの重要性などを伺った。
取材、文/クリモトコウダイ

受託病はクリエイターを“スケジュールを守るだけの人間”にする?
――「受託病」という言葉を使い始めたのは會津さんとお伺いしています。まずは「受託病」というのはどんな病なのかを教えていただけますか?
會津卓也氏(以下、會津氏):
ゲーム開発には、大きく分けて自社開発と受託(委託)開発の2パターンがあります。

前者は文字どおりパブリッシャー【※1】が自社内の制作チームなどで開発するものです。後者はパブリッシャーとの協議のうえ、デベロッパー【※2】が開発をするもの。
そしてその後者の場合は、納期の設定が特に厳しくなるんです。「アニメがこの時期に始まるので、この前の月に売りたい」、「3月末が年度末だから、それまでに売らなければならない」といった感じですね。
そのために何が起こるかというと、クリエイターとして納得していなくても、納期が来たら開発の手を止めてフィニッシュさせなければならないことが多々あるんです。
※1 パブリッシャー
ゲーム業界においては、ゲームソフトの販売や広報、製品管理を行う会社を指す。
※2 デベロッパー
ゲーム業界においては、ゲームソフトの開発を行う会社を指す。
――なるほど、クライアントと契約のうえで仕事を請け負っているわけですから、設定された納期を守る必要があるわけですね。
會津氏:
その通りです。契約の約款(やっかん)の中には「遅延損害金」という項目もありますので、往々にしてクリエイターの意図よりもスケジュールが優先されてしまうことがあります。
もちろん受託された側もプロですので、面白いゲームを作り、かつ納期を守るのができて当然であるべきなんですが……スケジュールの厳守に慣れてしまうと、一方で「ゲームが動けばいいんでしょう?」というところまで意識が堕ちてしまうことがあるんですよ。
――スケジュールと引き替えに意識が堕ちる。そんなこと、実際にあるんでしょうか。
會津氏:
最初は、誰しも面白いものを作ろうとゲーム業界に入ってきます。ところが現実には、開発のさなかであっても、「時間が来ました。ここで終わりです」と切られるわけです。しかも何度も何度も。
 |
すると、「良いものは作りたいが、時間で切られる……。だったらどうせ適当に作ってもリリースされるんでしょう?」、「これはこうしたほうが面白いに決まってるけど、そうするとスケジュールが遅れるからやらない」など、クリエイティブな方向ではなく、「どうしたらスケジュールが遅れないか」ということに知恵を使い始め、いつのまにかスケジュールを守るだけの人間になってしまうんです。
そしてさらに悲しいのが……「いま作っているこのゲームは、自分の作品じゃないし」という考えかたになってしまう――これが受託病です。
――……かなり根深そうな病ですね。一方、SWERYさんも前職のアクセスゲームズ【※】で、受託で開発されていたことが何度もあったと思います。同じ悩みを経験されましたか?
※アクセスゲームズ
日本のゲーム開発会社。設立は1996年で、当時は映像開発部門だけだったが、2002年に社名をアクセスゲームズに変更。同時にゲーム部門が設立された。受託で『機動戦士ガンダム 戦場の絆ポータブル』や『ACE COMBAT X Skies of Deception』に携わるほか、『D4: Dark Dreams Don’t Die』といった自社IPもリリースしている。
SWERY氏:
これまでの職場では、僕も會津さんが言う受託病に悩んでいました。

受託病には他にも、リテイクに対してネガティブになるという現象があります。そもそもリテイクとはゲームをよくするための行為のはずですが、その分スケジュールが遅れてしまいますからね。
そこからもっと受動的になると、クライアントの指示が良いのか悪いのか判断せず、言われたことをただやるようになってしまいます。
會津氏:
「どうせ先方が判断して、駄目なら言ってくるし」ってなってしまうんですよね。どんどんクリエイティブな部分が削がれ、機械的になっていく。
もちろん100%機械的にはならないですよ。そうなるとゲームなんて作れませんから。ただ、「この子ならもっと凄いものが作れるだろう」と思っていても、その子が自分自身でリミッターを掛けてしまうので、指示する側からすればとても残念な気持ちになってしまいます。
SWERY氏:
これ、受託病にも関連することだと思うんですけど、社内のやりとりで「発注」という言葉を使う人っているじゃないですか。
 |
使いやすい言葉なんですけど、「企画チームから発注があったんでこれを作りました」って言われると、「あれ、孫請けが発生した!」って思っちゃうことがあって。個人的なこだわりですが、発注という言葉がキライなんですよ。
會津氏:
それは私もありますね。まだ現場にいたころに、「指定書」と「指示書」という呼びかたがあって、どちらの名前を使うかで議論したことはありますね。「お前に指示される筋合いはない! 指定書やろって!」って(笑)。
SWERY氏:
「指示書を下さい」と言われると、「指示がないと動けんのか……」と思ってしまいますしね。もちろんアウトソーシングする場合は指示は絶対にするべきことですけど、「ええ……社内やん」と思うことはあります。
 |
もちろん指示書も書きますが、「ここはお任せ」と書くことは多いですよ。「ここは才能を発揮してください」と(笑)。
會津氏:
仕様書を細かく書く人がいますが、あまりに細かすぎるとどこが重要かわからなくなりますよね。だから「ここは絶対に外さないで!」という部分だけ詳しく書き、「あとはお任せ」というのもいいかもしれませんね。
“デベロッパーのロゴを隠す”ことでゲームが売れる時代があった
――受託されたゲームは、プレイヤーから見れば「外注されたゲーム」ということになります。プレイヤーから、“外注=できが悪い”という声を聞くことがありますが、そこには受託病が関係しているんでしょうか。
會津氏:
一概には言えませんが、その可能性はあります。ただ、“外注=できが悪い”というのは、昔のイメージがそのままになっているという気もしますね。
 |
ゲームには出せば売れていた時期があり、クオリティーよりも本数が優先されていたこともあったんです。ファミコンやスーパーファミコンの時代ですね。
SWERY氏:
その結果いろいろな会社が外の会社を使うようになり、クオリティコントロールができなくなりました。ですが、もうそんな時代は終わっていて、90年代ぐらいから価格競争と技術競争の時代に突入しています。ちゃんとしてないとデベロッパーは生き残っていけません。
それから20年以上経ちましたけど、一部には当時の感覚が残っていると思います。
會津氏:
最近は変わってきていますよね。パブリッシャーがデベロッパーの名前を出すようになり、プレイヤーの皆さんがデベロッパーの存在を意識するようになっていったんです。
 |
その結果、「ちゃんとデベロッパーを表記したほうがいい」という風潮はできつつありますね。今は日本に比べて海外マーケットのほうが元気あるので、彼らの風習が浸透してきたという背景も関係しているでしょう。
――たしかに、近年は「デベロッパーがここだから面白いに違いない」という意見も多く聞きます。そうなると、そもそもなぜパブリッシャーたちはデベロッパーの名前を出さなかったんでしょうか。
會津氏:
一概には言い難いですが、一つは先ほど話にあった「内製か外注かでのイメージの違い」ですね。
「外で作っているものは買わない」という意識がプレイヤーの皆さんにあったわけですから、作品に外注先のロゴや権利表記が書かれていたらバレバレですよね。
SWERY氏:
僕は実際に言われたことがありますよ。有名な某タイトルのお手伝いをしたとき、「ゲームはパブリッシャーのロゴを出すことで売れる。だからデベロッパーのロゴは隠したほうがいいんだ。そちらにとっても、そのほうが得でしょう?」って(笑)。
 |
會津氏:
ありそうな話ですね。それにプラスして、権利の問題があると思います。パブリッシャーさんの多くは、社内でゲームを作る文化を持ったまま大きくなってきました。つまり、権利を100%持っているものを自社で売ることで成長してきたわけです。
ところが、先ほどの話にあったとおり、そこに外部のものがやってきます。これは想像にすぎませんが、「内製品と外注品にあるいろいろな差をどちらに合わせるか」という話になった時に、内製に合わせることになったんだと思います。
その結果、たとえ外部が手掛けた作品であったとしても、パブリッシャーの製品として売られるようになったんでしょう。
――確かに当時のことだけを考えると、「デベロッパーのロゴを隠したほうが売れる」というのは一理ある気もします。
會津氏:
当時のカプコンさんの製品ではデベロッパーのロゴはあまり出ていなかったのですが、弊社は出していただけていたんですよ。
すると、ロゴが出ているので、誰から見ても「あの時、あのゲームを作っていた会社だ」ということが分かるわけですよね。権利は残りませんでしたが、実績は残ったわけです。
 |
従来は自分から「あれを作りました」と言わないと広まらなかったものが、ロゴ一つ出すだけで自分たちの未来の資産になったんですね。
だからあの当時はロゴを出さないほうが売れたかもしれませんが、出していただけたことにより、今の我々があるんです。
――目先のことだけではなく、先行きのことを考えると大きな転換点ですね。
SWERY氏:
僕も最後までロゴを出すことにはこだわってきましたね。デベロッパーって、認知されないと食べていけないので、自社IP【※】やクリエイティブな面でのオリジナルIPを目指しているなら、絶対にロゴは出したほうがいいです。
 |
※IP
知的財産。Intellectual propertyの略で、オリジナルのキャラクターなどを指す言葉。
會津氏:
本当にその通りだと思います。名前を出すことにより手を抜けなくなりますしね。手を抜くとバレちゃいますから。「どこどこのゲームだけど、作ったのはあのデベロッパーで、あそこのゲームは面白くないよね」と言われちゃうわけじゃないですか。
そう言われてしまうのは嫌だったし、自分たちの作ってるものには自信も誇りもあったので、ロゴだけは出してもらうようにしています。出すことにより「手抜きにはなりませんよ」という約束にもなりますしね。
――たしかにインティ・クリエイツさん【※】は、よく横スクロールアクションゲームなどでロゴを拝見するので、「横スクロールアクションが得意なんだな」という印象があります。
※インティ・クリエイツ
日本のゲーム開発会社。カプコン出身のクリエイターが1996年に設立し、「ロックマン ゼロ」シリーズを手掛けるなど、横スクロールアクションゲームの開発に定評がある。2014年には初の自社パブリッシュ作品のリリース『蒼き雷霆 ガンヴォルト』をリリースする。
會津氏:
「こういうものを作れる会社はありませんか?」という相談が私の知人に行き、その知人が「ああ、その内容なら」と紹介してもらうということも実際にありました。それも含め、「こういう内容だからインティ・クリエイツに依頼したい」という件は増えてきましたね。
 |
SWERY氏:
そのあたり、凄く成功されているというか、ブランディングができていますよね。
初めてのお店で「ここの一番のオススメはなんですか」と聞きますよね。その時に「これです」って言えるのは強いと思うんですよ。前職の場合はそれを「フライト」と「アクション」と決めていました。
 |
White Owls【※】に関しては、「人がやらないことをなんとかしたい」、「あなたのためのゲームですよ」というものを目指しています。でもこれって、「あなた」が「プレイヤー」だから、対パブリッシャー向けではないんですよね……ですのでパブリッシャー探しには苦労しています(笑)。
※White Owls
『D4:Dark Dreams Don’t Die』や『レッド・シーズ・プロファイル』を手掛けたSWERY氏が、2016年に立ち上げたゲーム開発会社。現在、オリジナル企画第一弾『The Good Life』の開発が進められている。
會津氏:
(笑)。実はウチでも受託でいろいろなジャンルのゲームを作っていたのですが、公式サイトにも会社概要にも、あえて横スクールアクション以外は載せていないんです。それを10数年続けています。ただし、『ぎゃる☆がん』【※】だけは自社IPなので別ですが。

――だからこそ、3Dシューティングの『ぎゃる☆がん』が発表されたときは驚きました。
會津氏:
『ぎゃる☆がん』までは、あまりにも横スクロールアクションという色が強すぎて、2Dのもののオファーが中心になり、今のミドルウェア【※】を使ったものであるとか、3Dで「マテリアルが何々、ウエイトが何々、ボーンはいくつだ」みたいな作りかたに縁遠くなっていたんです。
そうすると、技術的な研鑽というか、自分の発展に前向きな社員が辞めていってしまうんですよ。
※ミドルウェア
コンピュータ用語。OSと個別のアプリケーションとのあいだを受け持ち、媒介的な処理を行うソフトウェアのことを指す。
SWERY氏:
なるほどなるほど。「同じのばっかりやんけ」と。
會津氏:
それもありますし、辞めないまでも社員たちのモチベーションが下がっていくんです。
それを防ぐには「先端技術をやりますよ」という姿勢が必要で、そういう視点から周りに置いていかれないために作り始めたのが『ぎゃる☆がん』になります。

ですので、弊害として「弊社は横スクロールアクションが強いメーカーです」と打ち出したがために、そういった開発現場のモチベーションが下がるという悪影響が出てしまっていたんです。これも受託病の症状の一つですね。
――突然の『ぎゃる☆がん』には、そういう深い理由があったんですね。