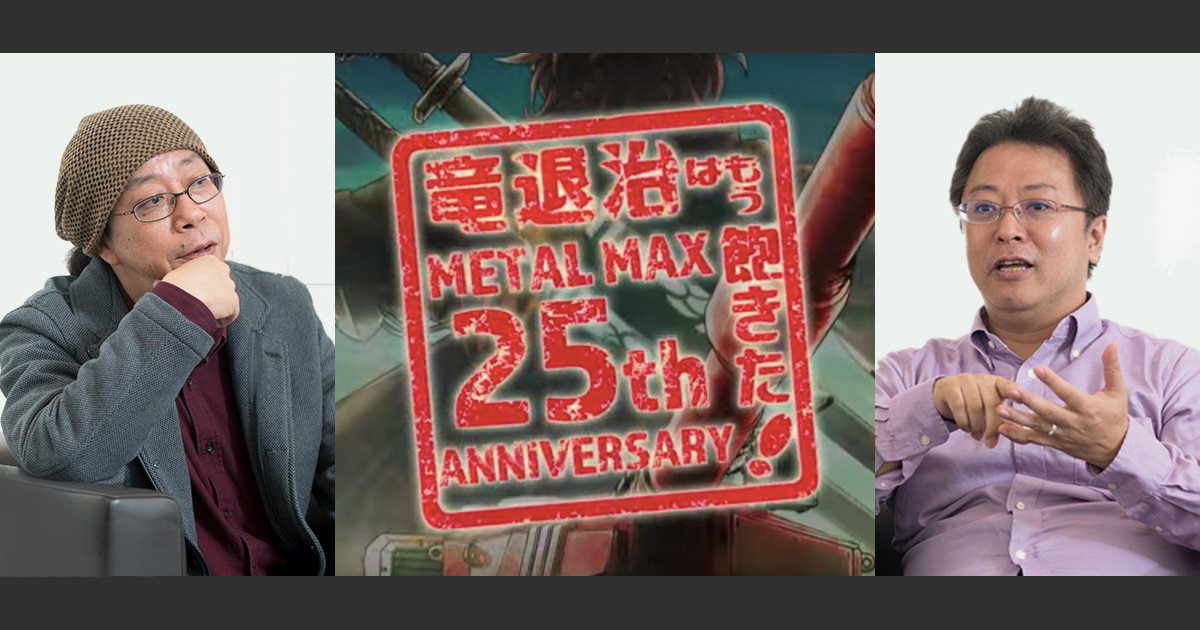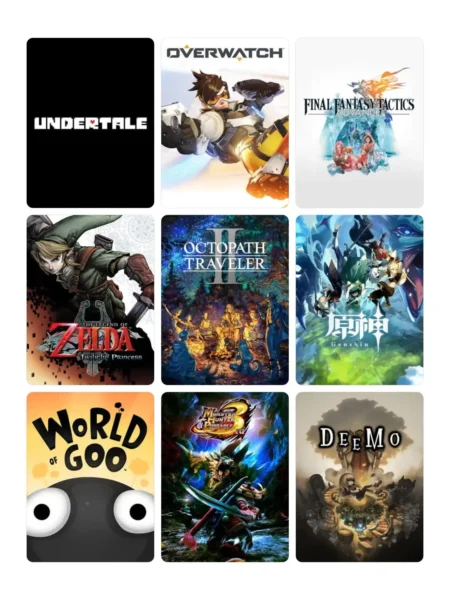そして『メタルマックス』の始まり
──長い前フリを越えて、ここからは『メタルマックス』の話になります。最初は『メタルマックス』というタイトルもついておらず、「とにかくゲーム作ろうぜ」と始まっています。その制作のキッカケはわたしも覚えていないんですが、いったい何だったんでしょう? 広告代理店からの依頼ですか?
宮岡氏:
ぼくは『ルーンマスター』を完成させられなくて、「やっぱり自分にはゲームデザイナーは無理なのか……」と思っていたの。
いちばんの理由はプログラムがわからないから。たとえばプログラマーが逃げたときに、その尻を拭く能力がないわけだよ。
ぼくにわかるのはBASICまでで、そこから先のことはわからない。覚えようとはしたけどね。
 |
……と思っていたら、昔の知り合いから「ゲームを作りたいと言っている会社があるんだけど、宮岡さんやってみない?」という話が来て、「じゃあ、最後にもう1回だけチャレンジしてみるか」と。
──ラストチャンスのつもりだったわけですか。
宮岡氏:
そう。「これをやってダメだったら、完全におれには向いてないってことだよね」という感じだったよ。そうであったにもかかわらず、データイーストの社長を前にしたプレゼンで、広告代理店の担当者は「宮岡寛というのは日本で五本の指に入るゲームデザイナーです」って言ってくれちゃってさ。
──ぶわははは! まったく広告屋さんってホラ吹きだなー(笑)。ともかくそれで「やりましょう!」ということになって、わたしも宮岡さんから「一緒にやんない?」と誘っていただいたんですよね。
そして、このことは過去にも『メタルマックス』攻略本のインタビューなどで語っていますが、最初はボードゲームを作ろうという話でした。
宮岡氏:
そう、「あまり予算がかからなくて、売れそうなものを」というようなオーダーがあったからね。
──あのころ、すでにさくまさんの『桃太郎電鉄』がヒットしていましたから、それをお手本にはしましたよね。
Nintendo Switch版の話も飛び出した! 6年振りに復活した『桃鉄』という唯一無二なゲームのすごさとは?
宮岡氏:
それもあるけど、あのころはほかに『鉄道王』というゲームもあって、まあ、そんなようなものをイメージして、「作るとしたらボードゲームかねえ」なんて話をしていた。
──いまなら違うと解るんですけど、あの当時は「ボードゲームだったらわりと簡単に作れるんじゃないか?」なんてタカをくくっている部分はありましたよね。
宮岡氏:
まあね。「RPGほど大変じゃないだろう」とは思っていたな。
──なのに、いろいろとアイデアを練っていくうちに、どうしてRPGを作ることになっていったのか。その経緯は当然わたしも知っていますが、できれば宮岡さんの言葉で聞かせてください。
宮岡氏:
そこは、あまり覚えていないんだよね。ただ、途中から「売れないわけにはいかない」という話になってきたんだ。
最初のうちは「ちょろちょろっと儲けようぜ」という感じだったのが、そのうち「会社としてはヒットしてもらわないと困る」という話が聞こえてきて。
 |
「ボードゲームは売れるのか?」なんて追求されても、「いやあ、どうでしょう……?」なんて言葉を濁したりして(笑)。
──そりゃ、作ってみないことにはわからないですよねえ。
宮岡氏:
それで、「どうしても売りたいならRPGにするしかないかもなあ」という流れだったと思うんだよね。
──わたしが当初のアイデアで記憶しているのはですね、ボードゲームのスタイルで、プレイヤーが陣地を取って領土を拡げ、遠くの土地で安く仕入れた資材を運搬して、こちらの土地へ高く売りさばいて……というような感じだったじゃないですか。
そこで「運搬に使うのは鉄道よりもトラックがいいな」ということになり、「運搬中の資材を奪う野盗なんかが出てくるだろうから、それに反撃するための武器を積んで、改造して……」という流れでしたよ。
宮岡氏:
わっはっは。ホント、それ?
──何を言ってんですか。「トラックに大砲つけようぜ!」って言ったの、宮岡さんじゃないですか。
 |
宮岡氏:
そうだっけ(笑)。「ロボットものとかも面白いな」とは思っていたんですよ。トラックでもロボットでも、人間が何かに乗って戦う。そうすると「『ドラクエ』とも差別化ができるし、新しいゲームとしての売りになるんじゃないか」とね。
──でも、以前『メタルマックス2』の攻略本を作ったときに宮岡さんへインタビューをしたら、「乗り物で戦うことがやりたかったけど、ロボットにはしたくなかった」って仰っていましたよ。
宮岡氏:
そう、そこがいちばん悩んでいたところだったんだ。アニメでもゲームでもあのころはロボットものが多かったから、「オリジナリティを出すにはロボットではダメだろう」というのは解っていた。
そこから、「現実にあるもので、武器が載せられて、改造もできるもの」ということで戦車になっていったんだね。
──そんな経緯もありつつ、正式にデータイーストからの承認を受け、『メタルマックス』のプロジェクトがスタートするわけですが、さて、ここにあらためて田内くんが登場してきます。
田内氏:
わははは。やっと呼ばれました。
 |
──データイーストで『メタルマックス』の開発がスタートしたとき、社内のスタッフはどのようにして編成されたのでしょう。田内くんは新人だったんですよね?
田内氏:
わたしは当時まだ1年目で、ゲームが作りたくて入社したのに、なぜか電子手帳の担当になっちゃったんですよ。
それでもなんとか仕事はしていたんですが、結局、その電子手帳の企画がポシャってしまって、手が空いていた。
そのときに課長の机の横を通りかかったら、『メタルマックス』の企画書が置いてあったので勝手に読んでいたんです。
──あー、悪い社員!
田内氏:
そうしたらそこに課長がやってきて、「どう? 面白そう?」って、とくに怒られることもなく感想を訊かれて。
「面白そうです!」、「やらせてください!」って自分を売り込んだところ、プロジェクトに参加させてもらえることになりました。
──プログラマーにはその課長と、田内くんと、あと同期の福島純くんもいたでしょ。
田内氏:
福島くんは最初から『メタルマックス』をやることになっていましたね。当時、彼と話していたんだけど、データイーストとしては『メタルマックス』は会社全体で力を入れていて、「これが売れなきゃもうダメ!」くらいのタイトルだった。
表向きには課長がプログラムのエースなんで、課長が先頭に立って『メタルマックス』をやっているという感じだったんですけど、課長は本当は別のゲームで忙しく、実質『メタルマックス』を作っているのは、ゲーム制作経験のないわたしと福島くんだったんですよ。
──うわっ、新人ふたりの肩に社運が(笑)。
田内氏:
これはわたしの推測ですが、おそらく反発心があったんだと思うんですよ。
それまでデータイーストは社内企画だけでやってきた会社なのに、「ここにきてなんで外部の持ち込み企画なんかやるんだ。そんなものに社内のエースなんか使ってられるか。新人で十分だろう」みたいなね。
──その気持ちはわかります。ここで宮岡さんにお訊きしますが、『メタルマックス』を作り始めたときの気持ちというか、「こういうものにしたい」という想いは、どんなものだったんでしょう?
 |
宮岡氏:
まあ、徹底的にこだわっていたのは「誰もやっていないことをやる」ということだよね。もっと言えば、『ドラクエ』がやらないことをやる。
──わかりやすいです(笑)。
宮岡氏:
方向性として、『ドラクエ』的なものは『ドラクエ』に任せたいと思っていた。要は「RPGの面白さは『ドラクエ』の面白さだけじゃないはずだ。もっとほかの面白さがあるはずだ」と。だからぼくは『ドラクエ』が行かない方向へ行こうと。
田内氏:
それでファンタジー路線じゃなかったんですか?
宮岡氏:
うん。いわゆる “神様に導かれた勇者がお姫様を助けて世界を平和にする”というようないい話は、まあ『ドラクエ』でやってくれと。「こっちはそういうんじゃない話をやるよ」と。
それで徹底的に「勇者じゃない」、「そこらの町工場のダメ息子」という設定にして、そいつがそんな気もなく世界を救っちゃう話にした。

(画像はメタルマックス プレイ映像より)
結局、主人公にしてみれば自分が最強になることが目的であって、「世界を救いたかったわけじゃないんだよ」という、ひねくれた話になったんだよね。
それは『ドラクエ』という王道に対するアンチテーゼというところで根本を考えていたから。
──そういう発想はプレイヤーから共感を得られると思いましたか?
宮岡氏:
いやあ、そんなこと考えていなかったね。やっぱり「自分で作りたいものを作る」ということに一所懸命だったから。だって、完成させられるかどうかもわからなかったんだから。
ただ、「自分のイメージどおりのゲームが作れれば面白くなるに決まっている」という、根拠のない自信だけはあったかな。でもそういう自惚れのない人間は、そもそも作家になろうなんて思わないわけで。
RPGだけどロールプレイをする必要はない
──徹底的に『ドラクエ』的な王道から外れていこうと決めた『メタルマックス』で、そのとおりにできた部分と、「やっぱり堀井さん正しかったな」という部分があったと思います。実際にはどういったものがありましたか?
宮岡氏:
えーと、ぼくの場合、基本のRPG作法は完全に堀井流です。
だから『メタルマックス』って「竜退治はもうあきた。」とキャッチコピーで言っているけど、やっていることは『ドラクエ』なんだよね。
たとえばダンジョンの中に分かれ道があるとしたら、その先には必ず宝箱が置いてある。ぼくは自分がプレイヤーだという気持ちで作るんで、長い分かれ道の先に何もないとムカつくんですよ。
だから、プレイヤーが手間をかけたら、その手間に見合う対価を用意しておきたくなる。
──行き止まりには何かしらのご褒美があるわけですね。
宮岡氏:
宝がないなら、情報を置く。あるいは思わぬ抜け道があるとか。何かが得られるようになっているというね。
だから、そのへんの「頑張ったら報われる」というのは“堀井流ゲームづくり”の基本だと思っているんで、そういう意味ではまったく堀井さんの流儀に従って作っている。
話とかがひねくれているだけで(笑)、RPG作法というか方法論としては、堀井さんのまんま。
──なるほど。ほかにも堀井流というのはありますか?
宮岡氏:
いっぱいありますよ。たとえば「世界は変わるべきじゃない」とか。
それはつまりRPGという世界の中ではパラメーターは自分だけなの。
──パラメーターは自分だけ?
宮岡氏:
変化するのは自分だけで、世界は変わらない。変わらないからこそ、自分が変わったことがわかる。
自分に合わせてスケーリングして強くなるRPGってあるじゃない? そうすると、どこへ行って戦っても、ほどよい歯応えはあるんだけど、自分が強くなったという実感は得られない。
そうではなくて、さっきまでムチャクチャ苦戦していた敵にレベルを上げてから再挑戦したら楽勝だった。
そういう体験によって自分が成長したことがよくわかる。「世界は変わるべきじゃない、変わるのは自分なんだ」というのはそういうこと。それは当時聞いて「へえ~」と思った。
──いまなら当たり前のことにも思えますけど、堀井さんが『ドラクエ』の1作目の時点でそういう考えを持っていたのがすごいですね。
宮岡氏:
あと「同じことは3回言え」とか。
──あはは、それはわかります。
宮岡氏:
漫画でもそうなんだけど、読者はセリフなんて覚えていないんですよ。10ページも前のことになると覚えていないから、そのセリフが伏線になっていても機能しない。
ゲームの場合も同じで、「北に行ったら洞窟があるよ」というのは、ひとりだけに言わせてもプレイヤーは忘れるから、いろいろなところで言わせないとならない。
──「大事なことなので2回言いました」みたいな。
宮岡氏:
そうそう。けっこう微に入り細に入り、堀井流というのがあるんですよ。やっぱ堀井さんは頭がいいんだよね。天才だと思いますよ。
──『メタルマックス』の戦闘画面って、横から第三者が見ている視点構成ですよね。それは『ドラクエ』よりも『ファイナルファンタジー』的だと思うのですが、それを選んだ理由はなぜでしょう?

(画像はニンテンドー3DSダウンロード版『メタルマックス』より)
宮岡氏:
戦闘画面が横になっているのは、イマ風に言えばTPS視点【※】に近い考えかたからですね。
※TPS視点
サードパーソン・シューティングゲーム(Third Person Shooter)と呼ばれるジャンルのゲームに特徴的な画面構成で、プレイヤーキャラクターをやや後方から追尾する第三者の視点のこと。
『ドラクエ』の場合は自分たちは人間だけど、『メタルマックス』では戦車に乗っていることもあれば、戦車を降りて歩いてることもある。戦闘中も乗り降りすることができるしね。そういった様子をひと目でわかるようにする必要があったわけ。
もっと言えば、苦労して手に入れた戦車が大砲を派手にぶっ放すところは見たいじゃない? そういう欲望もあるだろうというのは感じていたから。
──確かに、それは見たいです!
宮岡氏:
当時のファミコンの表現力を考えると無茶な望みではあったんだけど、何よりもまず画面写真を見た瞬間に『ドラクエ』とは違うものだっていうのを解らせたくてさ。それで、自分たちの姿を見せる形に落ち着いたの。
あの当時『ドラクエ』は、世界最高水準の記号表現を実現したゲームだったはず。それを出発点として、より記号表現を洗練して行くのではなく、よりリアルなビジュアルに近づけたいという願望があったわけ。
すでに『ファイナルファンタジー』が似たような戦闘画面で上手い見せかたをしてくれていたから、それは参考にさせてもらいました。
──なるほど。少しゲーム内容に踏み込みますが、システムで特徴的なレンタルタンクについても、ちょっと聞かせてください。
開発していた当時、レンタルタンクがわたしのゲーム哲学と合わずに、ずいぶん宮岡さんと衝突した覚えがあります。「借りないと大破した戦車を回収しに行けないのはシステムとして穴がある」というのがわたしの主張でした。
結果としては、レンタルというシステムが遊びの幅を拡げてくれたわけで、「それが正解だった」といまなら理解できるんですが、当時わたしを説得したように(笑)、もういちど宮岡さんの言葉でレンタルタンクの利点を説明していただけませんか。
宮岡氏:
うん……冷徹に言えば、レンタルタンクっていうのは論理的に「ハマる」可能性を排除するために必要なシステムだったってことだよね。戦車を何台持っていたとしても、そのすべてが自走不能になったら戦車を回収することができなくなってしまうから。

(画像は『メタルマックス』Wii版公式サイトより)
あの仕組みを最初に思いついたのは桝田(省治)くん【※】だったと記憶しているけど、ぼくはそのアイデアを聞いた瞬間に「面白そう!」って思った。
レンタルタンクという言葉がレンタルビデオを連想させる点もよかったね。
我々がビデオを借りるように、この世界のハンターたちは戦車を借りるのかもしれない。
我々が肌感覚で直感できる仕組みの中に、現実では絶対にあり得ないことが落とし込める。そういう点がすばらしいと思った。

──ええ、そう言われたらもう賛成するしかありません(笑)。
宮岡氏:
それと同時に、レンタルタンクの仕組みがあれば、プレイヤーは安心して無茶ができるようになるんですよ。ウォンテッドのモンスターと戦って全滅するリスクが致命的なものにはならないって保証されるから。
それどころか、どうせ死ぬなら最初からレンタルタンクでウォンテッドと戦えば、リスクなんかないに等しくなる。つまり、「遊びかたの幅が拡がる」と直感したんだ。
──実際、わたしもプレイヤーとして『メタルマックス』を遊ぶときには、レンタルタンクを借りまくりました。
宮岡氏:
レンタルタンクにはもうひとつ利点があって、普通のプレイヤーなら絶対に作らない変な戦車を“既製品”として見せられるんですよ。
武器など積まずにひたすらSP(耐久値のようなもの)を増やした回収専用の“防御型戦車”とかね。
それが発展して、『メタルマックス3』以後のレンタルタンクは、「こんな無茶なカスタマイズもできるぜ!」という見本展示場みたいな役割も果たしてくれた。
装備や性能の意外な組み合わせを見せることで、たとえばドリルだらけの戦車でプレイヤーを笑わせることもできるし、戦車をカスタマイズするときに「こんな考えかたもあるよ?」と“デッキ構築のヒント”を提示することができるから。
──もうひとつ。これも『メタルマックス』を遊んだ人が最初にびっくりするところだったと思うんですが、主人公が、とうちゃんと会話して“引退”を選ぶと、いつでもエンディングに行けてしまうじゃないですか。これもかなり掟破りのアイデアで、堀井流とはかけ離れた部分だと思うのですが……。
宮岡氏:
『メタルマックス』はね、大雑把に言えば敵を倒す、あるいは逃げ出すことさえできれば、先へ進んで行けるゲームにしたかったのね。
「強くなれ。力こそすべての世界だから」というのをモットーにして、成長するというその一点にプレーヤーの気持ちを集中させたいと思っていた。
ファンタジーにありがちな“神様のお導き”が存在しない世界を表現したかったからね。
そういう考えの延長線上に引退がある。
──強くなる自由があるけど、やめる自由もある。
宮岡氏:
そう。『メタルマックス』の主人公は“運命(さだめ)”に導かれた勇者ではない、ということ。高貴な血筋を引く若者が、下々の世界を流浪しつつ英雄になっていくという貴種漂流譚は、古くからいろいろな物語の中で語られてきたパターンのひとつなんだけど、『ドラクエ』以前からぼく個人としては、ずっとその貴種漂流譚の“貴種”の部分に引っかかりのようなものがあった。
たとえば『スター・ウォーズ』でも、普通の若者に見えていたルークがじつはジェダイの血筋を引く存在であって、ダース・ベイダーと血族だったっていう話になるでしょう?

(画像はスター・ウォーズ公式サイトより)
「彼がヒーローになるのは彼がヒーローの血筋だから」という背景説明が、ぼくにはどうにも“つまらない”ように感じられて。
──近年に公開された新作では、そのへんの設定でいろいろと物議を醸しましたね。
宮岡氏:
高貴な血筋などひとかけらも入っていない、そこらの修理屋のバカ息子が、たいした覚悟もないままに世界を救う。「だから面白いんじゃないの?」と。
主人公はただの普通の人だから、ふとしたはずみでモンスターを倒すのに嫌気がさして、引退したくなっちゃうかもしれない。
でも、引退するときだってたいした決意があるわけではなくて、平穏な暮らしに飽きたらまたハンターに戻ったりするかもしれない。
──それはゲームを遊んでいるプレイヤー自身と重なる気分ですね。
宮岡氏:
「『メタルマックス』はRPGだけれども、ロールプレイする必要はない。なぜなら、このゲームの主人公はあなた自身だから」。ぼくはそういう思いを込めて“引退”という仕組みを作ったんです。
──ハマる人がとことんハマるのは、「他人の話じゃない、自分の話だから」という、『メタルマックス』の魅力の根底が理解できるひと言ですね。