ファンタジーを描きたかった理由
──そもそも真島先生は、なぜファンタジーを描こうと思ったんですか?
真島氏:
もちろん僕自身、ゲームも含めたファンタジーが大好きだったのもあります。けれども、僕が『RAVE』を連載しはじめたとき、“「週刊少年マガジン」にはファンタジー漫画がなかった”というのが大きくて。
「これまでにないものをやりたい」という思いと、ファンタジーが隙間産業的にヒットするんじゃないかという考えがあったんです。
でも、いろんな人に「『マガジン』でファンタジーは受けない」と反対されて(笑)。
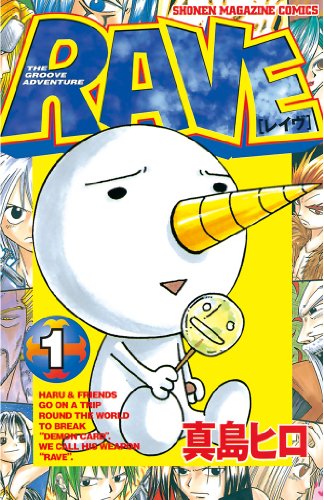
なので、「マガジン」でファンタジー漫画を成功させるためにどうしたらいいかを考えたのですが──そこで「王道の少年漫画をやるしかない」という結論になったんです。
今だから言えるのですが、当時、本当はそういう王道の少年漫画をやりたいわけじゃなかったんですよ。けれども、このときそうした少年漫画のやり方というか、“「マガジン」らしさ”というのを当時の担当編集に叩き込まれたことは、今に繋がっていますね。
中山氏&小高氏:
へー!
小高氏:
当時、『RAVE』はファンタジーとしてすごくすんなり読めたというか、「マガジン」から浮いているなんて、全然感じなかったですね。
真島氏:
日頃ゲームをしている層は、ファンタジーの文法に対してまったく違和感がないんですよ。
でも、当時「マガジン」を読んでいた人は、ファンタジーのなんたるかなんてまったくわからない人たち。だからこそ、細かい話で言うと「主人公の名前は、普通の日本人でもわかる名前にすべき」みたいなレベルからこだわりました。
 |
……その意味では、ファンタジーのイメージの基盤にもなっている『ドラクエ』がなかったら、そもそも今の僕はなかったとは思います。
小高氏:
「日本のファンタジーそのものが『ドラクエ』から始まっている」と言っても過言ではないですからね。外国だともともとファンタジーが好きだったりするけど、日本に“剣と魔法の世界”を広めたのは間違いなく『ドラクエ』だと思います。
でも思い返してみると、確かに、あの頃の「マガジン」にはまったくファンタジー作はありませんでしたね。
──むしろ、「マガジン」にどういうイメージを持っていますか?
小高氏:
僕はもう、中学生のときに読んでいた1990年代のヤンキー漫画のイメージが強いです。『カメレオン』とかの時代。
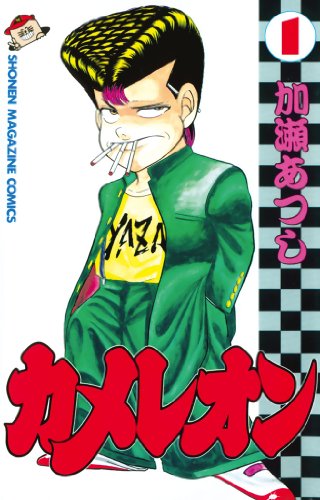
真島氏:
当時はヤンキー漫画全盛期で、『特攻の拓』とか『湘南純愛組!』がありましたね。僕が「マガジン」で描きたいと思ったきっかけも、そうしたヤンキーものに惹かれたからでした。
──そうなんですか、ちょっと意外ですね。
中山氏:
僕は『金田一少年の事件簿』がすごい好きだったので、そのイメージが強いですね。中学生のときに初めて模写した漫画が「金田一」だったので、思い入れも強いです。当時、「金田一」の眉毛だけ変えた主人公と、死体を食べるヒロインの漫画を描いてました(笑)。
一同:
へぇー!
マガジンらしさと「陰」と「陽」
──ちょっと話が戻りますが、先ほどの「マガジン」らしさをすごく叩き込まれたというのは、具体的にどういう内容だったのでしょう?
真島氏:
もちろん当時の「マガジン」の話なので、今は違うと思いますけれど──まず徹底的に「主人公を立てる」というスタイルですね。少年漫画でよくある「仲間キャラの誰々が敵の幹部と戦う」みたいな展開も、けっこうアツいシーンだと思うんですが、当時は主人公がきちんと立つまでは極力やらない方針でした。
 |
中山氏:
ああ、真島さんの作品を読んでいると、本当に主人公が「少年」としてまっすぐだなという感じを受けます。
真島氏:
僕は、それがとにかく大事なことだと思っているんですよね。
あとは、とにかく「感情を描け」ということ。特に言われたのが、「ファンタジーの世界は一般の人たちには行ったことがないからわからない。こんな生物はいないし魔法も使えないし剣もない。だけど、キャラクターの感情だったらわかるでしょ」と。
──当時、ファンタジーが隙間産業だったところから始まって、今や真島さんのファンタジー作品は「王道」と言われるようにまでになっています。ある意味、“「マガジン」らしさ”に忠実な作品づくりを積み重ねてこられた結果なのかなと、お話を聞いていて思いました。
真島氏:
漫画に「陰」と「陽」があるとしたら、僕の漫画は「陽」なんです。だから、代々の編集長からは「マガジン」での「陽のファンタジー漫画」と言われていて。
でも、本当は僕は「陰」も大好きなので、描きたい気持ちはめちゃくちゃあるんです(笑)。でも、「陽であることはブレちゃだめだ」「陰は他の作品に任せよう」という話になるんですよ。それで、見ようによっては恥ずかしいくらいに、まっすぐな少年漫画を今も描いているんです。
……その意味では、お二人の『ギャンブラーズパレード』は本当に羨ましいんですよ(笑)。
 |
中山氏:
ええっ、そうなんですか?
真島氏:
すごく羨ましいし、あんな尖ったキャラは、僕には絶対に描けないんですよ。
ある意味、長く続いている少年漫画雑誌である由縁でもあるとも思うんですけれど──「マガジン」って「こういうキャラクターだったら読者に嫌われない」みたいな、保守的なデザインが多いんですよ。
僕の漫画もそのひとつかなと思うんですが。
──なるほど。
真島氏:
でも、『ギャンブラーズパレード』はその中で、小高さんらしい独特のキャラクターと中山さんのデザインで異彩を放っていますよね。
そうしたあんまり少年誌っぽくないというか、「別マガ」に載っていたほうがもしかしたらヒットするような作品かもしれないものを、あえて週刊の方の「マガジン」の方で連載しているというのは、すごく意味があることだと思います。
たとえば「イケメンですよ、だからかっこいい」というキャラクターよりも、「こんな尖ったキャラですよ、でもかっこいいでしょ」というものは全然違う質のものというか。
『ギャンブラーズパレード』は後者の作品ですよね。
中山氏:
ありがとうございます、本当に恐縮です……。
 |
真島氏:
だから“「マガジン」らしさ”は要らないし、おふたりには今後も尖ったスタイルでいってほしいと僕は思いますね。『ギャンブラーズパレード』は「マガジン」の中でも、最高に尖った作品で、だからこそいいと思ってます。
──それにしても、真島先生自身が本当はそうした「陰」の方も描きたいというのは、とても意外に感じられます。
真島氏:
僕自身はそういう作品が大好きなんですよ。『ダンガンロンパ』もそうですしね。けれども、少年誌で連載しているという事情もあって、たとえば「Z指定のゲームをやっている」なんて、SNSでもあまりおおっぴらには言えないんです。実際、ダークファンタジーみたいなものもいつかやりたいなとアイデア自体は温めています。
──逆に、そうした気持ちもありつつも、何十年と連載を続けられてくる中で、真島先生自身が「“マガジン”らしさ」を担っているといいう心境はあったのでしょうか?
真島氏:
うーん、そういう気負いはありませんけれどね(笑)。でも、僕は森川ジョージさんとけっこう仲良くさせてもらっていて、あの人こそ「マガジン」のド中心なわけですよ。
でも、実力もキャリアもすべてが王様なあの人に「後は任せたよ」みたいなことをよく言われていて──まあ、そういうことも含めて「頑張らなきゃな」という気持ちはあります。
 |
でも確かに、長いこと漫画を描いていると、時折、何を描くべきか迷うときがある。でも、そのときに常に考えるのが「自分が描きたい」よりも「読者が見たい」を優先するということなんです。
読者の反応であったり、今の漫画の風潮から“この展開は好まれる・好まれない”とかだったり……そうした感覚を研ぎ澄まして考えるんですよ。
──それはたとえば、自分の中で「こういうものが描きたい」というものがあったとしても、読者の見たいものを優先するということですか?
真島氏:
最終的には、迷ったら絶対に「読者が見たいと思う」ほうを選ぶようにしています。
本当にまったく意識しなかったら、インディーや同人と変わらなくなっちゃうし、プロとして意識しないわけにはいかないですよね。やっぱり、僕は作品を作ることって究極的には「どれだけ読者と握手できるか」だと思っているんです。
……といっても、意外と「僕の描きたいもの=読者の見たいもの」みたいなところがあるので、僕はけっこう幸せなほうですね。
中山氏:
真島さんの漫画って、画面から「この人、本当に楽しんで描かれているのだろうな」ということがすごく伝わってきます。
真島氏:
ええ。もう、楽しくてしょうがないんです(笑)。
小高氏:
僕はこれまでニッチな商売で生きているので、世間の反応を気にせず、「自分のやりたいことをやるよ」みたいな感じで作っちゃうところがあって。でも、「マガジン」という巨大な雑誌の看板を担っていると、やはりいろいろなことを相当考えて作られているんだろうなと思います。
真島氏:
やっぱり、デザインもお話も保守的なところはあるなと思いますよ。その中でも精一杯はっちゃけて、読者が予想できない展開を……と、いつも考えてはいるんですけど、客観的にはそうは見えないかもしれません。
小高氏:
そういう真島さんの話を聞いていると、「僕は好き勝手やっているだけだから、アマチュアだなあ」と思っちゃいますね(笑)。
 |
──作品だけで考えると、まさに真島先生は「王道」で、『ギャンブラーズパレード』は「邪道」という感じの趣ですよね。
小高氏:
いやあ、僕の頭の中では『ギャンブラーズパレード』もめちゃめちゃ売れ線だと思っているんですけどね。「これは王道だなー」と思ってやっているつもりなのですが、真の王道の話を聞くと、インディーのなかで王道をやっているだけでしかないことに気づかされます……。
一同:
(笑)。
真島氏:
でも、「マガジン」にとってどっちのスタイルもあっていいでしょうし、最近はそういう尖ったものがヒットする時代だとも思います。結局、何が売れ線かなんてわからないものですよ。
今後について
──さて、お時間も迫ってまいりましたので、最後に皆さんの連載の意気込みをお伺いできればと思います。
真島氏:
『EDENS ZERO』では引き続き王道を目指してやっていますが、そのなかでも新しいことにチャレンジしていきたいと思っています。僕の漫画としては珍しい「メタな展開」を入れているので、どんな風にまとまっていくのか楽しみにしていただければと思いますね。

──今回、ヒロインがYouTuberというのが面白いなと思いました。
中山氏:
今の時代に合っていますよね。
真島氏:
あんまり実況者のヒロインっていないので、珍しいんじゃないかなと思ったんですよね。あとはまあ、僕はゲーム実況を見るのが好きだし、本当の実況者の友人がいたりもするので。
小高氏:
でも、「再生数のために冒険に行く」というのは、冒険ものとしてはめちゃめちゃいい動機づけですよね。実際“YouTuberが危険なところにいく”といった冒険みたいなことをするのは現実で起こっていることですしね。あの設定は早い者勝ちでしたね。
真島氏:
あとは、「SF」という設定も、ちょっと時代を意識したんです。
今までは、剣と魔法ばかり描いてきたので、「うーん、SFってちょっとどうだろう」とは思っていましたが、SFといっても「サイエンス・フィクション」ではなく「スペース・ファンタジー」だと言い張ることにしたんです。「これは宇宙が舞台なだけのファンタジーなんだ」と。これも早い者勝ちかなと思って(笑)。
 |
──そういう新作のアイデアはどこから出てこられるのでしょうか?
真島氏:
それこそゲームからですね。とくに最近の海外のゲームって、表現が豊かになっていることもあって、SFものをやりたがる人は多いじゃないですか。
だけど漫画って、SF自体はすごく多いけれど、ハイ・ファンタジーならぬハイ・SFみたいなものが多いんですよ。なんというか、本当に昔からSFとか物理が大好きな人たちが描いているものが多いので、そうじゃない人が描いている自由なSFもあってもいいかなと(笑)。
ある意味では、『ドラゴンボール』であったようなSF感というか、ああいうのって今は誰もやってないなと思ってて。
小高氏:
ミステリもそうですけど、SFには“警察”が多いですからね。そういう意味では『ダンガンロンパ』も同じような感じでしたね。ミステリ的にダメなオチでも、「まあいっか、面白いし」みたいなノリでやったので、言わんとしていることはわかるところがありますね。
──小高さんは『EDENS ZERO』を読まれていかがでしたか?
小高氏:
あれだけの大作って、なかなか始まりに立ち会えないじゃないですか。『FAIRY TAIL』もとても長いですし。その意味で、『EDENS ZERO』の始まりにリアルタイムで立ち会えているのは、これからどうなるなろうとワクワクします。ちなみに、想定何巻ぐらいなのでしょうか?
真島氏:
今のところは、20〜30巻くらいですかね。まあ、そう思っていても続くときは続きますし、終わるときは終わるので。『FAIRY TAIL』も最初は10巻ぐらいで終わらせようと思っていたら、思いのほか人気があったので、あれだけ長くなっちゃいましたけど。
小高氏:
ちなみに、終わり方とかは考えているんですか?
真島氏:
作品によって違いますね。『RAVE』は終わりまでビシッと決まっていたんですけれど、逆に『FAIRY TAIL』はまったく決まっていなかったです。『EDENS ZERO』はその中間で、ポイントポイントは決まっているんだけど、毎週の「ライブ感」みたいなのは大事にしようと思っています。
あと、今後の意気込みとしては、いつかゲームを作ってみたいですね。以前、WEBでやっていたGoogleのCMに出たときに、「今年の目標は、ゲームを作ります!」って言ったんですよ。
昔から『RPGツクール』を使ったり、『ドラクエ』の新作の設定をノートに勝手に描いたりしていた子どもだったので、やっぱりゲーム作りは夢ですね。
小高氏:
でも僕らの世代って、そういう遊びがけっこう流行っていましたよね。ノートに『スーパーマリオ』の面みたいなのを描いたり。
真島氏:
あ、描いた描いた! 僕の場合、『パロディウス』の面を作って、主人公機を紙に描いて動かしてプレイしてました(笑)。
──そんな真島先生のゲーム作品、いつか見てみたいですね。『ギャンブラーズパレード』のおふたりの、今後の意気込みは?
中山氏:
意気込みかぁ……えっと、はっちゃけていきたいです(笑)。
小高氏:
そうですね、もっと“ギャンブルもの”という枠を飛び出して──いっそギャンブルしなくなるくらいの勢いで、早くトーナメント制の殴り合うバトルとか始めたいなと思っています。
 |
一同:
(笑)。
中山氏:
あと、今のところ自分が小高さんのファンなので、原作を面白いと思っちゃうんですよね。「これをどう増幅できるかな」というところをもっと頑張りたいと思っています。
小高氏:
中山さん頼みでだんだん手を抜いて、原作を白紙で渡すようになったりして……「あいつ、何もやらなくなった!」なんて言われないようにしたいですね(笑)。
あるいはタイトルだけ考えて、「今週は『蜘蛛手、死す』でお願いします」みたいな。
中山氏:
そんな原作がきたら、めちゃめちゃプレッシャーですよ(笑)。
真島氏:
というかそれ、『遊戯王』のパクリじゃないですか! たぶん、「ジャンプ」の編集長からお怒りの電話がかかってくるでしょうね(笑)。
一同:
確かに(笑)!(了)
 |
今回の取材で垣間見えたのは、真島氏の「ゲーム世代」としての一面である。
連載で忙しい中でも、ゲームをプレイする時間を捻出することに対するひとかたならぬ執念。そして具体的な内容こそ伺えなかったものの、氏の創作がそうしたゲームたち──とりわけ『ドラクエ』『FF』などのRPG──から受けた確かな影響が語られたのは、貴重な証言だったと言えるのではないだろうか。
そして、「ドラクエ」が切り開いたファンタジーの地平の先に、真島氏の作品が存在していることもまた、今回改めて認識させられたゲームのひとつの功績であるように思う。
そして、今でこそ氏の漫画が「王道」としての地位を築いていることは衆目の一致するところであるが、真島氏もまた「マガジン」という舞台でひとり、ファンタジーというジャンルを開拓してきた人物であった。
それは、意外にも「陰」なものに対する憧れを滲ませつつ、「陽」のファンタジーを貫いてきた20年という長いキャリアによって確立したポジションなのだということもまた、今回明らかになったことだろう。
そして、そんな真島氏が羨む「陰」の漫画ど直球の、中山、小高両氏による『ギャンブラーズパレード』の今後に期待が高まる取材でもあった。
「陽」と「陰」、「王道」と「邪道」──その両者が同居する「マガジン」の今後に目が離せない。
【お知らせ】
原作:小高和剛 漫画:中山敦支『ギャンブラーズパレード』第1巻が2019年01月17日に発売されます。
【あわせて読みたい】
90年代格闘ゲームがジャンプ作家に与えた衝撃。『るろ剣』再開の和月伸宏が語るその影響近年、『るろうに剣心』は再評価が著しい。『龍馬伝』や『ハゲタカ』の大友啓史氏が監督を務めた映画版三部作は大きな人気となり、宝塚の公演は高い評価を得た。子供の頃に「ジャンプ」で『るろ剣』が直撃した世代が父や母になり、子連れで会場に足を運ぶこともある。「歴女」なる言葉も生まれた現代では、そもそも若者向けのサブカルチャーで時代劇は定番ジャンルだ。
『るろ剣』は広い世代に愛される、まさに“国民的作品”となったのだ。
だが、連載当時の『るろ剣』は、漫画好きの間で少なからず物議を醸した漫画でもあった。それは、この漫画が背負わされてしまった、漫画史の「偶然」によるものだろうか?




































