ストレートエッジのでっかい夢は「マーベルになる」こと
佐藤氏:
最初の話に戻すとさ、昔の独立する人は、自分が会社を運営するリスクをそれほど考えなくてよかったというか、自分がそれまでやってきたことをそのままやれる。たとえば編集プロダクションであれば、今までやっていた雑誌を新しい編プロでそのまま任されるとか。あるいはデザイン事務所だったら、ページを引き続き任されるとか。そういう環境の中で独立できたと思うんだけど。あまりリスク計算せずに済んだんじゃないか。
それに対して、今みたいに業界全体が右肩下がりの時に独立すると、リスクに対して慎重にならざるを得ない。三木だって相当に慎重だったと思うんだけど、そのへんの見通しはどうだったの?
三木氏:
今、ストレートエッジには有り難いことに、15人ぐらいスタッフがいるんですけど……。
佐藤氏:
そんなにいるんだ! スゴイな。
 |
三木氏:
独立したときは1人でしたし、自分だけ食えればいいから、ぶっちゃけ楽勝だなと思っていました。もし仮に失敗しても、再就職すればいいじゃんと。
佐藤氏:
リスクについて、そんなに厳密に考えていたわけではないんだ。
三木氏:
でも独立するさいに、有り難いことに何人もの作家さんがストレートエッジと契約してくださって、結果的に、7~8人の作家さんがチームに入ってくださいました。
佐藤氏:
それはまだ会社を興す前に、それだけの作家さんが「いいよ」と言ってくれたんだね。
三木氏:
そうです。その時までは、僕としては、自分1人なら潰れてもどこかに行けばいいと思ってたんですが、契約して頂いた作家さんに対する責任が生まれたわけです。しかも、エージェントは普通の編集者よりもすごく時間を使ってコミットしなければいけないので、一度に3人から5人ぐらいしか担当できないと肌で分かっていたので、これは一人でやるわけにはいかないなと……。社員編集者時代は、1人で30人ぐらいの作家を担当していたんですけど。
7~8人の作家さんと契約するには、僕1人ではやっていけないので、他の社員も雇わなきゃいけない。そうすると、その社員の人生も背負わなきゃいけなくなる。そのへんから、事業計画を立てたりして、経営という大きな枠組みを考えていった感じです。
佐藤氏:
事業計画を立てたということは、作家さんと共にあるというだけじゃない、会社としての夢をどう描いたの?
三木氏:
ぜんぜんその計画が達成できていないので、言うのも恥ずかしいんですが、3年後には、ストレートエッジがIPとして著作権を持っているようなオリジナルの作品、ゲームでもアニメでも本でもいいんですけど、そういった作品を発売して大ヒットさせると、事業計画書には書いていました。ただ、もう3年経っちゃってるんですけど。
 |
佐藤氏:
それはエージェントとして作家をプロデュースする以上の夢が叶っていないということ?
三木氏:
そうですね。あと、超々でっかい夢としては「マーベルになる」【※】って書いてあります。アメリカの出版社は会社に著作権が帰属していて、アメコミ作家さんは依頼を受けて作品を描き上げている。それのいちばん良いところは、未来永劫ずっとフランチャイズできる。その規模の大きさとか、そういうのを見て、マーベルみたいになれたらいいなと思っています。
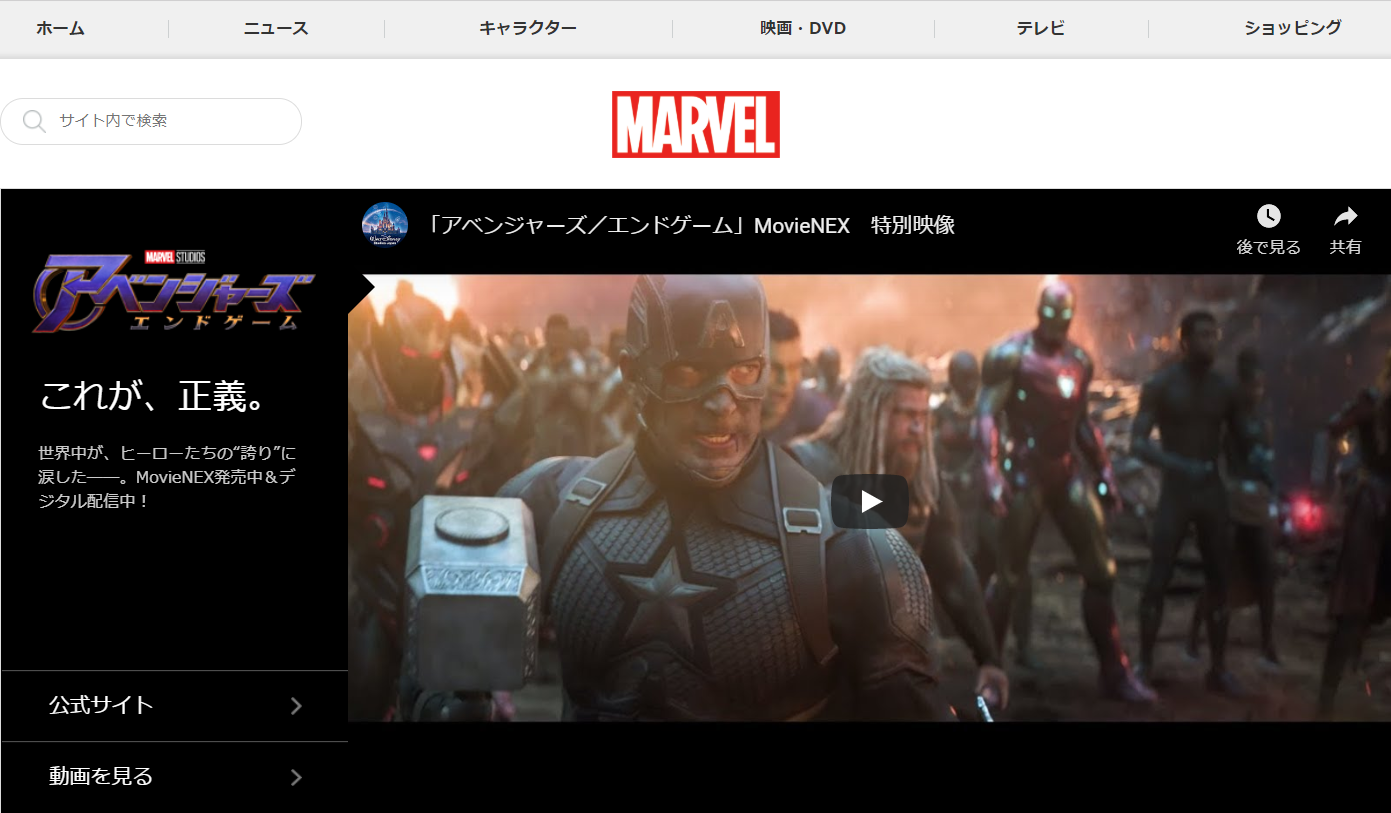
(画像はマーベル公式|Marvelより)
佐藤氏:
「マーベルになる」って、これだけでいろんな話ができると思うけど。マーベルになるための第一歩は? たとえば著作権の話だとか。
三木氏:
日本ですと、著作権は作家さんが持っていますよね。出版社は作家さんから、著作財産権の中の複製権などの独占貸与を契約で結んでいます。ゲームやアニメでは、著作権を買い取る契約も多いので、出版契約書は作家さんには手厚い契約とも言えます。ストレートエッジも同じように作家が生み出したオリジナルIPを借り受けて、僕らの会社が大手のプラットフォーマーと二社間契約を結んで、そのオリジナルIPを運用していく……というビジョンがあります。
──それはまだ具体的にやってはいないのですか?
三木氏:
もうやってますね。すでに発表されているものだと、9月10日にアプリがリリースされた、『ゼノンザード』【※】というバンダイさんのゲームがそうです。
※『ゼノンザード』……「カードゲーム対戦特化型AI」を搭載し、人間とAIの対戦・共闘や、AIの育成といった要素を盛り込んだ、次世代型デジタルカードゲームアプリ。原案/世界観設定を『ブギーポップは笑わない』の上遠野浩平氏が手がけており、WEBでのコミック連載や、YouTubeでのアニメ無料配信なども行われている。
(画像は『ゼノンザード<ZENONZARD>』公式サイトより)
──日本の出版業界の権利の持ち方だと、たとえば、人気作の原作者が亡くなったらその家族が出てきて揉めるみたいに、いろんなトラブルや難しい問題が出てくることも含めて、課題があるなと感じるんです。三木さんとしては、日本式のやり方とマーベルのやり方のメリット・デメリットを、どのように見ていますか?
三木氏:
会社がIPを持つメリットは、意志決定が迅速であり、しかも私情が介在しないので、盛り上げようとした時に爆発的に広げることができる。悪く言うと下品な方法も取れる。でも一方で、「空気を読んだメディアミックス」をするのは難しくなる。ファンの人たちが幻滅するようなメディアミックスは、クリエイターがジャッジをせずに、経営陣がジャッジをしたときに起こるケースもあります。そのへんがデメリットになると思います。
作家がIPを持っているメリットは、自分のファンのことを思って意志決定をすることができる。ファンのためのメディアミックスを、丁寧にやることができる。あと監修がブレない。ぜんぜん中身が違うし、キャラも違ってない? みたいなことは、作家さん自身が見ていると起こらない。会社にIPが帰属している場合、今まで中心になっていた人が退社した時に別物になるケースが多いじゃないですか、そういうことが防げるとは思います。
 |
──もう少し突っ込んでお聞きしたいのですが、編集者は作家を守る側じゃないですか。IPが会社に帰属することについて、否定的なのか肯定的なのか、三木さんはどっちなんだろうかというのを聞いてみたいんです。
三木氏:
そこはちょっと卑怯な表現ですが、ケースバイケースですね。作家さんの意思と相談して決めています。
主導したりハンドリングしたりするウェイトが僕のほうが高い時には、IPを会社に帰属させることもありますが、逆に作家さんのクリエイティブがとても重要なプロジェクトは今まで通り作家さんに帰属されています。
佐藤氏:
それはアニメファーストとか小説ファーストという言い方をすると、企画ファーストなの?
三木氏:
企画ファーストですね。
佐藤氏:
企画をゲームなりアニメなりに落としていく、そこの中心に三木がいるということね。
三木氏:
そうです。それを今、やろうとしています。
佐藤氏:
三木はそういうことをやりたかった、ってことだよね。それは出版社の枠組みの中では、いろんな権益が絡んできて難しかったかもしれないね。ただKADOKAWA自身も、そういうことをやろうとしてるんだよ。
三木氏:
それは分かります。僕も自分の会社も結局、作家さんがいないと成り立たないので。
出資せずにプロジェクトの主導権を握るには、会議の現場で「空間支配」を行う
──すごく下世話な話ですけど、ゲームやアプリを作る場合、ストレートエッジからも出資するのですか?
三木氏:
今後発表されるものの中には、出資しているものもありますね。ただ、出資額は本当に少ないですよ。
──もし出資しないのであれば、どうやってプロジェクトの主導権を握って動かしていくのかが気になるんです。
三木氏:
それは、いい質問ですね(笑)。
中二的な言い方をすると「空間支配」です。打ち合わせの現場で、クリエイティブや世界観やシナリオにおいて、自分がいちばん面白いものを作れるんだというふうに、その空間を支配するんです。一応、今までの自分の経験やステータスが上げ底をしてくれているんですけど、それだけじゃなくて議論の進め方とか、まとめかたとか。打ち合わせの現場で「こいつ使えねぇな」と思われたら負けですから、そこが今の自分の戦場というか、戦う場所になっていますね。
 |
──ただお金をもらってプロジェクトを立ち上げるだけだと、上手くやらないとやり損になってしまうというか、上手く使われただけで終わっちゃう可能性が、結構あるんじゃないかなと思うんですよ。
三木氏:
そうですね。それについては、信頼している相手だけと組むしかないと思います。
佐藤氏:
でも本当のことを言えば、出資してその配分を受けないと、どう考えたって支配はできないよね。
三木氏:
はい。本当の意味ではそうなんです。なので、今はありがたいことに僕と価値観を共有してくれるゲームやアニメのプロデューサーさんたちがたくさんいらっしゃるので、その方々とお仕事をしています。
──ストレートエッジのメンバーは、どういう人が集まっているのですか?
三木氏:
ありがたいことに自分の考えに賛同してくれている人が集まっていますね。たとえば、出版が好きだけど、出版の将来に危機感を持っている人とか。作家さんと一緒に何かを作りたいと思っていて、新しいことをしたいと思っているとか。あとはシンプルに「三木さんのところで働きたいです」と言ってくれた人とか。
──いろんな会社をインタビューさせてもらって思うのは、会社やチームの純度の高さって大事だなと。大企業のやりにくさの1つに、純度の薄さがあって。やりたいことをやろうとした時に、みんなの足並みが揃っていないと、いろいろ軋轢が生まれるじゃないですか。だけど小さいチームだったり、三木さんのようにゼロから立ち上げた会社であれば、その純度の高さを保つことができる。
三木氏:
それは僕もかなり意識しています。「管理できる限界は30人まで」というビジネスの掟みたいなものがあるじゃないですか。今の会社はもちろんそれよりも少ないので、みんなが一丸となっている感じはすごく得られていて、有り難い限りです。
 |
──ちなみに三木さんご自身は、何か独立するきっかけになるような出来事があったんですか?
三木氏:
ありましたよ。あったけど言えない(笑)。
佐藤氏:
働き方改革じゃないの? ゲーム業界でも「こんなことじゃゲームなんて作れない」とか、出版社でも「これじゃあ雑誌が出せない」とか言ってるんだから、そういう一般論として言えば大丈夫だよ。
三木氏:
ストレートエッジの採用に響きますよ(笑)。
WEB小説を理解はできないが、読者に喜んでもらえる小説を作る自信はある
佐藤氏:
三木が電撃文庫に入った頃(編注:2001年)は、ライトノベルがこれから始まるという時期だよね。その前の時代は、僕もまだ現役だったけど、富士見ファンタジア文庫だとか、角川スニーカー文庫だとかで、ゲーム系のファンタジー小説が1つの時代を築いていて。
それが、三木が入った頃からライトノベルという言葉が生まれて。今まではSFだったりファンタジーだったりミステリーだったり学園物だったりと呼ばれていたものが、ライトノベルというものにジャンルを超えて再生されていく、みたいなイメージを持っているんだよね。
 |
そのライトノベルブームが10年ぐらい続いて、2013年から2014年をピークに、ライトノベルがちょっと頭打ちになった。その頭打ちになった理由と、その後のことを聞きたいんだけど。たとえば『魔法科高校の劣等生』【※】もそうだけど、インターネットから生まれた小説が出てきたりとか。そのあたりは三木の中で、どういうふうに整理されているの?

(画像は 電撃文庫・電撃の新文芸公式サイトより)
三木氏:
ラノベが頭打ちになる時も、その前からずっと、誇大に成長している気がしていたんですよ。なぜかというと、一般文庫は成長が止まって右肩下がりになっていて、雑誌ももちろん右肩下がりで、ラノベだけが右肩上がりだったんです。それ自体がそもそも異常なことだと思っていました。
しかもその右肩上がりは、レーベルの数が増えることによって生み出された刊行点数の増加が原因だったので、だから1作あたりの平均部数みたいなものを考えると、これは油断できないぞという兆候が、すでにあったんですよ。
でも、だからといって全レーベルが「刊行点数を抑えよう」と思うわけもありませんから、ずっと刊行点数が増え続けていって、その先に待っているのはバブルがはじける瞬間ですよね。それが、2013~14年あたりだったんじゃないかなと結果論ですが思います。といったような事象があるだけなので、自分はこの歴史について、なにかしらの個人的な感情は持っているわけではないですね。
重要なのは、佐藤さんもさっきおっしゃられましたけど、その次のトレンドがいったい何なのか、ということだと思います。
昔は富士見ファンタジア文庫みたいなファンタジーの勢いがスゴかったのが、その次は学園異能物に代替わりしたのと同じように、だんだんと「学園異能物はもういいよね」という空気になってきて。
そこにちょうど、WEB小説の台頭がやってきたんだと思います。
だからムーブメントやトレンドに憂いがあるとか、これがこうあるべきみたいな感情は一切なくて。今こうだから、自分はどうしようかというだけですね。
サーフィンって、波の大きさを自分で変えたり、台風を呼んできたりはできないじゃないですか。そういう波が来るのなら、今日はこうやって乗ろう、しかないというイメージですね。
佐藤氏:
僕は60歳をとうに過ぎてるから、トレンドみたいなものは分からないって素直に思うけどさ、そういう恐怖はないの?
三木氏:
あります。めちゃくちゃあります。僕も42歳なので、絶対にセンスとか、経験による勘とかが錆びてきていますから。でも、やるしかないですよね。常にその恐怖とは戦っています。
佐藤氏:
社員が十何人いるのなら、若い編集者に任せれば?
三木氏:
もちろんそうしてますが、一方で、部下には負けないぞという気持ちもある(笑)。そう思っていないと、なかなか創作に携わる仕事は難しいです。ただ、僕のセンスが壊滅的になって、全ハズレし始めたら、早く引導を渡してほしいと、それは思っています。
 |
『性癖』は作家にしか出せないが、ストーリーは考え抜いたら絶対に面白いものができる
佐藤氏:
時代のセンスに関しては、もしかしたらそういう恐怖感があるのかもしれないけど、作家を育てるという根本の部分に関しては、三木はしっかりとした考えを持っているよね。『面白ければなんでもあり』【※】という三木の本を読むと、一緒に作品を作っていく時に、どういうふうに作家の能力を引き出していくのかが、わりと執拗に書かれていて。
編集者って2種類いてさ、作家の先生から玉稿を頂いて「ありがとうございます」っていう編集者と、イチから一緒に作っていくタイプの編集者と。三木はやっぱり後者でずっとやってきたんだなって感じがするよね。本の中にも、「その小説でやりたいことを『家訓』として定義して、『家訓』を決めるのは作家の『性癖』だ」とか書かれていて。
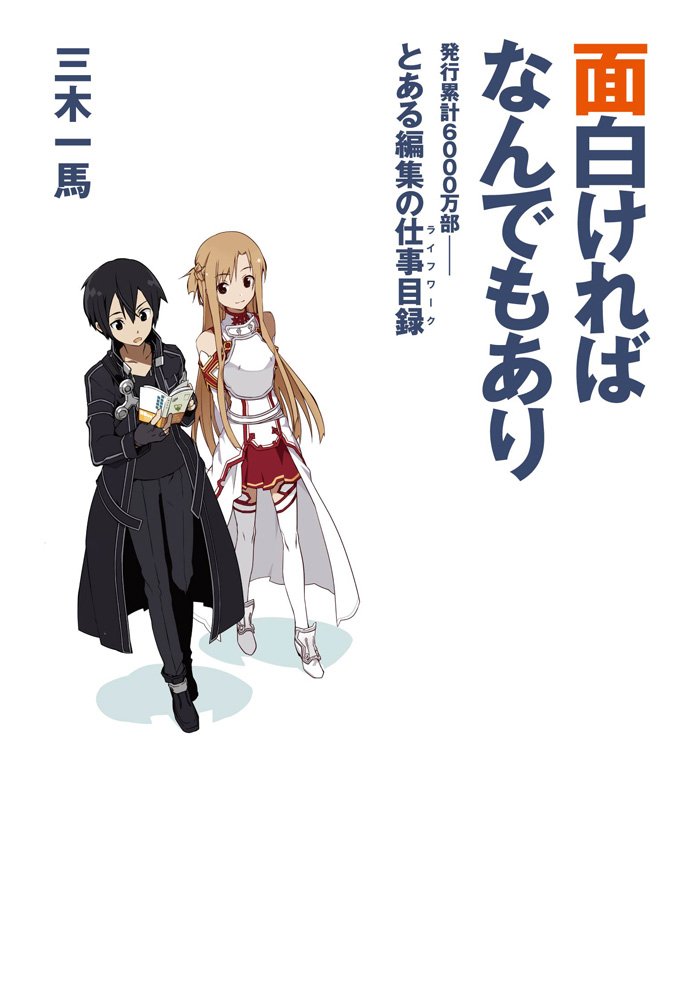
(画像はAmazonより)
三木氏:
ストーリーについては、誰か1人だけでも思いつきますが、みんなで考え抜いたら絶対に面白いものができると考えています。ストーリーはメソッドだと思うからです。一方で個性的なキャラクターや、作品の根幹から滲み出るテーマみたいなものは、絶対に作家さんじゃないと生み出せないとも思います。
そこがさっきの「『性癖』」の部分です。それがあった上で、そこに計算し尽くされたストーリーを乗っけることができると、その作品の質はとても高くなる。逆に、「これは良くできたストーリーだ」というだけですとダメなんですよね。味気ないというか、「良いんだけど、なんかチェーン店の普通のラーメンみたいだな」とか。やっぱりクセがないとダメで、そのクセは作家さんじゃないと生み出せないんです。
──でも一方で、作家さんは成功すればするほど、カッコつけようとするんじゃないかと思うのですが?
三木氏:
僕が知ってる作家さんは、カッコつけるよりも、より多くの人に見てほしいというタイプの方が多いので、それはないかもしれないですね。
自分が面白いと思うものを他人に不器用に伝えたら、相手も良いと思ってくれて、お互いにハッピーになる。これが創作の根本的にあるものだと思うんです。
佐藤氏:
今の話に出てきた「不器用に伝える」という意味は、自分が面白いと思っていることは、必ずしも自分にとって理想型じゃないというか、いつも表面的に考えていることではない、ってことだよね。つまりそれが『性癖』だと思うんだけど。
たとえば、僕が何か書こうと思うと、やっぱりカッコつけるよね。日記をつける時に、ウソの日記をつける気分。そういう、作家自身が気づいていないその人の奥深くにあるものを掘り出してきて、外に晒させる。そうすると、その人のある種のクセだとか、本当に書きたいことが曝け出されて、本当の読者の共感を得られるっていう、そういう話だよね。
三木氏:
僕が「不器用」と言ったのはちょっと違うんですけど、でも今の話のほうが正しいなと(笑)。
これは面白いなと思ったら「これ面白いな」と口で言えばいいじゃないですか。それを作家さんたちは、わざわざ物語にするんですよ。自分でしゃべって伝えるよりも小説のほうが得意で、しかも三カ月とか時間をかけてそれを書くんですよ。そこまでして伝えようとする、その不器用さが凄いし、素敵ですよね。
佐藤氏:
そういう「不器用」なんだ。
 |
三木氏:
それが、みんなを惹きつけてやまないんです。「この女の子、可愛いよね」って、その言葉だけでもいいんだけど、作家さんたちは、どう可愛いか、このシチュエーションが可愛いとか、これはこうなんだとか、何万文字も使って表現するんです。そこがいい意味で不器用だなぁと。その不器用さがエンタメなんだ、というのが僕の解釈です。でも、今の佐藤さんの解釈もなるほどなと思いました。
佐藤氏:
それはね、鳥嶋和彦さん【※】も同じようなことを言ってたの。鳥山明さんと話をする時に、「あいつが表面的に描きたいと思っているものを描かせたらダメなんだ」って。それで延々とボツを出し続けて、やっとできたのが『Dr.スランプ』だった、という話をしていたんだよ。
それで、電撃に所属していた時は、新人作家を見つけることができる場所として、電撃小説大賞があったわけだけど。一方で三木の場合は、ネットで小説家さんや絵描きさんをいろいろ探していたじゃない。そこから生まれた作家もいるわけだよね?
※鳥嶋和彦
白泉社代表取締役会長。『週刊少年ジャンプ』の編集者として、鳥山明、桂正和に代表される多くの漫画家を育成したほか、『ジャンプ放送局』や『ファミコン神拳』などの企画ページも担当。『Dr.スランプ』に登場するDr.マシリトのモデルとしてもおなじみ。
三木氏:
僕の場合は、三秋縋さん【※】ですかね。あの人はWEBで有名人だったのをお声がけさせていただいたので。
※三秋縋……「げんふうけい」名義で2ちゃんねるなどWEB上で小説を執筆して人気を博し、2013年に『スターティング・オーヴァー』で作家デビュー。その他の作品に『三日間の幸福』『恋する寄生虫』『君の話』など。
(画像はメディアワークス文庫公式サイトより)
佐藤氏:
その段階ですでに有名だったの?
三木氏:
一部でとても有名、という感じですね。ウェブ小説を連載していたものが、まとめサイトに転記されてすごく人気になって、それで声をかけさせてもらったんですね。
佐藤氏:
小説家志望だったの?
三木氏:
その時は特に思っていなかったかもしれません。ウェブで書いていたものは、掲示板の書き込みを連続させて物語にしていたので、小説ではありませんでしたから。だから今、本になっているものは、すごく加筆修正しています。
僕が声をかけた時点で、すでに8社ぐらいから声がかかっていたんですけど、一部の編集者たちは、ネットに上がっているものをそのまま載せたいとオファーしていたようです。それに対して僕は、「あなたと小説家として仕事をしたいんです」とお話をして、それで選んでくださったと聞きました。
佐藤氏:
小説未満みたいな感じでも、ストーリー的な面白さはちゃんとあった?
三木氏:
それはありました。でも文章事態はすごくシンプルなものでしたね。
佐藤氏:
それを彼は苦労せず小説にできたの? それとも相当に指導しなければできなかった?
三木氏:
三秋さんはかなり才能があって、まったく指導しなかったです。すごくラッキーでした。
佐藤氏:
ストーリー的には光るものがあったけど、小説的にはぜんぜんダメで、それをいろいろ詰めていった結果、小説になったという人は?
三木氏:
いますけど、それをこの場で「この人です」って言えませんよ(笑)。でもそれはラブコメの作家さんに多いかもしれないですね。
佐藤氏:
あぁ、キャラクターそのものとシチュエーションはすごく上手いんだけど、っていう。
 |
三木氏:
そうです。ストーリー構成をしっかりさせるために、打ち合わせをします。めちゃくちゃ時間がかかるんですよ。ラブコメが打ち合わせにいちばん時間がかかりますね。
佐藤氏:
そうやってネットで見つけてくる作家さんもいる一方で、電撃小説大賞のように新人作家を見つける場所は、今の三木にあるの?
三木氏:
ありますよ。LINEノベル【※】で「令和小説大賞」というのを始めています。LINEノベルに投稿された作品の中で大賞を決めて出版するんですけど、その編集機能をストレートエッジが担っているので、そこが僕の新人育成の現場になっています。

(画像はLINEノベル – 「小説が楽しいをつなげる」WEB小説投稿サイトより)






































