美少女ゲーム30年の歴史の中で、“ヒット作”と呼ばれる作品というのは少なくない。しかし、そのゲームがムーブメントを作り、さらに一つのジャンルを確立する大きなきっかけになった作品というのは決して多くないのも事実だ。
そんな美少女ゲーム業界に「泣きゲー」というジャンルがある。感動的でドラマ性の高いシナリオを持ち、プレイヤーが思わず涙を流してしまう──そんな美少女ゲームジャンルだ。そして、この「泣きゲー」が確固たるジャンルとして確立するのに大きな影響を与えたのが、美少女ゲームブランドKeyの『Kanon』と『AIR』であることは、美少女ゲームファンなら異論のないところだろう。


そんなKeyをはじめ、スタジオメビウス、SAGA PLANETSにtone work’s──近年ではアニメ制作からソシャゲまで、数々のヒットコンテンツをリリースし続けている株式会社ビジュアルアーツで、1991年に設立されてから28年間、ずっとリーダーとして采配を振るっているのが、同社社長の馬場隆博氏だ。
美少女ゲーム業界参入当初はシナリオライターとプログラマーとしてゲーム制作の最前線にいた馬場氏だったが、1992年から美少女ゲーム会社としては初の試みとなるフランチャイズ制を敷くことで経営に専念。
数多くのゲームブランドとPCゲーム作品、アニメなどを世に送り出すことで、美少女コンテンツ市場の盛り上がりに大きく貢献してきた。PCゲーム市場が不調をきたした2010年代以降にも数々のヒット作をリリースしており、ビジュアルアーツとパートナーブランド作品は、つねにファンの注目を集め続けている。
このように、独自で斬新な経営アイデアで美少女ゲーム業界をリードしてきた馬場社長だからこそ見えている美少女ゲームの30年というものがあるはず。美少女ゲーム隆盛の平成年間をどのように駆け抜け、そして今後の展望をどのように考えているのか。
平成美少女ゲーム史を振り返るうえでも重要人物の一人である馬場社長に、じっくりお話を伺った。

はじめに
──9月8日に開催されたビジュアルアーツの美少女ゲームブランド「tone work’s」のライブイベント「FULL MOON PARTY」は大盛況でしたね。
馬場隆博氏(以下、馬場):
ありがとうございます。いままでビジュアルアーツといえば「Key」だったんですけど、「tone work’s」もずいぶん育ってきて、ファンも増えてきたことから、最近はそういうイベントやらサービスに力を入れているんですよ。「tone work’s」の連中もみんな育ってきてて、僕が任せっきりでも立派にやってくれるようになってきたしね。
──ゲーム作品でも昨年はKeyの『Summer Pocket』、そして今年はtone work’sの『月の彼方で逢いましょう』とヒット作も続いていますし、令和のビジュアルアーツに期待するファンは多いと思いますよ。


馬場:
まあね。サマポケは萌えゲーアワードの大賞もらったし(笑)。けど、それだけじゃぜんぜん喰えない(笑)。ネットとかグローバル化とか、そういうの、頭わるいからよくわかんないし。てかさあ、なんで僕なんかにインタビューするの? 読者はもっとイケてる若い経営者の話を訊きたいんじゃないの?
Keyはいろいろあって新しい話ができないし、PCゲームは業界全体が縮小気味で人気のサガプラはパートナー離脱、結局、昔話しかできない今のビジュアルアーツなんか、ぜんぜん面白くないよ。
美少女ゲームをビジネスととらえて業界参入
──それでは、まずは馬場社長のこれまでについて、お話をお聞きしたいと思います。馬場社長はどのようにしてPCゲームに興味を持たれたのでしょう?
馬場:
いきなり昔話かよ(笑)。もうなんども語ってるので、聞き飽きた人もいるんじゃないかな。……ふぅ、仕方ない。あきらめて真面目にしゃべるか。
まあ、言ってみれば純粋にビジネスとしてですね。自分が独立して何の仕事をしようか?と事業の柱を考えたとき、僕は何も持っていなかったんです。お金もない。そこで無限に増殖できるものを自分で作って、それを1個1万円で売って1億円稼ごう、と考えたんですね。ではそういうものはないか?と探した時にPCゲームに行きついた。
──それでは、そもそもPCゲームへの関心というのは……。
馬場:
まったくなかったよ。もちろん1960年代生まれの普通のテレビっ子ですから当時もアニメは見ていましたけど、とくにアニメやゲームだけが大好きだったというわけではないんです。
──ということは、独立されるまでもゲーム関係のお仕事をされていたわけではないんですか?
馬場:
僕は電気系、映像系、音響系の商品を取り扱う、いわゆる電材商社にいました。そこで映像系・音響系を主に扱う部署を自分で立ち上げたんです(笑)。
当時、商業施設で天井からモニターを吊るして映像を流したり、モニターを積み重ねて大型ビジョンを作ったりという映像演出や表現が流行っていたんですよ。それを「ビジュアルアート」というんですけど、僕はその企画・制作をやりたかったんです。
──自分で部署を立ち上げてしまうっていうのはすごいですね。
馬場:
カッコいい仕事をやりたかったんですよ。それで「映像系の企画をやる部署を作ります!」って立ち上げたんですが、入社4年で営業所長というのは、未だにその会社の記録だそうで(笑)。
 |
──それがどうしてエロゲーに辿り着いたのでしょう?
馬場:
まあ、落ち着きなさい(笑)。
ちょうどそんなことを考えている頃に、アダルト系のDMが届いたんですよ。大人のおもちゃとか精力剤とかの。それを「なんじゃこりゃ!?」って言いながら、つい見入っている自分に驚いたんですね。普通のDMなんか見ずに捨てますでしょ? いやあ、エロは強いな。やるならエロだな、と。
そんな時に、友人のUYE!【※】にエロゲーの存在を教えてもらって、これだ!と思って買いに行ったわけです。ほら、無限に増殖出来て、1万円を1万個売れそうでしょ?
それまではエロゲーなんて全く知らなかったから、日本橋のお店にズラーっと並んでいるのを見て、「こんな世界があったんか」と驚きました。
※UYE!
元ビジュアルアーツ社員。後にビジュアルアーツのフランチャイズブランド「13cm」「130cm」などを立ち上げる。
──その時買ったタイトルは?
馬場:
『天使たちの午後』(JAST)と『沙織 -美少女達の館-』(フェアリーテイル)ですね。後にわいせつ物として検挙され、ソフ倫設立のきっかけになった両タイトル(笑)。この話をすると「社長、引きが強い!」「見る目がある!」って言われます。

──確かに(笑)。
馬場:
で、その2本を研究して、プログラムとシナリオを自分で担当してエロゲーを作ったんです。もともとプログラムはできたし、シナリオも書けるだろうな、と。「他人にできるなら、自分にもできる」というのがモットーなんです(笑)。音楽はUYE!がやってくれました。
──その記念すべき1本目は、どのようなゲームだったのですか?
馬場:
『しぇいく!しぇいく!』(ボンびいボンボン!)。シナリオをたくさん書くのが嫌だったからクイズゲームにして、他のゲームでやっていないことをやりたくて、着信専用の電話回線を5本くらいひいて、そこに電話して流れる音声を聞きながらエロアニメを見られるというゲームを作りました。
 |
──かなり新しい、攻めたゲームですね。
馬場:
攻めてないよ。脱衣麻雀とかを作る方がよっぽど難しい。
ただ、その当時のクイズゲームって「何千問収録!」みたいな問題数の多さを競う風潮があったんだけど、そんなに問題を用意するのは大変だから、回答率じゃなく連続正解すればゲームが進むようにしたんです。そうすれば300問くらいですむので。
とにかく1本目は、自分のできる範囲でゲームを作ろう、ということだったんです。
──セールスはどうだったのですか?
馬場:
ゲーム自体は売れました。
でも、そのタイミングにさっき言った「沙織・天使たちの午後事件」(沙織事件)【※】が起きるわけですよ。それで『しぇいく!しぇいく!』も販売を中止して、ほとぼりが冷めるまで塩漬けせざるを得なくなった。
で、急遽ぜんぜんエロくない『うるま』というタイトルを出して、ようやくほとぼりが冷めたころに『しゃいくしぇいく 1・2 完璧版』、『ヌーク 〜あばかれた陰謀〜』を発売した。この『ヌーク』は売れましたよ。
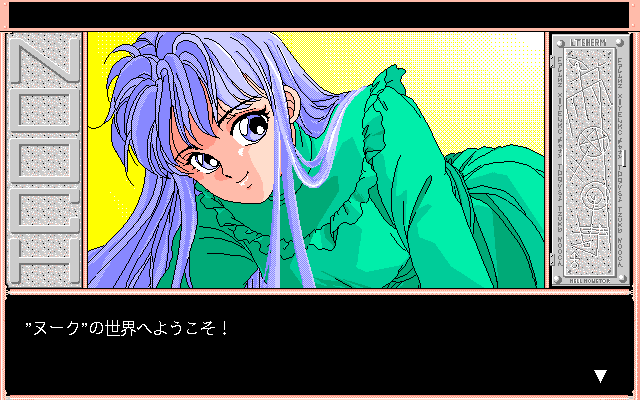
だって業界みんなが腰が引けてエロゲー作ってなかったから。僕は事件の内容を調べて検挙がわいせつ物というくくりだと知ったから。これなら大丈夫だと自信があったんです。
でも、あんまり作るのが大変なので、そこで自分でゲームを作るのをやめたんです。
※沙織事件
1991年(平成3年)にアダルトゲーム『沙織 -美少女達の館-』を開発・発売したフェアリーテールが摘発された事件。
ゲーム制作の最前線から経営に転身。導入したフランチャイズ制
──え!? そんなに早く!? なぜですか?
馬場:
正確には次の『美少女ハンターずっこんX』を出して、ですね。
その当時でも、ゲームソフト1本作るのに10カ月くらいかかっていたわけですよ。その時点で自分のビジネス人生をあと30年と考えて、作れるソフトは30本くらい。それも途切れることなく作り続けてですからね。
これではあまりにも効率が悪いし、30年後に振り返ったときに机の上に乗るくらいのソフトがすべてというのを考えると、バカバカしくなってしまった。それで考えたのがフランチャイズ化だったんです。

──今のビジュアルアーツのビジネススタイルですね。
馬場:
その当時、同じようなアドベンチャーゲームなのに、各メーカーがタイトルごとに同じようなプログラムを作り、「プログラマーがいなくなりました」と言っては困り、というのを繰り返していたんですね。
ならば共通のアドベンチャーゲームエンジンを作り、各メーカーはそれに絵とシナリオを乗せてもらい、我々がセールスと在庫管理、サポートを一元管理すればビジネスになると考えたんです。
──なるほど。
馬場:
それと同じ時期にUYE!が会社を辞めて独立すると言い出したわけです。それで今後どうしていくのか、という相談に乗っているうちに、このフランチャイズ化というのが現実味を帯びていったんですね。
──一緒にやってきた仲間が辞めるというのはマイナスのイメージが強いですが、そこから新しいものが生まれてきたわけですね。
馬場:
その頃の美少女ゲーム業界というのは、辞める人間をいじめていたんです。流通に「取引するな」とか妨害したり。
でも、僕はそれをくだらないと思った。なぜかというと、当時エロゲーメーカーだけで40社くらいあって、それ以外でもエンターテインメント系の会社は無数にあるわけです。もともとそこと戦っていかなければいけない状況で、さらに辞めた仲間と喧嘩するなんてナンセンスですよ。
だったら逆に、できるだけ協調した方がいい。
 |
それで「ここは手助けできる」「ここは協力していこう」と話し合っているうちに、「これなら日本中のエロゲーメーカーとも同じことができるんじゃない?」と。
現在でもビジュアルアーツを辞めていった人間をサポートしたり協力し合ったりしているわけですが、その転機となったのがUYE!で、アーヴォリオというブランドを立ち上げました。これが後の13cmになるわけですね。
──それ以降もたくさんのブランドがビジュアルアーツとフランチャイズ契約をしていきましたが、馬場社長から、もしくはビジュアルアーツから営業をかけていったということは……。
馬場:
ない……あんまり(笑)。というのも、当時の市場規模が100億円。最盛期でも400億円しかなかったわけですよ。そこで強力な営業体制を敷いたとしても、ローソンにはなれない。
だから基本的にこちらから声をかけるのは、独立する社員にだけ。でも、いつの世もお金の匂いがするところには、向こうから声をかけてくるわけですよ(笑)。それでブランドが増えていきました。
結果的にその後の20年で1000タイトルくらいリリースしました。最盛期には20~30くらいのブランドがフランチャイズとなって、毎月のように新作ゲームを発売していました。
──そのフランチャイズ化を進める中で、馬場社長ご自身はクリエイティブな仕事をしてみたいという欲求は……。
馬場:
ない!(笑)
これはKeyの出現が契機になるわけだけど、それまでの美少女ゲームというのは、作品ではなくソフトウェア、あくまで工業製品だったわけです。ですから、自分がエロゲーに作品性を込めるなんて思いもよりませんでした。
馬場社長の美少女ゲーム感を変えた『Kanon』の衝撃
──他社タイトルの中でも、そこをあまり意識した作品はありませんでしたか?
馬場:
『同級生』(elf)【※1】や『To Heart』(Leaf)【※2】というタイトルで作品性の萌芽のようなものはありましたけど、それは少し専門的な話になります。
たとえば『同級生』は、それまで「場所」に紐づいていたシナリオを「キャラクター」に紐づけた作品として画期的でした。キャラクターにシナリオを紐づけることで、より人物を掘り下げることができるようになったんです。これは衝撃的でしたね。
※1 同級生……1992年12月17日にエルフから発売された18禁恋愛アドベンチャーゲーム。後の18禁ゲームに大きな影響を与えた大ヒット作。
※2 To Heart……1997年にLeafから発売された学園ラブコメビジュアルノベル。大ヒットを記録し、のちの学園もの18禁ゲームに大きな影響を与えた。
(画像はAmazon | 同級生 、ToHeart|Leafより)
──具体的には、どういうことでしょう。
馬場:
それまでのエロゲーは、場所という概念にシナリオが入っていて、どこかの場所に行くと、そこに女の子が登場してシナリオが進むわけです。
でも『同級生』は個々のキャラクターにシナリオが収められていて、どの場所で会っても同じシナリオになる。その結果、キャラクターは場所という縛りから解放されて自由に世界を移動できることになった。これはかなり人間に近い。もちろんキャラクターを立てることにもなった。
──それまでのエロゲーとは違ってたわけですね。
馬場:
それ以前のエロゲーでキャラが立っていたのは主人公だけで、主人公が移動した先でイベントが起きて、女の子が出てきてエッチする。
でも『同級生』では主人公が、ヒロインがどこに登場するか考えながら追いかけていくわけでしょ。これはそれまでのアドベンチャーとは異なる、新しいゲーム──キャラクターゲームですよね。それの行き着く先が、萌えゲーだったわけです。
たとえばウチの『Kanon』【※】では選択肢を選ぶことで好感度が変わり、ヒロインそれぞれのストーリーを楽しむことができる。作品全体はあゆというヒロインの存在で一つに包まれているんですけど、過酷な運命を背負った少女をテーマにした試練と成就、という重厚で泣ける物語はヒロインそれぞれに用意されているんです。
そういうところに向かっていったきっかけになった作品が『同級生』であったと言えるんじゃないでしょうかね。
※Kanon
Keyが1作目に制作した恋愛アドベンチャーゲーム。キャラクター性、ドラマ性の高さで多くのファンの支持を集め大ヒット。特に感動的なストーリーは高評価となり、後の「泣きゲー」ムーブメントのきっかけとなった。
 |
──そこから作品としての美少女ゲームになっていくわけですね。
馬場:
キャラクターをシナリオでより掘り下げていくことで、作品性が生まれてきたということでしょうね。例えば『同級生』はその萌芽ではあっても、物語はあくまでエロゲーの装置にすぎず、各ヒロインに付随するシナリオはそこまで多くはないわけです。
でも『Kanon』じゃエロと物語の主従が完全に逆転しちゃった。ヒロインひとりあたりのストーリーが本2冊分くらいあって、それぞれがファンタジーやホラーといった切れ味のいい違いと、明確なオチがついていながら、全体をひとつの世界観でまとめるという美少女ゲームの作法が生まれた。これは今も続いています。
──その意味では、Keyが1999年にデビューして『Kanon』をリリースしたというのは、美少女ゲームの歴史の中でも非常に大きなエポックだったと思います。そんなKeyのデビューに馬場社長は関わられているのですが、最初はどのようなブランドと見られていましたか?
馬場:
もともと原画家の樋上いたる【※1】はビジュアルアーツの社員だったんですけど、辞めてTacticsさんでゲームを作っていたんです。
そんな樋上いたるから、「チーム全員でTacticsを辞めたので、丸ごと入れてほしい」と言ってきたわけです。それで「いいよ」となったときに麻枝准【※2】がやってきて、「雇ってくれるなら条件がある」と言ってきたわけです(笑)。
※1 樋上いたる
ゲーム原画家、イラストレーター。TacticsやKeyなどで美少女ゲームの原画を担当し、数々のヒット作を手掛ける。
※2 麻枝准
Key所属のゲームシナリオライター、脚本家、作詞家、作曲家、音楽プロデューサーとして活躍するマルチクリエイター。
──それはなかなか……。
馬場:
今でもなんですが、当時から熱いヤツだったんです(笑)。
で、最初に僕の方から「引き抜きじゃないし、そう思われるのは嫌だから、給料は上げないよ」と言ったら、「それはどうでもいいんです」と。で、どんな条件かを聞いたら、「自分たちの好きなものを作らせてください」「このチームをバラさないでください」と。それで「OK」と。
──ビジュアルアーツに来る前はTacticsで『ONE 〜輝く季節へ〜』という人気作品を送り出していたチームでしたが、この作品を馬場さんはどのように評価されていたんですか?

馬場:
単に知らなかった。『ONE 〜輝く季節へ〜』の人気とか、発売直後に僕には聞こえてこなかったんですよ。
爆発的に人気が出たのではなく、ジワジワ~っと人気が盛り上がった作品だったじゃないですか。しかも盛り上がってきたときには、もうビジュアルアーツに来ていましたし。
──そうだったんですね。
馬場:
だから普通にエロゲーの1本という認識だったんですが、当時は「この絵でエロゲーとして成立するのか?」と思いましたね。してなかったんですけどね(笑)。
 |
──確かに、エロという部分での評価は高くありませんでした。
馬場:
だから僕も『Kanon』で勉強した。うちのスタッフも『Kanon』で勉強しました。
当初は「あいつらなんか作っているけど、本当に売れるんかな?」みたいに思っていました。その頃Keyは別の場所でゲーム制作を進めていたので、実際にどんな風に制作していたのか、こっちはまったくわかっていなかったわけですから(笑)。
──それは確かに不安もあったでしょうね。
馬場:
不安というか、「何を作っているのかな?」と。それが変わったのがデバッグした時です。制作はKeyでも、デバッグはビジュアルアーツのクオリティーでやらなければならない。
というのも、彼らの話を聞くとデバッグが適当なんです。「そんなんでバグなくせるんか?」と聞くと「なくせませんけど、それが深いって言われます」とか、わけのわからないことを言ってる(笑)。
これじゃいかんと、「フローチャートを用意して、●月〇日までにゲームを持ってこい」と指示して、全社でデバッグを始めたら、その時に空気が変わった。
「あれ? これ面白いぞ」と。それで「これは本気で売り出さなければいけない!」となったんです。
──その要因が、先ほどお話された「作品性」なのでしょうか。
馬場:
それまでも「恋愛ゲーム」というジャンルはあったのですが、『Kanon』は、確かにモニターの向こうの女の子たちに恋愛感情のようなものを抱けたんです。そこにはキャラクターを愛するようになるシナリオがあるわけですが、日常の会話などを繰り返していくことで女の子を好きになっていく。それって実際の恋愛と一緒だな、と。
会話するときに、返ってくる言葉を予想しながら話すじゃないですか。その時に、相手がちょっと想像と違うことを返してくる。それがいい感じなんですよね。
そこで「あ、この子、ええ子やな」って思える。それをなんども繰り返すことで、どんどん好きになっていく。そうして関係が深くなっていったときに試練があって、解決があって、そこに泣けるスイッチが用意されているとだーっと泣けてしまうんです。
そういう物語の組み上げ方を久弥直樹【※】や麻枝はやろうとしていた。その中で『Kanon』が出来上がったわけです。
そのKeyのゲーム作りというものを、僕はまるで分析官のように分解して、それ以降のゲーム作りに生かそうと思ったんです。
※久弥直樹
シナリオライター、小説家。Keyの創立メンバーの一人として『Kanon』の企画原案とシナリオを担当した。
──馬場さんの中でも、『Kanon』という作品で美少女ゲームへの認識が変化したということでしょうか?
馬場:
そうですね。ガラッと変わりました。それまでのエロゲー、たとえば『雫』や『To Heart』にも、いいストーリーはありました。
でも、あくまで「エロゲーの中で」なんです。そこを超えるものでないのであれば、よりエロいゲームを作った方がいいと思っていました。でも『Kanon』はその価値観を逆転させてしまった。物語とエロの主従が逆転どころか、エロをテイストの一部にしてしまった。

だって『Kanon』のエロなんて、正直どうでもいいレベルですよ(笑)。だからもう、これはエロゲーじゃないなって。じゃあ何かって考えたら、ファンタジーなんですよ。
特に麻枝の作るものはファンタジー色が強い。だってヒロインが狐の化身でっせ?(笑)
──確かに『Kanon』をプレイすると、それまでのエロゲーとはまったく違うものを提示されているような印象がありました。
馬場:
そうでしょう。そしてそれは、麻枝だけでもできなかったし、久弥だけでもできなかった。久弥の描く女の子は魅力的だけど引き出しが少ない。麻枝はその引き出しが多彩なんです。二人が融合し、お互い刺激し合うことで生まれたのが『Kanon』であり、Keyというブランドの魅力なんですね。
『Kanon』1作で久弥はKeyから去るわけですが、彼が残したものは大きかったですね。その後に麻枝と僕らが目指したKeyらしさというのは、まさに久弥が残したもので、過酷な運命を持つ少女と、主人公のその少女への想いや瑞々しい憧れ、日常を通した恋愛感情があって、その果てに試練があって解決する、という物語なんです。
 |
──そしてKeyは『Kanon』で「泣きゲー」というジャンルを確立しました。
馬場:
当時、泣かすためのスイッチにはどんなものがあるんだろう?と、いろいろ考えました。ただ切ない設定や物語を作るだけではなく、スイッチになるたったひとことのセリフだったり、タイミングよく流れてくる音楽だったり。
──そんな中で、馬場社長は、どういったレベルでクリエイティブに介入されていくのでしょう?
馬場:
僕の場合は、まずは企画の段階で関与して、それがよければ進めさせて、ダメなら介入します。制作に入ったら、まずはやらせてみますね。
──企画段階で、馬場さんが一番重要視するポイントはどこなのでしょう?
馬場:
いろいろありますよ。絵であり、タイトルであり。でも、一番大事なのは認識ですね。「何を作ろうとしているか」という認識。『Kanon』以降、様々な方向性のタイトルが生まれてきて、「ストーリー系」「萌え系」「凌辱系」といろいろある中で、どんな作品を作るのかというのがブレちゃダメなんです。
逆にそれがブレなければ、様々なジャンルのゲームを出しても問題ない。ビジュアルアーツとしても『Kanon』を出した翌月には『絶望 -青い果実の散花-』を発売していますしね(笑)。



































