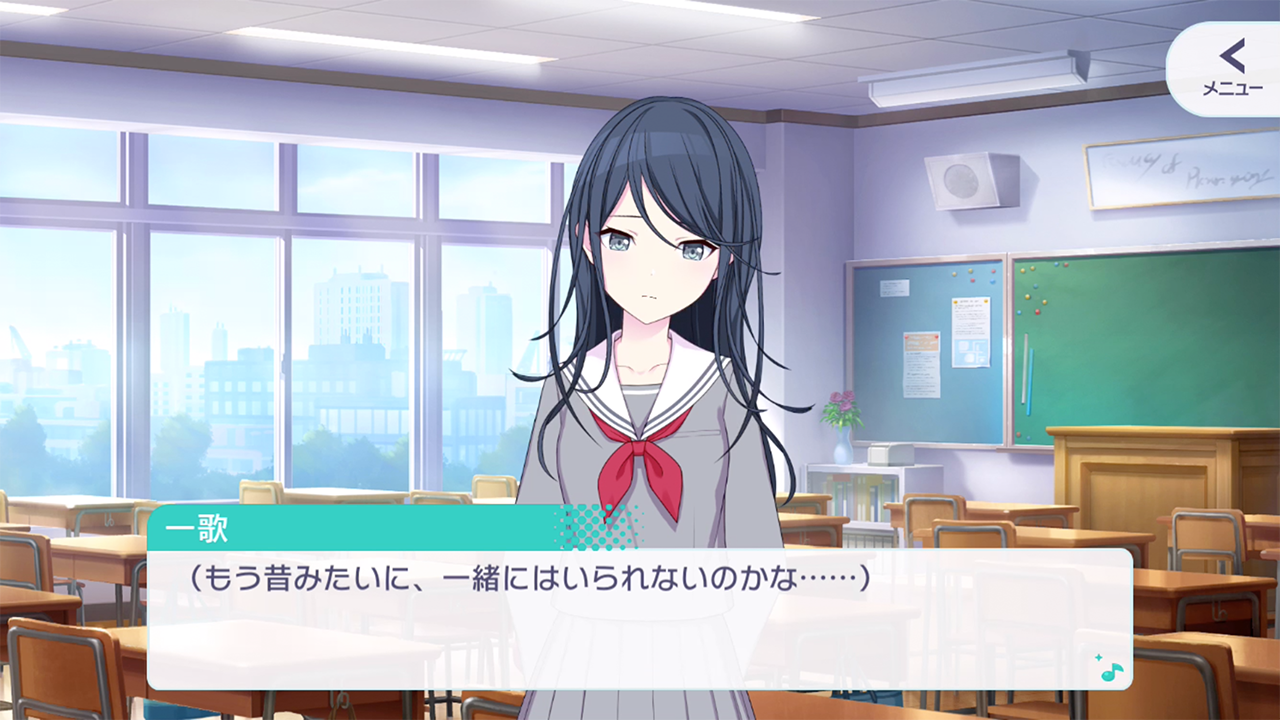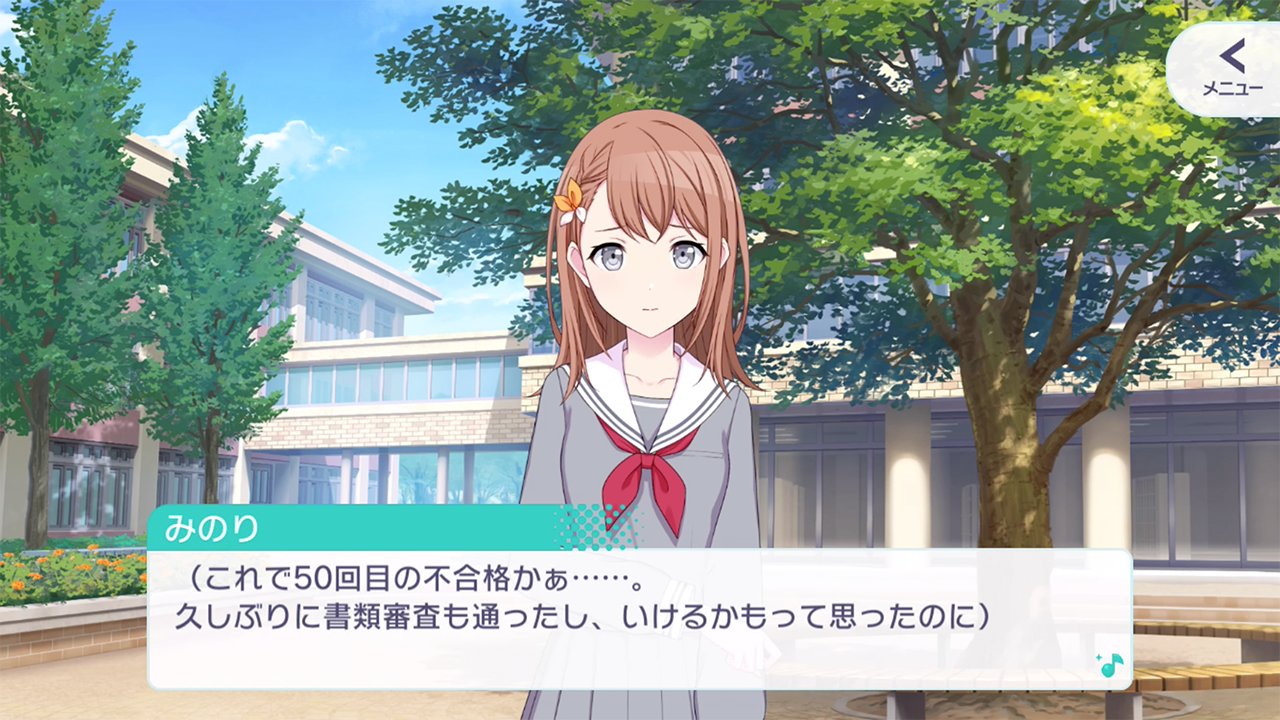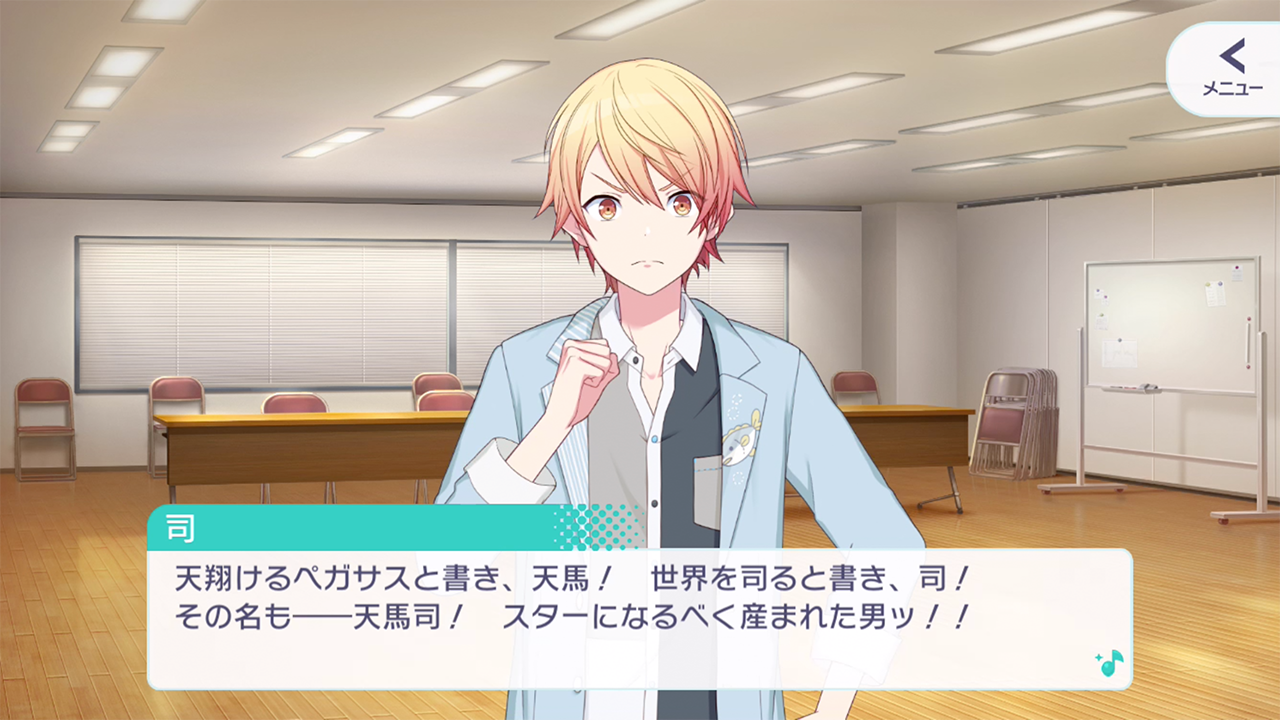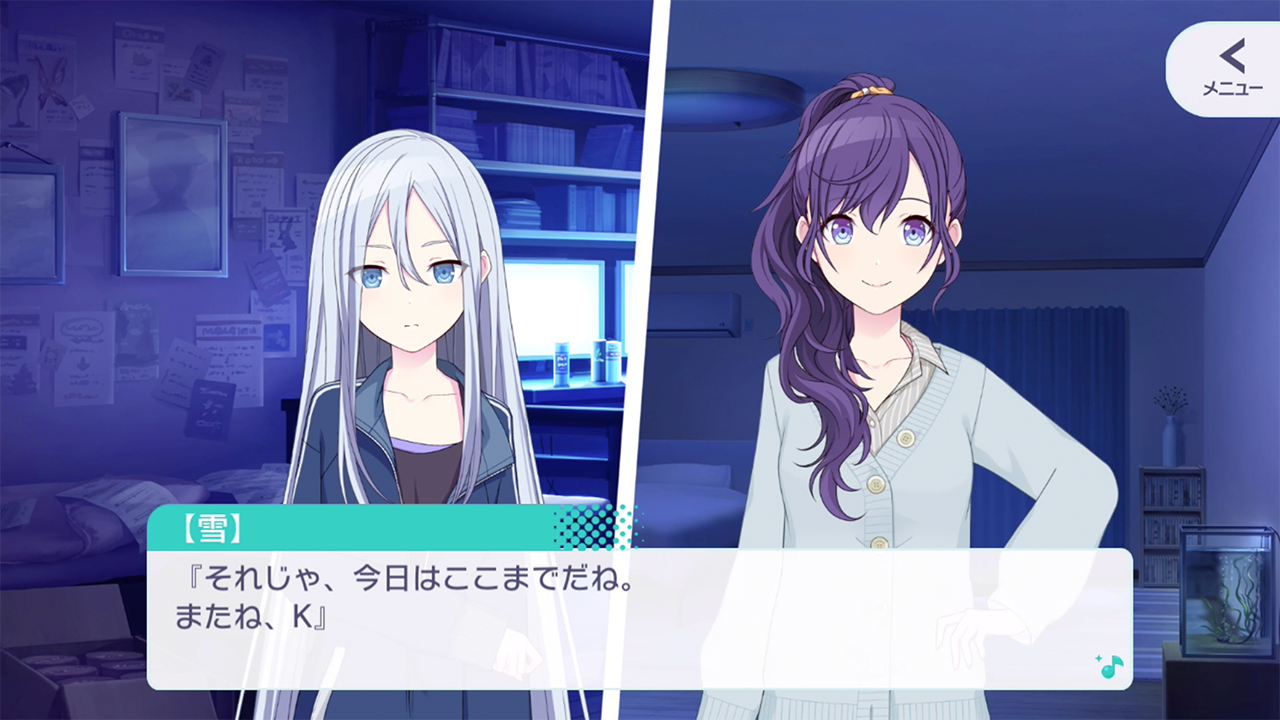|
セガとCraft Egg/Colorful Paletteが共同開発するスマートフォン向け新作リズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』が、2020年夏~秋リリース予定で、現在事前登録の受付が開始されている。
セガの初音ミク関連ゲームと言えば、2019年に10周年を迎えた『初音ミク -Project DIVA-』シリーズがおなじみだ。しかし本作はそうした先行作品とは、ゲームの構成がやや異なっている。
 |
『プロジェクトセカイ』では、インターネットなどで人気のボーカロイド曲が「バンド」「アイドル」「ストリート」「ミュージカル」「アングラ(アンダーグラウンド)」という5つのカテゴリーに分類されて収録されている。
 |
そして、この5つのカテゴリーに各4人ずつ、総勢20名のオリジナルキャラクターが登場し、4人が音楽ユニットを結成して活動する青春ストーリーが展開される。
それぞれのストーリーを楽しみながらリズムゲームをプレイしていくのが、本作のメインとなっているわけだ。






『Project DIVA』シリーズをはじめとする、これまでの初音ミク関連のリズムゲームでは、プレイヤーとミクやその仲間たちが直接向き合い、リズムゲームなどでコミュニケーションする形だった。
それに対して本作は、オリジナルキャラクターの想いから生まれた空間である「セカイ」に存在しているミクたちバーチャル・シンガーが、物語を通じてキャラクターたちと関わり合うという、ストーリー性の強い形式になっている。
 |
いったいなぜこのような構成になったのか。そしてこのストーリーを通じて、どういったことを伝えようとしているのだろうか。
ここでは本作の開発を担当しているColorful Paletteから、プロデューサーである近藤裕一郎氏と、シナリオを手がけた桝井愛氏のお2人にお話を伺った。
Colorful Paletteは、人気リズムゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ』(『ガルパ』)の開発で知られるCraft Eggの新設スタジオであり、近藤氏はプロデューサーとして同作の立ち上げ時から携わっていた人物でもある。
出席者の顔ぶれから分かるように、今回はリズムゲームの部分ではなく、『プロジェクトセカイ』の企画意図とストーリー面を中心に、お話を伺っている。
リリース開始前のスマホゲームについて、そのストーリーを深く掘り下げるという、やや異例のインタビューとなったわけだが、それこそがまさに『プロジェクトセカイ』の最大の魅力だということを、このインタビューを通して感じてもらえればと思う。
なお、本稿には多少のネタバレが含まれているので、気にされる方はご注意いただきたい。
取材・文/伊藤誠之介
編集/クリモトコウダイ
カメラマン/佐々木秀二

若い世代の人たちに、ボカロ曲を聴いてもらうための「入口」となる作品を目指す
 |
──これまでの初音ミクのリズムゲームというのは、プレイヤーとミクたちが直接向き合ってコミュニケーションする関係性だったと思います。ところが今回の『プロジェクトセカイ』では、プレイヤーとミクたちの間に総勢20人ものオリジナルキャラクターが入ってくる形になっていますよね。こうした構成になった理由はなぜでしょうか?
近藤氏:
そもそも今回のプロジェクトは、若い世代の人たちにボーカロイドやインターネット発の音楽をもっと聴いてもらいたい、というところから始まっているんです。そこで「どうすれば若い人たちが興味を持ってくれるのか?」と考えて、今の形になっていきました。

今の若い人たちに興味を持ってもらうには、現実世界が舞台のほうがいいんじゃないか、とか。ボーカロイドの音楽が今はもう無数にあって、単純なジャンルでは語り尽くせないので、ある程度デフォルメしてカテゴライズすることで「どこから手をつけていいのか分からない」という人にも入口として分かりやすくしよう、とか。そういう考え方からいろいろなことが決まっていった経緯があります。
──ということは、まず前提として、ボーカロイドの音楽が、今の若い人たちにはそんなには聴かれていないんじゃないか、という認識が開発スタッフのみなさんにあったということですか?
近藤氏:
僕自身は高校生ぐらいからずっとニコニコ動画に浸かっていましたし、じつは自分でボーカロイド曲を作って、投稿などもしていたんです。
ただ、そういう形でのムーブメントとしては、2011年~2012年ぐらいがいちばん盛り上がっていたという感覚が、やっぱり自分の中にあって。最近はあまりボーカロイド曲を聴かなくなったという人が、周りで増えてきている実感も少しありました。
そういう時に、セガさんから「一緒につくりませんか」とご提案いただいたんです。
自分としては、そもそもボカロ曲を作っていなかったらクリエイターとしての道を歩んでいない、みたいな感覚もあって。それだけに「ビジネス以上の感覚でやろう」という気持ちは正直ありましたね。「恩返し」と言っていいのかはわからないですけど。
もちろん、僕の認識とセガさんの認識とクリプトン・フューチャー・メディアさんの認識は、それぞれ異なっているとは思います。
【田中圭一連載:初音ミク編】ブルーグリーンの髪の少女は、やがてユーザーコンテンツの旗手となった。生みの親・佐々木渉がともに歩んだ10年、ともに歩む未来【若ゲのいたり】
──ボーカロイドの文化って今は、かなり一般化してきた気がするんです。なにしろ、最初はボカロPとして世に出たアーティストさんたちがヒットチャートの常連となって、NHKの紅白歌合戦に出場したりしているぐらいですから。そうやってパイとしてはすごく大きくなったぶん、「濃さ」としては薄まっているように感じるのかな? とも思うんですけど。
近藤氏:
それは僕も感じますね。昔の「濃い」「熱い」ではなくて、そのあたりに自然にあるもの、みたいな感じで広まっていっているので。音楽シーンとして衰退したかどうかというと、そうではないのかなという気は、僕もなんとなくしています。
ただその一方で、今はボカロ曲を作っても「聴いてもらいにくい」環境にあるとは、正直思っています。
僕が初めてボカロ曲を作って投稿した頃は、「良いものを作ったら曲を聴いてくれる、動画を見てくれる」みたいな感覚がありましたし、実際にそうだったんです。それが現状では、ちょっとずつですけど厳しい状況になっているのかなと。
だとしたらそこに、サポートというわけじゃないんですけど、何か刺激みたいなものを与えることができればいいな、と思っていて。
たとえば、みなさんの作った曲が『プロジェクトセカイ』にちょっとずつ収録されていったりとか、そういうことで新しいモチベーションを感じて、曲を作ってくれる人が出てきたりするといいな、と思います。
だから『プロジェクトセカイ』が体現したいこととして、ネットの音楽シーンが盛り上がるきっかけのひとつになれば、というのはかなり大きいですね。
──これは私個人の認識なんですけど、ニコニコ動画でボカロ曲が盛り上がって、それがCD化されたりしてちょっとメジャー化した段階で、いったん落ち着いた時期があったと思うんです。そこに初代『Project DIVA』が発売されたことや、初音ミクのライブコンサートが始まったりしたことで、また一段階ハネた印象があったんですね。だからそういう意味では、現在でも何かきっかけさえあれば、またハネるのかなと思うんです。
近藤氏:
そうですね。そういう役割を担うことができるようにはしていきたいですね。
Craft Eggが開発している『ガルパ』でも、ある時期からボカロ曲を入れていこうということになって、「アスノヨゾラ哨戒班」とか、いろんな曲が入っているんです。そうすると『ガルパ』きっかけで初めてそれらの曲を聴いて、「いい曲だな」と感じたという人が増えたりもしていて。それと同じようなことが『プロジェクトセカイ』でもできれば、すごくいいのかなと思っています。
ボカロ曲をカテゴライズする上で「アンダーグラウンド」は絶対に必要だった
 |
──今の若い人たちにも分かりやすい入口として、ボカロ曲を5つのカテゴリーに分けられたというお話がありましたが、なぜこの5つだったのでしょうか?
近藤氏:
じつはカテゴリーに関しては、わりとすぐ決まったんですよね(笑)。
──そうなんですか。
近藤氏:
セガさんと僕と、あとはクリプトンさんに佐々木渉【※】さんというプロデューサーがいらっしゃって。そのメンバーで話し合っているなかで、「まあこれだよね」と。じつはあともうひとつ、「和風」というカテゴリーもあったりはしたんですけど。
※佐々木渉
クリプトン・フューチャー・メディアで初音ミク開発プロデューサー/音声チームマネージャーを務める。初音ミクの総合プロデュースを担当している。
 |
──あぁ、たしかにあってもおかくしくはなさそうですね。
近藤氏:
でも「和風」は音楽性というよりも、どちらかというと音色だったりアレンジだったりするので。それでカテゴライズするのは難しいかも……ということで、今の5つに収まりました。
──実際のゲームの上では、5つのカテゴライズとオリジナルの各キャラクターが、すごく結びついているように見えるのですが。でも順番としてはあくまでカテゴライズが先で、キャラクターやストーリーが後だったのですか?
近藤氏:
そういうことです。やっぱり音楽コンテンツなので、音楽から先に決めていますね。
──ボカロ曲をカテゴライズしていく上で、ここは特に大事だった、というところは?
近藤氏:
ボーカロイドの音楽シーンを考えた時に、絶対に外せないカテゴリーがあるんです。
ここではそれを「アンダーグラウンド」と名付けていますが、その表現自体が正しいかどうかは、いまだにちょっと迷っているところなんですけど。
ただ、ここにカテゴライズされた楽曲の持つ雰囲気だとか、歌詞の雰囲気だとかはすごく大事だと思っていて。
正直を言うと、キャラクターコンテンツではなかなかやりづらい「死生観」にまで踏み込んだようなところもあるんですが、そういったものも含めたアンダーグラウンドさというのは、ここに踏み込むなら絶対にやらなきゃいけないと思っています。
──ボカロ曲の世界をカテゴライズするにあたって、王道のバンド楽曲やアイドル楽曲だけではなくて、タイトルや歌詞がけっこう過激な内容だったりするアンダーグラウンドなテイストの曲もないと、それはボカロ曲の世界ではないということですか?
近藤氏:
そうですね。再生数が特に伸びたりするような楽曲は、そういったネットならではの音楽だったりもしますから。ここを外して「ボカロの音楽ゲームです」というのは、それはちょっと難しいねとクリプトンさんとも話して、すぐ決まりましたね。
桝井氏:
そんなふうに決まった、というのは今、初めて知りました(笑)。

──シナリオを書かれる立場の桝井さんとしては、5つのカテゴライズを最初にご覧になった時はいかがでしたか?
桝井氏:
「わかるな」というのがいちばん最初にありました。それぞれのジャンルを見た時に「この曲だ」っていう、それぞれの代表曲と言うとヘンですけど、それが頭にパッと浮かんだので。
特にアンダーグラウンドは、確かになかったらちょっと別のものになってしまうだろうなというのは、私自身も思いましたし。この区分で私は良かったと思います。
初音ミクの「多様性」を表現するために、いろいろなキャラの想いから生まれる「セカイ」が必要だった
 |
──これまでの初音ミクのゲームと比べて、『プロジェクトセカイ』は世界観も特徴的だと思うんです。オリジナルキャラクターが日常を送っている、現代の渋谷のような「現実世界」がまずあって。それに対して一方では、バーチャル・シンガーたちのいる「セカイ」という、カタカナで表記される空間が存在していて。これについては、いったいどういったことを表現する意図があるのでしょうか?
近藤氏:
音楽のカテゴライズとかはスッと決まったんですけど、今言われた部分に関しては、相当に悩んだところなんです。何度も話し合って、すごく時間がかかりましたね。
初音ミクやほかのキャラクターも含めたバーチャル・シンガーというのは、やっぱり多様性ですから。それこそ各ボカロPごと、各楽曲ごとに、それぞれのミクさんがいるわけで。さらに言うと、楽曲を聴くリスナーがそれぞれ考えた、自分だけのミクさんもいますし。
そこに対して、ある1つの「初音ミク」というキャラクターを登場させるだけだと、それは既存のファンや、初音ミクが持っている10年以上の歴史に対してちょっと失礼だというか、やってはいけないことだなと思ったんです。
 |
あとはミクさんだけでなく、それぞれの楽曲ごとにも、いろんな世界がありますよね。それをやっぱり表現していかないといけない。
そういうことを考えた時に生まれたのが、「セカイ」というアイデアなんです。いろんな「セカイ」に楽曲ごとの世界が形成されていて、そこにはその楽曲の世界に合わせたいろんなミクさんたちがいるという形にすることで、初音ミクの多様性も表現できるんじゃないか。そういった流れですね。
それだけに途中で出た案としては、カテゴリーじゃなくて楽曲ごとにセカイがある、というものまであったんです。
──なるほど。それはそれで納得できますね。
近藤氏:
ボカロの歴史としては、それ自体はすごく正しいことなんですけど、そこまでやってしまうと今度は逆に分かりにくくなるというか、多すぎてユーザーも理解できないだろうなと。
あとは正直、それを現実的にやれるのか、みたいな話があって。それで今の形に落ち着きました。
もともとの考え方がそういったところから来ているので、今あるセカイが今後広がっていったりだとか、新しいセカイが今後出てくるというのも、けっこう想定した上でベースの世界観を作っています。
「Leo/need」では、今の学生がリアルに感じている「心のすれ違い」がテーマに
 |
──それでは、5つのユニットのストーリーについて、具体的に伺っていきましょうか。まずは「Leo/need」(レオニード)について、どういったユニットで、送り手が考える「ここが見どころ」という部分を教えてください。
桝井氏:
「Leo/need」については「等身大の普通の女の子たちを描きたい」というのが、いちばん最初にありました。
そのために物語としては、何かこう大きな出来事があってそれを乗り越えていくというよりは、もっと繊細な方向を目指していて。友情や人間同士の関係性で悩んだり、相談し合ったりというのを大事にして書いています。
一歌(いちか)というキャラクターがいるのですが、彼女はこのユニットの主人公的な存在なんです。若い方の中には、「自分がこれからどうしたいのか」を決められなくて、それが分からないままフワッと進んでしまっている人が、けっこういらっしゃるのかなと思っていて。
そういう感じの女の子である一歌が、ミクに背中を押されることで、自分の中の新しい一歩を踏み出すことができるというのが、いちばんの見どころだと考えております。
 |
──「Leo/need」のストーリーですごく感じたのは、ここで起こる事件自体はバンドだけの話ではなくて、本当に今の学生の子たちがリアルに感じているような、友達との関係みたいなところにフォーカスされていて。すごく身近なお話なんだな、というのを感じました。
近藤氏:
ただ、リアルだからこその「エグさ」みたいなものもあるかもしれないですね。高校生ぐらいの時期って、そういうところで本当に悩むじゃないですか。彼女たち自身からするとすごく真剣な悩みを抱えているところを、今回がんばって描いてくれたんじゃないかなと思います。
そのぶん、「キラキラしたガールズバンドのお話かな」と思って中身を開いたら、ギャップはけっこうあるかもしれないですね。
何かファンタジーなことが起こったり、大きな問題に直面したりするわけではないんだけど、彼女たち自身にとってはものすごく真剣な話というか。
そういった感情の変化の機微みたいなところは、桝井がすごくがんばって書いてくれたと想います。……それが大変だったかな?
 |
桝井氏:
……ですね(苦笑)。
近藤氏:
「Leo/need」は5ユニットのうちで、2番目に大変だったユニットですから。
桝井氏:
そうですね。なかなか難しくて。
 |
──今回シナリオを拝見して、青春物として王道なお話なので、比較的スッと出てきたのかなと思っていたのですが、そうではなかったのですか?
近藤氏:
なんていうか、さじ加減をちょっと間違えてしまうと、読み手の側からも嫌われてしまうかもしれないラインを攻めてはいるので。
キャラクター本人としては真剣に悩んでいるんだけど、読み手からすると「なんかウジウジしているな」と思われてしまいかねない、みたいな。そのラインを見極めるのが、すごく大変でしたね。
 |
──気持ちのすれ違いを扱っているだけに、ともすると、読んでいるユーザーさんともすれ違ってしまう可能性があるということですか。
近藤氏:
そういうことです。それがないようにしなければいけなくて。
桝井氏:
大きな流れはスッと決まったんですけど、それをどう見せるというところで、難しかったですね。
近藤氏:
なんだか苦い顔をしてるね(笑)。
桝井氏:
「あぁ、大変だったなぁ」って(笑)。
 |
お話としてはちゃんとすれ違いながらも、「本当は一緒にいたいんだよ」という気持ちを、どうにかして伝えられないものかと。自分もそうなんですけど、女の子同士の間だと「言える」「言えない」とか、いろんなことが起こったりするので(笑)。
そういったことも思い出しながら、それでもがんばって想いを伝えようというのを描くことで、読んでくれる人の背中を上手く押せる感じになれたらいいな、というふうに思っております。
「MORE MORE JUMP!」ではアイドルという存在に一歩踏み込んで、彼女たちを人間として描く
 |
──では、次は「MORE MORE JUMP!」(モアモアジャンプ)についてですが。
桝井氏:
「MORE MORE JUMP!」は一言でいうと、とにかく壁にぶつかってもがんばり続ける、希望を届けるアイドルユニットですね。
「アイドル」というカテゴリーに対する自分の中のイメージとしては、今はアイドル戦国時代と言いますか、本当にいろいろなアイドルがたくさん出てきていると思っていて。じつは私の知り合いにも、地下アイドルをやっている子がいたりするんですけど。
近藤氏:
それは初耳だ(笑)。
 |
桝井氏:
そういうのもあって、テレビに出てくるようなアイドルから、草の根活動している子まで、本当にいろんなアイドルがいるな、と思っていて。それだけにアイドルそれぞれの立場だからこその大変さがきっとあるんだろうなと、自分の中でまず想像をしていました。
その中で、アイドルとしてがんばるうちにいろんな壁にぶつかりながらも、「それでもがんばっていく」という女の子たちの姿を描けたら、私としてはきっとその子たちをすごく応援したくなるだろうなと。そういう気持ちから、今回の設定を想像していった形になります。
「MORE MORE JUMP!」のストーリーでは、アイドルに憧れる“みのり”という子が主人公なんですけれども。彼女は自分がアイドルを目指すきっかけになった遥(はるか)を、「彼女みたいなアイドルになりたい」という想い一本だけで助けにいくんです。
とにかくアイドルなので、お互いに想いを与え合い、もらい合いながらというところを、キラキラ描けたらいいな、と思いながら書きました。
 |
──アイドルが題材なので、もっとキラキラしたお話なのかな、と思っていたら、むしろ「アイドルとは何か」という本質を突いたお話になっていて、「スゴイな」と思いました。
桝井氏:
アイドル業界の「エグみ」みたいなものも、ちょっと出してみたりもしたんですけれど、それはやっぱり壁があるからこそ、がんばりを見せられるんじゃないかと思って。ちょっと高めの壁を用意しておりますが、基本的には一直線な物語になっておりますので。
近藤氏:
これだけじゃなくて、『プロジェクトセカイ』のストーリー全体で体現したいと思っていることとして、「遊んでくれる方から共感されるようにしなければいけない」というのと、「登場する彼女ら、彼らを“人間として描く”」というのがあるんです。
 |
「コンテンツ」としてデフォルメすればするほど、登場する彼女ら、彼らが“人間として”というよりは、どこか作られたキャラクターみたいな感覚が、僕らとしてはやっぱり出てくるので。
これは3年前に自分がプロデューサーとして前に携わったタイトルの時も同じで。当時のアイドルコンテンツとかに対して、もうちょっと踏み込んでリアルさや人間らしさみたいなものを描きたいという気持ちがあったんです。それから3年経って、そこがさらにリアルになったという(笑)。
もちろん、あまりやりすぎてしまうと、読了感というか、読み終わった時に「良かったな」という気持ちになれなくなってしまうので、あくまで程度の話ではあると思うんですけど。
 |
──その3年間の間に何か、考え方の変化があったりしたのでしょうか?
近藤氏:
というよりは、「前に携わったタイトル」をリリースした時に「キャラクターゲームでこういう踏み込み方をするのは本当にいいのかな?」という、自分でも半信半疑みたいな部分が正直あって。
でも実際にリリースしてみたら、そのリアルさというか、人間らしさの部分にちゃんと共感してもらえた感覚があったんです。
「彼女たちが人間としてこの世界にいたら、こういうことが起きて、こういう問題に直面する」というものを、その時その時の時代に合わせてデフォルメする加減を変えるというか。それは絶対に必要なんだというのが、3年前に確信したことですね。
ただ、そのデフォルメの加減がちょうどいいかどうかというのは、実際にリリースしてみないと分からないところなんですが(笑)。でも僕らとしては、「けっこういいんじゃないかな」とは思ってはいますね。
桝井氏:
そうですね。じつは構成を考えてシナリオを書き始めた時に、現実のアイドル業界でいろんな出来事が起きてしまって。
なんだかリアルタイムすぎて、逆に「どうしようかな」っていう気持ちには、ちょっとだけなってしまいました(笑)。
近藤氏:
まったく意識してないですけどね。本当にたまたまで。
 |
桝井氏:
本当にたまたま似たような事例がいくつかあって、ビックリしてしまいました。
──ある意味、それだけリアルというか(笑)。
桝井氏:
そう……なんですかね? 実際のところ、社内にもアイドルを好きな方が大勢いるので、ヒアリングしたりはしていました(笑)。
「こういうことが起こるんだよ」というのを聞いたりもしていたので、そこはやった甲斐があったのかなと。
──現実のアイドルを追いかけている人だと、そういうリアルなところもたぶん見ていると思うので。納得感があるような気はします。
近藤氏:
納得感はあってほしいですね。「MORE MORE JUMP!」はわりと読みやすいというか、展開はすごくおもしろいので。
「Leo/need」みたいな複雑な感情変化ではなくて、わりとストレートで分かりやすいので、5ユニットの中では読みやすいほうかな、とは思います。
──書きやすさ的にはいかがでしたか?
桝井氏:
中盤ぐらいまでは問題なくいけたんですが、後半は遥とみのりの関係性を描くのがけっこう大変でしたね。
 |
オーディションに落ち続けている女の子が、ずっとトップを張ってきた女の子にどこまで踏み込めるのか、というところの説得力がないといけないので、そこはすごく難しかったですね。
ただ、彼女たちの想いを叶えられたらすごくカタルシスが大きいだろうし、ユーザーさんも楽しんでくれるだろうと思ったので。「MORE MORE JUMP!」に関しては、熱いものをたくさん入れられたので、良かったなと思っています。
ストリートの音楽シーンとして納得感のあるものを目指した「Vivid BAD SQUAD」

──次は「Vivid BAD SQUAD」(ビビッドバッドスクワッド)についてですが。
桝井氏:
「Vivid BAD SQUAD」は一言でいうと、「志(こころざし)があるユニット」ですね(笑)。
近藤氏:
「友情・努力・勝利」だよね。
桝井氏:
「MORE MORE JUMP!」と毛色はちょっと近いんですけれども、音楽を介して自分たちの夢に共通点を見つけていって、そこをきっかけにひとつになっていくところを、「Vivid BAD SQUAD」ではより大事にしました。
ストリートは楽曲的にもカッコイイものが多くて、信念を持ってやっている感じがありますよね。
もちろん、他のカテゴリーの方もきっとそうだとは思うんですけども、ストリートの楽曲からは、「自分たちのカッコ良さ」だとか、あとはバイブスと言うんでしょうか、そういったものを貫いている印象が、とても強かったので。
だからこそ、そういった部分を侮られたり、弱く見られたりすることに対して「許せない」「嫌だ」という、男の子たちと女の子たちのちょっとしたバトルなんかもあるんですけれども。そういった、お互いにぶつかり合いながらも成長していく姿を描けたらいいなと思っていました。
 |
──見どころとしては?
桝井氏:
基本的には、杏(あん)がこはねという相棒を見つけたことをきっかけに、こはねからすると、それまで自分がまったく知らなかった世界に踏み込んでいくことになるんですね。そうして踏み込んだ結果、新しい仲間を自分の手で見つける、というか作ることができていくところは、すごく見てほしいと感じています。
特に、最初は敵対する相手として出てくる、彰人(あきと)と冬弥(とうや)という2人の男の子がいるんですけれども、こはねとしてはけっこう苦手というか、怖い存在なんですね。
彼らは彼らで芯があるからこそ、ちょっと自分とは違う相手だったのに対して、こはね自身が成長することで関係性が変わっていく。そういったところは意識して書いています。
 |
──本作に出てくる20人のキャラクターは、もちろん個々にいろんなストーリーがあるとは思うんですけど、この4人に関しては本当に、それぞれにドラマチックなストーリーがあるというか。なんだか特に濃いメンバーが揃っているなという印象を受けました。
桝井氏:
そうですね。さっき申し上げた通り、やっぱり彼女ら、彼らが持つ芯の強さみたいなものを描きたいという気持ちがけっこう前面に出たなと、自分としては感じています。
意図的に濃くしたというよりは、それぞれに「どうしてそこまで音楽に熱い思いを持つのか」というのを突き詰めていくと、結果としてそうなった形ですね。
近藤氏:
あとは、構成の影響がけっこう大きいのかもしれないですね。他のユニット、たとえば「Leo/need」だったら一歌と咲希(さき)の視点で物語が進んでいきますし。「MORE MORE JUMP!」であれば、みのりの視点で進んでいくんですけど。
ところが「Vivid BAD SQUAD」の場合は、4人全員の視点が入れ代わりながら、物語が進んでいくんです。
 |
──たしかにそうですね。
近藤氏:
だから他のユニットだと、誰かひとりが主人公的な存在というか、そういう形の構成になっているんですけど、「Vivid BAD SQUAD」の場合はある意味、全員が主人公みたいな感じで。
僕ら自身も話し合いの中で「Vivid BAD SQUADは全員が主人公かもね」みたいなことを言いながら作っていったので。
 |
──物語の作りやすさとしては、いかがでしたか?
近藤氏:
「Vivid BAD SQUAD」は「頂点を目指す」という、すごく分かりやすいストーリーではあるので。そういう意味では5ユニットの中で、いちばん読みやすくはあると思います。
それよりはどちらかというと、ストリートシーンの音楽をどう扱うかという点で苦労しましたね。
パッと思い浮かべると、ラップやヒップホップみたいなイメージが出てくるんですけど、最近のストリートシーンをちゃんと調べたりすると、意外とそうではなかったりするので。
ストリートの音楽シーンって、活動の起点がすごく多岐に渡っていて。路上でラップをするみたいなこともある一方で、ちょっとオシャレなバーやカフェで演奏したりというのもあって。もちろんライブハウスもありますし。
だからどちらかというと、そこらへんのシーンをうまく取り入れていくことに、苦労しましたね。
桝井氏:
苦労しましたね……。
 |
近藤氏:
「ストリート」と謳っているからには、実際にストリートの音楽シーンで活躍されている方から見て、違和感がありすぎるのもダメだと思ったので。ひたすらMCバトルをしているだけがストリートではないんだ、というのはすごく気をつけました。
じつは、最初にお名前の出てきたクリプトンの佐々木さんが、ストリートの音楽シーンにメチャメチャ詳しい方で。それで佐々木さんからは、すごくインプットしてもらいました。
──「これは実際のストリートではありません」みたいなこともあったんですか?
近藤氏:
最初はけっこう意見交換をしましたね。僕らとしても「ウソっぽすぎない」というのは大事だと思っているので。そこはかなり意見交換した上で、今の形に落ち着いています。
──そういった意味では、「Vivid BAD SQUAD」の物語だけでなくこのゲーム全体に言えることですが、ただ単にリズムゲームというだけではなくて、「現場の音楽」に密着しているゲームなんだというのは、すごく感じました。
近藤氏:
そうですね。音楽コンテンツでもありますし、「初音ミク」自体が音楽とすごく深いつながりのあるIPなので、音楽である必然性みたいなところは、かなり意識しています。
 |
「この物語に音楽っていらないじゃん」「ミクがいる意味ないじゃん」というふうになってしまうと、それはボカロファンのみなさんに対しても、ボカロシーンをこれまで追いかけてきた方々に対しても良くないので。「彼女ら、彼らは音楽があったからこそ、出会って成長できたんだね」と感じてもらえるように、そこはすごく意識しています。
「ワンダーランズ×ショウタイム」では、共同作業で作品を生み出す楽しさを伝えたい

──次は「ワンダーランズ×ショウタイム」ですね。
近藤氏:
これはいちばん話しやすいのでは?
桝井氏:
えー、どうだろう(笑)。「ワンダーランズ×ショウタイム」は、とにかく「にぎやかなお祭りユニット」ですね。
最初のほうで近藤が言っていましたが、「楽曲ごとにセカイを作ろう」だとか、いろいろと話している頃に提出した初期のアイデアが、そのまま最後まで生き残ったという、ちょっと稀有な例なんです。
──そうなんですね。
桝井氏:
主人公の司(つかさ)というキャラクターが、最初は「自分が」「オレが」と言っていたのに対して、個性的な仲間と出会うことで少しずつ変わっていくという、オーソドックスではあるんですけれども、そこがいちばんの見どころになります。
 |
なんでそういうお話になったのかと言いますと、最初の頃はシナリオチームで、改めてボカロシーンについて分析したり、考えてみようということをやっていたんです。
その時に思ったのは、ただ曲を作るだけではなくて、絵を描いたりマンガを描いたり、それぞれが自分自身のできることを持ち寄って、ニコニコ動画という場所でみんな一緒にワッと楽しめる。そこがいちばん魅力的なところだったのかなと。
そういう個性の集まりというか、みんなで一緒になって新しいおもしろさをどんどんと作り上げていくところを、描いてみたいと思ったんです。
さらに欲を言えば、自分たちもこんなふうにやってみたら、何かおもしろいものが生まれるかも……と思ってもらえたら幸いだなと。そういう気持ちで書いておりました。
 |
──このユニットに関しては、いい意味で他のストーリーとは違う、ハメの外し方があると思うんです。それは物語だけでなく、キャラクターも含めてですけれども。
近藤氏:
このセカイに登場するミクさんが、そもそもアッパーな感じなので(笑)。
ミクさんたちの声質のチューニングは、クリプトンさんが全部やってくださっているんですけど、ここだけはかなりアッパーな感じにチューニングしてくれていて。それもあって、楽しく、元気に、カオスな感じになっていますね。
桝井氏:
他のユニットに比べるとややライトな感じで、ライトノベルを意識しているというか。
近藤氏:
そういう意味では、「笑顔になりたいな」という気持ちの時に読んでもらうぐらいがいいかもしれないですね。
桝井氏:
ちょっと落ち込んでいる時にでも読んでもらえるといいですね。自分が落ち込んでいる時に「Leo/need」の物語を読むと、「そうだよなあ……」って、さらに考え込んだりしてしまいそうなので(笑)。
みんなでワイワイできるというこの物語の雰囲気は、すごく大事にしたいと思っております。
 |
──あと、これはストーリーのオープニングで描かれているのでネタバレにはならないと思うのですが、主人公の天馬司は「Leo/need」のメンバーである天馬咲希(さき)のお兄さんで、しかも咲希の存在が司のモチベーションになっているというのは、けっこう驚きました。
近藤氏:
あー、たしかに珍しいかもしれないですね。じつはあのオープニングは、いちばん最後に書き足されたものなんです。
司自身は、自分がなぜショーをやりたいのか、という理由を忘れてしまっているんですけど。でも読み手もそこを知らないままだと、ただの目立ちたがり屋に見えてしまうんですよ。
 |
──たしかにその通りですね。
近藤氏:
だから司自身が忘れてしまっているとしても、読み手は理解できるようにしておかないと、本当はすごくいい子なんですけど、誤解されてしまう恐れがあるので。そのために急遽あのオープニングが書き足されて、スチルも描き足されたと、まぁそんな経緯があります。
──先ほどのお話にもつながると思うんですけど、このユニットはわりとアッパーでキャラクターが振り切っているぶん、誤解も受けやすいと?
近藤氏:
そうですね。そういう意味では、オープニングを作って良かったですね。
桝井氏:
良かったですね(笑)。こちらの胸の中にあるだけでは、意味がないですし。
全年齢で表現できるギリギリまで“心の闇”に切り込んだ「25時、ナイトコードで。」

──最後は「25時、ナイトコードで。」です。ここまでのお話を総合すると、このユニットがいちばん大変だったのではと思うのですが……?
近藤氏:
その通りですね。
桝井氏:
概要を言ってしまえば、お互いに顔も名前も、何も知らない女の子たちが、音楽だけでつながり合っているサークル、というくくりになるのかなと。
桝井氏:
それで見どころなんですが……見どころ……(苦笑)。
近藤氏:
見どころは難しいですね。他の4ユニットに比べると、各自がなかなか解決しがたい課題を抱えているので。
──事前にシナリオを拝見していますが、たしかにその通りですね。
近藤氏:
それでも物語が進むうえで、彼女たちの中ではある一定の納得感があるものが見つかって、だからこそ次のステップに進めていける。そこがひとつの見どころかもしれないですね。
なので、読み手のほうとしても「すごく納得感のある物語だった」という読了感よりは、「彼女たちがそう決めたのなら応援しようか」みたいな感じになってもらえるといいのかな、とは思っています。
 |
──彼女たちもそれだけ重たいものと向き合っているから、ですよね?
近藤氏:
そうですね。心の闇の部分というか、苦しいだとか葛藤している部分が描かれますし。あるキャラクターに関しては死生観といった部分にまで、若干ですが踏み込んでいます。
 |
「アンダーグラウンド」というテーマを描くにあたって、その深さをどれぐらいのものにするかというのが、メチャメチャ難しくて。
深すぎると全年齢コンテンツにできないし、そもそも初音ミクのIPをお借りしてやるべきものにはならない。かといって、浅すぎたら浅すぎたで、このテーマをそもそも扱ってはいけないというか。
そんな中で、どうしてこういう状況になったのかみたいなことを、納得感があるように表現しようとすると、書き方だとかすべてにおいて、さじ加減がとにかく難しくて(苦笑)。本当に大変でしたね、これは。
桝井氏:
書き直しにつぐ書き直しをさせていただいたりしておりましたね……。
 |
──そこの調整に関しては、かなり時間がかかったのでしょうか?
近藤氏:
すごくかかりましたね。
桝井氏:
それを最後までやっていたな、という感じですね。
ボカロでそういうアンダーグラウンド系の曲を聴くと、そこに込められている想いがやっぱり、すごく切実だなと感じることが多くて。だからこそ、いろんな人がその曲に助けられていると思うんです。
「私だけじゃなかったんだ」というコメントがついていたりして。
このやりとりは、ボカロシーンにおいてはすごく必要なものなんだなと、個人的に感じていて。その部分を出せたらいいな、というのは感じていました。
 |
さっき近藤が、「どこまで深く書くか」というところに触れていたんですけれど。でも絶望的な状況で、絶望的な音楽があるからこそ、自分はここにいられる、というところは守りたいなと思っていました。
近藤氏:
現存する全年齢向けキャラクターコンテンツの中では、ギリギリのところまで踏み込めたかなという気はしますね。対象年齢を引き上げてしまえば、いくらでもいけるとは思うんですけど。
ただ、これが受け入れてもらえるかどうかは、実際に出してみて、ユーザーさんに読んでもらうしかないという感じなので。
──確かに反発する人もいる気もしますが、でも一方で、刺さる人にはすごく刺さるストーリーなんじゃないかなとも思います。
近藤氏:
そもそもアンダーグラウンドというテーマなので、万人受けは難しいかなとは思っています。
──先ほど、曲についているコメントも参考にされたというお話もありましたが?
近藤氏:
どちらかというとコメント自体を参考にしているというよりは、その曲に救われている人がいる事実を重く受け止めて書いている、というところですね。決して気軽な気持ちで書いているわけではなくて、そういう人たちから見ても共感してもらえたらとは思っていますし。
あとは、「25時、ナイトコードで。」の物語はクリエイターサイドの話でもあるので、クリエイターの方々から見ても違和感がないようにはしたいですし。特にクリエイターとしての葛藤みたいな話は、僕ら自身も知っている部分が多いので。
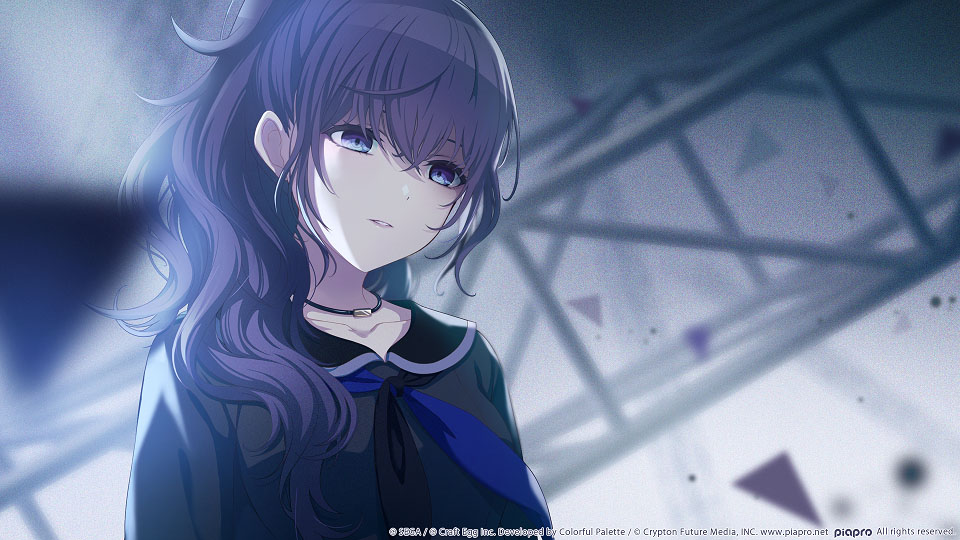 |
──今、「クリエイターサイドの話」という話題が出ましたが、この「25時、ナイトコードで。」の物語は、お互いに顔も知らない女の子たちがネットを通じてボーカロイド曲の動画を一緒に作っているという、「ボカロP」の話にもなっていますよね。ある意味、メタな作りになっているので驚いたのですが?
近藤氏:
いちばん最初にお話ししたように、このプロジェクトはそもそも「若い子に新しく興味を持ってもらいたい」というのが根底にあるんです。
そのためには、今の子たちがネットを通じて何かを作って、それを気軽に配信できたりだとか、そういったところも描いていかなきゃいけないよねという話が、ボカロPとかそういったところとはまた別角度であって。
それとアンダーグラウンドという音楽ジャンルが、上手く噛み合ったんです。最初からボカロPの世界観を描きたかったというよりは、それぞれの素材が作業を進めていく上で結びついていった形ですね。
音楽ソフトである『初音ミク』の立ち位置から、キャラの「背中を押す」存在として解釈
 |
──5つのストーリーすべてに言えるとは思うんですけれども、『プロジェクトセカイ』でのミクたちの立ち位置は、あくまでユニットメンバーたちの「背中を押す」というスタンスになっていますよね。その部分でのキャラクターとミクたちの距離感を、どういうふうに捉えられているのでしょうか?
近藤氏:
それは本作におけるミクさんたちバーチャル・シンガーを「どう解釈するか」という話になってくると思うんです。
キャラクターではなくて、本来のボーカルソフトウェアとしての『初音ミク』は、それ単体からは音楽は生まれてこない存在ですよね。
誰かクリエイターさんがいて、彼らの中に「何かを作りたい」「何かを表現したい」という“想い”があって、その想いが『初音ミク』というツールが噛み合って、音楽が生まれる。初音ミクという存在の「原点」は、そこにあると思うんです。
なので『プロジェクトセカイ』でもミクさんたちは、キャラクターの「想い」をサポートするという、そういう形になっています。それはつまり、音楽ソフトウェアとしての初音ミクの立ち位置を、そのまま解釈しているんですね。
 |
──なるほど。キャラクターとしてのミクたちとして登場しているけれども、それは同時に「音楽ソフトウェアとしての『初音ミク』」でもあるという。
近藤氏:
そうですね。ボーカルソフトウェアとしての『初音ミク』を、『プロジェクトセカイ』なりにデフォルメして解釈しているというのが、本作の設定や物語にいちばん影響を与えている考え方だと思います。
──その考え方はすごくおもしろいですね。
近藤氏:
個人的には別に奇をてらったつもりはまったくなくて、「そうだよな」って感じなんですけど。たぶん、自分自身が音楽ソフトとして『初音ミク』を使っていたからでしょうかね。
 |
──確かに、最初にボカロPとしての経験があったというお話を伺って、そういうスタンスだからこそ生まれてきたゲームなんだ、というところは確かに感じました。
「ここにいる」という垣根を飛び越えられるのも、初音ミクの持つ多様性だ
──さて、5つのユニットの物語を、ここまで書き終えてみていかがでしたか?
桝井氏:
ミクちゃんたちが本当にいろんな人に愛されていて、いろんな姿、いろんな性格で描かれているのを見ていると、本当に愛されているキャラだからこそ、最初は書くのがすごく怖かったんです。
「こういうものだ」とこちらで決めてしまうような行為に思われてしまうんじゃないのかな、というのがあって。
でも実際にプロジェクトが動きだしてみると、「いろんなミクちゃんがいていいんだ」と思っている方がすごくたくさんいて。それならば私も、その波の中に一緒に入ればいいんだなと思えたんです。
だからこれは私たちが出すひとつのミクちゃんだけれども、『プロジェクトセカイ』に出てくるミクちゃんは、キャラクターたちの心の中にある何かを反映した存在なので。ユーザーのみなさんの中にもきっと、それぞれのミクちゃんがいると思います。そのミクちゃんと一緒に、「こういうミクちゃんもいるんだ」と楽しんでいただければいいなと思っています。
 |
個人的にはミクちゃんって、世界を股にかけるというか。もちろん世界的な展開はしているんですけど、それ以上にもっともっと広い、どこか私たちの知らないところまで連れて行ってくれるみたいな存在なのかな、と自分の中では思っているんです(笑)。
──今のお話を伺って思い出したのですが、『プロジェクトセカイ』の設定からはなんとなく、ミクたちがセカイの中でキャラクターたちを見守っていたり、手助けしたりするイメージがあったんです。でもシナリオを読み進めていくと、キャラクターたちが生活している現実世界に対しても、意外とミクやKAITOたちが干渉してきますよね? そこにちょっとビックリしたんですけど。
桝井氏:
なんていうか、垣根を自由に飛び越えられるというところも、ミクの多様性みたいなものの結果として出せたらいいかな、とは考えておりまして。別に「ここにいる」と決めなくてもいいのかなと(笑)。
──なるほど、それはすごく納得がいきました。近藤さんのほうはどうでしょう?
近藤氏:
今、このゲームを作るというのは、ある種のチャレンジだと思っていて。自分としてはそこをやることに対して、単なるビジネスを超えている部分があるんです。
 |
最初にお話ししたように、ボカロ曲を作っていなかったら自分はクリエイターとしての道を歩んでいないということだったり、現在のシーンの変化などを見ていて、自分にもし何かやれることがあるのなら……というのが根底にあるので。
だから、本作にオリジナルキャラクターを登場させたりするのも、それはただゲームを売りたいから、みたいな話ではなくて、「新しい人たちに入ってもらうきっかけとして、絶対に必要だ」という気持ちでやっているんですよね。
このプロジェクトを発表した当初に比べると、そこの部分に関して、少しずつ理解してもらえてきているのかなという気はします。
もちろん、まだ抵抗感のある方がいるのも知ってはいます。けれども、最終的にこの『プロジェクトセカイ』を通じてネットの音楽シーンが盛り上がったりだとか、楽曲のクリエイターが増えたりとかいったことが実現できて、中長期的にみんなが良かったね、という話になればいいなと思っています。
それを実現させるためにも、まずはゲームをリリースして成功させなければいけないので。そこはがんばらないと、ね?
桝井氏:
そうですね。がんばらないと……。
 |
各ユニットが新たな課題に向き合う際に、他のユニットとの出会いが成長を促す可能性も
 |
──今回、5つのユニットを描いた物語をあらかじめ拝見させていただいて、ある意味、5つのユニットのオリジンストーリーというか、ユニットが誕生するまでの流れがすごく良く伝わってきたと思います。なのでこれを読んだユーザーさんからは、「このユニットが今後どうなるのか?」という部分もきっと気になると思うんですけども。そこに関しては、何か計画があるのでしょうか?
近藤氏:
そうですね、売り切りのゲームというわけでは、もちろんないので。
彼女たちが成長を続けられる舞台だったり、環境だったりというのはずっと用意していかなきゃいけないと思っています。なるべく長い期間楽しんでいただけるように、わりと先のことまで考えて進めていますね。
各ユニットにもそれぞれ、まだ解決していない問題がありますし。そういったものをこれから時間をかけて、少しずつ解決させていくという感じですね。
- 天馬司
- 天馬咲希
──あともうひとつ、5つのユニットの物語を拝見して気になったことがあるんです。「ワンダーランズ×ショウタイム」の司と、「Leo/need」の咲希が兄妹だという話が先に出ましたけど、それだけでなく違うユニットのキャラクター同士が同じ高校に通っていたりだとか、それぞれが相互に関係していますよね。そういった「セカイ」ではない劇中の現実世界での広がりみたいなものも、想定されているのですか?
近藤氏:
やっぱり、ずっと同じユニットというか、同じ関係性の中で物語が展開していくだけだと、行き詰まってしまうので。
僕ら自身もそうですけど、たまにはこう、斜め前にいる人と話したりすることで生まれる気づきであったりとか、そこから発展する関係性とかもあると思うので。
各ユニットの彼女ら、彼らがこれから人間として成長していくことを考えると、いろんな出会いやいろんな広がりがあってしかるべきかなとは思っています。
──5つのユニットが同じ街に存在している、そのトータルの世界観で描きたいものもあったりするのですか?
近藤氏:
うーん、そこでじゃあ5つのユニットが集まって、ミクたちも含めた全員で何かをするというのは、予定していないですね。もともとはそういう話もあったんですけど、なんというか……あんまりピンと来なかったよね?
桝井氏:
その展開もやってみたいという気持ちはありつつも、なかなか難しかったところはありますね。
 |
近藤氏:
結局、根幹にあるのは彼女ら、彼らの「成長」を描きたい、描くべきだということで。そうなった時にやっぱり、ひとりひとりの人物だったり、あるいはユニットごとにフォーカスしていったほうが、成長って生まれるんですよね。
それに対して、20数人が一度に集まって……みたいな話になってくると、どうしてもお祭り騒ぎというか、ちょっと楽しかったね、みたいな感覚になってしまって。それはそれで必要なコンテンツなのかもしれないですけど、それ自体がメインにはならないな、という感じですね。
なので今回に関しては、全員で何かをするというストーリーは、じつはゲームの仕様上、なくしてしまっていて。あくまでユニットごとのストーリーがメインだという見せ方にはなっています。
──なるほど、あくまでひとつのユニットのストーリーを楽しんでいる時に、別のユニットのキャラクターがチラリと出てきて「おっ!?」と思う、そういう隠し味的な要素だよ、ということですか?
近藤氏:
はい。あとは今後、新たなストーリーを追加していく際に、他のユニットとの出会いがなければ成長できなかったといったことも、きっと起きていくとは思います。なので、いつのまにか気づいたら全体がつながっていた、みたいな感じになるのかなと。
 |
──なるほど。では最後に、ゲームのリリースを楽しみにしているユーザーのみなさんに、一言お願いします。
桝井氏:
自分たちの知らない渋谷を冒険しながら、音楽とミクちゃんを一緒に楽しんでいただけたら、最高だなと思っております。よろしくお願いします。
近藤氏:
今回はキャラクターの設定を中心にお話ししたんですけど、それ以外のリズムゲームとしての部分なども、がんばって開発しておりますので。
この『プロジェクトセカイ』がきっかけになって、これまでボカロの音楽を聞いていたみなさんにも、何かしら「広がり」を感じてもらえるようになればいいのかなと思っています。僕らとしても、それに向かって全力でがんばりますので。なにとぞ、遊んでいただければと思います。(了)
 |
今回の取材の準備として、資料として受け取った『プロジェクトセカイ』のシナリオを読み進めながら、考えたことがある。
『プロジェクトセカイ』のストーリーで描かれているのは、音楽に対して真剣に向き合おうとしているキャラクターたちの姿だ。仲間と一緒にユニットを結成し、ライブハウスやステージなどでパフォーマンスを披露する。
その過程で彼女ら、彼らがさまざまな困難に直面した時には、「セカイ」にいるミクたちバーチャル・シンガーが、そっとその背中を押してくれる。
一方で今、2020年の現実世界に目を向けると、ドームツアーから日本各地のライブハウスまで、大小数え切れないほどの音楽イベントが新型コロナウイルスの影響で中止や延期になってしまい、大勢のアーティストの方々がその活動の場を奪われている。まさに未曾有の困難が音楽の世界に襲いかかっている時に、本作に登場するミクたちから伝わってくる優しさは、そうした音楽イベントの一観客の立場でしかない自分にとっても、ある種の救いのように感じられたのだ。
今回の取材の際に、近藤氏と桝井氏のお2人にこの感想をお伝えしたところ、「たまたま時流が重なっただけで……」という、ある意味で当然の反応が返ってきた。とはいえ、筆者がこのようなことを考えたのも、本作のストーリーが「音楽と人間の関わり」を、確かな視線で描き出しているからだと思う。
『プロジェクトセカイ』は、これまでの初音ミク関連のリズムゲームとはスタイルこそ異なるものの、音楽と人間の関わりを支える“初音ミク”という存在を明確に具現化した作品である。本作のリリース時には、ぜひ自身の目と耳と指先で、その感触を確認していただきたい。
【この記事を面白い!と思った方へ】
電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。
頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応
※クレジットカードにのみ対応
【あわせて読みたい】
【田中圭一連載:初音ミク編】ブルーグリーンの髪の少女は、やがてユーザーコンテンツの旗手となった。生みの親・佐々木渉がともに歩んだ10年、ともに歩む未来【若ゲのいたり】田中圭一先生による人気連載『若ゲのいたり』第7話もあわせてお楽しみください。生誕10周年を迎えたバーチャルシンガー『初音ミク』の生みの親・佐々木渉氏がゲストです。ひとりの少女がなぜ小さなクリエイター達に革命を起こしたのか? その歴史に迫ります。