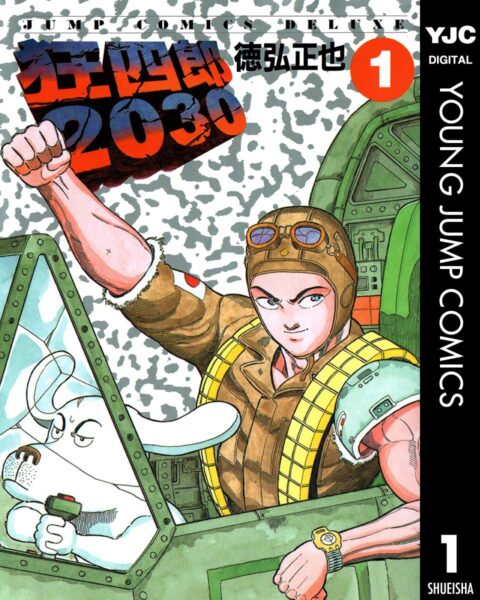知ってる人にはいまさらな説明になるが、電ファミニコゲーマーは、元々はKADOKAWAグループの中で立ち上がったサービスであり、ニコニコ動画の運営元として知られるドワンゴで運営されていたという歴史がある。
それが、ドワンゴの業績悪化とそれに伴うKADOKAWAグループの再編の中でサービス中止が言い渡されたものの、当時、編集長を務めていた筆者(TAITAI)が継続を希望。事業自体を譲り受ける形で会社を興し、いまに至っている。
普通だったら「袂を分かつ」みたいな見え方もする一連の動きなのだが、ドワンゴやKADOKAWAとの良好な関係は引き続き継続しており、インフラ部分は未だにドワンゴのエンジニアが担当していたりもする。サービス中止!という厳しい決断があった一方で、「これは良いメディアだから……」という温情めいたやり取りがあったからこそ、いま現在も電ファミが存続できているという背景があるのだ。
そうした中で、ドワンゴの創業者である川上量生氏からの相談が電ファミ編集部に舞い込んだ。なんでも、「久しぶりにメディアに出たい。電ファミでこそ、話せることがあると思う」「他のメディアでは話せない、本音の話をしたい」と言うのだ。
そこで電ファミでは、特別に川上量生氏へのインタビューを実施。ゲームの話題ではないものの、川上氏がここ最近行ってきた教育事業の話や、氏がドワンゴの会長やカドカワの社長を辞めた背景についてなど、普段は聞けないようなことまで踏み込んで聞いてみることにした。
内容としては、以前、4Gamerで行っていた連載「ゲーマーはもっと経営者を目指すべき!」のような、取り留めのない放談が中心となっているが、映画『シンゴジラ』の舞台裏や、ネットのコミュニティ論、教育論などなど、多岐にわたる興味深い話を聞くことができたので、ぜひご一読頂ければと思う。
 |
数年ぶりになる、川上氏との長時間に及ぶ対話(インタビュー自体は、途中の休憩も挟んで、合計10時間以上にも及んだ)から見えてきたのは、川上氏の根底にある「居場所を作る」というテーマかもしれない。
ドワンゴの創業からニコニコ動画の立ち上げ、そして教育事業。その裏には、誰もが一度は考える「自分の居場所」というものへの問題意識があった。
聞き手・文/TAITAI
写真/佐々木秀二
不登校の子たちが行きたい通信制学校を作ろう
──取材という形で川上さんにお会いするのは、本当に久しぶりですね。今日は、主にドワンゴが運営している教育事業「N高等学校(以下、N高)」について話をしたいと伺ってますが、なんでまた、電ファミという媒体でそれを話そうと思ったんですか?
川上氏:
本当に久しぶりですよね。いや、今回は、僕が約2年ぶりにインタビューなどを受けようと思ったんだけど、それをぜひTAITAIさんにやってほしかったんです。(※取材は2020年9月19日に実施)また、僕がここ数年、真剣に取り組んできた教育事業について、やっぱり立ち上げた自分がちゃんと話さないとダメだなと思って。
 |
──なるほど。でも本来であれば、それこそ経済誌などで話すべき内容じゃないんですか?
川上氏:
うん。もちろん、そちらで話す予定はあります。でも、ここでは、もうちょっと踏み込んだ話というか、本音を話すような場も必要だなと思って。それは電ファミがいいんじゃないかと思ったんです。
あとはね、僕がカドカワやドワンゴの代表を降りることになって、いろいろなものが整理されて、TAITAIさんを含めていろいろな人に迷惑をかけてしまったじゃないですか。だから、ちゃんと謝ってもおきたくて。その意味でも、あの時に犠牲になったTAITAIさんのところで語るべきだなと思ったんです。
──分かりました。ありがとうございます。では、ちょっとゲームには直接関係ないかもしれないけど、今日は良い機会なので、最近の川上さんの考えていることだったり、いまやってる教育事業について、いろいろ聞かせてください。
川上氏:
はい。なんでも聞いてください。
──これは、たぶん直接聞いたことはなかったと思うんですが、そもそも、なんでドワンゴで教育事業をやろうなんて思ったんですか? 最初に聞いたとき、僕は正直いって意味が分からなかったんです。いまの日本は少子化で子供は少なくなっているわけだし、市場としても小さくなっていくわけじゃないですか。教育に関してはまったく門外漢だったドワンゴが、なんで新規参入で入っていく必要があるんだろうって、立ち上げ当時は、とても疑問に思っていたんです。
川上氏:
まあ、まず、少子化で減るのは日本を出ない限りは国内全部(の市場)だから、そこはあんまり関係ないですよね。
──じゃあ、言い方を変えて改めてお聞きしますが、川上さんは教育事業のいったいどこに、勝算というか、可能性を見出したんですか?
川上氏:
それはやっぱり、「ウチがやる意義があるから」ですよ。
──意義ってなんですか?
川上氏:
というのもね、まず最初にドワンゴと一緒に学校を作りたいと言ってきた人たちがいたんです。彼らが言うには、「いまの不登校の子たちって、大体ネットにハマっている」というんですよ。
──まぁ、そりゃ現実社会で活動の場がなければ、ネットにそれを求めるのは自然ですよね。
川上氏:
うん。で、さらに「みんな、ニコニコを見ている」と言うんです。そりゃそうだろうなと。

──2013年〜2014年前後であれば、とくにそうだったかもしれませんね。
川上氏:
そうそう。だから、そんなニコニコが作る学校だったら、行ってもいいかなって子がいるんじゃないかって話だったんです。僕は、確かにそうかもなぁと思ったし、それだったら僕ら作る意義があると思ったんです。
要するにね、不登校の子たちが行きたい通信制学校っていうのがないんですよ。もっと重要なのは、友達に「自分はあそこに通ってるよ」と胸を張って言えるような通信制学校がない。そういう意味ではさ、ニコニコを見ているような子たちが行きたくなる学校を作る、彼らの居場所を作るというのは、むしろ本業じゃないかと思えたんだよね。

──なるほど。
川上氏:
そういう世間のイメージを変えるような取り組みっていうのは、ドワンゴがずっとやってきたことだし。たとえばニコニコだって、政治を議論する場になるなんていうのは最初は誰も想像してなかったじゃないですか。そういうものを作るのっていうのは、僕らは得意だと思ったんですよ。
──そう聞くと、ドワンゴがいま教育事業をやってるのも、なんだか自然な流れに思えてきますね……。
川上氏:
そうだよ。とても自然な流れなんだって(笑)
──いやでも、最初に川上さんから「教育事業をやるんだ」って聞いた時は、僕でさえ「え、なんで!?」って感じだったんですよ(苦笑)
N高は”ゆとり教育の理想”を体現した学校
川上氏:
そうだ。N高の話をするにあたって、言っておきたいことがひとつあるんです。N高は、本当に教育を改革するつもりでやっている事業なんだけども、それはたぶん、世間が思っているストーリーとはちょっと違うってことなんです。
──どういうことですか?
川上氏:
つまりね、みんなが思う構図としてはさ、文科省がいままで変えられなかったことを、民間企業が立ち上がって変えていくっていう、そういうものを想像していると思うんですよ。
──え、違うんですか?
川上氏:
全然違う。実はN高って、もっとも文部科学省の言ってることに忠実に従っている学校でもあるんです。
 |
──すいません、どういうことでしょうか。
川上氏:
つまり、みんな文部科学省の悪口を言うじゃないですか。教育が変わらないのは保守的な文科省が何もしないせいだという漠然としたイメージをもっていませんか? でも、実際は文科省は何もしないわけではなくて、かつてのゆとり教育とか、昨年、炎上した英語入試改革とか、いろいろ変えようとしてきたことに世論が猛反発して潰してきたという歴史があるわけです。
──何もしないし、やるときは、とんでもないことをやる。そういうイメージは確かにありますね。
川上氏:
そうでしょう? たとえば、ゆとり教育は日本の教育水準を下げただのなんだのって、すごく叩かれて潰されてしまった。その結果、何が起きたかというと、いまの子たちが苦しんでいる、詰め込み教育への回帰だったんです。あれは、ゆとり教育の否定で始まっているんです。
──そもそも、ゆとり教育って、1980年代以前の詰め込み型教育に対する問題提起(多様化する社会、価値観にそれだと対応できない)から生まれたものだから、むしろ戻ったということなんですかね。
川上氏:
そう。戦後の詰め込み教育の反省自体はどう考えても正しかった。でも、結果として世の中がゆとり教育を潰して、詰め込み教育は改善されるどころか、さらに強化されてしまった。そうした状況の中で、いまの若い子は本当に勉強が大嫌いになっている。いま、N高ってすごく褒められていることが多いんですけど、いまN高が力を入れているアクティブラーニングとかアダプティブラーニングとかって、ゆとり教育が目指していた延長線上にあったはずで、ゆとり教育が潰されてなければ、とっくに日本の教育にもっと取り入れられていたはずですよ。N高が、やっていることなんて、新しくもなんでもない。
──なるほど……。それは興味深いですね。
川上氏:
だから、みんな文科省が改革しようとしたときにさんざん叩いているくせに、教育が変わらない責任を文科省に押しつけるのはおかしい。世の中を変える改革なんて、すべて正しくやるのは難しくて、そりゃ間違いも起こりますよ。でも、それはまた直せばいいんであって、やるなと叩くのは違う。N高は、教育を改革する、という高い志を持ってやってるけど、それは反文部科学省ということではないよね。というか、なんだったら我々、むしろ文部科学省寄りですから(笑)。
 |
ゆとり教育は、文部科学省の改革派の夢の跡
川上氏:
ゆとり教育の話でいえば、ひとつ印象深いエピソードがあってさ。これは実話なんだけど、僕が結婚したときに、新婚旅行で嫁(※)と大喧嘩したんだよね。それも日本の雇用政策かなんかで(笑)。
※須賀千鶴:経済産業省に務める官僚。現在は、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター長を務める。
──その話は以前にも聞いたことがあります。
川上氏:
それで、新婚旅行中だというのに、本当にすごい険悪になったわけ。で、そのときに僕は「経産省の政策の悪口はぜったいに言わないようにしょう!」と決めたんだけども、文部科学省の悪口なら大丈夫だろうってことで、ゆとり教育をバカにした発言をしたんだよね。
──いやいや。
川上氏:
そうしたら、なんと嫁が泣き出したんです。嫁って人前で泣くような人間じゃなくて、これまでの結婚生活の中で、嫁の涙を見たのはそのときだけです。
──あらら。
川上氏:
彼女が言うには、ゆとり教育っていうのは、文科省が戦後の歴史の中で、抜本的に改革を試みた最大の取り組みのひとつだったんだと。何も変えたくない人もたくさんいる中で、文科省内でも改革派の人たちが集まって、ゆとり教育を推進したらしいんです。
──でも結果的に、失敗の烙印を押されてしまった……。
川上氏:
そう。世間に叩かれて、改革は撤回させられた。嫁の仲がよかった改革派の若手の多くも、その後、不遇を囲っている。そして、世間が叩いた結果、教育はよくなったかっていうと、その後のすべての改革に大きなブレーキがかかっただけだと、世の中はそれを望んだんじゃなかったはずと、彼女は泣いたわけです。
──何かことを起こすことがリスクにしかならないと、そうなっちゃいますよね。
川上氏:
僕がこのエピソードから得た教訓はふたつあって、ひとつは経産省だけでなく、政府のあらゆる政策の悪口は言わないことにしようということ。どこに地雷があるか分からない(笑)
もうひとつは、リスクとって改革に取り組んでいるひとの足を引っ張るのは、やっちゃいけないということです。
結局のところ、みんな、表面的な結果しか見ようとしないじゃないですか。とくに状況が悪いところだと、だいたい問題が起こってるのって、何もやらないからじゃなくって、なにか”やれない理由”があることが多いんです。
そういうところに切り込んでいって、火中の栗を拾うような人たち、問題が起こっているところで頑張る担当者っていうのは、とても危険な仕事をやっている人たちだと思うんです。
でも、そういう問題が起こってるところっていうのは、世間的にはすごく批判されやすくて。そのときに、火中の栗を拾いに行った人をみんなが叩いちゃう。でも、それってさ、何も生産的なことを生み出さないよね。
──本来、リスクを背負って火中の栗を拾いに行く人たちは、それだけ信念があってやっているわけですしね。
川上氏:
本当にそうなんだよ。でも、結果的には、ゆとり教育っていうのは失敗の烙印を押されてしまった。詰め込み教育が推進されるようになったわけだけど、ぶっちゃけ詰め込み教育っていうのは、いま不登校が増えている原因になっているよね。近年、不登校の子がこんなに増えているのって、当時みんなでゆとり教育を叩いたせいなんじゃないかって。

──う、それは……。
川上氏:
そもそも、いまの学校教育のほとんどって、文科省が推奨することをあんまりやれてないんですよ。
──具体的にはどういうことですか?
川上氏:
たとえば、N高では、村上ファンドの村上世彰さんを招いて金融教育をやったりしてるんだけど、あれね、新しい学習指導要領の中に「これからは金融教育を推進する」って書いてあるんだよね。あとは、ちょっと前に麻生太郎を呼んで講演をしてもらったんだけど、あれも「主権者教育をもっとやりなさい」という文科省の指導に則っているだけなんです。でも、あんまりどこもやってない。
──それって、ほかの学校ができないのはなぜですか?
川上氏:
やっている学校はあると思う。でも、ほとんどの学校にとってはめんどくさいだけで、やるメリットがないからね。でも、それは当たり前でさ。大きな変化をさせなくたって、授業料とかは毎月入ってくるわけじゃないですか。教育をビジネスと考えるのもどうかと思うけど、頑張ってやっても売上は上がらないし、先生の評価も上がらないし、インセンティブが働かないわけです。
──それよりも、いい大学に受からせたほうがインセンティブが働きますよね。
川上氏:
これは文科省だけじゃなくって、文科省も含めた教育業界全体の責任で考えるべきですよね。文科省だけの責任にするのはフェアじゃない。
そもそも、N高でやりたいことを調べると、だいたい文部科学省がやりたいこととして過去に書いてあるんです。でも、それが実際は教育現場でなかなか実行できないという事情が、過去にはあったということなんです。
だからN高は、もともと文部科学省が示していた可能性を、具体的に実施してみせて、それが結果を出すことで、もっと教育政策の実効性だったり自由度を上げるほうに貢献したい。
──なるほど。文部科学省の提示する方針を、小回りが効く民間企業が率先して実践することが重要ということですか。
川上氏:
文科省の指示通りにN高を運営しているつもりはないですが(笑)、でも、僕らがやったほうがいいと思いつくアイデアのほとんどは、とっくに文科省のだれかが考えていたことなんですよ。
『シン・ゴジラ』に協力した理由
川上氏:
そういえば、これは公の場では話したことがなかったと思うんだけど、文科省のこととかで嫁と喧嘩した直後ぐらいに、庵野さんから相談を受けたんだよね。
──『エヴァンゲリオン』の庵野秀明(※)さんですか?
※庵野秀明(あんのひであき):日本を代表するアニメーター、映画監督。代表作は『新世紀エヴァンゲリオン』、『シン・ゴジラ』、『トップをねらえ!』、『ふしぎの海のナディア』など。川上氏とは、スタジオジブリの鈴木敏夫氏などを通じて知り合い、意気投合。川上氏は、庵野氏が代表を務める株式会社カラーの取締役も務めるなど、とても関係性が深い。
川上氏:
そうそう。そこで、どういう経緯だったか、いま話したようなエピソードを彼にも話したんです。そうしたら、いきなり庵野さんがね、実はそういう政治だとか官僚を単純に悪いって叩くんじゃなくて、政治家とか官僚たちが主役で活躍する日本で一番有名な怪獣が出てくる映画を撮ろうと考えている最中だと話し出したんです。
──おおお。それが『シン・ゴジラ』だったんですね。

川上氏:
そうなんですよ。で、それだったら喜んでってことで、僕と嫁が庵野さんの取材(映画作り)に協力することになった。だから、『シン・ゴジラ』制作における政治家とか官僚への取材っていうのは、基本的には僕らがアレンジしていたんですよ。
──川上さんが『シン・ゴジラ』に企画協力という肩書きで参加していたのは知っていましたが、そういうことだったんですか。
川上氏:
うん。でも、取材に協力をしてくれた官僚の方々の名前は表に出ていません。映画のスタッフロールに載っていたのは、官房長官をやっていた枝野幸男さんと、あとは防衛大臣をやっていた小池百合子さんの二人だけ。官僚っていうのは、そういうところに名前を載せるといろいろと差し障りがあるので、嫁の名前も当然載っていなかった。
──そうだったんですね。
川上氏:
でも本当は、『シン・ゴジラ』の取材で、一番お世話になった官僚の方がいたんです。井上宏司さんというんだけど、彼は、実は東日本大震災のときに官房長官秘書官だった人なんです。だからあのときに官邸にいた、まさに現場にいた官僚。
──それは、かなり凄い人ですね。
川上氏:
だから、井上さんが、震災のときに何があったのか、官邸の雰囲気とか状況の話をいろいろと助言してくれて。幹部レクってこうやるんですよとデモンストレーションして見せてくれたり。あとはロケ現場にも来てくれたことがありました。映画の中で(首脳陣が集まる)会議があったじゃないですか。
──総理や大臣たちがずらりと並んだ。
川上氏:
官邸では、会議で総理が入るときに、みんなが起立して総理が座るのを待つとか、いろいろな作法があるんです。ちょうどロケを見学にきてくれていた井上さんが飛び入りで、起立と着席はこんな感じでやります、タイミングはこうですって、演技指導もやってくれたんですよ。
──なるほど。だからあの映画には、あんなにリアリティがあったのか。

川上氏:
井上さんは、震災のときの官邸の現場にいたから、日本の機密とかは相当知っているはずだし、日本にとってとても重要な意志決定にも関わっているはずです。でも、そういうのって家族には、全然、話すことは出来ないわけです。まあ、それは当たり前なんだけど、官僚というのは重要な仕事をやっていても家庭では分かって貰えず、ただ「家に帰ってこないお父さん」とかになっていることが多い。井上さんには、なんのお礼もできませんでしたが、でも、この『シン・ゴジラ』に協力したという話をご家族にすれば、井上さんの普段の活躍が分かってもらえるんじゃないかって、嫁は僕に話していたんです。
──なるほど。数少ない家族サービスというわけですね。
川上氏:
残念なことに、井上さんはその後、退官して、まだ、それほどたっていないのですが、今年の6月に亡くなられてしまいました。それで、うちの嫁が告別式にいったら、井上さんが『シン・ゴジラ』の撮影に協力していたのは、ご家族も知らなかったみたいなんですよね。そんなことまで家族にも黙っていた。官僚っていうのは、こういう人たちなんだって、凄く思い知らされましたよね。
でも、じつは井上宏司さんは『シン・ゴジラ』の政府の描写のリアリティには、一番、貢献してくれたひとだったんです。それはちゃんと事実として残そうと、庵野さんも言ってくれて。この取材で話そうと思いました。