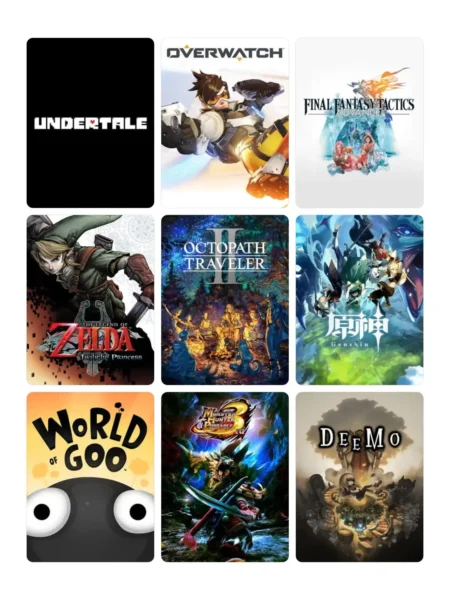ニッチでも深く刺しにいく……推理アドベンチャーゲームの可能性
梅田:
新作の「レインコード」はどうなんですか? それこそ「デスカムトゥルー」とか「ワールズエンドクラブ」のころからずっと作ってきたわけじゃないですか。
小高:
「ワールズエンドクラブ」よりも先に作り始めてましたね(笑)。
梅田:
ですよね(笑)。制作期間が長いからすごくこだわって、作りたいものができた作品なんじゃないかなと思っていますけど。
小高:
6年かかりましたから暗中模索が長かったんです。いままでにないような、システムというよりゲームとしての体感をどうゲームに落とし込むのか、答えが見つかるまでに時間がかかりました。
梅田:
ゲーム開発ではありがちですけど、並行していろんな開発を走らせるなかでの調整はあったんですか?
小高:
謎解きパートの「謎迷宮」はけっこうコロコロ変わりましたね。ビジュアル方面から攻めるのか、シナリオ方面から攻めるのかの綱引きがあって、そこの探り合いで時間かかりました。まあ最終的には物量ですね。僕がどうこうというより、物量が非常に多いので、そこで単純に時間がかかったというのがあります。
梅田:
ということは、6年の期間は物量に割いていたという感じですか?
小高:
謎迷宮に関して言うと、固まったのは1年ぐらい前です。いままでにないシステムだし、どういう体感になるんだろう、とずっと不安でしたよ。スタッフ内では、「謎解きなのになんでアトラクション的なことをやる必要があるんだ?」という声も出てきまました。その中で「いや、これがいいんだよ」と言い続けながら、とはいえ本当にこれでいいのかな、みたいな(笑)。
梅田:
最も大変だったことはなんですか?
小高:
謎迷宮というものを言葉で説明しても誰にも伝わらないということですね(笑)。
梅田:
なるほど(笑)。
小高:
スタッフに「事件を解くまでのフローチャートをそのままダンジョンにしたものなんだよ」と言っても「えっ?」と。しかも、これをどうユーザーに伝えたらいいかも分からない(笑)。けっきょく開発時に言語化できていなくて、メディアに載った記事を見てやっと腑に落ちたんです。“推理アクション”というジャンルには謎を解くという快感と、ものを壊したりするアクションの快感、それを同時に味わえるのが謎迷宮なんです、と。最初からこの説明ができていればよかったんですけど、僕の語彙力では出てこなくて(笑)。

梅田:
「ダンガンロンパ」でも思ったんですけど、小高さんの作品はアドベンチャーゲームが推理だけで進んでいくとか、テキストだけで進んでいくということに対してのアンチテーゼがありますよね。
小高:
まさにそうで、特に今回はテキストを読んでじっくり考えている人だけじゃなくて、それを見ている周りの人も楽しめるような内容にしたかったことがひとつあります。そこが発明できれば、アドベンチャーゲームの可能性はもっと出てくると思っていたので。
梅田:
3Dの演出は具体的にどういうところにこだわったんですか?
小高:
アドベンチャーゲームって立ち絵とセリフを出せば成り立つじゃないですか。なんですけど、基本的に「レインコード」では全部3Dのモデルに芝居を付けていて。芝居が付いているからこそ伝わる臨場感とか、キャラの良さとか、アニメを見ているような感覚でゲームを進めてほしい……そこが一番こだわった部分ですね。
梅田:
いまってゲームだけで言っても「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」が出て、「FINAL FANTASY XVI」が出て、「ディアブロ IV」も出て……と、これだけ人の余剰時間に対してコンテンツが飽和している状況ですけど、小高さんはクリエイターとしてどう感じてますか?
小高:
うーん……話をひっくり返すようですけど、僕はそもそも余剰時間でやるようなゲームを作っていないと思うんですよ。
梅田:
やりたいなら時間を空けろ、と(笑)。
小高:
そうですね。だって謎迷宮ですよ? よく分からないですよね、と(笑)。ある程度情報を得て、面白そうだなと思ってやってくれるわけだから、その人たちに興味を持ってもらえるような要素をどれだけ入れるかなんですよ。単純にいまはワールドワイドになってきているので、ニッチでも深く刺しにいって世界的に売れれば昔よりも広く売れるようになります。
梅田:
満遍なく刺しにいこうと思ってもすでにいろんなものがあるから、逆に誰にも刺さらない。けど、深く刺しにいけば刺さる人が少数でもワールドワイドにいるから、ニッチでも合計数は十分多いということですよね。
小高:
こっちからお客さんを迎えに行くというより、こっちに来させるというか。その感覚がずっとありますね。
 |
“外し”のないAIが作ったものに心を刺す力があるとは思えない
梅田:
僕はすごく覚えているんですけど、小高さんは「ゲームのシナリオもAIが書くようになるから」と2年前から言っていたんです。いま実際にその世界線に近くなってきたじゃないですか。
小高:
まだじゃないですか? つまらない町民のセリフだったら書けるかもしれないけど、シナリオは正直難しいんじゃないかなと思います。
梅田:
2年前と言っていることが逆になってる(笑)。つまりセリフとかキャラに魂を吹き込むとか、作家性を出すようなところが難しい、と。
小高:
僕の場合ですけど、求めているのはけっこうリズム感が変わる瞬間みたいなところで、たとえば「パルプフィクション」じゃないですけど、ジョン・トラボルタが主人公かと思ったら途中で死んでしまうみたいな、ああいうところにロマンを感じるんです。「スター・ウォーズ」とか、王道の展開のモノだったらAIを使えるかもしれないけど、僕が目指してるのはそっちじゃなくてタランティーノだから。
梅田:
そう考えると “ネクスト小高”じゃないですけど、新たなシナリオライターや若手クリエイターがこのAI時代で、どういうスキルを磨けばいいと思います?
小高:
スキル、そうだな……。若い人に伝わるか分からないですけど、「ドグラ・マグラ」みたいなアプローチで攻めるのがいいんじゃないかな、と。「狂人が書いているのか、これは」みたいな(笑)。
梅田:
まさに「ダンガンロンパ」がそうですからね(笑)。じゃあAIがどれだけ進化したとしても、ゲームクリエイターの居場所は奪わない、と。僕が想像していたのは「AIを使えば誰でもゲームクリエイターできるよ」みたいなことを言うかな思ったんです。少なくとも2年前はそのテンションだったので(笑)。
小高:
そうですね。アイデア出しみたいなことも、別にAIにやってもらわなくても自分の頭の中でシミュレーションできるし、そこにAIの力は必要ないかな。そもそもAIに僕の心を刺す力があるとは思えない。
梅田:
たしかに。言ってもディープラーニングなので、世の中に出ているものを徹底的に学習したうえで最適なものを出しているから、そりゃそうですよね。
小高:
だから、AIが“外し”を覚え始めたらいよいよ分からなくなってくる。AIがタランティーノみたいな会話劇を書いてきたり(笑)。
梅田:
そうですね(笑)。
小高:
でもいまはAIが流行ってますけど、その揺り戻しが来るかなとも思っていて。逆にAIじゃない、人間が作ったものがブランドになることも想定できる。AIが進歩すればするほど人間が作った人間らしいものが流行るんじゃないかな、と。
梅田:
ああ、それは感じます。そもそも小高さんは常に逆張りですよね(笑)。本当に世の中の風潮としてAIが流行り始めたから……。
小高:
ヤバい、逆だ、と(笑)。僕はサブスク派じゃないです、みんな映画館に行こう、いや逆にTSUTAYAでレンタル、カッコいいじゃん、みたいなね。
梅田:
そう言いつつ、また2〜3年経ったら逆になってるんですよね?
小高:
AIサイコー、みたいな(笑)。いや、AIはすごいと思うし、面白いと思うけど、AIで騒ぐクリエーターはたかが知れているじゃないですか。じゃあその作品見せてよ、と思うんです。AIを使って作った「ワンピース」以上にクソ面白いものを。
梅田:
たしかにそうですよね。
小高:
このAIの話って、やってる側の人はみんな分かっていると思うんですけど、出資を受けやすいんですよ。AIみたいな新しい技術を使えば。だからそういう山師かなと思ってしまうというか。
梅田:
AIがいかに大きいマーケットか説明して、これが将来すごくなるよということで出資を受ける、と。
小高:
しかも現時点で答えが出ていないから、なんとでも言えますしね。
 |