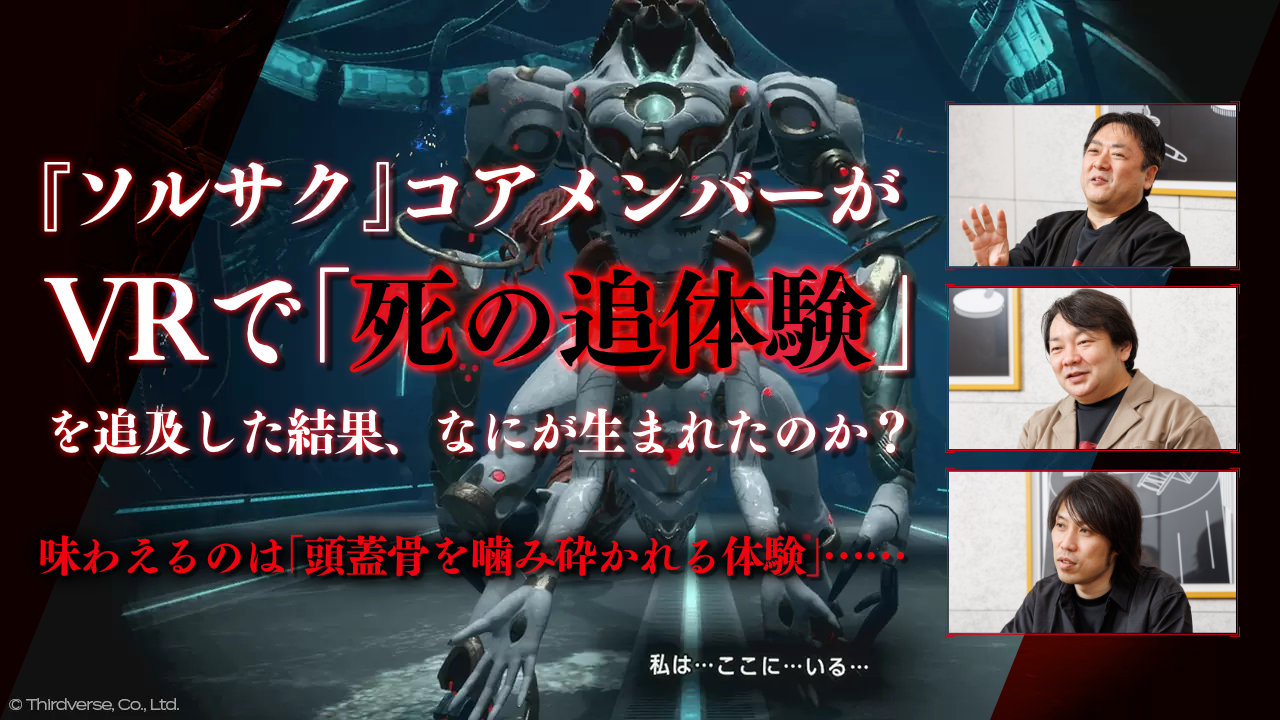このゲームを表現するうえで一番向いているのがVRだった
──プロジェクトが本格始動から約1年での発売ということですが、かなりスピーディーですよね。あと1、2年後の発売だったとしても不思議じゃないと思うのですが。
鳥山氏:
プロトタイプ開発が先行していたというのもありますが、なによりもVRのハード側の進化に合わせる必要があったんです。2年も3年もかけたら古くなってしまう。なので、企画時点からゲーム内容やボリュームなども考慮して設計しました。
本当ならコンシューマゲーム並みのボリューム感を出したいところなのですが、Meta Quest 3が想定よりも早く発売されたことや、他のVRゲームのボリュームや価格帯などを考慮しました。それでも他のVRゲームと比べてもボリュームが大きめのゲームになっていると思います。

下川氏:
でも「VRゲームを作っている」という感覚はあまりないですよね。もちろん、VRゲームだからこそできる体験を多少意識はしましたが、それでもコンシューマーゲームとしても一人前に戦えるようなものを作ったつもりです。
鳥山氏:
VRゲームを作るというよりも、このゲームに一番向いてる表現がVRだった……という方が近いですね。表現したいものがあって、その絵や音楽、ストーリーをVRで表現したのが今回の『ソウル・コヴェナント』になっています。
──なるほど。ただ一方で、「VRゲーム」というだけでハードルを高く感じる方も少なからずいらっしゃるかと思われるのですが、本作に対するユーザーの反応はいかがでしょうか?
鳥山氏:
ありがたいことに予想以上の反響をいただいています。
現状のVRゲームは身体を動かすことに重きを置いたゲームが多いなか、今作のようなストーリー体験を重視したゲームを求めている方の多さに驚きました。
また、本作は『ソルサク』のメンバーが関わってるということもあり、そのファン層がポジティブな反応をしてくれているのも感じますね。
岡村氏:
そうですね。「こういうゲームを待ってました!」という声も多くいただいています。
VRならではのアクション体験とゲームの魅力である物語としての楽しさをうまくマッチさせた状態でお届けできるゲームを作れていますし、それを期待していただけるようなプロモーションもうてているのではないかと思います。
鳥山氏:
さまざまな偶然が重なった幸運の賜物でもありますが、「このゲームではこんな体験が出来ます」という従来のVRゲームの売り出しかたではなく、コンシューマー作品のようにストーリー部分を大きく見せるようにしていたのが、うまく働いたのではないかと考えています。
下川氏:
僕らはもともとコンシューマー作品を作っていたこともあり、ゲームの作りかたが良くも悪くも作りかたがコンシューマー文法なんです。そのメンバーがVRと向き合ってチャレンジしてみた。それが今回は良い方向に働いてくれたのだと思います。
VRゲームでは快適な操作性を求めすぎてはいけない
──VRゲームと意識しないで作られたとのことですが、とはいえ、ハードとしてはVRで遊ぶゲームということで、コンシューマー作品と作りかたの違いはあるかと思います。開発において、VRゲームだからこそ苦労した点がありましたら教えていただけないでしょうか。
鳥山氏:
VRの場合、プレイヤーがどこを見るのも自由なので、目の前で重要なイベントが起きていたとしても後ろを見ていたら気づいてもらえない。大事なシーンでよそ見しないように、どう視線を誘導するかについてはずいぶん悩みました。ストーリー重視なゲームなのでなおさらです。
また、コンシューマーだとボタンひとつ押せば済んだ操作も、VRでは実際に手を動かしたり掴んだりすることでゲーム内の行動に反映されるわけです。この手を使っての作業をどう表現するか、伝えるかの試行錯誤はVRゲームならではでした。
岡村氏:
操作性について、開発に慣れてきた時期にチームが陥った問題なのですが……つい、面倒くさくないように作ろうとしてしまうんですよ。
──面倒くさくないように、ですか。操作性が快適なのはゲームとして良いことのように思えますが、なぜそれが問題なのでしょう?
岡村氏:
簡単に押せる位置にボタンを配置したり、頭を動かして視点を移動させなくていい範囲でイベントシーンを展開させたりすると、せっかくVRで360度見られる環境なのにまるでVRの中でモニターを見ているような体験になってしまうんです。
真後ろにボタンを配置するのはさすがに大変ですが、ある程度は身体を動かして普段体験できない映像体験をしてもらったほうがVRならではの楽しさが味わえるんですよね。
ずっとコンシューマー作品の開発をしてきたメンバーだからこそ、快適な操作性を求めてコンパクトに作ってしまいがちだったんです。
──快適すぎるとVRの醍醐味である臨場感や没入感が薄れてしまう……というのは興味深いお話ですね。
岡村氏:
スマホゲームの場合は「快適なプレイのために、いかに指が届く範囲にボタンを配置するか」が重要ですけど、VRゲームは逆に「ちょっと手を伸ばすことで体験できる面白さ」が大事だと思うんです。
鳥山氏:
バトルに関しても、今作では武器の変形システムがあるんですが、コンシューマーだったらワンボタンで変形するところを、わざわざ両手で握って操作する必要があるように設計しています。
岡村氏:
棒を振り回してチャンバラをしたり、傘で漫画の主人公の必殺技を真似したり、子供のころ夢中になっていた「ごっこ遊び」が本作のコンセプトとしてあるのですが、「両手で握って変形する武器」というのはオモチャでもあまりないので、そういう体験をVRでできるのは価値があるのかなと。
鳥山氏:
そのあたりは下川さんがすごくこだわってくれましたよね。
下川氏:
そうですね。コンシューマーのアクションゲームだったらノウハウが蓄積されていて、ある程度パターン化されているのですが、新しいハードであるVRだとまだ最適なゲームデザインが確立していないんです。そこが伸びしろでもあり難しいところでした。
武器の柄の部分に関しても、デザインをバイクのハンドルのようにして、説明がなくとも何となく「掴んでみる」行動をプレイヤーが起こすような見た目にするなど、そういう試行錯誤の積み重ねですね。
岡村氏:
「こめかみの前方を押してください」とメッセージを出しても「どこを押せばいいの?」と思ってしまうじゃないですか。
けれど「拳型のアイコン」を該当位置に配置すれば8割くらいの人はそこを押してくれる。そういう工夫の積み重ねでプレイへの導線が変わってきますね。
下川氏:
VRの場合、プレイヤーそれぞれの骨格も影響してくるのが難しいところです。僕はけっこう手が長いので、開発中に他のメンバーと意見が食い違うときもあって。
岡村氏:
他のメンバーが快適に遊べているところでも下川さんが遊び辛いと感じる部分があって……みたいなことはありましたよね。
でも外国の方は下川さんの体格に近い方が多いので調整が必要で、どの体格でも気持ちよく遊べるところを探るというのはコンシューマーにはない経験でした。
下川氏:
この点については、歴史を積み重ねていけばVRゲームのお作法ができてくるのかと思いますので、今だからこその課題な気がしますね。
「10年前の自分と戦っている気持ち」で挑んでいるストーリー演出
──ここからはより具体的なゲームの内容についてお聞きしていければと思います。『ソルサク』では本を読み進めるようなストーリー展開でしたが、今作『ソウル・コヴェナント』ではどのように展開されるのでしょう。
下川氏:
VRに特化したバトルに対して、ストーリーは本を読み進める『ソルサク』に近く、日記を読んでいくスタイルにしました。
「本を読み進めてストーリーを進行させる」というのは『ソルサク』のときに岡村さんとふたりで作った発明かなと思っているので、今ならさらにブラッシュアップしたものが作れるだろうと。
岡村氏:
今回はプラネタリウムのようにしたいというイメージがありました。
プラネタリウムのようなドーム状の空間に記憶の断片が広がっていて、プレイヤーは自分の意志で視点を動かしながら物語を読んでいく。そんな表現をしたくて、開発メンバーたちと相談しながら作っていきました。
鳥山氏:
下川さんのシナリオをVRならではの体験でどう表現すればいいのか考えていたときに、たまたま子供と一緒にプラネタリウムに行く機会があったんです。夜空の映像が流れ、解説してくれる語り部の方がいて「これだ!」と思いついて提案してみたのがきっかけでした。
VRゲームとの相性もよく、ストーリーが自然と入ってくるので非常にマッチしているなと自分では思っています。
岡村氏:
プラネタリウムを含め、ストーリーの演出についてはかなりこだわって制作しました。
大切な人が最後のセリフを言うようなシーンでは少しずつキャラクターの表情が浮かび上がる表現にしたり、敵が大量に襲ってきて囲まれたシーンでは広く見せて囲まれている状況を強調したり、いろいろと検証を重ねながら少しずつ調整して……。
鳥山氏:
めちゃくちゃ調整されてましたよね。この演出のこのフレームはこう調整しましょう、とかそういうレベルです。「そこまで調整するの!? もういいじゃない?」と個人的には思っていました(笑)。
ただ、その何フレームかの調整で間違いなく受ける印象が変わるので、そういった部分のクオリティは岡村さんが入らなければ実現できなかった部分ですね。
岡村氏:
正直、10年前の自分と戦っている気持ちです(笑)。
下川氏:
それはすごく伝わってきました。『ソルサク』にハマってくれて、今でもファンでいてくださる方々がどこに魅力を感じてくれているのか……それってやはりストーリーなわけじゃないですか。岡村さん自身、それはわかっていると思うんです。
もともと『ソルサク』はストーリーに注力する予定ではなかったんですよね。そんななか、当時、若造だった自分が「ディレクターをする以上、自分の色を出さないでどうするんだ!」と、岡村さんに相談したのがきっかけでストーリーを作りこむようになったんです。今でも覚えていますよ、岡村さんから「予算はないが任せてくれ」と言われたことを。
だけど今では10年以上愛してくださるファンがいるわけじゃないですか。「その期待に応えられなかったら終わりだ」というのは僕もそう思いますし、岡村さんからも同じ言葉を聞きました。それを考えると結構ピリピリしながら作っていたのかなとは思います。
──「10年以上愛してくれている」という熱烈な想いは嬉しい反面、プレッシャーにもなりますよね。
下川氏:
少し余談になるのですが、じつはイベントシーンを作っている開発メンバーのひとりが、中学時代に『ソルサク』を遊んでいたユーザーなんです。
捕食シーンの絵コンテを映像に起こす際の担当がその子だったんですけど、音がない絵だけの状態だったので、パスタを買ってきてボキボキに折ることで「頭蓋骨を食われる音」を録音していて(笑)。熱量とガッツが本当にすごいんです。
鳥山氏:
そのメンバー以外にも、『ソルサク』のファンだった若い子が開発メンバーにいて一緒に仕事をしています。自分も年をとったなあ……と思う反面、当時の僕らが目指していた想いを引き継いでくれるメンバーたちがいるというのは非常に心強いです。
こういう巡り合わせがあったからこそ、今作のストーリーを作り上げることができたんじゃないかなとも思います。