辻本憲三氏の言い間違えでカプコンの歴史は大きく変わった?
──1984年に『バルガス』でアーケードゲームに参入したのち、1985年には『1942』で家庭用ゲーム(ファミリーコンピュータ)に参入しています。
岡本氏:
カプコンが家庭用ゲーム市場に参入するときに、辻本さんがアーケードとコンシューマーでチームを分けることにしたんです。それで辻本さんから「どっちをやりたいか」と聞かれて、藤原がアーケード、僕がコンシューマーと答えたら、なぜか藤原がコンシューマーで僕がアーケード担当になって(笑)。
このあいだ藤原に会ったときに「あのときの担当割り振りってなんだったんだろうね」という話になり、「あれば8割方、言い間違いだった」という結論になりました(笑)。
──その言い間違いによって、ゲーム業界の歴史が変わっていますよね(笑)。
岡本氏:
そうですね。ですから結果的に辻本さんが正しいと言えるのですが、「なんで希望と真逆の担当になったんだろう?」といまだに思うときがあります(笑)。
──その選択があったからこそ、『ストリートファイターII』が生まれたわけで……。
岡本氏:
たまたまですよ、たまたま。1作目の『ストリートファイター』は西山隆志さん【※】が、経営会議のときに考えたんです。僕の隣りに西山さんが座っていて、暇だから企画を考えていたんですよね。そのときのコンセプトを見て、「それ、めっちゃおもしろいやん! やりましょう! 絶対売れますよ!」と生まれたのが初代『ストリートファイター』だったと。
※西山隆志:
『ストリートファイター』ディレクター。アイレム所属時代に『スパルタンX』を手がけ、1980年代以降の多くの格闘ゲームの原型を生み出す。その後カプコンに入社し、『闘いの挽歌』、『ストリートファイター』を手がけたのち、SNKへ。SNK時代には『餓狼伝説』、『龍虎の拳』、『ザ・キング・オブ・ファイターズ』などを開発。2000年にディンプスを設立し、代表取締役社長を務めている。

──1作目の『ストリートファイター』は対戦は可能であったものの、ひとりで楽しむ内容だったと思います。一方で、『ストリートファイターII』は対戦に特化していますが、1作目からの発想の転換は何がきっかけだったのですか?
岡本氏:
僕も初代『ストリートファイター』は大好きなんですよ。自分のゲームの作り方のひとつが、「大好きなゲームのどこがいけないのか?」を分析し、それを修正していくやり方。『ストリートファイター』の企画はすばらしくて、大型のキャラクターがふたりで戦って対戦もできるって最高じゃん、と。ただ、なんで「みんな対戦しないんだろうと?」という疑問が出てきたわけです。
『ストリートファイター』はアップライト筐体とテーブル筐体があり、アップライト筐体は加圧ボタンのため、ボタンが硬すぎるとか、波動拳とかの必殺技を出すのが難しいといった問題があったり、必殺技が出たらそれはそれで威力が高すぎて当たったらほぼ勝ちになってる。じゃあ、必殺技がバンバン出せて相手との駆け引きが生まれるようなゲームのほうが楽しいよね、と気づいたわけです。

岡本氏:
『ストリートファイター』の必殺技の出しにくさは、プログラムを解析してわかりました。加圧ボタンを採用していたため、押したときの強弱を圧力センサーが感知するボタンだったんです。ボタンを押すと圧力がかかり、手を離すと圧力が戻っていってそのときにボタンを押したことになる。押したときではなくて離したとき、というのが一般的な感覚とズレがあって、必殺技も出にくかったわけです。
『ストリートファイターII』では、ボタンのオンとオフの両方のタイミングで必殺技が出るようにしたんですが、その結果、アッパーキャンセル昇龍拳のような技が可能になってしまいました(笑)。

──通常技のキャンセルは想定外だったものの、あえて導入したと聞いています。
岡本氏:
ゲームがおもしろくなるならそれでいいんですよ。必殺技が出やすくなったことで威力を下げて、一撃必殺じゃなくなったことによって対戦が広がっていく。必殺技が当たったら終わり、だと対戦にならないですからね。あとは、体力が残り少なくなると、ダメージを受けた時のゲージの減りが少なくなるようにしました。
──俗にいう根性値【※】ですね。
※根性値:
体力が減少するにつれて受けるダメージが減るシステム。『ストリートファイターII』では、体力ゲージが半分以下になると発動する。
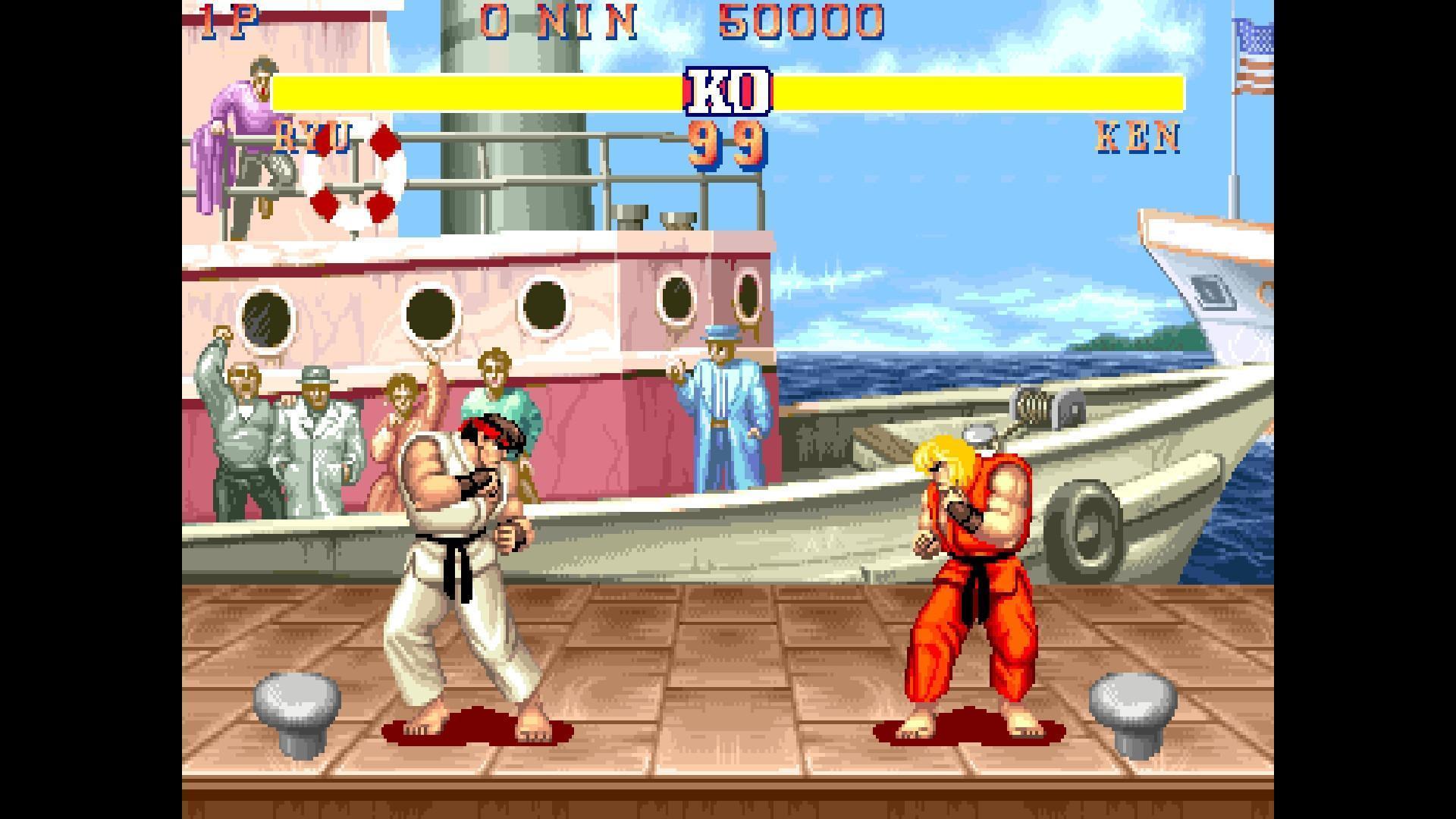
岡本氏:
最初は攻撃を当てるたびにどんどんゲージが減るんですが、後半はあまり減らなくなっていく。なぜこのシステムを入れたのかというと、対戦したあとに「けっこう削ったんだけど負けちゃったな~」と思えるじゃないですか。
相手の体力がぜんぜん減っていないと対戦したくなくなりますが、たとえば3分の2くらいまで削ることができれば「つぎは勝てるかも?」と善戦したと感じられるわけです。そうなれば「再戦しよう」という考えにつながりますよね。
──岡本さんが子どものときにやられていた、平等に楽しめるハンディキャップ、ローカルルールの設定に近いものがあるかもしれませんね。
岡本氏:
そうですね。みんなが楽しめる、負けた人も満足できる、という考えからの発想です。
おかげさまで『ストリートファイターII』発売後、どこのゲームセンターも10台くらい筐体を置いてありましたからね。ただ、『ストリートファイターII』も最初はそんなに売れていなかったんですよ。稼働開始すぐのころは誰も対戦してくれてなくて、みんなひとりでCPUを相手に遊んでいたんですね。ひとりで遊んでいると1日に100コインくらいしかインカムが稼げない。これが、シューティングゲームだと1日に150~200くらい叩き出すわけですよ。さらに、プレイヤーがうまくなってくるとプレイ時間も長くなるので、一部のゲームセンターでは買い控えが起こっていました。
対戦プレイがあっても、やはり知らない人の隣りに座って遊ぶというのは、当時はまだ抵抗があったわけです。そんななか、とあるゲームセンターのバイトの子が、向かい合わせた2台の筐体で遊べるように設置してくれた。当時の筐体は電力が少なくて画面が暗くなってしまったりもしたんですが、反対側に座って対戦しやすくなったことで「このゲームおもしろいぞ!」と話題になったんです。
その後、ゲーメスト【※】が気に入ってくれて扱ってくれて、対戦格闘が大ブームになったと。我々開発がやったわけでなく、マーケティング担当ががんばってくれた結果ですね。そのあと、コンシューマーに移植するのはめちゃくちゃたいへんだったらしいのですが、そこは藤原ががんばってくれて。
※ゲーメスト:
新声社から発行されていたゲーム情報誌。1986年創刊。アーケードゲームを専門に扱っており、専門性の高さや攻略の細かさなどが高い評価を得ていた。
──さまざまな要因によって広がり、対戦格闘ブームが生まれたんですね。
岡本氏:
ただ、僕はじつは格闘ゲームが好きじゃないんですよね。格闘技は好きだけど、趣味で格闘ゲームはプレイしない。本来の格闘技とは違うというのはわかっていながら、ゲーム好きじゃない僕でも遊べるのが格闘ゲームであるべきなんです。自分が好きじゃないゲームを作ることを心がけているわけですね。僕は本当はシミュレーションゲームが好きなんですが、そのジャンルは作っていないんです。もしシミュレーションゲームを真面目に作ることがあれば、こだわり過ぎてものすごくオタクっぽい内容になると思います(笑)。
藤原氏が残した『バイオハザード』
──カプコン在籍中を振り返って、とくに印象に残っているタイトルはありますか?
岡本氏:
助けられたのは1996年に発売した『バイオハザード』ですね。それ以前は言葉を選ばずにいうと「自分ひとりががんばっていれば何とかなる」と思っていました。そんななかで、『バイオハザード』は僕がまったく関与せず、藤原が生み出してくれたタイトルでした。
藤原がカプコンを辞めたのは「コンシューマーでオリジナルを作っても赤字になる、移植だけでいい」と言われ、「それだったらゲームクリエイターじゃないな」と思ったかららしいんです。僕も「ナンバリングタイトルだけを作れ」と言われていたので、藤原も同じようなことを言われていたんですね。
そんな状況で藤原が作ったのが、『アローン・イン・ザ・ダーク』に影響を受けた『バイオハザード』です。ただ、作っている途中で藤原が急に辞めてしまって、僕が面倒をみることになりました。

岡本氏:
藤原から開発のバトンを引き継いでテスト版の『バイオハザード』を遊んでみたら、とにかく操作が難しくて……。
操作方法のアイデアが、画面に対してスティックの操作通りに8方向に動くパターンと、キャラが向いている方向に対して動かすラジコン操作があったんですね。最初はラジコン操作を酷評したんですが、しばらく遊んでいるとおもしろくなってきて、「ラジコン操作のほうがいいかも」となったんです。
もちろん、直してほしいところは提案しました。これは海外版では対応していなくて日本版だけですが、銃を撃つときに方向をしっかりと合わせないと当たらないところを、オートエイムに修正しています。また、当初はインクリボンひとつで1回しかセーブできなかったのですが、「これだとゾンビから生き残るのではなくて、インクリボンを探すゲームになってしまう」と伝えて、複数回セーブできるように修正しています。とはいえ、ゲームとしてのバランスは最初からものすごくよかったんですね。
藤原の遺産だと思うと同時に、『バイオハザード』を残してくれたことがいまのカプコンを作っているのだと思っています。
ただ、僕が藤原に「辞めようと思っている」と話していたのに彼が先に辞めちゃったから、裏切られたという気持ちもありました。じつはずっとわだかまりがあったのですが、このあいだ会ったときに藤原が「俺はそれとは関係なく辞めるつもりだった」と。いやいや「それ最初に言ってくれや」と(笑)。そう返したら藤原が「でもそれを言ったら岡本が先に辞めてたよな?」と伝えてきて「なるほど、たしかに」となりました(笑)。
──そのタイミングで、岡本さんはアーケードとコンシューマーの開発部門をふたつ同時に統括することになったのですか?
岡本氏:
両方ですね。だから、給料上げてくれと(笑)。『バイオハザード』が完成して「さあ売るぞ」となったときに、「30万本売れるか売れないか」みたいな話になったんですね。前評判があまりよくなくて、発注が少なかったんです。当時、長期スパンで売れるゲームはほとんどなく、発売日に売って翌日に再受注してもう一度売り、たいていがそれで終わりという状況だったんです。
運がよかったのが、プレイステーション用ソフトだったので、媒体がCD-ROMだったということ。カートリッジの場合、発注から1ヵ月か1ヵ月半くらいかかるのですが、CD-ROMはすぐに作れるんですよ。メディアで取り上げられたことからタイトルの認知が広がっていき、毎週1万5000本ずつくらい出荷していって、最終的には国内だけで100万本を突破しました。
作り上げたチームメンバーもすばらしかったですし、三上(三上真司氏)【※1】や神谷(神谷英樹氏)【※2】といったスタッフへの感謝はもちろんあります。ただ、僕としては『バイオハザード』を残して辞めていった藤原得郎の思いを受け継いだという気持ちが強くて……。カプコンを去った藤原が外で飯を食べていくためにも、『バイオハザード』は売れなくてはならないと思って、だいぶ気合が入っていました。
※1三上真司:
『バイオハザード』ディレクターを担当。その後も数々のタイトルを手がけ、『バイオハザード4』でもディレクターを務めている。2005年にカプコン退社後、2010年にはTangoを設立し、『サイコブレイク』などを手がけている。
※2神谷英樹:
『バイオハザード』ではプランナー、『バイオハザード2』ではディレクターを務める。2006年にクローバースタジオを退職し、その後プラチナゲームズへ。『デビルメイクライ』、『大神』、『ビューティフル ジョー』、『ベヨネッタ』など、数多くのタイトルでディレクターを担当。現在はクローバーズのスタジオヘッド/チーフ・ゲームデザイナーを務めている。
──ちなみに、当時の主要なスタッフは、岡本さんが面接して採用されたのですか?
岡本氏:
三並(三並達也氏)【※1】、稲船(稲船敬二氏)【※2】、船水(船水紀孝氏)【※3】、三上らですかね? みんな面接しています。僕だけが面接を担当したのは船水かな。彼は当時、東京で面接して採用しました。
※1三並達也:
カプコン在籍時は移植作や続編、他社との共同開発作品などを多く手掛ける。2006年にカプコンを退社し、2007年にプラチナゲームズを設立。
※2稲船敬二:
代表作は『ロックマン』、『鬼武者』シリーズなど。2010年11月にカプコンを退社し、同年コンセプトを設立。
※3船水紀孝:
『スーパーストリートファイターII』、『バイオハザード』シリーズなどを担当。現在はバオバブゲームスタジオ代表取締役。
──そうそうたる面子ですね。岡本さんがアーケードゲームとコンシューマーゲームを両方見られるようになって、社内の体制は変わったのですか?
岡本氏:
アーケードは船水が見て、あとは多くのメンバーがコンシューマーゲーム担当です。アーケードは時代的にそのあとシュリンクしていくと予想していたので、船水には「殿(しんがり)」というあだ名をつけていました(笑)。なんとか赤字を出さない程度にやってほしいというのと、同時にコンシューマーも少しやるように、とお願いもしまして。
──それが、そのあとの『モンスターハンター』シリーズにつながっていくのでしょうか?
岡本氏:
そうです。オンライン3部作というのを作っていて、その最後が『モンスターハンター』でした。

──『グランド・セフト・オートⅢ』(以下、『GTA3』)【※】を、日本へ持ってこられたのも岡本さんだと聞いたことがあります。
※『グランド・セフト・オートⅢ』:
シリーズ初の3Dで描かれたクライムアクションゲーム。プレイステーション2用ソフトとして北米では2001年10月22日に発売。日本では2003年にカプコンよりCEROレーティング18歳以上のみ対象ソフトとして発売され、当時の海外製ゲームとしては異例の30万本を超えるヒットとなった。
岡本氏:
そうですが、あれは人様が作ったものをただ持ってきているだけですから。ただ、持ってきたときに志の高さはありました。「こんないい洋ゲーがあるよ」と。当時は、洋ゲーと言えば“ワンランク下のクオリティーのゲーム”というイメージがありましたが、こんなすばらしい洋ゲーがあるのに遊ばないのはもったいない、日本人が知らないのは未来の大きな損失になると。
ただ、いまでは当たり前になっていますが、ゲームのレーティングが導入された時期でしたのでさまざまな苦労がありました。海外でレーティングが語られ始めたタイミングで、日本でもレーティングを導入しようという話が出たんです。いろいろとあって「18歳以上のみ対象ソフト」となりました。
『GTA3』で印象深いのは、国内で30万本ほどしか売れていないこと。当時の日本のマーケットは保守的で、受け入れられなかった。『GTA3』がヒットする市場であれば、優秀なクリエイターも育つし、マーケットもつぎのいいタイトルをちゃんと拾えると思ったのですが、Xboxでいいタイトルが出ても拾わない。「わかってないなぁ」とずっと思っていました。

岡本氏:
海外のマーケットがいまと比べて小さかったのは間違いないんですが、成長速度がすさまじくて、海外産のゲームがグイグイ来ていた時代でした。カプコンとしてもそれがわかっていて「いずれ中国、インドネシア、マレーシアがマーケットになる」と当時から言っていたことを覚えています。
マイナーな海外版権を獲得してゲームを作り、いまのうちに海外でカプコンの名前を売っておこうと行動していたタイミングでもありました。海外に行って話を聞くと、「『ストⅡ』で遊んでいました!」と言ってくれるわけですよ。子どものころからカプコンって名前に触れてもらうことが大事だなと痛感しましたね。
下手だけど誰よりも遊んでいるからこそ、ゲームを熱く語ることができる
──岡本さんはゲームがそんなに好きではないとおっしゃっていますが、アンテナの張りかたや先見の明がすごいですよね。なぜ、それが実現できているのでしょうか?
岡本氏:
自分はセンスが悪いと思っているからですね。自分にはセンスがないので、アンテナを張ったり、人に会って情報を聞き出したりする時間が非常に長いんですよ。あとはゲーム嫌いと言っているものの、ゲームのプレイ時間は誰よりも長い。あ、桜井正博さんと比べればそうでもないかもしれないですが(笑)。
ゲームが下手なので「あまり遊んでいない」というのが通るんですが、下手だからこそ一所懸命に遊ぶわけです。ゲームが好きではないと言っている僕が「納得できるバランス調整をするにはどうすればいいのか」といったことを語れるのは、とにかくゲームを遊んでいる時間が長いからです。あと性格がしつこい(笑)。
──しつこい……ですか?
岡本氏:
誰よりもしつこいですね。自分では努力しているとは思っていなくて、とにかくしつこいヤツだと思っています(笑)。負けても気にせず、将来勝つために賭けているんだったら、いま負けていてもまったく苦にならない。株価が下がっていても、将来上がるのがわかっているなら持っておいたらいい、といった感じです。それを貫くことができる。
──そのハングリー精神はどのように培われたのでしょうか?
岡本氏:
家が貧乏だったからですかね(笑)。子どものころに苦労している子が伸びるというのは、これまでいっしょに仕事をしてきたスタッフたちを見ていて、整合性が取れているなと感じています。ハングリー精神が強い人たちは、決してギブアップしないんですよ。生活に余裕がないと後ろに下がれないから、前に出続けるしかない。
僕の場合、「ひどい会社でね~」などと口では言っているものの、実際にはなんとも思っていない(笑)。むしろ楽しかったくらいなんです。よく後輩たちと集まりますが、そのときに「楽しかったです」とか、「岡本さんがいたときがいちばんおもしろかった」と言ってもらえる。いまは淡々と作業していておもしろくないと。そういう意味では、僕は破天荒でおもしろかったと。
──岡本さんがチーム運営でいちばん意識しているのはどういったところなのですか?
岡本氏:
若いときは乱暴でしたよ(笑)。30代のときに開発本部長を務めていましたが、周囲は「やんちゃなおっさんやな」と思っていたでしょうね。いまだとコンプライアンスがどうのこうのとありますが、無縁な時代でしたから。会社のため、自分のため、マーケットのため、ユーザーのため……。いろいろありますが、がんばるならば誰よりも努力する、他者よりも働く。そうしなければいけないと、いまでも思っています。
そう考えると、いまの子はぜんぜんがんばっていない……というか、がんばれない環境ですよね。労働基準法に守られていますから。海外との差が広がるばかりですよね。
「ナンバリングタイトルだけを作れ」と言われてカプコンを退社
──岡本さんがカプコンを退社された理由はなんだったのですか?
岡本氏:
人が行動するときにはいくつか理由があって、「岡本、会社辞めるってよ」という話が出たときに当然「なんで辞めるの?」と聞かれるわけですが、明確な理由はとくにないんですよ。いろいろなものが徐々に蓄積していって、最後に何かのトリガーがあって積み重なっていったものが一気に崩れるというか。会社から「オリジナルのゲームを作らなくていい、ナンバリングだけ作れ」と言われたのもそのひとつで、かなり大きな要因のひとつかなと。それがきっかけで辞める考えに大きく傾いたのは間違いないですね。
このままシリーズ作品だけを作って、ポジションアップしながら一生を終えるのか? それとも独立してゼロからやり直すのか。そういった決断を改めて考えるときがあったのですが、「新しいことに挑戦したい」となったんですね。答えを出すまでに時間がかかりましたが、おのずと答えは出ました。
辞めることを選択したつぎに「いつ独立するのか」を考えるわけですが、まず社内は「岡本なしでもやっていけます!」とスタッフが成長しているのがわかっていたので大丈夫だなと。独立するタイミングとしては、コンシューマーのハードが一新されるときだと考えていました。ハードが代わるときに、それまで売れていたハードが必ず勝つとは限らないわけで。ちょうどプレイステーション3、Xbox 360に代わるタイミングが見えていた2003年にカプコンを退社しました。
──ゲーム制作者は組織に長く属していると、経営サイドにならざるを得ない状況となり、もの作りを続けるのが難しくなってしまうことがあります。そういったことも辞める決断をした要因としてあったのでしょうか?
岡本氏:
もの作りをしたいと思っていますが、経営に関わるのが嫌といったことはありません。むしろ、ある程度の役職にいないと決定権がなくて困ることになる。たとえば、カプコン時代に部下が「こんな作品を作りたい」と言ってきたとして、可否の決定権は僕が持っていました。専務取締役とかCOOといった役職がついているから即答できたわけです。
自分はだんだんとやりたいことができなくなっていったので、部下にはやりたいことをやらしてあげたいという気持ちが強く、そのためには経営にもある程度、足を突っ込む必要があるというのは若いときから気がついていました。もちろん、制作と経営の二足の草鞋がキツいということも知っています(笑)。
お墓が見える湘南のアパートを借りてゼロから再スタート
──独立するというのは最初から決めていたのですか?
岡本氏:
どこかの会社に入る、という選択肢はなかったですね。たとえば、どこか大手の会社からゲーム制作の声がかかって、別会社、子会社にしてくれる……という可能性はありました。ただ、完全にフリーのほうが仕事を受けやすいだろうと当時の僕は勘違いをしていて、自分で会社を立ち上げてしまった(笑)。まず最初に「岡本吉起、会社辞めるってよ」という話を自分で流したくて、「岡本がゲーム会社を作ったぞ」ということを伝える“おかつく”というサイトを立ち上げました。名前は『サカつく』【※】からパクったんですけども(笑)。
※『サカつく』:
セガのサッカークラブ経営シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう!』シリーズの略称。
実際にゲーム会社は作っていなかったのですが「ゲーム会社を作ったよ」と世間にはアピールしたんですね。そのときは湘南にアパートを借りて、細々とゲーム企画を考えていました。3階建ての木造アパートで、2階と3階部分がメゾネットになっていて、3LDKで家賃は11万5000円。屋根付きの車庫がついていてこの値段なのかと驚きましたね。窓を開けるとお墓しか見えなかったですけどね(笑)。湘南なのに海が見えないという。
──ゲームリパブリック設立の前に“おかつく”を作られたわけですね。
岡本氏:
そうですね。「釣りに行って、釣った魚をおかずにして食べた」みたいな日記を、サイトに毎日アップしていました。とにかく当時は貧乏でしたね。
離婚したときに慰謝料で貯金をすべて支払って、退職金も翌年の住民税の支払いに持っていかれ……。アパートに住みながら、中古のベンツを安く譲ってもらい、「退職金はまだあるけど、これももうなくなるな」と思いながらゲームのアイデアを考えていました(笑)。
──なぜその状況に身を任せられたのですか?
岡本氏:
自分のなかでは「ここからもう一度スタートする」という気持ちを強く持ちたかったんです。つぎの仕事を決めてから退社する人がほとんどですよね。カプコンを辞めるときには「辞めずにいったん休んだらどうだ」という提案もいただいたんですが、何もしないで給料をもらっていたら精神が腐っていくじゃないですか。
あとはギリギリのところに身を置きたかったのもあります。自分が何者でもない場所にいってみたかったというか……。家族がいたらできないことでしたから、離婚をしていたのはよかったのかもしれません。
──その後ゲームリパブリックを設立されたわけですが、心境の変化はなかったのですか?
岡本氏:
もともと、どこかのタイミングで会社を立ち上げようと考えていました。さきほど話したように、フリーのほうが仕事を受けやすいだろうと。とはいえ、会社に誰か合流してほしいとは思っていたのですが、ちょうど名古屋で働いていたメンバーが入ってくれることになったんです。話が通じる子たちといっしょに仕事ができるというのは本当にありがたい話で、そこからゲームのアイデアを考えていくことになりました。
版権タイトルはお金も含めて乗り越えなければいけない壁がたくさんあるので、お金がかからないけど注目度の高い題材を探していたときに目をつけたのが大河ドラマの『義経』でした。源義経はみんな知っているよねと。数社が同様のゲームを出してきたので、みんな同じことを考えるんだなと思いました(笑)。宣伝費をかけずに知名度を上げられるし、キックスタートするならそれなりのタイトルがいいよねと考えていたときに、ソニーがスポンサーについてくれて、『GENJI』を作りました。

──ゲームリパブリックをどういう会社にしたいと考えていたのですか?
岡本氏:
いちばんは“いいゲームを作りたい”。つぎに“儲かったお金を分配したい”ということです。儲からなかったら歯をくいしばってみんなでがんばる、でも“当たったときにはガッツリ払うぞ!”というのが僕の考え方です。カプコンのときは会社員ですから、IPの権利もなかったですし。
売れたときに作ったスタッフにインセンティブが入るようなシステムをちゃんと作りたかったんですね。
サラリーマンはどうやって生きていくべきか、どうやって引退し、どうやって再燃するのかと考えたとき、ゲームクリエイターという職種は難しさがありますよね。そこをクリアできる方法を模索する会社がゲームリパブリック。だから「ゲーム共和国」という名前なんです。王国制ではないということを伝える社名でもあったわけです。
──ゲームリパブリック時代を振り返っていかがですか? きびしい時代だったと思いますが……。
岡本氏:
とにかく僕が悪かったですね。経営がダメでした。どういったところが悪かったのかというと、いろいろな会社の人を入れたんですよ。元SNK、元カプコン、元SCE、元バンダイ、元ナムコ、元タイトー、元セガ……。みんな力量は高い。ところが、育った環境が違うと、ゲームの作り方も違うんです。自分が習ってきたもの、身につけてきたものがあって、それがぶつかり合ってしまう。僕はKONAMIからカプコンに行ったから、KONAMIではKONAMIの作り方、カプコンではカプコンの作り方をしていて、その会社のカラーで純粋培養されていたわけです。
ただ、いろいろな会社の人間が集まると、みんながそれぞれに違う文化を持っていて、意見がぶつかってしまう。それを僕がまとめるために、八方美人ではないですが「それぞれが正しい」と思っていたため、否定をすることがなかった。結果、意見をまとめきれず、社内で権力争いのようなことが起こってしまった。誰がナンバーツーだとか、誰がこのプロジェクトをまとめるのかとか。なんでもいいからホームランを打たないといけない事情があったのですが、まとまっていない状態でホームランなんて出るわけがなく……。結局8年半ほどやりましたが、1本もホームランは打てませんでしたね。ホームランが出れば踏ん張れたと思いますが……踏ん張り切れず、というのが答えかもしれません。
──ゲームリパブリック時代は、週刊ファミ通で連載をされるなど、会社とご自身のブランディングをされていましたよね。
岡本氏:
特別に自分をブランディングするつもりもなかったのですが、「岡本吉起がどういう人物なのか」を知ってもらいたかったことに加えて、後輩たちにそれを伝えたかった。いまもYouTubeをやっていますが、伝えたいことがあるから伝えているだけです。それを信じるか信じないかは皆さん次第で、強制しようとは思ってはいません。信じる人は信じればいいし、嫌いな人は嫌いって言えばいい。選択肢を提示しているだけなんですよね。





































