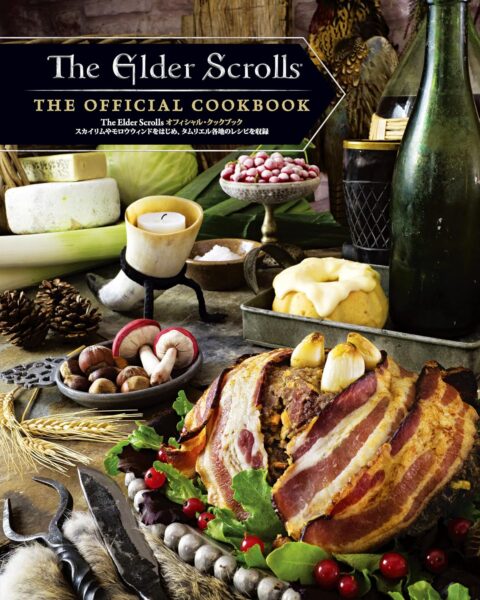『バーチャファイター』は“異端”だったという。
1991年に『ストリートファイターII』が誕生し対戦格闘ゲームのブームが幕を開けた。その約2年後にあらわれた世界初の「3D」格闘ゲームは、すでに華々しい成功を飾っていた2D対戦格闘ゲームの傍らで、まったく異なる文化を築き上げたのだ。

今でこそ「eスポーツ」の名も日本で広まり、ゲームをプレイすることがビジネスとしての価値を大いに見出されるようになった。しかし、その背景には、数多のプレイヤーが情熱とプライドを賭けて「対戦ゲーム」に挑んできた歴史があることを忘れてはならない。
『バーチャファイター』を代表するプレイヤーたち「鉄人」の視点から、当時の格闘ゲームシーンを群像劇風に描いたルポルタージュ『トウキョウヘッド』は、そのヒストリーを色濃く現代に伝えてくれる作品である。
狂気すらも感じさせるプレイヤーたちの姿をドラマチックに表現し、彼らの生の声をインタビューという形式で収録。ゲームセンターから始まったムーブメントを、情緒あふれる文体でまとめ上げた本書は、カルト的な人気を博し、2015年には舞台化も行われた。
そして、その作者である故・大塚ギチ氏の遺した資料をもとに、海猫沢めろん(ナカガワヒロユキ)氏が新たにまとめ上げたのが『トウキョウヘッド・ノンフィックス』だ。
 |
「バーチャ神」の愛称で知られる伝説的なプレイヤーかつ、誰よりもゲームを愛し続けた「ちび太」(小松栄治)氏をはじめとする、歴戦のプレイヤーたちの視点から描かれる『バーチャファイター』の物語。「鉄人」に憧れ、一心不乱に打ち込んできた若き闘争者の姿がありありと描写された本書には、読む者を圧倒する「熱」がある。
筆者自身は1998年の生まれであり、『バーチャファイター』のブームも、ゲームセンターの尖った空気も、対戦格闘ゲームの最盛期も知識や伝聞の形でしか知らない。しかし、昨今の競技シーンの盛り上がりの原点に「格闘ゲームブーム」の勢いがあったことは明白だ。その当時のプレイヤーの体験は貴重な資料であり、その生の言葉には何物にも代えがたいものがある。それらを歴史という言葉でただくくり、埋もれさせるべきではない。
そして今回、著者の海猫沢めろん氏の許可をいただき、本書の一部を抜粋して特別に掲載させていただけることとなった。eスポーツやプロゲーマー、そんな存在が日に日に一般的になっていく現代だからこそ、その原点ともいえる「鉄人」たちや、それに憧れる少年の姿を今一度見つめ直す価値があるというものだろう。彼らの熱を現代にも響かせる、その一助となれれば幸いだ。
※以下、『トウキョウヘッド・ノンフィックス』より「CHAPTER.0 ちび太/小松栄治」前編の内容を抜粋し、Web向けに体裁を整えたものとなります
遊びに飢えていた少年が見つけた「アーケードゲーム」という魔法
少年は「遊び」に飢えていた。
どこだっていい、なんだっていい、楽しい遊びを求めていた。
少年は退屈が嫌いだった。
誰もいない家、小学校の教室、そんな場所にいるより、兄とゲームセンターにいるのが好きだった。薄暗い「遊び場」のなかで、退屈を紛らわすためにコインをもてあそびながら、「楽しみ」を見つけた。
アーケードゲーム。
それは魔法だった。ルールと仲間と場所さえあれば、どこでも一瞬にして「遊び場」になる。
遊びに興じるうちに、仲間たちが彼の持つ才能に気づいた。
並外れた動体視力、思い通りに動く指先、柔軟で大胆な発想。
教えられたわけでもない。直感と感性で、あらゆるゲームを攻略していく彼の姿に誰もが魅了された。
誰かにゲームのことを聞かれると、いつも少年は笑ってこう返した。
―わかんない。けど、楽しい。
少年は、誰よりもゲームを愛していた。
四角く区切られたフィールド内で、男たちが銃を構えて走っていた。
「諦めるな! まだ取り戻せる」
2人の男が声を掛け合いながら遮蔽物の陰に回り込む。男の片方が、腹と背中に搭載された赤いパックのセンサーを確認する。
まだライフは残っている。パックからコードでつながった銃を握り、飛び出そうとしたそのとき。隣にいた仲間の背中のパックが、着弾のサインを示して震えた。
〈防衛シールド・作動。警報・警報・警報〉
銃から合成音が流れる。
「くそっ撃たれた! どこからだ?」
2度撃たれた仲間は、失ったライフ補充のために持ち場を離れた。索敵しているうちに、フィールドの仲間がどんどん倒されていく。
さっきからどうなってるんだ。なんでこんな早いんだ!?
焦って遮蔽物から身を乗り出すと、その瞬間自分のスーツが震えた。
撃たれた!? こんな一瞬で2度も?
男が射線の先をたどると、小さな影が見えた。
ゲーム終了の音が響く。
大差がついたスコアは、男のチームが完膚なきまでに叩きのめされたことを示していた。
フィールドの外で、男が落胆しながら体につけたパックを外していると、光線銃を持った少年が近づいてきた。
「ありがとう。お兄さん、またやろうね!」
小学生にしか見えない少年は、そう言うと、無邪気な笑顔で走り去った。
1994年、冬。
西荻窪のゲームセンター「アミュージアム」には、特別なゲームがあった。
『Q-ZAR』(キューザー)

都内でも設置数が少ないそれは、赤と緑のチームに分かれて光線銃で打ち合いスコアを競う、FPSをリアル体験するようなサバイバルゲームだった。
少年―小松栄治は、兄に連れられてこのゲームをプレイし、その面白さに魅せられた。大人たちに混じって、夢中でプレイしているうちに彼はあることに気づく。
このゲームは通常、相手に撃たれたあと、防衛シールドが作動し追加ダメージ入力を防ぐ仕様になっている。だが、シールド作動のほんのわずかなタイミングを狙うことで、連続してダメージを与えることができるのだ。
栄治はシステムの隙間をついたこの裏技を完全にマスターし、13歳ながらトッププレイヤーたちに一目置かれる存在となっていた。
いつものように『Q-ZAR』が一段落すると、仲間の大人たちは下の階に移動し、他のゲームをはじめる。
彼らは最近稼働を始めたばかりの『バーチャファイター2』に夢中だ。大人向けの3D対戦格闘ゲーム―栄治も好きだったが、みんなが『Q-ZAR』をやらなくなったら嫌だな、とも思っていた。
チームのリーダー格のクニさんが、『バーチャ』をプレイしながら言う。
「エイジくん、今日もいい動きしてたよ」
「ありがとう。うちのチームは世界一強いよね」
このチームは世界でも通用する―栄治はいつかみんなで『Q-ZAR』の世界大会に出ることを夢見ていた。
「ずっと『Q-ZAR』やれるといいなあ」
なぜかその言葉に、クニさんが困ったような顔をした。
「あのね、エイジくん……」
栄治から目をそらしてゲーム画面を見ながら言った。
「そろそろ終わるんだ」
「え? 終わるって? なにが?」
「もうすぐ終わるんだよ、『Q-ZAR』は」
何を言われたのか、理解できなかった。
「そんな……嘘でしょ」
クニさんが言うには、『Q-ZAR』は今月いっぱいでこのゲームセンターから消えるのだという。
当たり前のように続くと思っていたことが、あっさり終わる―その初めての経験に目の前が真っ暗になった。
電車の窓から見える冬の景色は、東京とは思えないほど寂しかった。
憂鬱な目で、夕日に染まって流れていく住宅の屋根を眺める。
家に帰っても誰もいない。
誰もいない家にいるのは、退屈だ。
退屈はきらい。
楽しいことが好き。
いつからだろう。外で「楽しいこと」を探し始めたのは。
栄治は、自分がどこで生まれたのか知らない。
住む場所は子供の頃からめまぐるしく変わり、家族も家をあけることが多く、ほとんどの時間を兄と一緒にゲームセンターで過ごした。
親がときどき家に残していってくれる軍資金は潤沢で、栄治は電車に乗っていろいろなゲームセンターへ行き、あらゆるゲームがプレイできた。
ゲームセンターはどこだってにぎやかで、人がいて、それが心地よかった。
それなのに―。
終わらないゲームはない。
頭ではわかっていた。
大好きだった「遊び場」を失うこと―栄治にとってそれは、身を切られるほどの悲しみだった。