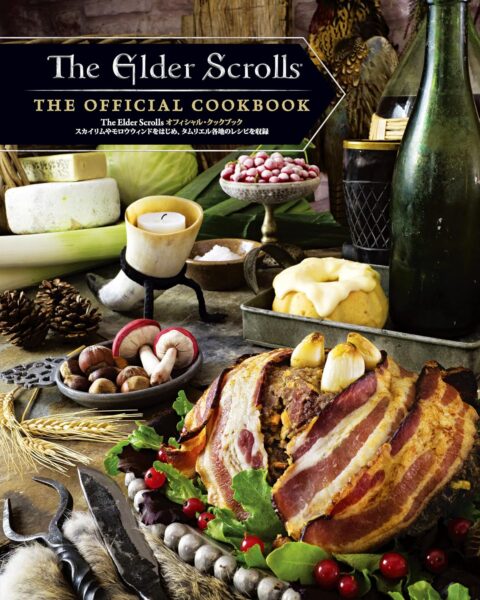初めてあこがれた「鉄人」の存在
「今日の試合、あの子供出てるよ」
「あいつめちゃくちゃ強いよな……」
「こないだ別の大会でも優勝してたよ」
午後から始まる大会を前に、店内に張り出されたトーナメント表の「ちびっこアキラ」の名前を見て常連たちがざわついていた。
「あんなガキがアキラスペシャル出せるだけでもすげえのに」
「三鷹のシングル大会のときはまだ弱かったけどなぁ。若いと成長早いわ」
この日、国分寺のゲームセンター「ハイテクランドセガ国分寺」では、バーチャファイター2公式全国大会の店舗予選が行われようとしていた。
店員が大会のスタートを告げると、挨拶もなしに順番に対戦が始まる。
栄治は「ちびっこアキラ」というリングネームで、この殺伐とした空間のなかに紛れ込んでいた。プレイヤーたちが苦々しい顔で眉をひそめる。
ガキがお遊びでバーチャやってんじゃねえよ……。
だが、一度対戦が始まるとそんな空気は一瞬にして消えた。
数時間後、トーナメント表の優勝者欄に書かれた名前は「ちびっこアキラ」だった。
バーチャを本格的にプレイし始めてから数ヶ月―栄治は都内の様々な場所に遠征して大会に出場していたが、そのほとんどで優勝か準優勝する破格の怪物に育っていた。
『Q-ZAR』がなくなっても、ゲームがやれなくなったわけではない。
そう、ゲームはまだいくらでもある─それが栄治の出した答えだった。
予選が終わると、ゲーム好きの常連たちは店を出て、そのなかの一人の家に移動し始めた。気づくと栄治もその群れのなかに紛れ込んでいる。
全員が困惑気味に顔を見合わせた。
―おいおい……このガキなんでついてくるんだよ……。
気まずい空気のなか、決勝で栄治に負けた高校生くらいのアキラ使いが、イライラした口調で言った。
「なあ、なんでここにいんの?」
「おい、別にいいだろアニアキ。大人気ねえぞ」
アニアキと呼ばれたアキラ使いは、仲間に諌められ、バツが悪そうに頭をかく。
「おまえさ……なんだっけ、名前」
本名を聞かれているのだろうか。栄治が返答に迷っていると、そのプレイヤーは「ああ、もういいや」と、投げやりに言った。
「ちびっこ―いや、ちび太。いいか、俺がお前に負けたのはたまたまだからな」
「うん。わかったよ」
栄治はニコニコしながらそう答えて、
―次もたぶん、たまたまぼくが勝つけどね。
心のなかでつぶやいた。

―おかしいな、たぶん新宿って言えばここなんだけど。
春の冷たい風を受けながら、栄治は新宿の路地をぶらついていた。
「GAME SPOT21」―そこに最強のバーチャプレイヤーがいるらしい。
ゲームセンターで誰かがそう言っているのを耳にしてやってきたものの、その場所にたどり着けない。
ギラついた刺激的な夜に比べると、昼の歌舞伎町はまるで気が抜けたコーラみたいにぼんやりしていた。
「おお! エイジ! 元気だったか?」
「エイジ! これ食べろよ」
昔、このあたりに住んでいたことがあるせいで、顔見知りの大人たちが声をかけてくる。
大人たちがくれたお菓子でお腹は一杯になったが、目的地が見つからない。
だらだらと歌舞伎町をうろつく。温かい飲み物を買うために入ったコンビニのマガジンスタンドには「阪神淡路大震災」「オウム・サリン事件」の文字が踊る週刊誌。
自分の世界の外で、なにかが起きている。
けれど、それよりも夢中なものがある。
栄治にとって大事なのは世間よりもゲームだ。
街をさまよっているうちに、時間は夕方近くになっていた。もどかしくなってきて、近くを歩いている若い大学生風の男性に声をかける。
「お兄さん、GAME SPOT21って知ってる?」
男は突然声をかけられたことに戸惑いながら、「西口じゃなかったかな」とわざわざその場所まで案内してくれた。
日暮れ前にたどり着いた「GAME SPOT21」は、通りに面したワンフロアのゲームセンターだった。店に入り、大型アーケード筐体の脇を通り過ぎると、奥に設置されたバーチャの筐体のまわりに人だかりができていた。
プレイしているのは、髪を短く刈り込んだ目つきの鋭い青年だ。画面のなかで彼が使うウルフが、ジャイアントスイングで相手のジャッキーを場外に投げ飛ばすのが見えた。
しばらく観戦していたが、誰一人勝てないまま、対戦相手だけがめまぐるしく入れ替わる。
ワクワクしながら待っていると自分の番がやってきた。
コインを入れて、アキラを選択。
レディー……GO! 掛け声とともに、栄治のアキラとウルフがリング中央でぶつかり合う。一進一退の攻防、軽く大技を決めてやろうと栄治が隙を見せた瞬間、ジャイアントスイングを決められ一気に体力が削られる。
―すごい! この人めちゃくちゃ強い。
負けたにも関わらず、席からすぐに立てないほど興奮していた。
ふと見ると隣の台にも列ができていた。ジェフリー使いが画面の対戦者をどんどん倒していく。
―新宿は強い人がいっぱいいるんだな。
また列に並び直していると、「おい、おまえ」と野太い声がした。
振り返るとスーツを着た補導員らしき大人がいた。その姿を見て、舌打ちしそうになった。
―うわ……めんどくさい。
「こんな時間になにしてる。中学生じゃないのか」
どう答えようか迷っていると、ウルフ使いが筐体の向こうから顔をのぞかせて言った。
「あ、そいつ俺の弟です」
疑うような目で補導員が栄治を見たが、「早く帰れよ」とだけ言って去っていった。
助かった……。
お礼を言ったが、彼はもうゲームに集中していた。
「ブンブン丸の知り合い?」
後ろに並んでいるプレイヤーが栄治に話しかけてきた。
「ブンブン丸?」
「え、知らないの? あのウルフ使い」
栄治は首をかしげる。
「ブンブン丸と、隣のやつは柏ジェフリー―ふたりとも「鉄人」なんだよ」
「鉄人……」
モニターのなかでウルフがまたジャイアントスイングを決めた。
栄治の胸に、初めて「あこがれ」という感情が芽生えた瞬間だった。

「鉄人」たちの敗北と少年が「神」と呼ばれるまで
夏の終わり、1995年9月24日、横浜ジョイポリス。
「ついにこの日がやってきました! バーチャファイターマキシマムバトル!」
プロレスラー風のマスクをかぶった司会者「エックス」の前口上が始まると、待っていたとばかりにギャラリーが歓声をあげる。
そこにいる誰もが強さに憧れていた。
血と汗にまみれたコインを貪欲に食らい続ける筐体の並んだ闘技場のなかで、勝利だけをひたすらに追いかけるプレイヤーたち。
強く、誰よりも強くなりたい。
最強―アスファルトにうかんだ陽炎のようにゆらめく曖昧な概念―それが今、目の前に実体を持って現れようとしていた。
『バーチャファイター2』公式全国大会「マキシマムバトル」。この日の出場者は、全国のセガ直営店で行われた予選11ブロックを勝ち抜いてきた38名に加え、前夜祭で正式に称号が授与された6人の「鉄人」と台湾代表をあわせた48名。
予選大会を通過できなかった栄治は、ステージ前のギャラリーたちの最前列に陣取って試合開始を待っていた。自分がステージにいないのは悔しいが、「鉄人」のプレイを間近で見られるのは楽しみだった。
「それでは決勝大会、開幕です!」
司会者の言葉とともに、戦いの始まりを告げる乾いたゴングの音が鳴り響き、栄治は期待に胸を膨らませた。
が―栄治の期待とは裏腹に、試合が進むにつれて思わぬ番狂わせが続き、鉄人たちが序盤で立て続けに敗北。
なんとか柏が準決勝まで進んだものの、最終的にファイナリストに残った鉄人はキャサ夫のみ。
決勝戦はファイナリスト3名による「巴戦」―もともと大相撲における優勝決定戦の方式の一種で、連続して2勝した者が優勝となる形式―で行われることになり、1試合目でキャサ夫が勝利したが、2試合目で逆転され、そのまま別の選手に優勝を許してしまう。
―あーあ……鉄人が全員負けちゃった。
こうしてすべての試合が終わった。
応援していた鉄人が全員負けたのは残念だったが、プレイヤーたちの試合にかける気迫と会場の熱気は歴代大会屈指のレベルだった。
歓声に湧く場内。
最後に、壇上に6人の鉄人たちが現れると同時に、新宿ジャッキーがマイクをとった。
とぎれとぎれに聞こえるセリフ。
「鉄人である……負けたことに……ふがいない……」
まわりの観客たちが不穏な空気にざわめく。
―え、どういうこと? なに言ってるの?
大会序盤に負けた新宿ジャッキー、池袋サラ、ブンブン丸、K・K雪風が「鉄人」の称号を返還する―そう言ったような気がした。
 |
近くの観客同士の会話が聞こえる。
「おい、鉄人返還だって?」
「なんでだ?」
「あの4人が負けたからだろう?」
―え! やめちゃうの? うそでしょ?
栄治の脳裏に『Q-ZAR』の悪夢が蘇る―ずっとあると思っていた場所と、一緒にいられると思っていた仲間がいなくなる恐怖。
やめないで。
小さく叫んだ栄治の声が、会場の騒音にかき消される。
壇上から去っていく鉄人たちの後ろ姿が、栄治の目にはまるで暗闇に落ちていく星のように見えた。
―そんな……このまま終わるはずないよね。
栄治は行き場を失った熱を閉じ込めるように、その拳を握りしめる。
鉄人がいなくなるの?
みんなバーチャをやらなくなっちゃうの?
そんなの嫌だ。
この日、少年の夢は終わった。
96年9月。『バーチャファイター3』の稼働が開始。
前評判が高かった『~3』だが、実際に稼働すると、『~2』とかけ離れたプレイ感に、多くのプレイヤーが困惑した。
新しく導入された「エスケープボタン」。
打撃と投げに加えて「避ける」という選択肢の追加。
高低差が攻撃に影響する「アンジュレーション」。
複雑化したシステムに耐えきれなくなったプレイヤーたちがどんどん脱落していく。
ついていけない旧世代、新環境に対応していく新世代―『バーチャ』に世代交代が起きようとしていた。
プレイヤーの温度差はインカムにも影響した。それはメーカー側にとって、苦渋の決断を迫られる現実的な問題だった。
結果的に、97年の7月を最後に、『バーチャファイター4』が稼働を開始する2001年まで、実に4年間もの長期に渡って公式全国大会が行われない冬の時代がやってくる。
栄治は時代の波を乗り越えてプレイしつづけた。
あの日終わった夢は、今や実現すべき「目標」へと変わっていた。
─僕が、鉄人になる。
『~3』からメイン使用キャラをリオンに据え、その強さはもはや誰も追いつけない未知の領域へ入っていた。
そんな彼の姿を見て、いつしか人は彼のことをこう呼ぶようになっていた。
―バーチャ神。
きまぐれな少年の姿をした「神」は、眠ることすら忘れて遊び続ける。
視神経を刺激するモニターのブルーライト。
鼓膜を震わせる電子音の洪水。
鼻腔を麻痺させる煙草の匂い。
どんな街のゲームセンターも、彼にとってはホームだった。
少年はただひたすら、戦い続けた。