00年代:大人が“ゲームを屋外に持ち出す”時代の到来
2000年代に入ると、インターネットが日本の社会にも本格的に普及し、ゲームにおいても仮想現実を大勢で共有する、オンラインゲームの時代となっていく。
そして2000年代後半から現在にまで至る時代を、『現代ゲーム全史』では《拡張現実の時代》と区分している。中川氏は、1990年代の《仮想現実の時代》が、現実とは違うもうひとつの世界をリアリスティックに作ることを志向していたのに対して、《拡張現実の時代》では現実空間そのものを拡げていくものとして、デジタルデバイスを使おうと志向していると語っている。
ARを活用した『ポケモンGO』はまさにその代表的な例だが、中川氏によると、任天堂がニンテンドーDSやWiiで展開した身体動作を重視したゲームも、《拡張現実の時代》の表れではないかという。

(中川氏pdf 10ページ目 2000年代前半)

(中川氏pdf 12ページ目 2000年代後半)
遠藤氏:
『脳トレ』の頃に、任天堂のTVCMが大きく変わるんです。それまではゲームの画面を映していたのが、ゲームを遊んでいる人の姿を映して、その体験の様子をおもしろがらせるというCMになったんです。
そうしたCMもあって、30代前後の女性がニンテンドーDSでゲームを遊び始めるようになったわけですが、この年齢の人たちってじつは、子どもの頃にゲーム&ウォッチで遊んでいた世代なんですね。ゲーム&ウォッチの最終形はデュアルスクリーンで、DSの形と同じなんですよ。だから大人の女性でも、この機械を持つことにまったく違和感がなかった。
それまでは、大人がゲーム機を電車の中で遊ぶということはあり得なかった。この女性たちが電車の中でDSを遊ぶようになって、大人がゲーム機を持ち歩いて恥ずかしくないという空気が生まれたんです。
中川氏:
屋外にゲーム機を持ち出して、現実空間のいろんなシチュエーションの中でゲームを遊ぶというのは、まさに《拡張現実の時代》が具体的に現れてきた形ですよね。その象徴とも言えるタイトルが、『モンスターハンターポータブル』(以下、『モンハン』)で。
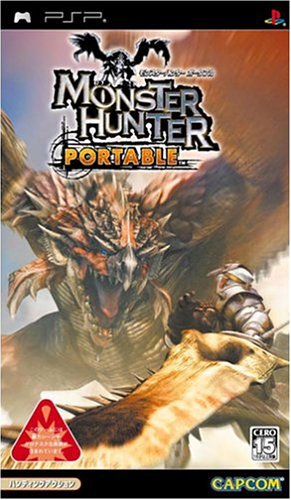
(画像はAmazonより)
遠藤氏:
カプコンは昔から、難易度の高いゲームを作らなければいけないカルマを負っていて、ヘタに難易度を下げると、熱心なファンに怒られちゃうんですよ(笑)。じゃあ、どうやって難易度を下げるのかという答えが、『モンハン』だと思うんです。1人で遊ぶととんでもなく難しいけど、4人で遊べばモンスターをタコ殴りにできるっていう。この『モンハン』が、女子会のコンテンツとして大流行するわけですよ。
“ゲームを屋外に持ち出す”という点では、今では携帯ゲーム機以上に、携帯電話でプレイするゲームがポピュラーになっている。遠藤氏は2000年代初頭、スマートフォン以前のフィーチャーホンのアプリでゲームがリリースされるようになった極めて初期の段階から、そうした携帯アプリゲームの開発を行ってきたという。
遠藤氏:
携帯電話にJava【※】が搭載されると最初に聞いた時、「それって絶対、ゲームにしか使わないじゃないか!」って思ったんです。そうして僕は、Javaの動く携帯電話がまだ基板に部品が載っている状態の時から、ゲームを作り始めていました。
※Java
コンピュータ上でソフトを動作させるプログラミング言語の1つ。プラットフォームに依存しないことを目標にしており、そのためWebページでのアニメーションやインタラクティブ操作、Blu-rayディスクで動作するコンテンツなど、多岐に渡って利用されている。
そんなふうに、携帯電話でゲームが遊べるようになった初期から作っていたので、大ヒット作もたくさんありますよ。ただ、そうしたゲームは僕が作ったとはわからない状態にしていたので、そのことを誰も知らない。それを語るのはキャバクラだけです(笑)。キャバクラ嬢がやってるゲームばっかり作ってましたからね、『占いバキューン!』とか。この時に初めて、ゲームを作っていて女の子にウケるという状況が生まれたんです。
そうしたスマートフォン以前の携帯アプリで登場したゲームの中で、中川氏が特に注目しているのが、2009年にモバゲーでリリースされた『怪盗ロワイヤル』だ。
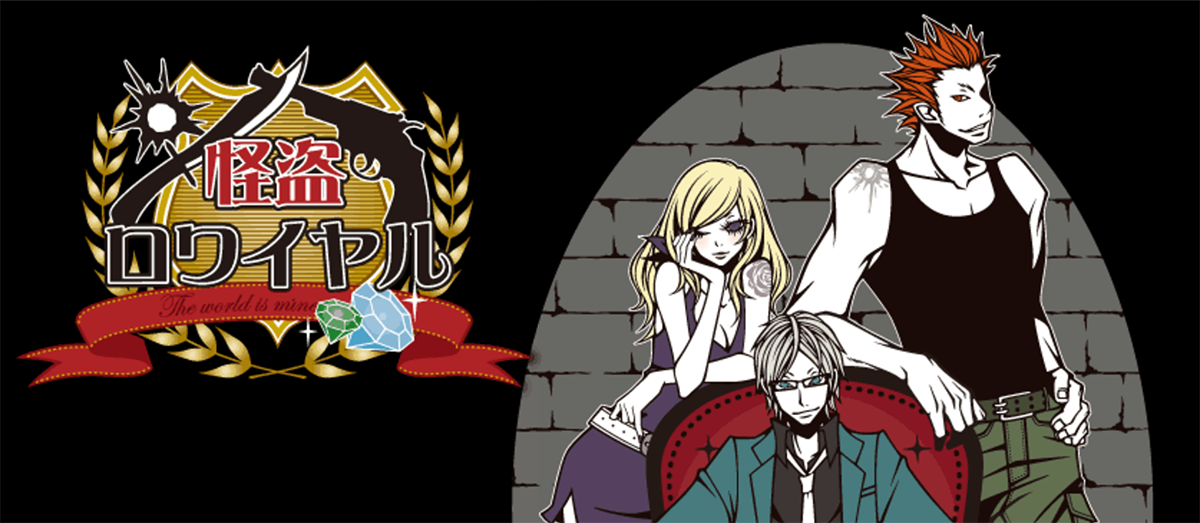
(画像は『怪盗ロワイヤル』の公式サイトより)
中川氏:
『怪盗ロワイヤル』がすごく衝撃的だったのは、日本のそれまでのゲームの発展の方向とはまったく違うことをやっていたという部分で。お互いに宝物を盗りあうっていう、ガチのPvPコンテンツが、ここで初めて日本のカジュアルなプレイヤーに普及したと思うんです。
だからこの当時、「こんなのゲームじゃない」ってよく言われていたんだけど、むしろこれこそがまさに“ゲームらしいゲーム”じゃないの、と思っていたんですよね。
遠藤氏:
この時期には、モバゲーやGREEやmixiといったWeb業界の人たちが、Webのインタラクティブ性をウリにしていくなかで、ゲームっぽいコンテンツを作り始めたんですね。だから彼らは、それまでのゲーム業界の常識に、まったく囚われていないんです。
日本のゲーム業界は、反社会的なテーマにすごくナーバスになっていて、そうした要素がある作品を絶対にやらないんです。でもWebの人たちが作った『怪盗ロワイヤル』がやってるのは、人様の物を盗むことじゃないですか。その後に『ロワイヤル』自体も変化して、作っている人も変わっていって、今ではだいぶ優等生になりましたよね。
『怪盗ロワイヤル』のような携帯電話のゲームが出てきた時には、「“もしもしゲー”はゲームじゃない」っていう人が、ゲーム“機”業界に大勢いたわけですよ。実際はソーシャルなんて、ゲームの中の要素にしか過ぎないんですけどね。
10年代:日本人は『ポケモンGO』にはハマりにくい!?
2010年代前半にはフィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が急速に進んだことで、《拡張現実の時代》がよりいっそう本格化してくることになる。
また、『怪盗ロワイヤル』をはじめとする携帯電話のソーシャルゲームでは、モバゲーやmixiといったSNSと密着していたのに対して、ガンホーによる『パズル&ドラゴンズ』のリリース以降は、スマホゲームのネイティブアプリが進み、ゲームプラットフォームとしてのSNSとの関連が薄れていった。そうした状況を、中川氏は「ソーシャル性のないゲームが“ソシャゲ”と呼ばれる、不思議な時代」と評している。

(中川氏pdf 13ページ目 2010年代前半より)

(中川氏pdf 14ページ目 2010年代後半より)
遠藤氏:
ゲーム開発者というのはたいてい、作っているゲームに対して奥さんの理解がないんです。「これをやってみて」と言っても、まず遊んでくれない。でも『パズドラ』を作った山本大介さんは、自分の奥さんに遊んでもらいたくて、『パズドラ』を奥さんが遊べるレベルまでチューニングしていったんです。そのおかげで“Easy to Start, Hard to Master”、つまり簡単に始められるけどマスターするのは難しいっていう、日本ゲームのものすごくいい状態に仕上がっているんです。
中川氏:
ガラケーのソーシャルゲームが「こんなものはゲームじゃない」と批判されたなかで、『パズドラ』の山本さんをはじめとする人たちは、その批判に対してものすごく良心的に答えようとした部分がありますよね。
遠藤氏:
その結果、ゲーム機が大好きな人たちが「スマホにもいいゲームがあるじゃないか」と、初めて認めてくれた。これ以降、ゲーム“機”業界が本当の意味でのゲーム業界になるために、スマホにも取り組むようになったんです。
中川氏:
ただ、ニンテンドーDSの時点で一足先に、スマホゲーム的な方向性に舵を切っていたはずの任天堂が、それをより徹底した形のスマホゲームを認めるまでには、けっこう時間がかかったという印象です。
遠藤氏:
それは先々代の山内社長が決めた方針を、前社長の岩田さんも守っていたからでしょうね。
任天堂も経営陣が変わって、ゲームを作っている人たちも若返っているなかで、これからもどんどんと新しいものが出てくるでしょうけど、そのなかで任天堂スピリッツというものはちゃんと維持されているんです。任天堂には知り合いも大勢いますし、教え子もたくさん任天堂に入ってますけど、彼らは“任天堂である”ということを、非常に大事にしているので。だからスマホのゲームも、必ずいい形で出てくると思いますよ。
中川氏:
その任天堂スピリッツと、文字通りの拡張現実的なゲームが初めて成功したナイアンティックの『Ingress』が一緒になることで、2016年の『ポケモンGO』の大ヒットに至るわけです。アメリカで発展してきた洋ゲー的なカルチャーや、情報技術で世界を覆い尽くして社会を良くしていこうというGoogleのマインドと、おもちゃ屋としてのプライドを持ちながらファミリー向けのゲームを作ってきた任天堂の哲学が、ものすごく幸福な形でくっついたと思うんです。
去年の8月に『現代ゲーム全史』を出版するタイミングで、この本で言いたいことのいちばんいい形で、『ポケモンGO』が出てきてくれたわけで。だから僕にとっては、まるで神風が吹いたみたいな受け止め方でしたね。
遠藤氏:
『Ingress』って、頭のいい人じゃないとおもしろさがよくわからないと思うんですよ。なぜなら目に見えないものを「そこにあるじゃないか」と提示されても、頭が良くないと一致しないんですね。ゲームの中に存在しているポータルと、自分が現実世界の場所に行くということが、なかなか一致しないんです。
でも日本人は、『Ingress』が大好きなんですよ。日本人は抽象的な概念に対する“見立て”や“見なし”が、ものすごく上手なんですね。僕自身はこれが、漢字が持っている力というか、漢字が育んでいる認識力が生んでいると思っています。日本人だけじゃなくて、アジアで漢字を使っている文化圏でも、よく似た傾向が見られるので。
そんなふうに頭のいい人じゃないとわからない『Ingress』に対して、『ポケモンGO』はさきほども言ったように、ARで目の前に見せてくれるシステムなので、そりゃアメリカで大流行するわけですよ。逆に日本では、若い人はわりとすぐに興味を無くして、ふだんはゲームをぜんぜんやらないおじさんやおばさんが、『ポケモンGO』に夢中になっていますから。
中川氏:
『ポケモンGO』が出てきたことによって、日本ゲームの何がグローバルに通じて、何が日本独特なものなのか、改めてサンプルが得られたという形ですか?
遠藤氏:
そうですね。ただ、何をもってグローバルというのか、という問題もありますけど。
去年ドイツに行った時に、ドイツ人から「アメリカって市場規模が大きいだけの田舎だよね」と言われたんです(笑)。市場規模が大きいとスゴいように思えるんだけど、あんなヤツらにわからなくてもいいよ、って。「日本のことはオレたちがちゃんとわかってるから、アメリカなんか気にせずに、日本は日本のゲームを作れ」と、ヨーロッパの人たちは言ってくれますね。
これから:『Rez Infinite』に見る、日本の長所
「『ポケモンGO』が登場する以前は、2010年代後半は“VRの時代”になると思っていた」と、中川氏は語っている。『ポケモンGO』の大ヒットによって、VRを飛び越えてARへの注目が一気に高まったとはいえ、2016年のゲーム業界でVRが非常に大きなトピックとなったことは間違いない。
今回のトークイベントの締めくくりとして、遠藤氏と中川氏はプレイステーション VRの発売以降のVRの状況について語り合った。それは『現代ゲーム全史』刊行後のゲーム業界について語るという、書籍のさらに先をゆく内容となっている。
中川氏:
2016年に出てきたVRコンテンツの中で、僕の周りですごく評価されているのは、水口哲也さんの『Rez Infinite』なんです。

(画像はPlayStationの公式サイトより)
VRってすごく欧米的な発想じゃないですか。この現実と同じような主観視点の感覚をわざわざ用意しなければ、もうひとつの世界を感じ取ることができないという。でも『Rez Infinite』は、この地上では体験することのできない無重力空間の心地よさというか、ユークリッド空間的な現実からいかにすれば人間の認識は解き放たれるのかということを、VR技術を使ってやろうとしているんだなと感じたんです。
遠藤氏:
“Sense of Agency”、行為主体感っていう言葉があるんですけど、じつはVRの中にはもう一段高い領域があって、没入感のさらにその上に、“プレゼンス”という領域があるんです。プレゼンスというのは、脳がそれを虚構であると理解していながら、それを脳自身が現実であると誤認している状況なんですね。
今、PS VRでリリースされているタイトルで、そのプレゼンスを実現しているのが、『サマーレッスン』なんです。『サマーレッスン』は、あの女の子がパーソナルエリア内に侵入してくる瞬間にプレゼンスが生じている。女の子が近づいてくる時に、体温を感じたり息づかいを感じたりといった、本来はあるはずのない感覚まで感じるようになるんです。
これを“クロスモーダル現象”というんですけど、パーソナルエリアに他人が侵入してきて不快感を感じるような状態になると、体温や息づかいを感じるといったことが起こり得ると、脳が勝手に情報を補完しているんですね。

(画像は『サマーレッスン』の公式サイトより)
中川氏:
VRが出てきたことによって、人間のリアリティを構築しているものはいったい何かということが問われてくる。
遠藤氏:
そうですね。だから今、真剣にVRに取り組んでいるゲーム業界の人たちは、「プレゼンスって大事だよね」と言い始めています。そのなかで日本人が求めているプレゼンスは、リアルに対するプレゼンスではないんです。
日本以外の人たちは、リアルな物を見せて、そこにプレゼンスを生じさせようとしています。でも日本人は違います。2次元とか2.5次元といった架空のもの、アニメのようなものに対して、それが現実であるかのように脳を誤認させたい。それが日本人の目指しているプレゼンスなんです。
中川氏:
僕が水口さんの『Rez Infinite』から感じたのも、それなんです。重力に引っ張られる3次元空間の規範というのが、欧米圏ではあまりにも強すぎて、それを異化する発想っていうのはやっぱり、日本のほうが長けているんじゃないかなと。そしてVR技術の可能性をより引き出すことができるのは、そっちの方向性じゃないかなと思うんです。
2000年代に入って以降、日本ゲームが市場規模的なシェアを落とした状態をすごく嘆かれてきたわけですけど、ここにきて新しい技術が出てきたことによって、日本ゲームはその使い道を、人間の身体性に即した形で提案していくことができるんじゃないかと期待しているんです。
遠藤氏:
ビジネスがシュリンクしたように見えるのは、ゲーム“機”業界だけなんですよ。スマホなども含めたゲーム業界として全体を捉えてみると、いまだにガンガン成長してるんですね。
問題は、日本のゲーム市場が成長する頻度に対して、世界のゲーム市場はもっと急激に増えているということです。なぜなら今までゲームをやってなかった人たちが、ゲームをやるようになったからです。日本人は昔から、けっこうゲームをやってるので。
ただ、そんななかでも言えるのは、自国だけで経営規模が成り立つぐらいの市場を持っているのは、日本とアメリカぐらいだということですね。だから日本はぜんぜん負けてるわけじゃないので、日本の若い人たちもヘンなコンプレックスに負けずに、ぜひがんばってほしいですね。
 |
コンピュータゲームの黎明期から最新のVRまで、ゲーム史を一通り語り終えたところで、ちょうどイベント終了の時間となった。遠藤氏は、ゲームの進化をリアルタイムで体験してきた人物だけあって、豊富な知識に裏付けされた開発者ならではの分析は、非常に示唆に富むものだった。
ところで遠藤氏は現在、大学でゲームデザインを学生に教える一方で、ゲーム研究者として日本のゲームデザインを学術的に理論化し、それを世界に伝えようと活動している。
ARに関するトークの中で、「日本人が“見立て”を得意としているのは、漢字を使っているからではないか」という話題が登場したが、じつは遠藤氏はこの点について、自ら研究を行っているという。トーク後の質疑応答の際には、大学での教材を使用して、実証を交えつつ“講義”してくれた。
アルファベットで表記された英単語は、その言葉自体を知らないと意味がわからないが、漢字はその文字自体の意味がわからなくても、部首ごとの意味の組み合わせによって類推できる。また漢字は一部が隠れていても、全体的なシルエットからその文字をなんとなく推測できる。こうした特徴を持つ漢字を日常的に使用しているため、日本人は抽象的なイメージを現実と結びつける“見立て”が得意なのでは、というのだ。
ゲーム開発者として確固たる実績を持つ遠藤氏が、日本のゲームデザインの真価を言語化し、それが広く共有されることこそが、もっと日本のゲームがおもしろくなっていくことに繋がっていくはずだ。
そして、もちろん、現代ゲーム史は今なお進行中のものであり、技術の進歩と社会の変化によって、これからも新たな状況が次々と生まれてくることだろう。イベント後半で語られたVRについての話題のように、中川氏にはゲーム批評の論客として、新たな時代の潮流を読み解くことを期待したい。



































